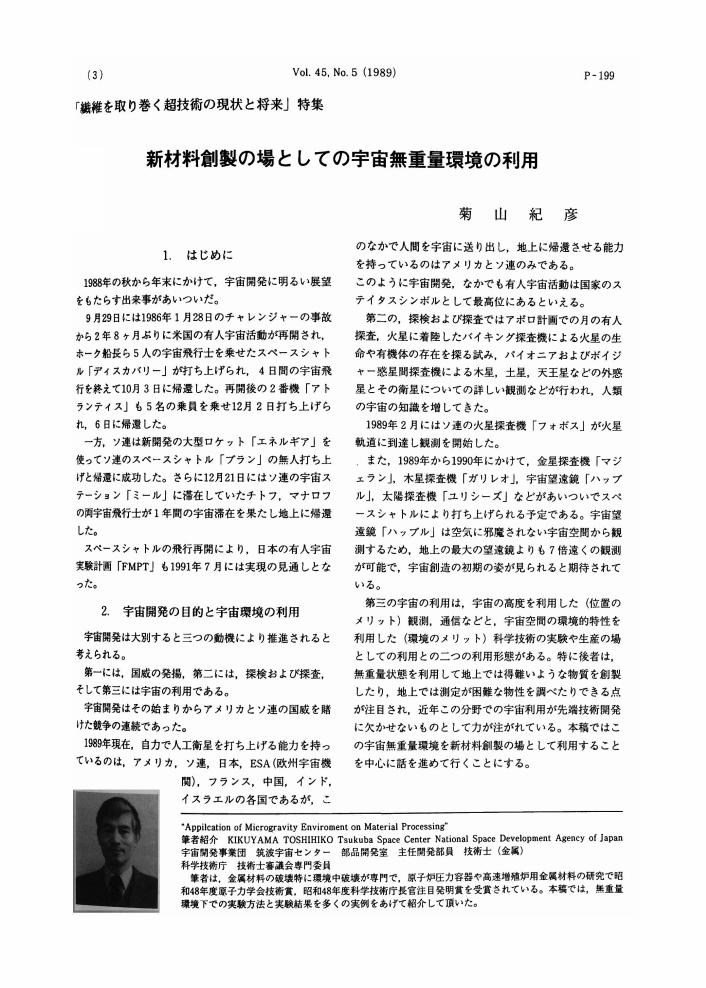2 0 0 0 OA Dark Triadの高い者はゴミのポイ捨てをしやすいのか
- 著者
- 下司 忠大 吉野 伸哉 小塩 真司
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.84-86, 2019-07-01 (Released:2019-07-06)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1 1
The purpose of this study was to examine the relationship between littering behavior and Dark Triad personality traits (Machiavellianism, narcissism, psychopathy). Forty-one college students (average age=19.83 years, SD=1.11; 9 males, 32 females) were assigned randomly into either a clean or a dirty laboratory condition, and participated in an experiment to assess their littering behavior. Results of Bayesian logistic regression analysis that predicted the littering index, indicated that cumulative probabilities that the odds ratio for narcissism and psychopathy exceed 1 in posterior distribution under dirty condition were 84% and 87%, respectively. The results of the present study showed that the Dark Triad personality traits may be related to littering behaviors, while previous studies focused on manipulations of condition.
2 0 0 0 OA 筋肉痛で発症し, 粟粒結核症で死亡した一剖検例
- 著者
- 大瀬戸 隆 惠 京子 神田 実喜男
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和医学会雑誌 (ISSN:00374342)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.8, pp.438-442, 1972-08-28 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 17
A 46-year-old woman noticed the muscle pain of the bilateral femur and diagnosed dermatomyosis.She was dead on July 1 1969 and diagnosed miliary tuberculosis including muscle tuberculosis by autopsy.
2 0 0 0 OA 離島における救急患者搬送の実態
- 著者
- 井上 仁 箕輪 良行 河野 正樹 崎原 永作 立花 一幸 沼田 克雄
- 出版者
- Japanese Association for Acute Medicine
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.32-41, 1994-02-15 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
本研究は,ヘリコプターなどによる救急患者搬送の諸問題に関して,搬送を要請する側の離島に勤務する現地医師の立場からの意見を,アンケート調査により集約し検討したものであり,この種の研究としては本邦ではじめてのものである。対象は,北海道,東京,島根,長崎,鹿児島,沖縄の6地域の遠隔離島などに在任中または勤務経験をもつ医師200人とし,記名による回答を94人(47.0%)から得た。収容病院の特徴としては,十分なコミュニケーションが可能な病院(68.1%),臨床研修を受けた病院(33.0%)が多くみられた。北海道や長崎の離島では,明確に規定された搬送要請基準が回答された。なかでも長崎では,極小未熟児分娩の予想される母体,先天性心疾患で緊急手術を必要とする症例など,適応疾患5項目を具体的にあげていた。2名以下の医師が勤務する東京,鹿児島,沖縄の小離島では,スタッフや施設機能の不十分に起因する要請が多く,診断がつかない場合や,長期入院を要する場合にも搬送要請の基準としている回答が多い傾向があった。要請から搬送までの問題点としては夜間,荒天時搬送機能の確保充実を求める回答が59.6%と最も多く,搬送時間短縮のために基幹病院ヘリポートの設置を求める意見が多くみられた。医師の添乗義務については,全例に必要と,重症のみ必要が同数であった(43.6%)。添乗医の確保ができず,要請を撤回することもある現状が9回答報告された。また,添乗医の安全性確保を現地医師の75.5%が強調していた。現状では搬送中機内での医療行為がほとんど不可能であることから,医師添乗を義務づけるならば医療行為可能な搬送専用ヘリコプターの導入が望まれる。問題点のある搬送76例,搬送を考えたが最終的には搬送しなかった37例が報告された。このなかで気象条件,患者の容態,要請手続きなどに関して具体的に問題点が指摘された。
2 0 0 0 OA フィリピン・台風ハイエンによる住宅及び人的被害の特性 ―災害被害と脆弱性の関連性―
- 著者
- 花岡 和聖 村尾 修 杉安 和也
- 出版者
- 一般社団法人 地域安全学会
- 雑誌
- 地域安全学会論文集 (ISSN:13452088)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, pp.1-9, 2014-11-07 (Released:2017-08-02)
- 参考文献数
- 24
In November 2013, Typhoon Haiyan (Yolanda) gave devastated impacts on both housing and people’s lives in the middle part of Philippines. The purpose of this paper is first to understand characteristics of such disaster impacts and the geographical distributions, and second to analyze relationships between impacts and vulnerabilities at the municipality level in a quantitative way. Our major finding is that social vulnerability, in particular poverty plays an important role in determining both housing damage and population suffering. Houses in highly urbanized and deprived municipalities were more likely to be destroyed possibly due to concentrations of poor households on high risk areas. Also, elderly, less educated and poor people were more vulnerable.
- 著者
- Aiko HATA Masaya ODA Takahiro ONO Akira SUZUKI Noriaki HANYU Masataka TAKAHASHI Toshio SASAJIMA Manabu HASHIMOTO Taizen NAKASE Hiroaki SHIMIZU
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.7, pp.404-413, 2021 (Released:2021-07-15)
- 参考文献数
- 21
The efficacy of stereotactic radiotherapy (SRT) has been well established for postoperative residual and recurrent nonfunctioning pituitary adenomas (NFPAs). However, the risk of visual impairment due to SRT for lesions adjacent to the optic pathways remains a topic of debate. Herein, we evaluated the long-term clinical outcomes of hypofractionated stereotactic radiotherapy (HFSRT) for perioptic NFPAs. From December 2002 to November 2015, 32 patients (18 males and 14 females; median age 63 years; range, 36–83 years) with residual or recurrent NFPAs abutting or displacing the optic nerve and/or chiasm (ONC) were treated with HFSRT. The median marginal dose was 31.3 Gy (range, 17.2–39.6) in 8 fractions (range, 6–15). Magnetic resonance imaging (MRI) and visual and hormonal examinations were performed before and after HFSRT. The median follow-up period was 99.5 months (range, 9–191). According to MRI findings at the last follow-up, the tumor size had decreased in 28 (88%) of 32 patients, was unchanged in 3 (9%), and had increased in 1 (3%). The successful tumor size control rate was 97%. Visual functions remained unchanged in 19 (60%) out of 32 patients, improved in 11 (34%), and deteriorated in 2 (6%). Two patients had deteriorated visual functions; no complications occurred because of the HFSRT. One patient developed hypopituitarism that required hormone replacement therapy. The result of this long-term follow-up study suggests that HFSRT is safe and effective for the treatment of NFPAs occurring adjacent to the ONC.
2 0 0 0 OA 社会的行動障害のリハビリテーションの原点とトピック
- 著者
- 村井 俊哉 生方 志浦 上田 敬太
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.5-9, 2019-03-31 (Released:2020-04-03)
- 参考文献数
- 11
社会的行動障害は高次脳機能障害の主要 4 症候の 1 つであり, 依存性・感情コントロール低下, 対人技能拙劣, 固執性, 引きこもりなどの多彩な症状を含む。これらの社会生活上問題となる行動や症状は, 1. 脳損傷の直接の結果として理解可能な, 前頭葉の関与する社会的行動障害 (遂行機能障害・アパシー・脱抑制) , 2. 他の認知機能障害 (せん妄や健忘症候群) を基盤とした社会的行動障害, 3. 心理社会的要因の関与の大きい社会的行動障害に分けることができると考えられる。こうした背景を理解した上で, 社会的行動障害がどのようなきっかけで生じるのか, 生活や訓練場面における文脈の調査に基づき評価を行う。リハビリテーションにおいては, 症例の生活で必要とされる具体的なスキルの獲得を目指すことが必要である。
- 著者
- Hiroshi ABÉ Tomiko ITO
- 出版者
- 日本ダニ学会
- 雑誌
- 日本ダニ学会誌 (ISSN:09181067)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.31-39, 2021-11-25 (Released:2021-12-03)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 青年・成人期の愛着スタイルの世代間伝達 愛着は繰り返されるのか
- 著者
- 金政 祐司
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.4, pp.398-406, 2007-10-25 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 8 2
This study was conducted to examine intergenerational transmission of attachment styles between late-adolescent children and their mothers. The purpose of the study was to reveal whether the two attachment dimensions, “Anxiety (about relationship)” and “Avoidance (of intimacy)” were related between children and their mothers, and whether these relations were mediated by the both children's and mothers' perceptions of parenting. Participants were 209 pairs of late-adolescent children and their mothers. Results revealed that the attachment dimensions of “Anxiety” and “Avoidance” in children significantly correlated to the same dimensions in their mothers. Based on attachment theory, it was hypothesized that intergenerational transmission of attachment styles was caused by the influence of the following factors: “(a) mothers' attachment styles, (b) mothers' perceptions of parenting, (c) children's perceptions of their mothers' parenting, and (d) children's attachment styles”, and possible causal models of the influence processes among those variables were developed and tested in the data analyses. The results showed the validity of these processes for the intergenerational transmission of attachment styles. These results are discussed in terms of the relationships between children and mothers and late-adolescent/adult attachment styles.
2 0 0 0 OA 絵画評価におけるDeath Positivity Biasの検討
- 著者
- 堤田 賢人 白岩 祐子
- 出版者
- Society for Human Environmental Studies
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.31-36, 2020 (Released:2020-06-30)
- 被引用文献数
- 2
死者は生者よりもポジティブに評価される傾向がある。death positivity biasと呼ばれるこの現象は、シナリオ実験と実際の雑誌記事の両方で確認されている。絵画の世界でも同様に、ゴッホやモジリアーニなど、死後になって評価が高まる画家の存在が知られている。死後に評価が向上する現象は、ゴッホのように傑出した才能をもつ特別な画家以外でも生起するのだろうか。つまり、death positivity biasは絵画全般において生起するのだろうか。この点を検証することが本研究の第一の目的であった。第二の目的は、上記でdeath positivity biasが確認されたとして、それが画家の死による効果なのか、あるいは作品の希少性の高まりによる効果なのかを検討することであった。筆者らはシナリオ実験を行い、架空の無名画家の死亡条件と存命条件、さらに活動停止条件で、絵画および画家への評価を比較した。分散分析の結果、death positivity biasは確認されなかった。この結果は、先行研究がターゲットとした実業家や一般人などとは異なり、画家は死による恩恵を受けにくいことを示している。death positivity biasの発生境界条件や今後の研究の方向性が議論された。
2 0 0 0 OA 洪積台地端部の斜面における地震動増幅特性の評価
- 著者
- 川又 優 関口 徹 中井 正一
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震工学会
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.8, pp.8_32-8_41, 2016 (Released:2016-07-25)
- 参考文献数
- 8
本研究では千葉県内の自然斜面及び、切土施工によって表面の軟弱な地盤を切り取った切土斜面を対象とし、それぞれの震動特性の評価を行った。斜面の法肩部と台地上の平坦な部分に地震計を設置し地震観測を行ったところ、自然斜面法肩部で地震動が大きく増幅していることが確認できた。そこで、地盤調査の結果に基づき地盤構造をモデル化し、2次元FEMを用いた動的解析による伝達関数の計算を行った。その結果、1次元解析では再現できない自然斜面法肩部での増幅特性を2次元解析で再現でき、斜面形状だけでなく台地端部表層の軟弱層が地震動を大きく増幅させることを確かめた。
2 0 0 0 OA 地球表層の主要陽イオンと炭酸塩の物質循環
- 著者
- 吉村 寿紘
- 出版者
- 一般社団法人日本地球化学会
- 雑誌
- 地球化学 (ISSN:03864073)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.131-142, 2018-09-25 (Released:2018-09-25)
- 参考文献数
- 59
Major cations (Na, Mg, K and Ca) are essential for life and play a major role in the global geochemical cycles. Dissolved cations in terrestrial waters derive from both silicate and carbonate rocks, and rivers and groundwater deliver them to the ocean, where there is a steady-state balance between inputs and outputs over geological time. Calcium carbonates are central components in understanding the chemical budgets of major cations for modern and past oceans. Biogenic CaCO3 is an important tool for elucidating the oceanic chemical evolution and past climate changes. Recent advances in mass spectroscopy techniques have made it possible to explore the stable isotope system of Mg, Ca, K and Sr in geologic materials, each of which are novel indicator for constraining the interplay of natural systems in the geological past; continental weathering, carbonate budgets, mid-ocean ridge spreading rates, etc.
2 0 0 0 OA 成人および高齢者の脳波
- 著者
- 山﨑 まどか 松浦 雅人
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.387-392, 2014-12-01 (Released:2016-02-25)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA カカオの温室栽培に関する研究
- 著者
- 佐藤 啓一 阪口 ナミ
- 出版者
- Japanese Society for Tropical Agriculture
- 雑誌
- 熱帯農業 (ISSN:00215260)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.115-119, 1967-12-28 (Released:2010-03-19)
- 参考文献数
- 4
電熱利用温室におけるカカオ樹栽培の結果, 毎年約20個のカカオの果実を収穫することが出来た.温室内においても, 開花結実はほとんど一年を通じて行なわれるが, 結実後の落果が多く, 収穫できるのは, 10月から12月頃の開花盛んな頃の人工受粉により得られたもので, その時の月平均気温は, 27℃前後であった.収穫したカカオの実は, 形態的にやゝ小さく, カカオ豆は不良豆がやゝ多く, 1個平均重もやS小さかったが・それを除けば, 充実した多くのカカオ豆を得ることができた.おわりにこの研究の発表を許可下さった森永製菓株式会社に深謝すると共に, 終始御助力下さった, 製菓鶴見研究所玉木技監, 塚口分室須山分室長に感謝の意を表する.
2 0 0 0 OA 新材料創製の場としての宇宙無重量環境の利用
- 著者
- 菊山 紀彦
- 出版者
- The Society of Fiber Science and Technology, Japan
- 雑誌
- 繊維学会誌 (ISSN:00379875)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.P199-P209, 1989-05-10 (Released:2008-11-28)
- 参考文献数
- 8
2 0 0 0 OA 超電導磁気軸受の基本構造とその応用
- 著者
- 高畑 良一
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.9, pp.1251-1254, 1995-09-05 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA 日本列島の地殻ひずみ速度 —測地学的データと地質・地形学的データの統一的理解—
- 著者
- 鷺谷 威 大坪 誠
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.128, no.5, pp.689-705, 2019-10-25 (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 63
- 被引用文献数
- 4 4
Geodetic estimates of crustal strain rates in the Japan islands were an order of magnitude larger than geological/geomorphological estimates, which has been an unresolved problem called the strain rate paradox. Ikeda (1996) postulated that geodetic strain mainly reflects elastic strain accumulation due to interactions at plate boundaries. This hypothesis was proven to be correct by the occurrence of the 2011 MW 9.0 Tohoku-oki earthquake. Confusion between elastic strain and inelastic strain was the cause of the paradox. Significant postseismic deformation observed after the Tohoku-oki earthquake made it possible to distinguish the inelastic contribution from the geodetically observed crustal strain through a comparison with the pre-seismic strain rate pattern, which promoted a better understanding of inelastic deformation in the Japan islands. On the other hand, migration of localized deformation and temporal changes of strain rate are identified over a geological time scale, implying that it is essential to carefully review the methods and the uncertainties of geological/geomorphological strain rates. An integrated understanding of crustal deformation in the Japan islands is being advanced through detailed investigations of crustal strain rates on variable temporal and spatial scales.
2 0 0 0 OA H-Iロケット開発の現況
- 著者
- 松田 敬
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.370, pp.603-611, 1984-11-05 (Released:2009-05-25)
2 0 0 0 OA 筋疲労について
- 著者
- 眞野 行生
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.9, pp.622-626, 1994-09-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 5
2 0 0 0 OA ツイートの分析からみた 鍼施術による長胸神経麻痺に関する報道の影響
- 著者
- 福島 正也
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学系物理療法学会
- 雑誌
- 日本東洋医学系物理療法学会誌 (ISSN:21875316)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.73-77, 2019 (Released:2020-05-20)
- 参考文献数
- 9
【緒言】2017 年9 月10 日から11 日にかけて、プロ野球投手が鍼治療のミスにより長胸神経麻痺に なった可能性があり、球団側が投手に謝罪したとの報道があった。この報道は、鍼治療と長胸神 経麻痺の因果関係が明らかにされないままに行われており、鍼治療のイメージに対する悪影響が 懸念される。Twitter は代表的なソーシャル・ネットワーキング・サービスで、そのコンテンツで あるツイートの分析は、社会心理学における感情反応の調査等に応用されている。本研究は、ツイー トの分析により、報道内容が鍼治療のイメージに与えた影響を調査することを目的に実施した。 【方法】調査は2017 年12 月に実施した。調査対象は、報道日と、その前後1 週間時点および前後 1 ヶ月時点のツイートとした。検索方法は、“鍼”or“針治療”or“はり治療”or“はりきゅう”or “針灸”を検索語とする掛け合わせ検索とし、日本語でのツイートを抽出した。抽出されたツイー トは、ツイート数の比較、およびKH Coder(Ver. 2.00f)を用いたテキストマイニングによる、頻 出語、コロケーション統計(“鍼”のコンコーダンス検索)、報道日の共起ネットワークの分析を行っ た。 【主な結果】報道日のツイートは、ツイート数が約4.4 倍に増加し、報道内容と関連した語が多く 抽出され、“怖い”“ 酷い”という語が共起していた。 【考察】調査結果から、報道内容は、一定の注目を集め、相応の社会的インパクトをもつものだっ たと考える。また、報道内容にネガティブな感情を抱いた者が多かったことが示唆された。本調 査結果は、報道内容に対する短期的な感情が反映された可能性が高いと考える。今後、報道の長 期的な影響の調査や、高度情報社会に対応した鍼治療のイメージブランディングが求められる。
2 0 0 0 OA 解説:我が国へのURAの導入 ―その経緯,活動と課題―
- 著者
- 山本 進一
- 出版者
- 独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構(旧 大学評価・学位授与機構)
- 雑誌
- 大学評価・学位研究 (ISSN:18800343)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, pp.27-38, 2020-03-01 (Released:2020-03-30)
- 参考文献数
- 18
URA(University research administrator)と呼ばれる新しい職種が2011年以降導入されてきた。主に米国を見習ったこの職種について,我が国の現在のURAはその職務内容や役割が極めて多様である。この多様性をもたらした原因について,米国におけるこの職種のあり方や現状について紹介し,その定義と導入の経緯の主な理由を検討した。そして,URAが現在果たしている機能と役割,実績と効果について公表資料を参考に列記し評価した。それらを基に,URAが現在抱える課題について質保証を中心にまとめ,今後の方向性について指摘した。