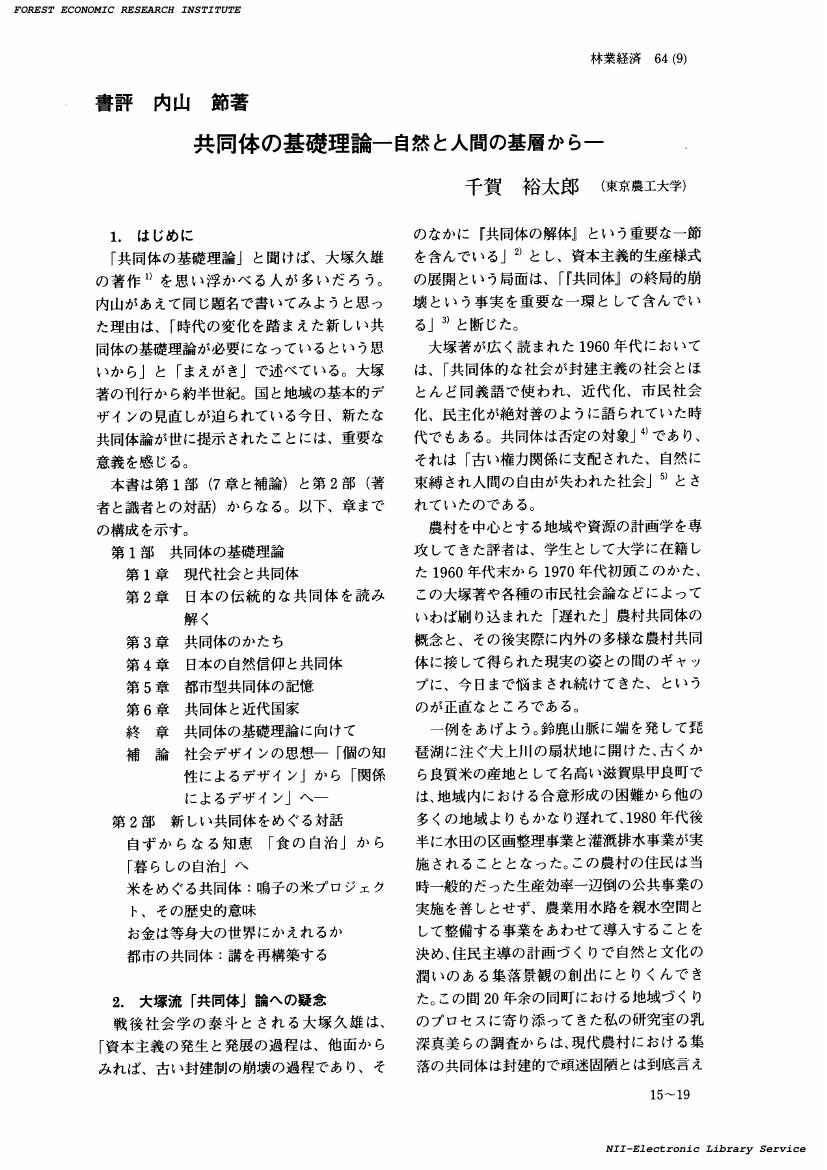2 0 0 0 OA マッスルスーツ®
- 著者
- 小林 宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.143-146, 2020 (Released:2020-03-18)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 OA 筋萎縮性側索硬化症に対する核酸医薬治療
- 著者
- 西田 陽一郎 横田 隆徳
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.258-261, 2017 (Released:2017-10-14)
- 参考文献数
- 9
Nucleic acid medicine treatment is a promising technology and improving the efficacy of therapeutic oligonucleotides is still needed for its broad use. Although antisense oligonucleotides (ASOs) and short interfering RNA (siRNA) have been well known as nucleic acid medicine, pharmaceutical developments by using them are not completely free to be done due to patent protection. Therefore, we developed a new technology, third generation oligonucleotide. We named it heteroduplex oligonucleotide (HDO). In addition, our original drug delivery system (DDS) using glucose trasporter–1 (GLUT1) made great enhancement on delivery of oligonucleotides into the brain through blood–brain barrier (BBB). In this symposium, we show above two new technologies we have developed, and outline the nucleic acid medicine treatment for amyotrophic lateral sclerosis (ALS).
2 0 0 0 OA プローブバイシクルを用いた車道走行自転車の安全感評価モデルの開発
- 著者
- 山中 英生 亀井 壌史
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.5, pp.I_623-I_628, 2015 (Released:2015-12-21)
- 参考文献数
- 15
国土交通省・警察庁が2012年発出した自転車ガイドラインでは自転車走行空間のネットワーク整備を推進するため,多くの街路において,車道部の活用を基本方針としており,自転車専用通行帯に加えて,自動車速度が低く,交通量の少ない道路では,車道部でのマーキングや指導帯等を用いて,車道混在形態の整備を進めることが示されている.しかし,我が国の自転車の利用者にとってこうした車道走行の安全感確保の視点からの評価に関して十分な研究はない.本研究では,走行中の自転車から,追越していく自動車の速度,離隔を計測することができるプローブバイシクルを開発し,安全感のプロトコル調査と組み合わせることで,自動車に追い抜かれる時の安全感モデルを開発した.
2 0 0 0 OA 内山節著『共同体の基礎理論-自然と人間の基層から-』(書評)
- 著者
- 千賀 裕太郎
- 出版者
- 一般財団法人 林業経済研究所
- 雑誌
- 林業経済 (ISSN:03888614)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.9, pp.15-19, 2011-12-20 (Released:2017-06-01)
2 0 0 0 OA フラクタルカインと炎症性疾患
- 著者
- 今井 俊夫 西村 美由希 南木 敏宏 梅原 久範
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.131-139, 2005 (Released:2005-06-30)
- 参考文献数
- 54
- 被引用文献数
- 9 12
炎症や免疫反応は生体局所で生じることから明らかなように,免疫細胞の時空間的局在は緻密に制御されている.免疫細胞は細胞接着分子と細胞遊走因子を巧みに利用して,炎症部位やリンパ組織に到達する.フラクタルカイン/CX3CL1は,ケモカインと細胞接着分子の2つの活性を併せ持ち,活性化血管内皮細胞上に発現する細胞膜結合型ケモカインである.その受容体CX3CR1は,NK細胞やcytotoxic effector T細胞(TCE)などの細胞傷害性リンパ球と成熟マクロファージや粘膜樹状細胞などの病原体や異常な細胞の排除に深く関わる免疫細胞に発現している.最近の臨床病態やマウス疾患モデルでの研究から,フラクタルカインは,関節リウマチや粥状動脈硬化症などの慢性炎症疾患にも深く関与していることが示唆されている.本稿では,フラクタルカインの特徴的な機能と炎症疾患における役割について概説する.
2 0 0 0 OA 科学者の社会的責任の現代的課題(科学は今…)
- 著者
- 藤垣 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.3, pp.172-180, 2010-03-05 (Released:2020-01-18)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
本稿では,現代における科学者の社会的責任について考える.責任を呼応可能性,応答可能性という意味で捉え直して再整理すると,現代の科学者の社会的責任は,(1)科学者共同体内部を律する責任(Responsible Conduct of Research),(2)知的生産物に対する責任(Responsible Products),(3)市民からの問いへの呼応責任(Response-ability to Public Inquiries)の3つに大きく分けられることが示唆される.この3つの区分を,ジャーナル共同体(専門誌共同体)との関係を用いながら考察し,最後にカテゴリー間の葛藤について考える.
2 0 0 0 OA 複数のダイナミックモデルに基づく蹴上がり動作スキルの解析
- 著者
- 中脇 ダレル 周 桑完 宮崎 文夫
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.1, pp.59-65, 2000-01-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 7 10
The kip is a fundamental gymnastic movement performed on a variety of gymnastic apparatuses at all levels of competition. We analyze the kip with a multi-model approach consisting of a pendulum and 3-link model. Our simulations have shown that a variable length pendulum model is sufficient for modeling the dynamics of an expert gymnast's center-of-mass without considering the complex parameters of the 3-link model. The optimized pendulum model can generate kip pattern variations which yield a midpoint target region of success. We then evaluate these kip patterns based on the center-of-mass and 3-link system's total energy.Experimental data of both success and failure performances show that the novice raises his center-of-mass too high during the forward swing thus resulting in failure. Analysis of midpoint kip pattern variations also indicate that raising the center-of-mass at the end of the forward swing is a cause of failure.
- 著者
- Junko SUZUKI Yohei NISHIO Yuki KAMEO Yutaka TERADA Ryusei KUWATA Hiroshi SHIMODA Kazuo SUZUKI Ken MAEDA
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医学会
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.11, pp.1457-1463, 2015 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3 18
In 2007–2008, a canine distemper virus (CDV) epidemic occurred among wild animals in Wakayama Prefecture, Japan, and many mammals, including the wild boar and deer, were infected. In this study, CDV prevalence among wild animals was surveyed before and after the epidemic. At first, an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with horseradish peroxidase-conjugated protein A/G was established to detect CDV antibodies in many mammalian species. This established ELISA was available for testing dogs, raccoons and raccoon dogs as well as virus-neutralization test. Next, a serological survey of wild mammalians was conducted, and it was indicated that many wild mammalians, particularly raccoons, were infected with CDV during the epidemic, but few were infected before and after the epidemic. On the other hand, many raccoon dogs died during the epidemic, but CDV remained prevalent in the remaining population, and a small epidemic occurred in raccoon dogs in 2012–2013. These results indicated that the epidemic of 2007–2008 may have been intensified by transmission to raccoons.
- 著者
- 岡田 匡史
- 出版者
- 大学美術教育学会
- 雑誌
- 美術教育学研究 (ISSN:24332038)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.1, pp.113-120, 2019 (Released:2020-03-31)
- 参考文献数
- 55
本稿は連稿後篇となる。前稿でレンブラント「夜警」読解に際し,7段階・15項目で成る鑑賞学習プログラムを提起し,第1・3段階(観察,解釈)を論じたが,本稿では第2・4・7段階(形式的分析,知識補塡[情報提供],補充課題)を扱った。第5・6段階(再解釈,判断&評価)は別の機会に譲る。第2段階で油絵の具の賦彩特性と画面構成上の特質を挙げ,形式的状態に主題把握に通ずる道筋が潜む点に言及した。第4段階の主要論題は,美術史的背景,図像学的特徴,エピソードとした。美術史学習の進め方に関し,藤井聡子・梶木尚美による歴史学習と絵画鑑賞を連結する教科横断型授業実践を参照した。図像学的観点から「夜警」を解す試みや,補助的だが時に主題に直結しもするエピソードの機能も論じた。第7段階(補充課題)では,東西比較,絵を聴く,自画像捜し,ロールプレイ,脱整列型記念写真撮影を概説し,本稿を締め括った。
- 著者
- 嶋林 ゆう子 林崎 規託 鳥井 弘之
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.163-175, 2008-09-26 (Released:2017-10-21)
- 参考文献数
- 44
科学技術と社会が健全な関係を維持するためには,科学技術と社会のコミュニケーションが求められる。本論は,科学技術の専門家が負う説明責任に焦点を絞り,責任が生じる局面の抽出を通して,科学技術における説明責任の概念に迫るものである。まず,説明責任の関連用語(アカウンタビリティ,知る権利,情報公開)の語義の分析に基づき,分野を科学技術に限定せずに,日本社会における説明責任の一般的な概念を整理した。さらに,社会システムを構成する一要素としての科学技術の特殊性を抽出した。これらの結果を踏まえて,科学技術の専門家に説明責任が生じる次の4つの局面を切り出した。(1)資源が負託されたとき,(2)権限が負託されたとき,(3)人体(個人/集団)に対する影響が生じるとき,(4)社会(現在/将来)に対する影響が生じるとき。これらと現行の科学技術政策において説明責任が生じるとされている局面を比較し,その差異について指摘した。本論によって,科学技術の専門家は自分たちがいつ社会に説明すべきかが分かり,自律的に説明責任を遂行することができるようになる。また,社会の側も,いつ専門家に責任追及すべきかを判別することが可能となる。さらに,説明責任を課せられた側と課す側がその責任の概念を共有できれば,専門家と社会の双方の参加による,「社会のための科学技術」の実現の一助となる。
2 0 0 0 OA カイコ胚休眠の研究 ─特に筆者の見聞を中心に─
- 著者
- 柳沼 利信
- 出版者
- 社団法人 日本蚕糸学会
- 雑誌
- 蚕糸・昆虫バイオテック (ISSN:18810551)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.2, pp.2_099-2_118, 2015 (Released:2017-10-09)
- 参考文献数
- 113
2 0 0 0 OA スマートライフケア社会創造のための基盤づくり
- 著者
- 柴田 智広 井上 創造 相馬 功
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.323-328, 2019-08-15 (Released:2020-02-15)
- 参考文献数
- 29
2 0 0 0 OA 集光型太陽熱発電(CSP)の技術と市場
- 著者
- 吉田 一雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.12, pp.810-814, 2012 (Released:2019-10-31)
- 参考文献数
- 8
集光型太陽熱発電(CSP)は,反射鏡で集光した太陽光をレシーバで熱へと変換し,一般には蒸気タービンを回して発電する技術である。本システムでは,蓄熱システムやボイラを組み合わせることにより,太陽が照っていない時間帯にも比較的低コストの発電が可能である。したがって,CSPは,電力需要曲線に合わせた電力供給が可能であり,ディスパッチャビリティが高い発電システムである。CSPでは太陽から直接地表に到達する直達光のみ利用できることから,中東・北アフリカ,米国南西部などサンベルトと呼ばれる地域で高効率の発電が可能であり,発電ポテンシャルも膨大である。CSPで得た電力を離れた地域で利用するため,北アフリカで発電した電力を高圧直流送電でEU諸国に送るデザーテック計画も進行している。
2 0 0 0 OA 症例 Pacemaker-twiddler'ssyndromeの2症例
- 著者
- 加藤 理 中田 八洲郎 住吉 正孝 久岡 英彦 小倉 俊介 桜井 秀彦 山口 洋 中里 祐二 南塚 只雄 羽里 信種
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.11, pp.1317-1320, 1990-11-15 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 18
ペースメーカー植え込み後にジェネレーターが回転しリードの捻れを生じる現象はPacemaker-twiddler'ssyndromeとしてよく知られているが,その発生は比較的まれである.我々は335例のペースメーカー症例のうち2例で本症候群を認めたので報告する.症例1は72歳,症例2は75歳の女性で各々身長(cm)153,146.5,体重(kg)75.5,64,で房室ブロックのため前胸部皮下にペースメーカーを植え込んだ.症例1では術後早期よりジェネレーターの回転が認められたが一過性に筋攣縮(twiching)が出現する程度でその後無症状であるため放置,4年後の現在も捻れは進行しているが右側臥位でジェネレーターが回転しそうになった時に患者自ら整復しペーシングも順調で経過観察中である.症例2では術後4カ月に筋攣縮出現リードの複雑な捻れを認め症状も持続するため再手術を行いジェネレーターを大胸筋に固定し,破損していたリードを修復した.2症例はいずれも高齢で高度の肥満があり皮下組織が粗であることが発生要因と考えられた.
2 0 0 0 OA 補文副詞の繰り上げ変形について そのコミュニケイション機能と許容度の考察
- 著者
- 大塚 賀弘
- 出版者
- 日本実用英語学会
- 雑誌
- 日本実用英語学会論叢 (ISSN:1883230X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.5, pp.1-11, 1997-09-23 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 19
This paper will give a functional account of preposing the adverbial phrase, during the weekend in the embedded clause of the matrix sentence: “Nine people are believed to have been killed during the weekend.”The author would tend to de-emphasize grammatical explanations for theplacement of “during the weekend” and rather look at it functionally. For most purpose of communication, the placement of an adverbial phrase becomes significant only when a matrix sentence is being crafted for a particular purpose.The reader or listener would be unlikely to be consciously aware of the subtlety in this case, though the impact would be greater.The author would depend on context to choose how to use the clause, “ during the weekend”.Case 1: Nine people are believed to have been killed during the weekend.In this case people and their number come to the fore. The “who” context rather than the “when” context is considered more important. This style would be used if the writer or announcer considered the human tragedy more worthy of attention than the time context.Case 2: During the weekend, nine people are believed to have been killed.As in the case of a broadcast news report, the announcer would begin a news story with these words to set a time coontext. He or she would also use the words to provide continuity with a previous piece also set in that time period; however, in that case he or she would be more likely to say, “Also during the weekend”.Case 3: Nine people are believed, during the weekend, to have been killed.This is the least likely case. The author finds the sentence awkward. This would be used only if it were necessary to provide emphasis to both “nine people” and “killed”. A newscaster might say, “Horror has struck Montana! Nine people are believed, during the weekend, to have been killed. Police are still searching for the gunman who....”.
2 0 0 0 OA ネオンサインの発光原理と器具材料
- 著者
- 吉野 禮之
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.235-238, 2002-04-01 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 亜熱帯メソサイクロンのメソ気象学的研究
- 著者
- 荒川 秀俊 渡辺 和夫 土屋 清 藤田 哲也
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.163-181, 1972-12-25 (Released:2012-12-11)
- 参考文献数
- 15
亜熱帯性メソサイクロンが各種大気じょう乱の聞で占める位置づけを,その大きさと強さによって求めたところ,温帯性メソサイクロンと弱い熱帯低気圧の中間に在ることがわかった。洋上に発生して,100kmからせいぜい200kmほどの大きさを持った亜熱帯メソサイクロンを既存の地上観測網で捕捉する機会はきわめて少く,したがって,その構造や性質を調べる手掛りはほとんどない。たまたま,1960年9月1日のこと,メソサイクロンが東支那海に発生して北東に進んでいることが名瀬レーダーで発見された。それから一昼夜して,それが九州中部に上陸して消滅するまでの状況をかなり刻明に記録することができたので,このじょう乱が亜熱帯メソサイクロンの良い例では決してないが,このケースを調べることによって,メソサイクロンの一般的構造や性質をうかがうことにした。メソサイクロンは亜熱帯じょう乱としての螺線状降雨帯を持っているが,中緯度に進んで来ると共に,収束の大きな東半円内にある降雨帯で数多くの積乱雲が発生して顕著なメソ高気圧を作ってゆく。ところで,じょう乱の主体であるメソサイクロンのスケールと副産物的なメソ高気圧の大きさと強さが同じオーダーであるために,後者は前者の構造を著しく変えてしまうことが特徴である。また循環が弱いために対称的構造をとることができず,著しい非対称になっていることも特徴といえる。限られた高層観測点と山岳測候所で得られた資料の時系列を使って内挿をほどこし,1kmから14kmまでを1km毎に14層の等高度面天気図を作ることによって3次元解析を試みた。その結果として,亜熱帯メソサイクロンへの空気流入量は,巨大積雲のそれと,発達期にある台風への流入量の丁度中間であることがわかった。
2 0 0 0 OA 嘉納治五郎の中国人留学生教育
- 著者
- 老松 信一
- 出版者
- 日本武道学会
- 雑誌
- 武道学研究 (ISSN:02879700)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.27-28, 1976-01-30 (Released:2012-11-27)
2 0 0 0 OA 現実の真贋
- 著者
- 石光 輝子
- 出版者
- Japanische Gesellschaft für Germanistik
- 雑誌
- ドイツ文學 (ISSN:03872831)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, pp.120-129, 1989-03-01 (Released:2008-03-28)
Über sein Werk "Marbot. Eine Biographie“ sagt Hildesheimer, er könne es nicht übertreffen, und habe sich mit ihm die Möglichkeit verstellt, jemals wieder ein erzählendes Buch zu schreiben. Tatsächlich hat er bis heute nichts mehr veröffentlicht, außer der kleinen essayhaften Prosa "Mitteilungen an Max“ und den Notizen und Vorträgen, die aus der früheren Zeit stammen. Worin liegt die Bedeutung des Buches, das seinen Verfasser zu einer solch endgültigen Absage kommen ließ?Dem Werk ist deshalb so große Aufinerksamkeit des Publikums gewidmet worden, weil es, obwohl der Autor es im Titel als eine Biographie bezeichnet und dementsprechend verschiedene anscheinend reale Schriften, Aufzeichnungen und Briefe hineingearbeitet hat, doch eine reine Fiktion ist. Der Schriftsteller, hier selber die Rolle eines Fälschers spielend, hat alle Dokumente gefälscht, um eine perfekte Biographie zustandezubringen. Das Fälschungsmotiv selbst ist dem Leser von Hildesheimer nicht neu; bereits am Anfang seines literarischen Schaffens kam das Motiv sehr oft vor, allerdings nur in scharf satirischen, ironischen Erzählungen. Und dieser satirisch-ironische Zug ist es, der die früheren Werke von "Marbot“ unterscheidet; jenen dient nämlich die Fälschung nur als Stoff für eine satirische Beschreibung, während sie bei diesem, in einem keineswegs für Satire zu haltenden Text stehend, auf eine mit dem Inhalt des Werkes zutiefst zusammenhängende Weise konsequent gefordert und determiniert ist."Marbot“ wind eine "fiktive Biographic“ genannt. Worin liegt der Unterschied zwischen fiktiver Biographie und bloßer Fiktion oder Erzählung? In der Gattung Biographie hat sich Hildesheimer bisher schon versucht, und ein erfolgreiches Ergebnis ist eben sein "Mozart“. Weil er aber in diesem Werk eine große Berühmtheit behandelt, kann er nicht urchin, den Meister nur auf der Basis der bereits in großer Zahl existierenden Materialien zu beschreiben. Bei "Marbot“ wählt er dagegen zum Objekt biographischer Darstellung eine Kunstfigur, damit es ihm ermöglicht werde, die bei "Mozart“ notwendigerweise fehlende Konsequenz und Folgerichtigkeit durchzuführen, und somit die Einschränkungen eines Biographen zu überwinden. So ist hier das Leben einer Person gefälscht, die nicht existiert. Man könnte auch sagen, daß hier der Autor sogar eine Wirklichkeit gefälscht hat. Was ist aber die Wirklichekit bei Hildesheimer? Er hat einmal mit G. Eich gesagt, daß Wirklichkeit keine Voraussetzung der Literatur, sondern deren Ziel ist, und daß man infolgedessen Romane nicht mehr schreiben kann, die die Wirklichkeit unbedingt vorraussetzen. Zwischen Wirklichkeit und Fiktion ist also von vornherein kein fester Unterschied; die Schwelle, die die beiden von einander trennt, kann allmählich verwischt werden. Mit dem Fälschungsmotiv hat Hildesheimer geradezu darauf gezielt. Je vollkommener gefälscht wird, desto mehr verliert das Echte Wert und Gültigkeit, während das Gefälschte um so wertvoller und gültiger wird. Wegen des Abscheus vor Schrecken und Unerträglichkeit der existierenden Wirklichkeit will der Schriftsteller sie ungültig machen kraft einer gefälschten, von ihm dargebotenen Wirklichkeit. In diesem Sinne ist das Buch "Marbot“ nicht nur die Flucht aus der Gegenwart, wie der Autor selbst erklärt, sondern auch die Flucht aus der Wirklichkeit in eine fiktive Welt.Indem er eine reine Fikton "Marbot“ schreibt und dennoch darauf besteht, es sei keine Fiktion, deklariert er das Ende der Fiktionen; so völlig in Widerspruch stehen seine Tat und Aussage.
2 0 0 0 OA 米麹を添加した芋焼酎粕飲料の生理作用(第2報)生体防御能亢進効果について
- 著者
- 池田 浩二 中野 隆之 米元 俊一 藤井 信 侯 徳興 吉元 誠 倉田 理恵 高峯 和則 菅沼 俊彦
- 出版者
- Brewing Society of Japan
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.11, pp.875-881, 2012 (Released:2017-12-15)
- 参考文献数
- 27
「芋焼酎粕飲料(新飲料)」の生体防御能亢進効果に関する試験を行った。新飲料のガン抑制能試験では,サルコーマを接種したマウスに新飲料区の摂取によって腫瘍の重量増加が抑制されており,両者間は5%水準の有意差であり,ガン細胞増殖抑制効果が認められた。このときの脾臓のNK活性はコントロール区に比べて高い値を示し,この両者間では0.1%水準で有意な差が認められ,非常に強いNK細胞活性を示した。新飲料の摂取によって生体防御能が高く維持され,また,新飲料に含まれるポリフェノールの抗酸化作用によっても腫瘍の増殖が抑制されたと考えられた。