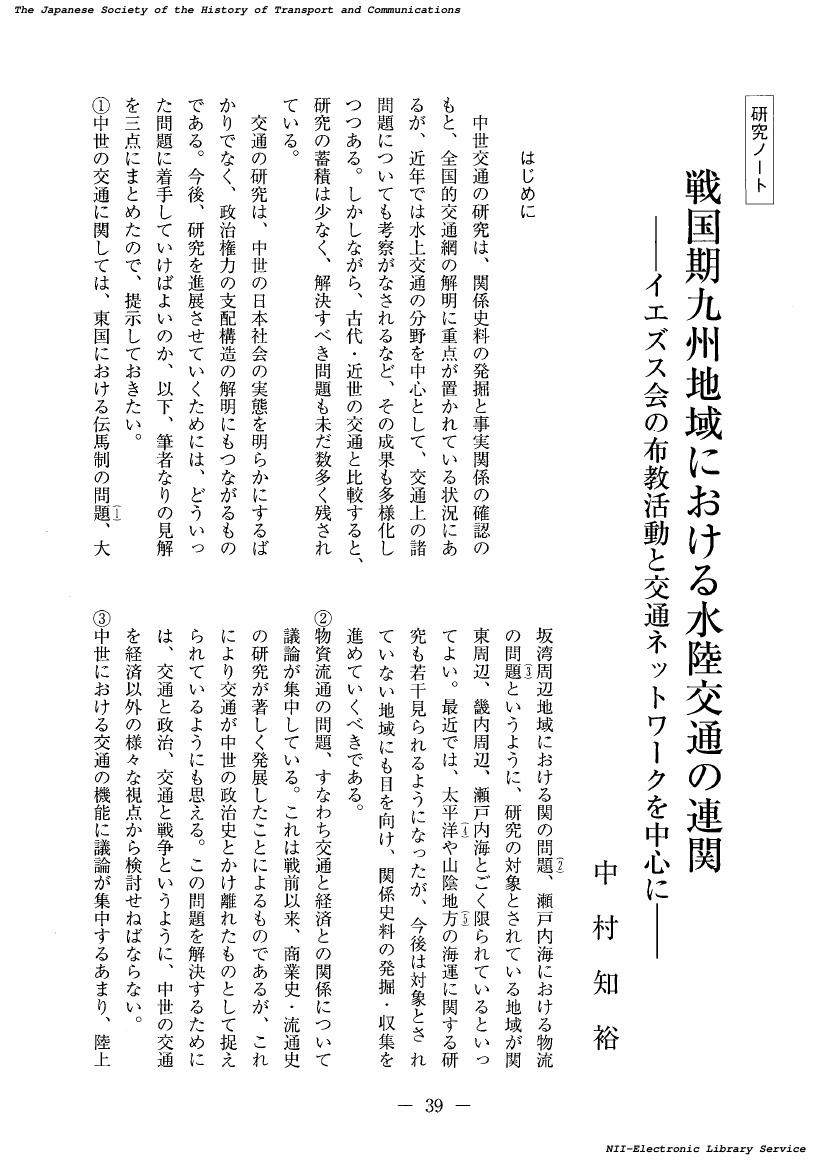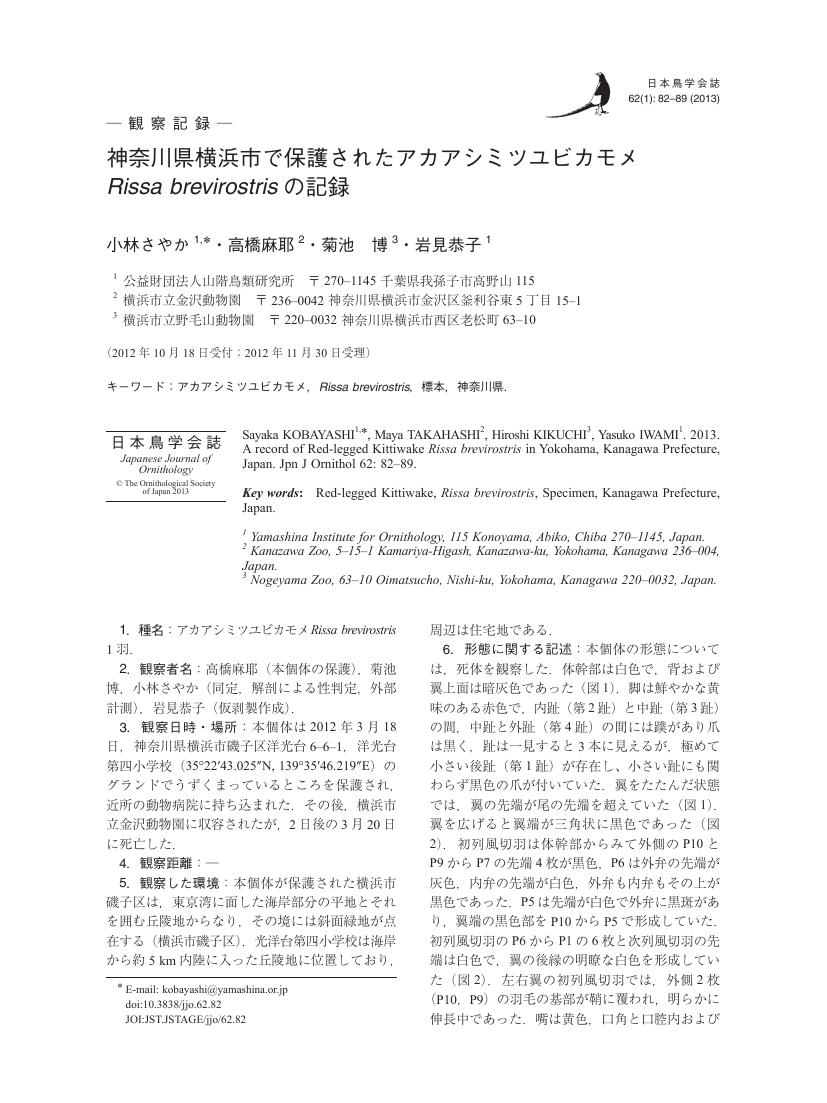2 0 0 0 OA 年齢・身体特性・ブラの種類が動作時の胸部動態・着装感に及ぼす影響
- 著者
- 薩本 弥生 丸田 直美 斉藤 秀子 諸岡 晴美
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.80-89, 2017-01-25 (Released:2017-01-27)
- 参考文献数
- 9
ブラジャー着装時のズレ防止や防振性の観点から,動作時の胸部動態や着装感に年齢・身体特性・ブラの種類が及ぼす効果を明らかにするために以下の実験を行った.被験者は若年群9 名(19-22 歳),中年群6 名(40-62 歳)を対象とした.胸部の身体特性を明らかにするため三次元画像解析による身体形状,胸部圧縮変形量,超音波画像診断による脂肪厚,衣服圧を計測した.振動やズレを計測するためにハイスピードカメラによる三次元動作解析を行った.ブラの着装条件は,補整ブラのワイヤ有とワイヤ無,スポーツブラ,ノーブラの4 種,運動は前方挙上(180˚)である.ハイスピードカメラによる三次元動作解析により動作時の乳頭点では,補整ブラよりスポーツブラの振動抑制効果が高く,中年群は若年群より振動が大きくブラによる差が小さいこと,中年群では脂肪厚が厚くカップサイズが大きい人ほど振動もズレも大きいこと,若年群では胸部の圧縮変形量が小さい人ほど振動が小さいことが明らかとなった.動作時の衣服圧は乳頭位とサイドパネルではスポーツブラが補整ブラよりも有意に小さいが,下部胸囲では逆だった.動作後の着装感評価でズレ感は振動感および快適感に相関があった.動作時には適度に下部胸囲位を圧迫したブラは振動やズレを抑えるため快適と感じると考えられる.
2 0 0 0 OA 骨髄移植の歴史
- 著者
- 正岡 徹
- 出版者
- 一般社団法人 日本造血細胞移植学会
- 雑誌
- 日本造血細胞移植学会雑誌 (ISSN:21865612)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.24-30, 2018 (Released:2018-01-15)
- 参考文献数
- 9
1960年代の白血病の死亡率は100%であった。我々は白血病が治るとは夢にも思わず,苦痛を少なく,見送ることが治療目標であった。大阪成人病センターで1963年成人急性白血病の治癒例を経験し,白血病治療の希望が生まれた。化学療法での効果が不十分で骨髄移植に進んだ。無菌室,成分採血,抗ウイルス剤,抗真菌剤,免疫抑制剤,コロニー刺激因子など多くの新薬の開発導入とともに適合同胞間骨髄移植は1984年から急速に成績が改善した。設立請願署名運動をうけて骨髄バンクが設立され,次いで臍帯血バンクも設立され,これの基盤強化を図る 「移植に用いる造血幹細胞の適切な供給の推進に関する法律」 も制定された。これには多くの方々の善意と支援がささえになっている。
2 0 0 0 OA 1 放射線化学とは—放射線と物質の相互作用—
- 著者
- 鷲尾 方一
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.10, pp.385-393, 2017-10-15 (Released:2017-10-15)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
放射線化学反応は,反応に影響を及ぼす物理定数やパラメータが多数にわたり,さらに放射線の種類によっても反応の初期の活性種の分布等が異なるため,その完全な理解のためには非常に複雑でかつ高度な知識が必要となる。そのため,この分野の研究者以外からみると,汚い科学という汚名を着せられたりもしてきた。しかし,放射線を使った産業,医療等への応用技術が大きく広がっている現在では,放射線化学の全知識を動員した反応への理解が極めて重要な状況を迎えている。放射線化学研究に求められる要請はますます深まるものと考えられる。本稿ではできる範囲で、この複雑な放射線化学の体系を概観した。
2 0 0 0 OA 雲仙普賢岳の火山災害における被災者対策に関する調査研究
- 著者
- 高橋 和雄 藤井 真
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.567, pp.53-67, 1997-06-20 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 10
地震, 風水害などの一過性の災害と異なって, 火山災害は長期化する特性をもつ. 火砕流に対して人命を守るために, 市街地で初めて警戒区域が設定された. わが国の災害対策は主として一過性の災害応急対策および被災者対策を対象としているために雲仙普賢岳の火山災害では被災者対策, 住宅対策, 生活再建計画などに多くの教訓と課題が生じた. 行政は, 現行法の拡大解釈および弾力的運用による21分野100項目の自立支援対策, (財) 雲仙岳災害対策基金および市町の義援金基金等によるきめ細かい被災者対策を行った. しかし, 災害対策システムの見直しなどの根本的な課題の解決はまだこれからである, 本報告では, 雲仙普賢岳の火山災害における被災者対策をまとめている.
2 0 0 0 OA 十五・十六世紀大友氏の対外交渉
- 著者
- 鹿毛 敏夫
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.2, pp.153-190, 2003-02-20 (Released:2017-12-01)
The Otomo family (大友氏), which dominated a large part of northern Kyushu (九州) had a firm intention to trade in Southeast Asia. The Muromachi shogunate (室町幕府) ordered them to remit sulfur for export. Then Otomo Ujitoki managed two sulfur mines in the mountain district of Bungo (豊後). Otomo Chikayo expanded the mining business geographically, and built a big ship called the "Kasuga-maru (春日丸)". The Otomos dispatched trade ships to Korea, China, the Ryukyus (琉球), and several countries of Southeast Asia. In particular, Otomo Yoshishige and Ouchi Yoshinaga, who were brothers, dispatched a fleet to China for trade, but they were considered as smugglers by the government. They went to the coastal areas of the South China Sea, and traded with the merchants who passed through there.
2 0 0 0 OA 戦国期九州地域における水陸交通の連関 : イエズス会の布教活動と交通ネットワークを中心に
- 著者
- 中村 知裕
- 出版者
- 日本学術会議協力学術研究団体 交通史学会
- 雑誌
- 交通史研究 (ISSN:09137300)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.39-52, 2006-08-22 (Released:2017-10-01)
2 0 0 0 OA 慢性疾患患児を育てる母親の心理的適応モデルの検証
- 著者
- 扇野 綾子 中村 由美子
- 出版者
- 一般社団法人 日本小児看護学会
- 雑誌
- 日本小児看護学会誌 (ISSN:13449923)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.3, pp.1-9, 2014 (Released:2016-12-09)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 3
本研究の目的は、慢性疾患患児を育てる母親の心理的適応の構造の特徴について明らかにすることである。 病児の母親247名と健康児の母親332名を対象に、自記式質問紙調査を行った。心理的適応に関連する要因として精神的健康度、コーピング、レジリエンスを測定し、分析は記述統計と平均値の差の検定の後、共分散構造分析を用い母親の心理的適応モデルを作成した。 各尺度の得点を比較した結果、病児の母親は健康児の母親に比べて精神的健康度が低く、レジリエンスの 「I AM」 「I WILL/DO」、コーピングの 「肯定的解釈」 が有意に低かった。共分散構造モデルについて、子どもの疾患の有無による多母集団の同時分析を行った結果、病児の母親の心理的適応を構成する要因では 「自信」 の影響が大きく、『柔軟な力』を構成する 「楽観視」 と 「こころのゆとり」 のパス係数が高かった。 これらの結果より、病児の母親に対しては育児を承認し、長期的な視点をもち関わるなど支援の方向性の示唆が得られた。
2 0 0 0 OA 頭部FLAIR 画像におけるpackage 数がコントラストに及ぼす影響
- 著者
- 小林 明日香 渋川 周平 高野 晋 室 伊三男
- 出版者
- 公益社団法人 日本放射線技術学会
- 雑誌
- 日本放射線技術学会雑誌 (ISSN:03694305)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.10, pp.1180-1185, 2018 (Released:2018-10-20)
- 参考文献数
- 12
We have found that the number of packages influences contrast for brain tissue signals on fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR). The purpose of this study was to evaluate the contrast of white and gray matters by changing the number of packages. In a volunteer study (n=8), FLAIR images were obtained with the various number of packages (number of package=2, 3, 4, 5). We investigated the same imaging condition at both 1.5 and 3.0T. The signal intensity of white and gray matters in all volunteers was increased as increasing the number of packages. Moreover, the contrast ratio between white and gray matters was slightly decreased. In our conclusion, the contrast between the gray and white matters on FLAIR was influenced by the number of packages.
2 0 0 0 OA 競技中における気持ちが切れることの防止要因の検討
- 著者
- 来間 千晶 小川 茜 関矢 寛史
- 出版者
- 日本スポーツ心理学会
- 雑誌
- スポーツ心理学研究 (ISSN:03887014)
- 巻号頁・発行日
- pp.2019-1814, (Released:2019-04-27)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2
The purpose of our study was (1) to clarify the elements and mechanisms of loss of spirit (LOS), and the ways to prevent LOS during competition, and (2) to identify the factors that prevent LOS. We interviewed 18 athletes and analyzed their interview transcripts by creating tags and categories. We divided the text of each transcript into text segments (tags) containing information about LOS or ways to prevent LOS. We then gathered tags with similar meanings and labeled the cluster of tags (categories) to briefly indicate the topic (Côté et al., 1993). Results revealed that the phenomenon of LOS had the following three phases: (1) cause of LOS (e.g., game situations, negative emotions), (2) condition of LOS (e.g., poor concentration, losing the will to fight, negative game situations), and (3) response after the game (e.g., undesirable result). The phenomenon of preventing LOS had the following five phases: (1) cause of nearly experiencing LOS (e.g., game situations, negative emotions), (2) condition of nearly experiencing LOS (e.g., decrease of concentration, losing the will to fight), (3) opportunity to prevent LOS (e.g., positive words and actions of others, heightening the fight), (4) condition after preventing LOS (e.g., improvement of performance, emergence of positive emotions), and (5) response after the game (e.g., evaluation of the game). Furthermore, a comparison of these phenomena revealed that LOS may be prevented by high levels of motivation before the game, positive words and actions of others, keeping the fight, reframing one’s thoughts, improving the game situations, and preserving stamina.
2 0 0 0 OA 審美性評価のための三次元計測装置を用いたブラジャー着用時の背部シルエットの定量化
- 著者
- 村﨑 夕緋 諸岡 晴美 渡邊 敬子
- 出版者
- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会
- 雑誌
- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.248-254, 2019-03-25 (Released:2019-03-25)
- 参考文献数
- 8
本研究では,三次元計測装置を用い,審美性に影響を及ぼす背部体表面の凹凸を定量化することを目的とし,30 歳代および60 歳代の被験者を用い,数種のデザインの異なる補整ブラを試料として実験を行った. はじめに,正中矢状面と肩峰点を通る前頭面との交線から放射状に背部の垂直断面を算出し,体表面の凹凸が最も明瞭に表れる部位が後ろ正中線から70°~75°の範囲であることを捉えた.後腋点を通る垂直断面で中心から体表面までの水平距離をL とし,ヌード時からの差をへこみ量(δ)と定義し,ブラの上辺および下辺テープ部分の衣服圧とδとの関係を検討し,δが衣服圧に依存していることを確認した.また,重回帰分析により,δが衣服圧および体表面の圧縮変形量と有意な関係をもつことが立証された.以上の結果から,δはブラ着用時の背部シルエットの凹凸による審美性の低下を最小にするブラの圧設計のための指標として有用であろうと結論付けられた.
2 0 0 0 OA 前頭葉の機能解剖と神経心理検査 : 脳賦活化実験の結果から
- 著者
- 佐藤 正之
- 出版者
- 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会
- 雑誌
- 高次脳機能研究 (旧 失語症研究) (ISSN:13484818)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.227-236, 2012-06-30 (Released:2013-07-01)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 1 1
前頭葉の機能解剖と前頭葉機能障害の自験例を呈示し, 前頭葉機能の測定に用いられる神経心理検査について frontal assessment battery (FAB) を中心に述べた。前頭葉は穹窿部, 眼窩面, 内側面に分けられ, それぞれの部位の障害により特徴的な症状を示す。いわゆる前頭葉機能検査には, Stroop test, 語想起, Trail Making Test, Wisconsin Card Sorting Test (WCST) , FAB などがあり, 脳賦活化実験により各々の検査の施行時に活性化する脳部位が調べられている。FAB は近年臨床場面で頻用されているが, FAB 低得点=前頭葉機能障害では必ずしもないことに注意しなければならない。
2 0 0 0 OA 特異的読字障害児の音読における視線の特徴
- 著者
- 北條 彰 田角 勝 阿部 祥英 花岡 健太朗 小林 梢 板橋 家頭夫
- 出版者
- 昭和大学学士会
- 雑誌
- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.5, pp.598-606, 2016 (Released:2017-03-16)
- 参考文献数
- 20
特異的読字障害は学習障害の一つであり,知的障害がないにもかかわらず,読字を苦手とする.近年の研究では,文字の音声化や単語や語句をひとまとまりとして認識することの障害と考えられている.今回,特異的読字障害の児童が読字をする際の視線を分析し,読み方の特徴を評価した.対象は,読字障害群(17人),ADHD(注意欠陥多動障害)群(10人),コントロール群(12人)の児童である.対象の児童に音読検査課題を実施し,読み飛ばしと読み誤りの回数を測定した.同時に音読検査課題中の視線の動きをTobii社製の眼球運動計測・視線追跡装置(アイトラッカー)を用いて,注視点の数(視線を動かした数)や注視点の大きさ(視線が停滞した時間)を比較し検討した.1.読み飛ばし,読み誤りともに読字障害,ADHD,コントロールの順に回数が多い傾向があった.2.4種類の音読検査課題において,読字障害群の注視点数がコントロール群の注視点数よりも有意に多かった(p<0.01).読字障害の児童の視線の動きをアイトラッカーで可視化することは,読字障害の児童がどのように読字に困難を伴っているかを理解するために有用である.
2 0 0 0 OA 開頭腫瘍摘出術後に前庭機能障害を呈した中耳悪性腫瘍の一例
- 著者
- 谷内 涼馬 山本 浩基 田代 桂一 道広 博之
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0906, 2015 (Released:2015-04-30)
【目的】聴覚器の悪性腫瘍は頭頸部悪性腫瘍の1%前後とまれな疾患である。中耳悪性腫瘍に対する腫瘍摘出術後の理学療法に関する報告は見受けられず,その経過は不明である。そこで今回,中耳悪性腫瘍に対する腫瘍摘出術後に前庭機能障害を呈した症例の理学療法経過を報告する。【症例提示】70歳代後半,女性。ADLは自立。手術を目的に当院へ入院され,左側頭開頭腫瘍摘出術施行。悪性所見を伴った骨浸潤を認めたため,三半規管は摘出された。術後より悪心・嘔吐,頭位変換に伴う回転性のめまいを認め,歩行時のふらつきが強く自立歩行困難であった。術後3日より,バランス機能改善目的で理学療法開始となる。【経過と考察】理学療法は平行棒内歩行より開始し,術後1週のFunctional Balance Scale(FBS)は15点であった。術後3週までは悪心・めまいが強く,現症を助長する急激な頭位変換に留意した。十分な上肢支持の下,side stepやtandem gaitなどを中心に実施。徐々に悪心・めまいが治まり,術後4週より手放しでの練習に移行。バランス機能も改善を認め,cross stepや振り向き動作を含むback gaitも実施。歩行については病棟内自立となった。術後6週よりダイナミックなバランス練習を開始。術後9週のFBSは51点となり,術後14週で自宅退院となった。一側前庭器官が不可逆な損傷を受けると,中枢前庭系には神経機能の左右差を是正する回復機構(前庭代償)が働く。しかし,健側前庭覚への入力停滞・遅延は前庭眼反射や前庭脊髄反射の低下を惹起し,前庭代償が十分に働かない。本症例では術後早期からバランス練習を実施し,健側前庭覚への入力を継続した。また,現症とバランス機能に応じて練習難易度を高め,前庭代償の停滞を防いだことも機能改善に寄与した可能性が考えられた。急性期の前庭機能障害に対する理学療法では,現症の回復時期に応じて練習難易度を変化させ,前庭代償を促進することが肝要であると思われた。
- 著者
- ATSUO IWASAWA YOSHIMI NIWANO TAKAYUKI MOKUDAI MASAHIRO KOHNO
- 出版者
- The Society for Antibacterial and Antifungal Agents, Japan
- 雑誌
- Biocontrol Science (ISSN:13424815)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.107-111, 2009 (Released:2010-01-26)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 18 29
Proanthocyanidin, which consists of (+) catechin, (-) epicatechin and their gallates (15%), (-) epicatechin gallate-dimers, -trimers, and -tetramers (80%), and (-) epicatechin gallate-pentamers, -hexamers, and -heptamers (5%), was evaluated for its antiviral activity against feline calicivirus F9 strain (FCV/F9), which is thought to be a surrogate for noroviruses, and coxsackievirus A7 strain (Cox.A7), which was selected as a representative enteric virus. To achieve a viral inactivation rate of 99% or greater after contact for 10 sec., at least 1 mg/ml and 10 mg/ml of proanthocyanidin were required against FCV/F9 and Cox.A7, respectively. Although the antiviral mechanism of proanthocyanidin is not clear at present, proanthocyanidin may be an effective disinfectant against enteroviruses such as noroviruses.
2 0 0 0 OA Twitter データを利用した言語地理学的研究の可能性
- 著者
- 峪口 有香子 岸江 信介 桐村 喬
- 出版者
- 計量国語学会
- 雑誌
- 計量国語学 (ISSN:04534611)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.8, pp.537-554, 2019-03-20 (Released:2020-03-20)
- 参考文献数
- 33
本稿では,Twitterからの方言語形抽出結果と,全国の高年層を対象に実施した方言調査の結果および全国の大学生を対象に実施した方言アンケート調査結果等との比較を行い,どのような違いがみられるかについて検討を行った.その結果,全国の高年層で使用される方言がTwitter上で忠実に反映されているとは言い難いが,Twitterデータの結果と大学生を対象としたアンケート調査結果とは,概ね一致した.この点で,Twitterデータをことばの地域差を見出すための資料として十分活用できる可能性があることが判明した.Twitterから得られた言語資料は,伝統方言の地域差の解明とまでは必ずしもいかないにしても,若者世代を中心に用いられる新しい方言や表現形式の分布のほか,「気づかない方言」などの地域差を知る手がかりとして,今後,有効活用が期待される.
2 0 0 0 OA REDUCEを用いたロボットアームの運動学および動力学方程式自動生成システム
- 著者
- 斉藤 制海 梅野 孝治 阿部 健一 桑原 耕治 前川 明寛
- 出版者
- The Institute of Electrical Engineers of Japan
- 雑誌
- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, no.2, pp.89-96, 1989-02-20 (Released:2008-12-19)
- 参考文献数
- 9
2 0 0 0 OA アレルギー性鼻炎による嗅覚障害
- 著者
- 松脇 由典
- 出版者
- 社団法人 におい・かおり環境協会
- 雑誌
- におい・かおり環境学会誌 (ISSN:13482904)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.282-286, 2014-07-25 (Released:2018-02-13)
- 参考文献数
- 23
アレルギー性鼻炎を有する患者の54~67%が嗅覚低下(嗅覚脱失,嗅覚低下)を自覚し,21~45%で嗅覚検査の有意な閾値上昇を認める.嗅覚障害の原因疾患別には鼻副鼻腔炎,感冒罹患後,頭部顔面外傷後の次に頻度が多い.アレルギー性鼻炎の嗅覚障害は,鼻粘膜の肥厚や鼻汁過多に伴う鼻閉によるいわゆる呼吸性嗅覚障害がメインで,既存のガイドラインでの治療法の選択は,少なくとも中等症以上の鼻閉型または鼻閉を主とする完全型が適応となる.比較的予後良好とされ,適切な治療により改善しうる病態と考えられている.
- 著者
- RYAN W. SCHMIDT KEN WAKABAYASHI DAISUKE WAKU TAKASHI GAKUHARI KAE KOGANEBUCHI MOTOYUKI OGAWA JORDAN K. KARSTEN MYKHAILO SOKHATSKY HIROKI OOTA
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- pp.200205, (Released:2020-03-20)
- 被引用文献数
- 1
Verteba Cave (VC) in western Ukraine dates to the Eneolithic period (c. 5500 YBP), and contains the largest collection yet found of human skeletal remains associated with the Cucuteni–Tripolye culture. The subsistence economy of this people was based on agropastoralism, and included some of the largest and densest Middle Neolithic settlement sites in all of Europe. To understand further the evolutionary history of the Tripolye people, we examined population genetics patterns in mitochondrial DNA from ancient human remains excavated from VC chambers. From five commingled and secondary burial sites within the cave, we obtained 368 bp mtDNA HVR1 sequences from 22 individuals assignable to eight haplogroups: H (three haplotypes), HV (two haplotypes), W, K, and T. Overall nucleotide diversity is low (π = 0.00621). The two largest samples, from Chamber G3 and Site 7, were significantly differentiated with respect to haplotype composition: G3 (n = 8) is dominated by haplotype W (π = 0), whereas Site 7 (n = 15) is dominated by H haplotypes (π = 0.00439). Tajima’s D as an indication of population expansion was not significantly negative for the complete sample (D = –1.37) or for sites G3 (D = –0.973) and 7 (D = –1.35), which were analyzed separately. Individuals from the Tripolye culture buried at VC c. 5500 YBP had predominantly haplogroup H and related haplotypes. This contrasts with predominantly haplogroup U individuals in preEneolithic peoples from the same area, which suggests lack of genetic continuity in a site that has been dated to the Mesolithic. Peoples of the Tripolye culture are more closely related to other early European farmers than to Mesolithic hunter-gatherers and/or preEneolithic cultures.
2 0 0 0 OA 出生率低下をどのようにとらえるか?
- 著者
- 廣嶋 清志
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.163-183, 2001-10-31 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 18
近年の合計出生率低下について,夫婦出生率低下が寄与していないという有力な見解が普及しているが,本研究はこの見解を生み出した年齢別有配偶出生率AMFRを用いた要因分解法を批判した。 コーホートの年齢別初婚率と結婚期間別夫婦出生率によって年齢別有配偶出生率AMRFを計算するモデルを基にして,コーホートの年齢別初婚率と結婚期間別夫婦出生率の水準と分布がそれぞれ変化する4つのシミュレーションによって,年次別合計出生率低下を年齢別有配偶率と年齢別有配偶出生率による要因分解の結果を観察した。その結果,初婚率分布の変化(晩婚化または早婚化)が生じていない場合のみ,その要因分解は適切な結果をもたらすが,初婚率分布が遅れると夫婦出生率に変化はないのにもかかわらず,年齢別有配偶率のみが低下をもたらし,年齢別有配偶出生率AMFRは上昇の効果をもつという結果となり,誤った解釈を生むことを明らかにした。 この問題はより一般的に,第1の行動を前提として第2の行動が生じる場合に,第1の行動経験者について第2の行動を年齢によって分析を行う際の注意点として一般化される。