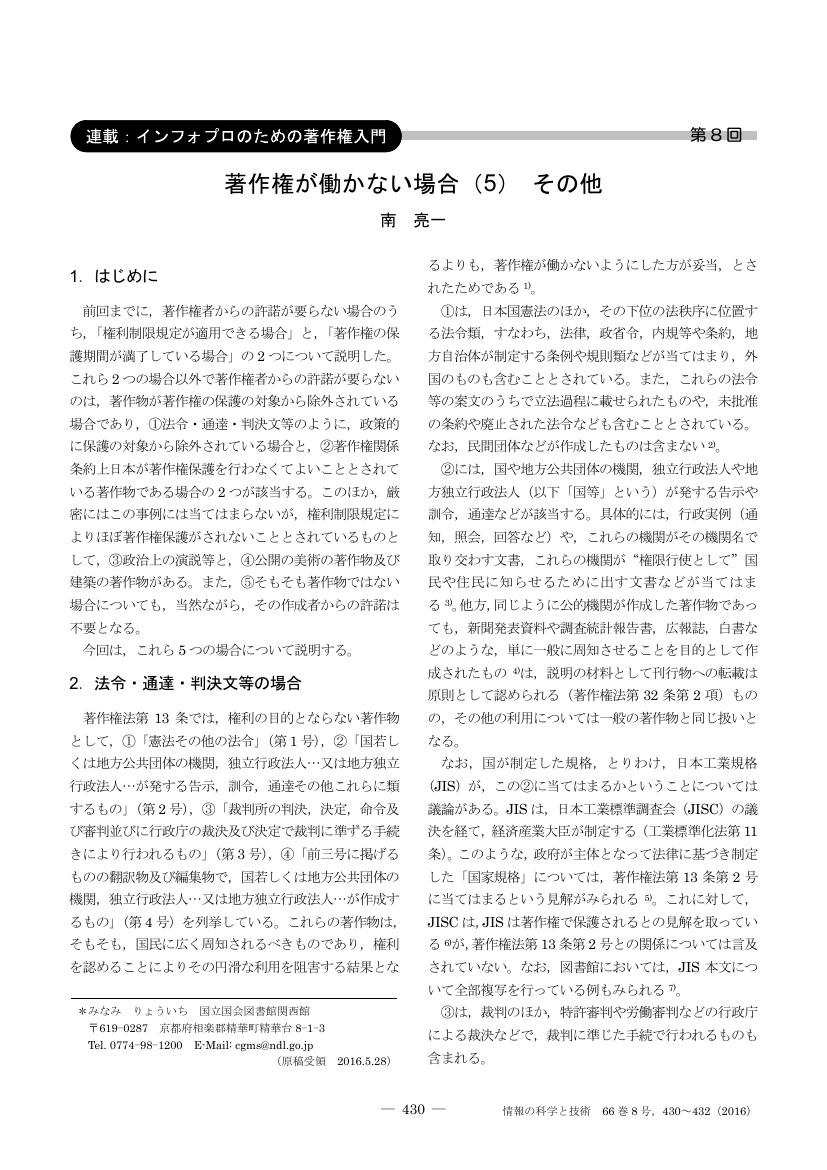58 0 0 0 OA ウィキペディアの基本的な編集方法と考え方 間違いを正しく編集する
- 著者
- 日下 九八
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.7, pp.481-488, 2012-10-01 (Released:2012-10-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1 1
本稿では,ウィキペディアの簡単な編集方法を解説することで,参加への障壁を取り除くことを試みる。ごく単純な間違いの修正,アカウントの登録とその取り扱い,自分自身または自分に密接に関わりのある記事の編集を扱う。
58 0 0 0 OA 競馬とプロスペクト理論:微小確率の過大評価の実証分析
- 著者
- 小幡 績 太宰 北斗
- 出版者
- 行動経済学会
- 雑誌
- 行動経済学 (ISSN:21853568)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.1-18, 2014 (Released:2014-06-19)
- 参考文献数
- 16
競馬の馬券市場においては,「本命–大穴バイアス(favorite–longshot bias)」という良く知られた現象がある.これは当たる確率が極めて低い大穴馬券への過剰な人気を指すものだ.このバイアスは,微小確率の過大評価傾向としてプロスペクト理論から説明できる.本論文では,近年の日本の馬券市場に特徴的な三連単馬券に関して検証を行い,より大穴な馬券ほど過剰に人気が集まる傾向にあるという大穴バイアスの存在が確認された.この結果は従来の研究と異なり,外れ馬券を含めた全ての馬券データを網羅的に分析し,投票行動の推計ではなく実際の得票数を用いた分析である点で,質的に新しい結果といえる.本研究は,微小確率に対する経済主体の実際の行動結果を表すデータを用いた分析であり,行動バイアスの実証分析として大規模なデータを用いた研究となることで,行動経済学の幅広い領域での実証研究の可能性について示唆を与える.
58 0 0 0 OA 天皇海山列 ―発見・命名のいきさつと生成の謎―(紹介)
- 著者
- 杉山 明
- 出版者
- 地学団体研究会
- 雑誌
- 地球科学 (ISSN:03666611)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.72-79, 2005-01-25 (Released:2017-07-14)
58 0 0 0 OA The Relationship between Seating Locations and Instructor-Student Entrainment in a Classroom
- 著者
- Masashi KOMORI Chika NAGAOKA
- 出版者
- Japan Society of Kansei Engineering
- 雑誌
- Kansei Engineering International Journal (ISSN:21857865)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.4, pp.179-182, 2012 (Released:2012-12-13)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
In face-to-face communication, the listener's body movements are often observed to occur nearly simultaneously with changes in the speaker's voice pattern. This synchronization between speaker and listener is called entrainment. The present study investigated the relationship between classroom seating positions and instructor-student entrainment. Four university instructors individually gave 60-minute lectures to classes of 36-64 students in classrooms. The body movements of the students were captured using a video camera, and the voices of instructors were recorded via a microphone. For each pixel, the covariance between the sound level changes of a instructor's voice and the power of the brightness fluctuations of the pixel was calculated as an index of the entrainment level of each location in the classroom. The results suggested that students sitting in the middle row of the middle column in the classroom showed higher entrainment levels. Moreover, changes of entrainment level were found to reflect changes in student's interest in the lecture.
58 0 0 0 OA アイヌ人骨の自然人類学的研究とその課題
- 著者
- 篠田 謙一
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.9, pp.9_83-9_87, 2011-09-01 (Released:2012-01-24)
58 0 0 0 OA インフォプロのための著作権入門 第8回 著作権が働かない場合(5) その他
- 著者
- 南 亮一
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.8, pp.430-432, 2016-08-01 (Released:2016-08-01)
58 0 0 0 OA 音響信号処理における位相復元
- 著者
- 矢田部 浩平
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.25-36, 2021-07-01 (Released:2021-07-01)
- 参考文献数
- 124
位相復元は,複素数として表現されたデータの絶対値のみから,元の複素信号を復元する技術である.絶対値を取ることによって失われるのは偏角の情報なので,偏角を復元すれば元の信号を得ることができる.複素信号の偏角は位相とも呼ばれるので,位相復元という名前がついている.位相復元は,光学分野では位相回復と呼ばれて古くから研究されており,そのため光学計測に則った問題設定や手法が中心的に研究されている.一方,音響信号処理においても位相復元が研究されているが,光学分野とは前提が異なるので,音響信号に対する特別な手法も考えられている.本稿では,前半で光学分野も含めた歴史的背景や一般の位相復元手法について概説した後に,後半で音響信号処理における位相復元についても述べる.特に,音響信号の短時間Fourier変換に基づく時間周波数領域の位相復元を扱う.
58 0 0 0 OA 内科プライマリ・ケア医の知っておきたい“ミニマム知識” 医学的に説明困難な身体症状
- 著者
- 宮崎 仁
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.1, pp.188-191, 2009 (Released:2012-08-02)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
58 0 0 0 OA ロボット工学を取り巻くメディア・コミュニケーションの動向
- 著者
- 森山 和道
- 出版者
- 一般社団法人 日本ロボット学会
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.124-129, 2011 (Released:2011-04-16)
58 0 0 0 OA 底生動物から見た小水力発電による減水が渓流生態系に及ぼす影響評価
- 著者
- 大山 璃久 佐藤 辰郎 一柳 英隆 林 博徳 皆川 朋子 中島 淳 島谷 幸宏
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集G(環境) (ISSN:21856648)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.6, pp.II_135-II_141, 2019 (Released:2020-03-16)
- 参考文献数
- 22
小水力発電は有望な分散型の再生可能エネルギーであり,日本各地への導入が期待されている。小水力発電は環境負荷が小さいと考えられているが,減水区間が生じるため,河川生態系の影響を正しく評価しておく必要がある.本研究では,小水力発電による減水が渓流生態系にどのような影響を与えるのかを定量的に明らかにするため,底生動物を指標として渓流のハビタット類型ごとに減水の影響度合いを評価した.研究の結果,加地川では,全ての渓流ハビタットにおいて減水による底生動物個体数,分類群数,及び生物の群集構造への影響は認められなかった.加茂川では,一部ハビタットにおいて減水区間の底生動物個体数及び分類群数が減少しており,生態系の変質が示唆された.原因として,砂防堰堤から取水されるため,土砂供給量減少が考えられた.
58 0 0 0 OA ため池の管理形態が水棲外来動物の分布に及ぼす影響
- 著者
- 西川 潮 今田 美穂 赤坂 宗光 高村 典子
- 出版者
- 日本陸水学会
- 雑誌
- 陸水学雑誌 (ISSN:00215104)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.261-266, 2009 (Released:2011-02-16)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 12
外来種はため池生態系の生物多様性を大きく減少させる主要なストレス要因である。ため池は,氾濫原湿地を棲み場とする生物の避難場所を提供することから,生物多様性の宝庫となっており,従来の灌漑用途だけでなく,生物多様性を含む多面的機能に配慮した管理法が問われている存在である。本研究では,兵庫県の64のため池を対象として社会調査と野外調査を行い,ため池の管理形態が水棲外来動物の出現に及ぼす影響を考察した。野外調査の結果,外来動物では,ブルーギル(Lepomis macrochirus)とアメリカザリガニ(Procambarus clarkii)が出現率およびバイオマスの面でもっとも優占していた。一般に外来魚の駆除対策として池干しが行われるが,予想に反し,ブルーギルの出現は池干しの有無には左右されなかった。一方,アメリカザリガニは池干しをする池に多く出現することが明らかになった。ブルーギルは,ダム水および農業排水を主要な水源とするため池で多く出現することから,ダム湖や用排水路などから再移住してくるものと考えられる。ブルーギルとアメリカザリガニの(排他的)分布が種間関係によって決まっている場合には,一方を駆除すると他方の個体数が増える危険性がある。
- 著者
- Tadafumi Sugimoto Atsushi Mizuno Takuya Kishi Naoya Ito Chisa Matsumoto Memori Fukuda Nobuyuki Kagiyama Tatsuhiro Shibata Takashi Ohmori Shogo Oishi Jun Fuse Keisuke Kida Fujimi Kawai Mari Ishida Shoji Sanada Issei Komuro Koichi Node
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-20-0302, (Released:2020-04-29)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 20
Background:Despite the rapidly increasing attention being given to Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection, more commonly known as coronavirus disease 2019 (COVID-19), the relationship between cardiovascular disease and COVID-19 has not been fully described.Methods and Results:A systematic review was undertaken to summarize the important aspects of COVID-19 for cardiologists. Protection both for patients and healthcare providers, indication for treatments, collaboration with other departments and hospitals, and regular update of information are essentials to front COVID-19 patients.Conclusions:Because the chief manifestations of COVID-19 infection are respiratory and acute respiratory distress syndrome, cardiologists do not see infected patients directly. Cardiologists need to be better prepared regarding standard disinfection procedures, and be aware of the indications for extracorporeal membrane oxygenation and its use in the critical care setting.
- 著者
- Satoshi Iwata Shinya Murata Shi Rong Han Akira Wakana Miyuki Sawata Yoshiyuki Tanaka
- 出版者
- 国立感染症研究所 Japanese Journal of Infectious Diseases 編集委員会
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- pp.JJID.2016.299, (Released:2016-12-22)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 10
A 9-valent human papillomavirus (HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58) virus-like particle (VLP) vaccine (9vHPV) has been proven highly efficacious in preventing anogenital disease related with vaccine HPV types in a pivotal Phase III study in women aged 16 to 26 years. We report here the results of an open-label phase III study conducted to bridge the findings in women age 16 to 26 years to Japanese girls aged 9 to 15 years. All subjects (n = 100) received a 3-dose regimen of 9vHPV vaccine at day 1, month 2 and month 6. Anti-HPV serologic assays were performed at day 1, month 7, month 12, month 24 and month 30. At month 7 (4 weeks after dose 3), 100% of subjects seroconverted for each vaccine HPV type. Increases in geometric mean titers of anti-HPV 6/11/16/18/31/33/45/52/58 in girls were similar to those in Japanese women aged 16 to 26 years in the pivotal phase III study. Persistence of anti-HPV responses was observed through 2 years after dose 3. In addition, administration of 9vHPV vaccine was generally well tolerated in Japanese girls.
58 0 0 0 OA 日本の第四紀淡水魚類化石研究の現状
- 著者
- 宮田 真也
- 出版者
- 日本古生物学会
- 雑誌
- 化石 (ISSN:00229202)
- 巻号頁・発行日
- vol.105, pp.9-20, 2019-03-30 (Released:2019-04-17)
Quaternary freshwater fish fossils are significant to consider the biogeographical history and evolution of Recent and Neogene freshwater fishes. In the present study, previous studies of Quaternary freshwater fish fossils from Japan are reviewed with the updated geological datum of each fossil bed. In Japan, Pleistocene sediments (e.g. Kobiwako Group) have yielded many pharyngeal teeth of cyprinids as well as spines and bones of siluriformes, which contribute to paleobiogeographical and histological studies of these taxa, although the fossils are fragments. Fish fossils from the Miyajima Formation of Tochigi and the Nogami Formation of Oita could possibly be utilized to calibrate molecular clocks of molecular phylogenetics, because these can be identified at the species level based on the articulated and well-preserved fossil specimens. Studies of fish bones and scales from shell mound remains of the Jomon period revealed the existence of extinct cyprinid groups of present Japan and regional extinction during the Holocene time in Japan. These studies are important to discuss the relationships between the transition of fish fauna and human activities.
58 0 0 0 OA 緊急時対応のための長距離大気拡散計算による放出源推定手法の開発
- 著者
- 古野 朗子 茅野 政道 山澤 弘実
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.229-240, 2006-09-25 (Released:2010-01-21)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 7 7
This paper describes a method of estimating source term, i.e., location, period and amount of atmospheric release of radioactive material in real-time during nuclear emergency. This method consists of: (1) trial simulations of atmospheric dispersions on the possible combinations of these parameters and (2) statistical comparison of model predictions with offsite measurements of air concentrations of radionuclides and/or air dose rates from monitoring stations, to find a set of release condition providing model prediction that fits best to the measurement. A parallel execution method for efficiently processing many possible initial conditions is also developed. The performance of this method is favorably evaluated by a verification study using the dataset from European Tracer Experiment.
58 0 0 0 OA 低線量放射線反復被ばくの発がんへの関与
- 著者
- 大津山 彰
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.175-183, 2016-06-01 (Released:2016-06-14)
- 参考文献数
- 27
2008年HLEG(High Level Expert Group on European Low Dose Risk Research)は低線量影響研究の意義とその重要性を提唱し,発がんも含めて低線量放射線影響研究は国際的関心事となってきている[1,2].我々は長年動物実験を行っているが,放射線発がん実験は動物種の選択や,放射線の種類,量,照射方法など組合せが複雑で,解析もマクロからミクロ,分子生物学分野におよび,線量と効果の関係の目標を定めにくい領域である.我々の実験系では特異的自家発生がんが少ないマウスを選択し,目的の誘発がんとしてマウスで自家発生が希有な皮膚がんを選択した.また被ばくによる他臓器への影響を避け,かつ皮膚限局照射が可能なβ線を用いた.これにより照射部位の皮膚のみをがんの発生部位とし,他臓器の放射線影響を最小限にして長期反復被ばくを可能にし,放射線誘発腫瘍が生じる実験系を作った.照射は週3回反復照射で1回当りの線量を0.5~11.8 Gyまで段階的に線量を設定した.11.8~2.5 Gy線量域ではどの線量でも発がん時期と発がん率に変化はなかったが,この線量域から1.5~1 Gy線量域に1 回当りの線量を下げると発がん率に変化はみられず発がん時期の遅延が生じた.1回当りの線量0.5 Gyではマウスの生涯を通じ照射を続けてもがんは生じなかった.この結果はマウスでは,生涯低線量放射線被ばくを受け続けても生存中にがんが発生しない線量,つまりしきい値様線量が存在することを示している.
58 0 0 0 OA 延性帯地熱系の把握と涵養地熱系発電利用への展望
- 著者
- 村岡 洋文 浅沼 宏 伊藤 久男
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.2, pp.343-362, 2013-04-25 (Released:2013-05-31)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 6 6
Current geothermal power generation from engineered geothermal system (EGS) technologies has two bottle-necks in practical use: one is that the recoverability of injected water is about 50% or less than that in fracture-dominant regions such as Japan, which inevitably requires replenishing large volumes of injected water throughout the power generation operation, and the other is that the injected water raises pore fluid pressures in crustal rocks, causing induced-earthquakes. This paper proposes a new power generation method, which has the potential to resolve these two bottle-necks using EGS technologies in ductile zones. With this method, an artificial brittle fracture reservoir system is completely surrounded by ductile zones at a temperature exceeding 500°C, the presence of which has already been confirmed at the Kakkonda geothermal field, northeastern Japan. The profitability of this method is highly dependent on the depth of drilling, but this concept could dramatically expand exploitable thermal conduction geothermal resources beyond the brittle zones.
58 0 0 0 OA 微生物2次代謝産物生合成の機能的改変による有用物質の生産
- 著者
- 池田 治生 大村 智
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.11, pp.761-771, 1996-11-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 14
- 著者
- Keisuke SASAKI Masayuki HAYASHI Takumi NARITA Michiyo MOTOYAMA Mika OE Koichi OJIMA Ikuyo NAKAJIMA Susumu MUROYA Koichi CHIKUNI Katsuhiro AIKAWA Yasuyuki IDE Naoto NAKANISHI Nobuaki SUZUKI Shigeru SHIOYA Akio TAKENAKA
- 出版者
- (社)日本農芸化学会
- 雑誌
- Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (ISSN:09168451)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.1596-1599, 2012-08-23 (Released:2012-08-23)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 13 6
This study examined the accumulation and tissue distribution of radioactive cesium nuclides in Japanese Black beef heifers raised on roughage contaminated with radioactive fallout due to the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Station on March 2011. Radiocesium feeding increased both 134Cs and 137Cs levels in all tissues tested. The kidney had the highest level and subcutaneous adipose had the lowest of radioactive cesium in the tissues. Different radioactive cesium levels were not found among parts of the muscles. These results indicate that radiocesium accumulated highly in the kidney and homogenously in the skeletal muscles in the heifers.
57 0 0 0 OA 注意欠如・多動症における時間知覚の最新知見
- 著者
- 江頭 優佳 岡田 俊
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.4, pp.109-115, 2020-11-25 (Released:2020-11-25)
- 参考文献数
- 51
In this article, we review the previous findings on relationships between the ability of time perception and pathology of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Time perception deficits are suggested to be the third neuropsychological pathway of ADHD. Even though it is well known that ADHD patients overestimate the time passed, these effects and related mechanisms on ADHD are still unclear according to the complexity of ADHD pathology. While the neural localization related to time perception and ADHD neural dysfunctions related to executive function and reward partially overlap, dysfunction peculiar to time perception is also observed. Furthermore, ADHD and the typical development group may have different relationships between task performance of time perception and executive function systems. In future studies, response for time perception tasks in individuals with ADHD should be examined closely in particular from the perspective of task characters and ADHD complexity.