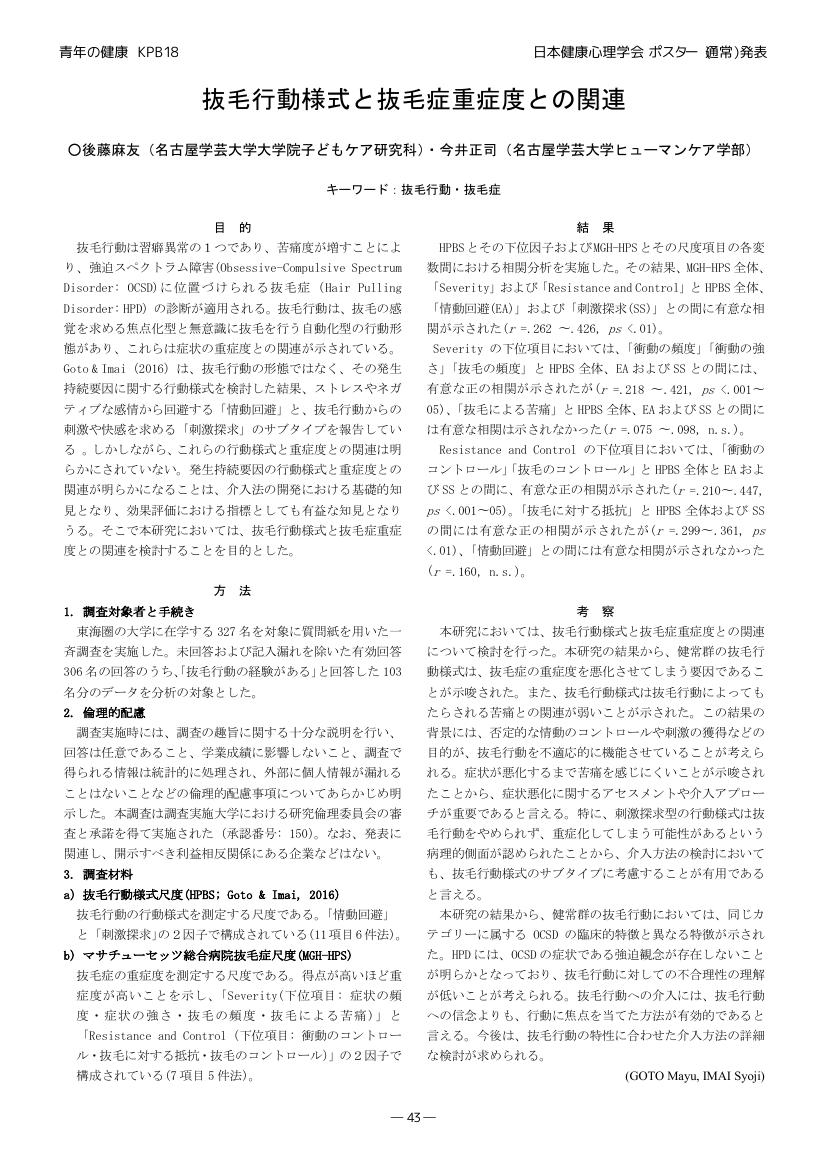2 0 0 0 OA 抜毛行動様式と抜毛症重症度との関連
- 著者
- 後藤 麻友 今井 正司
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 日本健康心理学会大会発表論文集 31 (ISSN:21898812)
- 巻号頁・発行日
- pp.P43, 2018 (Released:2018-08-14)
- 著者
- 今井 正次 赤松 光哉 中井 孝幸 上西 真哉
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.535, pp.107-113, 2000-09-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 9
This paper is aimed abstract the planning points in combined classes as the learnig space by investigation of learning activities . 11 cases in 6 School were investigated and then simulated the learning activity in other learning cases. Learning activities are classified into lecturer, discussion, exercise and practice. Some conclusions are follows; ・In combined classes, teachers and school children devise the layout of their desks and blackboards to keep away from disturb each grade. ・When there are two grades in one classroom, it is agreeable to set up another learning comer for the conversion of learning activities.
2 0 0 0 OA 熟成ろ材の長期保存のためのアンモニア酸化微生物活性に及ぼす温度の影響
- 著者
- 今井 正 出濱 和弥 坂見 知子 高志 利宣 森田 哲男 今井 智 岡 雅一 山本 義久
- 出版者
- 日本水産増殖学会
- 雑誌
- 水産増殖 (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.1, pp.93-100, 2021 (Released:2022-03-20)
- 参考文献数
- 21
本研究の目的は長期間,硝化作用を有する熟成状態のろ材を保存するための安定状態を評価することである。密封して保湿状態にしたろ材のアンモニア酸化活性に及ぼす保存温度の影響を調査した。ろ材のアンモニア酸化活性を25℃で測定した後,これらを海水から取り出してジッパー付き袋に入れて,1~35℃の8段階の温度で180日間管理した。1℃で保存したろ材のアンモニア酸化活性は最初と同様であった。加えて,アンモニア酸化古細菌とアンモニア酸化細菌の現存量は,それぞれ14%と10%でわずかな減少であった。5~20℃で保存したろ材の活性は約50%まで減少した。活性のさらなる減少は25℃以上で保存したろ材で認められた。また,1℃で約3年間保存した場合でも,ろ材の活性が33%残っていることが示された。ゆえに,硝化作用を有する熟成ろ材の長期間保存のためのアンモニア酸化微生物の保持は,設定温度温度内では1℃で最も高かった。
2 0 0 0 「扇の的」考:――「とし五十ばかりなる男」の射殺をめぐって――
- 著者
- 今井 正之助
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.5, pp.54-64, 2014
<p>中学校2年国語「扇の的」は、与一の技量および敵味方が称賛するすばらしさ((『平家物語』巻一一「那須与一」)から、与一を称賛して舞い出た平家方の「老武者」を射殺する場面(「弓流」)を加え、戦の非情さを考えさせることに力点がうつり、その方向に各教科書会社の足並みが揃いつつある。しかし、「老武者」は扇の的を立てた船に乗り組み、義経狙撃を企む一員であった可能性が高い。善良な老人を冷酷に射殺したと受けとめることは誤っている。また、義経は、敵は一人でも生かしておくわけにはいかない、と考え、与一に射殺を命じた、とみなされている。しかし、『平家物語』の義経の行動原理からはそのような理解は成り立たない。「老武者」が扇が立ててあった場所を占拠して舞を舞い、主役の座を奪うかの行為をしたことに対して、義経は激しく怒り、与一も同じ思いで矢を放った。</p>
2 0 0 0 2020年代の日本の金星探査
- 著者
- 中村 正人 山崎 敦 山城 龍馬 石井 信明 戸田 知朗 二穴 喜文 リメイエ サンジェイ 寺田 直樹 安藤 紘基 神山 徹 佐藤 毅彦 今村 剛 田口 真 林 祥介 堀之内 武 リー ヨンジュ 高木 征弘 今井 正尭 福原 哲哉 杉本 憲彦 樫村 博基 渡部 重十 佐藤 隆雄 はしもと じょーじ 村上 真也 マゴルドリック ケビン 阿部 琢美 廣瀬 史子 山田 学 小郷原 一智 杉山 耕一朗 大月 祥子 ペラルタ ハビエル 高木 聖子 岩上 直幹 上野 宗孝 坂野井 健 亀田 真吾 笠羽 康正 高橋 幸弘 佐藤 光輝 松田 佳久 山本 勝
- 出版者
- 日本地球惑星科学連合
- 雑誌
- JpGU-AGU Joint Meeting 2020
- 巻号頁・発行日
- 2020-03-13
- 著者
- 張 成年 今井 正 池田 実 槇 宗市郎 大貫 貴清 武藤 文人 野原 健司 古澤 千春 七里 浩志 渾川 直子 浦垣 直子 川村 顕子 市川 竜也 潮田 健太郎 樋口 正仁 手賀 太郎 児玉 晃治 伊藤 雅浩 市村 政樹 松崎 浩二 平澤 桂 戸倉 渓太 中畑 勝見 児玉 紗希江 箱山 洋 矢田 崇 丹羽 健太郎 長井 敏 柳本 卓 斎藤 和敬 中屋 光裕 丸山 智朗
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.4, pp.674-681, 2018-07-15 (Released:2018-08-31)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
スジエビには遺伝的に異なる2タイプ(AとB)が知られているが,簡便に判別できるマーカーがない。18S rDNAの塩基配列に基づき,これら2タイプを判別するマルチプレックスPCRアッセイを考案した。日本における本種の分布範囲を網羅する152地点で採集した422個体を分析したところ,各タイプ特有の断片を併せ持つ個体,すなわちヘテロ型は観察されず,AとBタイプは生殖隔離しているものと考えられた。両タイプとも全国的に分布するがAタイプは河川及び湖沼に分布する一方,Bタイプは河川のみで見られた。
2 0 0 0 漬物のかぐわしい香り (特集 漬物 : 発酵、醸される旨み)
- 著者
- 今井 正武
- 出版者
- カザン
- 雑誌
- 食生活 (ISSN:0386989X)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.1, pp.41-45, 2013-01
- 著者
- 今井 正浩
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究. 第II期 (ISSN:00227692)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.244, pp.268-269, 2007-12-26
- 著者
- 甲斐 知彦 鈴木 博和 小井出 桂祐子 松本 芳孝 今井 正裕 Tomohiko Kai Hirokazu Suzuki Keisuke Koide Yoshitaka Matsumoto Masahiro Imai
- 雑誌
- スポーツ科学・健康科学研究 (ISSN:13440349)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.11-18, 2008-03-31
2 0 0 0 IR 再論「拡大EU」 : 新規加盟国のパフォーマンスとユーロの浸透への予見
- 著者
- 今井 正幸
- 出版者
- 日本福祉大学
- 雑誌
- 日本福祉大学経済論集 (ISSN:09156011)
- 巻号頁・発行日
- no.30, pp.37-55, 2005-02-28
2 0 0 0 OA 淡水飼育条件下でのテナガエビ幼生の摂餌機会数と生存の関係
- 著者
- 今井 正 豊田 惠聖 秋山 信彦
- 出版者
- 水産増殖談話会
- 雑誌
- 水産増殖 = The aquiculture (ISSN:03714217)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.133-138, 2004-06 (Released:2011-03-05)
淡水飼育条件下において異なるアルテミアの給餌頻度でテナガエビ幼生を飼育することにより、幼生の摂餌機会数の違いと生残の関係を調べた。淡水湖の諏訪湖、汽水湖の佐鳴湖および河川の太田川に生息するテナガエビの幼生を淡水中でアルテミアを1日1回、2回、4回の3条件の給餌頻度で飼育した。諏訪湖産と佐鳴湖産では1日2回までの給餌ではポストラーバに到達できても20個体中1個体だけであったが、1日4回の給餌にすると繰り返した3回の実験それぞれで20個体中1~5個体がポストラーバに到達した。これに対し、太田川産では給餌頻度にかかわらず、第2ゾエア期へ脱皮する個体すらなかった。淡水湖と汽水湖に生息するテナガエビの幼生は、給餌頻度を増やすことで摂餌機会が増大し、淡水中でもポストラーバまで生残可能となることが明らかとなった。
- 著者
- 今井 正浩
- 雑誌
- 日本醫史學雜誌 (ISSN:05493323)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.385-388, 2012-09-20
- 著者
- 笠嶋 泰 今井 正次
- 出版者
- 一般社団法人日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. E-2, 建築計画II, 住居・住宅地, 農村計画, 教育 (ISSN:13414526)
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, pp.383-384, 2007-07-31
1 0 0 0 OA 糠みそ床の香気成分の生成に関する微生物と温度の影響
- 著者
- 今井 正武
- 出版者
- japan association of food preservation scientists
- 雑誌
- 日本食品低温保蔵学会誌 (ISSN:09147675)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.161-178, 1995-08-31 (Released:2011-08-17)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 OA 発達段階を考慮した注意制御とメタ認知の促進がストレス防御とQOL向上に及ぼす影響
注意制御とメタ認知(detached mindfulness:DM)がストレスに及ぼす影響について、小学生から大学生を対象に調査を行った。多母集団同時分析の結果、年齢が高いほど、注意制御や DMがストレス防御要因になることや、QOLの促進に寄与することが明らかとなり、特に、疲労症状において顕著な結果が示された。これらの結果をもとに、小学生と大学生を対象に、注意訓練課題を実施している際の前頭前野の活動性をNIRSによって測定し、疲労との関連性について検討した。その結果、小学生の疲労は前頭前野が過活動になりやすいことが要因であり、大学生の疲労は沈静化が促進されないことが要因であることが示唆された。
1 0 0 0 OA ある広汎性発達障害児の行動アセスメントにおけるシステム構造分析の試み(資料)
- 著者
- 今井 正司 今井 千鶴子 嶋田 洋徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.1-15, 2008-09-30 (Released:2019-04-06)
行動分析的な観点に基づくアセスメントと支援は、児童の行動を環境に適応させる効果的な方法であることが確認されている。しかしながら、従来型の行動アセスメントにおいては、多面的な問題行動を体系化する方法が確立されていないという問題点がある。そこで本研究では、システム構造分析を用いたアセスメント(システム行動分析)を適用し、多面的な問題行動を"反応階層"や"連鎖構造"からとらえることを試みた。その結果、問題行動の多面性を数量的に把握することが可能となり、効率的な支援を行うためのポイントが示された。最後に、従来型の行動アセスメントの知見を参照しながら、本研究で得られた知見の重要性について考察された。
1 0 0 0 OA 医学から「心身」の科学へ : ヒポクラテス『神聖病論』第14-17節の解釈を中心に
- 著者
- 今井 正浩
- 出版者
- 弘前大学人文学部
- 雑誌
- 人文社会論叢. 人文科学篇 (ISSN:13446061)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.45-65, 2002-02-28
1 0 0 0 OA 心理的構えがアレキシサイミア傾向を媒介した心理ストレスに及ぼす影響
- 著者
- 大村 安寿弥 酒井 志瑞花 杉山 瑞奈 今井 正司
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1EV-139, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
1 0 0 0 OA ギリシアの医学思想における「パンゲネシス」の系譜
- 著者
- 今井 正浩
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.249, pp.22-33, 2009 (Released:2021-08-04)
The Pangenetic theory which holds that sperm comes from all the body seems to have been one of the most remarkable doctrines in Greek biology in the fifth and fourth centuries BC, since Aristotle gives a detailed description of the theory and criticizes it severely. The main sources of information about the Pangenetic theory are several medical treatises in the Hippocratic Corpus. There are only some mentions of it in the extant fragments ascribed to Democritus. It would be probable, therefore, that the theory had the origin of its theoretical form in the tradition of Greek medical science, and then came to the focus of attention among the Presocratic philosophers. Some scholars, on the other hand, claim that Democritus had a decisive role in the formation and development of the theory, which was then taken over by the Hippocratic doctors in their attempt to give a systematic explanation for some of the important genetic issues, such as the inheritance of similarities from parents to their children. It must be kept in mind, however, that Hippocratic doctors thought of particular fluids or humours with their inherent powers (δυναμειs) as the essential constituents of human body. This fact leads us to have an idea that the doctors had a completely different view of matter from the corpuscular theory, although Lesky (1950) and Lonie (1981) assume them to have been almost dependent on the atomism of Democritus. We can conclude that the Pangenetic theory came originally from Greek medical science, and then developed into the most influential doctrine before Aristotle.
- 著者
- 今井 正浩
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.242, pp.78-90, 2007 (Released:2021-08-11)
The Hippocratic treatise De Vetere Medicina (On Ancient Medicine) has been the focus of attention among classical scholars and historians of medicine. The author attacks in ch. 20 doctors and sophists who base their own medical theories and methods on philosophical anthropology taken from the contemporary natural philosophers. Many attempts have been made to elucidate, as opposed to their philosophical inquiry into human nature, the author's way of understanding it, which still remains unclear. I draw attention to the following points to make it clear that the conceptual framework of the author's medical anthropology is different from theirs. Their philosophical inquiry into human nature has its starting point in fundamental element(s), from which human beings were originally formed. The author focuses on human beings as existent in their present states, whose conditions and functions must be investigated through interrelations between them and their external factors, such as foods and drinks. A medical investigation into the interrelations will give us a scientific idea about human body, whose constituents are taken to be a large number of humors, reacting against some external factors and accordingly making us feel pain. This may presuppose that, in the author's medical anthropology, human body is conceptually demarcated as the physical or material aspect of human being, within which all physiological events depending on external factors and the humors take place. In their philosophical anthropology, however, human body doesn't seem to have been clearly conceptualized as such, because our experience of feeling pain should be judged to take place within the actions of the fundamental element(s), which must be supposed to constitute our cognitive self.