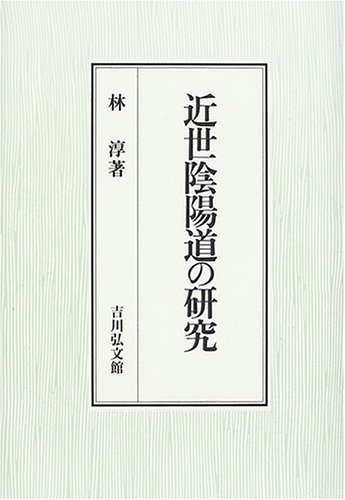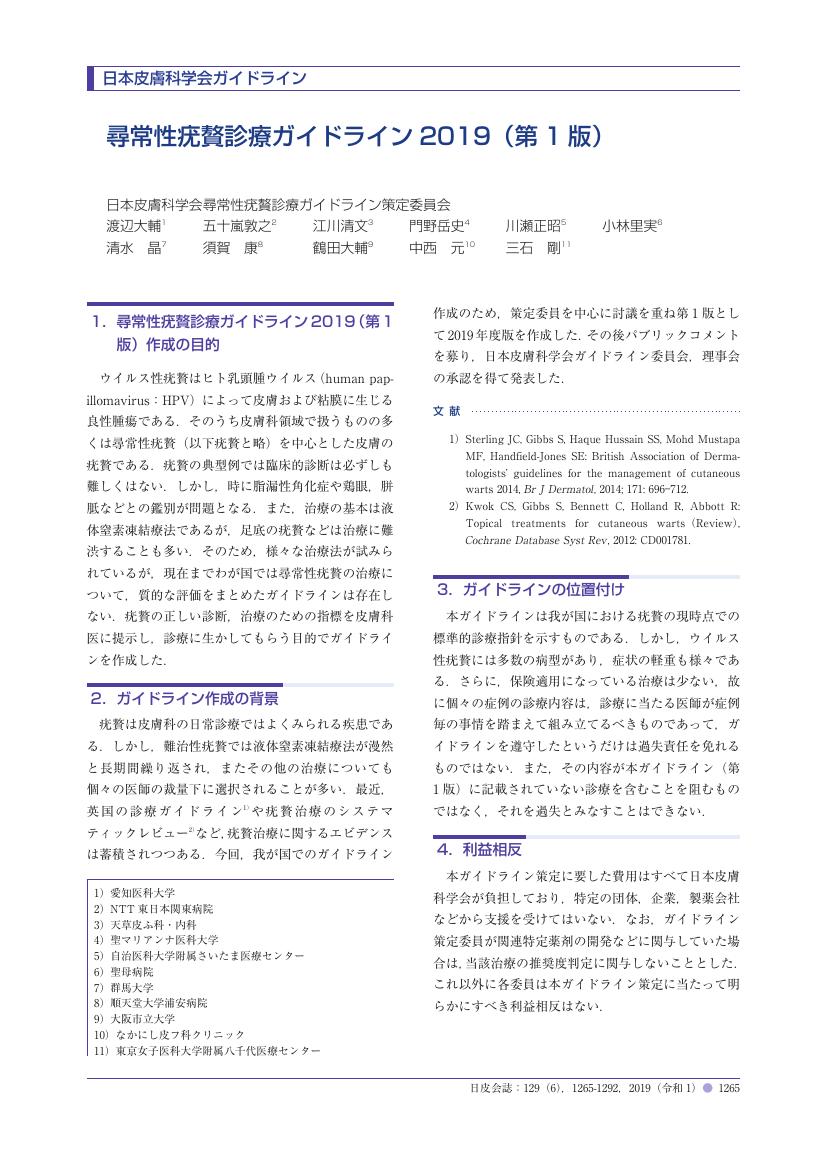- 著者
- 中林 克己
- 出版者
- 静岡産業大学
- 雑誌
- 静岡産業大学情報学部研究紀要
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.1-6, 2010-03-01
1 0 0 0 OA 絶飲食による口渇緩和に対するレモン酢の有効性の検討
- 著者
- 山本 愛 林 美恵子 飯田 智子 多田 あゆみ
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第55回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.75, 2006 (Released:2006-11-06)
<はじめに>術後の患者は、術前からの絶飲食、手術中の挿管による口腔内の乾燥、副交感神経遮断薬使用による分泌物抑制、また術後の発熱などによる不感蒸泄など、さまざまな要因で口渇が生じやすい。従来、当病棟では口渇時は水による含嗽をすすめている。しかし、術後口渇を訴える患者は多い現状にある。そこで今回、唾液の分泌作用・清涼作用のあるレモン酢に注目し、口渇への効果があるか検討した。<研究方法> 目的:口渇に対するレモン酢の効果を知る。 期間:平成17年12月1日から平成18年2月28日。 対象:全身麻酔下で消化器開腹手術を受けた、術後2から3日目の絶飲食期間の患者11名。 方法:1.患者11名に対し、レモン酢を40倍に希釈したレモン酢水(以下40倍レモン水)・50倍に希釈したレモン酢水(以下50倍レモン水)・水道水の3種類での含嗽を実施。実施後は、患者が口渇緩和になると感じた含嗽を行う。希釈倍数は、無作為に選出した看護師に2種類のレモン水含嗽を行い、40倍をすっぱいと感じ50倍をすっぱいと感じなかった結果から決定した。 2.含嗽後、アンケートに沿って聞き取り調査を行う。<結果>口渇は10名が感じ、口渇のなかった1名はレモン水含嗽を行うことで口渇だったことが分かったと答えている。2種類のレモン水含嗽で3名が口渇は残ると答え、「早く飲みたい」という意見が強かった。全員が50倍レモン水での含嗽を続けていた。水道水は、「味がなくすっきりしない」「口の中がすぐに乾燥する」、50倍レモン水は口腔内の潤いを感じたと全員が答えていた。50倍レモン水は、味覚において不快に感じた人はおらず、「すっきりする」「さっぱりして気持ちが良い」と全員が答えた。しかし、40倍レモン水はレモン特有の酸味が強くなり後味が悪くなると3名が答えた。また2名の患者が氷を入れて含嗽を行っており「すっきりする」「生き返ったようにな」との言葉が聞かれた。<考察>50倍レモン水で全員が口腔内の潤いを感じたことは、レモン酢に含まれるクエン酸や酢酸の唾液分泌効果によるものと考える。一時的とはいえ口渇への緩和につながったのではないか。今回、絶飲食を強いられた患者にとって飲めないというストレスが生じている。レモン水含嗽を行っても口渇が生じたことは「飲みたい」という意識が高まっているからだと考える。術後苦痛が強いなか、患者の言葉からも、口渇という苦痛を緩和させることができ、同時にストレスも緩和できたと考える。今回、すっぱいと感じる40倍レモン水で不快を感じたことから、レモン特有の酸味を強くすることは、術後の患者に刺激を与え不快を生じ逆効果とわかった。術後回復過程をたどる患者に、絶飲食中に爽快感を得る50倍レモン水含嗽は有効であった。また、氷を入れて含嗽を行っていることから、口渇緩和と温度の関係も調べていけたのではないか。<まとめ>1.50倍レモン酢水は、一時的な口渇緩和での効果がみられ、口渇という苦痛の緩和にもつながる。2.術後の患者には、40倍レモン酢水の強い酸味で不快を与える。
1 0 0 0 古くて新しい鎮痛薬アセトアミノフェン
- 著者
- 郡司 敦子 郡司 明彦 田村 幸彦 平尾 功治 町田 光 秋田 季子 小林 奈緒美 藤井 彰
- 出版者
- 日本歯科薬物療法学会
- 雑誌
- 歯科薬物療法 (ISSN:02881012)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.109-116, 2009-12-01
- 参考文献数
- 39
Acetaminophen is an antipyretic and analgesic drug that has a long history of 100 years or more and has been adopted in the WHO Model List of Essential Drugs in the category of non-opioids and non-steroidal anti-inflammatory medicines. In Japan, the analgesic effects of acetaminophen have not been sufficiently recognized, and NSAIDs have been used in the treatment of pain, even though acetaminophen is the first-choice analgesic worldwide.<br>Since acetaminophen, which is different from NSAIDs, does not inhibit the activity of COX-1 and COX-2, the risk of developing the 3 well-known adverse reactions of NSAIDs, peptic ulcer and gastrointestinal hemorrhage, renal dysfunction, and hemorrhage and platelet dysfunction, is very low. Aspirin is known to induce asthma and Reye's syndrome, however, acetaminophen is scarcely associated with these adverse reactions and can be used for treatment of viral diseases such as chicken pox and influenza. The safety of acetaminophen in pregnant women and elderly patients has been confirmed, and the position of acetaminophen as the first-choice analgesic drug has been established worldwide. In Japan, on the other hand, the effect of acetaminophen has not been sufficiently recognized due to the small doses (single dose, 300-500 mg; daily dose, 900-1500 mg/day) compared to other nations (single dose, 1,000 mg; daily dose, 4000-6000 mg/day). Further, the precautions for use indicated in the package insert of acetaminophen are the same as that indicated for NSAIDs; this may be a possible reason why acetaminophen has been misunderstood to be a kind of anti-inflammatory medication (NSAIDs) in Japan.<br>From above-mentioned viewpoint, the dosage of acetaminophen and expression of the precautions in packaging insertion should be reconsidered. The dosage of acetaminophen as a nonprescription drug should also be reconsidered because the dosage in OTC is further lower than that of the prescription drug. It is expected that when a more reliable analgesic effect is obtained by the administration of a higher dosage of acetaminophen and a more accurate profile of its safety is recognized, this drug will become the first-choice analgesic in Japan.
1 0 0 0 OA 平安文学における「雪」の学習指導
- 著者
- 平林 優子
- 雑誌
- 日本文學 (ISSN:03863336)
- 巻号頁・発行日
- vol.106, pp.55-73, 2010-03-15
1 0 0 0 9か月間の二酸化硫黄曝露による三宅島小児住民の呼吸器影響
- 著者
- 岩澤 聡子 道川 武紘 中野 真規子 西脇 祐司 坪井 樹 田中 茂 上村 隆元 道川 武紘 中島 宏 武林 亨 森川 昭廣 丸山 浩一 工藤 翔二 内山 巌雄 大前 和幸
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.39-43, 2010-01-15
- 参考文献数
- 7
<b>目的</b> 2000年 6 月に三宅島雄山が噴火し,二酸化硫黄(SO<sub>2</sub>)を主とする火山ガス放出のため同年 9 月に全住民に島外避難命令が出された。火山ガス放出が続く中,火山ガスに関する健康リスクコミュニケーションが実施され,2005年 2 月に避難命令は解除された。本研究では,帰島後 1 年 9 か月経過した時点における,SO<sub>2</sub> 濃度と小児の呼吸器影響の関連について,2006年 2 月から11月の 9 か月間の変化を検討した。<br/><b>方法</b> 健診対象者は2006年11月時点で,三宅島に住民票登録のある19歳未満の住民を対象とした。そのうち,受診者は,141人(受診率50.4%)で,33人は高感受性者(気管支喘息などの気道過敏性のある呼吸器系疾患を持つ人あるいはその既往のあり,二酸化硫黄に対し高い感受性である人)と判定された。<br/> 健康影響は,米国胸部疾患学会の標準化質問票に準拠した日本語版の自記式質問票により,呼吸器に関する自覚症状調査,生活習慣,現病歴,既往歴等の情報を収集した。努力性肺活量検査は,練習の後,1 被験者あたり 3 回本番の測定を実施した。<br/> 環境濃度は,既存の地区名を一義的な括りとし,当該地区の固定観測点での SO<sub>2</sub> モニタリングデータをもとに,避難指示解除より健診までの22か月間のデータについて,その平均値により居住地域を低濃度地区(Area L),比較的曝露濃度の高い 3 地域(H-1, H-2, H-3)と定義し,SO<sub>2</sub> 濃度(ppm)はそれぞれ0.019, 0.026, 0.032, 0.045であった。<br/><b>結果</b> 自覚症状では,「のど」,「目」,「皮膚」の刺激や痛みの増加が,Area L と比較すると,H-3 で有意に訴え率が高かった。呼吸機能検査では,2006年 2 月と2006年11月のデータの比較において,高感受性者では%FVC,%FEV1 で有意に低下(<i>P</i>=0.047, 0.027)していたが,普通感受性者では低下は認めなかった。<br/><b>結論</b> 高感受性者では呼吸機能発達への影響の可能性も考えられ,注目して追跡観察していくべきである。
1 0 0 0 OA 株式クオンツモデルでの過適合
- 著者
- 水田 孝信 小林 悟 加藤徳史
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告数理モデル化と問題解決(MPS)
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.41(2008-MPS-069), pp.35-38, 2008-05-09
株価予測モデルにおける過剰適合について調べた。定量的分析を行うために、中間層が 1 層のニューラルネットワークを用いて中間層の数と汎化誤差の関係を調べた。その結果、中間層が多すぎると汎化誤差が上昇し、過剰適合が発生することが分かった。この現象は、株価予測モデルが “複雑すぎる” ために予測能力が低下することが起こりうることを示している。また、学習させるファクターが異なる 2 つのモデルの予測リターンを比べた結果、適切な学習を行ったときに最も予測が似てしまうことが分かった。
- 著者
- 山本 静雄 栗林 尚志 本田 政幸
- 出版者
- 麻布大学
- 雑誌
- 麻布大学雑誌 = Journal of Azabu University (ISSN:13465880)
- 巻号頁・発行日
- no.15, pp.267-273, 2008-03-31
ヘモグロビンに代わる潜血の仮の指標として糞便および尿中の炭酸脱水酵素アイソエンザイム-I(CA-I)濃度を酵素免疫測定法(ELISA)により評価した。健康な各種年齢の実験用ビーグル犬113頭(雄50頭,雌63頭)における糞便中のCA-I濃度は,4.3から16.7ng/g便(平均;7.0±2.9ng/g便)であった。3頭の健康なビーグル犬から採取した血液1ml中に含まれるCA-Iは,それぞれ1,047, 1,062および1,150μgであった。自己血(10ml)を胃内へ注入したイヌの糞便CA-I濃度は大変低かった。しかし,自己血(5ml)を上行結腸部へ注入したイヌの糞便CA-I濃度は大変高かった。糞便中のCA-Iの検出は大腸からの出血があるイヌを見分けるのに有用であろう。健康な55頭のビーグル犬から採取した尿を化学的検査で調べた結果,44頭が陰性であったが,これら尿中のCA-I濃度はELISAで1.8から12.6ng/ml(平均;6.9±5.4ng/ml)であった。また,尿の潜血検査の結果が陽性であった11頭のイヌのCA-I濃度は,ELISAで41.2から525.0ng/mlであった。CA-Iは赤血球の特異的な指標ではないが,Hbに対する抗体を用いた特異的な免疫学的検査キットが開発されるまで,CA-Iはイヌの糞便および尿の潜血の検出に用いられるであろう。
1 0 0 0 OA 芭蕉の七夕歌 : 「常の夜にハ似ず」が示すもの
- 著者
- 小林 竜幸
- 出版者
- 上越教育大学国語教育学会
- 雑誌
- 上越教育大学国語研究 (ISSN:09135189)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.87-96, 2017-02-18
1 0 0 0 OA P-1-C14 睡眠障害のある重症心身障害児(者)へのオルゴール音楽を取り入れた関わり
- 著者
- 山本 梨絵 林 明子 高畑 卓子 芝山 和則 高橋 久恵
- 出版者
- 日本重症心身障害学会
- 雑誌
- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.263, 2015 (Released:2021-03-10)
目的 重症心身障害児(者)(以下、重症児(者))は不安や気分障害、中枢の機能障害のために睡眠リズムが不整でしばしば不眠が見られる。オルゴール音楽は睡眠障害に有効との研究があるため、重症児(者)にもオルゴール音楽が催眠効果や中途覚醒に有効か検証する。 方法 消灯から入眠までに1時間以上を要する、または中途覚醒があり睡眠時間が継続しない重症児(者)10名を選出。オルゴール音楽のCDを20時から4時まで流す。第1期:音楽非介入期、第2期:音楽介入期、第3期:音楽非介入期に分け、各28日間、21時から4時まで1時間毎に睡眠状態を記録。消灯から熟眠に要する時間は、測定開始から熟眠判定した時間を算出。睡眠状態については覚醒3点、浅眠1点、熟眠0点で調査し、中央値の比較とウィルコクソン検定を行う。 結果 消灯から熟眠に要する時間において、第1期と第2期では中央値は1.5時間から0.75時間となり熟眠までに要する時間は短縮された。第2期と第3期を比較し、中央値は0.75時間から2時間となり熟眠までに要する時間が延びた。睡眠状況において、第1期と第2期では中央値は9.5点から7点となり、熟眠、浅眠が増加した。第2期と第3期の比較では中央値は7点から9点となり、オルゴール音楽を中止した後も効果の持続がみられた。 考察 重症児(者)は中枢神経系に障害を持つことから、睡眠−覚醒パターンを整えるケアは重要である。今回、オルゴール音楽を睡眠前に流すことでヒーリングミュージックによるリラクゼーション効果が導かれ、副交感神経優位の状態に変化したと考えられる。また、侵襲が少なく簡易的なオルゴール音楽を取り入れたことで重症児(者)の心理的安定を促進し催眠状態に導くことが出来たと考える。 結論 睡眠前よりオルゴール音楽を取り入れることで、睡眠−覚醒パターンに変化が見られたことから、重症児(者)に対しても有効であることが明らかになった。
- 著者
- 村林 隆一
- 出版者
- 日本弁理士会
- 雑誌
- パテント (ISSN:02874954)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.79-84, 2003-04
1 0 0 0 OA 学生の主体的学習と授業評価 : 自己評価による精神障害作業治療学特論の学習目標の達成
- 著者
- 小林 夏子 山勝 裕久 徳江 与志子 松房 利憲 小此木 扶美
- 出版者
- 群馬大学
- 雑誌
- 群馬大学医療技術短期大学部紀要 (ISSN:03897540)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.103-108, 1997-03-31
We evaluated the course of occupational therapy for psychosocial dysfunction with student self-evaluation on achievement educational objectives, which have intended to learner-centered education. The results of this investigation shows that 93.8% students their whole objectives and there is difference between pre and post-evaluation with χ^2 test. But student self-evaluation are lower and they are not confident as their achievement more than the half(52.1%)are C-grade rating and also their comments of the course feedback. Therefore we have need to do more corrective observation and realizing problem solving in process of group independent learning.
1 0 0 0 OA 国文研ニューズ No.49 AUTUMN 2017
- 著者
- 横井 孝 大高 洋司 大橋 直義 小林 健二 大友 一雄 恋田 知子 小山 順子 宮間 純一 木越 俊介
- 出版者
- 人間文化研究機構国文学研究資料館
- 雑誌
- 国文研ニューズ = NIJL News (ISSN:18831931)
- 巻号頁・発行日
- no.49, pp.1-16, 2017-10-16
●メッセージ本文研究の近未来と集積の意味と●研究ノート「近世職人尽絵詞」影印・注釈の出版道成寺文書概観――特に「縁起」をめぐる資料について――ホノルル美術館リチャード レイン コレクションの「鉢かづき」●トピックス〈日本バチカン国交樹立75周年〉研究集会「バチカン図書館所蔵切支丹関係文書の魅力を探る」特別展示「伊勢物語のかがやき――鉄心斎文庫の世界――」関連のお知らせ日本文学資源の発掘・活用プロジェクト始動子ども霞が関見学デー津軽デジタル風土記、はじめの一歩――調印式・記念講演レポート――第41回国際日本文学研究集会プログラム総合研究大学院大学日本文学研究専攻の近況●表紙絵資料紹介山崎龍女筆「業平涅槃図」
1 0 0 0 OA 真名本『曽我物語』覚書 : <御霊>と<罪業>をめぐって
- 著者
- 小林 美和 コバヤシ ヨシカズ Yoshikazu Kobayashi
- 雑誌
- 帝塚山短期大学紀要. 人文・社会科学編・自然科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.32, pp.1-10, 1995-02-01
1 0 0 0 IR 真名本『曽我物語』覚書 : <御霊>と<罪業>をめぐって
- 著者
- 小林 美和 コバヤシ ヨシカズ Yoshikazu Kobayashi
- 雑誌
- 帝塚山短期大学紀要. 人文・社会科学編・自然科学編
- 巻号頁・発行日
- no.32, pp.1-10, 1995-02-01
- 著者
- 林 洋次 小松 裕太
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 年次大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2009, pp.135-136, 2009
For scientific engine analyses, authors proposed a simultaneous and approximate analyses for connecting rod big end bearings, for piston pin bearings and for crank shaft main bearings. However, to save computation time for engine bearing analysis, it is better to innovate new iteration methods to introduce solutions of partial differential equations in finite width bearing theory. In this paper, some kinds of Runge-Kutta methods are proposed by using variable step methods with inherent algorithm of engine bearings, and the characteristic of variable step's Runge-Kutta methods in engine bearing analyses are clarified.
1 0 0 0 OA 尋常性疣贅診療ガイドライン2019(第1版)
1 0 0 0 慢性腎不全患者の指示量に対する充足率について
1 0 0 0 IR エストロジェンカプセルを含むプロジェステロン徐放剤による分娩後乳牛の卵巣機能賦活
- 著者
- 下条 広介 羽石 敬史 加治佐 誠 Siswandi Riki 中山 緑 小林 郁雄 藤代 剛 福山 喜一 上村 俊一
- 出版者
- 宮崎大学農学部
- 雑誌
- 宮崎大学農学部研究報告 (ISSN:05446066)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.115-120, 2007-03
分娩後早期の乳牛に対して、エストロジェンを含むプロジェステロン徐放剤PRIDを膣内挿入することで新たな卵胞波が発生し、PRID除去時には直径10mm以上のクラスIII卵胞の形成がみられた。PRID除去後の定時AIにおいて、E2群1/5頭(20%)、GnRH群5/6頭(83%)が受胎し、最終的な分娩間隔は、E2群429±115.1日、GnRH群346±9.4日となった。PRIDは分娩後の乳牛の卵巣機能賦活に有効であった。