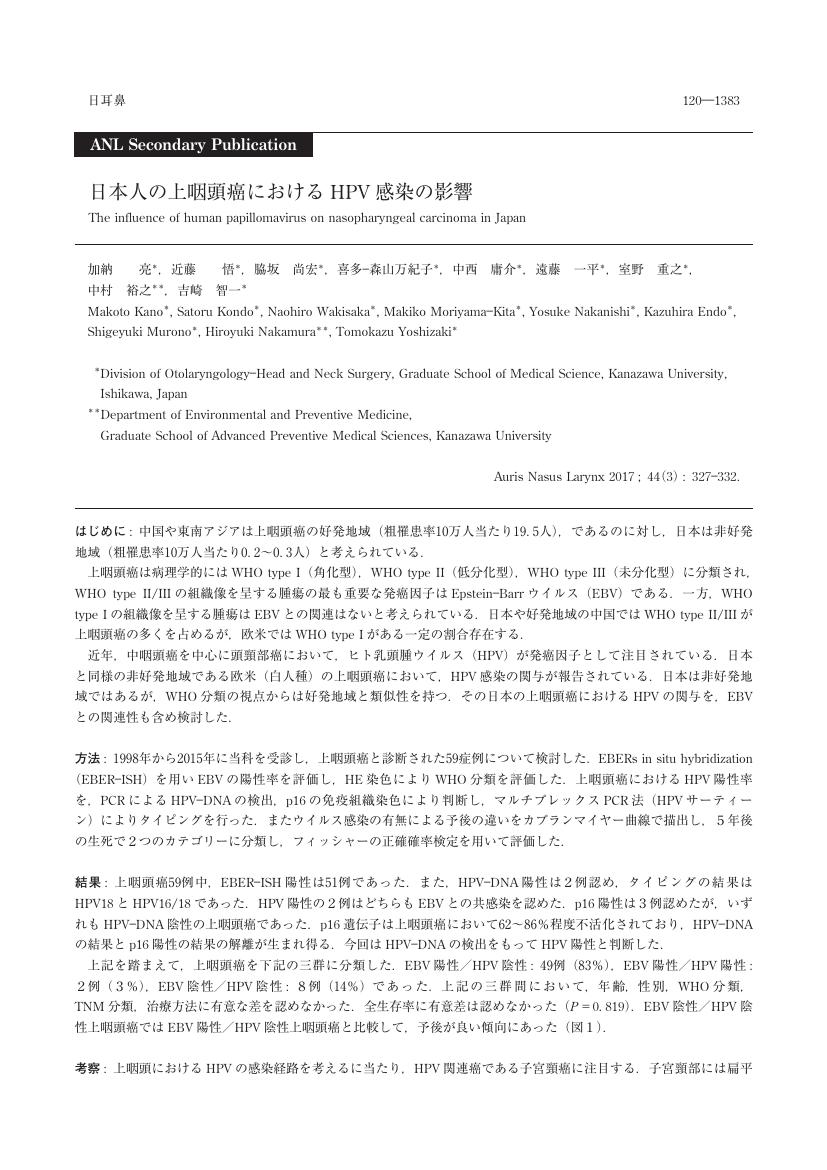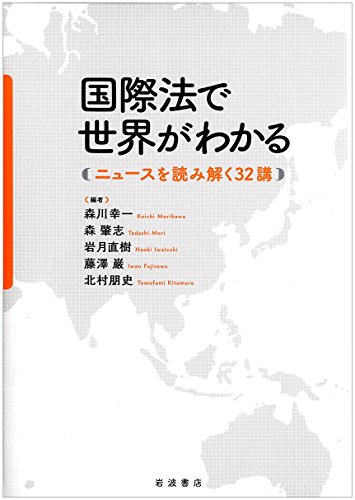1 0 0 0 OA 溶連菌感染症とA群溶連菌に関する疫学的研究特に, A群溶連菌の群別について
- 著者
- 森田 盛大 山脇 徳美 斉藤 志保子 庄司 キク 後藤 良一 岡村 敏弘 長沼 雄峯 鈴木 敞謙 熊谷 冨士雄 石田 名香雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本感染症学会
- 雑誌
- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.26-36, 1982-01-20 (Released:2011-09-07)
- 参考文献数
- 8
秋田県内における1970~1979年の猩紅熱罹患率 (対人口10万) を伝染病統計からみると, 20~54.7であり, 都市部が農村部より高かった. また, 本県で実施している感染症サーベイランス情報 (1978~1979年) から, 猩紅熱, リウマチ熱, 急性腎炎の患者発生実数を推計した結果, それぞれ, 年間25,143名, 495名, 1,192名であり, 猩紅熱と後2者の比は14.9: 1であった.一方, これらの病原となっているA群溶連菌の各種感染症患者からの分離頻度を菌型別にみると, 分離された216株 (分離率27%) のうち, 4型菌と12型菌が56.9%を占め, つづいて多かったのが6, 22, B3264, I型などであった.また, 県内住民のA群溶連菌に対するT抗体陽性率 (使用抗原は21種類の菌型) を測定した結果, 20種類のT抗体が検出され, このうち.2型が最も高率であり, 次いで, 4, 44, 14, 5, 28, 1型などが高かった. 年齢別T抗体陽性率分布を地域別にみると, 分布パターンそのものは概ね類似していたが, 陽性率の高さと陽性率上昇起点年齢が異なる傾向を示した.最後に, これらの各菌型の患者からの分離頻度と住民のT抗体陽性率から, 21種類のA群溶連菌の菌型を7群に群別すること, および, 試算値の病原指数を基礎に3群, 4亜群に大別することがそれぞれ試みられた.
1 0 0 0 OA Localized type malignant mesotheliomaの1例
- 著者
- 森藤 雅彦 浜中 喜晴 平井 伸司 宮崎 政則 中前 尚久
- 出版者
- Japan Surgical Association
- 雑誌
- 日本臨床外科学会雑誌 (ISSN:13452843)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.1, pp.94-98, 2001-01-25 (Released:2009-08-24)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1 1
中皮腫は漿膜最上層のmesothelial cellを発生母地とする腫瘍である.われわれは,肉眼的に限局した形態で発見された悪性胸膜中皮腫の1例を経験したので報告する.症例は57歳,男性.胸部異常陰影にて入院した.精査にて横隔膜原発腫瘍を疑い胸腔鏡下切除術を施行した.術中迅速病理にて悪性所見を認め,肺,横隔膜にも浸潤していたため右肺下葉,横隔膜の一部を合併切除した.術後の病理組織検査にてmalignant mesotheliomaが疑われ,免疫組織学的検討にてCytokeratin陽性, Vimentin陽性, CD34陰性であった.その後2度局所再発し,手術と化学療法を施行し,現在外来通院中である. malignant mesotheliomaは診断が困難であるが,他疾患との鑑別に免疫組織学的検索が非常に有用である.現在本疾患に対する有効な治療法はなく,予後も極めて不良と言われる.新たな治療法の解明のためにも他疾患との明確な鑑別診断が必要と考える.
1 0 0 0 OA 都市基幹公園における利用者の喧騒感に関する研究
- 著者
- 森長 誠 青野 正二 桑野 園子
- 出版者
- The Institutew of Noise Control Engineering of Japan
- 雑誌
- 騒音制御 (ISSN:03868761)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.292-302, 2005-08-01 (Released:2009-10-06)
- 参考文献数
- 20
公園の音環境デザインについて「地理情報」「音環境」「利用者の印象」の関連を喧騒感という視点から検討した。調査Aでは, 利用者の利用目的が静的か動的かによって音環境評価が大きく異なることを明らかにし, 公園を取り巻く幹線道路に接する静的な利用目的に供用された施設では, 喧騒感の高まりとともに環境全体の評価の低下が確認された。また調査Bでは噴水施設近辺での, 噴水音の認知と利用者の印象の空間的広がりについて検討を行い, 噴水音による喧騒感の緩和効果がみられた。なお, そのためには噴水音を認知できるか否かが重要なファクターであること及び, 噴水音の認知については空間的に明瞭な区分がなされる可能性が示唆された。
1 0 0 0 OA 難治性三叉神経痛に対する “nerve combing” による治療経験
- 著者
- 森 健太郎 佐々木 裕亮 酒井 淳 赤須 功 山川 功太 北川 亮 吉田 浩貴 沼澤 真一 伊藤 康信 渡邉 貞義
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.7, pp.464-469, 2022 (Released:2022-07-25)
- 参考文献数
- 14
微小脳血管減圧術を施行したが再発, あるいは未治癒の突発性三叉神経痛でカルバマゼピン非耐性の5症例に対して, 再手術の際に三叉神経知覚枝のnerve combingを施行した. 全例術直後からカルバマゼピン内服なく疼痛発作が完全消失したが, 5例中4例 (80%) に三叉神経第3枝領域を中心とした顔面知覚障害が残存した. 術後1~5年の時点で再発を認めずQOLも良好である. 再発三叉神経痛で責任血管が明らかでなく, かつカルバマゼピン非耐性例に対してはnerve combing法は有効な治療法と思われる. なお, nerve combing法を予定する場合は術前に顔面知覚障害をきたす可能性が高いことを説明すべきである.
1 0 0 0 御仕置伺集 : 長崎奉行所記録
1 0 0 0 OA 加熱人血漿蛋白液輸液とHBe抗原・抗体
- 著者
- 森 泰樹 緒方 正吾 阿多 実茂 百瀬 元大 中野 安二
- 出版者
- 一般社団法人 日本肝臓学会
- 雑誌
- 肝臓 (ISSN:04514203)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.5, pp.510, 1978-05-25 (Released:2009-07-09)
- 参考文献数
- 8
- 著者
- 有地 亨 森下 伸也 三島 とみ子 丸山 茂 南方 暁 久塚 純一 緒方 直人 小野 義美 森田 三郎 二宮 孝富 生野 正剛 畑 穣 江守 五夫 黒木 三郎
- 雑誌
- 海外学術研究
- 巻号頁・発行日
- 1987
本研究は昭和59〜61年度科研費補助大研究「現代家族の機能障害の実態と紛争処理の総合的研究・・・法・政策のための基礎的調査研究」の続編にあたり, その成果を, 深化, 発展させるものである. 当該研究においてわれわれは, 家族機能を活性化させるためには「家族問題総合センター」の設立が必要であることを提唱した(この件に関しては62年1月に文部省公開シンポジウム「大学と科学」で報告). 本研究はこの構想を具体化するために英・仏での実態を明らかにすることを目的とする.我が国は昭和35年以降急激な家族変動に見舞われたため, このことから生じた家族問題に適切に対処する手段を, これまで持たなかった. 翻って英・仏などの先進欧米諸国では, 家族の変動は比較的穏やかに進行し, その過程で生じてきた家族問題に対しても, 様々の有効な処置が講じられてきたと考えられる. そこでこれら一連のファミリー・エージェンシーのシステムを研究し, さらに現在なお存続する家族問題の実態を調査し, これと比較研究すれば, 我が国での今後の対策の在り方をより具体的に提言できるはずである. 予備調査では, 英国における当該援助機関の概要を専門家の協力を得て把握した. ここで, 諸機関の歴史的発展状況, その構造, 運用の実態, 諸機関相互の関連に関して, 一定の理解が得られた.われわれの今回の英国訪問は, 旅行期間を併せて2週間という非常に限られた日程のものではあったが, SocialーLegalーCenterのメンバーの全面的な協力を得られ, 4に掲載した内容の調査研究を速やかに実施することができた. その詳細は『英国の家族援助機関に関する予備調査報告』にまとめているので, ぜひ御高覧戴きたい(本報告書にその写しを添付している).この海外学術研究は, 過去3年間の日本国内における調査研究の成果から, われわれが提唱した「家族問題総合センター」の具体的なイメージを作り上げるためのものである. そこで予備調査では, まずこれまでのわれわれの家族問題に関する研究の枠組みが彼の国においてそのまま使用できるのかという点と, 具体的にどのような機関を調査対象とするのが有益であるのかという点に, 目標を絞った.前者においては, 英国の家族研究者は一般的に, 現代の家族変動自体は問題を有する事柄であるとは見ておらず, そのことに伴って生じる様々な問題をいかにケアしていくかに, 研究の重点を置いているということが理解できた. しかし彼らのこの態度の背景には, 家族の機能障害に関してはすでに私的な援助機関が広汎に活動をしているので, 公的には問題性が薄れてきているのではないかということも, またある程度推測できた. この意味では, やはり私的な援助機関およびその利用者をわれわれの手で直接に調査し, 家族問題の実態をより詳細に把握する必要を強く感じる.そこで後者ともつながるのであるが, 今後の計画としては, 今回訪問し職員から事情を聴取してきたもののうち, われわれの問題関心に非常に隣接した機関と思われる, マリッジ・ガイダンス・カウンシル, プロベイション・サービス, 高齢者のためのエイジ・コンサーンなどに調査対象を限定し, 問題を抱えている家族の実態調査, 家族援助機関の利用状況などの実態調査を進めていきたいと考えている.
1 0 0 0 OA 小学校における性教育 序論
- 著者
- 後藤 誠也 高森 裕子
- 出版者
- 奈良教育大学
- 雑誌
- 奈良教育大学紀要. 人文・社会科学 (ISSN:05472393)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.119-134, 1994-11-25
The discussion of sexuality education has been the most controversial issue since 1990. The revision of the Course of Study has led to teach sexuality in the subjects of natural science and health education. There are many problems to solve what should be the content of sexuality education, how to teach and what extent we are supposed to teach to. Teaching sexual intercourse, as a matter of course, is the most embarrassing question for every teachers in primary schools. Now in Japan, sex-educationists' views of teaching of sexual intercourse are divided into two groups. Both groups agree that sexuality education is not only illustrating genitals and teaching their function, but respectively showing their own ideas about content and the way how to teach that. One group insists that they need not teach genitals because the mere teaching of genitals could not be sexuality education, while the others assert that without to teach genitals they could not give the true recognition of sexuality. According to those separate standpoints, the former asserts that we should not include the sexual intercourse in sexuality education, but the latter asserts that we must include the sexual intercourse as the essential item of sexuality education. Here we take the stand of the latter opinion. In the case of primary school children, we might sometimes feel embarrassed in teaching the sexual intercourse, but considering the circumstance around children, the harmful effects were instilled by mass media, of which we are afraid they can often be inadequate or unnecessary sorts of imformation. So we should throw a new light on the sex or sexuality and lead children to the right direction. We inquired into the prevailing state in primary schools in Nara Prefecture about the sexuality education (their teaching plans, method and content etc.). We knew the following facts. In 90% or more of schools inquired sexuality education is under way, and they refer to the teaching of sexual intercourse, 36% of the whole schools actually introduced it into their class, and 37% think about translating their plans into practice at an early stage. The teachers of such schools have tried to answer to childrens' questions correctly. However there are many ptoblems awaiting solution with our efforts. We have to press for the sexuality education including the item of sexual intercourse as the key matters. For that purpose we must research many problems; such as teachers' concern about sexuality, the decision upon more specified content of sexuality education, increasing the opportunity of teachers in-service training, the development of teaching materials or tools, the negotiation with parents about sexuality education, and all that.
1 0 0 0 OA 中国・雲南省西南部の無塩漬物茶「酸茶」
- 著者
- 難波 敦子 宮川 金二郎 大森 正司 加藤 みゆき 田村 朝子 斎藤 ひろみ
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.8, pp.907-915, 1998-08-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 25
This report continues our study of post-heated and fermented tea which are produced in the northern area of South-East Asia and Japan. A search of Chinese literature for Suancha (a sour, non-salted pickled tea) reported it to be produced by hill tribes in the south-west of Yunnan province in China by a two-step fermentation process (under aerobic and anaerobic conditions) like Goishi-cha in Japan. Our study, however, clarifies that the present Suanchas are produced by a one-step fermentation process under anaerobic conditions like Lepet-so in Myanmar, Miang in Thailand and Laos, and Awa-bancha in Japan. Suancha is now produced by the Bulangzu living near Mt. Bulang in Xysanbanna and by the Daizu in Dehong province of Yunnan. Edible pickled teas, including Liangpan-tea and Yancha that is the other kinds of pickled tea in Yunnan are also discussed.
1 0 0 0 OA 長期線地電位試験観測
- 著者
- 森 俊雄
- 出版者
- 気象庁気象研究所
- 雑誌
- Papers in Meteorology and Geophysics (ISSN:0031126X)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.149-155, 1985 (Released:2007-03-09)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 6 6
日本電信電話公社の通信ケーブル施設を使って長基線の地電位試験観測を行った。現在、日本では陸上での地電位観測で数km以上の基線で観測されているものは、他にはない。関東北部の笠間、下館および小山の各電話中継所のアースおよびその間の通信ケーブルを用いて、笠間—下館間 (26.8km) および小山—下館間 (15.7km) の地電位変化を観測した。1Hz等の短周期ノイズが大きいため、カットオフ周期が6分のローパスフイルターを通したところ笠間—下館間では非常によい記録が得られた。ここでの地磁気変化による誘導電位変化は、柿岡地磁気観測所の地電位EW成分と類似している。小山—下館間では、直流電車からと思われる電気的ノイズが非常に大きく、良い記録は得られなかった。しかし、そこでは地電位変化が、笠間—下館間に比較して非常に小さいことも確かである。このような地電位変化の相違は、主にこの付近の堆積層の厚さに関係していると考えられる。今回の試験観測の結果、電々公社のケーブル施設を使って、長基線地電位変化を観測できることがわかった。このような観測は、地下構造の解析や地下電気抵抗の時間的変化の検出に利用できると考えられる。
1 0 0 0 OA 複数の車載センサーデータを統合した冬期の路面状態のLate Fusionによる推定モデル
- 著者
- 石附 将武 高橋 翔 萩原 亨 石井 啓太 岩﨑 悠志 森 徹平 花塚 泰史
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- AI・データサイエンス論文集 (ISSN:24359262)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.J2, pp.642-649, 2022 (Released:2022-11-12)
- 参考文献数
- 17
本論文では,複数の車載センサーのデータを統合して冬期の路面状態を推定する手法を提案する.提案手法は,カメラとタイヤ内加速度センサー,路面温度計,マイクのそれぞれから路面状態を推定する複数の識別器に加え,それらの出力である路面状態確率をLate Fusionするマルチモーダルモデルである.推定する路面は道路管理において使用されている乾燥,半湿,湿潤,シャーベット,凍結,積雪の6路面である.提案手法は冬期の一般道で実車から得るデータを用いた実験によって,その有効性が確認された.
1 0 0 0 OA INFOSTA Forum (326)
- 著者
- 笹森 勝之助
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.12, pp.490, 2022-12-01 (Released:2022-12-01)
1 0 0 0 OA 磁性からみた蛇紋岩化度:北海道岩内岳超苦鉄質岩体を例として
- 著者
- 森尻 理恵 中川 充
- 出版者
- 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター
- 雑誌
- 地質調査研究報告 (ISSN:13464272)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.7-8, pp.381-394, 2009-08-05 (Released:2013-08-05)
- 参考文献数
- 34
This paper is intended to show the relationship between susceptibilities and degrees of serpentinization of serpentinized peridotite. The susceptibility, magnetization and bulk density of 79 serpentinized peridotites were measured. Moreover, rock magnetic analyses, i.e., acquisition of IRM, thermal demagnetization of composite IRM, thermomagnetic analysis, and low-temperature magnetometry, were applied to selected samples obtained from the Iwanai-dake ultramafi c rock body in Hokkaido, Japan. Samples with similar peridotite contents were chosen to detect the serpentinization effects clearly. Results show that the magnetic carrier is mainly magnetite. Linear trends fell between 0.1 % and 0.4 % of the predicted volume of magnetite when observed susceptibilities were plotted against densities. The study results show that, if the magnetic carrier is magnetite, the relationship between susceptibility and density reveals the variation of serpentinization reactions. A significant spread of the data is apparent, but it remaines along each linear line of reactions. The volume of magnetite produced by serpentinization of other ultramafi c rock bodies is presumed to be similar in samples for which the magnetic carrier is magnetite. The different susceptibility is inferred to result from the volume of water reaction when these rock bodies come from the same peridotite series. The results suggest that comparable amounts of reacting water affect the ultramafic bodies. The water reaction was found to be an important approach to solving many tectonic problems. Therefore, we recommend that serpentinite, which has the same basic reaction should be used to elucidate tectonic problems.
1 0 0 0 OA エジプト産モカタム層石灰岩の塩害とスレーキング特性
- 著者
- 谷本 親伯 岸田 潔 小沼 栄一 森 邦夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本材料学会
- 雑誌
- 材料 (ISSN:05145163)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.502, pp.862-868, 1995-07-15 (Released:2009-06-03)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 3 3
The Great Sphinx-Giza, Egypt was carved out of Middle Eocene limestone formations. The upper part of the statue, including the neck and the head, consists of soft and marly formations (named Maadi Formation). They are highly porous and cavernous showing the evidence of having been greatly affected by water erosion. At present, the Great Sphinx as one of the most important World Heritages is being seriously subjected to aggressive deterioration of limestone members.Since it was not possible to employ any specimen sampled from the immediate site of the Sphinx, it was tried to investigate the process of deterioration of marly limestone in terms of Mokkatam Limestone (called Pyramid Stone) which is considered to be a little older than Maadi Formation. In the present study the process of recrystallization of salt substance on limestone surface and the transportation of salt and water through micro-pores were observed for the period of three months. The electron microscopic scanning was used to illustrate the pore-size, pore distribution and recrystallization of salt. The same test as described in this paper is recommended to be applied to the Maadi Formation for the feasibility study on the preservation of the Great Sphinx.
1 0 0 0 OA Lewy小体型認知症の治療
- 著者
- 森 悦朗
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.32-38, 2020 (Released:2020-07-21)
- 参考文献数
- 36
Dementia with Lewy bodies (DLB) causes various symptoms such as psychiatric symptoms, parkinsonism, and failures of autonomic nervous system in addition to cognitive impairment, all of which are clinical and care problems. This review provides evidence–based commentary on treatment of DLB. Donepezil has been the central means since its approval in 2014 for the treatment of cognitive impairment of DLB, and evidence of it is accumulating and gives clues of the usage of it. Although there is insufficient evidence on the efficacy of donepezil for BPSD, it is still the first choice before antipsychotics. On the other hand, motor disorders due to parkinsonism are also important therapeutic targets. Levodopa is the mainstay of treatment. Recently, multicenter, placebo–controlled, randomizeouble–blind, controlled trials have shown the efficacy of adding zonisamide over levodopa treatment for parkinsonism in DLB. Unfortunately, there is no high level of evidence of treatment for a variety of other conditions, and individual patients will be treated with knowledge of other diseases.
- 著者
- 森川 信之 神野 達夫 成田 章 藤原 広行 福島 美光
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING
- 雑誌
- 日本地震工学会論文集 (ISSN:18846246)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.1, pp.23-41, 2006 (Released:2010-08-12)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 10 7
異常震域を表現するための距離減衰式に対する補正係数の改良を行った。基準の式をKanno et al.(2005) によるものに変更し、応答スペクトルにも対応するようにしている。海溝軸に替えて、火山フロントまでの距離を導入することにより、一部地域に対して過大評価となっていた問題点を解決するとともに、対象地域を関東・甲信越地方まで拡大した。さらに、基準式では考慮されていない震源特性に関する検討を行った。地震動強さに関して震源の深さ依存性は見られなかったが、プレート間地震とスラブ内地震では明瞭な違いがあることが確認された。そのため、両タイプの地震に対する補正係数も新たに求めた。
1 0 0 0 OA 日本人の上咽頭癌における HPV 感染の影響
- 著者
- 加納 亮 近藤 悟 脇坂 尚宏 喜多-森山 万紀子 中西 庸介 遠藤 一平 室野 重之 中村 裕之 吉崎 智一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.120, no.11, pp.1383-1384, 2017-11-20 (Released:2017-12-16)
1 0 0 0 OA ビタミンK欠乏症が原因と考えられた胎児頭蓋内出血の一例
- 著者
- 米山 雅人 佐久間 淳也 小瀧 曜 鷹野 真由実 長崎 澄人 大路 斐子 早田 英二郎 中田 雅彦 森田 峰人
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.1, pp.142-146, 2022 (Released:2022-05-10)
- 参考文献数
- 17
胎児の頭蓋内出血は,1,000例に0.5-0.9例程度と稀な疾患である.今回,母体のビタミンK欠乏により胎児頭蓋内出血を来した一例を経験したので報告する.37歳,3妊0産.双極性感情障害のため内服加療をしていた.妊娠28週6日に精神症状の増悪に伴う摂食障害で受診し,入院管理とした.妊娠30週3日の超音波検査で左頭蓋内占拠性病変を認め,胎児MRI検査で頭蓋内出血と診断した.妊娠30週4日に胎児死亡を確認した.母体の精神状態の増悪を考慮し,全身麻酔下での帝王切開術による死産児の娩出を行った.母体血液検査で凝固能に異常値は認めなかったが,ビタミンK1,K2ともに≦0.05ng/mLとビタミンK欠乏を認め,胎児頭蓋内出血の原因と推測された.本症例のように,母体の血液検査にて凝固能に異常を認めない症例でも,胎児の出血を念頭とした管理が考慮される.また,胎児MRIは胎児頭蓋内出血の詳細の評価が可能であり,家族への病状説明や方針決定の際に有用であると考えた.
1 0 0 0 国際法で世界がわかる : ニュースを読み解く32講
- 著者
- 森川幸一 [ほか] 編
- 出版者
- 岩波書店
- 巻号頁・発行日
- 2016
1 0 0 0 OA 救急看護認定看護師の救命救急対応における看護実践能力の構造
- 著者
- 森島 千都子 當目 雅代
- 出版者
- 日本クリティカルケア看護学会
- 雑誌
- 日本クリティカルケア看護学会誌 (ISSN:18808913)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.49-59, 2016-03-22 (Released:2016-03-22)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3 3
本研究の目的は,三次救急患者に対応する救急看護認定看護師の看護実践能力の構造を明らかにすることである.グラウンデッド・セオリー・アプローチを用いた分析の結果,以下のストーリーラインが見出された. 認定看護師は,危篤状態で搬送されてくる患者に対して【得られた情報から直観的に患者の成り行きを予測する】アセスメントを行っていた.このアセスメントが【先を見越した準備で緊急事態を取り仕切る】ことを可能にし,さらには【エビデンスによる緊急度と重症度から優先度を見極める】ことで,緊急事態の状況や医師の指示に振り回されることなく【医師・救急隊と共通認識を図りながら協働する】ことができ,救急対応を円滑に進行していた.また,救急対応と並行して【突然の出来事に家族を向き合わせる】ことも行っていた. このような救急対応は,【経験知の差で即応性が決まる】ため,経験が必要不可欠であり,本研究の認定看護師は,経験知を増やすことで臨機応変な対応や咄嗟の機転が効くといった実践を可能にしていた.しかし,現在の三次救急医療の現場は,【救急対応の制約とやむを得ない救命がある現場】であり,救急対応だけに専念できる状況にはない.こうした状況への対策として,実践能力を【ジェネラリストに還元することでエキスパート性を確認する】ことが,認定看護師の看護実践能力の維持につながっていた.