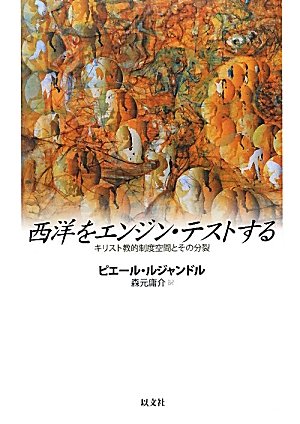1 0 0 0 OA 顎下部膿瘍からLemierre症候群に至ったと考えられた1例
- 著者
- 深川 智恵 古土井 春吾 高橋 英哲 山田 周子 渋谷 恭之 古森 孝英
- 出版者
- 社団法人 日本口腔外科学会
- 雑誌
- 日本口腔外科学会雑誌 (ISSN:00215163)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.10, pp.605-608, 2010-10-20 (Released:2013-10-31)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
Lemierre syndrome is a potentially life-threatening disease caused by an acute oropharyngeal infection with secondary septic thrombophlebitis of the internal jugular vein, frequently associated with abscess formation in distant organs.We report the case of a 78-year-old woman who received surgical therapy, chemotherapy, and radiation therapy for malignant lymphoma in 2001. She visited our hospital because of a swelling and pain of the left submandibular region in August 2009. The patient was immediately hospitalized to control the pain and infection. PET images showed tracer uptake in the lung. Bilateral multiple septic emboli of the thorax were detected on CT. On the basis of these findings, Lemierre syndrome was diagnosed. The patient was treated with antibiotics intravenously, and surgical drainage was performed. All symptoms improved, and she was discharged after 32 days.
- 著者
- 佐藤 友紀 都留 孝治 安藤 真次 竹村 仁 廣戸 桃香 井上 航平 真田 美紗 廣原 円 高森 洋子
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.G-59_2-G-59_2, 2019
<p>【はじめに・目的】今回,大分県中部保健所より「働き盛りの健康サポートプロジェクト」(以下,事業)として委託事業を受諾し,製造業系事業所の特性に合わせた運動介入を実施し,一次予防活動を実践した結果について報告する.</p><p>【方法】大分県中部保健所管内の各事業主に向けて導入研修会を開催し,アンケートや保健師によるヒアリングから事業所を選定した.事業目的は,「病気による事故や腰痛の予防」,「生活リズムや運動継続による体調の改善」とし介入した.対象者は事業所の管理職が,運動実践への取り組みが必要(検診結果の判定がC,独身で食習慣に偏りのある者,運動習慣のない者等)と判断した13名(平均年齢41.5±10.5,男性13名).介入期間は平成29年9月〜12月までの3ヶ月間とし,保健師同行のもと,初期評価,初回運動指導,2回目の運動指導,最終評価の合計4回事業所へ訪問介入した.また,評価や指導に関しては,従業員の仕事の一環とし,業務の時間内に実施した.運動介入の時間は約90分であり,内容は,ミニ講座(生活習慣病,食事,腰痛),運動指導(職場で行える4秒筋力トレーニングや有酸素運動,腰痛予防やラジオ体操の指導),部署別でのグループワークを実施した.その他,手帳を作成し目標や体重のグラフ,運動実践記録の見える化を図った.さらに,万歩計の配布や歩数の記録,努力した従業員への褒賞なども提案した.評価項目は,身長,体重,BMI,skeletal muscle index(以下,SMI),体脂肪率,ウエスト周径,身体活動量,健康感などに関して意識調査アンケートを実施した.介入前後の比較には,対応のあるt検定を用い,有意水準は5%とした.</p><p>【結果】運動介入前後の比較では,BMI(25.1±3.0→24.7±3.4,p>0.05),SMI(8.2±0.8→8.2±0.9,p>0.05),ウエスト周径(85.4±7.2→84.7±8.5,p>0.05)において,変化は認めなかったが,体脂肪率(22.2±6.3→20.5±6.8,p<0.05),身体活動時間(323.8±567.3→415±608.9,p<0.05)においては,有意な改善を認めた.今回の事業に参加して,「従業員同士のコミュニケーションが増加した」や「寝付きがよくなった」などの感想も聞かれた.</p><p>【結論】地域の事業所に対し,保健師と理学療法士が協働し,事業所に訪問を行い,業務内容の特色に合わせて運動指導することで,有意に体脂肪率の減少や身体活動量に増加を認め,健康に対する意識や運動に対する意欲が向上する結果となった.さらに,職場ぐるみの介入が,より効果を高め職場の雰囲気や働きやすい職場環境になるのではないかと考える.今後も産業疾病予防の領域まで理学療法士が地域の保健師や市の職員と協働し,職域の拡大を図っていく必要があるのではないかと考える.</p><p>【倫理的配慮,説明と同意】事業所および対象者には,本事業の趣旨と内容を,データの活用方法に関して文章による説明を行い,書面にて同意を得た.本事業は大分県中部保健所から委託事業として実践したが,その他の利益相反に関する開示事項はない.</p>
1 0 0 0 OA 車載型排気熱回収スターリングエンジンの開発
- 著者
- 片山 正章 吉松 昭夫 立野 学 小森 聡 澤田 大作
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.5, pp.763-768, 2014 (Released:2018-01-25)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
自動車排気から効率的に熱回収可能で,コンパクトなα型スターリングエンジンを利用した自動車用排熱回収システムを開発.高い熱交換性能と,熱変形への追従性の両立を狙った高温側熱交換器を考案.排気エネルギーを有効に利用するための熱流れシミュレーションの結果,ハイブリッド車両時速100km 運転条件で,回収効率7.6%を達成.
1 0 0 0 OA 腹横筋と腰部多裂筋の形態学的関連性
- 著者
- 三浦 拓也 山中 正紀 森井 康博 寒川 美奈 齊藤 展士 小林 巧 井野 拓実 遠山 晴一
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0512, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】体幹に属する筋群はその解剖学的特性からグローバル筋群とローカル筋群の2つに大別される。近年,この体幹ローカル筋群に属する腹横筋や腰部多裂筋の機能に注目が集まり,様々な研究が世界的に行われている。腹横筋の主たる機能として,上下肢運動時における他の体幹筋群からの独立的,かつ先行的な活動や腹腔内圧の上昇,仙腸関節の安定化などが報告されている。また,腰部多裂筋に関しては腹横筋と協調して,また両側性に活動することで腰椎へ安定性を提供しているとの報告がある。これら体幹ローカル筋群は主に深層に位置しているため,その評価には従来,ワイヤー筋電計やMRIといった侵襲性が高く,また高コストな手法が用いられてきたが,近年はその利便性や非侵襲性から超音波画像診断装置による筋厚や筋断面積の評価が広く行われている。腹横筋と腰部多裂筋は協調的に活動するとの報告は散見されるが,両筋の筋厚の関連性について言及した研究は少ない。本研究の目的は腹横筋と腰部多裂筋を超音波画像診断装置にて計測し,その関連性を調査することとした。【方法】対象は,本学に在籍する健常男性10名(21.0±0.9歳,173.9±6.6 cm,64.3±9.5 kg)とした。筋厚および筋断面積の計測には超音波画像診断装置(esaote MyLab25,7.5-12 MHz,B-mode,リニアプローブ)を使用した。画像上における腹横筋筋厚の計測部位は腹横筋筋腱移行部から側方に約2 cmの位置で,その方向は画像に対し垂直方向とした。腰部多裂筋の筋断面積計測におけるプローブの位置は第5腰椎棘突起から側方2 cmの位置で,画像上における筋断面積は内側縁を棘突起,外側縁を脊柱起立筋,前縁を椎弓,後縁を皮下組織との境界として計測した。動作課題は異なる重量(0,5,10,15%Body Weight:BW)を直立姿勢にて挙上させる動作とし,各重量条件をランダム化しそれぞれ3回ずつ計測,その平均値を解析に使用した。統計解析にはSPSS(Ver. 12.0)を使用し,Pearsonの相関係数にて腹横筋筋厚と腰部多裂筋筋断面積の関連性を検討した。統計学的有意水準はα=0.05とした。【結果】統計学的解析から,0%BW(r=0.78,p<0.05),5%BW(r=0.72,p<0.05)条件において腹横筋の筋厚と腰部多裂筋の筋断面積との間に有意な正の相関が認められた。10%BW,および15%BW条件においては有意な相関関係は認められなかった。【考察】本研究は,機能的課題時における腹横筋と腰部多裂筋の形態学的関連性を検討した初めての研究であり,体幹に安定性を提供するとされている両筋がどのような関連性をもって機能しているのか,その一端を示した有用な所見である。本結果より,低重量条件においては腹横筋筋厚と腰部多裂筋筋断面積との間に有意な正の相関が認められたが,重量の増加に伴い相関関係は認められなかった。先行研究によると腹横筋や腰部多裂筋は機能的活動中に低レベルで持続的な活動が必要であるとされており,かつ両筋は低レベルな筋活動で充分に安定化機能を果たすと報告されている。また,両筋は他の体幹筋群と比較して筋サイズも小さいため,高負荷になるにつれて筋厚や筋断面積の値はプラトーに達していた可能性があり,さらに,高重量条件では重量の増加に伴う体幹への高負荷に抗するため,体幹グローバル筋群である腹斜筋群や脊柱起立筋群などの活動性が優位となっていたために筋厚や筋断面積の関連性が検知されなかったかもしれない。本所見は上記の点を反映したものであると推察される。腹横筋や腰部多裂筋は活動環境に応じて協調的に働くことで体幹に対して適切な安定性を提供しているとされてきたが,様々な活動レベルを考慮したデザインにおいてその関連性を検討した研究は無く,明確なエビデンスは存在していない。本研究はその一端を示すものであり,今後は筋活動との関係性や他の体幹筋群との関係性,さらには腹横筋や腰部多裂筋の機能障害があるとされている慢性腰痛症例においてより詳細な検討が必要であると思われる。【理学療法学研究としての意義】体幹ローカル筋群である腹横筋と腰部多裂筋に関して,低負荷条件において有意な正の相関関係が認められた。本所見は,体幹へ安定性を提供するとされている両筋の形態学的関連性を示唆した初めての研究であり,リハビリテーションにおける体幹機能の評価やその解釈に対して有用な知見となるだろう。
1 0 0 0 OA 精神物理学の統一理論
- 著者
- 森 周司
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.2, pp.244-264, 1993 (Released:2019-07-24)
1 0 0 0 公正世界信念と犯罪不安,被害リスク認知が被害者非難へ与える影響
- 著者
- 柴田 侑秀 森永 康子
- 出版者
- 同志社大学心理学会
- 雑誌
- 同志社心理 (ISSN:0389312X)
- 巻号頁・発行日
- no.65, pp.1-7, 2018
1 0 0 0 特集 シンポジウム 和解学の創成
1 0 0 0 OA 試論:人はなぜ感情をもつのか ─行動決定における感情の計算論的役割─
- 著者
- 高橋 さゆり 森 ちか 佐藤 悠佑 山田 大介 平野 美和 河村 毅 上條 利幸 本間 之夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本泌尿器科学会
- 雑誌
- 日本泌尿器科学会雑誌 (ISSN:00215287)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.2, pp.525, 2010-02-20 (Released:2017-04-08)
- 著者
- 大森 俊夫
- 出版者
- 公益社団法人 全国大学体育連合
- 雑誌
- 大学体育 (ISSN:02892154)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.76-79, 2004-03-15 (Released:2017-07-03)
1 0 0 0 西洋をエンジン・テストする : キリスト教的制度空間とその分裂
- 著者
- ピエール・ルジャンドル著 森元庸介訳
- 出版者
- 以文社
- 巻号頁・発行日
- 2012
1 0 0 0 OA 健常者用幻聴様体験尺度(AHES)の作成および信頼性・妥当性の検討
- 著者
- 杉森 絵里子 浅井 智久 丹野 義彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.5, pp.389-396, 2009 (Released:2012-03-20)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 7 7
Auditory hallucinations are important symptoms when making a diagnosis of schizophrenia. Since normal people may also experience auditory hallucinations, there may be a spectrum of auditory hallucinations ranging from those experienced in schizophrenia to those experienced by normal people. To assess the propensity to auditory hallucinations in a non-clinical population, we selected forty items from the questionnaire in Tanno, Ishigaki, & Morimoto (1998) and developed the Auditory Hallucination-like Experience Scale (AHES). Test-retest reliability showed that the AHES was internally consistent. There were high correlations between the AHES and the STA subscale and the overall O-LIFE (especially ‘unusual experiences’), both of which are thought to be strongly related to schizophrenia. Furthermore, the rate of false positives was higher in people more prone to auditory hallucinations than in the group less prone to auditory hallucinations. Factor analysis revealed that the AHES consists of four factors. The results suggest that the AHES has high reliability and validity as a measure of susceptibility to hallucinations.
1 0 0 0 OA ダム堆積物の連携排砂が黒部川の下流に与える影響, その2
- 著者
- 田崎 和江 国峯 由貴江 森川 俊和
- 出版者
- The Clay Science Society of Japan
- 雑誌
- 粘土科学 (ISSN:04706455)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.64-74, 2001-12-31 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 1
In 1985, Dashidaira dam with discharge gate had been built for the first time in Japan, at Kurobe River in Toyama Prefecture. Six years later, in 1991, the dam sediments were flushed out for the first time and impacted on the downstream of Kurobe River. The dam sediments and the suspension contained a large amount of organic matter (with high C, N and S contents) with sludge-smell. The annual catch of bentic fishes (exp. flatfish) and the annual haul of wakame seaweed have been decreased year by year since the first discharge of the dam sediments in 1991. Until now, it has been reported that the sludge has deposited in the Toyama Bay which is apprehensive of influence of discharged dam sediments, because suspended particles affect the fish's gill respiration.In this study, suspension of river water were collected at three bridges during discharge from Dashidaira and Unazuki Dam in June 19th-22nd and in June 30th-July 2nd, 2001. River water quality and suspended solid were analyzed chemically, physically and mineralogically. Extremely low DO and Eh values were observed at the periods during first discharge in June 19th-22nd at two bridges. Moreover, during second discharge in June 30th-July 2nd, DO and Eh values were constant. Therefore it was shown that drastic decreased of DO and Eh values were a peculiar phenomenon during first discharge in June 19th-22th, 2001. The results of NCS elemental analyses were suggested that high organic contents were related with drastic decreased of DO and Eh values. Clay mineralogy of both Unazuki Dam sediments and suspended solid on the seabed at the offing of Kurobe River mouth, show abundant semctite with chlorite, mica clay minerals and kaolin minerals, suggesting those are the almost same origin. The dam sediments associated with organic matter impacted on downstream and the seabed, and was the cause of affecting bentic fishes and wakame seaweed.
1 0 0 0 OA 中耳腔に投与された薬剤の安全性について
- 著者
- 森園 哲夫
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.7, pp.663-669, 2002-07-01 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 2 2
A literature review of the safety or ototoxicity of antimicrobials applied to the middle ear cavity was performed. Animal experiments indicated ototoxic effects of otic drops used for the treatment of suppurative otitis media as well as some antiseptic solutions used for preoperative sterilization for the middle ear surgery. Clinical experience indicated fewer adverse effects following the use of antimicrobials and antiseptics in the middle ear cavity, although scant but serious side effects have been reported in the literature. The discrepancy of animal experiment and clinical experience is due largely to the anatomical differences of the cochlea, the round window of rodents are very thin and exposed into the middle ear cavity, whereas that of humans is thick and situated deep in the niche, and often covered with a pseudomembrane.We evaluated the safety of recently marketed eardrops Ofloxacin (OFLX) and Fosfomycin sodium (FOM). Based on the lack of reduction of the compound action potential in guinea pigs, we concluded that there was no ototoxic effect using OFLX or FOM.Also, the ototoxic effect of a Povidone-Iodine preparation was studied. Full strength solution instilled into the middle ear cavity did not cause sensorineural hearing loss at the 24 hours, indicating that rinsing the middle ear cavity with saline during surgery should prevent ototoxic effects of this product.
1 0 0 0 OA ダム湖の生態
1 0 0 0 OA 流域治水を実現する分散型市民多目的ダムの構築
- 著者
- 森山 聡之 武藏 泰雄 西山 浩司 渡辺 亮一 和泉 信生 森下 功啓 山口 弘誠 中北 英一 島谷 幸宏 河村 明 牛山 素行 松尾 憲親
- 出版者
- 福岡工業大学
- 雑誌
- 基盤研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2014-04-01
分散型多目的市民ダムをスマート化し、水資源確保と洪水制御を行う雨水グリッドとするために、(1)降雨量測定装置としての雨水タンクの検証を行い、雨量計としては利用可能なものの、雨水タンクが砕石充填方式の場合は圧力センサーを水位計として使用しない方が良いことを示した。(2)防災クラウドによる雨水の見える化として、センサーノードとゲートウエイの安定化を計った。(3)豪雨発生診断をSOMを用いて行ったが、予測精度はあまり高くないことが判明した。セキュリティー向上として、 OpenVPNを用い暗号化となりすまし防止を行った。(4)無線回線の安定化を図るためにLoRaWANを検証、良好な結果を得た。
1 0 0 0 OA 危機理論研究ノート(3)—ケース研究について
- 著者
- 森 武夫
- 出版者
- 日本犯罪心理学会
- 雑誌
- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.39-46, 1990 (Released:2018-12-29)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 西半球における宗教の政治化現象
- 著者
- 森 孝一
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.26, pp.145-164, 1992-03-25 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 60
1 0 0 0 OA 各種機器分析によるフルオロ-フェンタニル類の位置異性体識別
- 著者
- 金森 達之 岩田 祐子 瀬川 尋貴 山室 匡史 桑山 健次 辻川 健治 井上 博之
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.123-133, 2019 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 13
The isomers of fluoro-butyrylfentanyl, fluoro-isobutyrylfentanyl, and fluoro-methoxyacetylfentanyl, in which the position of fluorine on the N-phenyl ring varies, were synthesized, characterized, and differentiated by infrared (IR) spectroscopy, liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS), and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). The isomers could be clearly differentiated by their IR spectra. In the LC/MS chromatograms, the separation of the fluoro-butyrylfentanyl and fluoro-isobutyrylfentanyl isomers was insufficient. However, in the GC/MS extracted ion chromatograms, all compounds were completely separated. The LC/MS and GC/MS mass spectra of the isomers were similar, demonstrating that it is difficult to distinguish the positional isomers of fluorinated fentanyl analogs by their mass spectra.
- 著者
- 春田 祐輔 森田 敦 大槻 光彦 中園 陽子 中山 秀幸 八ヶ代 一郎 内川 貴志
- 出版者
- 日本法科学技術学会
- 雑誌
- 日本法科学技術学会誌 (ISSN:18801323)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.123-132, 2017 (Released:2017-07-27)
- 参考文献数
- 12
Several synthetic cannabinoids such as AM-2201 contain the 3-carbonyl-N-fluoropentylindole structure. This structure has fluorine positional isomers on the alkyl chain. In most cases, legal controls are placed only on the 5-fluoro analogue. Thus, differentiation of isomers is a significant issue in forensic science. In this study, we developed a method for the differentiation of positional isomers of 3-carbonyl-N-fluoropentylindole derivatives utilizing multiple-stage mass spectrometry using an ion trap tandem mass spectrometer. In addition, the analogues whose fluorine atom was replaced with a chlorine atom or hydroxyl group were also examined. With respect to each positional isomer of fluorine and chlorine, the ion at m/z 232 or m/z 248, obtained by MS2 analysis of [M+H]+, were selected as the precursor ions for MS3 analysis. The ion at m/z 232 and m/z 248 corresponded to the 3-carbonyl-N-fluoropentylindole and 3-carbonyl-N-chloropentylindole structures. Furthermore, the ion at m/z 212, corresponding to the de-halogenated fragments of the 3-carbonyl-N-fluoropentylindole- and 3-carbonyl-N-chloropentylindole-structures, was selected as the precursor ion for MS4 analysis. Consequently, combination of these MSn analysis achieved differentiation of all the positional isomers. With respect to positional isomers with the hydroxyl group, however, the fragment ion at m/z 212 was not observed from the MS3 analysis of m/z 230, which corresponds to the 3-carbonyl-N-fluoropentylindole structure. Therefore, differentiation of each positional isomer was not achieved by MSn analysis. This method is useful for the differentiation of positional isomers of 3-carbonyl-N-fluoropentylindole and 3-carbonyl-N-chloropentylindole derivatives.