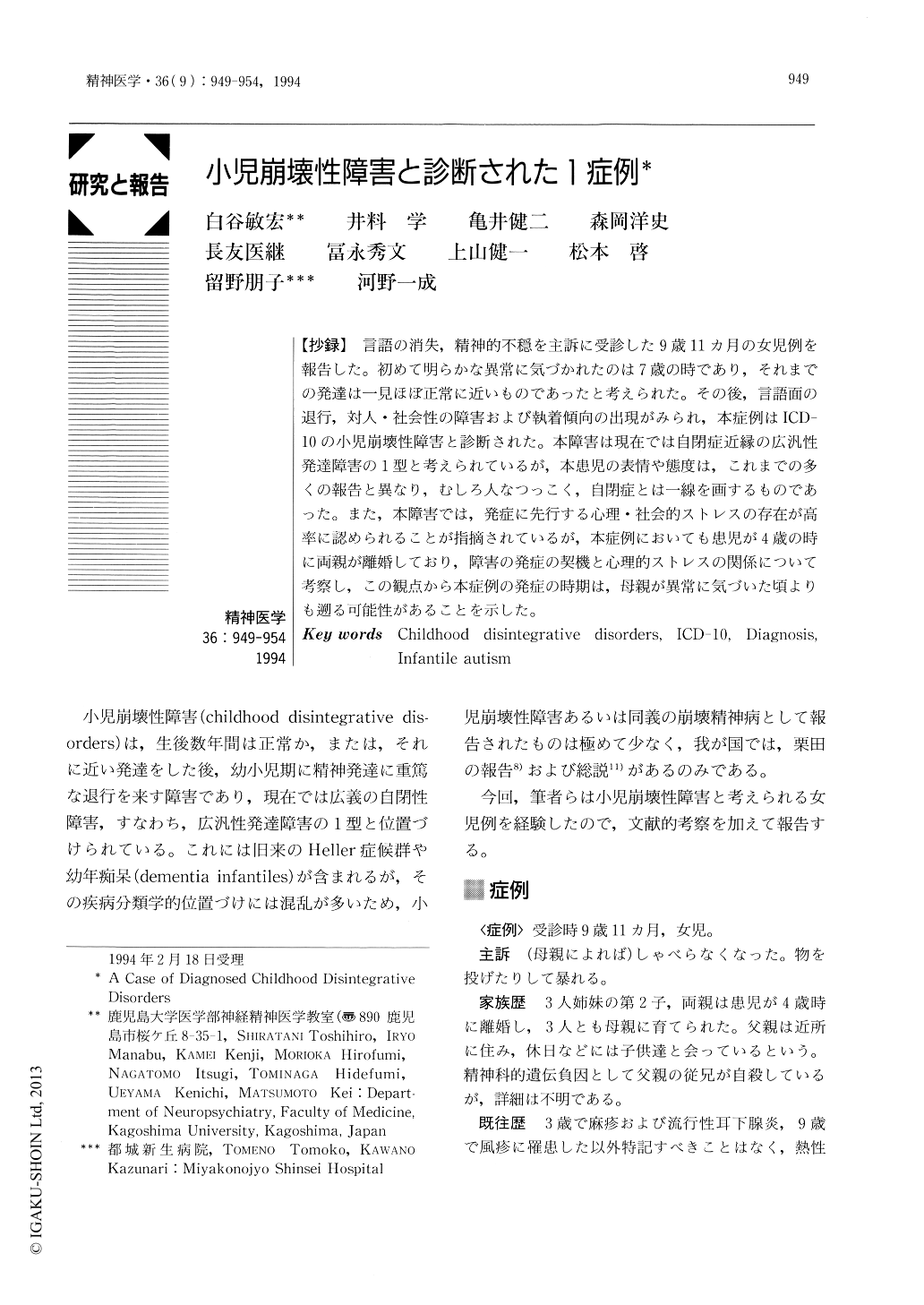1 0 0 0 OA 鯉を用いた宇宙酔いの基礎研究
- 著者
- 森 滋夫 御手洗 玄洋 高木 貞治 高林 彰 臼井 支朗 中村 哲郎 榊原 学 長友 信人 R. J. von BAUMGARTEN
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.489, pp.625-628, 1994-10-05 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 8
1 0 0 0 IR プラズマロケットの研究
- 著者
- 長友 信人
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.6, pp.178-182, 1962-06
大型ブースターロケットによる人工衛星の打上げと,原子力発電装置の開発は,惑星間飛行への道を開き,新しいロケットエンジンとして電気推進系の実現を可能にした.電気推進系のエンジンには種々のものが考案されたが,なかでもプラズマロケットは一般性と将来性を持つものである.この論文では,マイクロ波を電力源としてプラズマを加速するエンジンについて理論解析を行ない,ロケットとして用いる可能性を示した.目下簡単なモデルによる実験を行なっている.
1 0 0 0 小児崩壊性障害と診断された1症例
- 著者
- 白谷 敏宏 井料 学 亀井 健二 森岡 洋史 長友 医継 冨永 秀文 上山 健一 松本 啓 留野 朋子 河野 一成
- 出版者
- 医学書院
- 雑誌
- 精神医学 (ISSN:04881281)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.9, pp.949-954, 1994-09-15
【抄録】 言語の消失,精神的不穏を主訴に受診した9歳11カ月の女児例を報告した。初めて明らかな異常に気づかれたのは7歳の時であり,それまでの発達は一見ほぼ正常に近いものであったと考えられた。その後,言語面の退行,対人・社会性の障害および執着傾向の出現がみられ,本症例はICD—10の小児崩壊性障害と診断された。本障害は現在では自閉症近縁の広汎性発達障害の1型と考えられているが,本患児の表情や態度は,これまでの多くの報告と異なり,むしろ人なつっこく,自閉症とは一線を画するものであった。また,本障害では,発症に先行する心理・社会的ストレスの存在が高率に認められることが指摘されているが,本症例においても患児が4歳の時に両親が離婚しており,障害の発症の契機と心理的ストレスの関係について考察し,この観点から本症例の発症の時期は,母親が異常に気づいた頃よりも遡る可能性があることを示した。
- 著者
- 長友 拓憲 川平 和美 弓場 裕之 佐々木 聡 伊藤 可奈子 長谷場 純仁
- 出版者
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会
- 雑誌
- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)
- 巻号頁・発行日
- vol.2006, pp.149, 2006
【はじめに】<BR> 転落によりTh12からL2(L1粉砕骨折)の損傷による脊髄損傷患者に対し、両側KAFOの膝継手として、Spring assisted extension knee joint:伸展補助装置付膝継手(以下SPEX:アドバンフィット社製)を処方し、歩行の実用性に改善がみられたため報告する。SPEXの特性として、筋力に応じた膝伸展補助装置機能があり、伸展位固定でも軽度の屈伸の可動性が得られ、膝折れを予防する効果がある。そのため立脚初期に軽度の膝屈曲が出現し、二重膝作用が働き正常に近いスムーズな交互歩行が可能となる。リングロック固定式にも使用でき、無段階の可動域調整が可能である。また屈曲拘縮の矯正が0°から60°の範囲で一定のトルク負荷が可能であり、コイルスプリングをスチールロッドと交換し屈曲制限及び固定として使用可能である。適応は、脳卒中片麻痺、脊髄損傷、大腿四頭筋筋力低下、膝及び肘関節拘縮、進行性筋ジストロフィーに用いられる。<BR>【症例・理学療法経過】<BR>50才女性。転落によるTh12からL2(L1粉砕骨折)の損傷。胸腰椎骨折固定術施行。入院時評価:American Spinal Injury Association(以下ASIA)は運動C、感覚C。下肢は不全麻痺が両側に残存し、MMTにて股関節外転右2+、左2+、膝関節右伸展4左3+であった。歩行に関しては、膝折れが見られ、平行棒内軽介助レベルにて可能。ADLに関しては、移乗は軽介助レベル、寝返り・起き上がりは自立、座位保持は長座位自立、端座位は自立。立位は両上肢支持にて自立レベル。随意的な膝関節の屈伸運動が可能であるため、SPEXを用い下肢筋力増強、屋内歩行動作獲得を目標に用いた。約2ヶ月間理学療法を施行した。下肢の筋力増強プログラムと併用し、歩行期間に関しては約1ヶ月平行棒内、歩行器での歩行練習をコイルスプリングによる伸展補助力を微調整しながら施行した。退院時評価:ASIAは変化なし。下肢筋力が股関節外転右3+、左3+、膝関節右伸展4、左4に改善した。ADLは、車椅子への移乗が自立レベルに改善した。歩行に関しては、SPEX使用にて平行棒内歩行自立レベル、屋内歩行を歩行器にて監視レベルにて可能となった。<BR>【考察】<BR>今回はSPEXのコイルスプリングによる伸展補助力の微調整と足継手(ダブルクレンザック)の調整を行っていきながら歩行練習を行っていき、膝関節の屈伸運動を可能とし、随意的な収縮がみられたため、また自主練習にて平行棒内歩行練習を加え、通常のプログラムによる筋力増強運動も併用し、股関節・膝関節周囲筋の筋力増強がより効果的になり、歩行の実用性につながったと示唆される。<BR>【終わりに】<BR>今回はSPEXのコイルスプリングによる伸展補助力の微調整と足継手(ダブルクレンザック)の微調整をしながら、歩行練習を行ったが、下肢伸展筋力の個人差に対して、コイルスプリングの強度調整が困難であった。また歩行のアライメント調整のため、膝継手と足継手で通常は約2:1の割合で角度調整が求められるが、患者自身の能力、歩行練習中での問診、分析に応じて調整が求められる。今後症例を重ねて客観的な有効性を検討していく。
1 0 0 0 OA 妊婦に発生したメチシリン感受性黄色ブドウ球菌による化膿性仙腸関節炎の1症例
- 著者
- 川村 英樹 山元 拓哉 長友 淑美 鶴 亜里沙 石堂 康弘 横内 雅博 井尻 幸成 小宮 節郎
- 出版者
- 西日本整形・災害外科学会
- 雑誌
- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.277-281, 2007 (Released:2007-06-01)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
25歳女性.妊娠34週突然左腰殿部痛出現.仙骨硬膜外ブロック施行されるも疼痛軽減せず当院産科に緊急搬送となる.入院時疼痛強く仰臥位不能,左仙腸関節部に圧痛を認めた.発熱,炎症所見(白血球数9400/μl,CRP 11.91)があり,骨盤部MRI上左仙腸関節周囲の信号変化,また血液培養,カテーテル尿培養よりメチシリン感受性黄色ブドウ球菌を認め,尿路感染に伴う菌血症により発生した化膿性仙腸関節炎と診断し,セファゾリンによる抗菌化学療法を開始.症状改善し妊娠39週にて帝王切開により出産.母子ともに経過良好であり産後3週自宅退院となる.仙腸関節は菌血症性関節炎の好発部位の一つであり,妊娠にともなう子宮の増大等が誘因と考えられた.胎児への影響を考慮する必要があるため診断,治療に難渋するが,妊婦の腰殿部痛の原因として化膿性仙腸関節炎も鑑別する必要がある.
1 0 0 0 B. レーザー装置
- 著者
- 坂井 正宏 永井 伸治 河野 明廣 後藤 俊夫 古橋 秀夫 内田 悦行 佐々木 亘 米谷 保幸 河仲 準二 窪寺 昌一 加来 昌典 田中 鋭斗 島田 秀寛 和仁 郁雄 遠藤 雅守 武田 修三郎 南里 憲三 藤岡 知夫 河野 貴則 杉本 大地 川上 政孝 長友 昭二 梅原 圭一 砂子 克彦 登倉 香子 中澤 幹裕 福田 祥吾 草場 光博 綱脇 恵章 大東 延久 藤田 雅之 今崎 一夫 三間 囹興 大久保 宏一 古河 祐之 中井 貞雄 山中 千代衛 奥田 喜彦 太田 篤宏 直川 和宏 清地 正人 田中 秀宏 Roy Prabir Kumar 文 雅可 佐野 栄作 中尾 直也 沓掛 太郎 衣笠 雅則 山口 滋 森 啓 鈴木 薫 中田 順治 上東 直也 山中 正宣 和田 一津 内藤 靖博 永野 宏 蓮池 透 谷脇 学 清水 幸喜 佐藤 俊一 高島 洋一 中山 通雄 湯浅 広士 津野 克彦 滝沢 実 小西 泰司 畠山 重雄 沈 徳元 劉 安平 植田 憲一 桐山 博光 西田 幹司 日浦 規光 市位 友一 松井 宏記 田中 広樹 井澤 靖和 山中 龍彦 久保 宇市 神崎 武司 宮島 博文 宮本 昌浩 菅 博文 沖野 一則 今井 浩文 米田 仁紀 上田 暁俊 門馬 進 斎藤 徳人 赤川 和幸 浦田 佳治 和田 智之 田代 英夫 Droz Corinne 古宇 田光 桑野 泰彦 松原 健祐 田中 歌子 今城 秀司 早坂 和弘 大向 隆三 渡辺 昌良 占部 伸二 小林 準司 西岡 一 武井 信達
- 出版者
- The Laser Society of Japan
- 雑誌
- レーザー研究 (ISSN:03870200)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.27-55,60, 1998
1 0 0 0 OA 生胚内個別染色体動態解析および染色体操作による次世代胚操作技術の確立
核移植技術では核そのものを操作するが、それよりも小さな単位、すなわち染色体を操作するための技術開発を試みた。特定の染色体をラベルするためsuntag systemを使用し、ES細胞中のY染色体をラベルすることに成功し任意の染色体をラベルできる可能性を示した。また胚の染色体を分散させることで、生きた胚間での染色体移植が可能であることを示した。しかしながら、胚において特定染色体をラベルして操作するには至らなかった。加えて、染色体操作の使用が想定される絶滅危惧種において、個体を傷つけずに採取可能な尿中に含まれる極わずかな細胞から、クローン個体およびntES細胞株が樹立可能であることを示した。
1 0 0 0 西南暖地における豚の放牧に関する研究
- 著者
- 佐藤 勲 長友 安雄 安藤 忠治 稲沢 昭
- 出版者
- The Japanese Society of Swine Science
- 雑誌
- 日本養豚研究会誌 (ISSN:03888460)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.14-22, 1964
1) 豚の放牧による肥育は飼料の利用性, 発育, 斎度, 寄生虫, 皮膚病などにより問題があるとされていたが, 甘藷畑で放牧肥育を実施した結果, 1日平均659g~730gとすぐれた発育を示した。その発育に比較して飼料要求率は3.61~3.92とやや悪るく, 発育にバラツキが見られた。<br>2) 省力管理は期待できる。すなわち, 甘藷の収穫, 調理, 給与の手間がかからずに, しかも飼育管理でも1頭当り, 2時間53分, 1日1頭当り換算すると2分02秒であった。<br>3) 甘藷畑10aに肥育豚を10頭放牧して仕上げることができるかどうかは, 収量と放牧時期, 方法によるが, 本試験の結果では可能であり, 放牧豚はきわめて上手に甘藷を採食し, ロスが少なかった。<br>4) 甘藷畑放牧においては, 体重20kgより開始しても発育の停滞および事故はなかった。<br>5) 放牧期間中数回の降霜があったが, 降霜後の甘藷を採食しても事故はなく, また甘藷の品種による嗜好性の相違があった。<br>6) 肥育末期の舎飼は発育を良好にし, しかも飼料の利用性もよくなった。すなわち, BL区で1日平均増体重が14g, L区で12g半放牧区がすぐれ, 飼料要求率では, BL区で0.25, L区で0.3半放牧区がすぐれていた。<br>7) 甘藷の採食量は多く, 牧区拡張当日はやや過食の傾向があるので放牧方法を検討する必要がある。<br>8) 総給与量 (風乾量) に対し40%の甘藷を採食したが, 皮下脂肪が比較的うすく, 肉質良好, 腎臓脂肪が少なかった。<br>9) 寄生虫の被害は殆んどなかった。<br>10) 放牧のため発生したと考えられる疾病および事故はなかったが, 電気牧柵を利用した放牧であるため, 脱柵の習慣がついたものが生体重70kg時に1頭あった。これは甘藷を堀りながら前進するため架線が高いと知らぬまに脱柵していることから習慣となったものである。
1 0 0 0 OA 大学等の化学実験室における低予算での化学物質蒸気由来リスク低減の試み
- 著者
- 長友 重紀 藤井 邦彦 佐藤 智生
- 出版者
- 大学等環境安全協議会
- 雑誌
- 環境と安全 (ISSN:18844375)
- 巻号頁・発行日
- pp.17H0301, (Released:2017-07-01)
- 参考文献数
- 7
大学等の化学実験におけるリスク低減は長年の課題である。その中でも、多人数が同時に実験を行う学生実験室において揮発性の高い化学物質を使用する場合、実験を行う学生数に対して十分な数の囲い式フード型の局所排気装置を設置できていない状況がある。さらに、囲い式フード型の局所排気装置については、予算とスペースの問題から必要数を導入できない場合も多い。そこで、我々は低費用でリスクの低減化を図るために、通常の化学実験室に備えられている既設の設備を活用して外付け式フード型の局所排気装置を導入した。本報告では、その費用対効果と実際に使用した学生の意見を示し、化学実験における安全性の向上および教育効果を紹介する。
1 0 0 0 OA 古代日向における国際交流 宮崎県南郷村の百済伝説の考察
- 著者
- 長友 武 Takeshi NAGATOMO
- 雑誌
- 宮崎公立大学人文学部紀要 = Bulletin of Miyazaki Municipal University Faculty of Humanities
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.1-10, 1995-03-20
1 0 0 0 亜鉛及び銅過剰がキュウリの子づる・孫づる形成に及ぼす影響
- 著者
- 横山 明敏 佐伯 雄一 柴田 聡子 長友 由隆 赤尾 勝一郎
- 出版者
- 日本土壌肥料學會
- 雑誌
- 日本土壌肥料學雜誌 = Journal of the science of soil and manure, Japan (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.4, pp.475-478, 2004-08-05
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
宮崎県のハウス抑制キュウリ栽培の圃場において、本来ならば側枝となるべき側芽の伸長が抑制されたり、伸長しても途中で枯死する障害が多発した。その原因を究明するために、現地圃場の土壌調査と葉分析の結果から、亜鉛と銅の過剰障害による可能性が推定されたので、水耕法により検証した結果、亜鉛の過剰吸収が原因である可能性が強く示唆された。
1 0 0 0 OA 社会福祉労働論の基礎的研究
- 著者
- 長友 薫輝
- 出版者
- 三重短期大学
- 雑誌
- 紀要 (ISSN:09186948)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.27-31, 2006-03-20
1 0 0 0 OA <論文>液水/液酸ターボポンプ用ガスジェネレーターの開発研究
- 著者
- 棚次 亘弘 成尾 芳博 長友 信人 岩間 彬 秋葉 鐐二郎 倉谷 健治
- 出版者
- 宇宙航空研究開発機構
- 雑誌
- 東京大学宇宙航空研究所報告 (ISSN:05638100)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.2, pp.859-891, 1980-05
推力7トン級液水/液酸ロケットエンジン用ターボポンプを駆動するガスジェネレーターの設計および試験を昭和52年から実施し,その開発を完了した.このガスジェネレーターはリバースフロー型のものであり,撹拌リング付の球形燃焼室と12個の均一混合比型の同軸インジェクターおよびスタートバルブから構成されている.8回のガスジェネレーター単体での試験および10回のターボポンプとの組合せ試験によって,性能および機能の確認を行った.インジェクター,燃焼室およびタービン部に焼損は認められず,燃焼および混合が良好に行われているものと思われる.現在までの総燃焼時間は204秒である.ここでは,東大宇宙研において開発したガスジェネレーターの設計諸元,試験設備および試験結果を報告する.
- 著者
- 長友 孝文 大貫 敏男 服部 薫 石黒 正路 渡邊 賢一
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.Supplement2, pp.46-49, 1998-06-25 (Released:2013-05-24)
- 参考文献数
- 10
1 0 0 0 OA アドレナリン性β受容体の三次元構造およびアンタゴニストの結合様式の推定
- 著者
- 大貫 敏男 長友 孝文 石黒 正路
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.supplement, pp.123-126, 1999 (Released:2007-02-27)
- 参考文献数
- 8
二次元電子密度マップから推定されたbactehorhodopsinあるいはfrog rhodopsinの構造をテンプレートとして、コンピュータ解析によりヒト-アドレナリン性β受容体の膜貫通部位の三次元構造を推定した。それぞれのテンプレートに由来する二つのモデルにおいて、推定されたα-helix領域、およびその相対位置あるいは配向性などに違いが認められた。このモデルを用い、代表的β受容体アンタゴニストであるpropranolol、および当研究室が薬理学的研究を行ってきた持続性β受容体アンタゴニストであるbopindolol(4-(3-t-butylamino-2-benzoyloxypropoxy)-2-methylindole)の結合様式を推定した。どちらのモデルを用いても、アンタゴニストの結合様式を推定することができた。しかし、両モデルにおいて推定された結合様式は異なっていた。すなわち、両モデルにおいてN末端から3、4、5および6番目のα-helixが結合に関与すると推定された点では一致するものの、関与するであろうアミノ酸残基が異なっていた。さらに、推定された結合様式からpropranololおよびbopindololのサブタイプ選択性、つまりβ1およびβ2サブタイプに対して高親和性であるが、β3サブタイプに対しては低親和性である点を一部説明することができた。
- 著者
- 洗 津 山田 浩也 遠藤 玄 デベネスト パウロ グアラニエリ ミケーレ 風間 裕人 長友 一郎 広瀬 茂男
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- ロボティクス・メカトロニクス講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2013, pp."1A2-P20(1)"-"1A2-P20(2)", 2013-05-22
For the decommissioning of the Fukushima Daiichi nuclear power plant, we need robot arms which have long and slender shape, wide motion range, and radiation-tolerant system. However, existing robot arms are not capable of satisfying those requirements. In particular, the extremely large torque generated by the arm weight is the most difficult problem in the development of such long and slender arms. Therefore, in order to satisfy those requirements, we propose a new robot arm named "3D CT-Arm". The 3D CT-Arm uses a "coupled tendon drive", in which the all joints are driven by motors located on the base through wires and pulleys, and the all motors support the torque on the base joint. Thus, the 3D CT-Arm can maintain its posture even when it extends the arm horizontally. In this paper, we introduce the concept of 3D CT-Arm and show the design and test of a prototype.
- 著者
- 長友 由隆 庄子 貞雄 玉井 理
- 出版者
- 一般社団法人日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料學雜誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.5, pp.218-222, 1977-05-25
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA 〔翻訳〕周長軍「中国刑事訴訟法の改正およびその特徴」
1 0 0 0 表面筋電位を用いた個人認証手法の実現に向けた基礎研究
- 著者
- 山場 久昭 長友 想 油田 健太郎 久保田 真一郎 片山 徹郎 朴 美娘 岡崎 直宣
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. IOT, [インターネットと運用技術] (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.32, pp.1-6, 2015-05-14
近年,スマートフォンやタブレットのようなモバイル端末の普及に伴い,覗き見によって認証に必要な情報が第三者に取得されてしまてしまうことが問題となってきている.これを解決する技術として,指紋などの生体情報を用いた生体認証が注目されている.本論文では,そのひとつである筋電位を用いた個人認証について検討を行う.具体的には,前腕部の筋電位の波形が手首から先の手の動き (ジェスチャー) によって異なる波形を示すことを利用し,そのジェスチャーを組み合わせてパスワードとして用いる手法を提案する.今回は,個人認証に用いる生体認証として筋電位が利用可能であるのか,筋電位の波形からジェスチャーを判断することができるのか,また,それを計算機上に行わせるのが可能かどうかについて検討を行ったので,報告する.