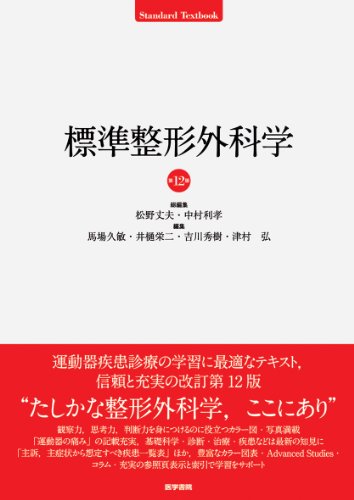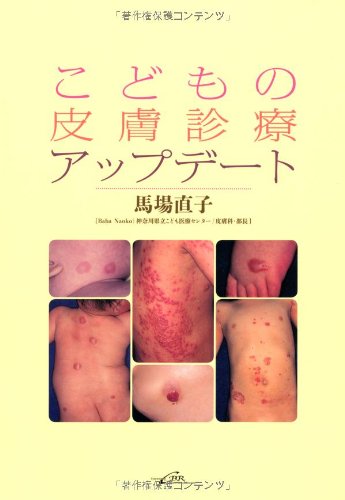1 0 0 0 OA 少量の氷点降下剤添加による小型氷蓄熱槽の氷充てん率改善効果の検証
- 著者
- 牟田 健二 馬場 敬之 酒井 孝司 石原 修
- 出版者
- 社団法人空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会論文集 (ISSN:0385275X)
- 巻号頁・発行日
- no.92, pp.1-9, 2004-01-25
直膨内融式スタティック型氷蓄熱槽は,ダイナミック型に比べて氷充てん率(IPF)を大きくとれるが,IPFはそれでもまだ0.65程度にとどまっている。これはこのシステムでは蓄冷材として市水(添加物を加えていない水)が用いられており,水が凝固する際の体積膨張により管群を破損する危険性があり,実際の製氷運転ではブリッジングが起こる前で製氷を停止しているためである。そこで本研究では,少量の氷点降下剤を添加した水溶液を凝固させると固一液が共存した凝固層ができる性質を利用して蓄冷材に用いることにより,従来の市水を用いる場合より氷充てん率が増加する可能性を検証した。
- 著者
- 馬場 安紀子 谷口 恭子 折原 俊夫 古谷 達孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.12, pp.1215, 1986 (Released:2014-08-08)
臨床的に鎖骨等の骨直上に好発する特異な色素沈着症いわゆるfriction melanosis(FM)の皮疹を呈し,しかも病理組織学的にアミロイドの沈着が認められた6症例を報告した.症例は男性1例,女性5例,年齢29~52歳,全例ナイロンタオル使用歴を有した.皮膚科外来を受診した種々の皮膚疾患患者を対象に,ナイロンタオルに関するアンケートを実施したが,男性274人中123人(44.9%),女性364人中234人(64.3%),総計638人中357人(56.0%)にナイロンタオル使用歴があり,年齢別では10,20,40各代の順に使用率が高かった.上記のアンケート調査638人中,骨直上に色素沈着が認められたものは,ナイロンタオル非使用者281人中1例(0.4%),使用者357人中18例(5.0%)の計19例(男性8例,女性11例)であった.当科において皮膚生検を施行したFM例は合計9例で,うち6例にアミロイドの沈着が認められた.自験例はFMに併発した続発性アミロイドーシスと考えられるが,本症と限局性皮膚アミロイドーシスの1型であるmacular amyloidosisとの関係についても論じた.
1 0 0 0 OA 1型糖尿病の早期発見・治療を介して患者予後改善に資する発症予知システムの構築
1 0 0 0 OA オリオン・クラウタウ『近代日本思想としての仏教史学』
- 著者
- 馬場 真理子
- 出版者
- 東京大学文学部宗教学研究室
- 雑誌
- 東京大学宗教学年報 (ISSN:02896400)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.251-258, 2014-03-31
書評/Book Reviews
1 0 0 0 大阪大学におけるキャンパスPKIの構築
- 著者
- 岡村 真吾 寺西 裕一 秋山 豊和 馬場 健一 中野 博隆
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. DPS,マルチメディア通信と分散処理研究会報告 (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, pp.67-72, 2006-03-16
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 4
大阪大学では、多くの学内システムを統合的かつ安全に機能させるため、全学にわたる公開鍵認証基盤(キャンパスPKI)を構築する計画を進めている。公開鍵暗号を用いた認証を行なうことで、パスワードによる認証において問題となるパスワード解読の脅威に対する耐性を高めることができる。キャンパスPKIを構築するにあたり、ユーザ公開鍵・秘密鍵の管理方法や認証局の運用形態といったPKIの運用方法や、Webシングルサインオンや計算機ログイン認証といったPKIを利用したアプリケーションについての検討を行った。本稿では、それらの検討内容や構築中のキャンパスPKIの構成について述べる。
1 0 0 0 OA 造血幹細胞のホメオスターシスの維持と破綻
造血幹細胞ニッチと幹細胞動態の研究、ならびに幹細胞におけるDNA損傷反応に関する研究を展開し、しかるべき成果を得て論文発表すことができた。幹細胞ニッチに関する研究に関しては、Integrin avb3 が周囲の環境に応じて、サイトカインシグナルを増強することを通して、造血幹細胞の維持・分化を制御することを示した(EMBO J, 2017)。造血幹細胞の代謝に関連した研究では、造血幹細胞が分裂する直前に、細胞内カルシウムの上昇を通して、ミトコンドリアの機能が活性化することを見出した。さらに、造血幹細胞分裂直前の細胞内カルシウムが上昇をカルシウムチャネル阻害によって抑制すると、① 造血幹細胞の分裂が遅延すること、② 分裂後の幹細胞性の維持(自己複製分裂)に寄与することを示した。また、in vivo において、造血幹細胞周辺のMyeloid progenitor(lineage-Sca-1-c-kit+)細胞が細胞外アデノシンが造血幹細胞の細胞内カルシウムの上昇やミトコンドリア機能の制御に関与することも確認した。さらに興味深いことに、Myeloid progenitorは、上記の細胞外アデノシンによる造血幹細胞の与える影響を増強していることも見出している(JEM in Revision)。造血幹細胞におけるDNA 損傷反応における研究では、Shelterinと呼ばれるタンパク複合体の構成因子Pot1aが、造血幹細胞のDNA損傷の防止に加えて、活性酸素(ROS)の産生を抑制し、造血幹細胞の機能維持に寄与することを新たに明らかにした(Nat Commun, 2017)。
1 0 0 0 OA 房総、姉ヶ崎-千葉市付近の更新統
1 0 0 0 OA 失語症非訓練例の回復について
- 著者
- 前島 伸一郎 種村 純 重野 幸次 長谷川 恒雄 馬場 尊 今津 有美子 梶原 敏夫 土肥 信之
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.123-130, 1992-02-18 (Released:2009-10-28)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 3 2 5
言語訓練をうけることができなかった脳血管障害による失語症患者30例を対象に,失語症状の自然経過を経時的に評価し,年齢,性,原因疾患,失語症タイプ等との関係を検討した,言語理解は,健忘型で3ヵ月まで改善を認め,他のタイプでは6ヵ月以降にも改善を認めた.発話は,健忘型で3ヵ月まで,表出型,受容型では6ヵ月以降にも改善を認めた.表出-受容型は初期よりほとんど改善を認めなかった.書字は表出-受容型を除くすべてのタイプで3~6ヵ月以降にも改善を認めたが,表出-受容型では初期より改善を認めなかった.重度の失語症では,非訓練例は訓練例のような改善を認めないため,体系的な言語訓練が必要と思われた.
1 0 0 0 OA SLTA成績にみる失語症状の長期経過 —発話項目に関する検討—
- 著者
- 下馬場 かおり 小嶋 知幸 佐野 洋子 上野 弘美 加藤 正弘
- 出版者
- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)
- 雑誌
- 失語症研究 (ISSN:02859513)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.224-232, 1997 (Released:2006-05-12)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
失語症状の長期経過を追跡する研究の一環として,失語症者の発話障害の長期経過を自発話,復唱,音読のモダリティ別に調査した。対象は,発症後16ヵ月以上最高287ヵ月経過した失語症者61例の文水準の標準失語症検査 (SLTA) 発話成績である。 〈結果〉SLTA でみる限り, (1) 3モダリティのなかで復唱はもっとも到達水準が低かった。 (2) 各モダリティの最高到達時の成績パターンは,本研究では6種に類型化が可能であった。 (3) 最高到達時の成績パターンは,発症初期には必ずしも同一のパターンではなかった。 〈結論〉(1) 失語症者にとって,文の復唱はもっとも難易度が高いと考えられた。 (2) 発話3モダリティは,発症年齢,病巣などの要因の関与により,異なる過程を経て特定のパターンに到達することが示唆された。(3) 以上の点は,発話障害の予後推測や,訓練の刺激モダリティ選択において有用な情報を提供すると考えられた。
1 0 0 0 救急車の警告音に関する隊員の意識調査
- 著者
- 馬場 紘彦 江端 正直
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会技術研究報告. SP, 音声
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.141, pp.47-53, 1995-07-14
本論文は、救急車の乗務員2,295人に対して、電子サイレン音についての意識調査を行い、出動中における電子サイレン音の効果や心身への影響等を調べたものである。そして主に次の様な結果が得られた。(1)電子サイレン音は、時と場合により音の大きさを変える必要があり、特に交差点や交通の多い所で大きく、住宅や夜間では小さい方が望ましい。(2)一般車が実際に避譲する距離は30m以内で83%である。(3)電子サイレン音は心身に影響があると回答した人は約41%であり、その内容は、頭痛や耳の障害の他、精神的苦痛等さまざまである。
1 0 0 0 2 パス限定投機方式の提案
- 著者
- 横田 隆史 斎藤盛幸 大津 金光 古川 文人 馬場 敬信
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌コンピューティングシステム(ACS) (ISSN:18827829)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.16, pp.1-13, 2005-12-15
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 23
LSI の高集積化にともない,計算機システムで利用可能なハードウェア資源の量は拡大の一途をたどっているが,一方でクロック速度の向上が飽和する状況になっており,命令レベル・スレッドレベルの並列性を活かした効果的な実行方式が求められている.本論文は,実行頻度の高いホットループに対して,次のイテレーションで行われる実行経路(パス)を予測して投機実行するパスベースの投機的マルチスレッド処理に関して,スレッドレベル並列性を得るための現実的かつ効果的な方法を検討する.パスを投機の対象とすることで,スレッド間依存の問題の緩和や,スレッドコードの最適化が図れるメリットを享受できるが,その一方で,効果的なパスの予測方法・投機方法が課題となる.本論文では,一般的なプログラムでは多くの場合,予測・投機の対象を実行頻度の高い2 つのパスに絞っても実質上問題にならないことを示し,2 つのパスに限定して投機実行する2 パス限定投機実行方式を提案する.実行頻度の上位2 つのパスが支配的である場合は,最初のパスの投機に失敗しても次点のパスが高確率で成功するために実行効率を上げられる.本提案方式をモデル化し解析的に性能見積りを行うとともに,2 レベル分岐予測器をもとにしたパス予測器を用い,トレースベースのシミュレータにより評価を行い有効性を示す.Modern microprocessor systems take their advantages by exploiting large hardware resources in a single chip and by accelerating clock speed. However, in near future, LSI integration will be continued while clock speed be saturated. Thus efficient instruction- and thread-level parallelism is required to achieve higher performance. This paper addresses a path-based speculative multithreading, where frequently executed path is predicted and executed speculatively. We propose a practical speculation method for path-based speculative multithreading. Most practical programs execute only one or two paths in hot-loops, while there are many possible paths according to many branches. We show most frequent two paths are practical candidates to predict and speculate, and thus we propose the two-path limited speculation method. Analytical performance estimation and trace-based simulation results show effectiveness of the proposed method.
1 0 0 0 標準整形外科学
- 著者
- 松野丈夫 中村利孝総編集 馬場久敏 [ほか] 編集 松野丈夫 [ほか] 執筆
- 出版者
- 医学書院
- 巻号頁・発行日
- 2014
1 0 0 0 OA 電解複合研磨-金属の超鏡面化技術
- 著者
- 馬場 吉康 佐藤 憲二
- 出版者
- 社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- 日本金属学会会報 (ISSN:00214426)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.11, pp.813-816, 1993-11-20 (Released:2011-08-10)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 電解複合研磨による金属の超鏡面化技術
- 著者
- 馬場 吉康 佐藤 憲二
- 出版者
- 公益社団法人 日本表面科学会
- 雑誌
- 表面科学 (ISSN:03885321)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.6, pp.368-374, 1990-07-20 (Released:2009-11-11)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 5
電解複合研磨は, 昭和51年に開発した金属表面処理技術で, ステンレス鋼はもとより, アルミ, チタン, 銅などの非鉄金属まで, 加工変質層を伴わずに200~300Åまでの高品位鏡面を, 安定した品質で加工できる新しい技術である。従来の研磨法では, 限界にきているULSI製造プロセスのウルトラクリーン化や, 超, 極高真空システムの高性能化など, 先端ハイテク分野へ貢献しうる電解複合研磨技術について紹介する。
1 0 0 0 OA 電解複合研磨による金属の超鏡面化技術
- 著者
- 河原 純子 兵藤 透 太田 昌邦 平良 隆保 日台 英雄 石井 大輔 吉田 一成 馬場 志郎
- 出版者
- The Japanese Society for Dialysis Therapy
- 雑誌
- 日本透析医学会雑誌 = Journal of Japanese Society for Dialysis Therapy (ISSN:13403451)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.8, pp.695-698, 2011-08-28
蛍光眼底造影剤は,眼科領域では網脈絡膜疾患の診断,治療効果の判定に不可欠な検査である.今回,糖尿病性腎症にて血液透析中の44歳女性に対し眼底出血の疑いのため蛍光造影剤(フルオレサイト<SUP>®</SUP>静注500mg,以下一般名フルオレセインと記す)を使用した.造影後に透析を行った際,透析液排液ラインに造影剤の蛍光色が視認できたため,独自に作製したカラースケールを用いて廃液ラインの排液色の変化による造影剤除去動態を1週間経過観察した.結果,カラースケール値では,1日目開始時90,1日目終了時50,3日目開始時20,3日目終了時10,5日目開始時0,5日目終了時0であったが,5日目終了時500mL程度排液を集めると,僅かに色を確認することができた.
1 0 0 0 こどもの皮膚診療アップデート
1 0 0 0 IR 機関リポジトリと研究者データベースの連携
- 著者
- 森 雅生 馬場 謙介
- 出版者
- 九州大学附属図書館
- 雑誌
- 九州大学附属図書館研究開発室年報 (ISSN:18813542)
- 巻号頁・発行日
- pp.11-13, 2012
- 被引用文献数
- 1
本稿は研究者データベースと機関リポジトリの連携を紹介する.研究者データベースに研究業績として登録された学術論文の書誌情報から,機関リポジトリに蓄積されるその論文の本文ファイルへのハイパーリンクの作成を考える.通常,こういったハイパーリンクは,バックグラウンドでの書誌情報の照合により実現される.本稿では,バックグラウンドでの書誌情報の照合を行わない方法を提案している.
1 0 0 0 昆虫機械感覚細胞の刺激受容初期過程の力学的研究
機械受容は、動物と外界との相互作用の「基本要素」であり、機械刺激の受容機構を抜きにして動物の進化・適応は語れない。従来、機械受容は「膜の張力によるイオンチャネルの開閉」といった「マクロで単純すぎる」図式でとらえられて来た。また、機械感覚の超高感度性の例として、ヒトやクサカゲロウの聴覚閾値での鼓膜の変位量が0.1オングストローム、つまり水素原子の直径の1/10に過ぎないことも、数多く示されてきた。しかし、変位で機械感度を議論するのは明らかに誤っている。感覚細胞は外界のエネルギーを情報エントロピーに変換する観測器であり、その性能はエネルギー感度で表現すべきである。エネルギーの授受無しの観測は「Maxwellの魔物」で代表される統計熱力学上の矛盾に行き着くから、いかなる感覚細胞も応答に際し刺激からエネルギーを受け取っている。コオロギの気流感覚細胞は、単一分子の常温における熱搖動ブラウン運動)エネルギーkBT(300°Kで4×10^<-21>[Joule])と同程度の刺激に反応してしまう。機械エネルギーが感覚細胞の反応に変換される仕組み、特にその初期過程は全く解明されていない。この未知の細胞機構を解明するため、ブラウン運動に近いレベルの微弱な機械刺激を気流感覚毛に与えたときの感覚細胞の膜電流応答の計測に、真正面から取り組んだ。長さ約1000μmのコオロギ気流感覚毛を根元から100μmで切断し、ピエゾ素子に取付けた電極を被せてナノメートル領域で動かし、気流感覚細胞の膜電流応答を計測した。長さ1000μmの気流感覚毛の先端は、ブラウン運動によって約14nm揺らいでいることは計測済みである。先端を切除した気流感覚毛を10-100nmの範囲で動かしたときの膜電流応答のエネルギーを計測し、刺激入力として与えた機械エネルギーと比べたところ、すでに10^6倍ほどのエネルギー増幅を受けていた。従って、機械受容器の初期過程は細胞膜にあるイオンチャンネルの開閉以前の分子機構にあることが明らかとなった。