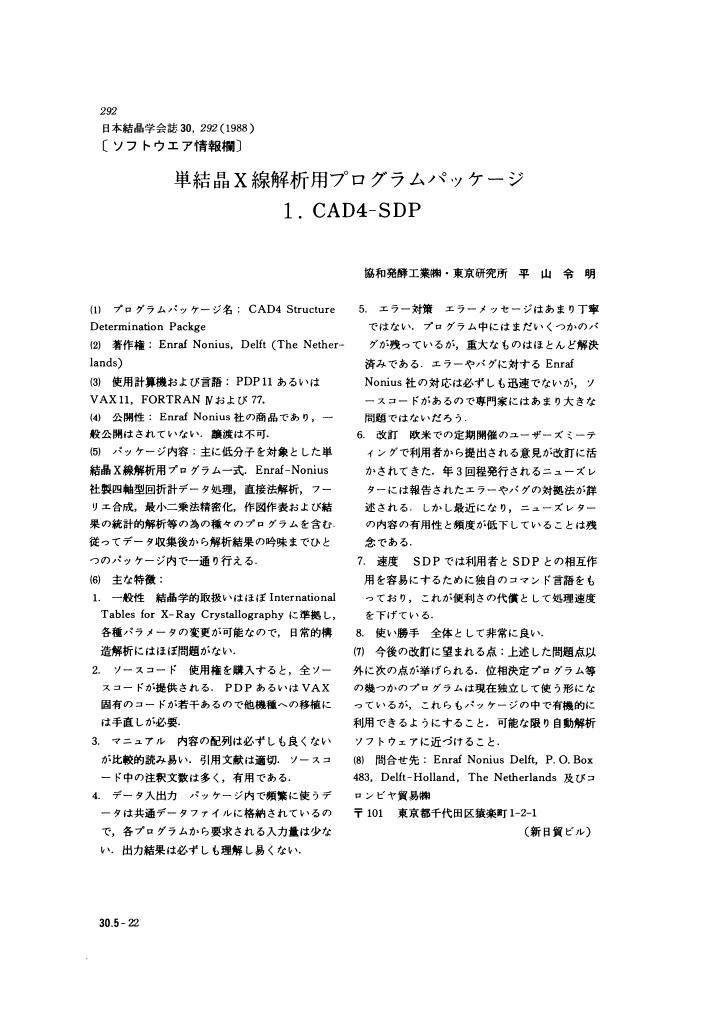- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.3_104, 2017-03-01 (Released:2017-07-07)
- 参考文献数
- 1
1 0 0 0 OA 屋号語彙に表れる地域の特性 旧唐桑町屋号電話帳にもとづく地理空間分析
- 著者
- 伊藤 香織 德永 景子 前橋 宏美 結城 和佳奈 髙栁 誠也
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.1570-1577, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)
- 参考文献数
- 9
本研究では,「唐桑町屋号電話帳」から作成した旧唐桑町全体の屋号語彙地理空間データに含まれる4600余語の屋号語の分布を地理的観点,社会的観点から定量的に分析し,屋号が人の認識を通して地域のどのような性質を表しているのかを探る.分析で得られた主な知見は,以下の通りである.(1)職業や家,分家,位置関係などを表す屋号語は出現頻度が高く,満遍なく分布しており,旧唐桑町全体に共通する共同体や位置関係の認識を表していると考えられる,(2)山,海,川,田,船,店,道など立地の地理的条件や人の活動を反映していると考えられる屋号語彙が多い,(3)特定の地区に集中する屋号語や特定の屋号語に偏った屋号語彙構成をもつ地区などが共同体の社会的条件を反映していると考えられる.
1 0 0 0 OA 都市景観要素としての人の存在 表情・アクティビティ・歩行者量が景観印象評価に与える影響
- 著者
- 前田 旭陽 伊藤 香織 高柳 誠也
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.1578-1583, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)
- 参考文献数
- 13
歩きやすい街を実現するためには、空間のデザインや配置、人々の活動が重要な要素と考えられている。さらに人間の表情も街並みの重要な要素となり得ると考える。本研究の目的は、人々のアクティビティと表情の関係を調査し、表情、アクティビティ、歩行者量が街並みの印象に与える影響を明らかにすることである。調査及び実験の結果、会話というアクティビティは、他の行動に比べて幸福な表情が増え、観察者に活気があり居心地良い印象を与えることがわかった。一人でのアクティビティは、悲しげな表情が増える傾向があり、観察者に活気のない印象を与える。また歩行者が多いと、観察者に活気のある印象を与えるが、居心地の良い印象にはならない。人が多いと活気はあるが居心地が悪い印象を与える一方、人が少なくても活気はないが居心地の良い印象を与える。そのため、1人でも複数人でも思い思いに活動できる公共空間の実現には、人が多く「活気」を感じる「賑わい」ある空間だけでなく、多様なアクティビティを許容する「居心地良い」空間が必要であると言える。
- 著者
- Masakazu Umezawa Hitoshi Tainaka Natsuko Kawashima Midori Shimizu Ken Takeda
- 出版者
- The Japanese Society of Toxicology
- 雑誌
- The Journal of Toxicological Sciences (ISSN:03881350)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.6, pp.1247-1252, 2012-12-01 (Released:2012-12-01)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 34 40
The production of man-made nanoparticles is increasing in nanotechnology, and health effect of nanomaterials is of concern. We previously reported that fetal exposure to titanium dioxide (TiO2) affects the brain of offspring during the perinatal period. The aim of this study was to extract candidate brain regions of interest using a specific group of Medical Subject Headings (MeSH) from a microarray dataset of the whole brain of mice prenatally exposed to TiO2 nanoparticle. After subcutaneous injection of TiO2 (total 0.4 mg) into pregnant mice on gestational days 6-15, brain tissues were collected from male fetuses on embryonic day 16 and from male pups on postnatal days 2, 7, 14 and 21. Gene expression changes were determined by microarray and analyzed with MeSH indicating brain regions. As a result, a total of twenty-one MeSH were significantly enriched from gene expression data. The results provide data to support the hypothesis that prenatal TiO2 exposure results in alteration to the cerebral cortex, olfactory bulb and some regions intimately related to dopamine systems of offspring mice. The genes associated with the striatum were differentially expressed during the perinatal period, and those associated with the regions related to dopamine neuron system and the prefrontal region were dysregulated in the later infantile period. The anatomical information gave us clues as to the mechanisms that underlie alteration of cerebral gene expression and phenotypes induced by fetal TiO2 exposure.
- 著者
- Tsubasa SASAKI Kenji SAWADA Seiichi SHIN Shu HOSOKAWA
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences (ISSN:09168508)
- 巻号頁・発行日
- vol.E100-A, no.10, pp.2086-2094, 2017-10-01
- 被引用文献数
- 14
This paper aims to propose a Fallback Control System isolated from cyber-attacks against networked control systems. The fallback control system implements maintaining functionality after an incident. Since cyber-attacks tamper with the communication contents of the networked control systems, the fallback control system is installed in a control target side. The fallback control system detects the incident without the communication contents on field network. This system detects an incident based on a bilinear observer and a switched Lyapunov function. When an incident is detected, normal operation is switched to fallback operation automatically. In this paper, a practical experiment with Ball-Sorter simulating a simple defective discriminator as a part of Factory Automation systems is shown. Assumed cyber-attacks against Ball-Sorter are Man In The Middle attack and Denial of Service attack.
1 0 0 0 OA CAD/CAMレジン冠の臨床と基礎研究:日本独自のメタルフリー治療の確立
- 著者
- 峯 篤史 萩野 僚介 伴 晋太朗 松本 真理子 壁谷 知茂 矢谷 博文
- 出版者
- 一般社団法人 日本歯科理工学会
- 雑誌
- 日本歯科理工学会誌 (ISSN:18844421)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.2, pp.135-141, 2022-05-25 (Released:2022-06-20)
- 参考文献数
- 13
2014年に保険導入されてから8年間で,CAD/CAMレジン冠は日本の臨床に着々と普及してきている.この新規補綴装置の質を向上させるために,わが国は「臨産官学民連携」で奮起してきた.臨床研究の成果として4年予後調査では,小臼歯CAD/CAMレジン冠の生存率は96.4%であり,脱離をトラブルと捉えた場合の成功率は77.4%であった.基礎的データの蓄積も進み,マトリックスレジンを被着対象としたレジンプライマーの有用性が明らかとなっている.このように,CAD/CAMレジン冠の臨床と基礎研究から,さらなるコンポジットレジン系材料としての可能性がみえてきている.今後,「日本独自のメタルフリー治療」が確立されるために,歯科理工学会にも強く期待せずにはいられない.本総説の内容は第78回日本歯科理工学会学術講演会(担当校:岡山大学)における学会主導型シンポジウム「さらなるコンポジットレジン系材料の可能性を探る!」で発表した.
1 0 0 0 OA CAD/CAMレジンブロックで製作した前歯部クラウンの臨床的評価
- 著者
- 吉田 圭一 平 曜輔 澤瀬 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本デジタル歯科学会
- 雑誌
- 日本デジタル歯科学会誌 (ISSN:24327654)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.112-119, 2018 (Released:2023-03-02)
- 参考文献数
- 19
CAD/CAMレジンブロックの前歯部クラウンへの応用を考え,臨床的な有効性を評価した.合計12本のレジン冠を製作し,平均18.7カ月後の臨床的評価を行った.評価項目はマージンの適合性,表面性状,隣接歯との接触状態,咬合接触状態,CAD/CAM冠の咬耗,変色・着色,プラークの付着,二次う蝕,歯肉の炎症,対合歯の摩耗の10項目とした.すべてのクラウンにクラックや破折,脱離は認められなかった.また,8.3%(1症例)でわずかな荒れや艶の消失が認められ,8.3%(1症例)でわずかな変色・着色が認められた.CAD/CAMレジンブロックが前歯部クラウンとして臨床的に応用できる可能性が示唆された.
1 0 0 0 OA 遺伝統計学的手法によるカンキツ在来品種の類縁関係推定とゲノム伝達様式の評価
- 著者
- 清水 徳朗
- 出版者
- 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2018-04-01
カンキツ在来品種2,000点以上の網羅的遺伝子型解析から、ナツミカン系統の同一性を確認するとともに、新規な親子関係を見出した。国内自生タチバナの調査から、自生地内でクローンとして個体が維持されていることを確認し、また新規8系統を含む11系統のタチバナを見出した。これらタチバナ系統の遺伝的類似性や地理的分布から、タチバナは主に宮崎県で発生し、タチバナ-Bがヤマトタチバナであることを見出した。系譜情報の育種実装を図るためにゲノムワイド多型の抽出法を確立し、従来の育種の制約を回避する新規な手法「カンキツ2.0」を提唱するとともに、GRAS-Diを利用したゲノムワイド多型推定法の開発を開始した。
上脈絡膜腔バックリング手術は強膜と脈絡膜の間に存在する上脈絡膜腔に充填物質を注入することにより網膜と脈絡膜のみを内陥させる新規的術式で裂孔原性網膜剥離に対する低侵襲治療として近年その有効性が報告されている。この手術は有望である一方で、一般化に向けた課題として1)術式に最適化された充填物質および2)術式に最適化された手術器具の研究の必要性が明らかになってきている。本研究では上脈絡膜腔バックリング動物実験モデルを用いて上脈絡膜腔バックリング手術に用いる充填物質と手術器具の最適化に向けた基礎研究を行う。
- 著者
- 有賀 ゆうアニース
- 出版者
- 日本スポーツ社会学会
- 雑誌
- スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.93-106, 2023 (Released:2023-10-26)
- 参考文献数
- 20
近年、ソーシャルメディアの普及を背景として、人種的マイノリティのアスリートによるレイシズムへの抗議が様々な競技で顕在化している。先行研究では、アスリートたちがアスリートとしての立場とアクティビストとしての立場の間でのジレンマに、またときには大規模なバックラッシュやファンとの葛藤に直面することが報告されてきた。本稿では、こうした状況のなかで例外的に反レイシズムに訴えつつ好意的な支持を広く集めたとされる、あるアフリカ系のプロ野球選手のBlack Lives Matter運動に関するTwitterの投稿を事例として取り上げる。人種的マイノリティとしての背景を持つプロアスリートがこうした困難な状況にいかに関与しているのかを分析する。テクスト上の表現を通じて人種や人種主義をめぐるアイデンティティや行為がいかに産出されるのかという視座からその投稿とそれに対するリプライを分析し、以下の知見を得た。彼は人種差別として理解されうる経験を物語りつつ、それが誰かへの非難として受け止められないように自らの物語を慎重にデザインすることで、レイシズムへの抗議とファン、ユーザーとの協調的関係の維持という困難な2つの課題を同時に追求していた。そしてその投稿に対するリプライも、一方では反差別の観点からアスリートへの共感や同調、他方ではスポーツの観点からアスリートへの賛美・応援にそれぞれ分岐することで、アスリートとオーディエンスたちの間で複合的な同調的関係が現出していた。以上の知見は、日本のスポーツ界において人種的マイノリティとしての背景をもつアスリートがいかなる課題に直面し、それを達成しようとしているのかを明らかにしている点で、スポーツ社会学研究へ貢献する。
1 0 0 0 OA 遺伝子発現とDNA超ラセン構造
- 著者
- 山崎 健一 黒木 和之 加納 康正 今本 文男
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.240-248, 1984-09-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 16
The intracellular DNA of bacteria, bacteriophage and plasmids is subject to topological constraints that function to maintain it in a superhelical conformation. For the last several years, accumulating evidence has indicated that supercoiling of DNA duplex is required for effective transcription, as well as for the replication and recombination of cellular DNA. The relevance of DNA superhehlicity to transcription in vivo has been suggested by the observations that the overall rate of transcription directed by the E. coli, bacteriophage and plasmid genomes is generally reduced when the activity of DNA gyrase is inhibited by the specific drugs, such as nalidixic acid or coumermycin. An interesting observation from our in vitro studies has been that stimulation of transcription by superhelicity of DNA is more pronounced with S 100 crude extract proteins than with pure RNA polymerase.DNA in the prokayrotic cell has a compact conformation due to its interaction with cellular proteins (Histone like proteins). Recentry, seven classes of those proteins (HLP I, HLP II, 28K protein etc.) have been isolated and characterized as essential components of the nucleoid. In this review, we focus on the effect of superhelical conformation of the DNA duplex and association of the DNA with the nucleoid proteins on transcription.
1 0 0 0 OA リハビリテーションの枠組みの中で行う嗅覚刺激療法の確立
- 著者
- 金井 健吾 岡 愛子 赤松 摩紀 渡部 佳弘 上斗米 愛実 北村 寛志 今西 順久 野口 佳裕 岡野 光博
- 出版者
- 日本鼻科学会
- 雑誌
- 日本鼻科学会会誌 (ISSN:09109153)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.300-309, 2023 (Released:2023-07-28)
- 参考文献数
- 26
嗅覚障害は,感冒罹患,鼻副鼻腔の慢性炎症,外傷,薬物や毒物の吸入,神経変性疾患や脳血管疾患などによって生じる。原疾患のコントロールを行うことで改善することもあるが,治療に難渋する症例も経験する。最近では新型コロナウイルス感染症に罹患し嗅覚障害を生じる症例も存在する。嗅覚機能検査として,T&Tオルファクトメーターを用いる基準嗅力検査や静脈性嗅覚検査などが一般的に施行される。嗅覚障害に対する新しい治療法として,患者が嗅素を積極的に嗅ぐことで,嗅覚の再生を促す嗅覚リハビリテーション(嗅覚刺激療法)が注目されており,欧州では安全で有効な治療法として診療に取り入れられている。嗅覚刺激療法は当院倫理審査で承認され,リハビリテーション科医師の指導の下で言語聴覚士が行っている。当院を受診し嗅覚障害と診断された患者を対象として,嗅覚刺激療法を3か月以上行い,治療前後の嗅覚を比較した。1日2回(朝・夕)4種類の嗅素(バラ・レモン・ユーカリ・シナモン)を一つの嗅素につき10秒ずつ嗅ぎ,3か月後には4種類の嗅素をラベンダー・オレンジ・ヒノキ・バニラへ変更している。治療前後の嗅覚の変化において,基準嗅力検査(平均認知域値と検知域値)では有意差は認めなかったが,日常のにおいアンケート,嗅覚に関するQOL質問紙,VASでは有意に改善を認めた。日本人にとって,より有効で統一的なプロトコールが確立されることが期待される。
1 0 0 0 OA 「アメリカ」 を語ること
- 著者
- 吉見 俊哉
- 出版者
- アメリカ学会
- 雑誌
- アメリカ研究 (ISSN:03872815)
- 巻号頁・発行日
- vol.2005, no.39, pp.85-103, 2005-03-25 (Released:2010-10-28)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 内視鏡検査・処置のトレーニングモデル:本邦の現状
- 著者
- 鈴木 翔 河上 洋 三池 忠
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.10, pp.2145-2158, 2023 (Released:2023-10-20)
- 参考文献数
- 9
消化器内視鏡は消化器診療において必要不可欠な医療機器で,検査・診断のみならず治療でも大きな役割を担っている.ルーチンのEGDや全大腸内視鏡検査(total colonoscopy:TCS)の他,胆膵内視鏡,EUS,ESDや止血処置・異物除去など内視鏡スキルは多岐に渡るが,内視鏡技術を向上させるには経験と時間が必要である.現在,様々なタイプのトレーニングモデルやシミュレーターが開発されており,初学者の練習や研修医・学生指導に用いられている.トレーニングモデルは簡便性や低コストが長所で,シミュレーターは豊富な種類の内視鏡検査・手技のトレーニングができる点で優れている.練習や指導の中でトレーニングモデルやシミュレーターを上手に活用して,個々のスキルアップ,実際の内視鏡診療の向上に繋がることが期待される.
1 0 0 0 OA 体細胞核移植クローン技術の人への使用と「生殖の自由」
- 著者
- 蔵田 伸雄
- 出版者
- 日本生命倫理学会
- 雑誌
- 生命倫理 (ISSN:13434063)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.1, pp.35-41, 2000-09-13 (Released:2017-04-27)
- 参考文献数
- 28
各国が体細胞核移植クローン技術の人への使用を法的に規制する方向に向かっているにもかかわらず、「生殖の自由」という権利に訴えてクローン技術の人への使用を肯定しようとする主張は少なくない。しかしそもそも「生殖の自由」という権利は、女性の中絶や避妊の権利を確保し、強制的な不妊手術等から女性を守るための権利である。そのような権利をクローン技術の使用を正当化することにまで用いることは濫用ではないだろうか。また男女両性の遺伝子が関与しないという点で、体細胞核移植クローン技術の使用は、体外受精、非配偶者間精子提供、代理母といった既存の人工生殖技術とは本質的に異なっている。生殖とは男女両性の遺伝子が関わることによってなされることであるとするなら、クローン技術を用いた児の産生は「生殖」ではない。したがって「生殖の自由」という権利によってクローン技術の使用を正当化することはできないだろう。
1 0 0 0 OA 市民共同再生可能エネルギー発電所成立要件としての地域連携
- 著者
- 中島 清隆
- 出版者
- 特定非営利活動法人 産学連携学会
- 雑誌
- 産学連携学 (ISSN:13496913)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.2_64-2_72, 2019-08-21 (Released:2020-03-06)
- 参考文献数
- 41
東日本大震災の被災地である岩手県における再生可能エネルギー事業の事例として,岩手県野田村の市民共同太陽光発電所の設立・運営を取りあげ,関係者へのインタビュー調査を踏まえ,地域主体間における地域連携に焦点を当てて検討した.対象事例は,固定価格買取制度,市民ファンドなど経済社会制度を活用し,対象地域内外のキー・パーソンである高齢被災者グループとNPO(非営利組織)による「民民連携」を中核に,「産学官民金連携」の相互支援的な関与で展開されていた.事例研究の結果を踏まえ,対象事例における再生可能エネルギー事業である市民共同発電所では,「民民連携」+「産学官民金連携」が多様かつ複合的な地域連携の一形態として成立していることを明らかにした.
1 0 0 0 OA 低周波ツボ表面療法 (第4報) 各種電極の効果比較
1 0 0 0 OA 単結晶X線解析用プログラムパッケージ1. CAD4-SDP
- 著者
- 平山 令明
- 出版者
- 日本結晶学会
- 雑誌
- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.5, pp.292, 1988-09-30 (Released:2010-09-30)
- 著者
- 信野 翔満 佐々木 葉
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.547-554, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)
- 参考文献数
- 19
駐車場のような低未利用地がランダムに出現する現象である「都市のスポンジ化」は、地方都市における深刻な課題である。この現象を構造的に理解することは、その対策のために必要である。本研究では、福山市を対象として、駐車場の立地状況の空間自己相関分析と、スペースシンタックス理論による街路構造分析とを行い、両者の関係を時間的に明らかにした。その結果、駐車場の集積と街路のアクセス性の傾向の時代的変化を明らかにした。また地区の詳細調査によって、コインパーキングがアクセス性の高い場所に立地している傾向を示した。以上より、ランダムと見做されている「都市のスポンジ化」現象の特性を都市空間構造との関係で読み取ることを可能にした。