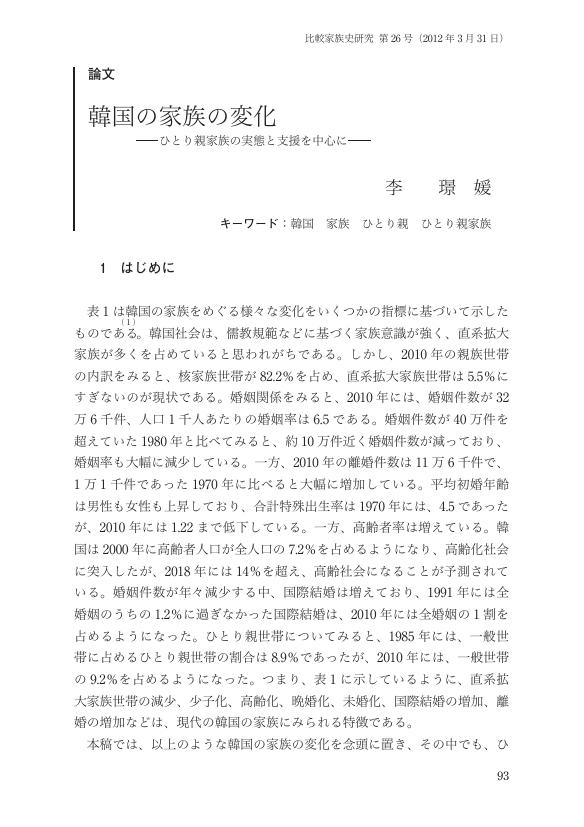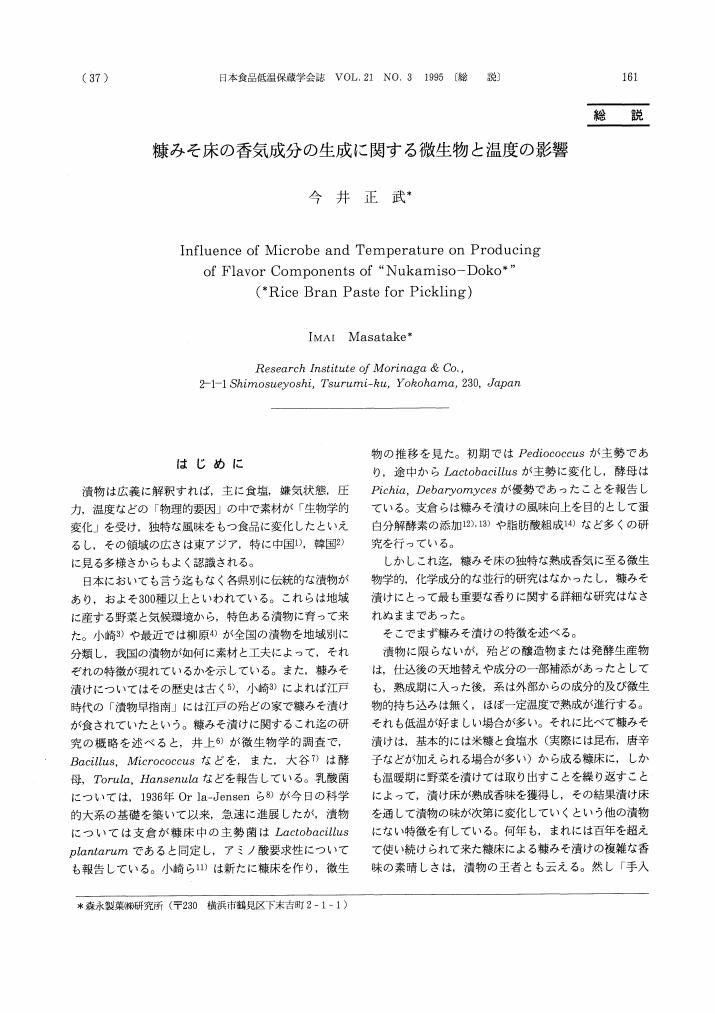- 著者
- James K CHAMBERS Soma ITO Kazuyuki UCHIDA
- 出版者
- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE
- 雑誌
- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-0322, (Released:2023-09-22)
Merkel cell carcinoma (MCC) is a rare skin tumor that shares a similar immunophenotype with Merkel cells, although its origin is debatable. More than 80% of human MCC cases are associated with Merkel cell polyomavirus infections and viral gene integration. Recent studies have shown that the clinical and pathological characteristics of feline MCC are comparable to those of human MCC, including its occurrence in aged individuals, aggressive behavior, histopathological findings, and the expression of Merkel cell markers. More than 90% of feline MCC are positive for the Felis catus papillomavirus type 2 (FcaPV2) gene. Molecular changes involved in papillomavirus-associated tumorigenesis, such as increased p16 and decreased retinoblastoma (Rb) and p53 protein levels, were observed in FcaPV2-positive MCC, but not in FcaPV2-negative MCC cases. These features were also confirmed in FcaPV2-positive and -negative MCC cell lines. The expression of papillomavirus E6 and E7 genes, responsible for p53 degradation and Rb inhibition, respectively, was detected in tumor cells by in situ hybridization. Whole genome sequencing revealed the integration of FcaPV2 DNA into the host feline genome. MCC cases often develop concurrent skin lesions, such as viral plaque and squamous cell carcinoma, which are also associated with papillomavirus infection. These findings suggest that FcaPV2 infection and integration of viral genes are involved in the development of MCC in cats. This review provides an overview of the comparative pathology of feline and human MCC caused by different viruses and discusses their cell of origin.
1 0 0 0 OA 坂口安紀 著 『ベネズエラ―溶解する民主主義、破綻する経済』 中央公論新社2021年
- 著者
- 村上 勇介
- 出版者
- ラテン・アメリカ政経学会
- 雑誌
- ラテン・アメリカ論集 (ISSN:0286004X)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.49-55, 2021 (Released:2021-12-31)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA 歴史記述と弁証法
- 著者
- 山田 信行
- 出版者
- The Japan Sociological Society
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.2, pp.158-171, 1995-09-30 (Released:2009-10-13)
- 参考文献数
- 35
本稿は, マルクス派の視点から歴史社会学の方法論を整備しようとする一つの試みである。本稿は三部から構成される。第一に, アメリカ合州国における歴史社会学の方法論論争を概観することによって, 求められている方法が演繹的な方法と「総体性」への志向であることを確認する。そのうえで, そのような要件をみたす方法が, 弁証法的なそれにほかならないことを提唱する。第二に, 史的唯物論の再構成の試みに見られる難点を確認したうえで, それを克服する試みとして, 多元的資本主義発展論としての弁証法的歴史社会学の構想を提示する。この際, 弁証法という論理が閉鎖的な「概念の自己展開」とは区別されるものであることが強調される。第三に, 弁証法的な論理の問題構制は「ポスト・マルクス主義」のそれと必ずしも抵触するものではなく, ギデンスも含めたポスト・マルクス主義的主張はかえって弁証法的方法の可能性を矮小化するものであることを指摘する。
1 0 0 0 OA <書評>堺屋太一『組織の盛衰』PHP 研究所, 1993 年
- 著者
- 遠田 雄志
- 出版者
- 法政大学経営学会
- 雑誌
- 経営志林 = The Hosei journal of business (ISSN:02870975)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.159-163, 1993-07-30
1 0 0 0 のねずみととってむちってむ
- 著者
- アカボシリョウエ作・絵
- 出版者
- 佼成出版社
- 巻号頁・発行日
- 1979
1 0 0 0 ねずみとくまとちからじまんたち
1 0 0 0 OA 社会物理学と感性 -エンゲージメントを要として組織の成長を助ける社会物理学-
- 著者
- 椎塚 久雄
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 感性工学 (ISSN:18828930)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.3, pp.103-115, 2019-09-30 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 22
1 0 0 0 OA 血糖持続モニタリングを用いて月経前に増悪する反応性低血糖が改善した1例
- 著者
- 齋藤 桃 岡田 洋右 鳥本 桂一 田中 良哉
- 出版者
- 学校法人 産業医科大学
- 雑誌
- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.301-306, 2022-09-01 (Released:2022-09-09)
- 参考文献数
- 14
症例は40歳女性.食後に生じる低血糖症状を主訴に当科紹介受診した.75g経口ブドウ糖負荷試験では,1時間後血糖245 mg/dl,2時間後血糖196 mg/dlであり耐糖能異常と診断した.しかし,6時間後血糖はインスリン遅延過剰分泌に伴い46 mg/dlと低血糖を呈しており,反応性低血糖と診断した.単純糖質を避けるなどの食事指導を行うとともに耐糖能異常・反応性低血糖に対してボグリボース0.6 mgの内服を開始した.低血糖症状の頻度は一旦減少していたが,徐々に低血糖頻度が再度増加した.詳細な問診により月経2-3日前に低血糖の頻度が多いことが判明したため,月経前後の血糖変動を確認するためFlash Glucose Monitoring(FGM)を装着した.FGMでは月経3日前より食後血糖の増悪とともに,反応性低血糖の出現を認め,一方月経4日後には食後高血糖は改善し,反応性低血糖も消失したことを確認した.月経前にはボグリボースの飲み忘れがないように服薬指導を行うとともに,月経数日前には昼食後の補食をするように指導を行い,低血糖出現頻度は減少した.これまで本例のように月経前に増悪する反応性低血糖症をFGMで評価し得た報告はない.反応性低血糖の診断や病勢評価,治療において,月経周期の血糖への影響についても考慮する必要がある.
1 0 0 0 花粉分析による南クック諸島・アチウ島の植生変化の復元と人類の影響
- 著者
- 藤木 利之 酒井 恵祐 奥野 充
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- pp.62.2202, (Released:2023-09-16)
- 参考文献数
- 43
クック諸島アチウ島Areora地区東部の湿地から得られた堆積物で花粉分析を行った結果,約1,600 cal BP (約350 cal CE) にココヤシと草本の花粉,シダ胞子,木炭片が急増し,タコノキ属花粉やヘゴ科胞子が急減するという劇的な植生変化が確認された.大規模な森林伐採などによるかく乱により,草原が拡大したと考えられた.アチウ島は約350 cal CEに人類が定住していたと考えられたが,この時代にアチウ島には人類定住の痕跡となる考古学データは全くない.また,約1100 cal CE以降にサツマイモなどの栽培植物花粉が微量ではあるが出現し,木炭片が急増した.よって,アチウ島への人類到達は2段階ある可能性が示された.年代は若干異なるが,この結果はTiroto湖の古環境データとほぼ一致している.堆積物を用いた古環境復元から人類定住年代を研究する場合は,島の様々な集水域の堆積物の分析を行って,多面的な分析結果から議論する必要があると考えられた.
1 0 0 0 OA 人物と相貌の認識の病理
- 著者
- 植野 仙経 上田 敬太 村井 俊哉
- 出版者
- 認知神経科学会
- 雑誌
- 認知神経科学 (ISSN:13444298)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3+4, pp.172-181, 2018 (Released:2019-02-01)
- 参考文献数
- 42
【要旨】1900年ごろ、Kraepelinはその『精神医学教科書』において人物に対する見当識の障害を含むさまざまな見当識障害を記述した。また見当識障害について、健忘やアパシー、認知機能の低下が関与するものと妄想性のものとを区別した。その後、精神医学において妄想性人物誤認の現象は既知性や親近感・疎遠感といった気分ないし感情の側面から考察されるようになった。また1930年前後にフランスの精神医学者が記述したカプグラ症候群とその類縁症状は、1980年前後に妄想性同定錯誤症候群としてまとめられ、神経心理学的なアプローチが盛んに行われるようになった。1990年、Ellisらは同定錯誤に関する鏡像仮説を提唱した。それによれば、相貌の認知には顕在的認知の経路(相貌の意識的な同定)と潜在的認知の経路(相貌に対する情動的応答)とがあり、前者が損なわれれば相貌失認、後者が損なわれればカプグラ症状が生じるという鏡像的な関係がこれらの症状にはある。この仮説は妄想性人物誤認において感情や情動に関わる異常が果たす役割を重視しているという点で、伝統的な精神医学と同様の観点に立っている。一方でKraepelinの見解が示唆するように、妄想的ではない人物誤認(人物に対する見当識障害)にはアパシーや健忘を背景として生じる場合が多い。
1 0 0 0 OA 言語行為としての社会学理論 性的主体化の権力を批判するということ
- 著者
- 大貫 挙学
- 出版者
- 日本社会学理論学会
- 雑誌
- 現代社会学理論研究 (ISSN:18817467)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.33-44, 2022-03-31 (Released:2023-06-15)
1 0 0 0 OA 未熟児脳室内出血と出血後水頭症の周術期管理
- 著者
- 宮嶋 雅一 木村 孝興 近藤 聡英 下地 一彰 新井 一
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.4, pp.276-282, 2013 (Released:2013-04-25)
- 参考文献数
- 34
未熟児の水頭症の主な病因は脳室内出血であり, 出血の程度と水頭症の発症には相関がある. 髄鞘化に乏しい未熟な脳は圧迫を受けると容易に変形するため, 未熟児では頭囲が拡大する前に著明な脳室拡大を生じる. 周術期管理は, 利尿剤やステロイド剤の投与などの内科的治療と腰椎穿刺の反復, 髄液リザーバー留置による間欠的髄液穿刺排液, 脳室帽状腱膜下シャント, PIカテーテルによる持続脳室ドレナージなどの外科的治療がある. その後進行性に脳室拡大を認める場合は, 患児の体重が2,000gを超えた時点で, VPシャントを行う. シャント術は機能不全や髄液過剰排出などの合併症が問題となるが, 特に未熟児脳室内出血後水頭症では, 治療に難渋する多嚢胞性水頭症や孤立性第4脳室をきたしやすい. 将来の精神運動発達障害の要因は, 水頭症よりも出血の重症度と分娩前後の問題によると考えられている. 未熟児水頭症では, その周術期管理が患児の予後を左右する重要な要因になる.
1 0 0 0 全国電源運用最適化シミュレーションモデルの開発
- 著者
- 本田 敦夫 手塚 孔一郎 岡村 智仁 河本 薫 清水 翔司 原田 耕平 田辺 隆人 白川 達也 高橋 智洋
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電気学会論文誌B(電力・エネルギー部門誌) (ISSN:03854213)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.11, pp.862-873, 2018-11-01 (Released:2018-11-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
Osaka Gas Co., Ltd., jointly with NTT DATA Mathematical Systems Inc., has developed unit-commitment model for optimizing dispatch of power generation units. Main purpose of this development is to simulate the future world of electric power system in accordance with national energy policy aiming to introduce large amount of renewable energy as well as vitalized cross-border power exchange via PX market to enhance economically-efficient power system operation. The model incorporates not only constraints of supply-demand balance but also constraints of operating reserves, regulation reserves, maximum CO2-emissions, etc.
1 0 0 0 生存と繁殖のトレードオフを考慮した生活史に関する数理生態学的研究
繁殖行動(繁殖の時期、産卵場所の選択、産卵する子の大きさなど)は、子孫を残すことに密接に関係をしている。そのため、繁殖行動は自薦選択によってどの様にデザインされてきたかを考えることは、行動の進化を研究する上で重要となる。産卵のためのコストと産卵された子どもの適応度の間にトレードオフの関係があるとき、産卵行動はそのトレードオフによってどの様の影響を受けるだろうか。寄生蜂(Dinarmus vasalis)を用いた実験から、寄生蜂の寄主選択は、産卵する雌が、交尾を受けているかどうかによって変わることが明らかになった(Nishimura,in MS)。生活史進化の数理生物学的解析によると、産卵のこめのコストと、産卵された子どもの適応度のバランスによって、寄主選択の仕方は左右される。寄生蜂は、未受精卵は雄となり受精卵は雌となる。卵の大きさに雌雄で違いはないので,寄主の条件が同じであれば、産卵のためのコストは、受精を受けた雌、未受精の雌の間で違いはない。産卵のためのコストと産卵された子どもの適応度の間にトレードオフがあるような2つのタイプの寄主(一方は、産卵しやすいが産みつけられた子どもの適応度が低くなる、他方はその逆)の利用の仕方は、産卵にかかるコストによって現在の生存率が減ることと、産卵のコストをかけることによって子どもの適応度が上がる事のバランスによって決まる。交尾を受けた雌では、よい発育条件のもとで、より適応度が上がる雌を産めるので、産卵に、よりコストをかけ、子どもの適応度が高くなるような寄主に産卵する、一方、未交尾雌では、よい発育条件のもとで雄の子が適応度を上げる利点よりも、産卵コストの少ない寄主に産卵して、生存率を高めた方が進化的に有利は方法となる。寄主選択は、生活史進化の解析から、交尾の有無、産卵にかけるコスト、産みつけられた子どもの適応度よって変化することが分かる。
- 著者
- Wataru Mimura Chieko Ishiguro Junko Terada-Hirashima Nobuaki Matsunaga Shuntaro Sato Yurika Kawazoe Megumi Maeda Fumiko Murata Haruhisa Fukuda
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20230106, (Released:2023-09-23)
- 参考文献数
- 33
Background: We evaluated the effectiveness of the BNT162b2 vaccine against infection, symptomatic infection, and hospitalization in older people during the Delta-predominant period (July 1 to September 30, 2021).Methods: We performed a population-based cohort study in an older adult population aged ≥65 years using data from the Vaccine Effectiveness, Networking, and Universal Safety Study conducted from January 1, 2019, to September 30, 2021, in Japan. We matched BNT162b2 vaccinated and unvaccinated individuals in a 1:1 ratio on the date of vaccination of the vaccinated individual. We evaluated the effectiveness of the vaccine against infection, symptomatic infection, and COVID-19-related hospitalization by comparing the vaccinated and unvaccinated groups. We estimated the risk ratio and risk difference using the Kaplan–Meier method with inverse probability weighting. The vaccine effectiveness was calculated as (1 − risk ratio) × 100%.Results: The study included 203,574 matched pairs aged ≥65 years. At 7 days after the second dose, the vaccine effectiveness (95% confidence interval) of BNT162b2 against infection, symptomatic infection, and hospitalization was 78.1% (65.2 to 87.8%), 79.1% (64.6 to 88.9%), and 93.5% (83.7 to 100%), respectively.Conclusions: BNT162b2 was highly effective against infection, symptomatic infection, and hospitalization in Japan's older adult population aged ≥65 years during the Delta-predominant period.
1 0 0 0 OA 韓国の家族の変化 —ひとり親家族の実態と支援を中心に—
- 著者
- 李 璟媛
- 出版者
- 比較家族史学会
- 雑誌
- 比較家族史研究 (ISSN:09135812)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.93-117, 2012-03-31 (Released:2013-03-31)
- 参考文献数
- 31
- 著者
- 乳原 彩香 松尾 雅博 石川 信一
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 日本認知・行動療法学会大会プログラム・抄録集 第44回大会 (ISSN:24333050)
- 巻号頁・発行日
- pp.146-147, 2018-10-26 (Released:2021-05-18)
1 0 0 0 OA 下北の村落共同体の音楽文化
- 著者
- 甲地 利恵
- 出版者
- The Society for Research in Asiatic Music (Toyo Ongaku Gakkai, TOG)
- 雑誌
- 東洋音楽研究 (ISSN:00393851)
- 巻号頁・発行日
- vol.1989, no.54, pp.1-45,L4, 1989-08-31 (Released:2010-02-25)
- 参考文献数
- 14
The purpose of this paper is to examine the social function of music transmitted in the village communities in the Shimokita region of Aomori Prefecture, in particular from the perspective of enculturation. The learning of a music within a community involves not only that music, but also the learning of various matters that are concomitant with it. This paper will therefore clarify the social structure of the communities in an attempt to understand the state of their music culture. It will then present an interpretation of how music has functioned within communal society, taking as an example the nomai of Ori in Higashidori-mura.A variety of types of folk music are transmitted in the Shimokita region. Almost all of them take the style of geino, that is performing arts, in which music, dance, and theatre come together. These include shishi-kagura (nomai and kagura), kabuki, matsuribayashi, nenbutsu (a type of wasan, colloquial Buddhist music), and several teodori. It is in the latter that the tendencies of the folk music of Shimokita are most clearly reflected. In the neighbouring regions of Tsugaru and Nanbu, folksongs developed as solo vocal pieces into what may be called a stage vocal art. In contrast, in Shimokita, folksongs are sung as an accompaniment to teodori, generally by a number of people together. Percussion instruments, taiko (drums) and kane (a type of small cymbal), are always used as well.The inclination of the music of Shimokita towards geino style is connected closely to the characteristic social structure of the communities of the region.Firstly, the primary industries of Shimokita were restricted by its cool climate and, up to the Second World War, did not produce adequately. For that reason, differences in economic well-being did not develop to the extent of dividing the society into classes. Within the community, the principle of not producing bunke (branch families) was observed, so that the division of property should not result in further poverty. Since the community is made up only of honke (head families), the status within the communities of each ie (family) is equal.One force that brings together these equal ie as a single community is that of the system of communal economy. (For instance, in a fishing community, the catch is sold through the community's fishing cooperative, and the profit is distributed equally between each ie, or used for communal purposes.)Another force is the existence of the ‘age group’. In Shimokita, a type of age grade system can be observed. The members of each ie participate in an appropriate group in accordance with their position in the ie. By doing this, they perform their roles as members of the community. Functions essential to communal life are traditionally distributed between the age groups. Those in festivals and ceremonies are especially well-defined.We may construe here that strong communal relationships of this type are reflected in the music culture of the communities, and further that the people living in them learn of ‘community’ (and, in turn, culture) by means of learning the music. Strong communal relationships between members of equal status were indispensable in the daily life of the Shimokita communities. The people play their part in this ‘community’ by participating in their appropriate age group, where they perform the music of festivals and ceremonies. This music, furthermore, takes the geino style. It is, in other words, music performed not alone but with others of the same age group. What is important in this case is not whether an individual is more skilled than his fellows, but rather whether he can participate in the realization of a geino by adjusting to them. The sense of collectivity or community that can be discerned in the style of the music
1 0 0 0 OA 素数を表わす多項式について
- 著者
- 和田 秀男
- 出版者
- 一般社団法人 日本数学会
- 雑誌
- 数学 (ISSN:0039470X)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.2, pp.160-161, 1975-04-30 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 4
1 0 0 0 OA 糠みそ床の香気成分の生成に関する微生物と温度の影響
- 著者
- 今井 正武
- 出版者
- japan association of food preservation scientists
- 雑誌
- 日本食品低温保蔵学会誌 (ISSN:09147675)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.3, pp.161-178, 1995-08-31 (Released:2011-08-17)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 2 1