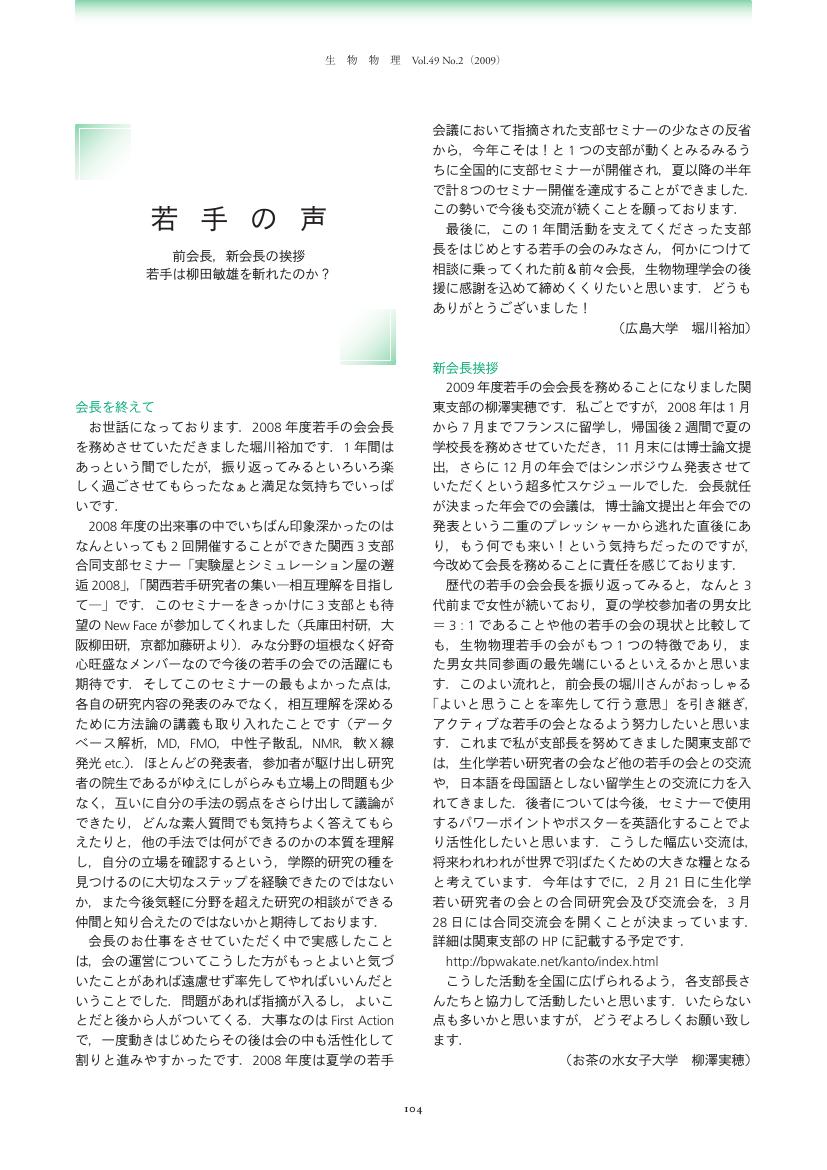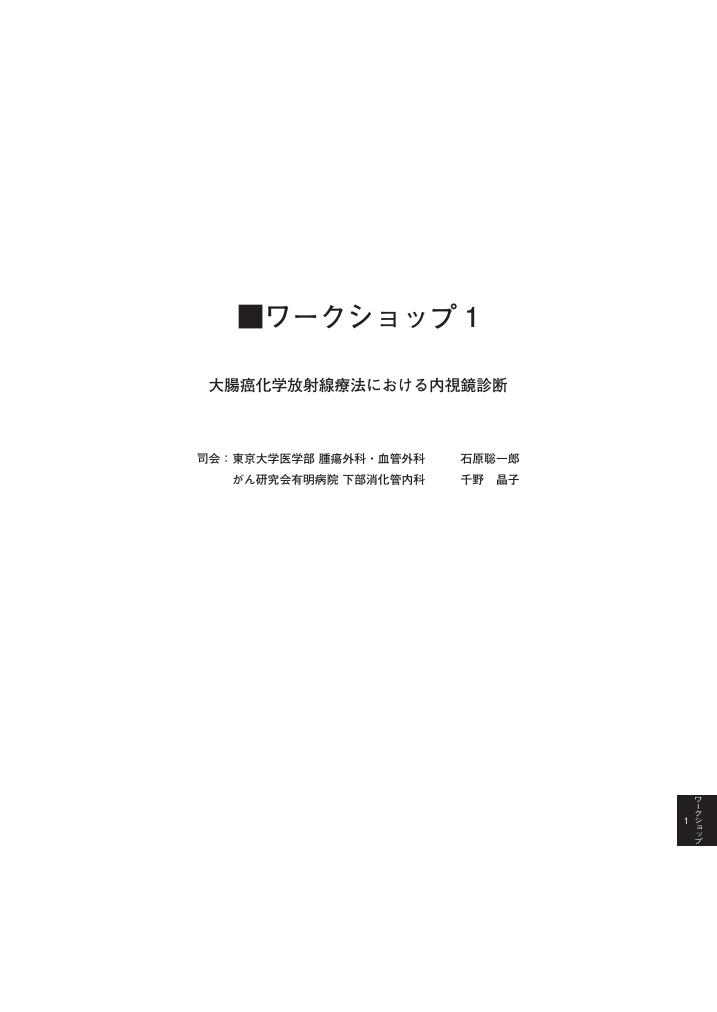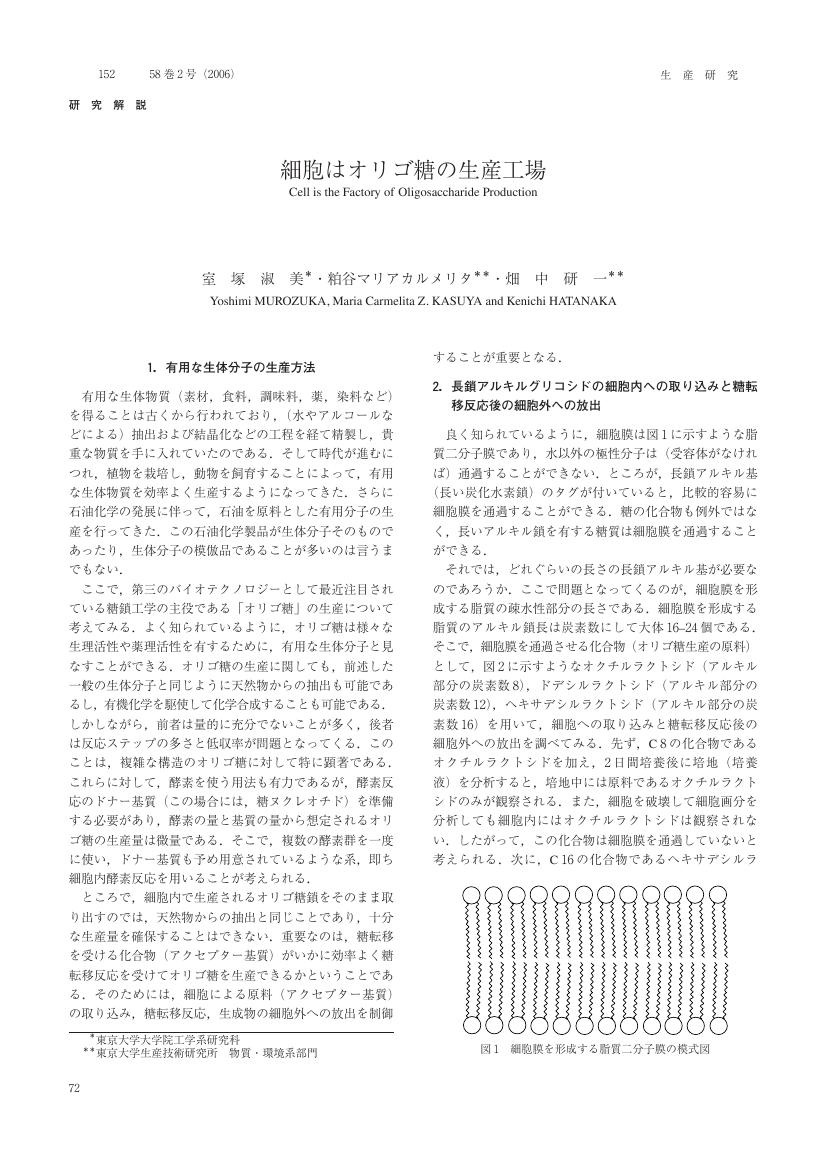1 0 0 0 日本地質学会学術大会講演要旨
- 著者
- 日本地質学会 [編]
- 出版者
- 日本地質学会
- 巻号頁・発行日
- 0000
1 0 0 0 OA 愛知県知多半島南部の中新世礫ヶ浦礫岩に含まれる変成岩・火成岩礫の起源
- 著者
- 足立 守 久保田 佳美
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 日本地質学会学術大会講演要旨 第114年学術大会(2007札幌) (ISSN:13483935)
- 巻号頁・発行日
- pp.455, 2007 (Released:2009-01-30)
1 0 0 0 OA 中新統師崎層群の球状炭酸塩コンクリーションと深海性動物群化石
- 著者
- 村宮 悠介 氏原 温 大路 樹生 吉田 英一
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.7, pp.355-363, 2020-07-15 (Released:2020-10-15)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 1
愛知県知多半島の南部には,前期中新世の深海底に堆積した師崎層群が広く分布している.師崎層群は,古くから地質構造および化石群集に関する調査・研究が行われてきた.とくに,師崎層群から産出する深海性の化石群集は,極めて保存状態が良いことで知られており,師崎層群は過去の深海性生物群集を垣間見ることができる重要な地層である.これらの化石群集については,現在も研究が進行中である.また近年には,師崎層群から大小の球状炭酸塩コンクリーションの産出と記載が報告され,深海堆積物中での急速な球状炭酸塩コンクリーションの形成に関する新たな知見が得られつつある.本巡検では,師崎層群から産出する球状炭酸塩コンクリーションおよび化石群集について,形成プロセスや産状などを紹介する.
1 0 0 0 OA 「蒲鮮万奴国号考」補正
- 著者
- 岩井 大慧
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.445-456, 1933-03
1 0 0 0 OA 蒲鮮万奴国号考
- 著者
- 岩井 大慧
- 出版者
- 東洋文庫
- 雑誌
- 東洋学報 = The Toyo Gakuho
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.439-528, 1932-04
1 0 0 0 OA 若手の声 前会長,新会長の挨拶/若手は柳田敏雄を斬れたのか?
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.104-105, 2009 (Released:2009-03-25)
1 0 0 0 OA オーラルヒストリー・インタビューから見たロシア語通訳者の学習に対する意識形成
- 著者
- ベリャコワ・エレーナ
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.51, pp.57-75, 2022 (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 29
This paper seeks to explore the perception of learning, including the factors which contributed to the spread of self-learning and collaborative learning in the Association of Russian Interpreters in Japan. The research is based on the oral history interviews of three pioneer Russian language interpreters who have taken part in the activity of the Association of Russian Interpreters since the 1980s. The paper briefly outlines the background of pioneer Russian language interpreters in Post-World War II Japan. Tokunaga Harumi, who was one of the founders of the Association of Russian Interpreters in Japan, highlighted the importance of sharing knowledge and continuous learning, and his beliefs significantly influenced Russian language interpreters’ attitudes towards learning. Next follows a description on how the three interviewed interpreters acquired necessary competence through interpreting and translation work, and it focuses attention on the fact that all of them emphasized the role of background knowledge. The paper highlights the importance of extralinguistic knowledge, including worldly knowledge and the country-specific knowledge suggesting the future possibilities of interpreter training within area studies. By analyzing the narratives, this study also demonstrates how the socio-political situation, i.e., the ups and downs in demand for interpreters at that time, was one of the factors which led to the collaboration of the interpreters. Characteristics of interpreter demand, such as the need to work in different spheres, have influenced not only the contents of interpreters’ learning but also the style of learning. This in turn fostered the spread of collaborative learning in the community of practice which enabled the interpreters in this study to exchange their experiences.
1 0 0 0 OA 修養の構造 翻訳の中で理解される日本特有の教育的伝統
- 著者
- 西平 直
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.4, pp.473-484, 2019 (Released:2020-06-12)
- 参考文献数
- 41
「修養」は翻訳語ではない。しかし江戸期から一貫して使われてきた言葉でもない。明治期の修養論だけ見ているとその「厚み」が見えない。本稿は江戸期と明治期を共時的に構造化する。加えて、欧米語の翻訳、とりわけcultivationに注目し、その周辺領域を検討する。論点は、1)政治との関連、2)道徳との関連、3)養生との差異、4)修行との差異、5)稽古との差異。「非」近代の営みを近代教育のカテゴリーに回収しないための手掛かりを翻訳の「ズレ」に見る。翻訳の中で理解される日本特有の教育的伝統を見る試みである。
1 0 0 0 OA ワークショップ
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.Supplement1, pp.667-729, 2022 (Released:2022-04-19)
1 0 0 0 OA 人権の脆弱性と宗教教育の役割 : とくにキリスト教教育の場合
- 著者
- 原 真和 Masakazu Hara
- 雑誌
- 聖和短期大学紀要 = Seiwa bulletin (ISSN:24239437)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.41-47, 2017-03-31
- 著者
- 橋田 慈子
- 出版者
- 日本社会教育学会
- 雑誌
- 社会教育学研究 (ISSN:21883521)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, pp.35-45, 2018 (Released:2020-12-04)
- 参考文献数
- 37
The purpose of this study is to clarify the problem-solving process for disabled children who were unable to go to school. This study focuses on the parental movements of children with learning difficulties. In Japan, children with learning difficulties had been excused from attending schools since 1900. After World War Ⅱ, this system has been continued by the School Education Act. In those days, there was a saying that nonattendance of disabled children was caused by parents’ negative attitudes toward special education. Therefore, it was argued that it was also necessary to change parents’ attitudes to promote special education for disabled children with learning difficulties. In the 1950s, parents’ association for with learning difficulties published the parental notes and tried to show the significance of special education. After these activities, many parents became supporters and driving force of special education. Based on an interview survey, it becomes clear that the participants of parents’ association had forced the nonattendance of disabled children by the local education authority. This involved sharing their problems with other parents after joining in it, and cooperating with teachers to reform educational systems for disabled children. As a result of this study, it is found that parents’ activities (recognizing the matters of disabled children and problem-solving with teachers) played important roles in acquiring the rights of education for disabled children.
1 0 0 0 OA 触れるケアをめぐる看護師の経験 ─身体論的観点からの分析─
- 著者
- 川原 由佳里 守田 美奈子 田中 孝美 奥田 清子 本江 朝美 田中 晶子 五味 己寿枝
- 出版者
- 日本看護技術学会
- 雑誌
- 日本看護技術学会誌 (ISSN:13495429)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.46-55, 2009-06-05 (Released:2016-08-25)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は, ①触れるケアをめぐる看護師の経験, ②臨床のなかでの触れるケアの位置づけ, そしてアロマセラピストの語りとの比較を通じて③看護における触れるケアの特徴を明らかにすることである. 看護師 13 名とアロマセラピスト 4 名に面接を行い, 参加者の語りを身体論的な観点から分析した. 結果, 看護師は生活援助やコミュニケーション等のさまざまな場面で, 直観的に相手のニーズを把握し, 即応的に触れるケアを行っていた. 触れている最中, 看護師は自らの手に感じられる相手の状態に集中し, 相手の心身の変化を感じとっていた. 看護師たちは触れるケアの効果を確信をもって語り, そうしたケアに看護職としての喜びを見出していたが, 治療中心, 効率性優先の臨床では, 触れるケアは特別な価値をもつものとは認識されず, その体験を誰かと共有することも少なかった. 看護師自身にも触れるケアの価値そのものが認めづらい現状が明らかになった.
- 著者
- 武永 美津子 平井 愛山 寺野 隆 田村 泰 北川 晴雄 吉田 尚
- 出版者
- 一般社団法人 日本動脈硬化学会
- 雑誌
- 動脈硬化 (ISSN:03862682)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.4, pp.825-829, 1985-10-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1
Arachidonic acid (AA) is well known to be metabolized to thromboxane (TX) A2, 12-hydroxyheptadecatrienoic acid (HHT) and 12-hydroxyeicosatetraenoic acid (12-HETE) in platelets. Prostaglandin endoperoxides and TXA2 are known to be potent aggregating agents. On the otherr hand, the labile 12-lipoxygenase metabolite, 12-hydroperoxyeicosatetraenoic acid (12-HPETE) has been reported to have a rather anti-aggregating action.It has been reported that eicosapentaenoic acid (EPA) has a potent inhibitory effect on platelet aggregation. TXA3 produced from EPA is nonaggregating agent. Although major metabolites of EPA in platelets is said to be those of 12-lipoxygenase pathway, the effect of them has not been clearly elucidated yet. So, we examined the effect of 12-lipoxygenase metabolites of EPA on platelet function and compared them with those of AA.Both of the labile 12-lipoxygenase metabolites, 12-HPETE and 12-hydroperoxyeicosapentaenoic acid (12-HPEPE) suppressed dose-dependently platelet aggregation and release of 5-hydroxytryptamine (5-HT) induced by collagen and AA, while 12-HETE and 12-hydroxyeicosapentaenoic acid (12-HEPE) had no such effects. The inhibitory effects of these 12-hydroperoxy compounds on platelet aggregation and release reaction seem to be almost equipotent. However, 5- and 15-hydroperoxy isomers were less potent in inhibiting aggregation.These results may indicate that 12-HPETE and 12-HPEPE have a potent anti-aggregatory activity and may play a role in regulating platelet aggregability.
1 0 0 0 OA インターバル・トレーニングの生理学的研究
- 著者
- 浅川 正一
- 出版者
- 順天堂医学会
- 雑誌
- 順天堂医学 (ISSN:00226769)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.45-54, 1961-02-10 (Released:2014-11-22)
- 参考文献数
- 10
Concerning to physical effect of interval training, 1) This training braing to develope respiration and bloodcirculation systems. 2) Oxygen debt is require more in first recovery term than in training term. 3) Pulse decreased 30 seconds to 1 minute in training over. It is most important things to determine the interval training rest. 4) Pace endurance work and Speed endurance work required O2 Uptake abilities and Long interval training required O2 debt abillities.
1 0 0 0 OA アメリカ合衆国における林地投資の新たな動向と育林経営
- 著者
- 大塚 生美 立花 敏 餅田 治之
- 出版者
- 林業経済学会
- 雑誌
- 林業経済研究 (ISSN:02851598)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.41-50, 2008-07-01 (Released:2017-08-28)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 2
1980年代半ば以降アメリカでは,年金基金や職員組合の退職金基金などの巨大投資ファンドを背景とした林地投資経営組織(TIMO)や,不動産投資信託(REIT)等によって林産会社の社有林が買収され,これまで見られなかった新たな大規模森林所有が形成されている。この林業を巡るアメリカの新たな動きは,アメリカ固有の特徴的な動きであるというばかりでなく,林業経営の世界史的な流れの中で捉えるべき育林経営の新たな段階の到来を示唆しているのではないかと我々は考えている。本稿では,それを明らかにするため,(1)アメリカにおける大規模育林経営の収益性,(2)林地評価額の上昇による林地売却の有利性,(3)不動産投資信託に対する税の優遇措置,の3つの課題を考察した。その結果,育林経営の内部収益率は概ね6%であることから,米国債や銀行利回りより高いリターンが期待できること,林産会社の所有林は,長い間産業備林として所有されていたため,今日の実勢価格はそれよりはるかに高く,林地評価額の上昇がもたらした林地売却に有利性があること,REITの経営によって得られた収益に対しては,二重課税を回避するため支払配当控除ができる税の優遇措置があることがわかった。
1 0 0 0 OA 環境不動産に投資するのは今である
- 著者
- 山本 良一
- 出版者
- 公益社団法人 日本不動産学会
- 雑誌
- 日本不動産学会誌 (ISSN:09113576)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.1, pp.8-12, 2015-06-25 (Released:2017-01-26)
1 0 0 0 OA 細胞はオリゴ糖の生産工場
- 著者
- 室塚 淑美 粕谷 マリアカルメリタ 畑中 研一
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.2, pp.152-155, 2006 (Released:2006-11-15)
1 0 0 0 OA 法律上の争いのある論点についての模擬裁判
- 著者
- 大久保 輝
- 雑誌
- 中央学院大学人間・自然論叢 = The Bulletin of Chuo-Gakuin University : man & nature (ISSN:13409506)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, pp.67-87, 2021-03-01
- 著者
- 福田 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.10, pp.371-376, 2012-10-05 (Released:2017-06-23)
- 参考文献数
- 22
軌道ベース運用(TBO:Trajectory Based Operation)は,航空機の4次元軌道(3次元位置と時間)を計画し,それに基づいて運航する将来の航空交通システムの運用概念である.航空機の最適な軌道を実現するため運航前から関係者間で軌道を調整し,飛行中は軌道を航空機と管制機関間で共有し,気象の変化などに対応して修正される.将来の航空交通システムに関する長期ビジョンCARATS(Collaborative Actions for Renovation of Air Traffic Systems)や国際民間航空機関のASBU (Aviation System Block Upgrades)構想には, TBOの施策が段階的に計画されている.本稿では,これらの施策に示されているTBOの実現のための主要な技術要素(時間管理,性能準拠型航法,データ通信,情報処理システムなど)について,現状,導入計画,国際基準の策定などを含めながら解説する.
1 0 0 0 OA 集合的行為としての拍手を支える時空間構造 -漫才鑑賞中の観客行動のマイクロ分析から-
- 著者
- 浅田 千晶 岡本 雅史
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会研究会資料 言語・音声理解と対話処理研究会 80回 (2017/7) (ISSN:09185682)
- 巻号頁・発行日
- pp.03, 2017-07-21 (Released:2021-06-28)