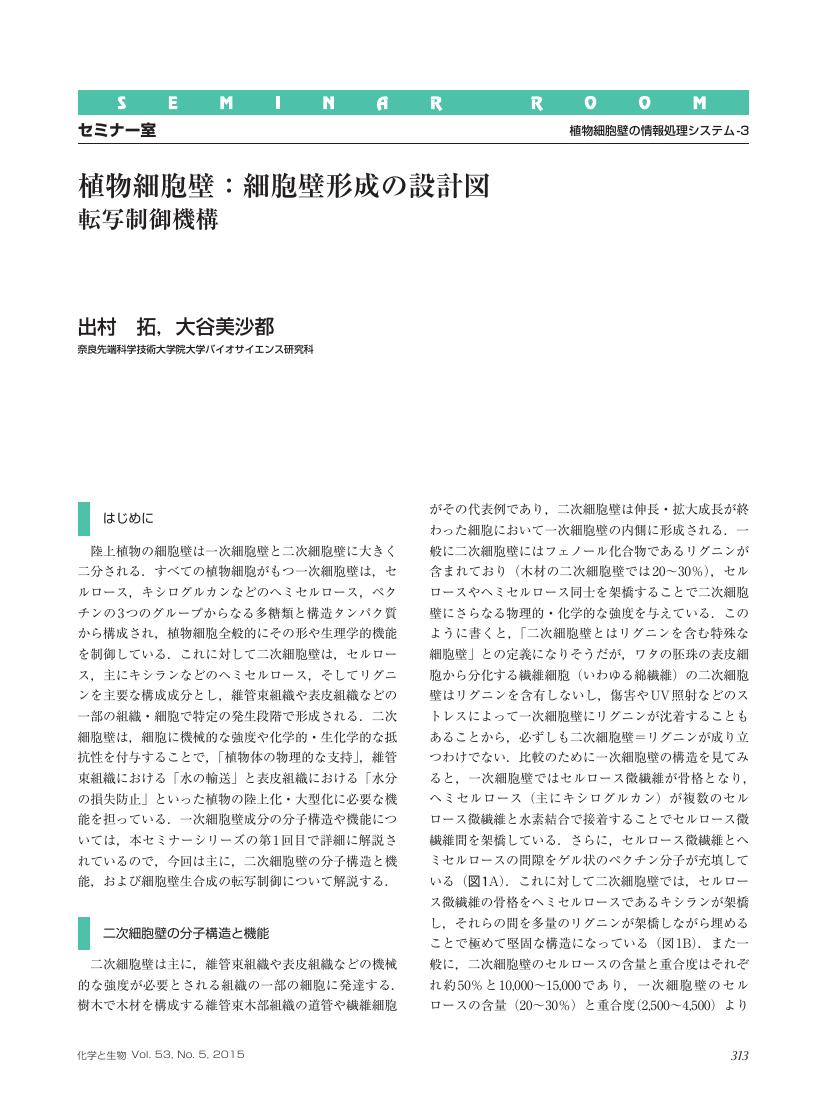1 0 0 0 OA 倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス
- 著者
- 岸本 直文
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.185, pp.369-403, 2014-02-28
1990年代の三角縁神獣鏡研究の飛躍により,箸墓古墳の年代が3世紀中頃に特定され,〈魏志倭人伝〉に見られる倭国と,倭王権とが直結し,連続的発展として理解できるようになった。卑弥呼が倭国王であった3世紀前半には,瀬戸内で結ばれる地域で前方後円形の墳墓の共有と画文帯神獣鏡の分配が始まっており,これが〈魏志倭人伝〉の倭国とみなしうるからである。3世紀初頭と推定される倭国王の共立による倭王権の樹立こそが,弥生時代の地域圏を越える倭国の出発点であり時代の転換点である。古墳時代を「倭における国家形成の時代」として定義し,3世紀前半を早期として古墳時代に編入する。今日の課題は,倭国の主導勢力となる弥生後期のヤマト国の実態,倭国乱を経てヤマト国が倭国の盟主となる理由の解明にある。一方で,弥生後期の畿内における鉄器の寡少さと大型墳墓の未発達から,倭王権は畿内ヤマト国の延長にはなく,東部瀬戸内勢力により樹立されたとの見方もあり,倭国の形成主体に関する見解の隔たりが大きい。こうした弥生時代から古墳時代への転換についても,¹⁴C年代データは新たな枠組みを提示しつつある。箸墓古墳が3世紀中頃であることは¹⁴C年代により追認されるが,それ以前の庄内式の年代が2世紀にさかのぼることが重要である。これにより,纒向遺跡の形成は倭国形成以前にさかのぼり,ヤマト国の自律的な本拠建設とみなしうる。本稿では,上記のように古墳時代を定義するとともに,そこに至る弥生時代後期のヤマト国の形成過程,纒向遺跡の新たな理解,楯築墓と纒向石塚古墳の比較を含む前方後円墳の成立問題など,新たな年代観をもとづき,現時点における倭国成立に至る一定の見取り図を描く。
1 0 0 0 OA 河内地域における弥生前期の炭素14年代測定研究
- 著者
- 小林 謙一 春成 秀爾 坂本 稔 秋山 浩三
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.139, pp.17-51, 2008-03-31
近畿地方における弥生文化開始期の年代を考える上で,河内地域の弥生前期・中期遺跡群の年代を明らかにする必要性は高い。国立歴史民俗博物館を中心とした年代測定グループでは,大阪府文化財センターおよび東大阪市立埋蔵文化財センターの協力を得て,河内湖(潟)東・南部の遺跡群に関する炭素14年代測定研究を重ねてきた。東大阪市鬼塚遺跡の縄文晩期初めと推定される浅鉢例は前13世紀~11世紀,宮ノ下遺跡の船橋式の可能性がある深鉢例は前800年頃,水走遺跡の2例と宮ノ下遺跡例の長原式土器は前800~550年頃までに較正年代があたる。奈良県唐古・鍵遺跡の長原式または直後例は,いわゆる「2400年問題」の中にあるので絞りにくいが,前550年より新しい。弥生前期については,大阪府八尾市木の本遺跡のⅠ期古~中段階の土器2例,東大阪市瓜生堂遺跡(北東部地域)のⅠ期中段階の土器はすべて「2400年問題」の後半,即ち前550~400年の間に含まれる可能性がある。唐古・鍵遺跡の大和Ⅰ期の土器も同様の年代幅に含まれる。東大阪市水走遺跡および若江北遺跡のⅠ期古~中段階とされる甕の例のみが,「2400年問題」の前半,すなわち前550年よりも古い可能性を示している。河内地域の縄文晩期~弥生前・中期の実年代を暫定的に整理すると,以下の通りとなる。 縄文晩期(滋賀里Ⅱ式~口酒井式・長原式の一部)前13世紀~前8または前7世紀 弥生前期(河内Ⅰ期)前8~前7世紀(前600年代後半か)~前4世紀(前380~前350年頃) 弥生中期(河内Ⅱ~Ⅳ期)前4世紀(前380~前350年頃)~紀元前後頃すなわち,瀬戸内中部から河内地域における弥生前期の始まりは,前750年よりは新しく前550年よりは古い年代の中に求められ,河内地域は前650~前600年頃に若江北遺跡の最古段階の居住関係遺構や水走遺跡の遠賀川系土器が出現すると考えられ,讃良郡条里遺跡の遠賀川系土器はそれよりもやや古いとすれば前7世紀中頃までの可能性が考えられよう。縄文晩期土器とされる長原式・水走式土器は前8世紀から前5世紀にかけて存続していた可能性があり,河内地域では少なくとも弥生前期中頃までは長原式・水走式土器が弥生前期土器に共伴していた可能性が高い。
1 0 0 0 OA 関東地方における弥生時代農耕集落の形成過程
- 著者
- 設楽 博己
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, pp.109-153, 2006-12-20
神奈川県小田原市中里遺跡は弥生中期中葉における,西日本的様相を強くもつ関東地方最初期の大型農耕集落である。近畿地方系の土器や,独立棟持柱をもつ大型掘立柱建物などが西日本的要素を代表する。一方,伝統的な要素も諸所に認められる。中里遺跡の住居跡はいくつかの群に分かれ,そのなかには環状をなすものがある。また再葬の蔵骨器である土偶形容器を有している。それ以前に台地縁辺に散在していた集落が消滅した後,平野に忽然と出現したのも,この遺跡の特徴である。中里集落出現以前,すなわち弥生前期から中期前葉の関東地方における初期農耕集落は,小規模ながらも縄文集落の伝統を引いた環状集落が認められる。これらは,縄文晩期に気候寒冷化などの影響から集落が小規模分散化していった延長線上にある。土偶形容器を伴う場合のある再葬墓は,この地域の初期農耕集落に特徴的な墓であった。中里集落に初期農耕集落に特有の文化要素が引き継がれていることからすると,中里集落は初期農耕集落のいくつかが,灌漑農耕という大規模な共同作業をおこなうために結集した集落である可能性がきわめて高い。環状をなす住居群は,その一つ一つが周辺に散在していた小集落だったのだろう。結集の原点である大型建物に再葬墓に通じる祖先祭祀の役割を推測する説があるが,その蓋然性も高い。水田稲作という技術的な関与はもちろんのこと,それを遂行するための集団編成のありかたや,それに伴う集落設計などに近畿系集団の関与がうかがえるが,在来小集団の共生が円滑に進んだ背景には,中里集落出現以前,あるいは縄文時代にさかのぼる血縁関係を基軸とした居住原理の継承が想定できる。関東地方の本格的な農耕集落の形成は,このように西日本からの技術の関与と同時に,在来の同族小集団-単位集団-が結集した結果達成された。同族小集団の集合によって規模の大きな農耕集落が編成されているが,それは大阪湾岸の弥生集落あるいは東北地方北部の初期農耕集落など,各地で捉えることができる現象である。
- 著者
- 石井 美和
- 出版者
- 一般社団法人 日本保育学会
- 雑誌
- 保育学研究 (ISSN:13409808)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.105-116, 2021 (Released:2021-11-25)
- 参考文献数
- 35
本研究の目的は,保育者が子育て支援という新しい実践を形成するプロセスを通じて,どのように保育者アイデンティティを再構築するのかを明らかにすることである。その際,新制度派組織論における制度ロジック概念を参照することにより,保育者が用いる論理に着目する。本研究では,子育て支援に早くから取り組んできた幼稚園教諭1名へのインタビューデータを分析した。その結果,市場ロジックと共同体ロジックの矛盾が子育て支援実践の形成の契機となっていることが明らかになった。また,保育者は自律性を拡大する形でアイデンティティを再構築していることが明らかになった。
- 著者
- 和田 有紀子 道下 尚文 森下 久 山本 温 松本 一弘 菱川 哲也
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- 電子情報通信学会論文誌 B (ISSN:13444697)
- 巻号頁・発行日
- vol.J105-B, no.11, pp.880-888, 2022-11-01
周囲環境からの影響の低減やデザイン性の向上といった観点から,アンテナや無線回路をスロット付金属きょう体の内部に含む無線通信装置が実用化されている.本論文では,スロット付金属きょう体の内部に折返しダイポールアンテナを備えたアンテナを提案し,金属きょう体上のスロットと折返しダイポールアンテナのインピーダンス特性と電磁界分布を調べ,動作原理を明らかにする.次に,その動作原理に基づき金属きょう体の薄型化とインピーダンス特性の広帯域化を検討する.その結果,金属きょう体幅を0.22λ0 (λ0:中心周波数の自由空間波長)から0.03λ0に減少させ,比帯域幅を7.6%から18.9%に拡大することができた.また,試作評価により,提案アンテナの広帯域動作を確認した.
1 0 0 0 OA リグニンの系統学的進化と多様性
- 著者
- 坂 志朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本エネルギー学会
- 雑誌
- 日本エネルギー学会機関誌えねるみくす (ISSN:24323586)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, no.3, pp.331-335, 2017-05-20 (Released:2018-03-30)
- 参考文献数
- 12
Global warming and depletion of fossil fuels are recently causing many problems. Under such a situation, a special attention has been paid to plant biomass for useful energy and chemicals. Therefore, in this study, phylogenic evolution and diversity of lignin in various biomass species in plant kingdom were first introduced so as to discuss topochemistry of lignin in plant cell walls such as chemical structure and distribution of lignin. In addition, chemical composition of various plant species on the earth were introduced to characterize taxonomically different biomass species. The lignocellulosics were then defined from a viewpoint of a role of lignin in plan kingdom.
1 0 0 0 OA 植物細胞壁:細胞壁形成の設計図 転写制御機構
- 著者
- 出村 拓 大谷 美沙都
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.5, pp.313-318, 2015-04-20 (Released:2016-04-20)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 植物細胞壁高次構造の構築と再編
- 著者
- 横山 隆亮 鳴川 秀樹 工藤 光子 西谷 和彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.107-114, 2015 (Released:2016-01-20)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 2 1
1 0 0 0 OA 二次細胞壁パターンの制御機構
- 著者
- 小田 祥久 福田 裕穂
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.12, pp.795-801, 2013-12-01 (Released:2014-12-01)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 1
セルロース微繊維を主成分とした細胞壁の沈着パターンは植物細胞の形態と機能を決める要因の一つである.木部細胞は強固な二次細胞壁を沈着することにより,植物体を力学的に支えると同時に通導組織として機能している.木部組織は木部繊維,原生木部道管,後生木部道管,仮道管などからなるが,それぞれの細胞が特有の二次細胞壁パターンを形成することにより,高度な機能分化を実現している.このような二次細胞壁の沈着パターンは,一次細胞壁と同様にセルロース合成酵素複合体の軌道を制御する表層微小管の配向に大きく依存している.われわれは転写因子を用いた in vitro 木部道管分化誘導系を確立することにより,木部細胞分化における特異的な遺伝子発現解析および機能解析,また,ライブイメージングによるタンパク質の動態,相互作用の解析を実現した.これらの解析手法を用いて,微小管付随タンパク質MIDD1と ROP GTPase が二次細胞壁のパターン形成において重要な役割を果たしていることを明らかにした.本稿ではこれらの研究成果を中心に,木部細胞における二次細胞壁パターンの制御機構に関する最近の知見を解説する.
1 0 0 0 OA 南部菱刺しの現状と課題― 地域の伝統文化の継承と活性化に向けて ―
- 著者
- 川守田 礼子
- 出版者
- 八戸工業大学
- 雑誌
- 八戸工業大学紀要 = The Bulletin of Hachinohe Institute of Technology (ISSN:24346659)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.11-22, 2020-03-03
1 0 0 0 OA 寒地水田における稲わらの分解促進と水管理によるメタン発生軽減効果
- 著者
- 後藤 英次 宮森 康雄 長谷川 進 稲津 脩
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.2, pp.191-201, 2004-04-05 (Released:2017-06-28)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 11
本試験は北海道立上川農業試験場の細粒褐色低地土水田を用いて,大幅なメタンの発生軽減を目標に稲わらの混和時期と窒素肥料および分解促進資材の添加,水管理(間断灌漑)の有待欧とそれらの組み合わせ効果を検討した.1)稲わらの分解は5℃の低温条件下でも進行し,この温度条件では窒素肥料および微生物由来の有機物分解促進資材の示加により一層分解が促進された.2)8cm程度の浅耕しによる稲わらの秋混和は春混和(秋散布後,地表面に放置)と比較して冬期間の分解が進み,これに窒素肥料および微生物由来の有機物分解促進資材を稲わら秋散布時に添加することでさらに促進された.また,稲わら秋混和は農家慣行に多く見られる稲わら春混和と比較して水田からのメタン発生量を軽減し,窒素肥料および分解促進資材を稲わら秋散布時に添加することでさらに軽減された.3)幼穂形成期前および出穂後の間断灌漑処理は,メタンの発生量を軽減し,中干し処理に近い効果であった.特に幼穂形成期前の間断灌漑処理では,作土の水分がpF 1.8以上になることで効果が高かった.4)稲わらの分解促進処理と水管理の組み合わせ「稲わらの秋混和+窒素肥料と分解促進資材の示加+強程度の間断灌漑」処理は,対照とした稲わらの「稲わら春混和+連続湛水」処理に比べてメタンの発生量を顕著に軽減することができた.
- 著者
- 池島 徳大 松山 康成
- 出版者
- 奈良教育大学大学院教育学研究科専門職課程教職開発専攻
- 雑誌
- 奈良教育大学教職大学院研究紀要「学校教育実践研究」 (ISSN:18836585)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.53-61, 2015-03-31
本研究は、PBIS(Positive Behavioral Interventions and Supports)における第2層支援のCICO(Check-in/Check-out)を参考に、学級に在籍する複数の教育的ニーズのある児童に対して、同じ手順で行える支援モデルをカウンセリングで用いられるスケーリング・クエスチョン技法と応用行動分析で用いられるトークン・エコノミー技法を統合して試作し、学級に在籍する特別支援学級児童1名、特別な教育的ニーズのある児童2名に実施し、その効果を検討した。その結果、対象児童の学校適応感と行動変容、仲間からの受容度の向上が見られた。本研究は近年必要性が論じられつつある多層支援の実現の一助となることが示唆された。
1 0 0 0 OA 会報
- 出版者
- 日本甲殻類学会
- 雑誌
- CANCER (ISSN:09181989)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, pp.73-80, 2022-08-01 (Released:2022-08-24)
本研究では,将来の豊かな社会発展に寄与するために,産業応用を目指した独創的・先駆的な研究に取り組む.具体的には,これまで管理された実験室環境において実施されてきた視知覚実験を実生活空間へと展開し,一般の照明環境下に設置された種々のディスプレイを用いた視覚実験を丁寧に実施する.これらの実験結果を解析することによって,新しい視物質であるipRGCの影響を考慮した色再現モデルを構築する.さらに,標準化されているデバイス間のカラーマネージメントシステムとの互換目指したプロトタイプシステムの構築を通じて,カラー画像再現における産業界の次世代デファクトスタンダードとなる基盤を確立する.
1 0 0 0 OA 照明の方向が顔および物体の印象に与える影響
- 著者
- 商 倩 落合 勇介 崔 庭瑞 日比野 治雄 小山 慎一
- 出版者
- 一般社団法人 日本デザイン学会
- 雑誌
- 日本デザイン学会研究発表大会概要集 日本デザイン学会 第57回研究発表大会
- 巻号頁・発行日
- pp.P37, 2010 (Released:2010-06-15)
照明方向が顔の印象に影響を与えることは先行研究によって指摘されているが,顔の好ましさに与える影響を定量的に評価した研究は行われていない.そこで本研究では,左または右からの照明が顔および物体の好ましさに与える影響について検討した.提示刺激は、顔に見える図形・物体に見える図形・顔写真の3種類であった.刺激として顔に見える図形と顔写真を提示する場合,単純に顔と認識させる事が重要であるため,表情による印象変化や顔の非対称性などの要因を排除した画像を用いた.明るさはグラデーションで表現した.左側が明るい画像,右側が明るい画像を画面の上下にランダムに提示し,被験者にはどちらか印象の良いほうを選ぶよう教示して印象を評価してもらった.さらに,刺激を倒立させて同様の実験を行った.結果としては3種類全ての場合において,左側を明るくした方が良い印象を与えるという傾向が認められた.特に顔に見える図形および顔写真ではその効果が大きかった.刺激を倒立させた場合は、物体に見える図形においてのみ,その効果は減少した.
1 0 0 0 OA 速読と眼球運動(読みと眼球運動,第22回大会 シンポジウム2)
- 著者
- 斎田 真也
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.64-69, 2004-09-30 (Released:2016-11-22)
- 被引用文献数
- 5
The eye movement patterns of the good readers, the skimmers who are normal readers but were instructed to read texts in the same speed as that of the good readers, and the normal readers, were investigated. The good readers and the skimmers had larger saccadic sizes and shorter fixation durations than the normal readers. This suggests that the good readers and the skimmers may have wider effective visual field in reading or may have just skipped the some words in scanning the text. To check the comprehension levels among those three subjects, the gist and detailed comprehension tests were done. The results of these tests indicate that the good readers had not lower scores than other subjects, which is different from almost all of the conclusions of past investigations. This means the good readers do not increase their reading speed by sacrificing the amount they understand from the text.
1 0 0 0 OA 子どもの自殺をめぐる人びとの実践の教育社会学的研究
- 著者
- 今井 聖
- 出版者
- RIKKYO UNIVERSITY(立教大学)
- 巻号頁・発行日
- 2022-03-31
1 0 0 0 OA 北海道のエゾシカ対策
- 著者
- 阿部 宣人
- 出版者
- 一般社団法人 日本治山治水協会
- 雑誌
- 水利科学 (ISSN:00394858)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.5, pp.27-42, 2014-12-01 (Released:2017-06-02)
- 参考文献数
- 2
1 0 0 0 OA 家父長制とコミュニケーション : ジェンダー変動過程における問題状況
- 著者
- 加藤 春恵子
- 雑誌
- 東京女子大学紀要論集
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.91-117, 1989-03-10
This essay is written from three points of view-women's study, the theory of communication, and the sociology of social change. It tries to investigate the meaning of discommunication in recent Japanese society, and to offer analytical tools to those who are in search of a deeper understanding of situation and self in the historical context. Table of contents is as follows: I. The Directions and Mechanisms in Social Change 1. The Inevitability of Social Change 2. The directions of Social Change 3. The Patterns of Social Change 4. Society and the Individual in the Process of Social Change 5. The Mechanisms of Social-Individual Change II. Gender Change as a Post-patriarchalization Process 1. Gender 2. Patriarchy 3. Changes in the Gender Role System 4. Changes in the Gender Personality System 5. Types of Processes in Post-patriarchalization III. The 'Patriarchy Complex' and Communication 1. The 'Patriarchy Complex' 2. Multiplying Relationships between Inter-personal and Extra-personal Discommunication 3. Nonverbal Communication and the Double-bind 4. Patriarchic Structure in Inter-personal Communication