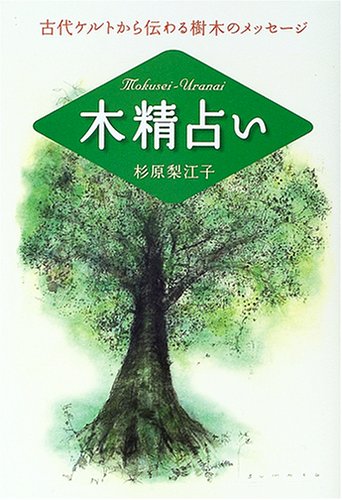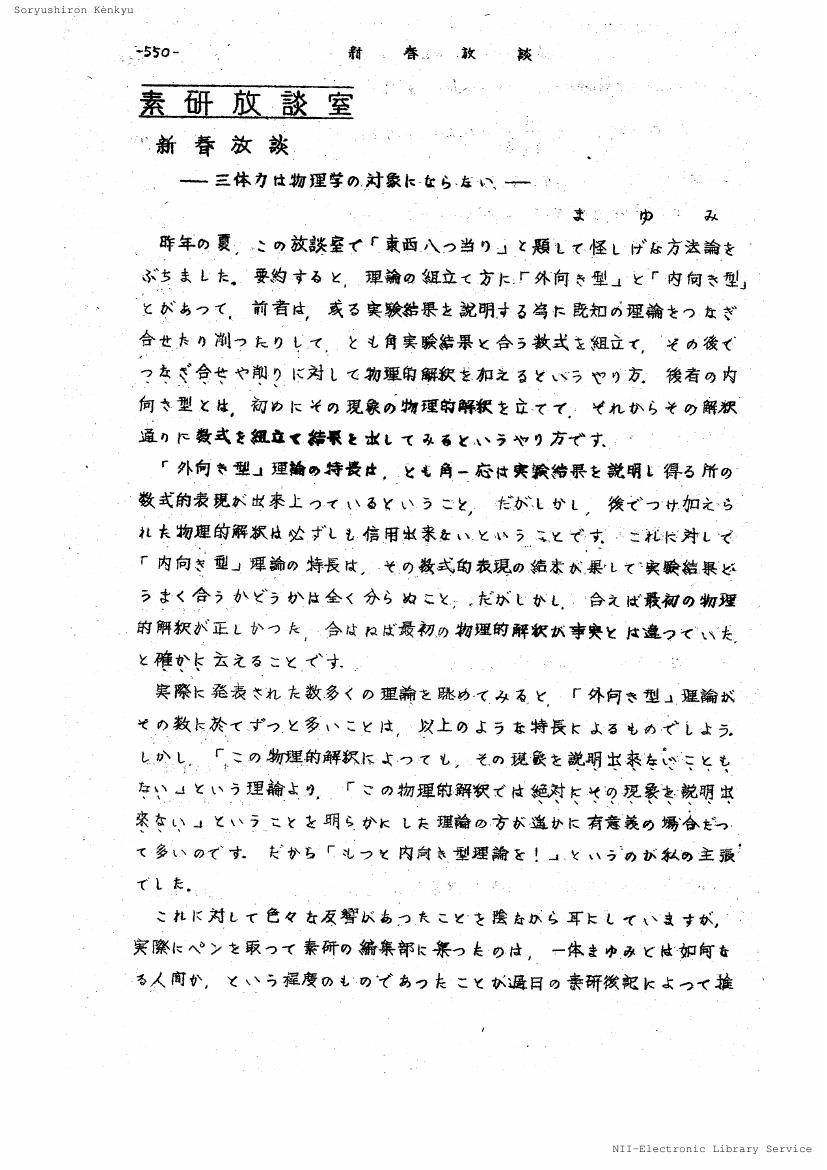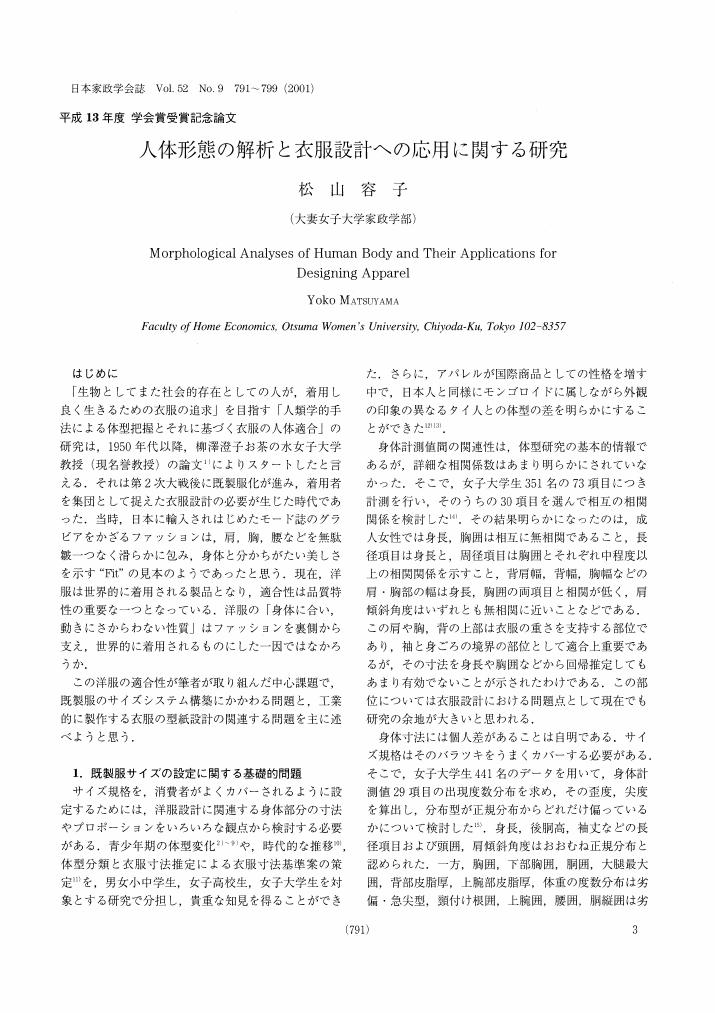1 0 0 0 脳動脈瘤の成因と動脈瘤壁不安定化機序の解明
1.脳動脈瘤モデルの確立と動脈瘤形成に至るホルモンの関与脳動脈瘤は1)比較的閉経期の女性に多く発症すること、2)高血圧がリスクファクターでありhemodynamic stressのかかる部位に発生し易いこと、3)estrogenがcollagenの維持に重要な役割を担っていることから、estrogen欠乏状態でcollagenの分解が亢進し血管が脆弱化している状況下で血圧が高ければhemodynamic stressを受け易い部位では脳動脈瘤が発生する可能性が高いと考え、ratを用いてestrogenの脳動脈瘤形成メカニズムへの関与について検討した。嚢状脳動脈瘤(stage III)は雌性高血圧ラット(卵巣摘出)で9/15(60%)に発生し、雄性高血圧ラット:3/15(20%)、雌性高血圧ラット(卵巣非摘出):3/15(20%)および無処置雌性ラット:0/15(0%)と比較して発生頻度が高く(p<0.05)、いずれも主に前大脳動脈-嗅動脈分岐部(7/9,78%)に認められた。また脳動脈瘤形成の初期変化と考えられる血管内皮の不規則な走行(satge I)および血管壁隆起(stage II)も卵巣摘出ラットで高頻度に観察された。この研究では卵巣雌性摘出ラットを用いて世界で初めて脳動脈瘤形成に至る血管内皮の初期の形態学的変化からestrogen欠乏が動脈瘤形成に関与することを示唆した(J Neurosurg,2005;103:1046-51)。さらにestrogen投与によるホルモン補充療法を行い、血管内皮の初期変化から嚢状動脈瘤形成に至るまでの形態学的変化を観察したところ、発生頻度は未治療群:13/15(86.7%)に対してホルモン補充療法群:5/15(33.3%)と有意に低下した(p<0.05)。以上の結果から動脈瘤形成に至る病因として血行動態や高血圧に加えてhormone特にestrogenが強く関与していることを実証した(J Neurosurg.2005;103:1052-7)。2.脳動脈瘤形成に至る血管内皮細胞傷害と炎症性変化血管内皮の形態変化と対応させて免疫組織学的変化を評価した結果、脳動脈瘤形成初期では血管内皮細胞のeNOS発現の減少がみられ、ついで病巣へのmacrophageの浸潤や中膜からの平滑筋遊走などの炎症性変化へと進行し、増加したmacrophageおよびMMP-9陽性細胞の強い発現により炎症性変化がさらに拡大し、血管壁の蛋白分解などによる血管壁の緋薄化が進行することで、ドーム状弛緩から脳動脈瘤形成に至ることを明らかにした(J Neurosurg.2007,in press)。今後脳動脈瘤の予防および治療法を確立するために動脈瘤の形成初期から増大に至る各stageでの分子メカニズムをさらに探求していく予定である。
1 0 0 0 OA 国際世論と国内世論の連関 -米国の湾岸危機・戦争に対する外交政策を事例として-
- 著者
- 西谷 真規子
- 出版者
- JAPAN ASSOCIATION OF INTERNATIONAL RELATIONS
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2001, no.128, pp.115-129,L13, 2001-10-22 (Released:2010-09-01)
- 参考文献数
- 61
In what situation does a chief of government regard international public opinion as important, and how does he use it?Like U. S. foreign policy during the Gulf Crisis/War, when a country forms an international coalition to threaten an enemy in a coercive way, the chief of government of that country has to rally international public opinion among coalition partners to unite the coalition. This serves to bolster the credibility of the coalition's will and capability to use coercive measures against the enemy.One way to lead international public opinion can be referred to as “symbolic appeal strategy”, which is basically the same concept as “reverberation tactics” in the logic of two-level games. This stratagem allows one to use political symbols to appeal directly to domestic public opinion in coalition countries in order to pressure coalition governments to maintain their coalition policy. During the Gulf Crisis/War, the United States-the leader of the anti-Iraqi coalition-used the United Nations Security Council, Syria's participation in the anti-Iraqi coalition and so on, as symbols to appeal to public opinion in coalition countries, particularly in the Arab world, Soviet Union, Germany, and Japan.Decision-makers' perception of international public opinion and public opinion in foreign countries is the basis for influencing international sentiment toward a given cause. Decision-makers tend to recognize the international situation based on their own stereotypes and conceptual lenses, and under high uncertainty they tend to be oversensitive to potential changes in the international community. During the Gulf Crisis/War, partly out of fear that Arab nationalists would unite and pressure Arab governments to split from the coalition, U. S. decision-makers were eager to directly engage the Arab public with political symbols and rhetoric to rally Arab opinion in support of U. S military intervention against Iraq.
1 0 0 0 OA 東日本大震災に伴う発電所被災がもたらす電力危機と波及的被害
- 著者
- 石倉 智樹 石川 良文
- 出版者
- 環太平洋産業連関分析学会
- 雑誌
- 産業連関 (ISSN:13419803)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.51-59, 2013-10-31 (Released:2014-08-07)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 2
東日本大震災は,地震や津波などの直接的被害に加えて,発電所被災がもたらす電力供給力不足という間接的な経済被害を引き起こした.本研究は,東日本大震災に起因する電力供給力不足,ならびに電力需要抑制策がもたらした経済ダメージについて,空間的応用一般均衡モデルを用いて分析した.分析では,首都圏経済とその他地域それぞれにおける不便益と,各産業部門における生産額変化に着目し,いかなる影響が及ぶのかを定量的に評価した.
1 0 0 0 OA 下水処理水が河川底生生物及び水環境に与える影響
- 著者
- 相澤 治郎 佐藤 義秋 伊藤 歩 北田 久美子 海田 輝之 大村 達夫
- 出版者
- Japanese Society of Water Treatment Biology
- 雑誌
- 日本水処理生物学会誌 (ISSN:09106758)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.247-259, 1999-12-15 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 6 3
Water environment of the River Mirumae receiving the effluent from a sewage treatment plant was investigated based on the data on water quality, attached algal biomass and benthic animals. Although residual chlorine remained in the effluent, the amount of attached algal flora was increased in winter. The inflow of the effluent decreased the diversity of benthic animals and it changed the structure of benthic animals in the River Mirumae. It was concluded that the secondary treatment can not conserve the sound water environment in river receiving the effluent from sewage treatment plants.
1 0 0 0 木精占い : 古代ケルトから伝わる樹木のメッセージ
1 0 0 0 OA 新春放談-三体力は物理学の対象にならない-(放談室)
- 著者
- まゆみ
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.5, pp.550-553, 1958 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 OA 東西八っあたり : もっと方法論を盛んにする為に(素研放談室)
- 著者
- まゆみ
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.5, pp.533-543, 1957 (Released:2017-10-02)
1 0 0 0 OA 運動時の乳酸生成によるCO2過剰排出と持久性パフォーマンスの関係
- 著者
- 平木場 浩二 丸山 敦夫 美坂 幸治
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.1, pp.69-77, 1990-02-01 (Released:2010-12-10)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 4 4
本研究の目的は, CO2過剰排出量 (CO2excess) と持久性能力の関連性を明らかにするために, 長距離走者と一般人の乳酸蓄積の結果生じるCO2excessを比較するとともに, CO2excessと持久性パフォーマンスとの関係について検討することであった.18才から22才の男子長距離走者6名 (LDR群) および21才から24才の健康な一般成人男子4名 (CON群) を対象とし, 自転車エルゴメーターでの負荷漸増法による最大下および最大運動テストと12分間全力走を実施して, それらの運動テストで得られたVO2max, VO2AT, CO2excessおよび12分間全力走パフォーマンスとの関係を検討した.本研究で得られた結果の要約は以下の通りである.1) CO2excess (ml) は, LDR群3, 442±677ml, CON群2, 677±437mlの値であったが, 両群間に有意な差はなかった.体重当りに換算したCO2excess/w (ml・kg-1) は, CON群 (40.3±3.54) と比較して, LDR群 (59.1±9.07) が有意に高い値を示した (p<0.01) .2) ΔLA (安静から運動直後1分目までの血中LAの増加分) に対するCO2excess/wの比率 (CO2excess/w/ΔLA) は, LDR群 (5.59±1.16ml・kg-1・mmol-1) がCON群 (4.46±0.69ml・kg-1・mmol-1) より高値を示す傾向にはあったが, 両群間に有意な差は認められなかった.3) CO2excess (ml) は, VO2maxとは有意に相関しなかったが, VO2ATとは有意に相関していた (r=0.763, p<0.05) .体重当りに換算したCO2excess/w (ml・kg-1) とVO2maxおよびVO2ATとの間にはそれぞれr=0.822 (p<0.01) , r=0.892 (p<0.001) の高い有意の相関係数が認められ, 体重当りのCO2excess (ml・kg-1) と持久性能力との間に関連性のあることが確認された.さらに, ΔHCO3- (安静から運動直後1分目までの血中HCO3-の減少分) とも有意の相関関係が認められた (r=0.649, p<0.05) .4) 持久性パフォーマンスの指標として採用した12分間全力走の走行距離とCO2excess (ml) およびCO2excess/w (ml・kg-1) との間にはそれぞれr=0.715 (p<0.05) , r=0.933 (p<0.001) の有意な相関関係が得られ, CO2excessの相対値 (ml・kg-1) の方が持久性パフォーマンスと密接に関連することが認められた.また, CO2excess/w/ΔLAの比率との間にも有意な相関のあることが示された (r=0.671, p<0.05) .5) 以上の結果から, 体重当りのCO2excess (ml・kg-1) およびCO2excess/w/ΔLAの比率には持久性能力と関連性があり, 乳酸蓄積を伴う比較的高強度の身体活動の維持が要求される持久性競技 (例えば, 3, 000~5, 000M走) のパフオーマンスを評価する上で重要な因子となることが示唆された.
- 著者
- 宮﨑 英一
- 出版者
- 香川大学大学教育基盤センター紀要編集委員会
- 雑誌
- 香川大学教育研究 = Journal of higher education and research, Kagawa University (ISSN:13490001)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.67-76, 2021-03
1 0 0 0 OA バベルの塔 : こども倫理学
1 0 0 0 OA 思想の自由と「公的な場」の「公正」 : 船橋市西図書館蔵書廃棄事件判決の評価
- 著者
- 前田 稔
- 出版者
- 日本図書館研究会
- 雑誌
- 図書館界 (ISSN:00409669)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.154-163, 2006-09-01 (Released:2017-05-24)
船橋市西図書館の蔵書廃棄事件最高裁判所判決が示した「公的な場」,「公正」について考察した。「公的な場」の概念とパブリック・フォーラム論との関係,「思想,意見等を公衆に伝達する」機能からみた図書館職員の職務の「公正」,購入と除去の違いについて検討した。その結果,表現の自由と思想の自由の両者を基礎に職務の独立性を支える新たな概念として「公的な場」概念が示されたと評価するに至った。
- 著者
- 大石 高典 山下 俊介 内堀 基光 Takanori OISHI YAMASHITA Shunsuke UCHIBORI Motomitsu
- 雑誌
- 放送大学研究年報 = Journal of the Open University of Japan (ISSN:09114505)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.63-75, 2013-03-21
2011年度放送大学学長裁量経費による研究助成を得て、放送大学に保管されている放送大学特別講義『HUMAN:人間・その起源を探る』の一部素材映像のアーカイブ化を行った。一連の作品は、撮り下ろし現地取材に基づく単発のシリーズとしては、放送大学のみならず、日本におけるこれまでで最大の教育用人類学映像教材作成プロジェクトであった。未編集のものを含む当該講義取材資料のうち約40%に当たる部分のアーカイブ化を行うとともに、当時現地取材や映像資料の作成に関わった放送大学関係者と自らの調査地に取材チームを案内した研究者らを中心に聞き取り調査を行った。「ヒューマン」シリーズ撮影から、既に15年以上が経過しているが、狩猟採集民、牧畜民、焼畑農耕民など、アフリカ各地の「自然に強く依存して生きる人びと」に焦点を当てた番組の取材対象地域では、取材後も撮影に関わった研究者自身やその次世代、次次世代におよぶ若手研究者が継続的に研究活動を行っている。これらの研究者との議論を踏まえれば、「ヒューマン」シリーズのラッシュ・フィルムの学術資料としての価値は、以下にまとめられる。(1)現代アフリカ社会、とくに生態人類学が主たる対象としてきた「自然に強く依存」した社会の貨幣経済化やグローバリゼーションへの対応を映像資料から考察するための格好の資料であること。(2)同時に、ラッシュ・フィルムは研究者だけでなく、被写体となった人びとやその属する地域社会にとっても大変意味あるものであり、方法になお検討が必要であるものの対象社会への還元には様々な可能性があること。(3)映像資料にメタデータを付加することにより、調査地を共有しない研究者を含む、より広範な利用者が活用できる教育研究のためのアーカイブ・データになりうること。本事例は、放送教材作成の取材過程で生まれた学術価値の高い映像一次資料は、適切な方法でアーカイブ化されることにより、さらなる教育研究上の価値を生み出しうることを示している。このような実践は、放送大学に蓄積された映像資料の活性を高めるだけでなく、例えば新たな放送教材作成への資料の再活用を通じて、教育研究と映像教材作成の間により再帰的な知的生産のループを生み出すことに貢献することが期待される。
1 0 0 0 OA 仙台西北部における北限ソヨゴ林の研究 2. 匍匐枝による更新について
- 著者
- 長島 康雄
- 出版者
- 仙台市科学館
- 雑誌
- 仙台市科学館研究報告 (ISSN:13450859)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.42-47, 2016 (Released:2021-09-07)
仙台北西部の宅地造成地に隣接する二次林でソヨゴ群落の調査を行った。落葉層を取り除き,ソヨゴの稚樹が匍匐枝由来であることを確認し,ソヨゴ群落の中央部,辺縁部に1m×1mの調査区を3ヶ設置し,匍匐枝をトレースすると共に自然高とシュートの着葉数を調べた。その結果,シュートを2型に分けることができること,その2型で更新に果たす役割が異なっている可能性があることを指摘した。
1 0 0 0 IR 憑きもの筋と婚姻規制 : 群馬県南西部の事例から
- 著者
- 飯島 康夫
- 出版者
- 新潟大学人文学部
- 雑誌
- 人文科学研究 = Studies in humanities (ISSN:04477332)
- 巻号頁・発行日
- vol.141, pp.Y21-44, 2017-11
1 0 0 0 IR FTMトランスの「カミングアウト」における,可視化と受容のポリティクス
- 著者
- 鈴木 綾
- 出版者
- 岩手大学大学院人文社会科学研究科
- 雑誌
- 岩手大学大学院人文社会科学研究科研究紀要
- 巻号頁・発行日
- no.27, pp.35-54, 2018-06
1 0 0 0 OA 放射線により誘発されるDNA変異の構造―イネ突然変異体の解析事例から―
- 著者
- 西村 実
- 出版者
- 日本育種学会
- 雑誌
- 育種学研究 (ISSN:13447629)
- 巻号頁・発行日
- pp.20J22, (Released:2022-03-19)
1 0 0 0 IR バス用タイヤの車外騒音に関する調査
- 著者
- 尾崎 秀生 佐野 翼 野吹 幸男 林 昇
- 出版者
- 全国自動車短期大学協会
- 雑誌
- 自動車整備技術に関する研究報告誌
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.37-40, 1983-08
大型車両のスパイクタイヤ騒音は,ノーマルタイヤにくらべてかなり大きいであろうと予測して,バス用のスパイクタイヤとノーマルタイヤについて,通常定行状態での騒音を計測し比較検討した。その結果,スパイク騒音がとりたてて著しく高いとはいえず,むしろスパイクによる路面損傷の方に問題があるのではないかという事がわかった。
1 0 0 0 OA 当院におけるリンクナース育成教育の試み
- 著者
- 小柳 浩子
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第60回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.470, 2011 (Released:2012-02-13)
<はじめに>リンクナースは、臨床現場(以下現場)において、感染対策の実践モデルとなるとともに現場の現状を把握し問題提起を行うなどの感染対策を推進するうえで重要な役割がある。その役割を担うためには、感染対策の基礎知識の習得が不可欠であり、リンクナースへの教育は院内感染対策上重要である。当院では、リンクナースの感染対策の知識の習得は、自己学習など本人の努力に任せている。そのため、感染対策の知識に個人差がみられた。そこで、「感染対策の実践モデルとなる」、「現場の現状を把握し問題提起できる」を目指し、リンクナース育成教育(以下勉強会)を開始した。その試みを報告する。 <方法>1.月1回開催する看護部感染対策委員会の時間を活用し、15分間の勉強会を実施 2.講義内容は、感染対策の基礎知識が習得できるよう10回に系統だて構成 3.毎回の資料に前月の復習問題をつけ、講義前に解答する 4.10回の勉強会終了後、小テスト、アンケートを実施 <結果>勉強会は、委員会の時間を活用したことで、ほぼ全員参加。アンケートでは、全員が「リンクナースとして勉強会は役にたった」、「今後も勉強会を続けた方が良い」と回答。また、半数が、「勉強会の内容を部署のスタッフへ時々伝達していた」と回答しているが、「他のスタッフへの伝達が難しい」という意見もあった。事前に資料を配布していたが、予習や復習問題の取り組み率が低いことも明らかになった。 <結論>1.系統だてた教育により、感染対策の基礎知識が得られた。2.基礎知識を習得することで、リンクナースとしての責任感や役割を認識するきっかけになった。3.得た知識を実践に活かせるように継続的な教育と活動のサポートが必要である。以上のことが再確認できた。今後も、知識の向上を目指し勉強会を継続していきたいと考えている。
1 0 0 0 OA 人体形態の解析と衣服設計への応用に関する研究
- 著者
- 松山 容子
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.9, pp.791-799, 2001-09-15 (Released:2010-03-10)
- 参考文献数
- 51
- 被引用文献数
- 1