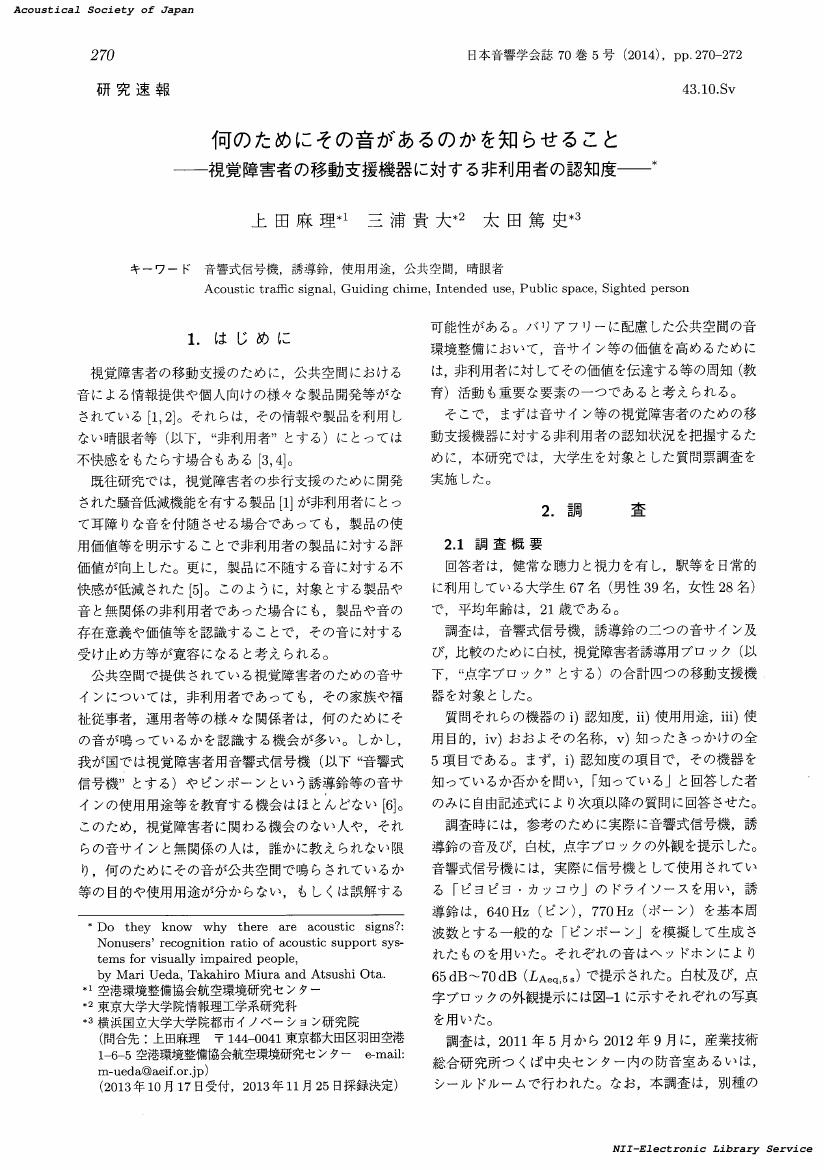1 0 0 0 OA 明治百年と漢方
- 著者
- 寺師 睦済
- 出版者
- 一般社団法人 日本東洋医学会
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.3, pp.159-161, 1969-01-30 (Released:2010-10-21)
1 0 0 0 OA 視覚障害者の道路横断行動と歩行支援情報システムの効果に関する研究
- 著者
- 柳原 崇男 三星 昭宏 北川 喜代治 藤田 和宏
- 出版者
- 一般社団法人 日本福祉のまちづくり学会
- 雑誌
- 福祉のまちづくり研究 (ISSN:13458973)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.23-32, 2007-01-31 (Released:2017-06-23)
- 被引用文献数
- 1
現在、わが国においては視覚障害者のための社会基盤整備として、視覚障害者用誘導ブロック、音響信号機、歩行者ITSなどの整備がされており、国際規格、国内規格化が進められている。それにより、視覚障害者の横断歩道に関する安全性確保は改善されつつある。しかし、歩行支援情報システムなどはその明確な評価方法がないこと、また、車両以外の歩行者・自転車などの他者交通との混合に関する問題も生じている。本研究では、視覚障害者の道路横断行動に関して2つの分析を行った。その一つは、特定の交差点を日常的に使用している視覚障害者を対象に道路横断分析を行うことにより、日常的な利用をしている視覚障害者の横断行動データを入手すること、また歩行支援情報システムの効果を主観評価ではなく客観的データにより分析を行なうことである。その結果、特定の交差点を日常的に利用している視覚障害者は横断歩道をはみ出るなどの危険行動はなく、非常にスムーズに横断していた。歩行支援情報システムを用いた横断においては、より直線的に歩行できるなどその効果を客観的データにより示すことが出来た。
1 0 0 0 OA 視覚障害者の行動に関する研究
- 著者
- 永松 義博
- 出版者
- 社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- 造園雑誌 (ISSN:03877248)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.5, pp.341-346, 1990-03-30 (Released:2011-07-19)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 5
社会福祉に対する関心が高まり, 街路空間, 歩行空間等の改善にもみられるように地域環境も整備されつつある。しかし視覚障害者にとっての配慮はまだ完全とはいえない。本研究では彼らの生活行動圏を拡大し, 単独歩行を可能とする都市環境形成の計画指針を得ることを目的とし, 盲人施設を対象に日常生活での利用施設, 視覚障害者対策設備の利用, 点字ブロック, 音響信号機に関する意識調査を実施した。日常生活では商業施設への利用が高く, 次いで文化教育施設である。公共施設では市役所, 福祉事務所等の訪問度が高い。視覚障害者が横断歩道を見つけるための手段として, 音響信号機点字ブロックといった設備が重要な役割を果たしている。
1 0 0 0 OA 盲人用音響信号機の信号音呈示方法の改良によるナビゲーション機能付加の可能性
- 著者
- 田内 雅規 澤井 元 高戸 仁郎 吉浦 敬
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.Supplement, pp.310-311, 1997-05-16 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 3
- 著者
- 上田 麻理 三浦 貴大 太田 篤史
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.270-272, 2014-05-01 (Released:2017-06-02)
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 尾張藩医宗浅井家の業績と国幹の「告墓文」について
- 著者
- 矢数 道明
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.263-273, 1994-01-20 (Released:2010-03-12)
1 0 0 0 IR つまずきの石としての1980年代 : 「半圧縮近代」日本の困難
- 著者
- 落合 恵美子
- 出版者
- 国際日本文化研究センター
- 雑誌
- 失われた20年と日本研究のこれから・失われた20年と日本社会の変容
- 巻号頁・発行日
- pp.171-182, 2017-03-31
失われた20年と日本研究のこれから(京都 : 2015年6月30日-7月2日)・失われた20年と日本社会の変容(ハーバード : 2015年11月13日)
- 著者
- 見市 建
- 出版者
- 日本貿易振興機構アジア経済研究所研究支援部
- 雑誌
- アジ研ワールド・トレンド (ISSN:13413406)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.11, pp.25-27, 2015-11
1 0 0 0 OA 新代数学 : 中等教科
1 0 0 0 OA いわゆるパンパ問題について
- 著者
- 朱澤 大二
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.5, pp.389-408, 1989-05-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 97
- 被引用文献数
- 2
Since Darwin's report on the Pampa grassland appeared, various opinions have been presented onthe problem (Grisebach 1872; Hann 1911; Köppen 1900, 1918 etc.). However, until the 1920's, the Pampa problem did not attract great attention in world academic circles. It was Schmieder's (1927) paper which marked the turning point in research on this problem. On the basis of various materials, he concluded that the Pampa is not a natural but a culturally induced grassland. His thesis became a focus of attention and, at the same time, of serious criticism. Kühn (1929), one of the reviewers, refuted the “evidence” referred to by Schmieder point by point, and concluded that the Pampa should be considered a natural grassland. Thereafter, hydroclimatic water balance, vegetation ecology, and regional ecology have been intensively studied, and the Schmieder's thesis has lost the backing of major researchers. Hydroclimatological research has contributed much to research on the Pampa problem. On the basis of intensive research on the relationship between the distribution of hydroclimatic water balance and the representative natural vegetation in the USA, Thornthwaite (1952) hypothesized the presence of a grassland climate. Similar results were obtained by his collaborators on the Pampa. He is of the opinion that the grassland is a natural phenomenon, in equilibrium with its climatic environment, and that it is possible to explain the presence of grassland on the basis of climate alone without bringing in other aspects such as human activities or fire; this is an openion in opposition to the thesis of Sauer (1950, 1956). Recent hydroclimatological research concluded that the Pampa should have a forest climate, i.e.mesophytic forest growth in the NE region, a transitional forest in the central region, and treeless steppe-like grassland in the W region, and extensive natural grassland which corresponds with an edaphic climax formation confined in the widespread azonal sites (Henning 1988). The concurrence between root systems of grasses and trees in the soil at given sites has also been intensively investigated, and as a result, it has become clear that the dominance in such a situation lies with the soil condition. In general, grasses dominate if soils are heavy, and trees dominate in light soils. In the Pampa, the boundary between grassland and woodland is approximately in accordance with that of heavy (in the east) and light (in the west) soils. Microscopic research on the soil, especially the humus, also gained remarkable results considering the former vegetation on the Pampa (Walter 1966, 1967; Wilhelmy and Rohmeder 1963; Troll 1968 etc.). Surrounding the Pampa are woodlands whose physiognomies are quite similar; however, their adaptabilities to climatic and hydroclimatic environments differ greatly, which complicated the Pampa problem (Walter 1967). It is certain that the results obtained by research on the Pampa problem contributed to the promotion of grassland studies elsewhere in the world and in turn on the Pampa. However, various problems regarding grassland have been raised with time. As is generally known, there are many research papers on the origin of savannas of the world, including Kadomura's (1984), Haruki's (1984) and Tamura's (1988) papers. The identification of climatic types on the basis of the effective method (for instance “savanna climate”) has been seriously criticized (Waibel 1948; Parsons 1955; Puson 1963; etc.). This and other methods must be re-examined.
1 0 0 0 OA 黒毛和種母牛の飼料変更による乳成分の変化と子牛の白痢
- 著者
- 岡田 啓司 深谷 敦子 志賀 瀧郎 平田 統一 竹内 啓 内藤 善久
- 出版者
- 公益社団法人 日本獣医師会
- 雑誌
- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.5, pp.311-315, 2003-05-20 (Released:2011-06-17)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1 1
黒毛和種母牛5頭を分娩後低でんぷん飼料で飼養し, その後にデントコーンサイレージ3kg/日を追加給与した結果, 全頭の子牛は給与開始後1~3日に軽度の糞便性状の変化 (前駆症状) を示し, 5~7日に水様性白痢を発症した. この時, 母乳の乳脂肪率は前駆症状発現当日および白痢発症当日の朝に増加した. 母乳のpHは白痢発症前日に大きく変動した. 乳脂肪中パルミチン酸とステアリン酸は前駆症状発現前日から増加した. 子牛の血中トリグリセライドと遊離脂肪酸濃度は前駆症状発現当日に低下したが, 白痢発症前日には元の値に復した. このように母牛の飼料の変更は母乳成分を変化させ, それにより子牛の消化管での脂肪の吸収低下が引き起こされて白痢の発症した可能性が示唆された.
- 著者
- 靏田 義成
- 巻号頁・発行日
- no.426, 1990
オピニオンダイナミクスの代表的な理論はHegselmann-Krause(2002)によるBounded Confidence Modelであるが,この数理モデルは人々が意見交換によって少しずつ歩み寄って合意の妥協点を見つける事が前提になっている。しかし,現実の社会の意見交換では歩み寄らない場合も少なくない.そこで石井は2018年に意見交換によって反発する場合とマスメディアなどの影響も含めた新しい理論を構築した。これをN人へ拡張してシミュレーションし、様々なWeb上のテキストデータを用いた測定からの裏付けをして、これを社会システム工学・ウェブ情報学に活かす。
1 0 0 0 OA 銀コロイド溶液の口腔内細菌に対する効果ならびにヒト歯肉および歯根膜線維芽細胞への影響
- 著者
- 織田 洋武 坪川 瑞樹 玉澤 賢 堀内 健次 鴨井 久博 中島 茂 佐藤 聡
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本歯科保存学会
- 雑誌
- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.6, pp.384-392, 2011-12-31 (Released:2018-03-20)
- 参考文献数
- 26
銀は一般家庭において除菌,抗菌,脱臭などの目的で高頻度に使用されている.銀コロイド溶液は,銀を電気分解して精製される無色透明の溶液であり,銀イオンよりも安定した状態で殺菌力をもつことで注目されている.また,銀コロイドは,特殊イオン交換体の相乗作用により殺菌,抗菌,脱臭の効果が増強することが報告され,食品の消毒や医療分野への転用が期待されている.本研究は銀コロイド溶液の口腔内病原細菌に対する殺菌効果,ならびにヒト歯肉および歯根膜より分離培養した線維芽細胞への影響についてin vitroにて検証した.殺菌試験は,Streptococcus mutans (ATCC25175), Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ATCC29522), Poyphyromonas gingivalis (W83, ATCC33277), Prevotella intermedia (ATCC25611), Fusobacterium nucleatum (ATCC25586)の6菌種を使用した.各細菌を洗浄後,滅菌蒸留水で希釈した銀コロイド溶液(1.5, 3, 30ppm)にて1分間処理した.その後希釈し,寒天培地に塗抹後A. actinomycetemcomitans, S. mutansは48時間, P. gingivalis, P. intermedia, F. nucleatumは72時間培養を行い,評価はColony Forming Units (CFU)で行った.細胞毒性試験は,ヒト歯肉線維芽細胞とヒト歯根膜線維芽細胞を用いた.細胞を培養後,滅菌蒸留水で希釈した銀コロイド溶液(1.5, 3, 30ppm)を30秒,1, 2, 4分間それぞれ作用させた.その後,8日間の細胞増殖の変化を測定した.また,歯肉線維芽細胞と歯根膜線維芽細胞に対し,銀コロイド溶液を1〜100ppmに調整した培養液にて培養し,検討を行った.その結果,30ppmの銀コロイド溶液はS. mutans (ATCC25175), A. actinomycetemcomitans (ATCC29522), P. gingivalis (W83, ATCC33277), P. intermedia (ATCC25611), F. nucleatum (ATCC25586)の6菌種に対して完全な殺菌効果を示し,1.5ppmと3ppmの濃度においても有意な細菌の殺菌力を示した.さらに銀コロイド溶液は30ppmの濃度において歯肉線維芽細胞と歯根膜線維芽細胞に抑制作用を示した.この作用は希釈により低下し,20ppmにおいては抑制作用を認めなかった.細胞生存率は,100ppm以下の濃度において歯肉および歯根膜線維芽細胞のLD50値は観察されなかった.以上の結果から,銀コロイド溶液は宿主細胞に影響しない濃度下で口腔内病原細菌に対して強い殺菌作用を示すことが認められた.
1 0 0 0 うつ病に対する行動活性化療法:―歴史的展望とメタ分析―
- 著者
- 横光 健吾 入江 智也 斎藤 了 松岡 紘史 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.2, pp.95-104, 2014
本研究の目的は、病的ギャンブリングに対する認知行動療法がどの程度有効であるかを検討するため、PGの診断を受けている参加者に対して実施され、かつ研究の質の高い治療効果研究を対象にメタアナリシスを実施することであった。論文検索にはPsycINFO、MEDLINE、PubMed、CiNii、医中誌を使用した(2012年2月時点)。また、各論文の引用文献による検索を行った。抽出された213件を対象に、適格基準と研究の質の検討を行った結果、4編の論文(7件の治療プログラム)がメタアナリシスの対象となった。その結果、認知行動療法は、治療終結期のギャンブル行動、ギャンブル費用、病的ギャンブリングの症状を減少させ、ギャンブル行動とギャンブル費用について、その効果が6ヵ月後においても維持されることが示された。今後の課題として、異質性と公表バイアスの結果から、今後の病的ギャンブリングに対する認知行動療法について、サンプルサイズの大きい研究の必要性が述べられた。
1 0 0 0 OA 欧米都市における文化生産と「日本らしさ」の構築
- 著者
- 藤田 結子
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.519-535, 2013-03-31 (Released:2014-03-31)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1
本稿は, 文化生産におけるナショナル・アイデンティティの構築について考察することを目的とする. 考察のため, 「欧米都市のアート・ワールドにおいて, どのような要因により『日本らしさ』の構築が促されているのか」という研究の問いを設定し, ファッション, インダストリアル・デザイン, 現代アートの各分野を対象に調査を行った. 調査方法にはマルチサイテッド・エスノグラフィーを用い, パリ, ロンドン, ニューヨーク, 東京などで参与観察とインタビューを実施した.調査の結果, 欧米都市のアート・ワールドでは異なる職業・役割をもつ人々を結びつける弱い紐帯が, さまざまな利益を生む活動に影響を及ぼしていた. しかし国境を越える人のフローが活発化し, アジア系のデザイナーやアーティストの活動が顕著になっている現在でも, バイヤーやコレクター, 記者・編集者など重要な判断や権力を行使する職業・役割においては, 白人が多数派を占めていた. この状況のもと, 白人性を「標準」とした価値観を基に, 日本出身のデザイナー, アーティストとその作品が本質的な「日本らしさ」と結びつけられていた.結論として, 制作者の「日本らしさ」への愛着によってナショナル・アイデンティティが再生産されているのではなく, アート・ワールドの職業・役割に見られる特徴的な人種関係と, その人種関係に基づく作者・作品への評価のあり方が「日本らしさ」の再構築を促していることが明らかになった.
1 0 0 0 OA 日高変成帯南部の深成変成岩類
- 著者
- 高橋 浩 志村 俊昭 加藤 聡美
- 出版者
- 一般社団法人 日本地質学会
- 雑誌
- 地質学雑誌 (ISSN:00167630)
- 巻号頁・発行日
- vol.124, no.6, pp.399-411, 2018-06-15 (Released:2018-08-18)
- 参考文献数
- 74
- 被引用文献数
- 1 5
日高変成帯は島弧ないし大陸地殻の衝上断片と考えられており,非変成堆積岩類からグラニュライト相に達する高変成度変成岩類まで観察できる世界的に見ても稀な地質体であり,島弧ないし大陸地殻の成因を解明するための絶好の対象となっている.1990年代~2000年代はじめまでに,日高変成帯の基本構造や発達史は確立されたかと思われた.しかし,2006年以降,変成岩類および深成岩類中のジルコンのU–Pb年代の報告によって,日高変成帯下部層(高変成度側)の主要変成作用の時期は19Ma頃であることが明らかとなり,従来の日高深成・変成作用の年代論(55Ma頃の主要深成・変成作用)の見直しが必要となった.また,日高変成帯上部層(低変成度側)は,中の川層群と漸移関係にあり,変成岩類の年代が40~30Ma頃を示すことから,変成帯下部層とは別のより古い時代の変成作用を被った地質体の可能性が浮かび上がってきた.つまり,日高変成帯はこれまで,古第三紀に形成された一連の高温型の変成帯と考えられてきたが,最近の研究成果に基づけば,新第三紀のグラニュライトを含む高変成度変成岩類と古第三紀に形成された角閃岩相から緑色片岩相で非変成中の川層群堆積岩類に移化する変成岩類とが接合した地質体である可能性がある.この巡検では,日高山脈南部地域において,日高変成帯上部層および下部層を構成する変成岩類および上部層に貫入する深成岩類を観察し,最新の研究成果を紹介する.