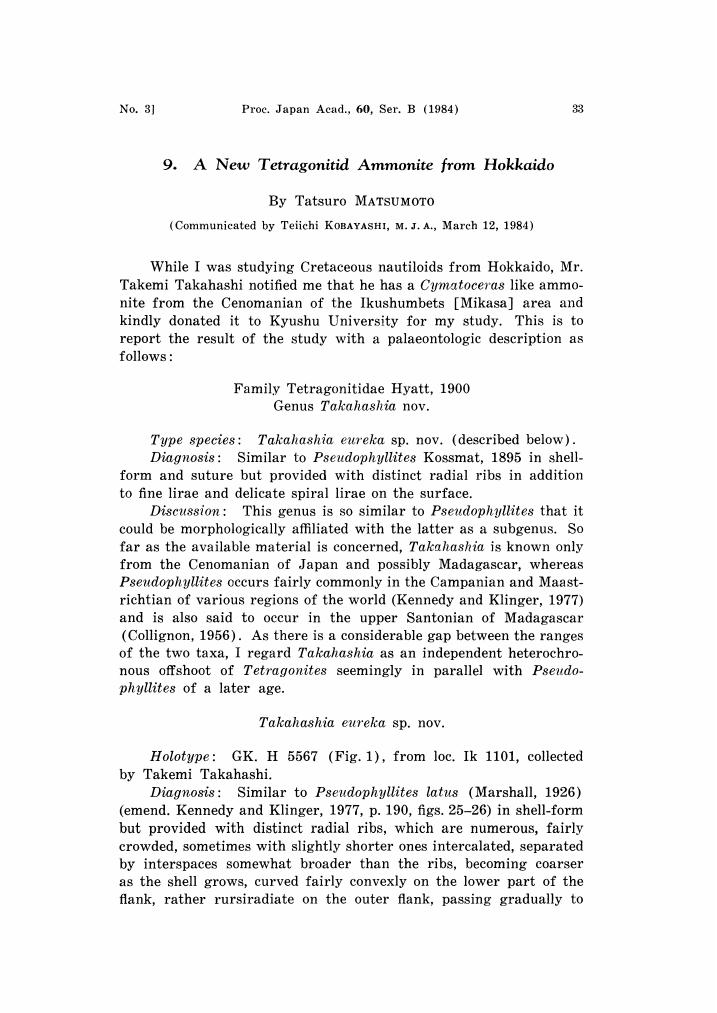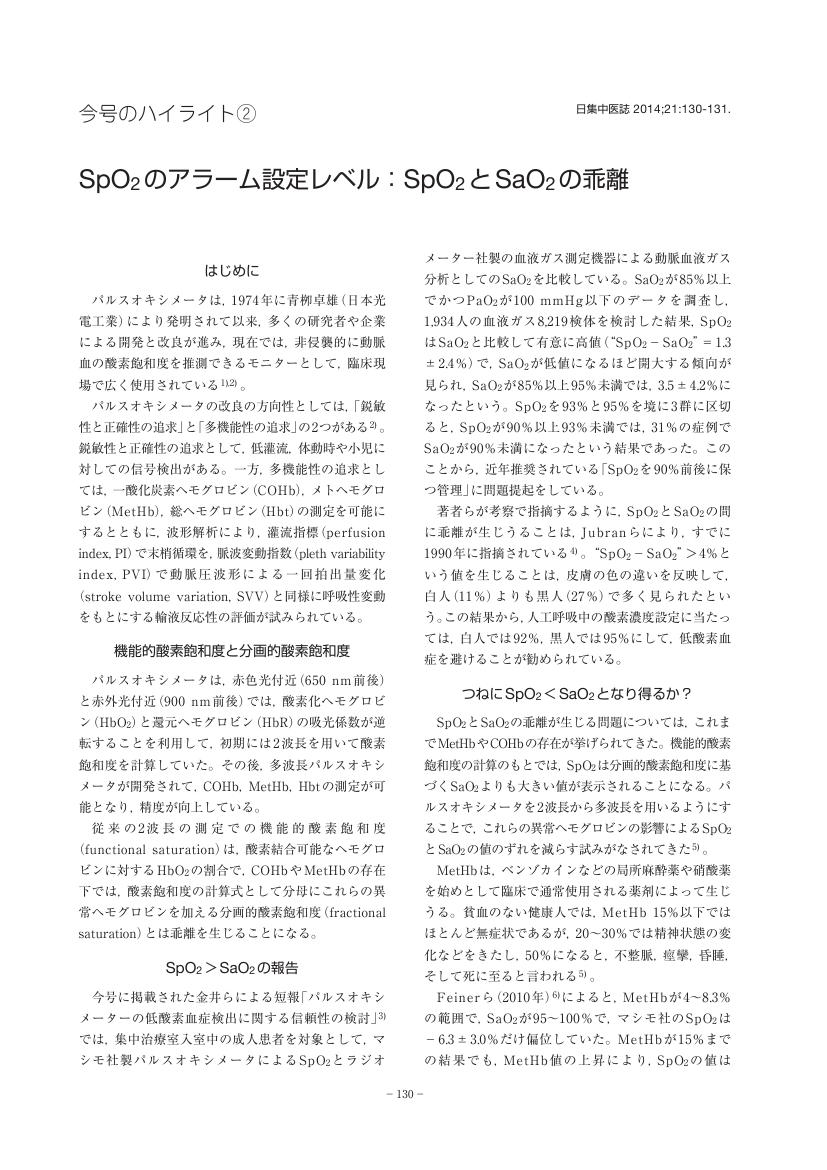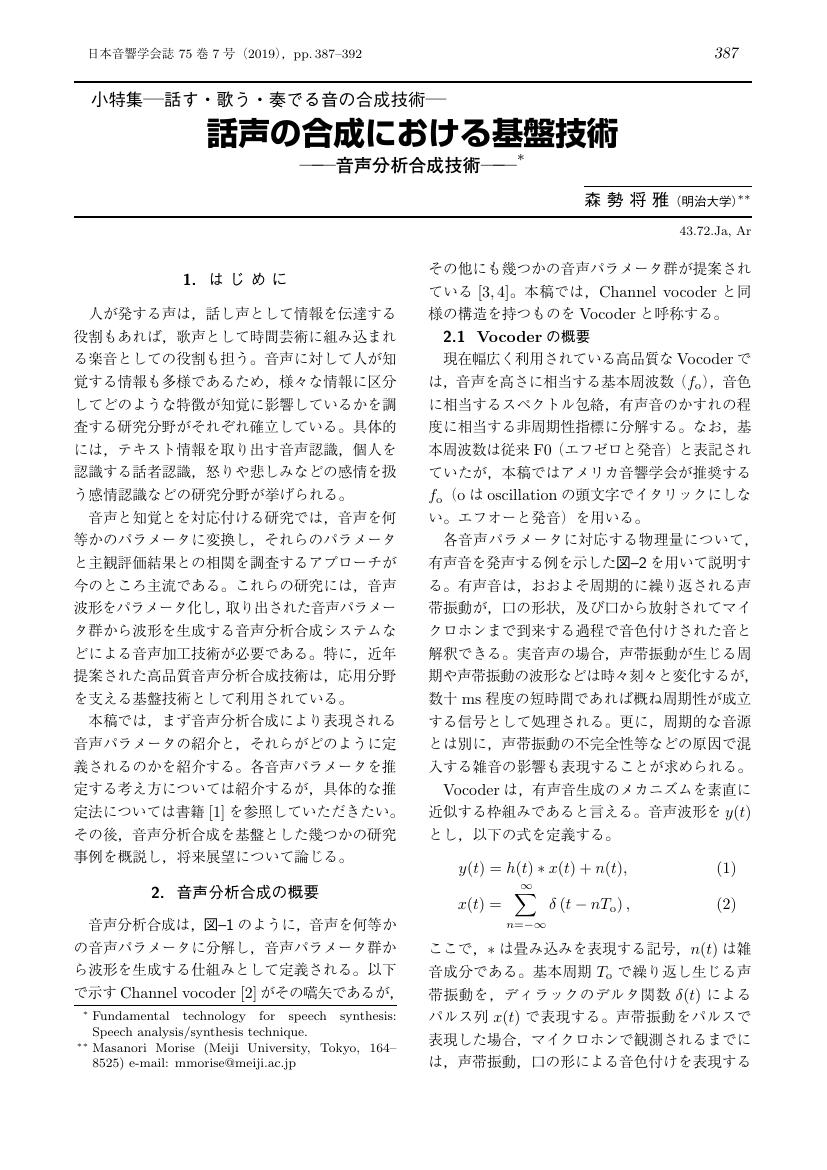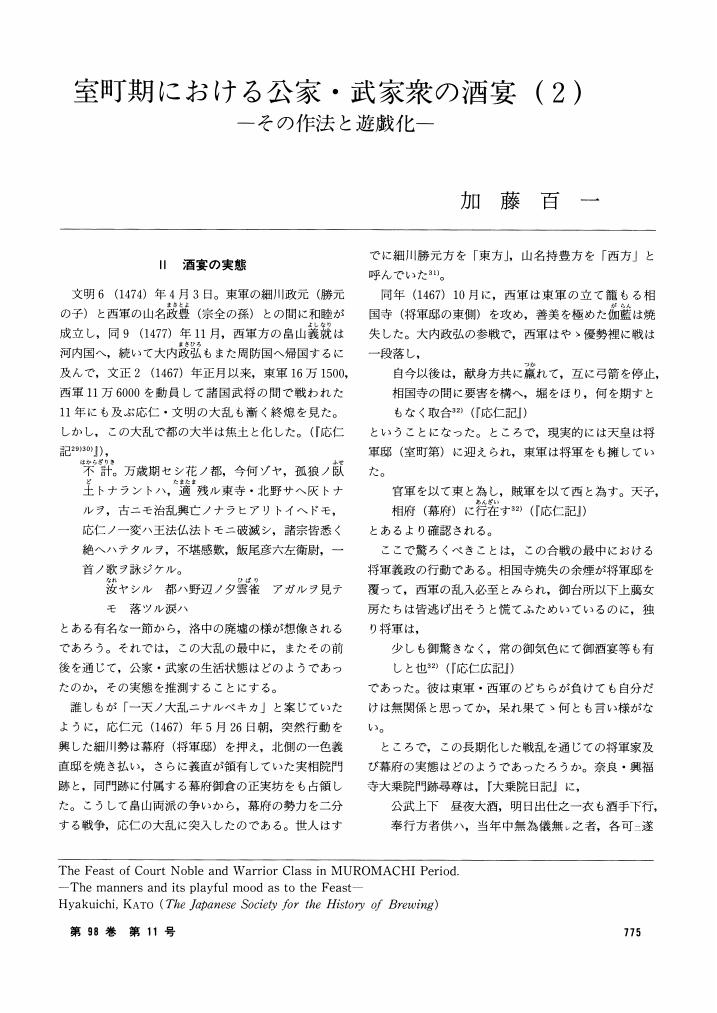3 0 0 0 滋賀県草津市常盤地区(旧栗太郡北部)の近世における条里地割の変化
- 著者
- 小西 佐枝 青柳 憲昌
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.734, pp.1099-1107, 2017 (Released:2017-04-30)
In the Siga prefecture, the boundaries of land lots were considered to be based on the Jo-ri grid pattern until disordered by the land consolidation after the World War 2. In previous studies, while many scholars analyzed about the Jo-ri grid pattern, Kenichi Tanaka pointed out that north-south distance of the each grid section was 110.48m and east-west distance was 109.59m in the south area of the Lake Biwa. According to research reports of excavations, Jo-ri grid patterns were rotated 33 degrees to the east from the north in Tokiwa area in Kusatsu city. In the Tokiwa area, there are historical documents such as Land Resister written in the Edo era and Topographic Maps produced in the early Meiji era. Mainly due to the measuring inaccuracies, those topographic maps have distortions, which therefore corrected in this paper by using old maps and aerial photos, creating reconstruction map of the boundaries of land lots in the early Meiji era. In the results, a large part of boundaries of land allotments formed square patterns in the outer field of 11 villages in this district but were disordered inner settlement area, riverside, and lakeside. Particularly, the roads were bent, the shapes of land were irregular inside settlements of villages. The transformation of land boundaries of the land units, Koaza, was analyzed in this paper by comparing the Tensho Land Resister written in 1591 and the Topographic Maps produced in 1873. Both of those documents contain information concerned with land ownership, names of the sections, sizes of lots, names of the landowners. However, the scale is different; 1 "ken" is converted into 6 "shaku" 3 "sun" ( 1 "tan" = 1090.9 square meters ) in the Tensho Land Resister, and 1 "ken" into 6 "shaku" in the Topographic Maps. In the Oroshimo village, it was in the settlement area of villages and its surroundings, namely farm, riverside, and lakeside, that boundaries of sections do not form in the square pattern. In the lakeside, it is said that development of new rice fields were conducted in the Edo era and village area has expanded 50,137 square meters. Also the area of settlement became approximately 4.7 times according to the comparison of two documents mentioned above. Boundaries of land sections seems not based on Jo-ri grid when new field and site were developed. In the Ashiura village, the boundaries of units were matched to the ancient Jo-ri grid when the Tensho Land Resister was written more than when the topographic map was produced in the Meiji era, especially inner part of settlement area. The size of settlement was approximately 17,560 square maters in the Tensho Land Resister, whereas 65,852 square meters in the topographic map. It is assumed that the transformations and distortions of the former grid boundaries inner villages and the surroundings were caused by enlargement of the settlement area. Historical documents indicates that area reductions or unifications of land section occurred according to the expansion of settlements.
3 0 0 0 OA ケージ産卵鶏に対する福祉的給餌法の検討 : 給餌器へのボールの設置が行動に及ぼす影響
3 0 0 0 OA 文化的自己観と感情認識の明瞭性とを結ぶ内受容感覚
- 著者
- 金井 雅仁 湯川 進太郎
- 出版者
- 日本感情心理学会
- 雑誌
- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.2, pp.71-81, 2017-02-28 (Released:2017-04-06)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 1 1
This study examined the relationships between cultural self-construal (independence/interdependence) and the clarity of emotional awareness, and if the relationships were mediated by interoceptive accuracy. Participants included 100 graduates and undergraduates. After completing scales that assessed cultural self-construal and private self-consciousness, participants performed a heartbeat tracking task, which assessed their interoceptive accuracy. They then viewed negative pictures and evaluated their emotional states. We found that, in males, independence was positively linked to the clarity of emotional awareness, and interdependence was negatively linked to it. Furthermore, when controlling private self-consciousness and heart rate during the heartbeat tracking task, only the relationship between a high sense of interdependence and unclear emotional awareness was mediated by inaccurate interoception. On the other hand, independence and interdependence were not linked to the clarity of emotional awareness in females. These results suggested the possibility that males who had a high sense of interdependence were not clearly aware of their own emotional states because of their insensitivity to internal bodily states.
- 著者
- 山本 英二
- 出版者
- 公益財団法人 史学会
- 雑誌
- 史学雑誌 (ISSN:00182478)
- 巻号頁・発行日
- vol.107, no.2, pp.259-266, 1998-02-20 (Released:2017-11-30)
3 0 0 0 OA 甲殻類の脱皮に関与するホルモン
- 著者
- 納谷 洋子
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.5, pp.447-454, 1988-05-01 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 1
The presence of a molt-inhibiting hormone (MIH) in crustaceans versus the molting hormone (ecdysteroids) has been biologically demonstrated, however, only a little of the chemical nature of MIH is known so far Our attempt to isolate MIH produced in the X-organ of the eyestalks (ES) resulted in the characterization of xanthurenic acid as an ecdysone biosynthesis inhibitor (EBI) In addition, it was found that 3-hydroxy-L-kynurenine (3-OH-K) present in the X-organ of ES was also biotransformed into xanthurenic acid. The inhibitory action was shown in the cultured Y-organ-complex homogenate as well as in the crayfish by injection of 3-OH-K that revealed the delay of ecdysis. The preliminary study of ED50 of the active compounds appeared to account for most of but not the full potency of ES extract. Therefore, a molt-inhibiting phenomena is probably the result of the action by the multiple factors including EBI. After the mode of inhibitory action of the recently isolated sinusgland neuropeptide is shown, the involvement of a hormone in the negative control of molting will be clarified.
3 0 0 0 OA A New Tetragonitid Ammonite from Hokkaido
- 著者
- Tatsuro MATSUMOTO
- 出版者
- The Japan Academy
- 雑誌
- Proceedings of the Japan Academy, Series B (ISSN:03862208)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.33-35, 1984 (Released:2006-10-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 3 4
3 0 0 0 OA 日本における闘牛の存続と特徴
- 著者
- 石川 菜央
- 出版者
- The Human Geographical Society of Japan
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.6, pp.514-527, 2009 (Released:2018-01-10)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 2 2
This paper has two purposes. One is to identify the features of Japanese bullfighting, which originated as an amusement during agricultural off-seasons, and has continued to exist as a traditional event up to the present time. The other is to show the significance and characteristics of Japanese bullfighting as compared to foreign, especially Spanish, bullfighting.The main factors that tend to support the tradition vary by district, for example, as a tourist event, as an appreciation of a traditional event, and as a local amusement. However, there is one overriding common factor. It is the social relationships among the actors engaged in bullfighting that keep it alive. Bull owners get acquainted and become familiar with each other through trading bulls. Bull owners and facilitators are tied together through a deep confidential relationship. Bull owners, their families, and neighbors strengthen the ties among them through cheering on their bulls together.Bulls in Spanish bullfighting symbolize nature. There, bulls are regarded as an enemy of humans. Compared with this, bulls in Japanese bullfighting symbolize humans. A strong bull symbolizes its owner’s power. A battle between bulls is like that between people. Therefore, people and bulls make up a team and fight together. Japanese bullfighting has a characteristic that the Spanish version does not have, which is a social relationship between people centered on their bulls. Networks of bullfighting actors are increasingly becoming widespread across the country. Such a social relationship created through bullfighting is called ushi-en.
- 著者
- Keisuke Matsubara Takuma Okamoto Ryoichi Takashima Tetsuya Takiguchi Tomoki Toda Yoshinori Shiga Hisashi Kawai
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.1, pp.65-68, 2021-01-01 (Released:2021-01-01)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 6
3 0 0 0 OA 行動学的手法で測定した牛の視力値
- 著者
- 萬田 正治 山本 幸子 黒肥 地一郎 渡辺 昭三
- 出版者
- 日本家畜管理研究会(現 日本家畜管理学会)
- 雑誌
- 日本家畜管理研究会誌 (ISSN:09166505)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.55-60, 1993-11-10 (Released:2017-10-03)
- 被引用文献数
- 1
牛の視力を牛の学習能力を利用した動物行動学的手法により検討した。そのため二叉迷路型の学習装置を用い、供試牛の前方左右に視力パネルとしてのランドルト環(正刺激)と同寸法の円(負刺激)を提示した。さらに配合飼料を視力パネルの後方に置き、供試牛が正刺激のランドルト環を選択した場合のみ、配合飼料が摂食できるよう学習訓練した。視力パネルの左右交換は乱数表によりランダムに行い、1セッション20試行とし、適合度の検定により、正反応率が80%以上に達した場合、供試牛はその学習試験を完了したとし、その供試ランドルト環を識別できたと判定した。ランドルト環は0.01のものから0.02刻みにその大きさを変えていき、識別できた最も小さいランドルト環の値をその供試牛の視力値とした。供試牛には鹿児島大学農学部付属農場入来牧場生産の成牛5頭を用いた。1号牛はランドルト環の0.08、2号牛は0.04、3号牛は0.07、4号牛は0.08、5号牛は0.07までそれぞれ識別することができた。したがって供試牛5頭の視力値はランドルト環図形ではおよそ0.04〜0.08の範囲を示し、人間に比べて視力が極めて弱いことが示唆された。日本家畜管理研究会誌、29(2) : 55-60.1993.1993年5月31日受理
3 0 0 0 OA 大沢さん追悼:50年先への千里眼(4) 50年先の生物物理学にのこせるものは
- 著者
- 冨樫 祐一
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3, pp.185-187, 2020 (Released:2020-05-27)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA 肩こりと身体アライメントとに関連はあるか?
- 著者
- 松本 元成 大重 努 久綱 正勇
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.42 Suppl. No.2 (第50回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.1822, 2015 (Released:2015-04-30)
【はじめに,目的】肩こりは医学的な病名ではなく症候名である。「後頭部から肩,肩甲部にかけての筋肉の緊張を中心とする,不快感,違和感,鈍痛などの症状,愁訴」とされるが,明確な定義はいまだない。平成19年の国民生活基礎調査によれば,肩こりは女性の訴える症状の第1位,男性では2位である。このように非常に多い症状であるにもかかわらず,肩こりに関して詳述した文献は決して多くない。我々理学療法士が肩こりを診る場合,姿勢に着目することが多いが肩こり者の姿勢に関する報告も散見される程度で,統一した見解は得られていない。臨床的には肩甲帯周囲のみならず,肋骨,骨盤なども含めた体幹下肢機能についても評価介入を行い,症状の改善が得られる印象を持っている。本研究の目的は,肩こり症状とアライメント,特に肩甲骨,肋骨,骨盤アライメントとの関連性について明らかにすることである。【方法】対象は当院外来患者で,アンケートにおいて肩こり症状が「ある」と答えた女性患者18名である。肩周囲に外傷の既往があるものは除外した。アンケートにおいて肩こり罹患側の左右を聴取した。罹患側の肩こり症状の強さをVisual Analogue Scale(以下VAS)を用いて回答して頂いた。アライメント測定は座位で実施した。座位姿勢は股関節と膝関節屈曲90°となるよう設定した。①体幹正中線と肩甲骨内側縁のなす角②胸骨体と肋骨弓のなす角③ASISとPSISを結んだ線が水平線となす角を,左右ともにゴニオメーターで測定した。①②③の角度を肩こり側と非肩こり側について,対応のあるt検定を用いて比較した。有意水準はそれぞれ5%とした。またPearsonの相関係数を用いて肩こり罹患側におけるVASと①~③のアライメントとの相関関係を検証した。【結果】①の体幹正中線と肩甲骨内側縁のなす角は,非肩こり側で12.50±6.13°,肩こり側で3.11±7.76°と肩こり側において有意に減少していた。②胸骨体と肋骨弓のなす角においては有意差を認めなかった。③ASISとPSISを結んだ線が水平線となす角は,非肩こり側で7.83±7.74°,肩こり側で3.17±8.59°と肩こり側において有意に減少していた。VASと①②③のアライメントについては有意な相関を認めなかった。【考察】本研究の結果より,肩こり側は非肩こり側に比べて肩甲骨の上方回旋が減少し,骨盤の前傾が減少していることがわかった。座位姿勢において土台となる骨盤のアライメントがより上方の身体へと波及し,肩こりに何らかの影響を及ぼしている事が示唆された。身体アライメントと肩こり症状の強さにはいずれも相関を認めず,症状の強さは今回調べた身体アライメントの異常だけでは説明がつかないことがわかった。本研究の限界として肩甲骨の上方回旋,下方回旋,骨盤では前後傾以外のアライメントには着目できていない。またあくまで同一被検者内での肩こり側,非肩こり側の比較である。今後,他のアライメントについてあるいは,肩こり者と非肩こり者間での検討も必要であると考える。【理学療法学研究としての意義】肩こりの理学療法において,肩甲帯周囲のみならず骨盤帯周囲に対しても評価,介入が必要となる場合があるかもしれない。また肩こり症状の強さについては,身体アライメントのみならず多角的な視点や介入が必要であることが示唆された。
3 0 0 0 OA 末期腎不全時に腎外クリアランスが変動する薬剤とその要因
- 著者
- 辻本 雅之 峯垣 哲也 西口 工司
- 出版者
- 一般社団法人 日本腎臓病薬物療法学会
- 雑誌
- 日本腎臓病薬物療法学会誌 (ISSN:21870411)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-13, 2012 (Released:2018-04-02)
- 参考文献数
- 28
本総説では、末期腎不全患者(CKDグレード5)における肝消失型薬剤の予期せぬ薬物動態変動に対して注意喚起を促すために、末期腎不全患者においてバイオアベイラビリティの増大や肝クリアランスの低下と言った腎外クリアランスの変動を生じる事例について紹介する。 具体的には、末期腎不全患者において、 1. バイオアベイラビリティ増大の可能性について、プロプラノロールおよびプラバスタチンの事例について示す。 2. 肝代謝阻害の可能性について、ロサルタンおよびワルファリンの事例について示す。 3. 肝取り込み阻害の可能性について、エリスロマイシン、フェキソフェナジンおよびジゴキシンの事例について示す。 4. 腎外クリアランスの増大の可能性について、CPT-11の事例について示す。 5. 特異的に生じる薬物間相互作用の可能性について、コルヒチン−クラリスロマイシン間およびジゴキシン−フェキソフェナジン間の事例について示す。 以上の事例から、末期腎不全患者においては、単に腎機能低下に伴う薬物投与設計では不十分な場合があり,薬剤または/および患者によっては、バイオアベイラビリティの増大、肝クリアランスの低下、腎外クリアランスの増大、薬物間相互作用の顕在化などに注意する必要がある。
3 0 0 0 OA SpO2のアラーム設定レベル:SpO2とSaO2の乖離
- 著者
- 瀬尾 勝弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.130-131, 2014-03-01 (Released:2014-03-19)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1
3 0 0 0 OA 関節リウマチに用いる生物学的製剤による重篤な感染症の解析
- 著者
- 豕瀬 諒 細見 光一 朴 ピナウル 藤本 麻依 髙田 充隆
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.10, pp.586-594, 2014-10-10 (Released:2015-10-10)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 4 3
To examine the association between biologics for rheumatoid arthritis and serious infections (hepatitis B, hepatitis C, tuberculosis, pneumonia and sepsis), we analyzed the US Food and Drug Administration Adverse Event Reporting System (FAERS) and the Japanese Adverse Drug Event Report database (JADER) of Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA). The reporting odds ratio was calculated and used to detect spontaneous report signals, with detection defined as a lower limit >1 in a 95% confidence interval. In addition, time to onset and age at onset of tuberculosis were investigated. Drug-reaction pairs were identified in both FAERS (n = 29,017,485) and JADER (n = 2,079,653). In both databases, significant associations were observed between biologics and infections (hepatitis B, tuberculosis, pneumonia and sepsis). JADER data revealed a significant association of etanercept with hepatitis C. In FAERS, the majority of tuberculosis events, associated with all drugs, were observed within 1 month of administration, whereas most tuberculosis infections associated with biologics were observed during the 5 months following administration. In JADER, most cases of tuberculosis associated with all drugs and with biologics, respectively, were observed during the 2 months after administration. In conclusion, hepatitis C associated with etanercept treatment should be closely monitored in clinical practice. In addition, tuberculosis associated with biologics should be carefully monitored for 5 months following drug administration. Further studies are needed to confirm these findings.
3 0 0 0 OA 話声の合成における基盤技術 ——音声分析合成技術——
- 著者
- 森勢 将雅
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.7, pp.387-392, 2019-07-01 (Released:2020-01-01)
- 参考文献数
- 35
3 0 0 0 OA 話声の合成における応用技術 ——DNNテキスト音声合成システム——
- 著者
- 高木 信二
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.7, pp.393-399, 2019-07-01 (Released:2020-01-01)
- 参考文献数
- 61
3 0 0 0 OA 絶滅のおそれのある九州のニホンリス,ニホンモモンガ, およびムササビ
- 著者
- 安田 雅俊
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.47, no.2, pp.195-206, 2007 (Released:2008-01-31)
- 参考文献数
- 62
- 被引用文献数
- 4
九州において絶滅のおそれのある樹上性リス類(ニホンリス,ニホンモモンガ,およびムササビ)3種について,江戸時代中期以降の各種資料(論文や報告,鳥獣関係統計,毛皮取引の記録等)をとりまとめ,生息記録と利用の変遷,および現在おかれている状況を種ごとに記述した.また,国,九州本土7県,および日本哺乳類学会のレッドデータブックにおける3種の取り扱いを比較した.九州において,(1)ニホンリスは狩猟による捕獲等の記録はあるものの,過去100年間以上,標本を伴った確実な生息情報がないこと,(2)ニホンモモンガは過去50年間の生息情報が極めて限られていること,および(3)近年ムササビの分布域が縮小してきていることが明らかとなった.これらの種の分布域の縮小に関連してきたと推察される要因として,戦後の拡大造林による天然林ハビタットの減少,樹洞や餌資源の減少,先史時代から続いてきた狩猟圧等を列挙した.今後の課題は,第一にニホンリスとニホンモモンガの残された個体群の探索であり,第二にそれぞれの種の分布域の縮小に,どの要因が,いつ,どれほど寄与したのかを解明することである.九州の絶滅のおそれのある樹上性リス類の保全は,県単位で対処できる課題ではなく,地方レベルで対処すべき課題であり,九州地方版のレッドデータブックの作成が考慮されるべきである.信頼性のある生息情報の収集に努め,残された個体群ごとに適切な保全策を講じるために,国の行政機関による強いイニシアチブの発揮が望まれる.
3 0 0 0 OA 柔道選手の握力に関する研究―多種目選手との比較から―
3 0 0 0 OA アジア歴史資料センター ―本格的なデジタルアーカイブを目指して―
- 著者
- 牟田 昌平 小林 昭夫
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.7, pp.477-483, 2002 (Released:2002-10-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
アジア歴史資料センターは,2001年11月30日,独立行政法人国立公文書館の組織として開設された。アジア近隣諸国との相互理解促進のために,政府が所蔵する戦前の公文書から,アジア諸国との関係資料をインターネットで「いつでも」「どこでも」「だれもが」「無料」で検索し画像データとして利用できる本格的なデジタルアーカイブである。閣議決定から開設まで2年間,最新の技術動向を踏まえながらも,できるかぎり既存の確立した技術を応用し,手書き文書も含めた文字情報の内容検索と閲覧,印刷,画像データダウンロードに機能を集中した情報提供システムである。本論では,センターの情報提供システムの特長と言える最新の画像圧縮技術を導入した画像提供システム,歴史用語と英語に対応する専門辞書,検索情報を充実させるための原文情報や英文検索対応の目録システムを中心に紹介する。
3 0 0 0 OA 室町期における公家・武家衆の酒宴 (2) その作法と遊戯化
- 著者
- 加藤 百一
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本醸造協会誌 (ISSN:09147314)
- 巻号頁・発行日
- vol.98, no.11, pp.775-784, 2003-11-15 (Released:2011-09-20)
- 参考文献数
- 16