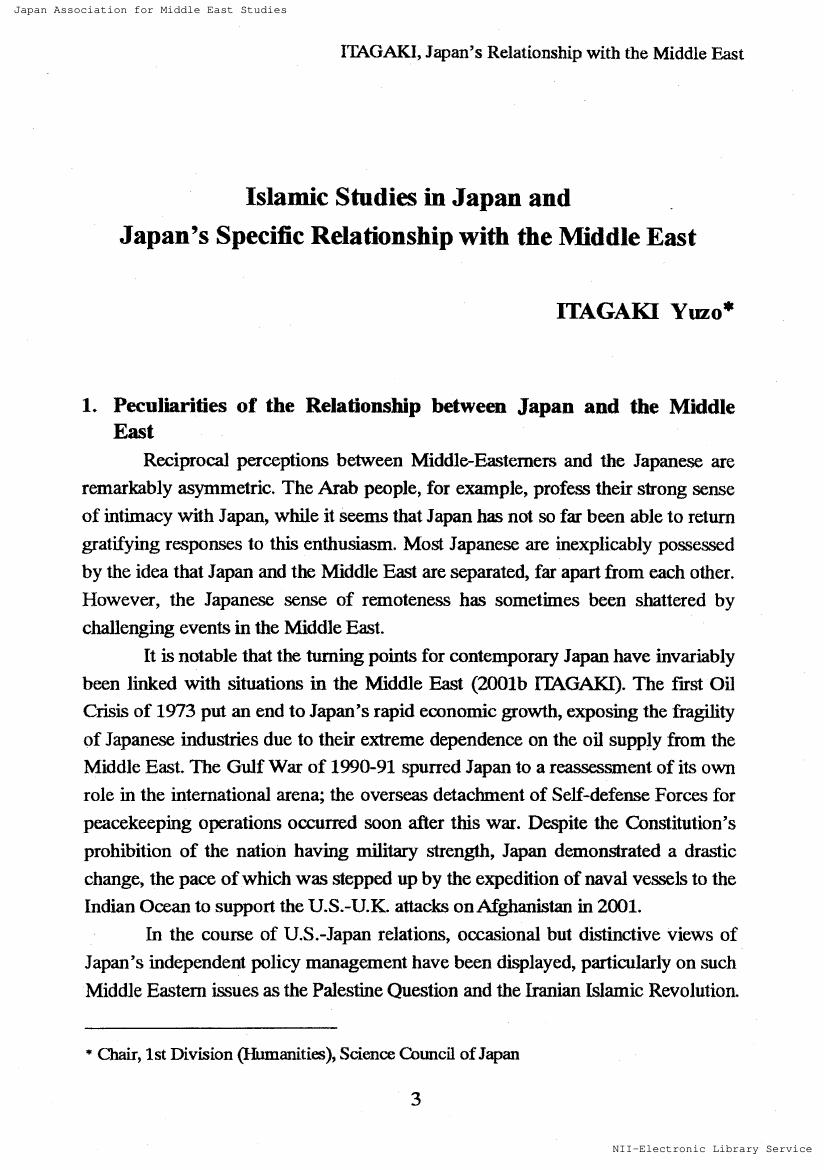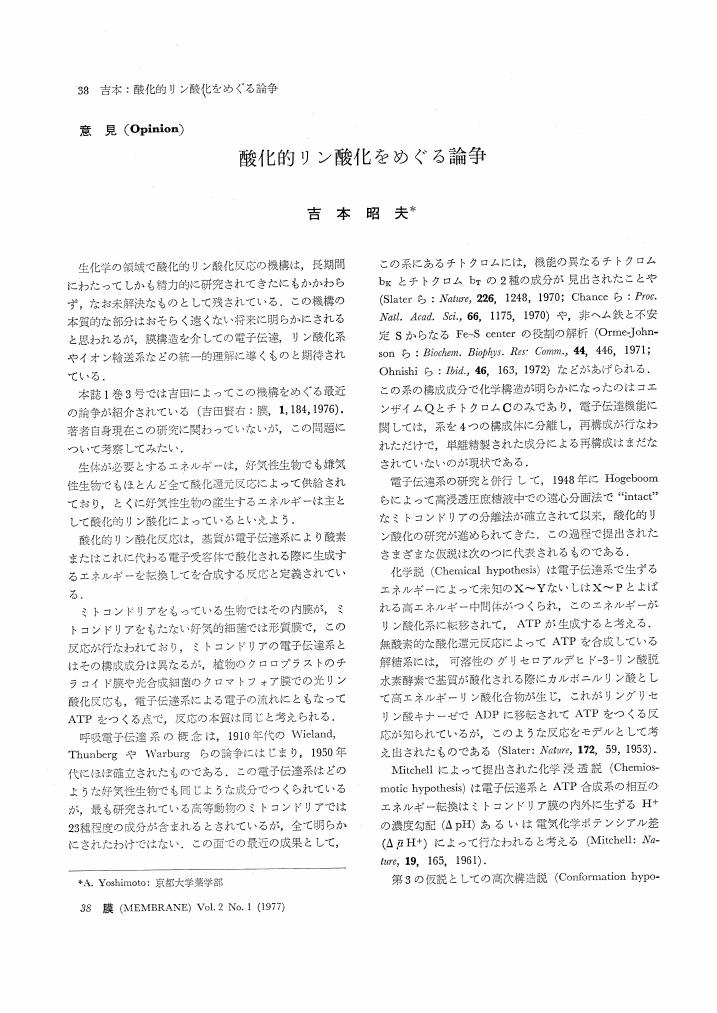3 0 0 0 OA Low-power High-performance 32-bit RISC-V Microcontroller on 65-nm Silicon-On-Thin-BOX (SOTB)
- 著者
- Trong-Thuc Hoang Ckristian Duran Khai-Duy Nguyen Tuan-Kiet Dang Quynh Nguyen Quang Nhu Phuc Hong Than Xuan-Tu Tran Duc-Hung Le Akira Tsukamoto Kuniyasu Suzaki Cong-Kha Pham
- 出版者
- The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers
- 雑誌
- IEICE Electronics Express (ISSN:13492543)
- 巻号頁・発行日
- pp.17.20200282, (Released:2020-10-06)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 7
In this paper, a 32-bit RISC-V microcontroller in a 65-nm Silicon-On-Thin-BOX (SOTB) chip is presented. The system is developed based on the VexRiscv Central Processing Unit (CPU) with the Instruction Set Architecture (ISA) extensions of RV32IM. Besides the core processor, the System-on-Chip (SoC) contains 8KB of boot ROM, 64KB of on-chip memory, UART controller, SPI controller, timer, and GPIOs for LEDs and switches. The 8KB of boot ROM has 7KB of hard-code in combinational logics and 1KB of a stack in SRAM. The proposed SoC performs the Dhrystone and Coremark benchmarks with the results of 1.27 DMIPS/MHz and 2.4 Coremark/MHz, respectively. The layout occupies 1.32-mm2 of die area, which equivalents to 349,061 of NAND2 gate-counts. The 65-nm SOTB process is chosen not only because of its low-power feature but also because of the back-gate biasing technique that allows us to control the microcontroller to favor the low-power or the high-performance operations. The measurement results show that the highest operating frequency of 156-MHz is achieved at 1.2-V supply voltage (VDD) with +1.6-V back-gate bias voltage (VBB). The best power density of 33.4-µW/MHz is reached at 0.5-V VDD with +0.8-V VBB. The least current leakage of 3-nA is retrieved at 0.5-V VDD with -2.0-V VBB.
3 0 0 0 OA ジャガイモのデンプン含量が調理特性に及ぼす影響
- 著者
- 小宮山 誠一 目黒 孝司 加藤 淳 山本 愛子 山口 敦子 吉田 真弓
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.4, pp.336-342, 2002-11-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 13
We examined the relationship between the starch content of potato and its cooking quality. Potato tubers were assigned according to their starch content from 12% to 16%. They were cooked by different methods and a sensory evaluation then carried out. In the case of boiling, steaming, frying and heating in a microwave oven, potato with the high starch content (HS) was evaluated as having a richer and more mealy feeling and better taste than potato with the low starch content (LS). On the other hand, in curry and nikujaga (pototo stewed with pork), LS was evaluated to be better than HS because of less collapse after cooking. In potato salad, HS was evaluated more highly than LS in taste only by the manufacturers' panel. The glutamic acid content was particularly low in potato tubers with a starch content of 15% and above.
3 0 0 0 OA <臨床に有用な基礎知識>顎関節症と咬合の関係に関するup-to-dateな見解
- 著者
- 矢谷 博文
- 出版者
- 一般社団法人 日本顎関節学会
- 雑誌
- 日本顎関節学会雑誌 (ISSN:09153004)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.36-43, 2018-04-20 (Released:2018-05-14)
- 参考文献数
- 53
顎関節症のリスク因子には,外傷,解剖学的因子,病態生理学的因子,心理社会学的因子など多くのものがあることが知られており,そのうち単一の因子,あるいは複数の因子の複合によって発症するものと考えられる。すなわち,顎関節症の原因は患者によって異なっており,生物心理社会学的モデル(biopsychosocial model)の枠組みのなかで,病歴聴取を含む臨床的診察や検査結果を基に,目の前の患者ごとにそれらの複数のリスク因子のなかから推定されるべきである。咬合因子の顎関節症発症における役割について論じた質の高い文献は依然少ないものの,それらの文献は,咬合因子は顎関節症発症のリスク因子の一つにすぎず,咬合が発症の最重要因子となっている症例は決して多くはないというエビデンスを一致して示している。このことは,不可逆的治療である咬合治療は顎関節症の治療法の第一選択ではなく,保存療法,可逆療法を優先すべきであるというメッセージをわれわれに伝えている。
- 著者
- 杉田 典正 松井 晋 西海 功
- 出版者
- Pro Natura Foundation Japan
- 雑誌
- 自然保護助成基金助成成果報告書 (ISSN:24320943)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, pp.187-198, 2020 (Released:2020-09-29)
- 参考文献数
- 17
日本ではウミスズメは北海道天売島の海食崖でのみ少数が繁殖する.緊急の保全策が必要にも拘わらず,保護増殖事業は未だ策定されていない.ウミスズメの野外調査が困難なため,保全管理に必要な生態・遺伝情報を得ることができなかったためである.しかし,2016年に営巣地付近で30羽のウミスズメの血液が採取され,天売島繁殖個体群の遺伝的特性の推定が可能になった.ミトコンドリアDNA分析では,天売島個体群とアリューシャン列島個体群は共通のハプロタイプをもっていたが,他の繁殖個体群とはハプロタイプを共有していなかった.この結果は,両個体群は異なる単位で保全管理される必要があることを示している.天売島個体群は,アリューシャン列島個体群と遺伝子流動は活発であり,遺伝的多様性が低いことを示す証拠は無かった.私たちは,天売島個体群の効果的な保全のために,営巣地の保全による管理を提案する.日本近海はウミスズメの越冬場所として重要な海域であり,より広域的な保全管理が必要だろう.
- 著者
- Jun Yasuhara Toshiki Kuno Moe Taki Koichi Toda Takashi Kumamoto Takuro Kojima Hiroyuki Shimizu Shigeki Yoshiba Toshiki Kobayashi Naokata Sumitomo
- 出版者
- International Heart Journal Association
- 雑誌
- International Heart Journal (ISSN:13492365)
- 巻号頁・発行日
- pp.19-099, (Released:2019-11-15)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
Postoperative arrhythmias are a frequent and fatal complication after the Fontan operation. However, clinical evidence demonstrating early postoperative arrhythmias in children undergoing the Fontan operation is limited. This study aimed to evaluate the prevalence of arrhythmias and identify the predictors of early postoperative supraventricular tachyarrhythmias (SVTs) after the Fontan procedure.Data were analyzed from 80 pediatric patients who underwent Fontan procedures between April 2000 and December 2017 in a single-center retrospective study. Early postoperative SVTs were defined as arrhythmias within 30 days after the Fontan procedure. We divided the patients into two groups, with or without early postoperative arrhythmias, and the predictors of early postoperative arrhythmias were analyzed. A multivariate logistic regression analysis was performed to determine independent predictors of early postoperative SVTs after the Fontan procedure.Early postoperative SVTs were observed in 21 patients (26.3%). The most common arrhythmia was junctional ectopic tachycardia. After an adjustment, an atrioventricular valve regurgitation (AVVR) grade of ≥2 (odds ratio 10.54, 95% confidence interval 2.52 to 44.17, P = 0.001) and preoperative arrhythmias (odds ratio 26.49, 95% confidence interval 1.64 to 428.62, P = 0.021) were significant predictors of early postoperative SVTs after the Fontan operation.An AVVR grade ≥2 and preoperative arrhythmia were significant predictors associated with early postoperative SVTs. Intervention for AVVR may provide clinical benefit for preventing early postoperative arrhythmias after the Fontan operation.
- 著者
- Yuzo ITAGAKI
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.2, pp.3-16, 2002-03-31 (Released:2018-03-30)
3 0 0 0 OA 片脚立位時の非支持脚挙上方向の股関節角度の相違が支持脚筋活動に与える影響
- 著者
- 會田 萌美 武井 圭一 奥村 桃子 平澤 耕史 田口 孝行 山本 満
- 出版者
- 公益社団法人 埼玉県理学療法士会
- 雑誌
- 理学療法 - 臨床・研究・教育 (ISSN:1880893X)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.25-28, 2016 (Released:2016-03-17)
- 参考文献数
- 7
【目的】本研究では,片脚立位における非支持脚拳上方向の股関節角度の相違に着目し,支持脚筋活動に与える影響を明らかにすることを目的とした。【方法】男子大学生13名を対象に,片脚立位姿勢(非支持脚股関節中間位,外転20度・45度,屈曲30度・90度)を保持させ,支持脚の大殿筋,中殿筋,大腿筋膜張筋,腓腹筋内側頭の筋活動を測定した。4筋における股関節中間位と外転位,股関節中間位と屈曲位の肢位間の筋活動を比較した。【結果】非支持脚を外転方向へ挙上した片脚立位では,角度の増大に伴い中殿筋に有意な筋活動の増加を認めた。外転45度・屈曲90度の片脚立位では,股関節中間位の片脚立位に比べ,中殿筋・大殿筋の有意な筋活動の増加を認めた。【結論】Closed Kinetic Chainでの筋力トレーニングとしての片脚立位は,股関節外転により支持脚中殿筋の筋活動を鋭敏に増加させ,外転45度・屈曲90度では股関節周囲筋の筋活動を増加させる特徴があると考えられた。
3 0 0 0 OA 地域における介護予防のエビデンス
- 著者
- 清野 諭 野藤 悠
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.5, pp.327-335, 2019-10-01 (Released:2019-10-01)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 2
Although multiple disability prevention efforts and interventions for older adults have been implemented in the community, only a limited number of studies have verified whether these efforts have actually reduced the occurrence of disability or frailty. This paper reviewed evidence on the effects of community-based interventions for disability prevention on risks of disability and frailty at both the individual and population levels. Consequently, first, participation in exercise or nutrition programs based on high-risk strategies significantly reduced the risk of disability occurrence and suppressed medical and care costs for frail older adults, compared with nonparticipants. However, the participation rate for elderly populations in such programs was extremely low. Second, the creation of self-management programs based on population strategies, such as exercise groups or community salons, significantly reduced the participant’s risk for disability and frailty. The number of such “gathering places” and the participation rate in the elderly population progressively increased, suggesting it may contribute to disability prevention not only at the individual level, but also at the population level. However, previous studies have required long terms (4–5 years) to confirm significant reduction in an individual’s risk for disability and frailty. Finally, although previous studies that verified the effects of disability or frailty prevention at the population level have been extremely limited, one study demonstrated it is possible to reduce the rate of disability at the population level. Further studies are needed to verify the effects of various community-based disability prevention efforts on individual- and population-level disability and frailty for older adults.
3 0 0 0 OA 糠床の熟成に関する研究 熟成中の菌叢および糠床成分の変化
- 著者
- 今井 正武 平野 進 饗場 美恵子
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11, pp.1105-1112, 1983 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 8 7
野菜を漬けた糠床Tと対照床Cにおいて, 120日間熟成し微生物叢と成分の変化を追跡した.成分的変化としては,糖は30日までにほとんど消費され酸に変化した.脂質は増加し,ホルモルN,揮発性塩基性NはT床において60日間で急激に増加した.菌叢の変化としては初めEnterobacterを中心とするグラム陰性菌が優勢であったが, 30日以内にLactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus, Pec. halophilusが菌叢の大部分を占めた.熟成が進むにつれ, T床では酵母,乳酸菌以外のグラム陽性菌,そしてProteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae類縁菌を中心とするグラム陰性菌が多数検出され,それらのバランスが熟成臭に重要な影響を持つと思われた. 糠床中の食塩濃度は酸の生成やグラム陰性菌等の生育に密接な関係を持ち,酸や揮発性塩基性物質等のフレーバーに影響する重要な役割を持っていると考えられる.
3 0 0 0 OA 無線LAN国際規格IEEE802.11の標準化―標準化作業手順とその最新動向―
- 著者
- ラナンテ レオナルド Jr. 長尾 勇平 尾知 博
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.2, pp.124-132, 2019-10-01 (Released:2019-10-01)
- 参考文献数
- 16
本稿では,IEEE主導の802.11委員会によって策定されている無線LAN国際規格IEEE802.11の標準化作業の手順や最近の規格動向について概説する.同規格では,最新の11ac改訂でダウンリンクマルチユーザ技術が導入され,もうすぐ標準化作業が完了する11ax改訂でOFDMA技術によるアップリンクマルチユーザ高効率通信が可能となる.筆者らは,それらの規格改訂において計3件(11ac改訂で2件,11ax改訂で1件)の技術提案が採択された経験を有している.また,次世代測位規格11azや次世代超高速通信規格11beなどの最新の標準化動向についても紹介する.
3 0 0 0 OA 鰤糸状虫の生活史に関する研究―I
- 著者
- 中島 健次 江草 周三
- 出版者
- The Japanese Society of Fish Pathology
- 雑誌
- 魚病研究 (ISSN:0388788X)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.12-15, 1970-09-30 (Released:2010-02-10)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 4
3 0 0 0 OA 漢方薬による間質性肺炎と肝障害に関する薬剤疫学的検討
- 著者
- 寺田 真紀子 北澤 英徳 川上 純一 足立 伊佐雄
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.5, pp.425-434, 2002-10-10 (Released:2011-03-04)
- 参考文献数
- 82
- 被引用文献数
- 14 16
In Japan, traditional herbal medicines (kampo medicines) have been widely used for various diseases as relatively safer drugs than Western medicines. However, serious adverse-events such as interstitial pneumonia (IP) and liver dysfunction (LD) have recently been reported. In this study, IP and LD associated with Kampo medicines were reviewed pharmacoepidemiologically to establish an effective monitoring protocol and appropriate treatment schedules while also elucidating the possible ingredients for IP and LD. Medline, JICST and J-Medicine databases were searched for IP and LD induced by Kampo medicines published in 1984-2000. Thirty-five cases of IP including 8 mortal cases and 28 cases of LD have been reported. As initial symptoms, 60-80% of IP patients developed dyspnea, fever and cough. On the other hand, the initial symptoms for LD patients were not characterized. Stopping the medications improved the symptoms in 29% of IP and 54% of LD patients. A total of 72 % of IP and 7 % of LD patients required corticosteroid treatment. Scutellariae radix was contained in Kampo medicines for 94% of IP patients and 89% of LD patients. A challenge test was positive in 9 cases of IP and 10 cases of LD. Scutellariae radix was contained in all positive Kampo medicines. Our review suggested that Scutellariae radix was a possible ingredient responsible for IP and LD. Monitoring the initial symptoms and immediately stopping medications were important steps for avoiding serious adverse-events associated with Kampo medicines.
- 著者
- 池内 裕美
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.10, pp.486-492, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)
「カスタマーハラスメント」とは,簡単にいうと従業員に対する顧客からの嫌がらせであり,悪質クレームとほぼ同義である。近年,流通業の店員の約7割がこうした迷惑行為を受けていた事実が明らかとなり,世の中を震撼させた。では,なぜカスタマーハラスメントは生じるのであろうか。増加の背景には,いかなる心理的・社会的要因が関係しているのだろうか。また,被害を受けた場合,従業員はどのように対処すればよいのか。本稿では,こうしたカスタマーハラスメントをめぐる諸問題について,心理学の知見や関連分野の先行研究を基に概説する。そして最後に,従業員保護の観点から組織の在り方について私見を述べる。
3 0 0 0 OA 静的OSのための静的APIとコンフィギュレータ
- 著者
- 高田 広章
- 出版者
- 日本ソフトウェア科学会
- 雑誌
- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.3_45-3_66, 2020-07-22 (Released:2020-09-22)
使用するOSオブジェクトをシステム構築時に生成する静的OSにおいては,OSオブジェクトの生成に必要なコンフィギュレーション情報を,何らかの方法で記述する必要がある.静的APIは,リアルタイムOSのコンフィギュレーション情報を記述するための記述言語である.μITRON4.0仕様においてはじめて導入し,TOPPERS新世代カーネル仕様において改善を行った.本論文では,静的APIに求められる要件と,それらの仕様における静的APIの具体的な仕様について述べる.また,静的APIを処理するコンフィギュレータの設計と実装について,TOPPERSプロジェクトにおける約20年間の開発の歴史に沿って述べる.
3 0 0 0 OA 酸化的リン酸化の機構をめぐる最近の論争によせて
- 著者
- 吉田 賢右
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.3, pp.184-186, 1976-09-10 (Released:2010-10-21)
3 0 0 0 OA 酸化的リン酸化をめぐる論争
- 著者
- 吉本 昭夫
- 出版者
- 日本膜学会
- 雑誌
- 膜 (ISSN:03851036)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.1, pp.38-40, 1977-02-01 (Released:2010-10-21)
3 0 0 0 OA わが国における薬剤による有害事象に関する判例の検討:判例誌掲載例の分類
- 著者
- 江口 里加 加藤 正久 金子 絵里奈 草場 健司 吉川 学 山野 徹 瀬尾 隆 萩原 明人
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.3, pp.501-506, 2015 (Released:2015-03-01)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
Much of the damage to health caused by drugs could be prevented by appropriate care. A well-defined duty of care and further information are required for healthcare professionals. Although there are many litigation cases to use as references, neither the extent of the duty of care nor the obligation to explain medication according to the type of drug prescribed has yet been fully established. Thus, we systematically collected decided cases of adverse drug events, and assessed the degree of the duties of care and information. Specifically, we collected decided cases in which physicians, dentists, pharmacists, nurses, or hospitals had been sued. Data were derived from Bessatsu Jurist Iryo-kago Hanrei Hyakusen, Hanrei Jihou, and Hanrei Times from 1989 to November 2013, and information on precedents in the records of the Supreme Court of Japan from 2001 to November 2013. We analyzed the cases, and assessed the following according to the type of drug: (1) standards and explanations when dealing with drugs that were critical issues in litigation, and (2) the degree of the physician's or pharmacist's duties of care and information. In total, 126 cases were collected. The number of drug categories classified was 27, and 9 were considered of practical importance. After this systematic review, we found a trend in the degree of the required level of care and information on several drugs. With respect to duties of care and information, the gap between the required level and actual practice suggests that healthcare professionals must improve their care and explanations.
3 0 0 0 OA スパイナルドレナージ併用の胸部ステントグラフト内挿術後に急性硬膜下血腫を生じた1例
- 著者
- 後藤 徹 田崎 淳一 東谷 暢也 今井 逸雄 塩井 哲雄 丸井 晃 坂田 隆造 舟木 健史 堀川 恭平 安部倉 友 宮本 享 木村 剛
- 出版者
- 公益財団法人 日本心臓財団
- 雑誌
- 心臓 (ISSN:05864488)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.465-470, 2013 (Released:2014-09-13)
- 参考文献数
- 7
症例は77歳, 女性. 脳梗塞の既往あり, 胸部大動脈瘤 (70mm) を指摘され当院受診した. 手術ハイリスクのためステントグラフト内挿術 (thoracic endovascular aortic repair ; TEVAR) を施行した. 術前評価にてAdamkiewicz動脈がTEVARに伴い閉塞することが明らかであり, スパイナルドレナージ (cerebrospinal fluid drainage ; CSFD) を挿入したうえで, TEVARを施行した. 外腸骨動脈の石灰化および狭窄のため大腿動脈からのTEVAR用シース挿入困難であり, 後腹膜アプローチにて総腸骨動脈からシースを挿入し, TAGステントグラフトを留置した. シース抜去時に血管壁を損傷したため, 術中から輸血を要し, 外科的に修復して閉腹した. 術後, 播種性血管内凝固症候群 (disseminated intravascular coagulation syndrome ; DIC) となり輸血を要したが, 翌日に意識混濁と右共同偏視を認め, CTで右急性硬膜下血腫を認めたため, 緊急開頭血腫除去術を施行した. 開頭術後は頭部再出血および出血による神経学的後遺症は認めず, 輸血治療によりDICは改善した. TEVAR施行後にendoleakは認めず, 術後47日目に転院となった. TEVARによる重篤な合併症の1つに対麻痺があるが, その予防目的にCSFDは有用な手段である. 急性硬膜下血腫はCSFDの予後にかかわる重大な合併症であるが, TEVARにおけるCSFD後の急性硬膜下血腫の頻度は報告されていない. 今回われわれは, 早期発見と他科との連携により後遺症を残さず救命に成功した症例を経験したので報告する.
- 著者
- 馬場 正美 洲崎 英子 平良 梢 伊藤 友里 加地 ひかり 岡田 温
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.3, pp.291-299, 2020-07-25 (Released:2020-09-04)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1
目的:コラーゲンペプチドが骨格筋量に影響を及ぼすかどうかを検討するため,回復期リハビリテーション病棟において,コラーゲンペプチド含有経口栄養補助食品摂取群(以下 介入群)と非摂取群(以下 コントロール群)の間に,体組成,身体計測値,Activities of Daily Living,食事摂取栄養量に違いがあるかどうかを検討した.方法:2018年6月1日~2018年8月31日までの間に骨折または脳卒中で回復期リハ病棟に入院した65歳以上の患者19名を対象とし,介入群にはコラーゲンペプチド10ℊを含有するONSを摂取させた.結果:患者の平均年齢は介入群が78.3±7.0歳,コントロール群が75.2±5.5歳,男女比は介入群が男性3名,女性7名,コントロール群が男性2名,女性7名であり,患者の在院日数は介入群が72.9±29.7日,コントロール群が69.7±15.4日であった.介入前後におけるFFMの変化量は,介入群が+0.55±1.4 kg,コントロール群が-1.67±2.2 kg,SMMの変化量は介入群が+0.29±0.8 kg,コントロール群が-0.96±1.3 kg,SMIの変化量は介入群が+0.11±0.3 kg/m2,コントロール群が-0.31±0.4 kg/m2であり,FFM,SMM,SMIのいずれの項目においてもコントロール群に比べて介入群の変化量は有意に大きかった.また,介入群のSMIは1日あたり0.002±0.03 kg/m2増加した.結論:コラーゲンペプチドの経口摂取は,回復期リハビリテーション病棟患者の骨格筋量を増加させる可能性が示唆された.
3 0 0 0 OA 食品機能性成分としてのスフィンゴ脂質の消化と吸収
- 著者
- 菅原 達也
- 出版者
- Japan Society of Nutrition and Food Science
- 雑誌
- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.4, pp.177-183, 2013 (Released:2013-08-16)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 3 2
スフィンゴ脂質は, 真核生物の細胞膜構成成分の一つであり, 細胞の分化やアポトーシスなどの生命現象に深く関わっていることが知られている。近年, 食品機能成分としても注目されつつあり, とくに皮膚バリア向上作用が期待されている。したがって, 経口摂取されたスフィンゴ脂質の消化と吸収の機構を明らかにすることは, その食品機能性を理解する上でも重要といえる。グルコシルセラミドやスフィンゴミエリンなどのスフィンゴ脂質は, 小腸内で消化を受け, その構成要素であるスフィンゴイド塩基にまで加水分解された後に小腸上皮細胞に取り込まれる。しかし, その分解効率は低く, 吸収率も低い。スフィンゴシンと比べて, それ以外の化学構造のスフィンゴイド塩基はP-糖タンパク質による排出を受けやすいため, 吸収はさらに低いことが示唆されている。スフィンゴ脂質の有効利用のためにも, その選択的吸収機構の詳細について, 今後明らかにされる必要がある。