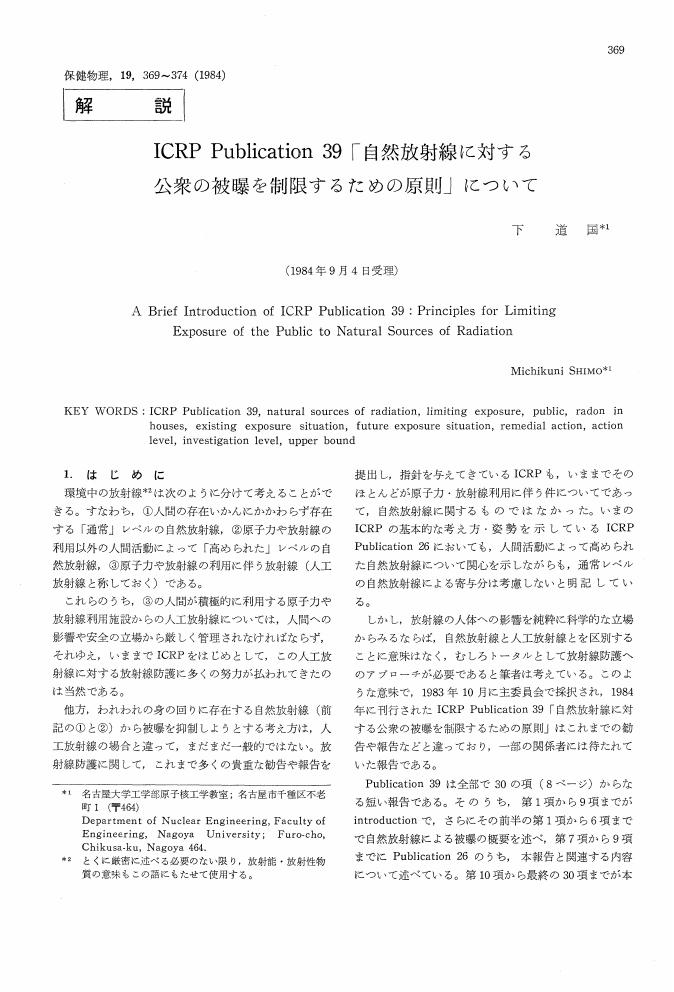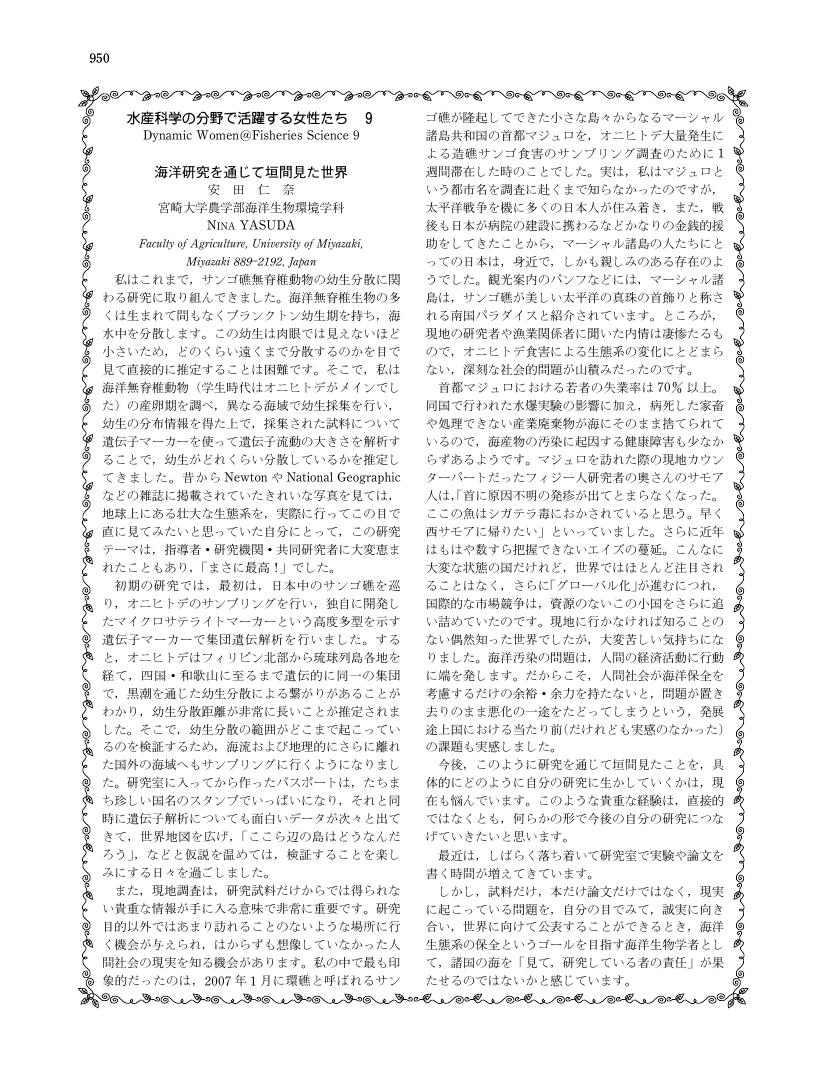- 著者
- Fraidoon Karimi Moeko Igata Takashi Baba Satoshi Noma Daiki Mizuta Jin Gook Kim Takuya Ban
- 出版者
- 一般社団法人 園芸学会
- 雑誌
- The Horticulture Journal (ISSN:21890102)
- 巻号頁・発行日
- pp.MI-158, (Released:2016-11-02)
- 被引用文献数
- 4
Pruning is a recommended cultural practice in blueberries (Vaccinium spp.) to maintain the balance between vegetative growth and reproductive development. Winter pruning is common and well-documented practice. Summer pruning, however, has been less studied. In this study, 5 primaryshoots (PSs) were selected per treatment (pruning date) on 5 different bushes (replications) of the rabbiteye blueberry (Vaccinium virgatum Ait.) ‘Tifblue’ and half-length headed back during its active growth period from June through Nov. The hypothesis tested in this study was that summer pruning induces flower buds at the basal area of PSs, controls the plant canopy and makes it possible to harvest fruits in the next summer season from the same shoots. In this study, there were no significant differences observed among any treatments with respect to yield and fruit quality. Early summer pruning (June) stimulated secondaryshoots (SSs) and later in autumn, terminal flower buds of these SSs produced fruits in the following year. However, no SSs were produced after summer pruning in Sept., and only vegetative buds that were at the basal area of PSs differentiated to flower buds and produced fruits in the following year. In conclusion, summer pruning can be practiced to complement or replace winter pruning and growers could decide the date of summer pruning in accordance with the size of plants’ canopies. Plants with smaller canopies can be pruned in June and those with bigger canopies can be pruned in Sept.
- 著者
- 宇津木 光克 松崎 晋一 蜂巣 克昌 矢冨 正清 久田 剛志 山田 正信 土橋 邦生 丸田 栄
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.73-77, 2016-04-30 (Released:2016-04-25)
- 参考文献数
- 7
チオトロピウムとインダカテロールを併用している慢性閉塞性肺疾患症例を対象として,グルコピロニウム/インダカテロール合剤への変更による有用性を検討した.対象症例は16例,平均年齢は72.9歳,FEV1は1.31±0.43 L,%FEV1は49.2±12.9%であった.薬剤変更後4週,12週とも肺機能検査では変化を認めなかったが,薬剤変更後12週でのCATは有意に改善した.またデバイスの嗜好性においては,各手技,吸入手技の自信,吸入の継続性に対して,ハンディヘラー®と比較しブリーズヘラー®の嗜好性が高かった.以上のことからチオトロピウムとインダカテロール併用からグルコピロニウム/インダカテロール合剤への変更は,合剤のメリットであるアドヒアランスの向上だけでなく,QOLの改善効果,さらには吸入デバイスに対する嗜好性から吸入の快適さも向上させうることが示唆された.
3 0 0 0 OA 個人情報の活用と保護の技術
- 著者
- 高橋 克巳
- 出版者
- 一般社団法人 情報科学技術協会
- 雑誌
- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.11, pp.585-590, 2016-11-01 (Released:2016-11-01)
個人情報の活用と保護の技術に関して,個人情報の取り扱いの原則を解説し,個人情報の定義を述べた上で,原則に基づいたデータ収集,データ処理,データ保管の技術的観点からの解説を行う。個人情報取り扱いの原則はOECD8原則やISO/IECプライバシーフレームワークを参照しながら,利用目的,データ最小化などという独特の概念を説明し,個人情報保護法が求める保護の技術的意味に迫る。さらにこれらに対してデータ最小化に貢献する匿名化技術や情報セキュリティに貢献する暗号技術の概要を解説する。
3 0 0 0 OA 悪人正機説の系譜について
- 著者
- 梶村 昇
- 出版者
- JAPANESE ASSOCIATION OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.348-353, 1970-12-25 (Released:2010-03-09)
3 0 0 0 OA 貨幣における包摂と排除
- 著者
- ボーン コルネリア 森川 剛光
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2015, no.28, pp.1-17, 2015-08-07 (Released:2016-10-12)
- 参考文献数
- 85
This paper explores the relationship between the money medium and the analysis of mechanisms of inclusion and exclusion. Such mechanisms currently follow a logic of plural or multiple inclusion as opposed to assimilation. In a full-grown monetary economy, money and property have emerged as regulative structures for the participation in economic practice. Discussing the approach of Luhmann, a distinction is drawn between center, semi-periphery, and periphery of the economic system. While the money medium includes the general population into the periphery of the economy through consumption, this contribution can show that the inclusionary mechanism of the center is creditworthiness. It can be demonstrated that in its historical formation the form of credit is organized in a twofold fashion itself: to make profit and to promote social inclusion. Microcredits are analyzed as a global form of inclusion into the center that does not bear on the distinction poor/wealthy.
3 0 0 0 OA Phenotypic Variability of ANK2 Mutations in Patients With Inherited Primary Arrhythmia Syndromes
- 著者
- Mari Ichikawa Takeshi Aiba Seiko Ohno Daichi Shigemizu Junichi Ozawa Keiko Sonoda Megumi Fukuyama Hideki Itoh Yoshihiro Miyamoto Tatsuhiko Tsunoda Takeru Makiyama Toshihiro Tanaka Wataru Shimizu Minoru Horie
- 出版者
- 日本循環器学会
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-16-0486, (Released:2016-10-25)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1 17
Background:Mutations inANK2have been reported to cause various arrhythmia phenotypes. The prevalence ofANK2mutation carriers in inherited primary arrhythmia syndrome (IPAS), however, remains unknown in Japanese. Using a next-generation sequencer, we aimed to identifyANK2mutations in our cohort of IPAS patients, in whom conventional Sanger sequencing failed to identify pathogenic mutations in major causative genes, and to assess the clinical characteristics ofANK2mutation carriers.Methods and Results:We screened 535 probands with IPAS and analyzed 46 genes including wholeANK2exons using a bench-top NGS (MiSeq, Illumina) or performed whole-exome-sequencing using HiSeq2000 (Illumina). As a result, 12 of 535 probands (2.2%, aged 0–61 years, 5 males) were found to carry 7 different heterozygousANK2mutations.ANK2-W1535R was identified in 5 LQTS patients and 1 symptomatic BrS and was predicted as damaging by multiple prediction software. In total, as to phenotype, there were 8 LQTS, 2 BrS, 1 IVF, and 1 SSS/AF. Surprisingly, 4/8 LQTS patients had the acquired type of LQTS (aLQTS) and suffered torsades de pointes. A total of 7 of 12 patients had documented malignant ventricular tachyarrhythmias.Conclusions:VariousANK2mutations are associated with a wide range of phenotypes, including aLQTS, especially with ventricular fibrillation, representing “ankyrin-B” syndrome.
3 0 0 0 OA 白内障スクリーニングのための簡易検査システムの開発に関する研究
- 著者
- 桜井 理紗
- 出版者
- ライフサポート学会
- 雑誌
- ライフサポート (ISSN:13419455)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.22-22, 2012 (Released:2014-01-27)
- 参考文献数
- 2
3 0 0 0 OA プレースメントテストや高校の履修状況などのデータを用いた初年時成績不振者の早期発見
- 著者
- 大河内 佳浩 山中 明生
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.1, pp.45-55, 2016-06-20 (Released:2016-06-17)
- 参考文献数
- 23
学期ごとに算出されるGPAを利用して退学者・休学者・留年者の分類を行い,入学直後のプレースメントテストや高校での履修状況・入学試験の結果を用いて分析を行った.その結果,数学プレースメントテストを利用することで,初年次に成績不振となる学生を50%程までに絞り込めることが判り,さらに初年次に退学者・休学者・留年者などの未進級となる学生の早期発見に利用できることも判った.一方,高校での履修状況や入学試験の結果と数学プレースメントテストとの間には明確な関係が見られず,それらを用いた初年次未進級学生の絞り込みも困難であることも判った.
3 0 0 0 OA タングステン繊條電球の交流特性
- 著者
- 鈴木 重夫
- 出版者
- 一般社団法人 照明学会
- 雑誌
- 照明学会雑誌 (ISSN:00192341)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.8, pp.176-184, 1932 (Released:2010-10-27)
- 参考文献数
- 7
3 0 0 0 OA がん疼痛治療と医療用麻薬
- 著者
- 鈴木 勉
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.135, no.12, pp.1325-1334, 2015 (Released:2015-12-01)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 1
The World Health Organization has reported that when morphine is used to control pain in cancer patients, psychological dependence is not a major concern. Our studies were undertaken to ascertain the modulation of psychological dependence on morphine under a chronic pain-like state in rats. Morphine induced a dose-dependent place preference. We found that inflammatory and neuropathic pain-like states significantly suppressed the morphine-induced rewarding effect. In an inflammatory pain-like state, the suppressive effect was significantly recovered by treatment with a κ-opioid receptor antagonist. In addition, in vivo microdialysis studies clearly showed that the morphine-induced increase in the extracellular levels of dopamine (DA) in the nucleus accumbens (N.Acc.) was significantly decreased in rats pretreated with formalin. This effect was in turn reversed by the microinjection of a specific dynorphin A antibody into the N.Acc. These findings suggest that the inflammatory pain-like state may have caused the sustained activation of the κ-opioidergic system within the N.Acc., resulting in suppression of the morphine-induced rewarding effect in rats. On the other hand, we found that attenuation of the morphine-induced place preference under neuropathic pain may result from a decrease in the morphine-induced DA release in the N.Acc with a reduction in the μ-opioid receptor-mediated G-protein activation in the ventral tegmental area (VTA). Moreover, nerve injury results in the continuous release of endogenous β-endorphin to cause the dysfunction of μ-opioid receptors in the VTA. This paper also provides a review to clarify misunderstandings of opioid analgesic use to control pain in cancer patients.
3 0 0 0 OA テレビ史にみる市民的人間型の生成
- 著者
- 棚田 梓
- 出版者
- 日本社会情報学会
- 雑誌
- 日本社会情報学会全国大会研究発表論文集 日本社会情報学会 第19回全国大会
- 巻号頁・発行日
- pp.191-194, 2004 (Released:2006-02-01)
- 参考文献数
- 3
1953(昭和28)年,日本でテレビ放送が始まって50年が過ぎた。テレビは戦前にはなかった,新しいメディアである。テレビ受像機が普及していなかった頃は,街頭テレビの前に集まってプロレスに熱狂した。このように,テレビを無料の娯楽と受けとめていた大衆が,やがてニュースショウを好んで見るようになった。ここ半世紀の変貌を「市民的意識の生成」と捉え,その経過を分析した。 テレビ放送開始から現在までを6つに区切り,テレビ年表でそれぞれの時期の特徴を明らかにする。 ?(前史―1952) テレビ放送前夜 ?(1953―1959) 一億総白痴化 ?(1960―1970) アクセルとブレーキ ?(1971―1984) もうけ主義と合理化 ?(1985―1992) ニュースショウの時代 ?(1993―現在まで)メディアの失われた10年
3 0 0 0 OA 30 秒椅子立ち上がりテスト(CS-30)中の呼吸循環応答と骨格筋酸素動態
- 著者
- 田口 飛雄馬 田平 一行
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.48101113, 2013 (Released:2013-06-20)
【はじめに,目的】全身持久力評価は,最も客観的な心肺運動負荷テスト(CPX)やフィールド歩行テストである漸増シャトルウォーキングテスト(ISWT),6 分間歩行テスト(6MWT)を用いられることが多いが,これらの評価法は高価な機器や,広いスペースが必要であり,また高負荷であるためリスクの観点からも通所施設や在宅分野では使用しにくい問題がある.一方,CS-30 はJanesらによって考案された下肢筋力評価法であり,片麻痺患者の最速歩行速度や排泄自立度,転倒予測などとの関連も報告されている.また,試験は椅子から立ち座りを繰り返すことから,全身持久力の評価になり得る可能性がある.そこで今回,健常者を対象にCS-30 とCPXを行い,CS-30 から最高酸素摂取量(VO2peak)を予測可能であるか,またCS-30 の運動強度や呼吸循環器系・筋酸素動態への影響を検証することを研究目的とした.【方法】健常大学生20 名(男性10 名,女性10 名,年齢21.0 ± 1.1 歳)を対象に,2 種類の負荷試験(CS-30,CPX)を実施した.その間,血圧監視装置tango(Sun teck社)を用いて収縮期血圧(SBP),心拍数(HR)を,呼気ガス分析装置(MataMax, Cortex社)を用いて分時換気量(VE),酸素摂取量(VO2)を,組織血液酸素モニター(BOM-L1TRM,オメガウェーブ社)を用いて右外側広筋の骨格筋酸素動態{総ヘモグロビン量(totalHb),脱酸素化ヘモグロビン量(deoxyHb)}を,自覚的運動強度は旧Borgスケールを用い呼吸困難感,下肢疲労感を測定した.またCS-30 は立ち上がりの回数も測定した.負荷プロトコル:CS-30 は高さ40cmの椅子に腰掛け,両下肢を肩幅程度に広げて両腕は胸の前で組ませ,30 秒間で可能な限り立ち座りを繰り返させ,その回数を数えた.CPXは自転車エルゴメーターを用い,ランプ負荷(男性:20W/min,女性:15W/min)で,ペダル回転数60rpmを維持させ症候限界まで運動させた.CPXとCS-30 の測定は1 日以上を空けランダムに実施し,中止基準は目標心拍数・自覚症状などとした.解析方法:1)CS-30 とCPXの各測定項目の比較:安静時を基準とした100 分率を用い,最大値(max),回復1 分(rec1),2 分(rec2)の値を算出した.解析は二元配置分散分析を用い,同時間における比較には対応のあるt検定を用いた.2)CS-30 の回数とVO2peakとの関係:従属変数VO2peak,独立変数をCS-30 の回数とする単回帰分析を行った.いずれも有意水準は5%未満とした.【倫理的配慮,説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に基づき,対象者の保護には十分留意して実施した.全対象者には本研究の趣旨と目的を説明し,自署による同意が得られた後に実施した.また研究は,事前に本学倫理委員会の承認を得た.【結果】1.CS-30 とCPXの各測定項目の比較:totalHb,deoxyHbを除く全ての指標でCS-30 の方がCPXよりも有意に低値であったが,全てにおいて時間要因との交互作用を認めた.また各時間における比較は,SBP,HR,呼吸困難感,下肢疲労感,VEで,全ての時間帯で有意差を認めた.また,最大値におけるCS-30 のCPXに対する割合は,SBP:83%,HR:84%,VO2:49%,VE:38%,呼吸困難感:74%,下肢疲労感:71%,totalHb:94%,deoxyHb:91%であった.2.CS-30 の回数とCPXのVO2peakとの関係:相関係数0.484(p<0.05)の有意な相関が得られ,VO2peak=-0.58+0.928 ×CS-30(回数)の予測式が得られた.【考察】CPXに対するCS-30の割合では,VO2maxで49%であった.これは運動強度がCPXの49%であることを意味している.また循環器系,呼吸器系の各パラメーター,呼吸困難感,下肢疲労感もCPXに対して有意に低値を示したことより,CS-30はCPXに対して負荷の少ない評価法であることが確認された.一方, deoxyHbは有意差がなく,骨格筋にはCPXと同等の脱酸素化が起こっていると考えられた.更にrec1:129%・rec2:126%と高く,CS-30 で回復が遅延することを示しており,これは骨格筋への負荷はCPX以上であることが推察された.また,CS-30 の起立回数とVO2peakには有意な相関があったが,決定係数は低いため,大まかな予測は可能であるが,精度を高めるには他の要因も考慮する必要があると思われた.【理学療法学研究としての意義】症候限界まで運動を行うCPX に対して, CS-30 は短時間で終了し,安全で理解しやすい利点がある.また本研究から,CS-30 は低負荷であり,全身持久力(VO2peak)との相関が確認された.CS-30 による全身持久力予測が可能となれば,通所リハビリテーション施設・在宅分野など,測定環境が不十分な施設で有用であると考える.しかし,下肢筋への負担は大きいことから実施後の転倒には十分気をつけなければならない.
3 0 0 0 OA 情報科学の動向
- 著者
- 北川 敏男
- 出版者
- 一般社団法人 電気学会
- 雑誌
- 電氣學會雜誌 (ISSN:00202878)
- 巻号頁・発行日
- vol.89, no.972, pp.1609-1616, 1969-09-01 (Released:2008-11-20)
- 著者
- 下 道国
- 出版者
- 日本保健物理学会
- 雑誌
- 保健物理 (ISSN:03676110)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.369-374, 1984 (Released:2010-02-25)
3 0 0 0 OA 移動データからの生活パタンの抽出
- 著者
- 相薗 敏子
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第11回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.161, 2013 (Released:2013-11-05)
人々は日常生活で鉄道や通信など多様なサービスを利用しており,それによって社会インフラ上には交通系ICカードや携帯電話の利用履歴,あるいはPOSデータなど膨大なデータが日々生成・蓄積されている。我々は,社会インフラ上のシステムの全体最適化や顧客サービスの満足度向上を目的として,これらデータを人々の生活履歴のデータと捉えて生活のパタンや行動特性を抽出・活用する研究を行っている。本稿では,鉄道の移動データから人々の生活パタンを抽出する手法および鉄道移動データによる実験結果について述べる。
3 0 0 0 OA 領事裁判と明治初年の日本
- 著者
- 福島 小夜子
- 出版者
- 一般社団法人 日本オリエント学会
- 雑誌
- オリエント (ISSN:00305219)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.2, pp.99-116, 1980 (Released:2010-03-12)
Treaties, concluded by Japan for the first time with foreign countries during the years of 1854-58, were unequal treaties including such stipulations as consular jurisdiction, tariff rate by agreement and unilateral most favored-nation clause.One of the most important tasks of Meiji new government was to negotiate with each country for the revision of these unequal treaties. For this accomplishment, the government modernized the Japanese legal system. Japanese codification was based chiefly up on the model of French and German laws, under the leadership of foreign advisers, such as Dr. Boissonade. On the other hand many practical jedges came into contact with foreign laws especially English law by going through the consular courts. And, during the process of negotiation Japan had known several Middle East legal institutions. For instance, at Constantinople, Egyptian Foreign Minister Nubar Pasha gaved useful advice about mixed court to a member of Iwakura Mission in 1873. And Egyptian rules for mixed courts were translated into Japanese in 1874. At the same time Japanese jurists asked for Dr. Boissonacle's lectures concerning the history of consular jurisdiction and Islamic law.When Japan demanded the revision of the treaty to each country, Great Britain made decision to set up a mixed court for Japan as like Egypt. The Conference for the Revision of the Treaty was held in 1886, and “Draft of the Treaty for Jurisdiction” was proposed by Great Britain and Germany, which asked for Japan to adopt foreign judges. In those days the movement against the Revision of the Treaties arose in all over Japan. At that time Dr. Boissonade's opinion was known to Japanese, and it made the movement more violent. He insisted that the adoption of foreign judges by an independent state meant a loss of independence of its judicial power, and would lead subsequently to the national independence. Japanese government could not help postponing the negotiation for the revision of the treaty by the time when the codification had been concluded. Japan had strived for the Europeanized legislation, therefore the research on Egyptian or Islamic laws were discontinued. As Japanese constitution was promulgated in 1890 and many laws followed it, Japan assumed the form of a modern state. Thus, consular courts in Japan were abolished in 1899.
3 0 0 0 OA 理学療法士のアイデンティティ
- 著者
- 福井 勉
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.3(第51回日本理学療法学術大会 講演集)
- 巻号頁・発行日
- pp.23-26, 2016 (Released:2016-10-20)
- 著者
- Baofeng SU Noboru NOGUCHI
- 出版者
- 日本生物環境工学会
- 雑誌
- Environmental Control in Biology (ISSN:1880554X)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.277-287, 2012 (Released:2012-10-30)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 1 3
The availability of agricultural land use information allows decision makers and managers to establish short-term and to long-term plans for land conservation and sustainable use. The objective of this study was to develop a method for extraction of agricultural land use information based on remote sensing imagery. By combining particle swarm optimization (PSO), k-means clustering algorithm and minimum distance classifier, a PSO-k-means-based minimum distance classifier for agricultural land use classification was developed. Crop planting information was collected and divided into five classes: water bodies, paddy fields, bean fields, wheat fields and others (windbreak, roads, rare areas, and buildings, etc.). K-means, a widely used algorithm in pattern recognition for unsupervised classification, became a part of supervised classification by using PSO to find the optimal initial position vectors in a training sample pretreatment process. The optimal cluster of each subclass was finally used for minimum distance classification. The results obtained from Miyajimanuma wetland land use information extraction showed that merely using a small feature space composed of the first three principal components of a SPOT 5 image enabled classification accuracy of 93%.
3 0 0 0 OA 水産科学の分野で活躍する女性たち 9~海洋研究を通じて垣間見た世界~
- 著者
- 安田 仁奈
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.77, no.5, pp.950-950, 2011 (Released:2011-10-11)
3 0 0 0 OA 人間の感性に基づく動物型ロボットのための4脚歩容生成
- 著者
- 鈴木 秀和 西 仁司 瀧 晃司
- 出版者
- 日本知能情報ファジィ学会
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.653-662, 2009-10-15 (Released:2010-01-12)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1
近年,AIBOやParo等に代表される動物型ロボットが話題を集めており,その愛らしい仕草によるエンターテインメント効果のみならず,ロボットセラピーにおけるヒーリング効果が注目を集めている.ヒーリング効果への影響を考えた場合,ロボットが動物らしく行動することが重要であるが,実環境では複雑な動的干渉の影響を受けるため,歩行等の複雑な行動を動物らしく実行することは難しい.そこで本報告では,人が「動物らしい」と感じる4脚歩行ロボットのための歩容生成を目標に,AIBOを用いた地面での動物的な歩容の生成を試みる.脚式ロボットの歩容生成が多次元時系列空間における軌跡の最適化問題であることに着目し,複合特徴領域から成る最適歩容領域への到達方法として,特徴群を1つずつ最適化して辿る手法を提案する.具体的には,動物の歩容に基づいた基本形状とGAによる中間軌道の最適化により,効率よく推進力を発生できる単脚軌道の生成を4脚歩容生成の導入として行う.生成された単脚軌道の連携のために動物学における歩容分類を適用し,人間が動物らしいと感じる感性を取り入れるためにデューティ比と周期を変えたアンケートを実施した.さらに,アンケート結果より得た動物的な歩容に対し,GAを用いた地面での適応学習を行うことにより,人が動物らしいと感じる歩容形態を維持したまま効率よく前進できる歩容の実現を試みる.