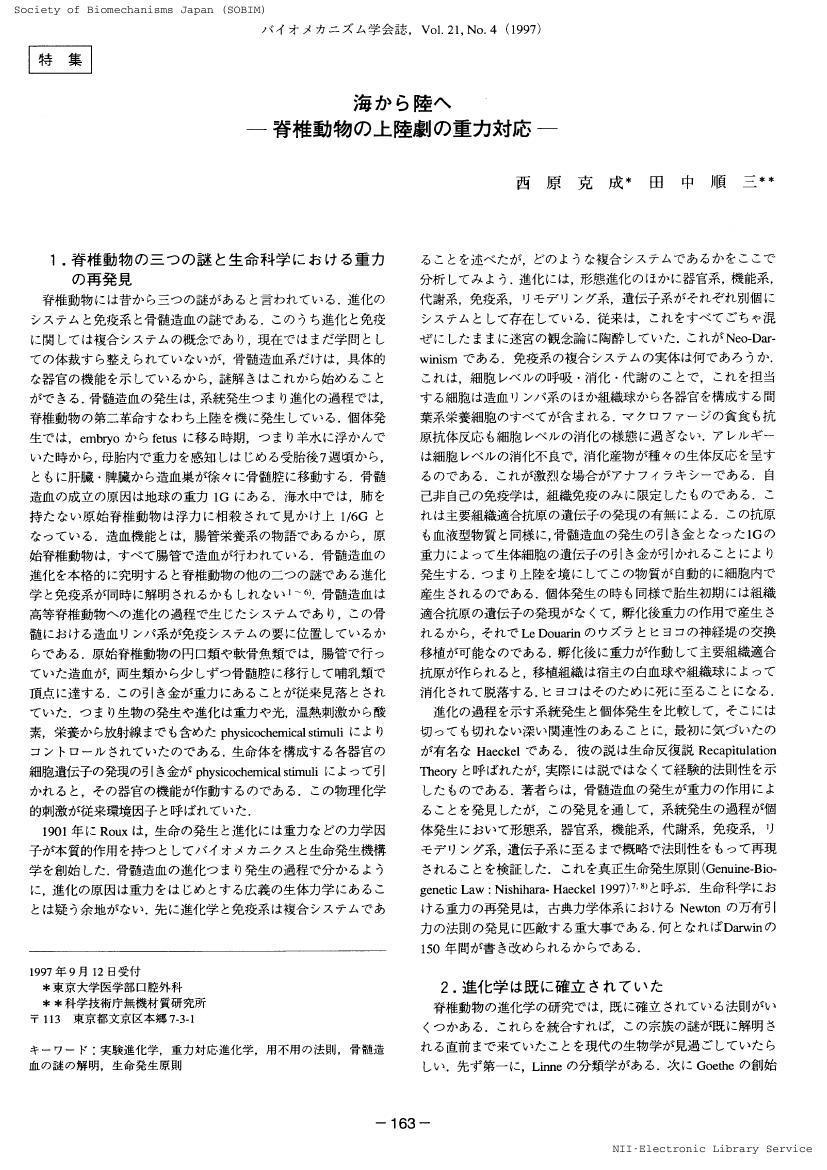2 0 0 0 OA 350. 他動的ストレッチングの施行時間について
- 著者
- 田中 敦 寺西 利生 岡西 哲夫 土肥 信之 川口 浩太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.21 Suppl. No.2(第29回日本理学療法士学会誌 第21巻学会特別号 No.2)
- 巻号頁・発行日
- pp.350, 1994-04-01 (Released:2017-07-24)
2 0 0 0 OA 浜岡原子力発電所1号機のコンクリート工事
- 著者
- 堀内 稔 杉原 一雄 岩沢 二郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.8, pp.11-20, 1975-08-15 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 1
- 被引用文献数
- 2 3
2 0 0 0 OA 小特集 社会学におけるゲーム理論の新展開
- 著者
- 大浦 宏邦
- 出版者
- 数理社会学会
- 雑誌
- 理論と方法 (ISSN:09131442)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.277-280, 2018 (Released:2019-09-28)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA 価値規範と生活様式
- 著者
- 佐々木 洋成
- 出版者
- 関東社会学会
- 雑誌
- 年報社会学論集 (ISSN:09194363)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.13, pp.239-251, 2000-06-05 (Released:2010-04-21)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
In this paper, we discuss youth with low educational attainment who are second-generation manual laborers. A case study was undertaken to explore the reasons they chose such jobs. The author worked for a transport company where he observed and interviewed six young men between the ages of 16 and 21. Their choice to enter a manual-labor job was seen to be influenced by the following factors: first, the value norm that gives importance to freedom and independence in their teenage years, and second, the relative comfort and ease of the life-style associated with manual labor when compared with jobs requiring higher levels of education.
- 著者
- 岩本 佳子
- 出版者
- Japan Association for Middle East Studies (JAMES)
- 雑誌
- 日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.69-95, 2017-01-15 (Released:2018-06-01)
本稿は、枢機勅令簿やワクフ総局所蔵台帳といった、遊牧民の定住化に関して発布された命令の記録を含むオスマン語公文書史料を基本史料として、17世紀末から18世紀初頭にかけてのクルド、テュルク系遊牧民のシリア北部、特にラッカ地域への大規模定住化政策を分析した研究である。 17世紀末の軍事および財政改革の中で、クルドやテュルク系遊牧民は、ラッカ北部地域を中心とした地域の農地開発のために定住化させられるようになった。その背景には、この時期に、遊牧民の夏営地・冬営地間の季節移動そのものを問題視し、農耕民として定住化させることを是とするように、遊牧民に対する認識が変化したことがあった。この点で、17-18世紀は、オスマン朝における対遊牧民政策の転換点であると見なすことができる。しかしながら、全ての遊牧民が強制的に定住化させられたわけではなく、イスタンブルに位置するウスキュダル地区のヴァーリデ・スルタン・モスクのワクフに属する遊牧民や自発的に定住化した遊牧民が、強制的な定住から免除される事例も存在した。 遊牧民への定住化政策においては、主な定住先はシリア北部、特にラッカ一帯であり、次点がキプロス島であった。また定住地から逃散して叛徒化した諸部族をラッカへ定住化させる、数度にわたって逃散や叛徒化を繰り返した部族に定住化を命じるなど、処罰としての定住化命令という側面も見られた。一度逃散した部族に対しても、以前に定住を命じた土地と同じ場所へ再度の定住することを命令し、命令に従わない部族を武力で制圧するなど、元の命令を実行することに固執する傾向が強くあった。このことは逃散と再定住化というパターンの固定化へとつながっていった。そのため、17世紀末から18世紀にかけて相次いだ遊牧民の定住化令は、遊牧民の逃散や叛徒化による治安の悪化に対する有効な手立てではなく、むしろ、逃散や山賊の固定化をもたらし、さらには、シリア北部のみならずアナトリアにも及ぶ地域の変化の一因にもなりえていたのである。
2 0 0 0 OA 道路整備における保全対策技術~海浜植生の復元技術事例
- 著者
- 桒原 淳 今井 久子 出繩 二郎 櫻井 日出伸
- 出版者
- 応用生態工学会
- 雑誌
- 応用生態工学 (ISSN:13443755)
- 巻号頁・発行日
- pp.21-00003, (Released:2021-09-20)
- 参考文献数
- 16
臨港道路「霞 4 号幹線」の整備では,高松海岸や干潟の多様な機能の保全を目指し,各種の環境保全対策を実施した.これらのうち,整備に伴い撤去した範囲の海浜植生を復元する,全国的にも少ない技術事例を報告する.復元する植生の配置は,整備撤去範囲外に残る海浜植生との連続性や地形条件を考慮して決定した.また,復元に使用する海浜植物は,復元群落の面積と植栽密度から必要数量を算出し,整備撤去範囲外の海浜植生から調達した.また,復元工事の施工時には,施工業者に対し,復元作業手引書に基づいた現地指導を行った.
2 0 0 0 OA エリクソン理論における漸成的発達図式の検討 Virtue概念を基軸に
- 著者
- 鬢櫛 久美子
- 出版者
- 教育哲学会
- 雑誌
- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)
- 巻号頁・発行日
- vol.1992, no.66, pp.15-28, 1992-11-10 (Released:2009-09-04)
- 参考文献数
- 39
The aim of this article is to read and interpret the writings of Erikson as a theory of development. This attempt implies, while filling in some missing points on research on Erikson, to arrive at a comprehensive and new interpretation of Erikson's theory.In this paper, in order to understand Erikson's thought, the method was applied to analyzing his 'Epigenetic Chart' which forms through out the undercurrent of the basis of his theory, and thus to re-read Erikson's writings as development theory.As a result, important concepts are discussed separately which were coined to explain his 'epigenetic chart', and in order to rectify the over-all meaning of development as understood by Erikson, furthermore, in order to rectify the fact that the meaning of sinister terms has been de-emphasized because these terms were loaded with energy, hence difficult to handle, it is my understanding that the concept of virtue should be introduced.When the epigenetic chart is examined with a focus on the concept of virtue, it becomes clear that its terminology and methodology were constantly revised. When I started to examine the virtue concept, the ritualization etc., newly added concepts and terms, while considering the development of Erikson's theory and its relation to education, I reached the conclusion that it can be re-stated as development theory opening up new horizons.
2 0 0 0 OA イノベーションのためのデザインの新機軸 ― 科学技術と社会をつなぐシンセシスの役割 ―
- 著者
- 田浦 俊春 妻屋 彰 山田 香織
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.1, pp.38-55, 2018-06-30 (Released:2018-12-14)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 1 1
本稿では,イノベーションの進む方向性とイノベーションのためのデザインに寄与する創造的思考について論じる。まず,イノベーションは利便性や効率を重視する「量的イノベーション」とライフスタイルや文化の変化をもたらす「質的イノベーション」に区分されるとし,現代社会では質的イノベーションへの転換が必要であることを述べる。次に,イノベーションのためのデザインを,プロダクトを介して科学技術と社会との間を橋渡しすることと捉えた上で,デザインの起因に注目し,それを社会のニーズにおく「ニーズ先導型」,科学技術の探求におく「シーズ先導型」,両者の橋渡しをするプロダクトの構想からはじめる「プロダクト先導型」に区分できることを示す。これらの区分を2軸として戦後日本のイノベーションを対象に事例調査を行った結果,質的イノベーションではプロダクト先導型のデザインが多くみられた。さらに,質的イノベーションに寄与する創造的思考について議論し,ブレンディング型のシンセシスやプロダクトと場の組合せ型のシンセシス,シンセシス型の創造的思考に則ったタイプのメタファ型のシンセシスを用いた創造的思考が効果的であることを述べる。
2 0 0 0 OA ホームレス結核患者の服薬支援と治療成績に関する検討
- 著者
- 松本 健二 小向 潤 笠井 幸 森河内 麻美 吉田 英樹 廣田 理 甲田 伸一 寺川 和彦 下内 昭
- 出版者
- 一般社団法人 日本結核病学会
- 雑誌
- 結核 (ISSN:00229776)
- 巻号頁・発行日
- vol.88, no.9, pp.659-665, 2013 (Released:2016-09-16)
- 参考文献数
- 19
〔目的〕ホームレス結核患者の治療成績に関連する要因と服薬支援の状況について検討した。〔方法〕平成19~21年の大阪市におけるホームレスの結核新登録患者433例を対象とした。治療成績に関連する要因として,入院期間,外来治療予定期間,DOTSの型等を検討した。対照として大阪市における平成19~21年のホームレス以外の肺結核新登録患者3047例を用いた。〔結果〕①治療成功と失敗中断における服薬支援等の状況:治療成功は311例で219例(70.4%)が院内DOTSにて入院のまま治療を終了した。失敗中断は48例で35例(72.9%)は自己退院であった。肺結核患者における失敗中断率はホームレス結核患者が11.0%であり,ホームレス以外の結核患者の6.5%に比べて有意に高かった(P<0.001)。②地域DOTSと治療成績:地域DOTS実施は102例で,週5日以上の服薬確認は66例(64.7%)と最も多くを占めたが,失敗中断は10例(9.8%)であった。入院および外来治療予定期間と治療成績では,入院期間は脱落中断が2.0±1.6カ月,治療成功が4.4±2.5カ月であり,外来治療予定期間は脱落中断が7.9±2.7カ月,治療成功が3.6±2.1カ月であり,入院期間の短い例と外来治療予定期間の長い例で脱落中断が有意に多かった(P<0.01)。〔結論〕ホームレス結核患者の失敗中断率は高く,自己退院によるものが多かった。治療成功例では入院のまま治療を完遂することが多く,地域DOTSにつながった例では週5日以上の服薬確認を行っても失敗中断率は高く,特に入院期間の短い例と外来治療予定期間の長い例では十分な支援が必要と考えられた。
2 0 0 0 OA 炭鉱都市の類型化と都市構造の時系列的変化 福岡県の炭鉱都市を対象として
- 著者
- 牝小路 諒 猪八重 拓郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.814-820, 2020-10-25 (Released:2020-10-25)
- 参考文献数
- 9
炭鉱都市とは石炭産業に関連して栄えた都市で、炭鉱を中心に集落が形成された都市であり、エネルギー革命による石炭産業の撤退以降、人口減少に代表される様々な問題が発生した。しかしながら、石炭産業という一定の産業の下、都市構造が形成されたわけであるが、石炭産業撤退後の変容は一様ではない。そこで本研究では、まず炭鉱都市を人口、産業に関連する指標の変化を価値基準において類型化し、数値的および時系列的にその変容を考察する。また、スペースシンタックス理論を用いて道路網および主要施設の時系列的変化から都市構造の変化を捉えることで、類型化されたパターンと都市構造の関係性を道路網構成の観点から明らかにすることを目的とする。
2 0 0 0 OA サイン音に和音を用いることの効果の検討
- 著者
- 岩宮 眞一郎 中嶋 としえ
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.6, pp.329-335, 2009-12-15 (Released:2010-12-17)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 3 2
メッセージを伝えるサイン音には,音の断続パターンだけでなく,短いメロディや和音などの各種の音楽的表現を用いることも多い.本研究では,サイン音に和音を用いることの可能性を検討するために,各種の三和音表現とサイン音としてのイメージおよびその印象の関係を,評定尺度による評価実験に基づいて検討した.終了感を出すのに,音楽の終止形として用いられている,属和音あるいは下属和音から主和音の進行が利用できることが示唆された.これらは,快適で,明るい印象があり,日常生活で頻繁に使われるサイン音としては適しているであろう.警報感を出すには,短三和音,減三和音がふさわしい.これらの和音は,不快で,暗い印象がある.増三和音は,呼び出し感を出す機能があり,報知感も強い.本研究により,サイン音に和音を用いることで,特定の機能イメージや印象を引き出すのに有効であることが示された.
- 著者
- Yuko Tokudome Keiko Okumura Yoshiko Kumagai Hirohiko Hirano Hunkyung Kim Shiho Morishita Yutaka Watanabe
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.11, pp.524-530, 2017 (Released:2017-10-05)
- 参考文献数
- 32
- 被引用文献数
- 29
Background: Because few Japanese questionnaires assess the elderly's appetite, there is an urgent need to develop an appetite questionnaire with verified reliability, validity, and reproducibility.Methods: We translated and back-translated the Council on Nutrition Appetite Questionnaire (CNAQ), which has eight items, into Japanese (CNAQ-J), as well as the Simplified Nutritional Appetite Questionnaire (SNAQ-J), which includes four CNAQ-J-derived items. Using structural equation modeling, we examined the CNAQ-J structure based on data of 649 Japanese elderly people in 2013, including individuals having a certain degree of cognitive impairment, and we developed the SNAQ for the Japanese elderly (SNAQ-JE) according to an exploratory factor analysis. Confirmatory factor analyses on the appetite questionnaires were conducted to probe fitting to the model. We computed Cronbach's α coefficients and criterion-referenced/-related validity figures examining associations of the three appetite battery scores with body mass index (BMI) values and with nutrition-related questionnaire values. Test–retest reproducibility of appetite tools was scrutinized over an approximately 2-week interval.Results: An exploratory factor analysis demonstrated that the CNAQ-J was constructed of one factor (appetite), yielding the SNAQ-JE, which includes four questions derived from the CNAQ-J. The three appetite instruments showed almost equivalent fitting to the model and reproducibility. The CNAQ-J and SNAQ-JE demonstrated satisfactory reliability and significant criterion-referenced/-related validity values, including BMIs, but the SNAQ-J included a low factor-loading item, exhibited less satisfactory reliability and had a non-significant relationship to BMI.Conclusions: The CNAQ-J and SNAQ-JE may be applied to assess the appetite of Japanese elderly, including persons with some cognitive impairment.
2 0 0 0 OA 姉妹都市提携の変容と展望
- 著者
- 豊田 哲也
- 出版者
- 公立大学法人 国際教養大学 アジア地域研究連携機構
- 雑誌
- 国際教養大学 アジア地域研究連携機構研究紀要 (ISSN:21895554)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.9-22, 2016-03-31 (Released:2018-04-27)
姉妹都市提携は当初は平和運動の一環であったが、戦争体験が遠のくにつれてその目的が文化・教育交流や経済連携へとシフトしてきた。秋田県の自治体の有する22の姉妹都市提携の中では秋田市とウラジオストク市(ロシア)との姉妹都市提携および秋田県と沿海地方(ロシア)との姉妹都市提携が経済連携としての意義を持ちうるが、この2つは例外的なものである。一般に、地方都市が他国の地方都市と経済連携の実を挙げられる状況は限られており、地方都市にとっての姉妹都市提携の意義は文化・教育交流としてのそれが中心になる。目的と手段を明確にしながら、長く続けられる姉妹都市事業を展開していくべきであろう。
- 著者
- Satoru Iwashima Takamichi Ishikawa
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.8, pp.2009-2014, 2012 (Released:2012-07-25)
- 参考文献数
- 30
Background: The ophthalmic artery Doppler waveform (OADW) is thought to correlate with severity of systemic atherosclerosis. The goal of the present study was to evaluate risk of cardiovascular disease (CVD) in newborns small for gestational age (SGA) and appropriate for gestational age (AGA). Methods and Results: A total of 15 SGA and 26 AGA newborns were enrolled in the study. OADW was compared between SGA and AGA groups. The median Doppler maximums of both eyes in the SGA group were significantly smaller than in the AGA group (maximum average velocity (max A) 6.4cm/s vs. 8.3cm/s, P=0.028; maximum end diastolic velocity (max D) 2.2cm/s vs. 3.4cm/s, P=0.003). The maximums of both eyes for the maximum resistivity index (max RI) and maximum pulsatility index (max PI) in the SGA group were significantly greater than in the AGA group (RI, 0.88 vs. 0.82, P=0.005; PI, 2.23 vs. 1.72, P=0.002). When a multiple linear regression analysis of the SGA group with a stepwise procedure was applied to positive variables from 2-sided comparisons, significant correlations were noted for max A and max PI (max A: R2=0.495, β=0.541, P=0.034; max PI: β=-3.318, P=0.012). Conclusions: OADW in SGA newborns may be related to future risk of CVD, which is undetectable in infancy, and can provide information to estimate future cardiovascular health. (Circ J 2012; 76: 2009–2014)
2 0 0 0 OA 攻撃行動尺度の作成と信頼性・妥当性の検討(資料)
- 著者
- 佐藤 寛 高橋 史 杉山 恵一 境 泉洋 嶋田 洋徳
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.33-44, 2007-03-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は、攻撃行動をパーソナリティ変数としてではなく、観察可能な行動として測定する尺度である攻撃行動尺度を作成し、信頼性と妥当性を検討することであった。まず、研究1では大学生372名を対象に調査を実施し、攻撃行動尺度の作成と内的整合性の検討を行った。その結果、「身体的・物理的攻撃」「言語的攻撃」「間接的攻撃」の3因子17項目からなる攻撃行動尺度が作成された。また、攻撃行動尺度はある程度の内的整合性があることが示された。次に、研究IIにおいて、大学生406名を対象に、攻撃行動尺度とAnger Expression Scaleを用いた調査を実施し、攻撃行動尺度の妥当性を検討した。分析の結果、攻撃行動尺度は適切な交差妥当性と構成概念妥当性を有していることが示唆された。最後に、本研究の限界と今後の課題に関する議論が述べられた。
2 0 0 0 OA 重力と進化―真正用不用の法則
- 著者
- 西原 克成
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.48-61, 2000-07-30 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 OA 真正生命発生原則 ―個体発生と系統発生の関連性
- 著者
- 西原 克成
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本顎咬合学会
- 雑誌
- 日本顎咬合学会誌 咬み合わせの科学 (ISSN:13468111)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.495-506, 2000-03-30 (Released:2010-09-09)
- 参考文献数
- 23
2 0 0 0 OA 海から陸へ : 脊椎動物の上陸劇の重力対応(<特集>人類の起源)
- 著者
- 西原 克成 田中 順三
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.163-170, 1997-11-01 (Released:2016-11-01)
- 参考文献数
- 26
2 0 0 0 OA アリアケヒメシラウオの分布と形態
- 著者
- 田北 徹 川口 和宏 増谷 英雄
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.497-503, 1988-02-25 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 7
Distribution of the salangid fish, Neosalanx reganius Wakiya et Takahasi was investigated in the rivers around Ariake Sound which is located in western Kyushu. They were only found in the Chikugo River and the Midori River located about 50km apart from each other and were regarded to be endemic to those rivers. They inhabit the tidal area of the downstream occur-ring mainly in fresh water, although some are found in the waters having low seawater con-centration near the mouth of the rivers. Morphological examination revealed no meristic difference, but some statistically significant differences in the body proportions between the two populations indicating their entire isolation from each other.
2 0 0 0 OA 少量アスピリンの抗血小板療法について 血小板凝集能からの検討
- 著者
- 谷口 直樹 山内 一信 近藤 照夫 横田 充弘 外畑 巌
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.6, pp.463-468, 1981-11-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 10
aspirin は抗血小板薬として従来より各種血栓症の治療に使用されている. 近年 aspirin の大量投与は prostacyclin 合成を阻害し, 血栓生成に作用すると指摘され, その投与量が再検討されつつある. 本研究の目的は aspirin の種々の単回および連日投与における血小板凝集能抑制効果を検討することより, その至適投与量を決定することである. 対象は虚血性心疾患, 弁膜症および大動脈炎症候群などの心疾患患者71名であり, 健常人13名を対照とした. aspirin 1日80, 160, 330, 660および990mg連日投与群における4μM ADP最大凝集率には有意差は認められず, いずれの群の凝集率も aspirin 投与を受けていない健常群のそれに比して低値を示した. aspirin 160mg以上の単回投与では投与後1時間以内に凝集能抑制効果が出現した. 単回投与の凝集能抑制効果持続日数の平均値は330mg投与では4日, 660mgでは5.5日, 1320mgでは6日であった. aspirin による胃腸障害, 出血等の副作用の出現頻度は dose dependent であることを考慮すると, 本薬を長く投与する必要がある場合, 可及的少量が望ましい. ADP凝集抑制効果の観点からは1日量80mgの連日投与または160mgの隔日投与が至適投与法と考えられた.