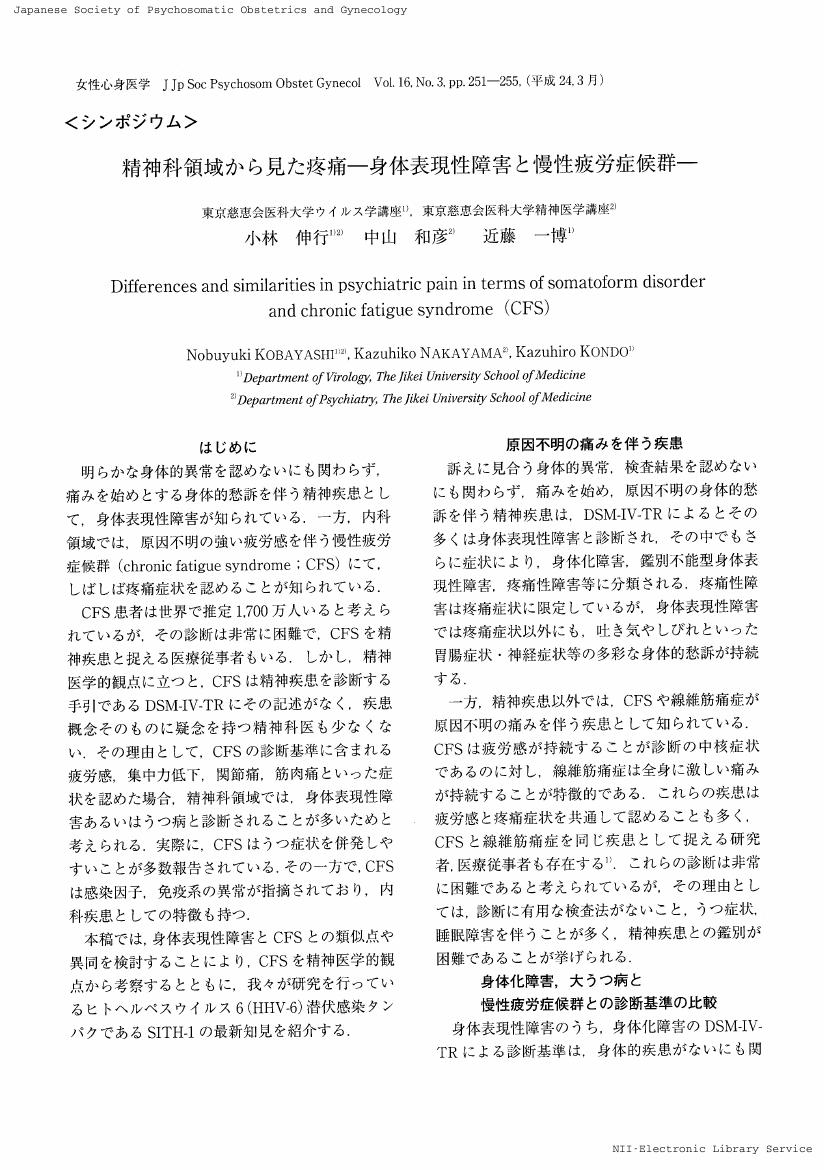2 0 0 0 OA 高齢者の買物環境と生活満足度 ―東京都多摩ニュータウン地域を対象として―
- 著者
- 佐藤 龍一 大江 靖雄
- 出版者
- 地域農林経済学会
- 雑誌
- 農林業問題研究 (ISSN:03888525)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.4, pp.209-214, 2017-12-25 (Released:2018-01-06)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2 1
With the progress of the aging society, how to maintain the daily shopping environment for the elderly has attracted growing attention from a perspective toward life in good health. Thus, this study investigated the life satisfaction of the elderly living in Tama Newtown, Tokyo, which is one of the rapidly aging local communities in urban areas, by focusing on the daily shopping environment. For this purpose, the study applied a two-stage estimation model that first determined the shopping satisfaction and then the life satisfaction of the elderly based on data obtained from a questionnaire survey. The result of the model estimation revealed that shopping satisfaction was positively related to the life satisfaction of the elderly, and that economic factors, infrastructure, and daily life factors are important for the enhancement of their life satisfaction.
- 著者
- 小林 伸行 中山 和彦 近藤 一博
- 出版者
- 一般社団法人 日本女性心身医学会
- 雑誌
- 女性心身医学 (ISSN:13452894)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.251-255, 2012-03-31 (Released:2017-01-26)
2 0 0 0 OA インターネット・アンケートを利用した医学研究 本邦における現状
- 著者
- 康永 秀生 井出 博生 今村 知明 大江 和彦
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.40-50, 2006 (Released:2014-07-08)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 14
アンケート調査の方法として,従来から郵送調査法・面接調査法などが汎用されている。インターネット調査法の医学研究への適用は,その有用性や妥当性についていまだ評価が確立していない。今回,2005年 4 月現在までに報告された,インターネット・アンケートを利用した邦文医学研究論文36編をレビューした。インターネット調査法を用いた原著論文の絶対数は,近年若干の増加傾向を認めるものの依然として少ない。アレルギー疾患(アレルギー性鼻炎,アトピー性皮膚炎,蕁麻疹など)など,青壮年層の患者数が多い疾患を対象とした研究が比較的多い。従来法と比較して,インターネット調査法の利点として,(1)調査者・回答者双方の利便性が高い,(2)データ回収が迅速である,点が挙げられる。欠点として,(1)利用者の年齢層が偏っている,(2)モニター登録という有意抽出法が採用されるため,無作為抽出法と比較して標本誤差が発生しうる,点が挙げられる。しかしながら,近年のインターネットの爆発的な普及拡大によって,利用者の年齢層の偏りは解消されていくことが期待される。高齢者層にもアンケート対象が拡大すれば,より多くの疾病について研究が可能となる。インターネット調査法の利点を考慮すれば,今後は社会医学・臨床医学研究における有力なツールのひとつになりうると考えられる。
2 0 0 0 OA 福祉社会学の課題と方法
- 著者
- 副田 義也
- 出版者
- 福祉社会学会
- 雑誌
- 福祉社会学研究 (ISSN:13493337)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.1, pp.5-29, 2004-05-31 (Released:2012-09-24)
This paper discusses the following three matters.1) Welfare sociology is one of the hyphen sociologies, and is based on general sociology or theoretical sociology.2) Welfare sociology is the science of social welfare as social action by interpretation, or the science of understanding social welfare as the product of a total society by analysis.3) In Japan, welfare sociology was established as late as the beginning of the 21century.
2 0 0 0 OA 副田義也編『内務省の歴史社会学』
- 著者
- 上村 泰裕
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.3, pp.510-511, 2013 (Released:2014-12-31)
2 0 0 0 OA 日本水道生物学誌
- 著者
- 近藤 正義
- 出版者
- 日本水処理生物学会
- 雑誌
- 日本水処理生物学会誌 (ISSN:09106758)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.3-12,19, 1964-06-15 (Released:2010-02-26)
- 著者
- サトウ タツヤ
- 出版者
- 日本青年心理学会
- 雑誌
- 日本青年心理学会大会発表論文集 24 (2016) (ISSN:24324728)
- 巻号頁・発行日
- pp.16-17, 2016 (Released:2017-09-11)
2 0 0 0 OA タイから得られた淡水産大型アカエイの新種, Himantura chaophraya
- 著者
- Supap Monkolprasit Tyson R. Roberts
- 出版者
- The Ichthyological Society of Japan
- 雑誌
- 魚類学雑誌 (ISSN:00215090)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.203-208, 1990-11-30 (Released:2010-06-28)
- 参考文献数
- 7
アカエイ科の新種, Himantura chaophraya, をタイのチャオプラヤ川から採集した標本に基づいて記載した.本種は500kg以上になるといわれ, 主に淡水域に分布する種グループに属して, 大型になること, 吻端が著しく突出すること, 幅広くて薄い円型の体盤をもっこと, 眼が小さいこと, 体盤の腹面が黒くふちどられること, 尾部基底部が非常に狭いこと, 胸鰭条数が158-164であること, 腸のらせん弁の回転数が21であることにより特徴づけられる.この種グループはインド, ボルネオ, ニューギニアから知られ, またメコン川にも出現するようであるが, 博物館収蔵標本としてはチャオプラヤ川と東ボルネオ (インドネシアのカリマンタン) にあるマハカム川流域からのものが現存するだけである.
2 0 0 0 OA 好酸球性食道炎の診断と治療の進歩
- 著者
- 阿部 靖彦 佐々木 悠 上野 義之
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.225-242, 2019 (Released:2019-03-20)
- 参考文献数
- 104
- 被引用文献数
- 1
好酸球性食道炎は主に食物抗原に対するIgE非依存型(遅延型)アレルギー反応によって好酸球浸潤を主体とする炎症が食道上皮を中心に発生,慢性的に持続し,食道運動障害や食道狭窄をきたす疾患である.元々は小児領域の疾患と考えられていたが,近年,とくに欧米において成人のつかえ感,food impactionの主な原因として注目されている.好酸球浸潤は食道に限局し,好酸球性胃腸炎とは独立した疾患単位として取扱われる.診断は自覚症状と組織学的に有意な好酸球浸潤を証明することが基本となり,内視鏡検査で縦走溝,白色滲出物,輪状溝などの特徴的な所見を認識しつつ,生検を行うことが必要となる.治療においては,原因食物の特定と除去食の有用性が確認されているが,その実施には極めて高度な医学的管理を要するため適応は限定され,薬物治療が主体となる.第一選択はPPI投与,無効な場合はステロイド食道局所(嚥下)治療が推奨されている.本邦では欧米と比較し症状や所見が強い典型例は少ないが,近年のアレルギー疾患の増加とともに今後増加してくる可能性がある.厚生労働省の指定難病としても告示されており,その病態や診断,治療について理解しておく必要がある.
- 著者
- 中村 統太 富田 裕介
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 大学の物理教育 (ISSN:1340993X)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.30-33, 2016-03-15 (Released:2020-03-26)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 回復期リハビリテーション目的の入院脳卒中患者における転倒,転落事故とADL
- 著者
- 鈴木 亨 園田 茂 才藤 栄一 村田 元徳 清水 康裕 三沢 佳代
- 出版者
- 社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- リハビリテーション医学 (ISSN:0034351X)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.180-185, 2006 (Released:2006-05-01)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 8 5
回復期リハビリテーション目的で88床のリハビリテーション病棟に入院した脳卒中患者の転倒の現状とADLの変化について検討した.脳卒中患者256名を対象に,転倒の有無,回数,場所,転倒までの期間,時間帯,ADL状況を調査した.ADLはFIMにて入退院時に評価した.256名のうち121名で延べ273回の転倒事故があった.病室とトイレで229件の転倒があり,入院から4週以内の転倒は147件,朝6時から10時までと夕方4時から8時までで129件であった.入院時のFIM車椅子移乗の自立割合は転倒なし群で58.5%,転倒1回群で30.5%,複数転倒群で15.9%であった.入院時に運動合計が38点以下でかつ認知合計が19点以下の36例中,24名が2回以上の転倒を経験したが,運動合計65点以上,認知合計20点以上の者94名中73例が転倒しなかった.運動,認知とも低下している脳卒中患者では転倒を繰り返す危険性が高かった.このような患者では朝夕を中心とした注意深い観察が必要であろう.
2 0 0 0 OA 高度復元ばね特性の非線形解析 (釣竿の大たわみ変形)
- 著者
- 大槻 敦巳 竹内 稔朗
- 出版者
- 日本ばね学会
- 雑誌
- ばね論文集 (ISSN:03856917)
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.64, pp.15-21, 2019-03-31 (Released:2019-10-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
In recent years, leisure activities, such as tennis, golf, skiing, fishing, etc. are very popular. The performance of various instruments used in such leisure activities is also greatly improved. Scientific analysis on the function of such instruments is essential in order to develop practical instruments in the field of sports-leisure. Various experiential studies that clarify the characteristics of fishing rods have been published. However, there are very few scientific studies about fishing rods in the field of the so-called sports-leisure. This study deals with large deformation of fishing rods that would be useful in the development of the characteristic design of fishing rods. In this report, based on the nonlinear large deformation theory, new fundamental equations are introduced for thin, straight tapered fishing rods with a circular cross-section under concentrated loads at the free end. As a result, it is found that the large deformations of fishing rods can be described by nondimensional load parameters, the ratio of rod diameter at end and bottom, and supporting angles. Furthermore, the experimental verification of this analysis is carried out using a flexible rod acquired in the market. The theoretically predicted results are in fairly good agreement with the experimental data. Consequently, the new deformation theory is proved to be of practical use.
2 0 0 0 OA 食材の物性に及ぼす影響から見た市販とろみ調整食品の分類
- 著者
- 中村 愛美 吉田 智 西郊 靖子 林 静子 鈴木 靖志
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本栄養改善学会
- 雑誌
- 栄養学雑誌 (ISSN:00215147)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.1, pp.59-70, 2012 (Released:2012-02-27)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 8 8
【目的】デンプン系,グアーガム系,キサンタンガム系およびその他の各種市販とろみ調整食品が緑茶,牛乳,オレンジジュースおよび味噌汁に与える影響を物性面から解析し,性能に基づくとろみ調整食品の分類を行うことを目的とした。【方法】15種類のとろみ調整食品を4種類の食材に溶解して調製した各種とろみ液の粘度およびテクスチャーを測定し,とろみ調整食品の機能性を反映する指標として,粘度力価,添加時および安定時粘度ばらつき,初期粘度発現率および付着性を算出した。さらにこれら5つの指標を用いて主成分分析およびクラスター分析を行った。【結果】粘度力価は4種の食材すべてについてグアーガム系が大きかった。添加時および安定時の粘度のばらつきはとろみ調整食品の種類と食材の組合せによって傾向が異なった。初期粘度発現率は食材によって特徴があり,緑茶ではキサンタンガム系が,オレンジジュースではデンプン系が高い値を示した。付着性は4種の食材すべてについてデンプン系が大きかった。5つの指標を用いて食材別に主成分分析を行なうと,とろみ成分による分類とは異なる分布を示した。一方,全食材の5つの指標を説明変数にとり,クラスター分析を行った結果,とろみ成分に応じたクラスターが形成された。【結論】市販とろみ調整食品が食材の物性に及ぼす影響をもとに分類を行なうと,各とろみ剤の特徴が食材の種類によって異なることが明らかとなった。したがって,とろみを付与する食材や目的に応じて適切な製品を選択することが重要である。
- 著者
- 南郷 栄秀 田中 雄二郎
- 出版者
- Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
- 雑誌
- Journal of Medical and Dental Sciences (ISSN:13428810)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.109-118, 2010 (Released:2016-09-26)
- 参考文献数
- 30
BACKGROUND: The effect of multidisciplinary education on clinical decision making by medical students is not well known. METHODS: Twenty of fourth, fifth or sixth year medical students were randomly assigned to multidisciplinary groups (MultiG, n = 7) with two medical, pharmacy and nursing students or medical student groups (MedG, n = 10) with six medical students only and given a two-day PBL program using evidence-based medicine (EBM) methodology. The main outcome measure is clinical decision making by medical students for the case, measured by a 100 mm visual analog scale (VAS). Additional patient information requested and self-evaluation of the PBL program were also measured. RESULTS: Correct answers to assess clinical epidemiology knowledge increased significantly in both groups (4.1 to 9.9 points in MultiG, p < 0.001: 3.6 to 9.7 points in MedG, p = 0.002), while scores at baseline and post-program were not significantly different. The number of additional patient information cards requested was not significantly different (p = 0.10). After the program, the VAS for clinical decision making was significantly different (54 mm and 89 mm, p = 0.013), although preprogram values for both groups were similar. CONCLUSION: Pharmacy and nursing students may have potential to change the clinical decision making by medical students.
- 著者
- 平野 明日香 加藤 正樹 藤村 健太 早川 美和子 加賀谷 斉 向野 雅彦 才藤 栄一
- 出版者
- 公益社団法人日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学 (ISSN:02893770)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.3, pp.255-262, 2016 (Released:2016-06-20)
- 参考文献数
- 18
- 被引用文献数
- 2
【目的】急性期病院では高齢障害者が増加し,リハビリテーションの重要性が高まっている。当院急性期病棟に理学療法士を病棟配置した効果を検討した。【方法】疾患別リハビリテーション実施者を対象とし,病棟配置前の44例を対照群,病棟に専任配置後の79例を専任群,専従配置(ADL維持向上等体制加算算定)後の83 例を専従群とし,当院患者データベースより後方視的に調査した。【結果】専従群は他2 群よりリハビリテーション実施割合が有意に増加,リハビリテーション開始までの日数,在院日数は有意に短縮した。アンケート調査より,病棟医師・看護師は情報共有がしやすい,リハビリテーション専門職は病棟とのパイプ役として期待との回答が多かった。【結論】理学療法士の専従配置は病棟医師・看護師と情報共有を密に行え,治療の効率化が図れると示唆された。
2 0 0 0 OA 造血微小環境と血球増殖・分化
- 著者
- 相澤 信
- 出版者
- 日本大学医学会
- 雑誌
- 日大医学雑誌 (ISSN:00290424)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.3, pp.131-136, 2021-06-01 (Released:2021-08-06)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA ノルウェーの高等教育機関と先住民族教育 ─サーミ大学を事例として─
- 著者
- 田辺 陽子
- 出版者
- 日本国際教育学会
- 雑誌
- 国際教育 (ISSN:09185364)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.49-64, 2017 (Released:2018-12-31)
- 参考文献数
- 22
Sámi are an indigenous people who originally inhabited Sápmi, the traditional Sámi land that cross-borders Norway, Sweden, Finland, and Russia. Today, it is estimated that approximately 40,000–60,000 Sámi live in Norway (roughly 1% of the total Norwegian population); 20,000 live in Sweden; 7,500 in Finland; and 2,000 in Russia (Sollbakk & Varsi, 2014). During the post-war period, Norway’s welfare state steadily expanded, and the 1950s and 60s witnessed economic prosperity and national development. However, as a tradeoff for modernisation, “Sáminess” was considered unfavourable, and the Sámi people were forced to assimilate into Norwegian society. Against the backdrop of this Norwegianization policy, Sámi peoples—particularly the young, educated Sámi—started to engage in political activities. Among these activities, the damming of the Alta-Kautokeino River in the 1970s was a turning point in the Sámi rights movement. It is noteworthy that the Sámi restored their inherent rights by the end of 1980s and have since been enjoying a relatively high level of self-determination in areas such as education, culture, language and traditional livelihood. In 1988 the Norwegian government amended its constitution, and in October of 1989 it opened the Sámi Parliament of Norway. The year 1989 also marked the establishment of Sámi University College (or Sámi allaskuvla in Sámi) in Kautokeino. It is Europe’s first and only indigenous higher-education institution. The SUC has three departments: linguistics, social science, and Duodji and teacher education. It offers programmes at the bachelor, masters, and doctoral levels, and their unique programmes attract not only Sámi students from Sápmi, but also non-Sámi people from all around the world. However, the total pool of applicants is small, and the university struggles to tackle particular challenges that are unique to them as an indigenous institution. The purpose of this research paper is twofold: (1) to review current Sámi research and education in Norway’s higher-education sector, and (2) to report characteristics and challenges of the educational programmes provided at Sámi University College (SUC) as a case study. In the first section, this reseach examines indigenous education programmes and higher education in Norway by referring to Norwegian government reports, statistics, and newspaper articles. The next section focuses on current issues at SUC, including programmes, student statistics, and other challenges. This research paper should be considered a work-in-progress report. However, considering the limited number of articles on Norway’s higher educaiton available in Japan, it will offer new insights on the progressive, rights-oriented approach of Sámi education. In that sense, the significance of this research lies in the light it sheds on the relatively unknown areas of indigenous education and higher education institutions in Norway.
2 0 0 0 OA 濃硫酸の関与する反応の化学反応式についての一考察
- 著者
- 大川 忠
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.180-181, 1998-03-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 1
2 0 0 0 OA 1.医療におけるAI活用とICD-11導入による展望
- 著者
- 今井 健
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.242-247, 2019-07-25 (Released:2019-07-31)
- 参考文献数
- 8
医療におけるAI技術応用研究の歴史は古いが,近年では深層学習を始めとした機械学習の応用が盛んに行われており,医用画像の解析を始めとして成果を上げつつある.今後さらなるAI技術の発展のためには,学習に必要なきめ細やかで質の高い保健医療データの大規模収集が欠かせない.ICD11は従来の疾病分類体系にとどまらず,より詳細な病態の記述や生活機能レベルの評価までを包含し,詳細にコード化できる土壌が整いつつある.今後我が国でのICD11導入に向け,これを適切に活用しAI発展のための良質なビッグデータを生み出す仕組みづくりの議論が必要である.
2 0 0 0 OA 組織状大豆たん白食品の歩み
- 著者
- 菊池 三郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 調理科学 (ISSN:09105360)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.308-318, 1987-12-20 (Released:2013-04-26)