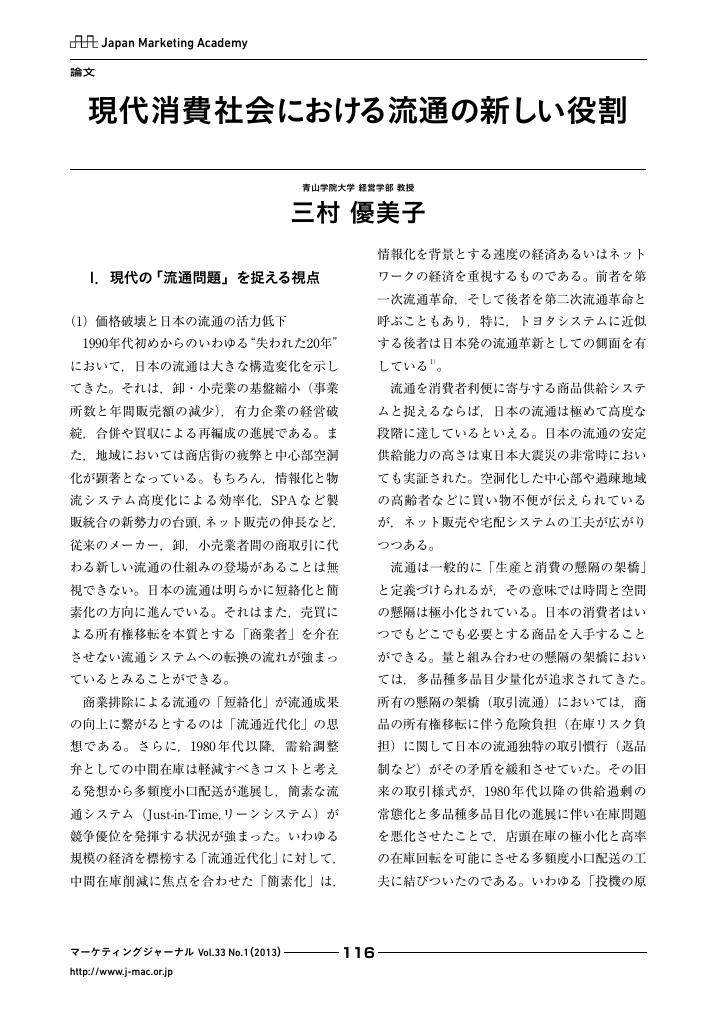2 0 0 0 OA 情報処理スタイルが不思議現象の信じやすさに及ぼす影響
- 著者
- 唐沢 かおり 月元 敬
- 出版者
- 人間環境学研究会
- 雑誌
- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.1-5, 2010 (Released:2010-06-30)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 2
A survey study was conducted to examine the effect of the information processing styles (rational processing vs. intuitive processing; Epstein, 1994) on the beliefs toward paranormal phenomena. Five-hundred and fifty Japanese citizens who reside in the metropolitan area in Japan were randomly selected and received the questionnaire, and 116 citizens responded. The information processing style was measured with the short version of Rational and Intuitive Information-Processing Style Inventory developed by Naito et al (2004). We also asked the participants to indicate the degree to believe the three kinds of paranormal phenomena; fortune telling ("a horoscope" and "blood type fortune-telling", para-science ("UFO" and "supernatural power", and conventional religion ("gods or Buddha" and "a curse". To examine the effect of the information processing style, we first divided the participants into 4 groups (high-rational and high-intuitive, high-rational and low-intuitive, low-rational and high-intuitive, and low-rational and low-intuitive), and submitted the ratings for the degree to believe the three kind of paranormal phenomena for 2 (high-rational vs. low-rational) x 2 (high-intuitive vs. low-intuitive) ANOVAs. The analyses revealed the significant interaction of rational processing and intuitive processing for fortune telling; the participants who were high-rational and low-intuitive believed the fortune telling less than other. Furthermore, a tendency for the main effect for para-science indicated that those who were high-rational believed para-science more than those who were low-rational. For conventional religion, no effect of information processing style was revealed. The discussion argued that these results were to some extent due to the social functions of three kinds of paranormal phenomena.
2 0 0 0 OA ヒュームにおける心身問題について ―懐疑主義から自然主義へ―
- 著者
- 真船 えり
- 出版者
- 日本イギリス哲学会
- 雑誌
- イギリス哲学研究 (ISSN:03877450)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, pp.5-19, 1998-04-01 (Released:2018-04-25)
This paper aims to clarify some of the intentions of Hume's arguments concerning the mind-body problem in his Treatise of Human Nature, I, iv, 5. It attempts to examine three main things: (1) the features of Hume's arguments compared with those of Locke; (2) Hume's own use of the words, such as ‘notion’, ‘fiction’ or ‘feign’, and ‘imagination’ or ‘fancy’; and (3) Hume's new method of explanation in terms of human nature on the problem concerning a conjunction of mind and body in place. In the course of these examinations, it will be shown that Hume's sceptical arguments suggest a new solution on the problem concerned, and lead to the naturalism, presented in the light of human nature.
2 0 0 0 OA 店舗内における非公式リーダーの発生要因:店員の能力限界に着目して
- 著者
- 犬塚 篤
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.3, pp.75-85, 2020-03-20 (Released:2020-08-13)
- 参考文献数
- 34
集団内において非公式リーダー(公式リーダーよりもリーダーシップ行動が顕著な部下)が生じる状況要因を,国内アパレルチェーン410店舗に勤める1719名の店員への質問票調査により明らかにした.その結果,非公式リーダーの登場を促進・阻害する要因が,構造づくり行動に関しては集団サイズや公式リーダーの課題達成力,配慮行動に関しては公式リーダーや部下の成員理解力にあることが示された.
2 0 0 0 OA 困難に陥った一般病棟看護チームのレジリエンス表出による回復のプロセス
- 著者
- 柏 美智
- 出版者
- 日本精神保健看護学会
- 雑誌
- 日本精神保健看護学会誌 (ISSN:09180621)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.29-39, 2021-06-30 (Released:2021-06-30)
- 参考文献数
- 22
本研究は,困難に陥った一般病棟看護チームのレジリエンス表出による回復のプロセスを記述することを目的とした.看護師経験が6か月以上で,一般病棟に勤務する常勤看護師20名を対象に半構造化面接を行い,修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチの手法に基づき分析した.困難に陥った一般病棟看護チームのレジリエンス表出による回復のプロセスは,【混迷】の中でチームが粘り強く耐えて【模索】し始めることで,看護師個々の相互関係を【醸成】し,さらにチームとして【強化】することで,安心空間の創出という【変容】に至るプロセスをたどったと解釈された.これら5局面において,【醸成】における〔対話の成立〕の有無がその後の【変容】にまでつながる契機となり,チームは相互作用を高めながらレジリエンスを表出して回復すると考察された.このプロセスにおいて,省察の場,つながりを求めること,経験知を蓄積していくことの重要性が示唆された.
- 著者
- 山口 秀二 勝間田 静江
- 出版者
- 公益社団法人 自動車技術会
- 雑誌
- 自動車技術会論文集 (ISSN:02878321)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.5, pp.1275-1280, 2013 (Released:2018-01-25)
- 参考文献数
- 11
交通事故における衝突速度と死亡や重傷の受傷確率の関係を,いくつかの衝突形態毎に解析し例示する.目的はISO26262自動車の機能安全規格に定められた危害度severityを区分する境界速度を設定するための参考データを提供することである.文献調査を実施し,発表されていない衝突形態や条件のデータを主に解析した.解析には,米国のNASS-CDSおよびNASS-PDCSデータと日本のITARDA統計データを用いた.
2 0 0 0 OA 生理・心理学的感情分析の哲学的批判
- 著者
- 斎藤 博
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.3, pp.128-136, 1961-09-30 (Released:2010-01-22)
- 参考文献数
- 25
2 0 0 0 OA 旃陀羅の史的考察(二)(智豊合同教学大会紀要,興教大師850年御遠忌記念号)
- 著者
- 宮坂 宥勝
- 出版者
- 智山勧学会
- 雑誌
- 智山学報 (ISSN:02865661)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.71-87, 1993-12-12 (Released:2017-08-31)
漢訳『摩登伽経』は、経名の通りにマータンガ(matanga)すなわちチャンダーラにまつわる経典として、夙に知られる。本経に登場するマータンガ種族のトゥリシャンク(Trisanku.漢訳、帝勝伽)王は、チャンダーラ出身である。この王を中心とした物語は『ディヴィヤーヴァダーナ』(Divyavadana)、叙事詩『ハリヴァンシャ』(Harivamsa)などにも伝える。階級批判さらには社会的差別の否定がストーリーのなかでどのように展開するかを考察するのが本稿である。前回発表した同題(一)の続篇になる。なお前篇のチャンダーラ観の構成は、次のとおりである。(1)階級批判もしくは社会的差別の対象としての存在。(2)救済譚における存在。(3)出家についての比喩。(4)差別是認または社会的差別さらには蔑視対象。(5)尊格化。(6)その他。
2 0 0 0 OA 新自由主義的な震災復興とコミュニティ戦略
- 著者
- 吉原 直樹
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.10, pp.10_44-10_48, 2013-10-01 (Released:2014-02-07)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 現代消費社会における流通の新しい役割
- 著者
- 三村 優美子
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.116-125, 2013-06-30 (Released:2020-12-18)
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 市販薬の使用における副作用の「罹患性」の自覚を高める保健の授業
2 0 0 0 OA 就労者の心理的ウェルビーイング促進要因
- 著者
- 岩野 卓 樋町 美華 坂野 雄二
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.1, pp.52-63, 2012-08-20 (Released:2013-09-06)
- 参考文献数
- 55
- 被引用文献数
- 2
Psychological wellbeing (PWB) is known to be critical for promoting mental health. However, to date, the exact features resulting in PWB have not been identified. Therefore, the effects of factors promoting PWB suggested in previous studies were compared. Workers (n=447) that were covered different types of work such as medical, industrial, and educational staff, responded to the Psychological Well-Being Scale, the Automatic Thoughts Questionnaire-Revised, Positive and Negative Affect Schedule, Stress Coping Inventory, and the Job Content Questionnaire. Result of the multiple regression analyses and path analyses indicated that positive and negative automatic thoughts that comprised positive thinking and negative thoughts about the self, as well as the decision latitude had significant effects on PWB. Therefore, it is concluded that automatic thoughts and decision latitude are critical for promoting PWB.
2 0 0 0 OA Factors affecting an increase in core body temperature and heat tolerance during hot water immersion
- 著者
- Yuta Masuda Issei Kato Kei Nagashima
- 出版者
- The Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine
- 雑誌
- The Journal of Physical Fitness and Sports Medicine (ISSN:21868131)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.5, pp.243-253, 2021-09-25 (Released:2021-09-16)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
The aim of the present study was to clarify the factors affecting an increase in core body temperature during 40°C water immersion to the subclavian level. Fifteen healthy males were immersed in water for 60 min. Rectal temperature (Trec) and skin temperature (Tsk) at four skin sites were determined. Minute ventilation (VE) was measured, and metabolic rate was determined by indirect calorimetry. Skin blood flow and sweat rate at the forehead were assessed using laser-Doppler flowmetry (%LDFhead) and dew hygrometry (SRhead), respectively. Hot feeling was assessed with a visual analog scale. When Trec reached 39°C or participants reported an extremely hot feeling, the experiment was ceased. Eleven participants were unable to complete the protocol (ten participants due to Trec > 39°C; and one due to excessive hot feeling). Trec increased with immersion period. Mean Tsk was unchanged from 20 min. VE and metabolic rate increased with immersion period. %LDFhead and SRhead increased after immersion and remained unchanged from 15 and 30 min, respectively. Change in Trec from the baseline at 15, 30, and 45 min was correlated to cumulative change in metabolic rate from the baseline at 0-15, 0-30, and 0-45 min. No correlations were observed between change in Trec and cumulative changes in VE, %LDFhead, and SRhead from baseline, hot feeling, body weight and body composition. Water immersion at 40°C induced a large difference in the increase of Trec, in which metabolic responses to heat stress may be involved. The relationship between heat tolerance and change in Trec is different among individuals.
2 0 0 0 OA J-pop : リズムと歌詞の入れ込みルールの変遷
- 著者
- 疇地 希美
- 出版者
- 日本音楽教育学会
- 雑誌
- 音楽教育実践ジャーナル (ISSN:18809901)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.25-31, 2007 (Released:2018-04-11)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 鉱物学雑感
- 著者
- 熊沢 峰夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本鉱物科学会
- 雑誌
- 鉱物学雜誌 (ISSN:04541146)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.73-81, 1983-03-30 (Released:2009-08-11)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 1
A personal view on the current state of mineralogical communities is presented in order to facilitate the expansion of future possibilities.
2 0 0 0 OA マツタケ人工栽培の展望
2 0 0 0 OA 野菜に含まれる硝酸塩は毒か薬か? 還元的NO合成経路の研究小史
- 著者
- 山崎 秀雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.11, pp.665-668, 2019-11-01 (Released:2020-11-01)
- 参考文献数
- 10
2 0 0 0 OA はつもみじの後代にみられる不発酵個体の遺伝
- 著者
- 鳥屋尾 忠之
- 出版者
- Japanese Society of Tea Science and Technology
- 雑誌
- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)
- 巻号頁・発行日
- vol.1970, no.32, pp.10-13, 1970-01-30 (Released:2009-07-31)
- 参考文献数
- 10
紅茶用品種はつもみじとはつもみじの次代との戻し交雑を行ない,クロロホルムテストによって発酵性を調べたところ,四つの組合せで,3:1の分離比で,正常個体と不発酵個体が出現することが確かめられた。この不発酵性が,1個の遺伝子nfで支配されているとすれば,はつもみじはこの遺伝子のヘテロ個体で,その遺伝子型はnf/+であり,不発酵個体はホモ型で,nf/nfの遺伝子型となる。このことから,供試した親品種の範囲の発酵性は,1座位の複対立遺伝子で支配され,nf遣伝子はこれの一突然変異であると推定される。不発酵個体は,クロロホルムテストで全く赤変せず,黄緑色のままであり,ポリフェノールオキシダーゼ活性は,ほぼ完全に失われており,これは発酵性に関する遺伝的閉鎖と思われる。このような,不発酵個体は,いわゆる弱発酵個体とは,明らかに区別ができる。また,不発酵個体は枕崎支場の多数の保存系統の中からは発見されていない。不発酵個体と正常個体の間には,樹勢ではっきりした差異があり,不発酵個体が劣ることが確かめられた。
2 0 0 0 OA 2.JAIWR30周年―女性の人権の新たな課題とは
- 著者
- 林 陽子
- 出版者
- 国際女性の地位協会
- 雑誌
- 国際女性 (ISSN:0916393X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.1, pp.41, 2017 (Released:2020-02-13)
2 0 0 0 OA 神と命 -古代日本民族の言靈信仰について-
- 著者
- 城戸 幡太郎
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.5, pp.644-672, 1928 (Released:2010-07-16)
2 0 0 0 OA 1.長寿の遺伝素因:百寿者研究,高齢者疫学研究から得られた知見より
- 著者
- 赤木 優也 神出 計
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.554-561, 2018-10-25 (Released:2018-12-11)
- 参考文献数
- 34
双子研究により長寿には遺伝素因の寄与率は15~25%と推計されており,長寿の遺伝素因を明らかにするためにこれまで多くの遺伝子解析が行われてきた.長寿に関連する遺伝素因としてAPOE,FOXO3などが報告されてきたのに加え,近年GWASなどの網羅的な遺伝子解析が行われているが,再現性が確認され長寿への関与が強い遺伝子は数少ない.長寿遺伝子と言われているAPOEやFOXO3以外にもこれまでの研究からは,生活習慣病や老年病などの長寿と関連している環境要因の遺伝素因が長寿に関与する可能性が高いと考えられ,今後のさらなる検討が求められる.