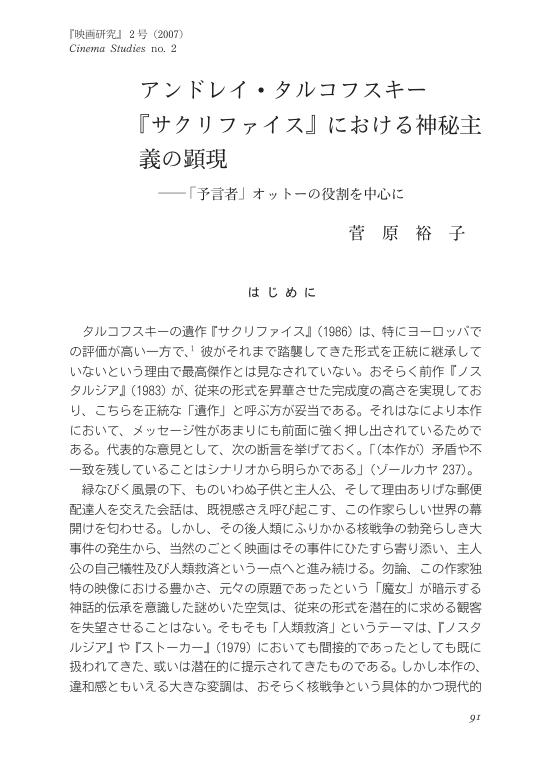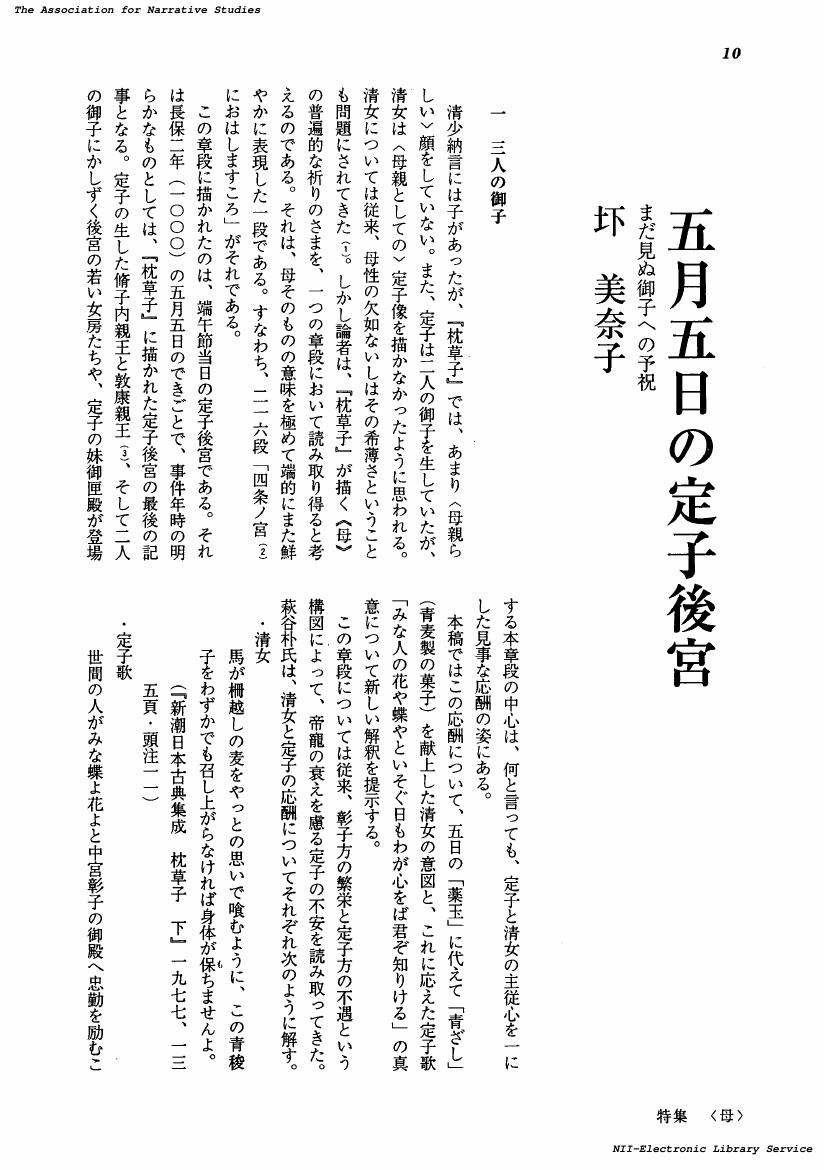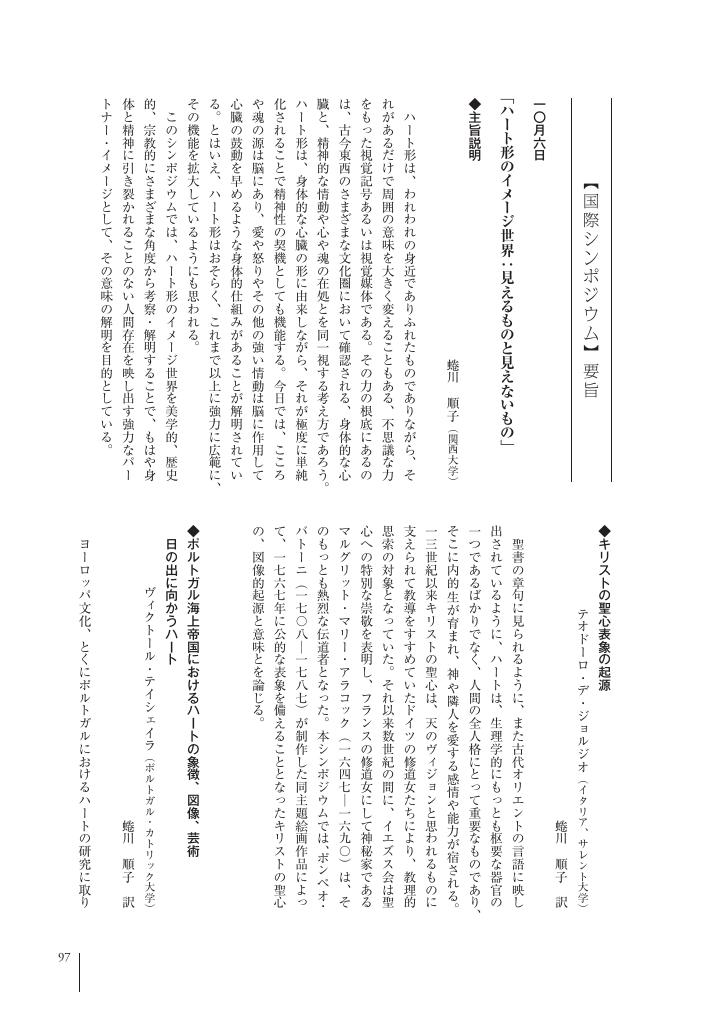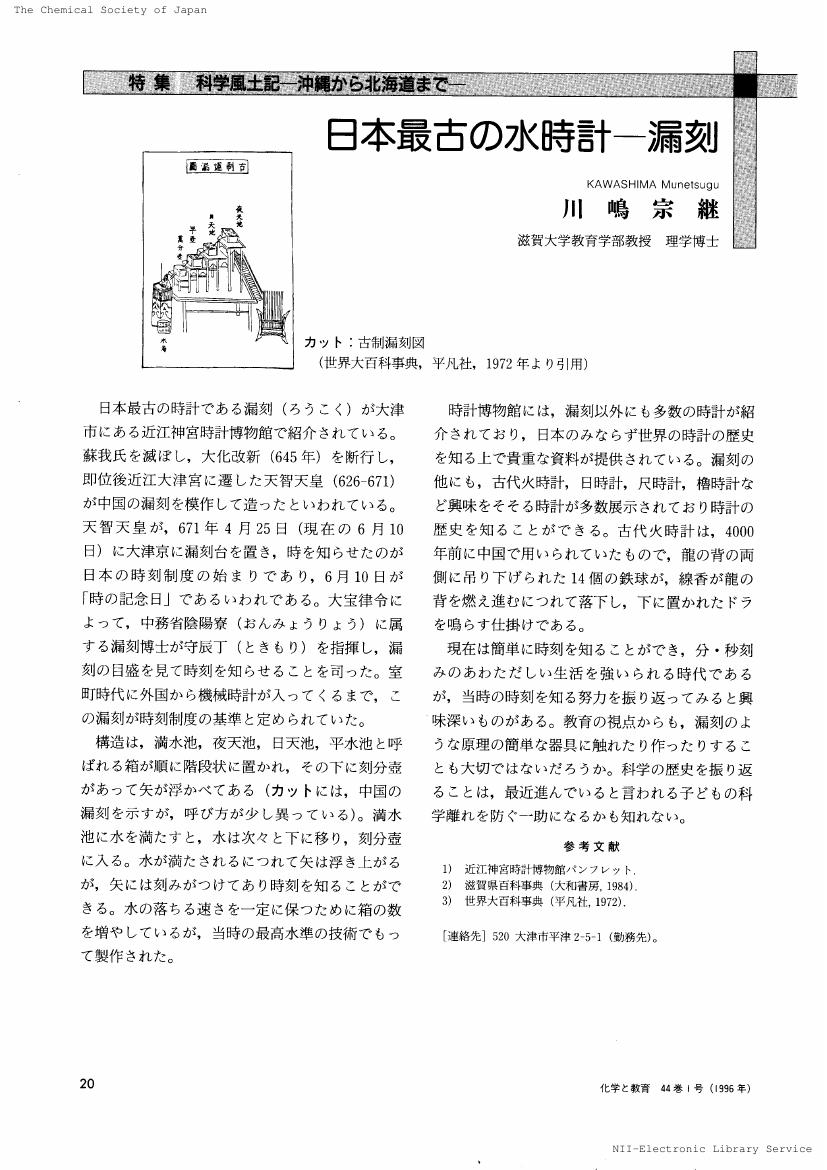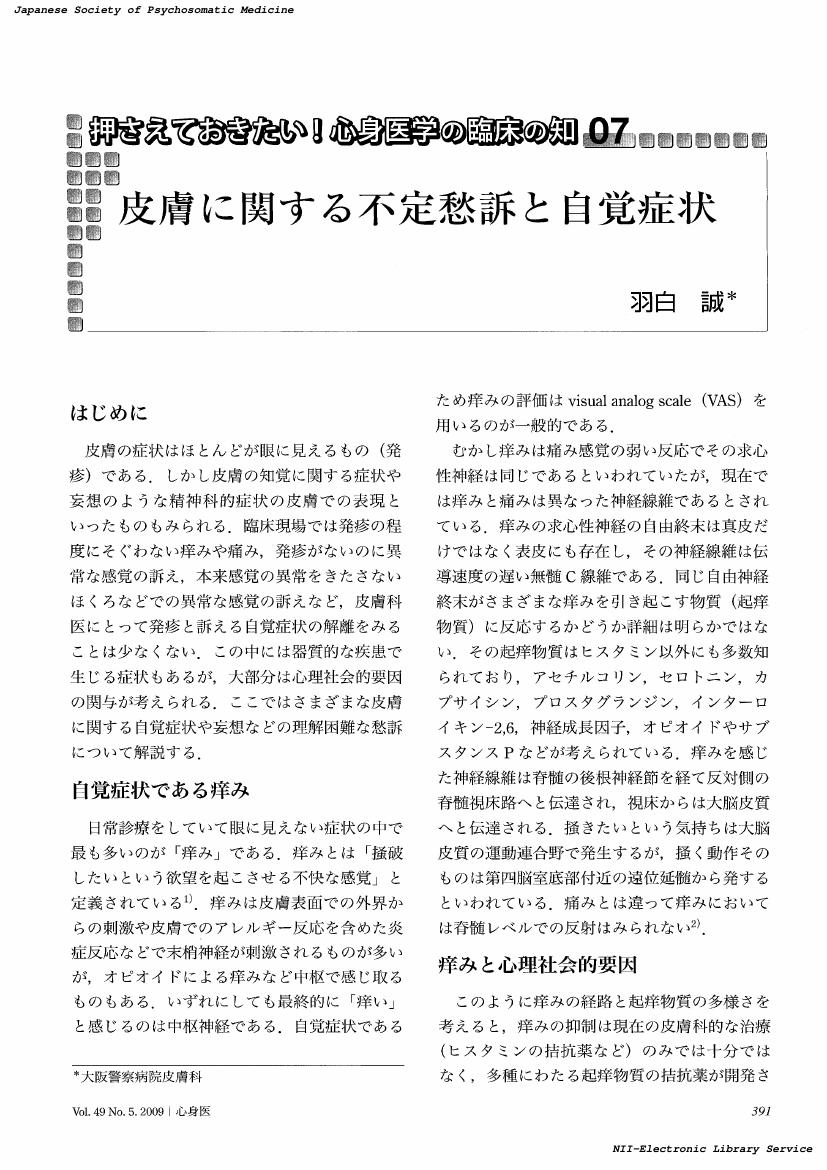2 0 0 0 OA 「随伴性とは縁である」に導かれ : 我々行動分析学の学徒の使命
- 著者
- 三田地 真実
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.31-32, 2011-07-25 (Released:2017-06-28)
2 0 0 0 OA フランクルと滝沢における「過去存在」の思想 : 田辺の<死の哲学>との関連で
- 著者
- 芝田 豊彦
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.1, pp.47-70, 2008-06-30 (Released:2017-07-14)
田辺の<死の哲学>は、他者としての死者を対象としている点で画期的な意義を有する。しかしながら田辺の<死の哲学>の問題点として、<絶対無の働き>と<死復活という行>との不可逆の関係が曖昧なこと、および死者が絶対無にどのような仕方で入れられているのかが不明であること、この二点を指摘できる。フランクルの「過去存在」の思想では、人生における人間のすべての営みが過去存在として永遠に保存される、と主張される。滝沢においては、死者は過去存在として絶対無に入れられており、フランクルとの大きな類似が見出される。滝沢の思惟の根底には常に「神人の原関係」があり、「死ぬ」ということも神人の原関係から、或は神の空間(絶対無)から脱することなどではあり得ない。死者を絶対無における「過去存在」として捉えることによって、死者と死者の記憶は区別され、さらに幽霊現象も視野に入り得るのである。最後に幽霊現象を扱ったベルゲングリューンの珠玉の短編が紹介される。
2 0 0 0 OA 日本語の「認識的モダリティ」の形式の使い分けを目指して その意味分類をめぐって
- 著者
- 康 秋月
- 出版者
- 北海道教育学会
- 雑誌
- 教育学の研究と実践 (ISSN:13498266)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.55-64, 2002 (Released:2019-04-30)
2 0 0 0 OA 競争ダイナミクスの文献サーベイ
- 著者
- 柴田 健一 立本 博文
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- pp.0160726a, (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 65
本稿では競争ダイナミクスの主な先行研究のレビューを実施した。競争ダイナミクスは、企業の競争行動が競合企業のどのような反応を引き出し、それがどうパフォーマンスにつながるのかを実証的に研究する領域である。競争ダイナミクスの歴史はまだ浅いが、近年は多くの研究成果が発表されている。本稿では、競争ダイナミクスの研究の中から主要な論文を抽出し、そこで用いられている具体的な説明変数、被説明変数を整理し、競争ダイナミクスの研究領域を明確にすると同時に、現時点での当該分野における研究の成果について詳しく議論していく。
- 著者
- 菅原 裕子
- 出版者
- 日本映画学会
- 雑誌
- 映画研究 (ISSN:18815324)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.91-108, 2007 (Released:2019-12-07)
- 参考文献数
- 17
2 0 0 0 OA 6.医療資源配分とQALYに関する倫理的側面からの考察
2 0 0 0 OA 五月五日の定子後宮 : まだ見ぬ御子への予祝(<特集>母)
- 著者
- 圷 美奈子
- 出版者
- 物語研究会
- 雑誌
- 物語研究 (ISSN:13481622)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, pp.10-25, 2003-03-31 (Released:2018-03-27)
- 著者
- 菅野 均志 西尾 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.86, no.1, pp.60-65, 2015-02-05 (Released:2017-06-28)
2 0 0 0 OA 国際シンポジウム要旨
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.97, 2018 (Released:2020-03-23)
2 0 0 0 OA 日本最古の水時計 : 漏刻(<特集>科学風土記 : 沖縄から北海道まで)
- 著者
- 川嶋 宗継
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 化学と教育 (ISSN:03862151)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.20, 1996-01-20 (Released:2017-07-11)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 OA 水運儀象台の復元
- 著者
- 土屋 榮夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本時計学会
- 雑誌
- 日本時計学会誌 (ISSN:00290416)
- 巻号頁・発行日
- vol.145, pp.56-70, 1993-06-20 (Released:2017-11-09)
2 0 0 0 OA 1896年ブダペスト建国千年祭博覧会の会場計画について
- 著者
- 水野 貴博
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.654, pp.2029-2037, 2010-08-30 (Released:2010-10-08)
In the 19th century Budapest, two exhibitions were held in the park Városliget. For the first exhibition in 1885, Industry Pavilion was built as the main building at the center of the axial structure of the site, but for the Millennium Exhibition in 1896, History Pavilion, the new main building, should be emphasized more than Industry Pavilion. To solve this problem, a new entrance was planned at the end of the Andrássy Street, a radial street which connected the center of the city and the park, and a promenade circuit was introduced to connect all major pavilions in the site. History Pavilion was built as a complex of imitations of several historic buildings in Hungary and placed picturesquely on an island in a lake. After the exhibition, a square was formed at the entrance and the History Pavilion was rebuilt as a durable building. The adoption of a promenade circuit as the main traffic line and an asymmetric picturesque building as the main pavilion was unique solution at the time, since most of the sites of the world exhibitions in the 19th century were based on classical symmetrical layout.
- 著者
- 平瀬 達哉 井口 茂 中原 和美 松坂 誠應
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.1, pp.1-5, 2011 (Released:2011-03-31)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 4 1
〔目的〕在宅虚弱高齢者に対し異なる運動介入を行い,身体機能に及ぼす影響について経時的な変化から検討することである。〔対象〕65歳以上で要支援1~要介護1の在宅虚弱高齢者51名とした。〔方法〕対象者を事業所別にバランス運動群24名,筋力増強運動群27名に振り分け,週1回1時間の運動を3ヶ月間実施した。身体機能として,開眼片足立ち,椅子起立時間,Timed Up & Go Test(TUG),下肢筋力を評価し,各運動群におけるそれらの経時的変化を解析した。〔結果〕経時的変化では,バランス運動群は下肢筋力が1ヶ月後より有意に増加し,その後全ての身体機能評価が有意に改善されていた。筋力増強運動群では,下肢筋力が2ヶ月後より有意に増加し,その後椅子起立時間,TUGが有意に改善されていた。[結論]各運動群ともに下肢筋力の増加後にパフォーマンス能力が向上していた。また,バランス運動と筋力増強運動では効果の反応が異なることが示された。
2 0 0 0 OA 東海道新幹線における地震対策
- 著者
- 村松 浩成
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.1_37-1_42, 2011 (Released:2011-12-01)
- 参考文献数
- 8
- 被引用文献数
- 1 2
- 著者
- 佐藤 智明
- 出版者
- 日本認知心理学会
- 雑誌
- 日本認知心理学会発表論文集 日本認知心理学会第7回大会
- 巻号頁・発行日
- pp.29, 2009 (Released:2009-12-18)
エントロピーの概念は分かりにくい概念のひとつである.そのため,熱力学の教育においてその概念をどのように表現するかということは非常に重要である.本報では,抽象的なエントロピー概念を説明する際に最も重要である言語表現に着目した.ここでは,これまで一般的に用いられてきたエントロピー概念を表す言語表現について調査し,特に熱力学的エントロピー概念を表現する場合の言語表現の問題点について検討した.更に,実際の分子運動を表現した粒子のアニメーションを制作し,運動範囲(体積)や粒子速度(温度)の異なる8種類の映像を被験者に見せ,それぞれ粒子の運動から計算によって得られるエントロピー値による順位と代表的な数種類の言語表現によって順位づけされた映像の順位との相関性について検討した.その結果,「拡散の度合い」と「捕まえにくさの度合い」という言語表現がエントロピー値と相関が高いことが分かった.
2 0 0 0 OA ゴンズイ・ヒメジにおけるヒゲの味覚系
- 著者
- 清原 貞夫 塚原 潤三
- 出版者
- 日本比較生理生化学会
- 雑誌
- 比較生理生化学 (ISSN:09163786)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.1, pp.18-30, 2003-03-31 (Released:2011-08-04)
- 参考文献数
- 59
2 0 0 0 OA サルトルにおける真理のラディカリズム ─「民衆法廷」という実践的モラル─
- 著者
- 南 コニー
- 出版者
- 日本フランス語フランス文学会関西支部
- 雑誌
- 関西フランス語フランス文学 (ISSN:24331864)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.63-74, 2020-03-31 (Released:2020-07-10)
Le radicalisme de la vérité chez Sartre ̶ Le tribunal populaire, lieu de la morale pratique ̶ Le Russell Tribunal, également appelé Tribunal Russell-Sartre, s’est réuni à Stockholm, à Tokyo et à Roskilde en 1967. Cette institution n’avait pas de précédent : tribunal sans juges et sans pouvoir, établi par Russell et Sartre avec le concours de Vladimir Dedijer et Simone de Beauvoir, ainsi que d’une délégation japonaise, afin de révéler au monde les crimes de guerre commis pendant la guerre du Viêt-nam par les États-Unis, de peur que malgré leur atrocité sans pareille, ils ne soient étouffés par les dirigeants politiques. Une double tâche occupe ses animateurs : établir un procès-verbal sur lequel puisse s’appuyer une dénonciation virulente de la politique étrangère américaine, mais aussi informer l’opinion que le procès en cours d’instruction est en destiné à accoucher d’une vérité. C’est le sens de cette phrase de Sartre dans son discours inaugural à Stockholm : « cette session est une entreprise commune dont il faut que le terme final soit selon le mot d’un philosophe : une vérité devenue ». La divulgation de cette vérité, dont il emprunte le concept à Kierkegaard, doit rompre le silence en le condamnant pour ce qu’il est : un crime, fruit de l’ignorance du grand public, non moins cruel que ceux qui sont perpétrés sur les champs de bataille du Viêtnam. Telle est la mission qu’assigne au philosophe sa définition de lui-même comme « universel singulier ; totalisé et là même, universalisé par son époque ».
2 0 0 0 OA 皮膚に関する不定愁訴と自覚症状(押さえておきたい!心身医学の臨床の知07)
- 著者
- 羽白 誠
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.5, pp.391-395, 2009-05-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 7
2 0 0 0 OA 慢性疼痛下におけるモルヒネ依存の修飾とその機序
- 著者
- 鈴木 勉
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.121, no.12, pp.909-914, 2001-12-01 (Released:2002-09-27)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 10 10
Clinical studies have demonstrated that when opiates are used to control cancer pain, psychological dependence and analgesic tolerance are not a major concern. The present study was, therefore, designed to investigate the modulation of rewarding effects of opiates under inflammatory chronic pain in SD rats. Formalin (2.5%, 50 μl) or carrageenan (1%, 100 μl) was injected into the plantar surface of the rat paw. Formalin and carrageenan reduced the paw pressure threshold. The hyperalgesia lasted for 9 to 13 days. Rewarding effect of morphine was evaluated by conditioned place preference paradigm. Morphine produced a significant place preference. This effect was significantly attenuated in inflamed groups as compared with the respective non-inflamed groups. Furthermore, the morphine-induced place preference in the inflamed group gradually recovered to the respective control level as the inflammation healed. On the other hand, we found that κ-opioid receptor agonists markedly inhibit rewarding effect of μ-opioid receptor agonists. Therefore, to elucidate the mechanism of this attenuation, the effects of pretreatment with κ- and δ-opioid receptor antagonists, nor-binaltorphimine (nor-BNI) and naltrindole (NTI), on the development of the morphine-induced place preference under inflammation were examined. Nor-BNI, but not NTI, eliminated the suppression of the morphine-induced place preference in inflamed groups. The morphine-induced increase in dopamine turnover in the limbic forebrain was suppressed under inflammation, and the suppression was abolished by the pretreatment with nor-BNI. These results suggest that endogenous κ-opioid systems may be activated by chronic inflammatory nociception, resulting in the suppression of the development of rewarding effects produced by morphine.
2 0 0 0 OA 量子力学を使った情報処理
- 著者
- 加藤 豪
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.268-276, 2014-05-01 (Released:2020-09-29)