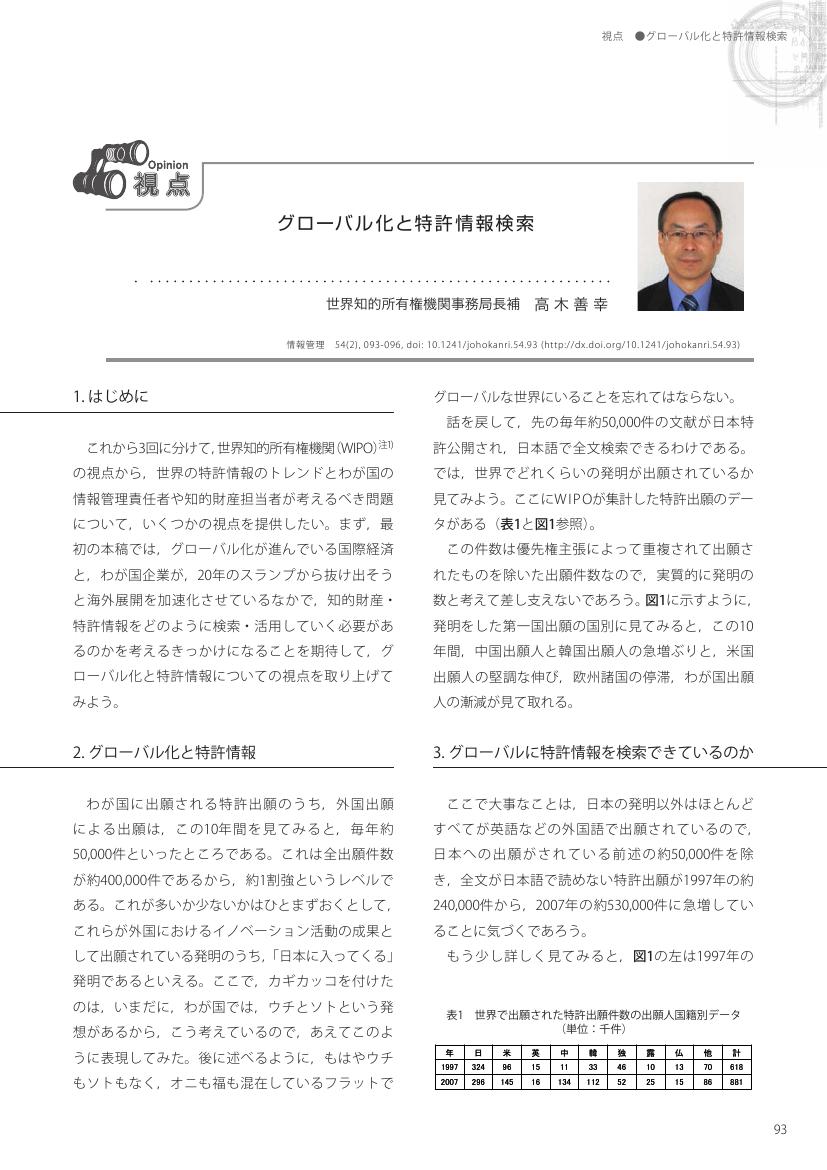1 0 0 0 611 日本刀の振動特性解析(材料力学(4))
- 著者
- 豊東 宣行 臺丸谷 政志 藤木 裕行 塩崎 修
- 出版者
- 一般社団法人日本機械学会
- 雑誌
- 北海道支部講演会講演概要集
- 巻号頁・発行日
- vol.2008, no.47, pp.161-162, 2008-09-27
1 0 0 0 OA 国際的な特許分類調和の動向と五庁共通ハイブリッド分類プロジェクト
- 著者
- 小原 一郎
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.73-78, 2011 (Released:2011-05-01)
- 参考文献数
- 3
- 被引用文献数
- 2 1
2011年に,IPCはフルIPCとなり,コアレベル・アドバンストレベルが統合され,IPCの内容が変更されるとともに,IPC改正の手続きも変更された。このような背景には,三極や五庁を中心に検討されている分類調和プロジェクトを通じたIPCの細分化も無関係ではない。2011年はこの分類調和プロジェクトが三極から五庁にその舞台を本格的に移行することとなっている年でもあり,五庁における分類調和プロジェクトである,共通ハイブリッド分類プロジェクト(CHC)がどのようなものであるのか,およびどのような手続きによって進められているのか,わが国特許庁における検討体制も交え説明をするものである。
1 0 0 0 OA グローバル化と特許情報検索
- 著者
- 高木 善幸
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.93-96, 2011 (Released:2011-05-01)
1 0 0 0 一体感が実感できる身体的コミュニケーションインタフェース
かかわりが実感できるコミュニケーションを実現するためには、身体性を活かす仕組みの導入が不可欠である。本研究では、身体的リズムの引き込みに着目することで、人のコミュニケーション特性に立脚したインタラクションを実現するインタフェースの研究開発を進めている。本年度は、以前から開発を進めてきた、語りかけに対して葉っぱと茎が絶妙のタイミングでうなずき反応する、うなずく草花「ペコッぱ」「花っぱ」の身体的集団引き込みシステムを開発展開し、デモンストレーション実験を積極的に行い、システムとしての完成度を高めるとともに、各種イベントで公開展示し、身体的インタラクションの不思議さや重要性をアピールした。また、インタラクションにおける身体的引き込みによるキャラクタへのなりきりに着目し、音声入力と頭部動作入力を併用した身体引き込みキャラクタケータイを開発することで、遠隔非対面、二人一組で評価実験を行った。その結果、身体動作として重要な頭部動作量を直接反映させることで、キャラクタへのなりきりが容易に実現可能であることを示した。また、複数人でのなりきりの効果を活かすアプリケーションとして、実空間と仮想空間の双方を共有することで、ごっこ遊びのようにグループワークを進め、コミュニケーションを楽しむことができるエデュテインメントシステムを開発した。これら一体感が実感できる身体的コミュニケーションインタフェースのプロトタイプ開発の研究成果に関して、ヒューマンインタフェースシンポジウム2010優秀プレゼンテーション賞,第12回IEEE広島支部学生シンポジウムHISS優秀プレゼンテーション賞を受賞した。
1 0 0 0 IR 子宮原発悪性リンパ腫の2例
- 著者
- 島 由実子 滝沢 憲 尾崎 郁枝 井口 富美子 武田 佳彦 西川 俊郎 笠島 武 河上 牧夫
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.283-283, 1991-03-25
第9回学内病理談話会 平成2年11月10日 東京女子医科大学南別館2階大会議室
1 0 0 0 IR ラット坐骨神経系の第1次感覚ニューロン中枢性軸索の脊髄後索内分布
- 著者
- 山本 健詞 丸山 勝一
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.281-281, 1991-03-25
第9回学内病理談話会 平成2年11月10日 東京女子医科大学南別館2階大会議室
本年度は死因調査に関する法的仕組みの構造的な把握を進めた。このことは死因調査に関する情報が法医解剖情報のデータベース化等により利活用されるための前提となる理論的基礎を提示することに資するものである。具体的には、死体解剖保存法や刑事訴訟法などに基づく各種の解剖・検視・検案が、行政各部においていかなる目的のもとにどのような仕組みをもって運用されているかについて整理・検討するとともに、現行法制度の形成に至る歴史的な経緯について調査した。明治期の刑法制定過程と現代の法医学につながる裁判医学の成立過程の関係からは国家による死因調査の対外的な要請も垣間見られ、また昭和の初期においては医学教育研究の進展に伴う死体解剖の構造的な変革を伴った社会的要請が行政による死因調査に大きくのしかかってきていたのではないかという仮説を持つにいたった。これら史的調査によって浮かび上がってきた課題をここに集約すれば、「なぜ行政が死因調査を担うのか」という観点からの再検討の必要性であり、かつ、この議論の成熟化の要請である。とくに第二次大戦後、検視規則と死体取扱規則によってある種の整理をみたと考えられた行政上の死因調査の枠組みも、その根源的な目的についての議論の成熟化をみないままになされたと考えられるふしがあり、そうしたことが司法検視と行政検視の後付けによる振り分け等、現行制度に内在的な問題を生じさせている一因であると考えられた。こんにちの死因調査法制の整備にあたっては、行政による死因調査の目的に対する議論の成熟化がより一層求められるものと考えるが、本研究はそうした議論の一助となるものと思われる。
1 0 0 0 OA 戦後スイスの国民統合と言説の共同体-作家たちの未公刊ドキュメントを手がかりにして
1 0 0 0 IR 緑内障モデルの可能性 : Lapine glaucomaの1剖検例
- 著者
- 上芝 秀博 金井 孝夫 植木 キク子 亀山 和子 堀 貞夫 小山 生子
- 出版者
- 東京女子医科大学学会
- 雑誌
- 東京女子医科大学雑誌 (ISSN:00409022)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.3, pp.282-282, 1991-03-25
第9回学内病理談話会 平成2年11月10日 東京女子医科大学南別館2階大会議室
1 0 0 0 OA 北村季吟の古典研究の文化的・社会的影響力の研究……源氏物語研究の視点から
1 0 0 0 IR 「叱ること」についての臨床教育学的考察
- 著者
- 吉岡 恒生
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学教育創造開発機構紀要 (ISSN:21860793)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.183-190, 2011-03-31
本論は、臨床心理士の経験と知識を踏まえて、教育現場の問題に主体的に参画し、教育の場における問題を検討していくという臨床教育学の視点から、「叱ること」について論じたものである。実践報告という形式を取り、ある小学校での保護者向けの子育て相談会と教員向けの研修会において、筆者が講師として「叱ること」について当事者との対話を通して検討していった。保護者との間では、「きょうだいのなかで叱ること」「どこまでを叱るべきなのか」について、教員との間では、「叱ったあとの失敗感を分かち合う」「叱られたら子どもも苦しむ」「子どもの変容についていけない大人たち」「子どもの言い訳を封じてはいないか」「叱ることができない悩み」「発達障害児への特別な叱り方はあるのか」「それぞれの子どもに応じた叱り方」「自分のことを棚に上げていないか」などについて検討がなされた。
1 0 0 0 IR 不登校リカバリー群の心理・発達的特性--不登校経験者に関する準備的研究
- 著者
- 松浦 直己 岩坂 英巳 松浦 直己 岩坂 英巳 MATSUURA Naomi IWASAKA Hidemi
- 出版者
- 奈良教育大学教育学部附属教育実践総合センター
- 雑誌
- 教育実践総合センター研究紀要 (ISSN:13476971)
- 巻号頁・発行日
- no.20, pp.73-78, 2011-03
1 0 0 0 IR 健常児と発達障害児の交流態度の比較検討
- 著者
- 水口 啓吾 里見 有紀子 前田 健一
- 出版者
- 広島大学大学院教育学研究科心理学講座
- 雑誌
- 広島大学心理学研究 (ISSN:13471619)
- 巻号頁・発行日
- no.10, pp.101-109, 2010
本研究では, 発達障害児が在籍する通常学級の中から, 発達障害児と接触頻度の高い健常児である接触頻度高群(16名), その他の健常児である接触頻度低群(129名), および発達障害児群(10名)を選出し, 架空の物語場面を用いて健常児と発達障害児の交流態度について比較検討した。架空の物語場面では, 問題の原因が健常児側にある場面と発達障害児側にある場面の2場面を呈示し, その後で登場人物の発達障害児に対する印象評定と行動評定を求め, 3群間で比較した。その結果, 印象評定では2つの場面とも, 3群間に有意差は見られなかった。しかし, 行動評定では接触頻度高群が最も好意的態度を示した。発達障害児と日頃接触している接触頻度高群でも, 発達障害児の唐突な言動に対しては好意的印象を持たないこと, しかし発達障害児と一緒に勉強する・遊ぶなどの交流行動では寛容的であることが明らかになった。
1 0 0 0 OA 東北地方太平洋岸の海面水温と気温の年々変動
- 著者
- 野口 泰生
- 出版者
- 社団法人日本気象学会
- 雑誌
- 天気 (ISSN:05460921)
- 巻号頁・発行日
- vol.48, no.10, pp.747-757, 2001-10-31
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 5
親潮の異常南下が注目される東北地方太平洋岸で海面水温変動の特徴を緯度経度1度のグリッド水温(1950〜)で検討した結果, 常磐沖を含む中緯度帯に一年を通して水温が長年低下傾向にある海域が広範囲に確認され, 夏の常磐沖水温変動には明瞭な6年周期が見られた.東北地方太平洋岸の気温も1950年頃から1980年代後半まで一年を通して低温化傾向にあったが, 夏の低温化は東北地方太平洋岸の局地的現象で, この中にやはり6年の周期性が認められた.また, 沿岸から内陸に向かって気温に海の影響が認められた.常磐沖の長期的な水温低下は, 宮城県江ノ島の長期海面水温データや北太平洋指数(Trenberth, 1990), 冬の北太平洋SST指数(Deser and Blackmon, 1995)から判断して, 高緯度大気変動に伴う長期変動の一部である可能性が高く, 同海域では40〜50年の長周期的変動と6年の短周期的変動がオーバーラップしていると推測された.
平成21年度の代表的な研究成果として、第25回日本中東学会年次大会において、クルド系アレヴィーの人々に関する社会範疇に関する考察を報告した。ここでは、対象となるアレヴィーの人々の自民族範疇、そして周辺村落の人々による「名付け」に見られる、さまざまな名称を整理検討した。そこから得られた知見をさらに実証的なデータとともに検討し、日本オリエント学会刊『オリエント』に、クルド系アレヴィーの人々に見るオジャクと呼ばれる社会範疇に関する整理検討を行い、その成果が学術論文として掲載された。オジャクには、儀礼集団としての側面と、預言者一族にその系譜を求める「聖者の系譜」としての側面があり、この2つの構造ともにオジャクの名で語られるのが通常であり、アレヴィーたちは自らがどの儀礼集団に属し、その儀礼集団を束ねているのはどの系譜に属する宗教指導者であるのかを語ることによって、自らをアレヴィーとして名乗ることを明らかにした。しかしながら、客観的に観察可能な差異から出発して各々の社会範疇を導き出すことは、論理的に不可能である。博士論文では、本研究で扱われる社会範疇の区分けがいずれも斉一に体系化されたものではなく、範疇に対する例外的な事象はいずれの水準においても存在しており、そうした例外や齟齬を含みつつ、自明の前提として人々の間に通用するこれらの範疇の内実を、大まかではあるが具体的に示すことができた。
- 著者
- 山内 悟 澤田 敏雄 河野 澄夫
- 出版者
- 公益社団法人日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.4, pp.747-752, 1999-07-15
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 10 8
インタラクタンス方式の光ファイバープローブを用いて, 冷凍カツオの脂肪含量を非破壊的に測定する方法を検討した。スペクトル(400-1100nm)と脂肪含量化学分析値(範囲1-55%)を基に重回帰分析を行い, 表皮から5mmの深さまでの魚肉の化学分析値とスペクトルデータとの間で最も良い結果が得られた。脂肪の吸収バンドである926nmを第1波長とする検量線において良好な結果が得られ, この場合の相関係数は0.91,SECは5.8%であった。検量線評価用試料により得られた検量線の精度を確認した結果, SEPは6.4%, バイアスは-1.0%であった。魚体の解凍に伴い, 表皮に発生する水により推定値に誤差が生じたが, 凍結状態であれば本測定方式は有効であると判断された。
1 0 0 0 OA ラジオテレメトリー手法によるシシャモの産卵遡上行動の解析
- 著者
- 新居 久也 牧口 祐也 藤井 真 上田 宏
- 出版者
- 公益社団法人 日本水産学会
- 雑誌
- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.5, pp.855-869, 2010 (Released:2010-11-01)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 3 4
シシャモの産卵遡上の知見を蓄積するために,超小型の電波発信機の体内装着が魚体に及ぼす影響を水槽実験により検証した。さらに,装着魚(鵡川産の雄 14 個体)の河川内行動を受信機により追跡した。装着魚と非装着魚の間に,泳力,産卵行動,生理学的ストレス指標値に差はなかった。河川内では,平均遡上速度が 3.8~17.8 cm/sec であり,流心部を避けて遡上した。定位箇所は,流速が遅く(60 cm/sec 以下),倒木等のカバーが存在した。小型の遡河回遊魚であるシシャモの遡上行動が初めて連続的に解析された。
近年、地球温暖化や化石資源枯渇等の影響を受け、再生可能な資源である植物バイオマスからエタノールや有機酸等の有用物質を生産することが望まれている。植物バイオマスの主成分であるセルロースから酵素を利用してグルコースを得るには、セルラーゼによりセルロースをセロビオースなどの可溶性糖へ変換した後、それらに対してβ-グルコシダーゼ(BGL)を作用させグルコースへ変換する必要がある。そのため植物バイオマスの酵素糖化においては、高温、酸性条件下においてセロビオースに対して高い反応特性を示すBGLが求められている。しかしながら、それらの性質を併せ持つBGLはこれまでに報告されていない。そこで本研究では、BGLの「酸性域において高い活性を保持するために必要な因子」、「セロビオースに対する親和性を高める因子」を解明する事を目的として研究を進め、最終的には温度安定性に優れる高熱菌由来BGLに点変異導入により上記した2つの性質を付与する事で、「セルロース系バイオマスの酵素糖化を目指したβ-グルコシダーゼの高機能化」を目指した。「酸性域において高い活性を保持するために必要な因子」および「セロビオースに封する親和性を高める因子」に関する立体構造学的知見を得るため、酸性域における活性保持率とセロビオースに対する親和性が異なる担子菌Phanerochaete chrysosporium由来BGL1A、BGL1Bを研究対象とし、BGL1Bの結晶構造解析を試みた。さらに両酵素の高発現生産系を確立するため、フィンランド技術研究センターにてトリコデルマ菌の組換え系構築法を取得した。