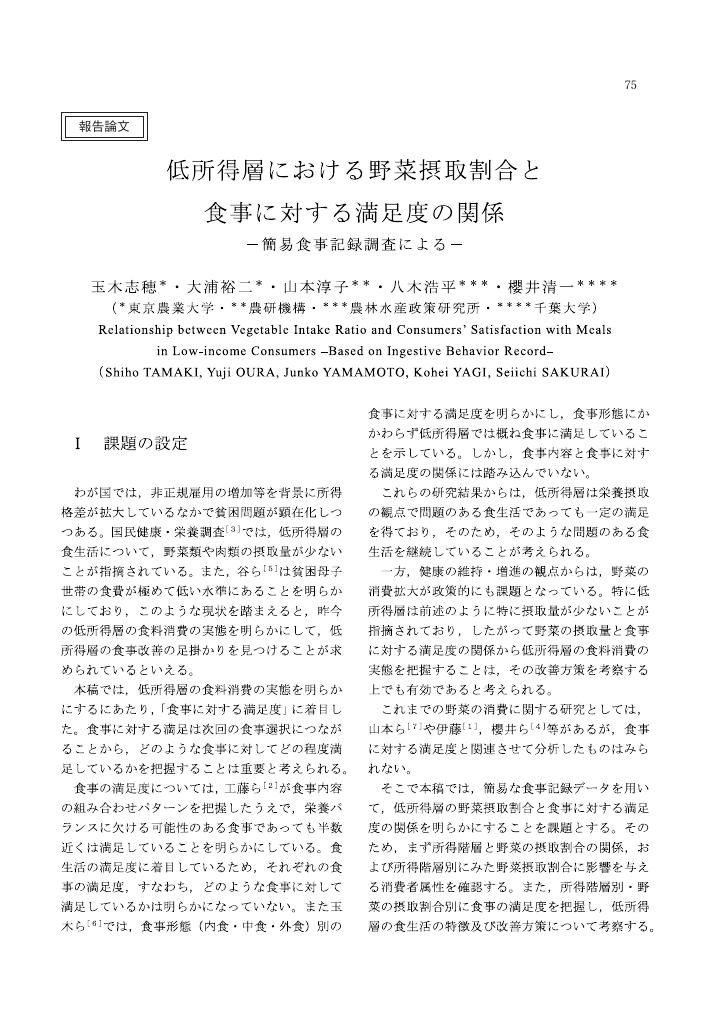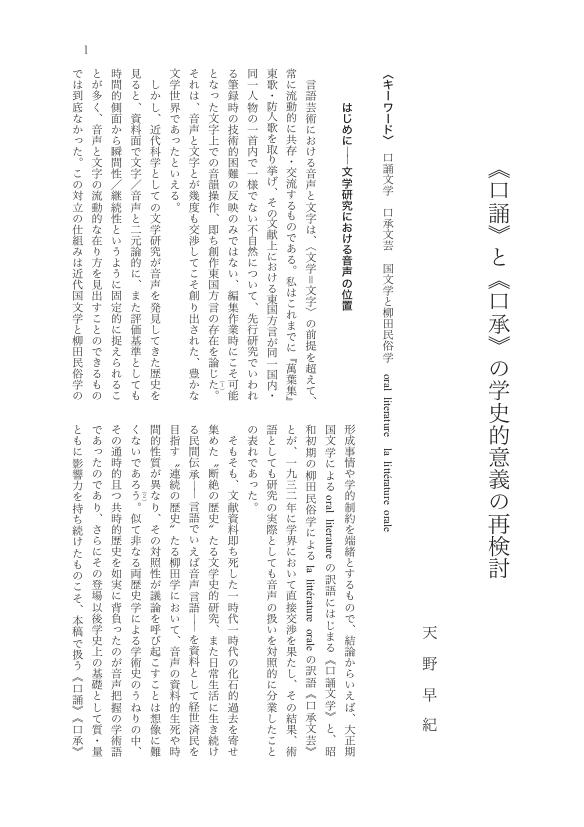- 著者
- 野原 康弘 佐藤 栄治 三橋 伸夫
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.719, pp.153-161, 2016 (Released:2016-01-30)
- 参考文献数
- 26
The purpose of this study is to obtain the knowledge about the assessment methodology of present environmental condition for the elderly people in residential area. And the methodology will be able to judge the future situation whether the residential area would be habitable. We analyze the characteristics of the local, Nasushiobara city in Tochigi. And to use GIS and to calculate the physical environment clarified the situation of local areas quantitatively. As the results of the analysis, we made sure of distribution of the accessibility between the urban area and the agricultural and mountainous rural area. The most accessible facility is “bus-stop”, and the agricultural and mountain area have relatively low accessibility. The worst accessible facility is "medical institution". Distribution of accessibility with regard to police station and post office is low.
2 0 0 0 OA 地方中核都市における高齢者の徒歩アクセシビリティ特性からみた住宅地の評価
- 著者
- 原 拓也 石坂 公一 大橋 佳子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.635, pp.129-135, 2009-01-30 (Released:2009-11-02)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 6 2
The purpose of this study is to develop a method to evaluate walking accessibility of elderly people including topographical aspect, and to analyze the current condition and dynamic trend of elderly people's accessibility using developed method. The results are as follows;1. Generally, the arrival area by foot of elderly people is 10% to 25% less than youths. 2. There is district where the accessibility is improving when being elderly, around station in suburban area, because of target faculty change as being elderly.3. A measure for improving accessibility or promoting rehabitation to more convenient district is necessary in old hilly residential area, because of increasing of elderly people.4. Accessiblity problems won't become serious in center districts but in suburban area there is a possibility to become worth.
- 著者
- 山岸 輝樹 鈴木 雅之 広田 直行 服部 岑生
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.686, pp.801-806, 2013-04-30 (Released:2013-06-04)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 3 4
The purpose of this study is to propose a method of evaluation and visualization of accessibility to regional facilities for elderly peoples, and to verify the validity of proposed method through comparative study of 3 residential areas.In this study, the following subjects were studied.1) In each area, the different type of facility is the cause of poor accessibility for many blocks.2) If facility location lacks continuously, there are poor total accessibility blocks.3) In the near future, the accessibility to Regional facility will become a problem for many blocks around Tokiwadaira-danchi and around Kitanarashino station.
- 著者
- 大野 拓也 柏原 士郎 吉村 英祐 横田 隆司 阪田 弘一 木多 彩子
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.536, pp.149-156, 2000-10-30 (Released:2017-02-03)
- 参考文献数
- 19
- 被引用文献数
- 2 2
This study aims at finding problems of facility planning for aged society, using questionnaire survey with an inter-generational comparison of evaluation on development of a residential area under the land readjustment enterprise project. Under a rapid increase in population, this area has enough commercial facilities to satisfy the residents, but it lacks in public ones. The aged residents' usage rate of facilities in the residential area is generally higher than that of the other residents'. And the aged go to those facilities on foot more often. Therefore, the result shows the importance of further improvement on facilities within the residents' walking distance, in order to provide residents easy access to stores, clinic and other public places that are essential for their daily life.
- 著者
- 井上 猛 小山 司
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.4, pp.291-297, 2009-04-01 (Released:2017-08-01)
- 参考文献数
- 17
選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)はほとんどすべての不安障害亜型に対して有効であるが,その作用機序は十分に解明されていない.われわれは恐怖条件づけストレス(conditioned fear stress;CFS:以前に逃避不可能な電撃ショックを四肢に受けたことのある環境への再曝露)を不安・恐怖の動物モデルとして用い,不安・恐怖とセロトニンの関連について検討してきた.すくみ行動を不安の指標として用いると,ベンゾジアゼピン系抗不安薬と同様に,SSRIはラットのCFSで抗不安作用を示す.SSRIの両側扁桃体基底外側核への局所投与はCFSで抗不安作用を示した.さらに,CFSによって扁桃体基底外側核のc-Fos蛋白発現は亢進し,SSRI全身投与はCFSで抗不安作用を示すと同時に,CFSによるc-Fos蛋白発現を抑制した.以上のことから,SSRIの不安障害への効果は扁桃体に対する抑制効果を介していることが示唆された.
- 著者
- Atsushi Ishimura Yutaka Shimizu Ayano Onishi Naohiro Yabuki Yoshikazu Matsuda
- 出版者
- Japanese Society for Applied Therapeutics
- 雑誌
- アプライド・セラピューティクス (ISSN:18844278)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.16-21, 2023 (Released:2023-05-15)
- 参考文献数
- 14
Magnesium oxide, a low-price laxative without a habit-forming tendency after long-term use, is widely used for treating constipation in Japan. However, its use has been associated with hypermagnesemia in patients with impaired magnesium excretion function such as renal insufficiency. Therefore, in this study, we investigated the use of magnesium oxide tablets, which may be administered to the elderly on a long-term basis. We found the total number of prescriptions has increased year by year and exceeded 4 billion tablets in FY 2020. The use and number of prescriptions were highest among individuals in their 80s, and more than 70% of patients taking the drug are aged 70 years or older. Since the elderly experience physiological functional decline, pharmacists must make effective use of not only age but also laboratory data listed on prescriptions when dispensing these medications in order to prevent adverse events.
2 0 0 0 OA 低所得層における野菜摂取割合と食事に対する満足度の関係 簡易食事記録調査による
2 0 0 0 OA 在宅医はどのように処方薬を評価し,どのような処方行動をとるのか?~質的帰納的研究~
- 著者
- 舛本 祥一 春田 淳志
- 出版者
- 一般社団法人 日本在宅医療連合学会
- 雑誌
- 日本在宅医療連合学会誌 (ISSN:24354007)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.2, pp.40-48, 2023 (Released:2023-05-13)
- 参考文献数
- 19
在宅医が在宅患者の処方薬をどのような視点で評価し,どのような処方行動がなされていくのか明らかにするため,個人インタビューを用いた質的帰納的研究を実施した.在宅医療に従事する医師 17 名に対し,半構造化個別インタビュー調査を行い,録音データを逐語録化し,テーマ分析を行った.在宅医は,薬剤の身体的影響,患者の予後や QOL,患者・家族との関係性などを考慮しつつ,多職種とのやり取りを含めた在宅医療特有の様々な要因を考慮して,処方行動の判断を行っていることが明らかとなった.処方薬変更のプロセスの見える化,多職種間での処方行動への共通理解が進むことで,在宅医療における処方の質向上につながると期待される.
2 0 0 0 OA 飲酒運転撲滅のための光学的血中アルコール濃度計測法の実用化に向けた挑戦的開発研究
諸外国では飲酒運転防止装置の実用化が進み,呼気ガス式手法が一般的になってきたが,様々な問題点がある.そこで,光電容積脈波を利用し,血中成分の吸光特性から指尖部の入射光に対して散乱された光を検出する方法に着目した.しかし,アルコール固有の吸収帯域は水への吸収度が高い近赤外長波長帯域の905 nm,1185 nm,および1690 nmに存在し,人間の身体のほとんどが水分であり,検出される光が極めて微弱で,動作や外部環境に敏感でノイズが多く,これを如何に低減できるかの実験検討をまず行い,次いで人を対象とした飲酒負荷実験を行った結果,光電容積脈波にて血中アルコール濃度が予測可能であることが示唆された。
2 0 0 0 OA 視聴者反応と音響特徴量に基づくサムネイル動画の生成手法
- 著者
- 中村 聡史 山本 岳洋 後藤 真孝 濱崎 雅弘
- 雑誌
- 情報処理学会論文誌データベース(TOD) (ISSN:18827799)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.3, pp.148-158, 2013-06-28
本稿では,動画共有ウェブサイトにおいて日々アップロードされる膨大な楽曲動画について,ユーザがその動画に対して興味があるかどうかを短時間で判断する手段として,15秒のサムネイル動画を自動生成する手法を提案する.ここでは,楽曲動画作成者と楽曲動画視聴者に注目し,楽曲動画のサビ検出技術と,視聴者の盛り上がり検出技術を使うことにより,サムネイル動画を自動生成する仕組みを実現する.また,評価実験により,組合せ手法の有効性とその特徴を明らかにする.
2 0 0 0 OA 斉一説に関する学説史的考察 その変容,謬説,現代的意義
- 著者
- 岡 義記
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 地理学評論 Ser. A (ISSN:00167444)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.8, pp.527-549, 1995-08-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 69
- 被引用文献数
- 1 1
斉一説は160年の長期間にわたり使用されてきた言葉である.その意義は地質学・地形学の進歩に対応して変容してきた.同時に斉一説に関する多様な誤記・謬説が生み出されてきた.本稿では,斉一説の意義を歴史的に整理して,誤記・謬説のルーツを追いながら誤りを訂正し,斉一説の現代的意義について考察した.その結果,「斉一説」という用語は,歴史的用語として,初期の斉一説に限定して使用すべきことを主張した.また,それ以後の斉一説(方法論的斉一説など)は科学一般に採用されるべき常識的な考えになってしまっている.今日,斉一説を唱えることは時代錯誤になっている状況を概説した.
- 著者
- 栗原 隆
- 出版者
- 日本シェリング協会
- 雑誌
- シェリング年報 (ISSN:09194622)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.130-139, 2020 (Released:2020-10-13)
2 0 0 0 OA 自己認知の複雑性に関する研究 Linvilleの指標をめぐって
- 著者
- 林 文俊 堀内 孝
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.6, pp.452-457, 1997-02-28 (Released:2010-07-16)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 6 5
The purpose of the present study was to evaluate H statistic, proposed by Linville (1985, 1987), as an index for cognitive complexity of the self. Linville asserted that high self-complexity would act as a buffer against life stress or depression. One hundred and eighty-seven undergraduates sorted 40 personality-trait adjectives into as many categories as necessary in order to describe themselves. In addition, 126 participants filled out several scales including self-consciousness and esteem. Main findings were as follows: (a) H statistic was not significantly associated with any variable related to the self-ratings, and showed no stress-buffering effect. (b) On the other hand, participants who had high cognitive complexity for the negative aspects of the self, as operationalized by Woolfolk, Novalany, Gara, Allen, and Polino (1995), were low in self-esteem and high in public self-consciousness. The results suggest that cognitive complexity of the negative self may indicate a predisposition for depression or neurosis. (c) Also, women scored significantly higher than men on cognitive complexity of the negative self.
2 0 0 0 OA 人工知能は読者/作者になれるのか 自然言語処理技術が国語教育にもたらす可能性
- 著者
- 藤田 彬
- 出版者
- 全国大学国語教育学会
- 雑誌
- 全国大学国語教育学会国語科教育研究:大会研究発表要旨集 135 (ISSN:24321753)
- 巻号頁・発行日
- pp.221-224, 2018-10-27 (Released:2021-12-03)
2 0 0 0 OA 《口誦》と《口承》の学史的意義の再検討
- 著者
- 天野 早紀
- 出版者
- 全国大学国語国文学会
- 雑誌
- 文学・語学 (ISSN:05251850)
- 巻号頁・発行日
- vol.233, pp.1-13, 2021 (Released:2022-12-30)
2 0 0 0 OA 死は本当にわれわれにとって何ものでもないのか? : エピクロスに見る死の分析
- 著者
- Miura Kaname
- 出版者
- 金沢大学哲学・人間学研究会 = The Society for Study of Philosophy and Philosophical Anthropology, Kanazawa University
- 雑誌
- 哲学・人間学論叢 = Kanazawa Journal of Philosophy and Philosophical Anthropology (ISSN:18848990)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.43-64, 2011-03-31
2 0 0 0 OA COVID-19と抗リン脂質抗体
- 著者
- 家子 正裕 大津 瑛裕 前田 峻大 下瀬川 健二
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.625-627, 2021 (Released:2021-10-22)
- 参考文献数
- 22
2 0 0 0 OA NETsと自己免疫疾患
- 著者
- 平橋 淳一
- 出版者
- 一般社団法人 日本血栓止血学会
- 雑誌
- 日本血栓止血学会誌 (ISSN:09157441)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.6, pp.679-686, 2021 (Released:2021-12-25)
- 参考文献数
- 50
新たな生体防御機構として2004年に発見された好中球細胞外トラップ(neutrophil extracellular traps: NETs)は,自然免疫にとどまらずその制御不全が自己免疫疾患にも根本的に関わることが明らかとなってきた.NETsは自己免疫疾患の発症と進展へ少なくとも次の4つの点で寄与している.①病原性自己抗体産生における自己寛容(tolerance)の破綻②NETs成分の露出による自己抗原の供給③炎症の増幅④炎症に伴う血栓症(thromboinflammation)である.2007年,NETsが臓器損傷を誘発して宿主を傷つける可能性が初めて示唆されたのを契機に,NETosis阻害により様々な感染症における組織損傷を軽減できることが報告され,現在では,全身性エリテマトーデス(systemic lupus erythematosus: SLE),関節リウマチ(rheumatoid arthritis: RA),糖尿病,アテローム性動脈硬化症,全身性血管炎,血栓症,がんの転移,創傷治癒,外傷など様々な病態に関与していることが報告されている.しかし,NETsは本来生体防御機構の一つであり,感染防御のみならず何らかの有益な機能を果たしている可能性も忘れてはならず,NETsの制御法は重要な研究テーマの一つとなっている.
2 0 0 0 OA カラス類による巣箱破壊の経年変化
- 著者
- 峯岸 典雄
- 出版者
- 特定非営利活動法人バードリサーチ
- 雑誌
- Bird Research (ISSN:18801587)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.S5-S8, 2005 (Released:2005-09-16)
- 参考文献数
- 4
- 被引用文献数
- 1
全国21か所のゴルフ場に約3,000個の巣箱を設置し,1991年から2001年まで巣箱の鳥類による利用状況についての調査を行なってきたが,1995年にこれまでは数件しかなかったカラス類による巣箱の破壊が急激に増加し,1999年までは多くの巣箱が被害を受けた.しかし,2000年以降は被害がほとんど無くなった。カラス類の個体数には大きな変化はなく,なぜ全国ほぼ一斉に被害がはじまり,5年で被害がなくなってしまったのかは不明である.