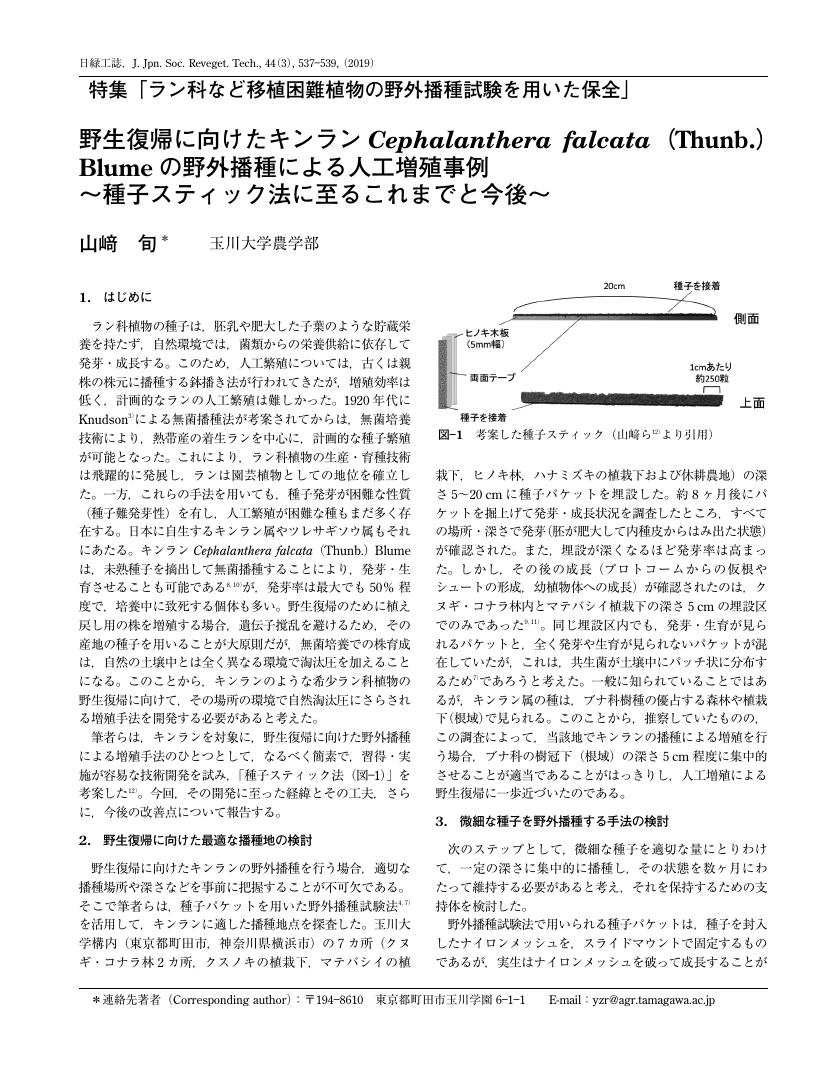2 0 0 0 OA コミュニケーション手段として指書が出現した自閉症児の一事例(実践研究特集号)
- 著者
- 渡部 信一
- 出版者
- 一般社団法人 日本特殊教育学会
- 雑誌
- 特殊教育学研究 (ISSN:03873374)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.33-39, 1996-03-30 (Released:2017-07-28)
今回筆者は、それまで全く指導を受けたことのなかった「指書」をコミュニケーション手段として突然使い始めたひとりの音声言語を持たない自閉症児を経験した。本事例は幼児期から文字に対しては著しい興味を示し、「指書」出現以前にも単語(ひらがな、カタカナ)の書字はある程度可能であったが、それをコミュニケーションに用いることは全くなかった。初めて「指書」が出現してから3ヵ月後には30単語、6ヵ月には100単語以上が観察され、その後も2単語の連続や品詞の拡大(形容詞、動詞、助詞、感情語)などの発展が認められた。従来、自閉症児に対し音声言語以外のコミュニケーション手段を意図的・系統的に指導した報告は多数あるが、本事例では事例自らが「指書」という新たなコミュニケーション手段を使い始めたという点で従来の研究とは異なった意味を持つと考える。
- 著者
- 山﨑 旬
- 出版者
- 日本緑化工学会
- 雑誌
- 日本緑化工学会誌 (ISSN:09167439)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.537-539, 2019-02-28 (Released:2019-07-27)
- 参考文献数
- 12
- 著者
- 星 泉 岩田 啓介 平田 昌弘 別所 裕介 山口 哲由 海老原 志穂
- 出版者
- デジタルアーカイブ学会
- 雑誌
- デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, no.s3, pp.s198-s201, 2022 (Released:2022-11-02)
- 参考文献数
- 3
チベット高原では都市への移住と村落部の生活変化が急速に進み、家畜飼養と密接に結びついて長期間かけて形成されてきた民俗文化が、十分な学術調査がなされないまま、急速に失われようとしている。発表者らはこれを憂慮し、チベット高原東北部の青海省ツェコ県において、牧畜民出身の研究者と現地の人々とともに6年間にわたる現地調査を実施し、牧畜民の民俗文化を体系的に整理した『チベット牧畜文化辞典』を刊行した。調査の過程では、辞典には収録しきれない語り・映像・写真・音声・文学作品など多岐にわたる情報が得られ、発表者らの手元に残されている。これらを有機的に結びつけた形でアーカイブすることによって民俗文化を再現的に活写することを課題とし、現在実験的試みを続けている。本発表では、この一連のプロセスから成る研究の営みを「フィールド・アーカイビング」と位置づけ、その意義と可能性について論じる。
2 0 0 0 OA 耳科手術支援ロボットの開発
- 著者
- 藤田 岳 上原 奈津美 山下 俊彦 西川 敦 河合 俊和 鈴木 寿 横井 純 柿木 章伸 丹生 健一
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会報 (ISSN:24365793)
- 巻号頁・発行日
- vol.126, no.3, pp.181-184, 2023-03-20 (Released:2023-04-01)
- 参考文献数
- 12
頭頸部外科領域にロボット手術が保険適応となり, 耳鼻咽喉科医にとってもロボット手術は身近な存在となってきた. しかし泌尿器・消化器領域で発展してきた手術ロボットを, そのまま耳や鼻の手術に応用することはまだ難しい. 私達は経外耳道的内視鏡下耳科手術 (Trans-canal Endoscopic Ear Surgery : TEES) を支援するロボットの研究・開発を複数の大学の工学部と共同で行っている. 手術ロボットの研究を通して, 自分たちの手術の特徴や問題点を改めて見直す機会が得られている. 本稿では, これまでの耳科手術用ロボットや内視鏡保持ロボットについて概略を述べ, 現在研究中の TEES 支援ロボットのコンセプトと試作機について述べる. また, 将来ロボット自身が自律的に手術を行うことを目標とした, ロボットの自律レベル向上に向けた研究についても紹介する.
2 0 0 0 OA 「物語の境界」についての一考察:物語作品の発話様態をめぐって
- 出版者
- 金沢大学外国語教育センター
- 雑誌
- 言語文化論叢 (ISSN:13427172)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.15-28, 2008-03-31
2 0 0 0 OA もっと知りたい!遺伝のこと
- 著者
- サイエンスウィンドウ編集部
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- サイエンスウィンドウ (ISSN:18817807)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.C3, pp.1-81, 2016 (Released:2019-04-12)
子ども向けの本「もっと知りたい!遺伝のこと」の冊子体一式(PDF版)およびE-BOOK版は下記のURLで閲覧できます。 https://sciencewindow.jst.go.jp/kids/04.html 目次 登場人物 第1章 家族が似ているのはなぜ? p.04 生まれてくる赤ちゃんは誰に似ている? p.08 ぼくたちはご先祖様にも似ている? p.12 コラム 何千年も謎だった生き物の親子が似る不思議 第2章 【まんが】遺伝の謎を解き明かした人々 PART1 p.24 コラム 遺伝の謎を追いかけた科学者たち 第3章 いろいろな生き物がいるのはなぜ? p.26 人はどんな動物に似ている? p.30 どうしてたくさんの生き物がいるの? p.32 受けつがれるバトンって何? p.34 塩基はどれくらい並んでいるの? p.36 コラム ゲノムがわかると恐竜の姿がわかる? 第4章 遺伝情報はどうやって伝わる? p.38 DNAはどこにあるの? p.40 両親から受けつぐものは何? p.44 DNAに遺伝情報が書き込まれている? p.46 コラム ゲノムから見る人類の広がり 第5章 わたしの体はどうやってできる? p.48 どうやってわたしたちの体を作っている? p.52 体のことは全部遺伝子で決まるの? p.56 【まんが】遺伝の謎を解き明かした人々 PART2 p.58 【まんが】遺伝の謎を解き明かした人々 PART3 p.60 コラム 遺伝子技術の歴史 p.62 コラム まったく同じ遺伝子を持つ一卵性双生児 第6章 自分の遺伝子を知ること p.64 遺伝子から何がわかるの? p.68 どうやって遺伝子を調べるの? p.70 これからの医療はどうなる? p.72 一人ひとりが違っているね p.74 たった一つのわたしの命を大切にしたい p.76 遺伝に関わる仕事 p.78 遺伝のことをもっと知りたい p.80 あとがき
2 0 0 0 OA 児童の認知の誤りが社会的スキルの自己評定と社会不安へ与える影響(原著)
- 著者
- 加計 佳代子 佐藤 寛 石川 信一 嶋田 洋徳 佐藤 容子
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.2, pp.113-125, 2008-05-31 (Released:2019-04-06)
- 被引用文献数
- 1
本研究は児童の社会的スキルと認知の誤りが社会不安に与える影響について検討することを目的とした。対象者は小学4年生から6年生1,163名(男子575名、女子588名)であった。対象者は、SocialPhobiaandAnxietyInventoryforChildren日本語版(石川ら,2008)、Children'sCognitiveErrorScale改訂版(CCES-R;佐藤ら,2004)、小学生用社会的スキル尺度(嶋田ら,1996)への回答を求められた。対象者1,163名のうち、無作為抽出された197名の児童の担任教師40名は小学生用社会的スキル尺度(嶋田ら,1996)を他者評定用に改訂したものに回答した。分析の結果、認知の誤りの高さが社会的スキルの自己評定と他者評定の差に関係していることが明らかになった。また、社会的スキルよりも認知の誤りの方が児童の社会不安に直接影響していることが示され、児童の認知変数への介入が有効である可能性が示唆された。
- 著者
- Mayer Oliver
- 出版者
- 愛知教育大学
- 雑誌
- 愛知教育大学研究報告. 人文・社会科学編 (ISSN:18845177)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.96-104, 2022-03-01
Third-sector railways are independent railway operators that were originally part of the Japanese national rail network, but were split off in the 1980s. They play an important role in providing a transport infrastructure for their local areas, but as many of them are located in rural areas they suffer from a loss of passengers. This article looks at some of these third-sector railways in detail.
2 0 0 0 OA 障害児の母親の就労に影響を与える要因―障害児の母親を対象とした調査研究をもとに―
- 著者
- 江尻 桂子 松澤 明美
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.3AM-047, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
- 著者
- Amy K. PARKIN Amy J. ZADOW Rachael E. POTTER Ali AFSHARIAN Maureen F. DOLLARD Silvia PIGNATA Arnold B. BAKKER Kurt LUSHINGTON
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- pp.2022-0078, (Released:2022-08-08)
- 被引用文献数
- 4
Due to the COVID-19 pandemic, the number of employees in flexible work from home has increased markedly along with a reliance on information communication technologies. This study investigated the role of an organisational factor, psychosocial safety climate (PSC; the climate for worker psychological health and safety), as an antecedent of these new kinds of demands (specifically work from home digital job demands) and their effect on work-life conflict. Data were gathered via an online survey of 2,191 employees from 37 Australian universities. Multilevel modelling showed that university level PSC to demands, y=−0.09, SE=0.03, p<0.01, and demands to work-life conflict, y=0.51, SE=0.19, p<0.05, relationships were significant. Supporting the antecedent theory, university level PSC was significantly indirectly related to work-life conflict via demands (LL −0.10 UL −0.01). Against expectations PSC did not moderate the demand to work-life conflict relationship. The results imply that targeting PSC could help prevent work from home digital job demands, and therefore, work-life conflict. Further research is needed on the role of digital job resources as flexible and hybrid work takes hold post COVID.
2 0 0 0 OA 脳腫瘍治療による画像所見
- 著者
- 金子 智喜
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.169-172, 2020-06-10 (Released:2020-07-07)
- 参考文献数
- 5
- 著者
- Mikiyuki Katagiri Akira Satoh Shinji Tsuji Takuji Shirasawa
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.2, pp.102-107, 2012 (Released:2012-08-30)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 44 70
In this study we tried to confirm the effect of an astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract on cognitive function in 96 subjects by a randomised double-blind placebo-controlled study. Healthy middle-aged and elderly subjects who complained of age-related forgetfulness were recruited. Ninety-six subjects were selected from the initial screen, and ingested a capsule containing astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract, or a placebo capsule for 12 weeks. Somatometry, haematology, urine screens, and CogHealth and Groton Maze Learning Test were performed before and after every 4 weeks of administration. Changes in cognitive performance and the safety of astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract administration were evaluated. CogHealth battery scores improved in the high-dosage group (12 mg astaxanthin/day) after 12 weeks. Groton Maze Learning Test scores improved earlier in the low-dosage (6 mg astaxanthin/day) and high-dosage groups than in the placebo group. The sample size, however, was small to show a significant difference in cognitive function between the astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract and placebo groups. No adverse effect on the subjects was observed throughout this study. In conclusion, the results suggested that astaxanthin-rich Haematococcus pluvialis extract improves cognitive function in the healthy aged individuals.
- 著者
- Akira Satoh Shinji Tsuji Yumika Okada Nagisa Murakami Maki Urami Keisuke Nakagawa Masaharu Ishikura Mikiyuki Katagiri Yoshihiko Koga Takuji Shirasawa
- 出版者
- SOCIETY FOR FREE RADICAL RESEARCH JAPAN
- 雑誌
- Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition (ISSN:09120009)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.3, pp.280-284, 2009 (Released:2009-04-25)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 72 96
Astaxanthin (Ax), a carotenoid ubiquitously distributed in microorganisms, fish, and crustaceans, has been known to be a potent antioxidant and hence exhibit various physiological effects. We attempted in these studies to evaluate clinical toxicity and efficacy of long-term administration of a new Ax product, by measuring biochemical and hematological blood parameters and by analyzing brain function (using CogHealth and P300 measures). Ax-rich Haematococcus pluvialis extracts equivalent to 4, 8, 20 mg of Ax dialcohol were administered to 73, 38, and 16 healthy adult volunteers, respectively, once daily for 4 weeks to evaluate safety. Ten subjects with age-related forgetfulness received an extract equivalent to 12 mg in a daily dosing regimen for 12 weeks to evaluate efficacy. As a result, no abnormality was observed and efficacy for age-related decline in cognitive and psychomotor functions was suggested.
2 0 0 0 OA 遊里における音曲の受容に関する東西比較 ― 上方の当道と江戸の男芸者 ―
- 著者
- 長谷川 慎 日比谷 孟俊
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 年報 = Nenpo (ISSN:09100679)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.137-171, 2023-03
ページ他に口絵あり
2 0 0 0 OA 隋唐期道教祭醮と密教星供の供物
- 著者
- 張 名揚
- 出版者
- 実践女子大学
- 雑誌
- 年報 = Nenpo (ISSN:09100679)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, pp.7-31, 2023-03
- 著者
- 明石 純一
- 出版者
- 日本比較政治学会
- 雑誌
- 日本比較政治学会年報 (ISSN:21852626)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.217-245, 2009 (Released:2020-03-16)
- 参考文献数
- 20
2 0 0 0 OA 元禄・享保期民間社会における経済思想史研究の視角と対象
- 著者
- 田口 英明
- 出版者
- 湘南工科大学
- 雑誌
- 湘南工科大学紀要 = SHONAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY JOURNAL (ISSN:09192549)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.57-73, 2023-03-31
本稿の目的は,筆者がこれまで行ってきた元禄から享保期の上層民を対象とした経済思想史研究の論点を整理し,それをまとめるための視角を設定することにある。本稿では,江戸時代の実務家の経済思想史研究の流れの中に本研究を位置付け,元禄・享保期に着目する理由を明らかにした上で,経済思想史研究と書物の社会研究史の架橋となるような視角として,当該期の実務家の思想の中に「作為」の意識を析出するという枠組みを設定している。それを踏まえて,当該期の上層民に「自然」なものと認識されていた社会観・経済観を概観する。そして,元禄期に萌芽的に見られた「作為」の意識が,幕府の制度変更に対応・対抗する形で成長していく過程を,田中休愚の事例を中心に考察している。I have, in the last three years, published several papers concerning economic thoughts of upper town people from GENROKU to KYOHO period. This paper aims to review main points of these papers and constitute a study framework for this theme. In the first part of this paper, I will survey previous studies of history of economic thoughts and will try to position my study into them. I assume that in economic thoughts of upper town people in these periods, we can detect personalities which allowed them to adapt themselves to changes in society and economy they faced. They also tried to take ingenuity and intentional activities to improve their domestic economy and then their local economy.