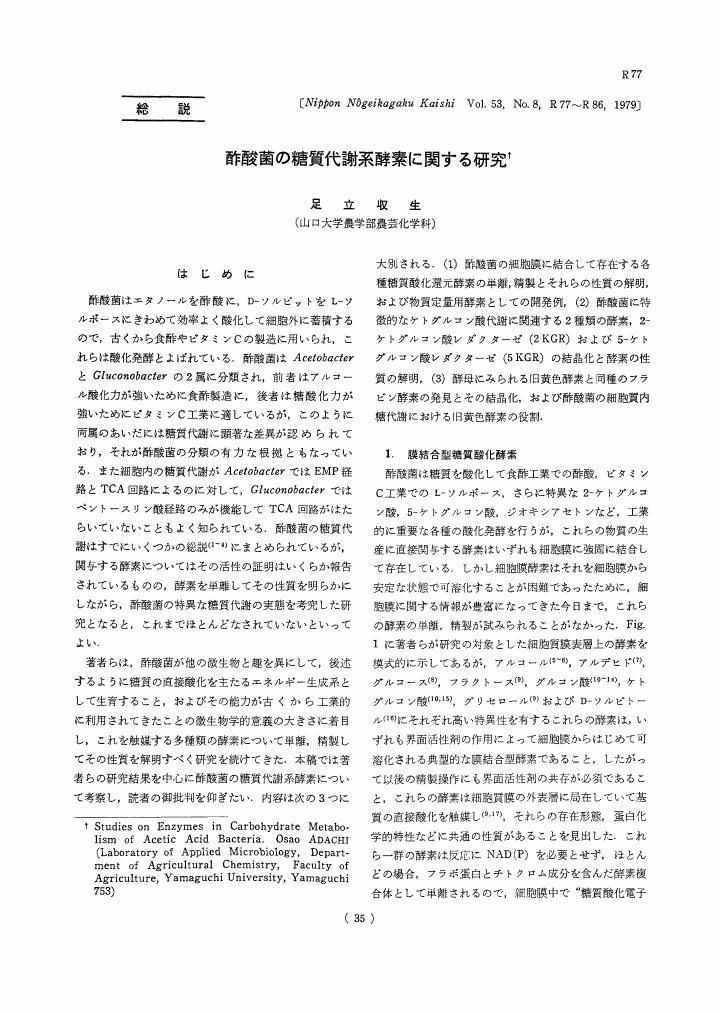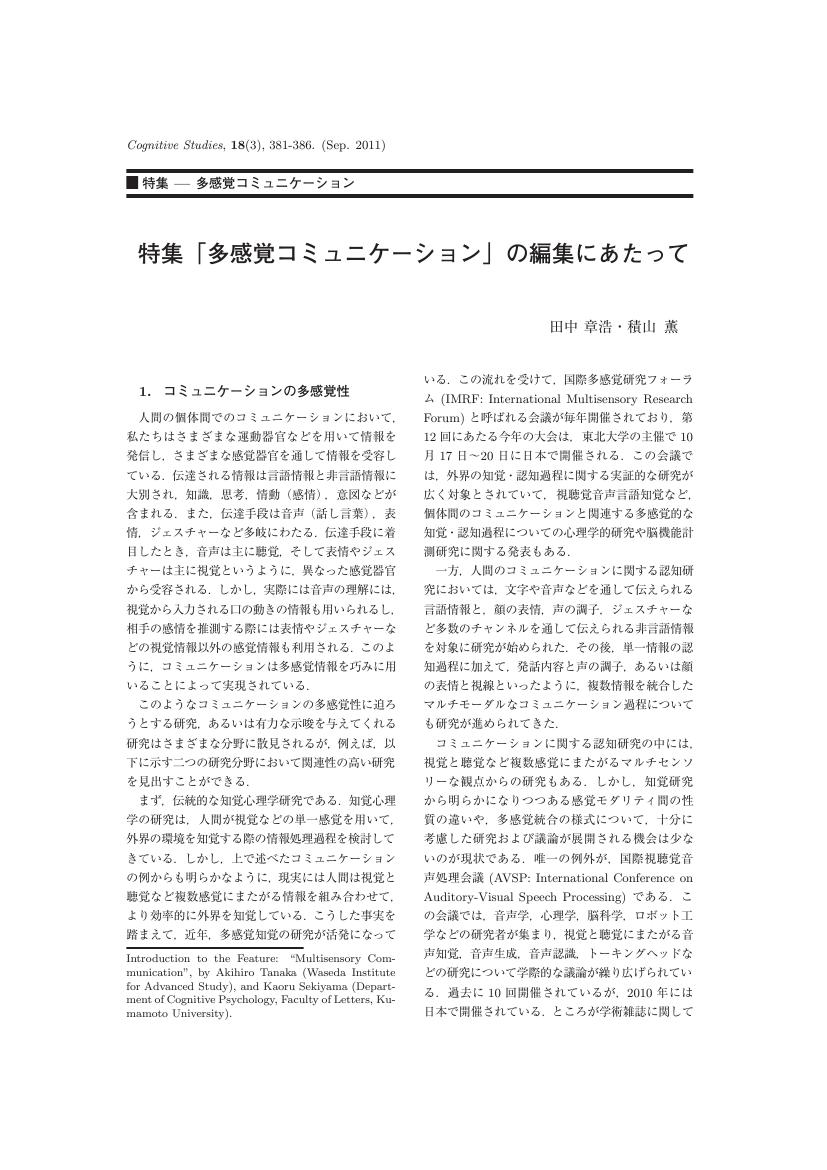1 0 0 0 OA 酢酸菌の糖代謝系酵素に関する研究
- 著者
- 足立 収生
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.8, pp.R77-R86, 1979 (Released:2008-11-21)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 2 2
1 0 0 0 OA 受診を中断している境界型(IGT)の人における療養行動の改善を目指した認知の変容の有効性
- 著者
- 井澤 美樹子 伊坂 裕子
- 出版者
- 一般社団法人 日本健康心理学会
- 雑誌
- 健康心理学研究 (ISSN:09173323)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.2, pp.67-76, 2009-12-31 (Released:2014-03-28)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
Patients with Impaired Glucose Tolerance (IGT) require maintenance of self-care behaviors, such as diet and exercise, as well as regular check ups and consultations. However, many patients discontinue self-care behaviors and subsequently progress to diabetes. The need to continue self-care behaviors in daily life may lead to psychological stress. In this study, we considered the discontinuation of self-care behaviors and associated consultations as a form of maladjusted behavior among patients with IGT. We hypothesized that the patients' behavior was caused by cognitions such as expectations, judgments, thoughts, and belief systems. We conducted an intervention for modifying the cognitions regarding the self-care behaviors of patients with IGT who were discontinuing consultations, and assessed changes in their self-care behaviors. The results revealed cognitive changes in addition to improvements in self-care behaviors. These findings suggest that cognitive changes are effective for improving the maladjusted behavior of discontinuation of self-care behaviors among patients with IGT.
1 0 0 0 OA 硫安施肥に伴うジャーガル(陸成未熟土)と国頭マージ(赤黄色土)の塩基の形態変化
- 著者
- 金城 和俊 渡嘉敷 義浩
- 出版者
- 日本熱帯農業学会
- 雑誌
- 熱帯農業研究 (ISSN:18828434)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.2, pp.47-52, 2015 (Released:2016-03-29)
- 参考文献数
- 25
本研究ではジャーガルと国頭マージにおける硫安の施肥による塩基の可溶化のメカニズムを考察した.硫安の施肥量の増加に伴い,両土壌では共に土壌pHが低下し,硝酸の生成量は両土壌間で異なった.ジャーガルでは施肥した硫安由来のアンモニア態窒素の多くは硝酸態窒素に変化し,国頭マージでは硝酸態窒素の生成量は少なかった.土壌間における硝酸態窒素の生成量の違いはジャーガルと国頭マージの塩基の可溶化のメカニズムが異なることに起因した.土壌塩基の可溶化のメカニズムをまとめると,ジャーガルでは硝化作用に伴い,放出される水素イオン,国頭マージでは硝化されずに残存したアンモニウムイオンと一部硝化作用で放出される水素イオンが塩基の可溶化に関与していることが示唆された.
1 0 0 0 OA 速く走るためのシューズ
- 著者
- 金子 靖仙
- 出版者
- 公益社団法人 精密工学会
- 雑誌
- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.4, pp.460-465, 1997-04-05 (Released:2009-06-30)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 人工肺の研究開発動向と新しい展開
- 著者
- 巽 英介
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.9, pp.749-753, 2007-09-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 26
開心術用の人工肺が十分な性能を有するに至った一方で,補助循環分野で臨床例の増加と次世代型の人工肺を目指した研究開発が活発に行われている。高性能人工肺の開発は多くの患者に福音をもたらし,企業の立場からも市場拡大につながる。今後この分野における開発研究のいっそうの推進と,より優れた装置の実用化・臨床応用の発展が期待される。
1 0 0 0 OA 望ましい食習慣の形成を目指した学校における食育の評価
1 0 0 0 OA 山口県中東部, 徳佐-地福断層と迫田-生雲断層の性状および活動性
- 著者
- 佐川 厚志 相山 光太郎 金折 裕司 田中 竹延
- 出版者
- 一般社団法人 日本応用地質学会
- 雑誌
- 応用地質 (ISSN:02867737)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.78-93, 2008-06-10 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 3 6 4
徳佐-地福断層北東部と迫田-生雲断層中部の性状および活動性を明らかにする目的で, 地形判読, 断層露頭調査, トレンチおよびボーリング調査を実施した. 徳佐-地福断層北東部のトレンチ調査に基づくと, 断層の最新活動時期は10,800~3,400年前となる. 既存のトレンチ調査での14C年代値を再検討した結果, 断層全域 (長さ約35km) が6,300~5,200年前に同時に活動した可能性が出てきた. 一方, 1997年山口県北部の地震 (Mj6.6) の震央から南西約10kmで実施した迫田-生雲断層中部のトレンチ調査により, 断層の最新活動時期は14,500~8,500年前と見積もられた.これらの最新活動時期と既存の研究からのデータを組み合わせると, 迫田-生雲断層から徳佐-地福断層を経て, その南西に隣接する大原湖-弥畝山西断層系を構成する木戸山西方断層へと, 断層活動がマイグレーションする傾向が認められた.
1 0 0 0 OA “そそる看板”デザインの基礎的考察
- 著者
- 小山 雅明 高橋 由樹 椎塚 久雄
- 出版者
- 日本感性工学会
- 雑誌
- 日本感性工学会論文誌 (ISSN:18840833)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.65-73, 2016 (Released:2016-02-26)
- 参考文献数
- 5
The purpose of signboard is primarily up to indicate the store or company name of that exists in the location where you want to post it. In addition, other general advertising purposes (companies, products, people of talent, and movies, etc.) can be considered. However, there is a variety of purposes, usual route, display of the evacuation route, etc. (some are also referred to as a guide plate), such as the sign for the warning (including, for example, signs that are used during the road construction). In noticing the existence of such a signboard, under some influence from there depicted designed (including characters and the like), a person is considered to move to a specific action. Therefore, such a series of operations may be regarded as a “stimulus” → “thinking” → “action”. For this reason, signboards can be considered as one system. In this paper, by capturing the environment surrounding the signboard, including the people as one of the system, using the concept of production system, we propose a new point of view and its model to the signboard design. This model is based on the basic idea for a person to design as “intrigued by” the curiosity and interests saw the signboard.
1 0 0 0 OA クロマトグラフィーによる光学異性体の分離分析
- 著者
- 大井 尚文
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.9, pp.600-605, 1986-09-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 7
1 0 0 0 OA 結晶化による有機化合物の光学分割法の開発とその応用に関する研究
- 著者
- 野平 博之
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.1, pp.14-23, 1992-01-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 2 4
Some new methods and practical strategies for the efficient resolution of a wide variety of organic componds by means of such crystallization procedures as preferential crystallization, diastereomeric salt formation and their combination are described. Utilizing the organic compounds with high optical purities thus obtained, application study in the following field has been performed;1) verification of the Brewster's theory of optical activity, 2) syntheses of pharmaceutical, agricultural and perfuming chemicals, 3) preparation of optical purity determining agents, 4) preparation of atropisomeric bis (triarylphosphine) as a catalyst for asymmetric hydrogenation, 5) syntheses of ferroelectric liquid crystals. In this article, an outline of our investigation in the above mentioned fields is also described.
1 0 0 0 OA 全学理科系学生を対象とした “自然科学総合実験”
- 著者
- 須藤 彰三
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.1_41-1_44, 2009 (Released:2009-02-10)
- 参考文献数
- 1
In 2004, Tohoku University started a new introductory experimental science course for freshmen. This course was intended to aid students in thinking logically and in understanding the fundamental concepts of natural phenomena. We combined physics, chemistry, biology, and earth sciences and set up a five themes entitled, “Life, Energy, Earth and Environment, Materials, and Science and Culture” . More than 1,800 students, including 810 engineering students, of all the science-related subjects attended these classes. Of the students taking the classes, 62% were favorable to them in 2004 and 68% in 2007, whilst only 50% of the students were positive about the old course in 2003.
1 0 0 0 OA 都市計画事業家・根岸情治の履歴と業績に関する研究
- 著者
- 中島 直人
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.283-288, 2011-10-25 (Released:2011-11-01)
- 参考文献数
- 15
本研究の目的は、根岸情治の履歴と業績を明らかにすることを通して、「都市計画事業家」の実質的内容について考察を行うことである。根岸は幾つかの区画整理事業の現場を渡り歩きながら、区画整理実務を身につけ、キャリアを形成していったが、その仕事内容は単なる事務仕事に留まらず、各種の折衝、啓蒙宣伝、事業後の宅地の販売促進までを含む広いもので、創造性や根岸の人格が反映されたものであった。池袋駅東口地下街の建設においても、都市計画事業の民間代行による地下街建設という新しい試みに際し、事業の進展に応じて、政治的活動を含む柔軟な活動を展開した。こうした姿から浮かび上がる「都市計画事業家」の存在は、公的セクターによる強力な土地利用規制ではなく、民間の地権者の協同による事業に支えられた我が国の都市計画の特質と深く関係している。
- 著者
- Yohei Migiyama Katsunori Yanagihara Norihito Kaku Yosuke Harada Koichi Yamada Kentaro Nagaoka Yoshitomo Morinaga Norihiko Akamatsu Junichi Matsuda Koichi Izumikawa Hirotsugu Kohrogi Shigeru Kohno
- 出版者
- 国立感染症研究所 Japanese Journal of Infectious Diseases 編集委員会
- 雑誌
- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.91-96, 2016 (Released:2016-03-23)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 36
Pseudomonas aeruginosa bacteremia occurs mainly in immunocompromised patients. However, P. aeruginosa bacteremia in immunocompetent patients has also been reported. The aim of this study was to evaluate the clinical characteristics of P. aeruginosa bacteremia in relation to the immune status of the patients. The medical records of 126 adult patients with P. aeruginosa bacteremia in Nagasaki University Hospital were retrospectively reviewed between January 2003 and December 2012. Of 126 patients with P. aeruginosa bacteremia, 60 patients (47.6%) were classified as immunocompetent. Mortality in immunocompetent patients tended to be lower than in immunocompromised patients (7-day mortality, 8% vs. 30%, P < 0.01; 30-day mortality, 23% vs. 39%, P = 0.053). Multivariate analysis showed that a higher sequential organ failure assessment score (hazard ratio [HR]: 1.27, P < 0.01) and underlying malignancies (HR: 3.33, P < 0.01) were independently associated with 30-day mortality. Initial antibiotic therapy (HR: 0.21, P < 0.01) and patients' immune status (HR: 0.29, P = 0.02) also had a significant impact on survival. However, there was a significant interaction between these 2 variables (P = 0.03 for interaction). A subgroup analysis showed that in immunocompromised, but not immunocompetent patients, initial appropriate antibiotic therapy was associated with lower mortality (30-day mortality 20.5% vs. 66.7%, P < 0.01 by log-rank test).
1 0 0 0 OA 嫌気性細菌による食品加工廃棄物からの水素生成
- 著者
- 水野 修 大原 健史 野池 達也
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 土木学会論文集 (ISSN:02897806)
- 巻号頁・発行日
- vol.1997, no.573, pp.111-117, 1997-08-22 (Released:2010-08-24)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 1 10
豆腐製造工程で排出される残渣「おから」を基質とし, 嫌気性細菌によるおからの分解に伴う水素生成を, 35℃における回分実験により研究した. 固形物濃度を2.3-9.2%の範囲で変化させて, 累積水素生成量および水素生成活性に及ぼす固形物濃度の影響およびおからの分解特性を検討した.最大累積水素生成量は0.020m3・kg VS-1 (固形物濃度6.4%), 累積生成ガスの54-78%は水素であり, 累積水素生成量は固形物濃度による大きな影響を受けなかった. 水素生成は, おからより溶出した溶解性糖濃度の低下に伴って起こり, 主な代謝産物は酢酸, プロピオン酸, n-酪酸およびエタノールであった.
1 0 0 0 OA 日本老年社会科学会に就いて
- 著者
- 渡辺 定
- 出版者
- 社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 老年病 (ISSN:04854349)
- 巻号頁・発行日
- vol.1962, no.Special, pp.299-299, 1962-10-05 (Released:2009-11-24)
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 特集「多感覚コミュニケーション」の編集にあたって
1 0 0 0 OA 1. はじめに
- 著者
- 植松 俊彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床薬理学会
- 雑誌
- 臨床薬理 (ISSN:03881601)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.481-482, 1999-03-31 (Released:2011-02-25)
1 0 0 0 OA 日台経済交流の礎を築いた人々
- 著者
- 根橋 玲子 岸 保行 福岡 賢昌
- 出版者
- 特定非営利活動法人 グローバルビジネスリサーチセンター
- 雑誌
- 赤門マネジメント・レビュー (ISSN:13485504)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.127-158, 2015-03-25 (Released:2016-03-25)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- Ahmed ALI Yasmine ABOULEILA Sara AMER Rie FURUSHIMA Samy EMARA Sebastien EQUIS Yann COTTE Tsutomu MASUJIMA
- 出版者
- The Japan Society for Analytical Chemistry
- 雑誌
- Analytical Sciences (ISSN:09106340)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.2, pp.125-127, 2016-02-10 (Released:2016-02-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 12 40
The locations and volumes of the contents of a single HepG2 cell were visualized under three-dimensional (3D) holographic and tomographic (HT) laser microscopy, colored by refractive index, not staining. After trapping the specific area of a target cell in a nanospray tip, quantification was performed by live single-cell mass spectrometry. Comparison of the HepG2 cells’ before and after 3D-HT images allowed the inference of the precise volume and original location of the trapped cell contents. The total amount of a trapped molecule was estimated. The images also revealed morphological changes in the cell structure caused by the manipulation.
1 0 0 0 OA フェノール製造プロセスの推移
- 著者
- 篠原 好幸
- 出版者
- 社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.138-146, 1977-02-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 40
- 被引用文献数
- 1 2
フェノールは合成樹脂, 合成繊維, 農医薬, 界面活性剤等の原料中間体として有機化学工業における重要な基礎物質の一つである。現在全世界で約300万トン以上使用されている。フェノールはF.F.Rungeによって1834年コールタール中より発見され, Karbolsäaure (石炭酸) と命名された。19世紀後半における有機化学工業の発達にともない, フェノールはコールタール中のタール酸より分留により工業的に製造されるようになった。フェノール誘導体の伸張はタール分留のみによる供給に不足をきたし, 合成法が研究され, ベンゼンスルフォン化法 (硫酸法) が1890年代にドイツで企業化された。フェノールは軍用火薬ピクリン酸の原料としても大量使用され, 第1次, 第2次大戦において合成フェノール工業は急速に拡張され, 硫酸法の改良, 塩素化法の企業化等の技術的な発達を促した。第2次大戦中アメリカで発達した石油化学工業はフェノール合成法にも原料, 技術の面で大幅な進展を遂げ, ラッシヒ法の工業化, クメン法の発見, 工業化技術の完成, トルエン法の企業化と目覚ましい展開を見るに至った。現在全世界のフェノールは90%以上が合成法により供給され, コークス炉ガス, コールタール, 石油よりの回収いわゆる天然フェノールは10%以下である。また合成法の80%はクメン法によって生産されている。本稿はフェノール合成法の概略について歴史的に振り返り, 技術的経済的問題についても述べたい。