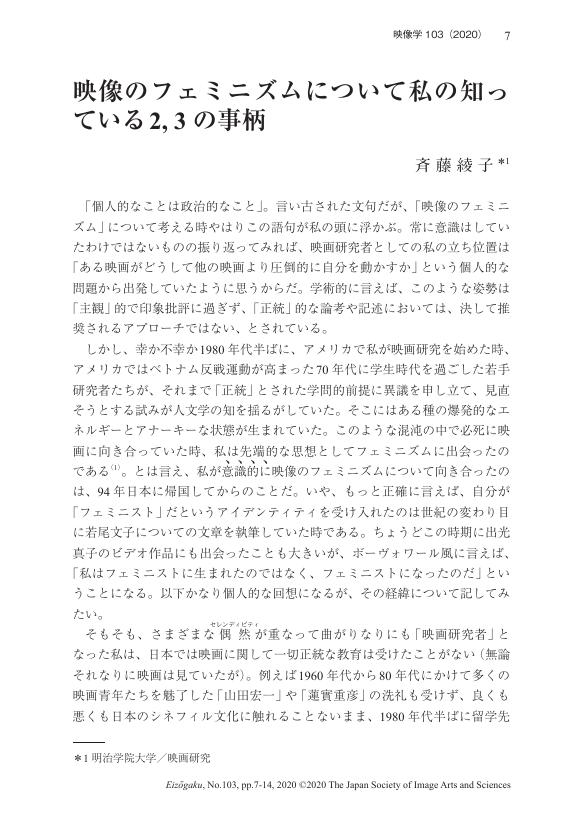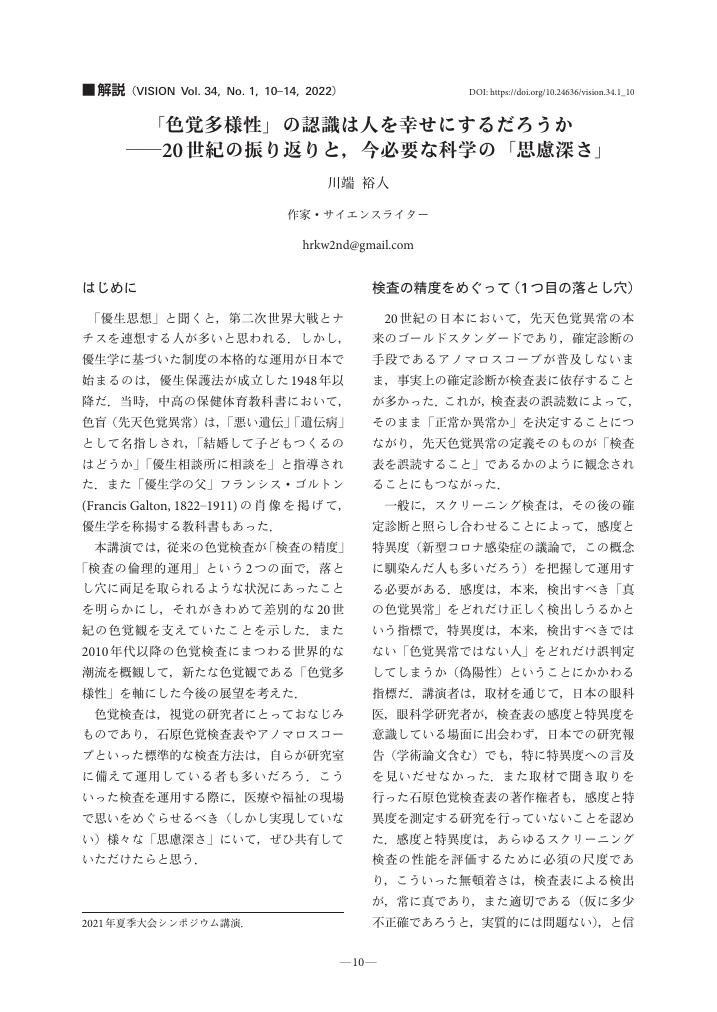55 0 0 0 OA 映像のフェミニズムについて私の知っている2, 3の事柄
- 著者
- 斉藤 綾子
- 出版者
- 日本映像学会
- 雑誌
- 映像学 (ISSN:02860279)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, pp.7-14, 2020-01-25 (Released:2020-02-25)
55 0 0 0 バーチャルシンガーを実在化させる技術と演出の実践的報告
- 著者
- 佐久間 洋司 PIEDPIPER
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.4, pp.494-501, 2023-07-01 (Released:2023-07-01)
55 0 0 0 OA 不確定性原理・保存法則・量子計算
- 著者
- 小澤 正直
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.3, pp.157-165, 2004-03-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 39
古典力学は,過去の状態を完全に知れば,それ以後の物理量の値を完全に知りうるという決定論的世界観を導いたが,量子力学は,測定行為自体が対象を乱してしまい,対象の状態を完全に知ることはできないことを示した.ハイゼンベルクは,不確定性原理により,このことを端的にかつ数量的に示すことに成功したといわれてきたが,測定がどのように対象を乱すのかという点について,これまでの関係式は十分に一般的ではなかった.最近の研究により,この難点を解消した新しい関係式が発見され,これまで個別に得られてきた量子測定の精度や量子情報処理の効率の量子限界を統一的に導く第一原理の役割を果たすことが明らかになってきた.
- 著者
- 大沢 文夫
- 出版者
- 素粒子論グループ 素粒子論研究 編集部
- 雑誌
- 素粒子論研究 (ISSN:03711838)
- 巻号頁・発行日
- vol.112, no.6, pp.F155-F171, 2006-03-20 (Released:2017-10-02)
- 被引用文献数
- 1
55 0 0 0 OA 東京電力のトラブル隠し事件と2006年以降の津波想定の比較分析 行動倫理学の観点から
- 著者
- 松井 亮太
- 出版者
- 日本経営倫理学会
- 雑誌
- 日本経営倫理学会誌 (ISSN:13436627)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, pp.117-133, 2019-02-28 (Released:2019-05-27)
This paper conducted a comparative analysis about the falsification scandal uncovered at the nuclear department of the Tokyo Electric Power Company(TEPCO)in the 2000s and the insufficient tsunami risk assumption prior to the Fukushima nuclear accident which occurred in 2011 from a behavioral ethics standpoint. For the information source, I used the external lawyer investigation reports of the falsification scandal and the official investigation reports of the Fukushima nuclear accident. This paper also used the testimonies of the government investigation committee on the Fukushima nuclear accident which were publicly disclosed in 2014. As a result of the analysis, the common factors for the falsification scandal and the insufficient tsunami risk assumption were egocentric bias, loss framing, and moral licensing. In order to prevent unethical behavior and risk neglect, I made two recommendations based on the previous researches of behavioral ethics.
55 0 0 0 OA 近代真宗本願寺派の中国における活動
- 著者
- 野世 英水
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.2, pp.1015-1011, 2008-03-20 (Released:2017-09-01)
55 0 0 0 OA 声優が朗読する「女生徒」を聴く 声と実在性の捉え方
- 著者
- 広瀬 正浩
- 出版者
- 昭和文学会
- 雑誌
- 昭和文学研究 (ISSN:03883884)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, pp.15-27, 2015 (Released:2022-11-19)
55 0 0 0 OA 人はなぜ音読をするのか
- 著者
- 高橋 麻衣子
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.1, pp.95-111, 2013 (Released:2013-09-18)
- 参考文献数
- 108
- 被引用文献数
- 3 2
書き言葉を読んで理解する能力は活字媒体から情報を取得するために必要な能力であり, これを効果的に育成することは学校教育の大きな目標の一つである。読解活動の形態には大きく分けて音読と黙読が存在するが, 読解指導の場面では最終的に黙読での読解能力を習得させることを目的としている。本論文では, 読解能力の発達段階によって音読が読解過程に及ぼす影響はどのように異なるのか, そして, 黙読での読解能力を習得する上で音読はどのような役割を担うのかを考察することを目的とした。まず, 成人と児童それぞれにおける音読の有用性を検討し, 読み能力によって音読の役割が異なることを示した。特に児童においては, 読解中に利用可能な認知資源の量が少なくても, 構音運動や音声情報のフィードバックによって音韻表象を生成し利用できることが, 音読の利点として挙げられた。そして, 読解中の音韻表象の生成と眼球運動のコントロールに着目して, 音読から黙読への移行についての仮説的モデルとこれに即した指導法を提案し, 今後の課題を述べた。
55 0 0 0 OA わが国における研究不正 公開情報に基づくマクロ分析(1)
- 著者
- 松澤 孝明
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.156-165, 2013-06-01 (Released:2013-06-01)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 6 13 3
本報告は,研究不正に対する関心の高まりを受け,その低減を図る観点から,わが国の研究不正についてマクロ分析を行ったものである。筆者は,データの捏造,改ざんおよび盗用を含む科学における不正行為について公開情報を収集し,必要に応じて,不正行為の発覚から,調査,確定までのプロセスを整理することにより,わが国の研究不正の特徴について考察を行った。
55 0 0 0 OA 心理学史におけるLittle Albertをめぐる謎
- 著者
- 高砂 美樹
- 出版者
- 一般社団法人 日本行動分析学会
- 雑誌
- 行動分析学研究 (ISSN:09138013)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.128-134, 2019-02-10 (Released:2020-02-10)
- 参考文献数
- 16
John B. Watsonの条件性情動反応の研究(Watson & Rayner, 1920)に出てくるAlbert B.として知られるLittle Albertは本当は誰だったのだろうか。この9か月齢の子どものことは心理学史ではよく知られてきたが、Albertは実験の後に生後ずっと暮らしていた大学病院から連れていかれ、その後どうなったかについては何の手掛かりもなかった。近年になって、Beck et al. (2009)は、Little Albertは実際にはDouglas Merritteという名前の子どもで、1922年に水頭症を患い、1925年に亡くなっていると主張した。さらに2012年の研究でBeckのグループはAlbertの神経学的障害の徴候を見落としていたと報告し、もしそれが事実であったならばWatsonがこの子どもを虐待していたことになることを示唆した。しかしながら、2014年になると、もう一つのグループの心理学者らがAlbert Bargerという別の子どもをより適切なAlbert B.の候補として同定した。本論ではLittle Albertを探す一連の論争について概観する。
55 0 0 0 OA 「色覚多様性」の認識は人を幸せにするだろうか――20世紀の振り返りと,今必要な科学の「思慮深さ」
- 著者
- 川端 裕人
- 出版者
- 日本視覚学会
- 雑誌
- VISION (ISSN:09171142)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.1, pp.10-14, 2022-01-20 (Released:2022-02-01)
- 参考文献数
- 7
55 0 0 0 OA 頭部伝達関数の計測とバイノーラル再生にかかわる諸問題
- 著者
- 平原 達也 大谷 真 戸嶋 巌樹
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 基礎・境界ソサイエティ Fundamentals Review (ISSN:18820875)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, no.4, pp.4_68-4_85, 2009-04-01 (Released:2011-05-01)
- 参考文献数
- 109
- 被引用文献数
- 5 5
音源信号に頭部伝達関数が畳みこまれたバイノーラル信号によって立体音像空間を再現する場合に,頭部伝達関数やバイノーラル信号再生系の音響的な厳密さが重要視されている.しかし,受聴者の頭部運動に追従する動的バイノーラル信号を用いると,頭部伝達関数やバイノーラル信号再生系に要求される音響的厳密性を緩和できる.本解説では,複数箇所で多数回計測した実頭とダミーヘッドの頭部伝達関数を精査し,頭部伝達関数の音響計測の問題点,頭部形状の変形に伴う頭部伝達関数の変化,および,頭部伝達関数の比較尺度について論じる.また,様々なバイノーラル信号を用いた一連の音像定位実験の結果に基づいて,静的バイノーラル信号と動的バイノーラル信号が再現する立体音像空間の差異についても論じる.これらを通じて,頭部伝達関数の計測とバイノーラル信号の再生にかかわる諸問題について論考する.
55 0 0 0 OA 焼酎の経肛門的投与により発症した化学的(アルコール性)直腸結腸炎
- 著者
- 河村 攻 澤田 武 原 威史 兒玉 達樹 真田 治人 島崎 正晃 麦倉 光哉 西田 泰之 大原 裕康 松下 和彦
- 出版者
- Japan Gastroenterological Endoscopy Society
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.6, pp.1019-1022, 2002-06-20 (Released:2011-05-09)
- 参考文献数
- 9
症例は45歳の男性で,肛門からアルコール濃度35%の焼酎を注入したところ下.血を生じ,当院へ入院した.大腸鏡検査では,肛門からS状結腸下部まで連続性に潰瘍,びらん,発赤,浮腫が見られた.病変部と健常粘膜との境界は明瞭であった.組織像では表層にちかづくほど粘膜の著しい壊死,脱落が見られ,腺管構造の破壊,血管の破綻による出血,滲出が見られた.アルコール注腸による直腸結腸炎は極めてまれであり貴重な症例である.
55 0 0 0 OA 奄美大島における自動撮影カメラによるアマミノクロウサギの離乳期幼獣個体へのイエネコ捕獲の事例
- 著者
- 鈴木 真理子 大海 昌平
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.241-247, 2017 (Released:2018-02-01)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 2
イエネコFelis catusによる在来種の捕食は,日本においても特に島嶼部において深刻な問題である.鹿児島県奄美大島と徳之島にのみ生息する遺存固有種アマミノクロウサギPentalagus furnessiの養育行動を2017年1月から3月にかけて調査していたところ,繁殖穴で離乳間近の幼獣がイエネコに捕獲される動画を自動撮影カメラによって撮影したので報告する.繁殖穴における出産は2017年1月14日~15日の夜に行われたが,幼獣(35日齢)がイエネコに捕獲されたのは2月19日1時ごろで,この前日は繁殖穴を母獣が埋め戻さずに入り口が開いたままになった初めての日であった.この動画の撮影後,幼獣は巣穴に戻っていないことから,捕食あるいは受傷等の原因で死亡した可能性が高い.イエネコは幼獣の捕獲から約30分後,および1日後と4日後に巣穴の前に出現し,一方アマミノクロウサギの母獣は1日後に巣穴を訪問していた.幼獣の捕食は,本種の個体群動態に大きな影響を与えうる.本研究により,アマミノクロウサギに対するイエネコの脅威があらためて明らかとなった.山間部で野生化したイエネコによるアマミノクロウサギ個体群への負の影響を早急に取り除く必要がある.
55 0 0 0 OA 鉄道忌避伝説に対する疑問
- 著者
- 青木 栄一
- 出版者
- 日本地理教育学会
- 雑誌
- 新地理 (ISSN:05598362)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.4, pp.1-11, 1982-03-25 (Released:2010-04-30)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 1
There have been many oral traditions relating to oppositions against railway constructions in the early period of railway development in Japan. The most famous oral traditions have been in Shukubamachis (towns or villages with facilities for relay post-horse), where the inhabitants had There have been many oral traditions relating to oppositions against railway constructions in the early period of railway development in Japan. The most famous oral traditions have been in Shukubamachis (towns or villages with facilities for relay post-horse), where the inhabitants had opposed to railway constructions for fear of losing their travel customers. Curiously, however, in Japan, there have been no reliable historical documents relating to the oppositions, or no historical articles certifying the facts of oppositions, using reliable records. Many stories of railway opposition have remained in vague condition from a view-point of positivism, today. The author insists that it is necessary to prove the fact of railway oppositions, through the following procedures. They are, (1) discovery of reliable documents written contemporaneously, (2) consideration to policies and general opinions about railways on the day, and (3) investigation of ideal rail-routes in relation to topographic feature and railway track gradient (25‰ in maximum gradient in case of Japanese trunk railways).There were two periods of railway mania in Japan, in the closing years of 19th Century, 1885-90 and 1894-99. In those days, inhabitants of rural towns made passionate movement to raise their fund for private railway construction, or to introduce national railways to their towns. It is unreasonable to suppose railway oppositions in those days without showing any reliable documents. As for the Kobu Railway, between Tokyo and Hachioji (opened in 1889), having famous oral traditions of railway opposition by shukubamachis along a traditional trunk road, we have no reliable records to prove the existence of oppositions, and many preserved documents showing the insistence of introduction of railway construction in those days, showed the decision in ideal rail-route in relation to topographic feature and track gradient.There were some categories of railway oppositions, capable to certifying their existence by reliable documents. They were, (1) the oppositions to coastal or riverside railways, which compete with steamship operations, by officers of national railways, (2) the oppositions by military authorities or conservative samurais (feudal warriors) class, insisted the precedence of military expansion or anti-foreign spirit, and (3) the oppositions by farmers, protested the change for worse utilization of water in paddy field, because of the construction of embankment for railways. The first and second categories had lasted by about 1880s and 1870s, respectively, but the third one has continued toward the 20th Century. The author presents some examples belonging to the first and the third categories of oppositions during the Meiji Era (1868-1912) in this article.
55 0 0 0 OA 私のブックマーク:不均衡データ分類
- 著者
- 大崎 美穂
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能 (ISSN:21882266)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.376-381, 2022-05-01 (Released:2022-05-01)
- 著者
- 志賀 隆
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.375-383, 2013-11-30 (Released:2017-04-28)
- 参考文献数
- 49
55 0 0 0 OA 二酸化炭素濃度と気候変動史
- 著者
- 大嶋 和雄
- 出版者
- 石油技術協会
- 雑誌
- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.4, pp.300-309, 1991 (Released:2008-03-27)
- 参考文献数
- 19
On the geological scale, earth history yields vital information concerning past environments and climates. This highlights the urgency for increased collaborative international response and research into solutions of problems posed by current climatic changes, whether natural or induced by the activities of man. Climatic changes occur on variety of timescales, ranging from catastrophic volcanic eruptions (minutes or days), through gradual changes in Earth's orbital parameters (104-106 years) to tectonically driven changes (106-108 years). It seems likely that the long-term fluctuations of climates (less than the time-scale of planetary evolution), which give rise to glacial epochs, are largely determined by continental plate distributions and movement, whilst the shorter-term fluctuations which produce glacial and inter-glacial periods in glacial epochs reflect variations in coming solar radiation.Attention is focussed on the possible existence of an anoxygenic, primeval atmosphere and on the history of atmospheric CO2. Five great biologic revolutions have occurred through earth history that have fundamentally shaped the modern geochemical picture. It is significant that organisms have controlled their own environment. Organic CO2 and calcium budget have played critical roles.
55 0 0 0 OA 減量しながら筋肉量および基礎代謝量を高めることは可能か?
- 著者
- 田中 喜代次 中田 由夫
- 出版者
- 一般社団法人日本体力医学会
- 雑誌
- 体力科学 (ISSN:0039906X)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.3, pp.209-212, 2017-06-01 (Released:2017-05-17)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
Most people who go to fitness clubs or sports gyms for weight control, and many co-medicals and physicians believe that an increase in muscle mass and/or basal metabolic rate (BMR) is possible through a combination of regular exercise and optimal protein intake during weight loss. This seems a myth, and the reasons are discussed in this article. First, muscle mass is quite difficult to quantify. The limitations of body composition measurement should be well understood. Second, increasing muscle mass during weight loss is difficult. This might be attained through strict implementation of a protein-rich, low-carbohydrate diet; high-intensity resistance training; and aerobic exercise for a long duration. However, such a strict regimen is not feasible for most people. Finally, a 1-kg increase in muscle mass corresponds to an increase of only 13 kcal of BMR per day. Thus, an increase in muscle mass of 1 kg is difficult to achieve, while the gained BMR is approximately equivalent to a decrease of 13.5 kcal of BMR according to a 3-kg decrease of adipose tissue. Weight loss, unless through an extremely sophisticated weight control program, contributes to a decrease in BMR. However, it is an accomplished fact that women with significantly less muscle mass and lower BMR live longer than men with more muscle mass and higher BMR, regardless of ethnicity. Maintaining activities of daily living and daily activity function might be more essential.
55 0 0 0 OA ジャポニカ米を用いた米粉麺の調製条件と力学的特性の検討
- 著者
- 中津川 かおり 喜多 記子 植草 貴英 田代 直子 長尾 慶子
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成16年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.62, 2004 (Released:2004-09-09)
[目 的]米粉を主原料とした麺には、中国のビーフンやベトナムのフォーが代表的である。一般に諸外国で普及している米粉麺は、アミロース含量の高いインディカ米を主原料とし、独特のコシと歯ごたえを有するのが特徴である。そこで、ジャポニカ米の中でもアミロース含量が約20%のうるち米を用いた米粉麺の調製条件の検討とテクスチャーの改良並びに米の第一制限アミノ酸であるリジンの補足効果を目的として実験を行った。<BR>[方 法]インディカとジャポニカ種の精白米各々を一晩浸漬後ミキサーで粉砕し、50%米粉液を調製した。これを5倍希釈し、攪拌加熱(75_から_90℃)したゾルの流動特性をE型粘度計により測定した。またDSC及び光学顕微鏡観察により糊化特性を比較検討した。次いで各々の50%米粉液を65_から_75℃で半糊化させ、製麺後、蒸し加熱し、力学的測定と官能評価を行った。さらにジャポニカ種の品質改良のためタピオカ澱粉を添加した試料並びにアミノ酸の補足効果のため豆乳を添加した試料についても同様の測定を行った。<BR>[結 果]ジャポニカ種米粉ゾル(90℃加熱)は、高粘度でチキソトロピー性が顕著であった。DSC及び光学顕微鏡観察の結果、インディカ種の糊化温度がより高いことを確認した。タピオカ澱粉添加のジャポニカ種米粉ゾルはチキソトロピー性が低下し、豆乳添加では増大した。何れもCasson解析で降伏値の増大を確認した。米粉麺においてジャポニカ種は軟らかく、付着性が高く、官能検査での評価が低かったが、タピオカ澱粉や豆乳添加により無添加麺よりも総合的に高い評価を得た。(尚、演者は東横学園女子短期大学非常勤講師であり、実験は東京家政大学調理科学研究室の協力の基に行った。)