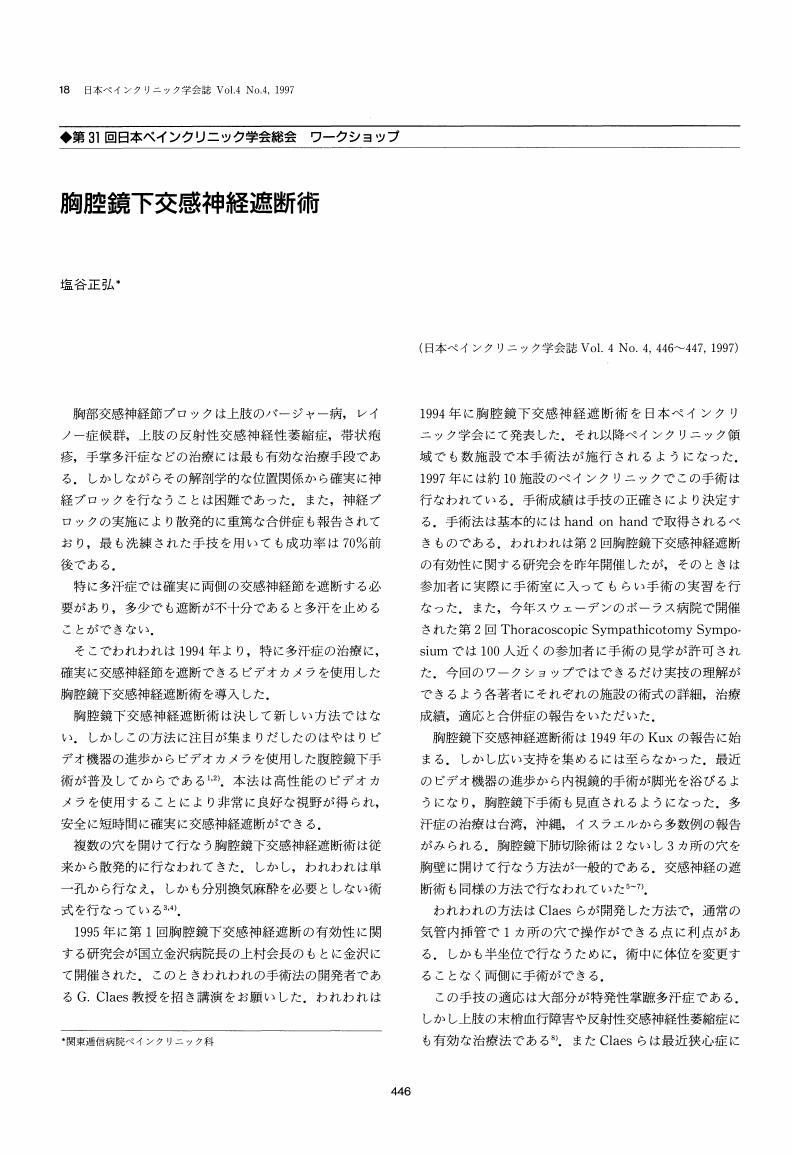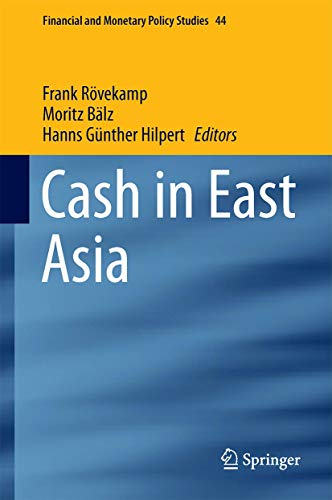1 0 0 0 OA 成人における座位行動および身体活動の日内パターン― システマティックレビュー ―
- 著者
- 黒澤 彩 柴田 愛 石井 香織 澤田 亨 樋口 満 岡 浩一朗
- 出版者
- 日本運動疫学会
- 雑誌
- 運動疫学研究 (ISSN:13475827)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.5-19, 2019-03-31 (Released:2019-06-14)
- 参考文献数
- 52
- 被引用文献数
- 1
目的:座位行動や身体活動の日内パターンの解明を主目的とした研究についてシステマティックレビューを行い,これまでの知見を整理し,今後の課題を明らかにすることを目的とした。方法:5つの文献データベースで検索した論文について,採択基準(成人,時間帯別の座位行動または身体活動に関する内容を含むなど)を基に該当論文を選定し,1)座位行動および身体活動の日内パターンの分布・傾向,2)座位行動および身体活動の日内パターンに関連する要因,3)座位行動および身体活動の日内パターンと健康アウトカムの関連という3つの観点から整理した。結果:採択論文27編のうち,2015年以降欧米や豪州の高齢者層を中心に,加速度計法で評価した座位行動や身体活動を1時間ごと,あるいは1日を3つに区分して検討した研究が主流であった。分布・傾向を検討した12編の主な傾向として,日内の遅い時間帯で座位行動レベルの上昇と身体活動レベルの低下がみられた。また,関連要因を検討した21編の多くで,性別や年齢,肥満度と座位行動や身体活動パターンに関連がみられた。健康アウトカムとの関連を検討した研究は1編のみであった。結論:座位行動や身体活動の日内パターンを検討した論文は少なく,対象者の居住地域や年齢,扱われた関連要因や健康アウトカムに偏りがあった。 セグメント化した介入のため,今後は対象者の特性別,特に我が国の壮年・中年層を含めた研究成果の蓄積が必要である。
1 0 0 0 OA M.ブーバーとE.ゴッフマン G.ベイトソンの視角から
- 著者
- 阪本 俊生
- 出版者
- 社会学研究会
- 雑誌
- ソシオロジ (ISSN:05841380)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.2, pp.77-96,187, 1988-09-30 (Released:2017-02-15)
E.Goffman's argument undoubtedly owes a lot to G.Bateson. Above all, one of Goffman's main concepts 'frame' is obviously inherited from Bateson and used in accordance with his originally intended meaning. Therefore, it will be meaningful to consider Bateson in order to gain a clearer idea of Goffman's viewpoint. Bateson's introduction of the theory of "logical-types" in relation to the study of social communication, which can be considered to be the main point of his 'double-bind theory', is, of course, immediately concerned with 'frame'. And the dynamic property of Goffman's arguement in "Frame Analysis" can be considered in part a product of this Bateson's idea. This paper attempts to make a comparison between the sociology of E.Goffman and that of M.Buber from Bateson's unique point of view. In various aspects, Buber sociology is thought to be the opposite of Goffman's. It is the above mentioned insight of Bateson that can be used here to describe the contrast between these two antipodal scholars. Each of the directions they took is asserted to be correspondent to two principal 'ethoses' of Western society, that is to say, love and skepticism. By examining Buber's ethos of love and Goffman's ethos of skepticism, the significance of the angle that Goffman takes can be reconsidered.
1 0 0 0 OA 地下空間の水害リスクに関する検討
1 0 0 0 OA 鈴木大拙はどうして初期禅宗史研究を始めたか
- 著者
- 伊吹 敦
- 出版者
- 東洋大学東洋学研究所国際禅研究プロジェクト
- 雑誌
- 国際禅研究 = INTERNATIONAL ZEN STUDIES (ISSN:24338192)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.131-195, 2020-11
1 0 0 0 OA 細線加熱法による粘度測定とプロセス・コントロール
1 0 0 0 OA 細線加熱法による流体の粘度計測技術の開発
- 著者
- 堀 友繁
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.52-56, 1988-01-15 (Released:2011-02-17)
- 参考文献数
- 34
1 0 0 0 OA 細線加熱法による粘度測定指標値の特性
- 著者
- 堀 友繁
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- 日本食品工業学会誌 (ISSN:00290394)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.6, pp.461-466, 1993-06-15 (Released:2010-01-20)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 胸腔鏡下交感神経遮断術
- 著者
- 塩谷 正弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本ペインクリニック学会
- 雑誌
- 日本ペインクリニック学会誌 (ISSN:13404903)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.4, pp.446-447, 1997-10-25 (Released:2009-12-21)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 Cash in East Asia
- 著者
- Frank Rövekamp Moritz Bälz Hanns Günther Hilpert editors
- 出版者
- Springer
- 巻号頁・発行日
- 2017
1 0 0 0 OA 鈴木大拙における禅仏教の論理と民族主義
- 著者
- 元 永常
- 出版者
- 日本印度学仏教学会
- 雑誌
- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.1129-1124, 2009-03-20 (Released:2017-09-01)
- 著者
- 福岡 梨紗 五味 郁子
- 出版者
- 公益社団法人 日本栄養士会
- 雑誌
- 日本栄養士会雑誌 (ISSN:00136492)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.277-284, 2022 (Released:2022-05-01)
- 参考文献数
- 25
本研究は、訪問診療利用高齢者の栄養状態の評価・判定を行い、「低栄養」または「低栄養のおそれあり」に判定された者かつ、「食べることに対する義務感がある」者を「摂食困難」と定義し、在宅療養高齢者の摂食困難の実態として、対象者の属性や身体計測値、栄養・食事に対する自己評価との関連を検討した。対象者は、A市内の診療所Bの訪問診療を月1回以上利用している65歳以上の療養者28人であった。MNA®-SFにて、「低栄養」および「低栄養のおそれあり」と判定された者は21人(75.0%)、「栄養状態良好」と判定された者は7人(25.0%)であった。前者のうち、「食べることに対する義務感がある」摂食困難群に該当する者は10人(35.7%)、「食べることに対する義務感がない」非摂食困難群に該当する者は11人(39.3%)であった。摂食困難群の平均年齢は78.5±7.1歳であり、3群間に有意な差は認められなかったが、非摂食困難群86.3±7.5歳と比較し、有意に低値を示した(p=0.025)。BMI、%AMCは、3群間に有意な差が認められ(p=0.043)(p=0.027)、摂食困難群は良好群と比較し有意に低値を示した。訪問診療利用高齢者は、低栄養のリスクが高いことが明らかになった。 また、摂食困難群が持つ食べることに対する義務感は、在宅療養高齢者の年齢が低いことが関係していることが示唆された。
1 0 0 0 安定なジアゾ移動剤の開発―グアニジノジアゾニウム塩の合成と反応
- 著者
- 北村 充
- 出版者
- 公益社団法人 有機合成化学協会
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.14-25, 2014-01-01 (Released:2014-03-04)
- 参考文献数
- 87
- 被引用文献数
- 8 13
2-Azido-1,3-dimethylimidazolinium chloride (ADMC) and its corresponding hexafluorophosphate (ADMP) were found to be safe and efficient diazo-transfer reagents to various organic compounds. ADMC was prepared by the reaction of 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride (DMC) and sodium azide. ADMP was isolated as a crystal having thermal stability and low explosibility. ADMC and ADMP reacted with 1,3-dicarbonyl compounds under mild basic conditions to give 2-diazo-1,3-dicarbonyl compounds in high yields, which are easily isolated because the by-products are highly soluble in water. Naphthols also reacted with ADMC to give corresponding diazonaphthoquinones in good to high yields. Furthermore, ADMP shows efficient diazo-transfer ability to primary amines even without the aid of a metal salt such as Cu(II). Using this diazotization approach, various alkyl/aryl azides were obtained directly from corresponding primary amines in high yields. In addition, ADMC/ADMP could be used as azide-transfer and amidation reagents.
1 0 0 0 OA オイラーの公式の一般化とその整数論への応用 –アイゼンシュタイン三角形に関連して–
- 著者
- 高村 明
- 出版者
- 独立行政法人 国立高等専門学校機構豊田工業高等専門学校
- 雑誌
- 豊田工業高等専門学校研究紀要 (ISSN:02862603)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, pp.51-12, 2019 (Released:2019-02-12)
3辺の長さが整数であって,1つの角度が120◦(あるいは60◦)の三角形は(あるいは半角)アイゼン シュタイン三角形と呼ばれる.アイゼンシュタイン三角形の3辺を求める問題は,楕円上の有理点を求める 問題に翻訳することが出来る.その一方,オイラーの公式を一般化することで楕円上の点を表す新しい関数 が定義できる.この新しい関数は三角関数と類似の加法定理を満たす.この新しい関数を,このノートでは 楕円型2次曲線関数と呼ぶことにする.このノートの後半では,この楕円型2次曲線関数を整数論へ応用す る.アイゼンシュタイン三角形の有理点を与えるパラメータ公式が,この楕円型2次曲線関数の半角の公式 から導けることを示す.
1 0 0 0 OA 神経筋疾患におけるNPPVインターフェイスとしてのマウスピース活用
- 著者
- 高田 学 竹内 伸太郎 石川 悠加
- 出版者
- 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
- 雑誌
- 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 (ISSN:18817319)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.1, pp.131-136, 2014-04-30 (Released:2015-11-13)
- 参考文献数
- 18
神経筋疾患の非侵襲的陽圧換気療法(noninvasive positive pressure ventilation; NPPV)の覚醒時インターフェイスとして,マウスピースを活用した.マウスピース使用経験のある17名を対象に,導入と中止など使用状況を調査し,マウスピースの利点と問題点について検討した.導入は,覚醒時NPPVが必要になった時期であった.中止は,疾患進行によってマウスピースを使いこなすための体幹や頸部の運動機能や口唇の力が低下してきた時期で鼻プラグなどに変更した.マウスピースの利点は,視野が広く皮膚への侵襲がなく,自身でマウスピースをくわえたり離したりすることで,NPPVの開始と中断を自由にコントロールできることである.このため,NPPVの合間に飲食や会話がしやすい.しかし,マウスピースを口元から離しているときに低圧アラームを制御する工夫を要する.マウスピースによるNPPVは,適応や導入時期,使用方法により有効活用が可能である.
- 著者
- Campana Maurizio
- 雑誌
- 阪南論集.人文自然科学編
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.69-82, 2019-03
1 0 0 0 ユーザ同士のインタラクションを抽出するIoTシステムの研究開発
1 0 0 0 OA ザンジバルにおける日本製タイルの流通と利用―タイル考古学的アプローチ―
- 著者
- 増田 研 深井 明比古
- 出版者
- 長崎大学多文化社会学部
- 雑誌
- 多文化社会研究 = Journal of Global Humanities and Social Sciences, Nagasaki University (ISSN:21891486)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.29-53, 2019-03-18
日本と東アフリカのあいだのヒト、モノ、情報の交流は、いわゆる「日本-アフリカ交流史」として1960年代から少しずつその実態が明らかにされてきた。なかでも近代の人的交流については多くのことが判明しており、九州北部地域出身の人々がすでに明治時代から東アフリカに居住していたことが分かっている。本研究は日本-アフリカ交流史の探求において手薄であった「モノの交流」を明らかにする取り組みの一環として、日本製タイルの流通に着目するものである。筆者らは2017年から2018年にかけてタンザニアのウングジャ島(ザンジバル)にて日本製タイルが墓地やホテルにおいて使用され、かつ、骨董品として流通している状況を確認し記録した。こうした日本製タイルの多くは大正時代から昭和初期にかけて淡路島や名古屋、岐阜で生産されたものである。本論文ではそうしたタイルの「身元」を、考古学的手法を用いて同定し、その使用実態を記述することを通して、20世紀前半に日本製タイルが東アフリカにまで流通していたことを主張する。
1 0 0 0 OA 広島市、天満川におけるタイル散布地:生活史へのタイル考古学的アプローチ
- 著者
- 増田 研 深井 明比古 マスダ ケン フカイ アキヒコ Ken Masuda Akihiko Fukai
- 雑誌
- 半田山地理考古
- 巻号頁・発行日
- vol.8, pp.1-15, 2020
- 著者
- 増田 研 深井 明比古
- 出版者
- 長崎大学多文化社会学部
- 雑誌
- 多文化社会研究 = Journal of Global Humanities and Social Sciences, Nagasaki University (ISSN:21891486)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.305-317, 2021-03-23
長崎市南山手の旧レスナー邸は明治中期に建築された、長崎洋館群の一画をなす建物である。この建物の玄関部ポーチに敷かれたタイルについてはいくつかの文献において紹介されているが、その由来については不明なままであった。本稿はこの玄関部ポーチで用いられたタイルを詳細に記述し、長崎における洋館建築史への一助としたい。また、玄関ポーチのタイルについては損傷が著しく、保存や修復のためにもその現況を詳細に記していくことが必要である。“Sigmund Lessner’s House” is a western-style building constructed in the Meiji era (late 19 c). While its floor tiles used at the entrance porch were introduced in several publications, no details were mentioned. This is a brief report of our preliminary research conducted in February 2020 to record a detailed description. We found four types of ceramic tiles used, among which several types are made in Belgium and others are made in Japan. The made-in-Japan tiles are products of Awaji-seito factory of Awajishima (Hyogo prefecture) that are not well-known even among the study of industrial history of ceramic tiles. Our research also discovered the floor tiles are so damaged that an engineering assistance to preserve the historical heritage is recommended.
1 0 0 0 OA 「福島県庁舎」の設計と建設の過程
- 著者
- 速水 清孝
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.734, pp.1039-1049, 2017 (Released:2017-04-30)
This study is a report on the design and construction process of “Fukushima Prefectural Government Office Building (1954)”. This building was designed by Koichi Sato (1878-1941). It began to construct from 1938 before WWII but completion was in 1954 after WWII and designed by Takekuni Ikeda (1924- ) who belonged to Toshiro Yamashita Architects Firm. Namely, on this building, two architects, who were famous for Japanese modern architectural history, were involved until completion. But information more than that, for example, the details of design before WWII and competition after WWII is not clear. In this study, author tried to find it by the newspaper articles and the document which remains in government office. The results are as follows: 1. This building project was begun earlier than “Shiga Prefectural Government Office Building” project which was the final completion before WWII. Nevertheless, it was not completed by delay of preparation of the construction materials. Author clarified the development process of the design of this building. Koichi Satoh designed five prefectural government office buildings. From the view of Satoh's careers of architectural work, this is the largest scale, the design which reflected all of his method of prefectural government buildings. And in case of “Shiga Prefectural Government Office Building”, he collaborated with Hiroshi Kunieda on the detail design phase. But in case of this, he designed alone. From these points, author showed that this building should be thought the grand sum for him in his prefectural government office building designs. 2. At first this building was designed in Reinforced Concrete Structure. But the construction of this building was cancelled after finishing first floor in 1939. After that, in 1940, this building extended second floor designed by Koichi Satoh by wooden frame structure. This extension is “Fukushima Prefectural Government Office Temporary Building” which no one knows in his architectural works. Author found its' outside appearance. 3. Author clarified, to some extent, the detail of the nomination design competition held in 1952. About this competition, only Takekuni Ikeda, who joined this as a chief designer of Toshiro Yamashita's Architect Firm wrote, but no one knows more than that. Four architects, who were Toshiro Yamashita, Yoshitoki Nishimura, Gumpei Matsuda, and Takeo Satoh, submitted their design for this competition. And Design Committee consisted of three referees, who were Hideto Kishida, Denji Nakamura, and Seiichi Kobayashi, chose Yamashita's design. Author found three designs to four submissions. As a result of comparison, instead of the design like a symbol of the authoritarianism before WWII, referees seek the design like a symbol of the democracy, and they finally chose Yamashita's design.