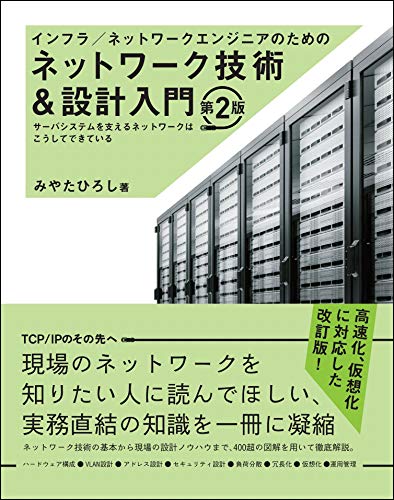1 0 0 0 OA 19世紀アメリカにおける有料道路建設 : 北東部諸州を中心として
- 著者
- 加勢田 博
- 出版者
- 關西大学經済學會
- 雑誌
- 關西大學經済論集 (ISSN:04497554)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.3-4, pp.401-419, 2004-11-11
19世紀初頭に始まるアメリカ工業化への助走は、生産組織や技術進歩にみられる多くの革新に加えて、国内市場の拡大に繋がる交通の改良によってはじめて人や物の移動および情報の伝達をスムーズにし、大量生産をその最大の特徴とする工業化時代の到来を可能にした。本稿では、この交通改良において重要な役割を演じた有料道路(Turnpike Road)の建設を北東部を中心に概観する。
1 0 0 0 OA 読み書きにつまずきのある子どもに対する学習支援の実際
- 著者
- 林 真理佳
- 出版者
- 明星大学発達支援研究センター
- 雑誌
- 明星大学発達支援研究センター紀要 : MISSION = MISSION (ISSN:21899312)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.7-27, 2022-03-31
【特集:LD-SKAIPによる学習の評価と支援】 2020 年度公開講演会 講演録
- 著者
- 友田 昌宏 安本 篤史 桑谷 立
- 出版者
- 日本情報地質学会
- 雑誌
- 情報地質 (ISSN:0388502X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.47-52, 2020-06-25 (Released:2020-06-25)
- 参考文献数
- 16
電子線マイクロアナライザー(electron probe microanalyzer; EPMA)は,岩石中の鉱物の化学組成の空間分布を定量的に明らかにすることが可能であり,岩石形成プロセスの解明のために大きな威力を発揮する分析装置である.一方,岩石中に多数存在する鉱物種の空間分布を正確に把握し,点分析すべき箇所を適切に決定することは,岩石学の深い知識と経験が必要となり,一般的に容易ではない.本研究では,代表的なクラスター解析手法であるK平均法を基にして,面分析結果から,鉱物の空間分布および各鉱物種の代表組成となりうる座標の候補を出力するプログラムを開発した.
1 0 0 0 OA 内視鏡により摘出しえた大腸異物の3例
- 著者
- 木幡 義彰 宮原 健夫 清水 直樹 渡辺 浩一 内山 和郎 井川 守仁 篠原 靖 白鳥 泰正 窪田 良彦 竹下 俊隆 宮岡 正明 斉藤 利彦 古畑 総一郎 木下 剛 福武 勝秀
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 関東支部
- 雑誌
- 消化器内視鏡の進歩:Progress of Digestive Endoscopy (ISSN:03899403)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.211-214, 1993-12-01 (Released:2015-07-15)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
症例1は51歳男性。腹痛を主訴に入院した。腹部X線検査にて横行結腸と思われる部位に針様陰影を認め,停滞したため大腸内視鏡検査を施行し,生検鉗子を用いて横行結腸より縫い針を摘出した。症例2は61歳女性。義歯誤飲にて受診した。腹部X線検査にて上行結腸に異物を認め,大腸内視鏡検査を施行し,生検鉗子およびポリペクトミー用スネアを用いて義歯を摘出した。症例3は59歳男性。自慰行為にて肛門から挿入したバイブレーターが抜去困難となり受診した。大腸内視鏡検査を施行し,スネアを用いて摘出した。3例とも摘出による合併症の出現はなかった。異物は時に消化管穿孔や出血などをひき起こし,外科的処置が必要となる場合がある。内視鏡的異物摘出は上部消化管においては普及しているが,下部消化管ではまれである。大腸異物の内視鏡的摘出は安全かつ有用な手技であると考えられた。
1 0 0 0 OA 演劇的手法が高校生の自己認知, 対人認知に与える影響
- 著者
- 中田 貴子
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第78回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2AM-1-082, 2014-09-10 (Released:2021-03-30)
1 0 0 0 OA 新體制下に於ける教育家の使命
- 著者
- 加藤 仁平
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育学会
- 雑誌
- 教育学研究 (ISSN:03873161)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.10, pp.1048-1067, 1941 (Released:2009-01-13)
1 0 0 0 OA 242 「規範-基本判断」判定法に基づく道徳性の発達に関する研究(発達5,発達)
- 著者
- 荒木 紀幸 吉田 重郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 日本教育心理学会総会発表論文集 第27回総会発表論文集 (ISSN:21895538)
- 巻号頁・発行日
- pp.104-105, 1985-08-20 (Released:2017-03-30)
1 0 0 0 OA 鉄鋼の相変態 I ─初析フェライト成長における界面の平衡条件とα/γ界面エネルギー─
- 著者
- 榎本 正人
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.1, pp.12-17, 2015 (Released:2015-01-01)
- 参考文献数
- 20
1 0 0 0 OA 患者家族と一般家族の統合失調症に対する社会的距離とイメージ : 多面的調査からの比較
- 著者
- 鋤田 みすず 辻丸 秀策 大西 良 岩永 直美 大岡 由佳 山口 智哉 福山 裕夫 石田 重信 牧田 潔 内野 俊郎 Misuzu Sukita
- 出版者
- 久留米大学文学部
- 雑誌
- 久留米大学文学部紀要. 社会福祉学科編 = "Bulletin of Faculty of Literature, Kurume University. Social welfare" (ISSN:13455842)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.57-67, 2005-03-31
精神障害を持つ家族(患者家族)と精神障害者とかかわりのない家族(一般家族)を対象に統合失病症に対するイメージと社会的距離を多面的調査から検討を行った.その結果,患者家族は一般家族よりも社会的距離は低く,精神障害に対する知識も豊富であることがわかった.しかし,病気に対する知識は豊富であるにもかかわらず,統合失調症に対するイメージは一般家族と変わらず危険なイメージであった.一般家族は,精神障害者と触れ合う機会がないのが現状であったため,主体的な関係として接触経験を行うことの必要性と,啓発活動や施設の開放化などの積極的な活動が大切だということが考えられた.また,患者家族に対しては,家族のニーズを踏まえた上で具体的な情報を提供していくことと生活の中で活かしていけるようなサポートの必要性を感じた.
1 0 0 0 OA 熟練した精神科看護師による統合失調症者の術後疼痛の判断
- 著者
- 米村 法子 福井 里美 勝野 とわ子
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 日本保健科学学会誌 (ISSN:18800211)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.4, pp.167-175, 2017 (Released:2019-10-14)
- 参考文献数
- 25
目的:本研究は,熟練した精神科看護師による統合失調症者の術後疼痛の判断を明らかにすることを目的とした. 方法:精神科経験3 年目以上で外科系病棟での勤務経験もある看護師9 名を対象に半構造的面接を行い,質的帰納的に分析した.結果:熟練した精神科看護師による統合失調症者の術後疼痛の判断として【手術侵襲の影響と回復状態からの判断】,【幻覚・妄想からの判断】,【疼痛時・不穏時・不眠時指示薬からの選択の判断】,【言語的表現と客観的情報の整合性からの判断】,【複数の立場からの判断】の5 カテゴリーが明らかとなった.考察:【幻覚・妄想からの判断】,【疼痛時・不穏時・不眠時指示薬からの選択の判断】は術後疼痛のある統合失調症患者への特有の判断と考えられた.これらの判断には難しさを伴い,看護師が 仮説的に判断してケアを行うことや,熟練した精神科看護師が中心となって振り返る機会がより求められる.
1 0 0 0 OA 統合失調症患者のきょうだいとしての体験 -語りの分析から-
- 著者
- 岩﨑 みすず 水野 恵理子
- 出版者
- 一般社団法人 日本看護研究学会
- 雑誌
- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.4, pp.4_101-4_109, 2009-09-01 (Released:2016-03-05)
- 参考文献数
- 25
統合失調症患者の地域生活において家族の支援は重要であり,今後,高齢化する親に代わってきょうだいの存在が注目される。本研究では,統合失調症患者のきょうだいの体験を明らかにすることと,支援の方向性への示唆を得ることを目的として,きょうだいへの半構成的面接を思いと対応に注目して分析した。 長い経過を経ても,病気と患者の受け入れに対する葛藤を抱えてアンビバレントな心的態度が認められ,患者のきょうだいであることを不名誉に感じることが,他者に配慮する姿勢につながっていると考えられた。しかし,患者を抱えた負担感を持ちながらも,患者のニーズとともに,自身のニーズの充足に対処しており,体験をとおして自分の存在や生き方に新たな価値観を見出していた。きょうだいが抱えるアンビバレンスの理解と,きょうだいのニーズを的確に把握して,医療や社会資源とのつながりが保てるように支援していく必要性が示唆された。
- 著者
- 平井 李枝 Rie HIRAI
- 出版者
- 宇都宮大学共同教育学部
- 雑誌
- 宇都宮大学共同教育学部研究紀要. 第1部 = The Research Bulletin of the Cooperative Faculty of Education Utsunomiya University. Section 1 (ISSN:24325546)
- 巻号頁・発行日
- no.72, pp.315-332, 2022-03-18
1 0 0 0 OA 末期癌患者を対象とした録音音源を活用した音楽療法介入の臨床的意義の検討
- 著者
- 三道 ひかり 戸田 陽子 Hikari Sandhu Yoko Toda
- 雑誌
- 洗足論叢 = Memoirs by the members of Senzoku Gakuen College of Music, Senzoku Junior College of Childhood Education (ISSN:24339237)
- 巻号頁・発行日
- no.50, pp.83-95, 2022-03-28
1 0 0 0 OA 過酷な環境を生きる深海微生物の新規な難分解性多糖分解酵素
- 著者
- 大田 ゆかり 秦田 勇二
- 出版者
- 日本高圧力学会
- 雑誌
- 高圧力の科学と技術 (ISSN:0917639X)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.4, pp.354-361, 2010 (Released:2010-12-11)
- 参考文献数
- 14
Deep-sea microorganisms have a wide variety of useful and undiscovered enzymes for their survival in extreme environment. In this article, recent advances in the fundamental and applied researches on several recalcitrant seaweed polysaccharide degrading enzymes, which are newly obtained from the deep-sea bacteria, were described. The enzymes hydrolyze the backbone of the polysaccharides such as agarose and carrageenans to produce various oligosaccharides with great potentials for our health promotion. Furthermore, owing to the unique and profitable properties of the enzymes, they are used as powerful tools for researches in molecular biology and food analysis.
- 著者
- 西島 千尋
- 出版者
- 日本福祉大学社会福祉学部
- 雑誌
- 日本福祉大学社会福祉論集 = Journal social Welfare, Nihon Fukushi University (ISSN:1345174X)
- 巻号頁・発行日
- no.146, pp.59-86, 2022-03-31
本論文の目的は,「生/ライヴ」以外の音楽が「ほんもの」の「代替品」とみなされがちであったこれまでの傾向において,新型コロナウイルスの感染拡大によって普及したリモートによる音楽療法の実践の意味を整理することである. そのためにまず,リモートによる音楽の授業や,音楽療法のリモートセッションの実例を参照し(第 1 章),次に音楽療法の一手法であるミュージック・ケアのフィールドワークをもとにリモートセッションの実体を明らかにする(第 2 章).音楽療法のリモートセッションには対面にはないメリットが認められつつあるが,本論文ではリモートセッションでより明らかとなった音楽療法の「思い込み」の作用に着目することで(第 3 章),音楽療法の本質を再考する.
- 著者
- Masazumi FUJII Satoshi MAESAWA Sumio ISHIAI Kenichiro IWAMI Miyako FUTAMURA Kiyoshi SAITO
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.7, pp.379-386, 2016 (Released:2016-07-15)
- 参考文献数
- 57
- 被引用文献数
- 24 41
The neural basis of language had been considered as a simple model consisting of the Broca’s area, the Wernicke’s area, and the arcuate fasciculus (AF) connecting the above two cortical areas. However, it has grown to a larger and more complex model based upon recent advancements in neuroscience such as precise imaging studies of aphasic patients, diffusion tensor imaging studies, functional magnetic resonance imaging studies, and electrophysiological studies with cortical and subcortical stimulation during awake surgery. In the present model, language is considered to be processed through two distinct pathways, the dorsal stream and the ventral stream. The core of the dorsal stream is the superior longitudinal fasciculus/AF, which is mainly associated with phonological processing. On the other hand, semantic processing is done mainly with the ventral stream consisting of the inferior fronto-occipital fasciculus and the intratemporal networks. The frontal aslant tract has recently been named the deep frontal tract connecting the supplementary motor area and the Broca’s area and it plays an important role in driving and initiating speech. It is necessary for every neurosurgeon to have basic knowledge of the neural basis of language. This knowledge is essential to plan safer surgery and preserve the above neural structures during surgery.