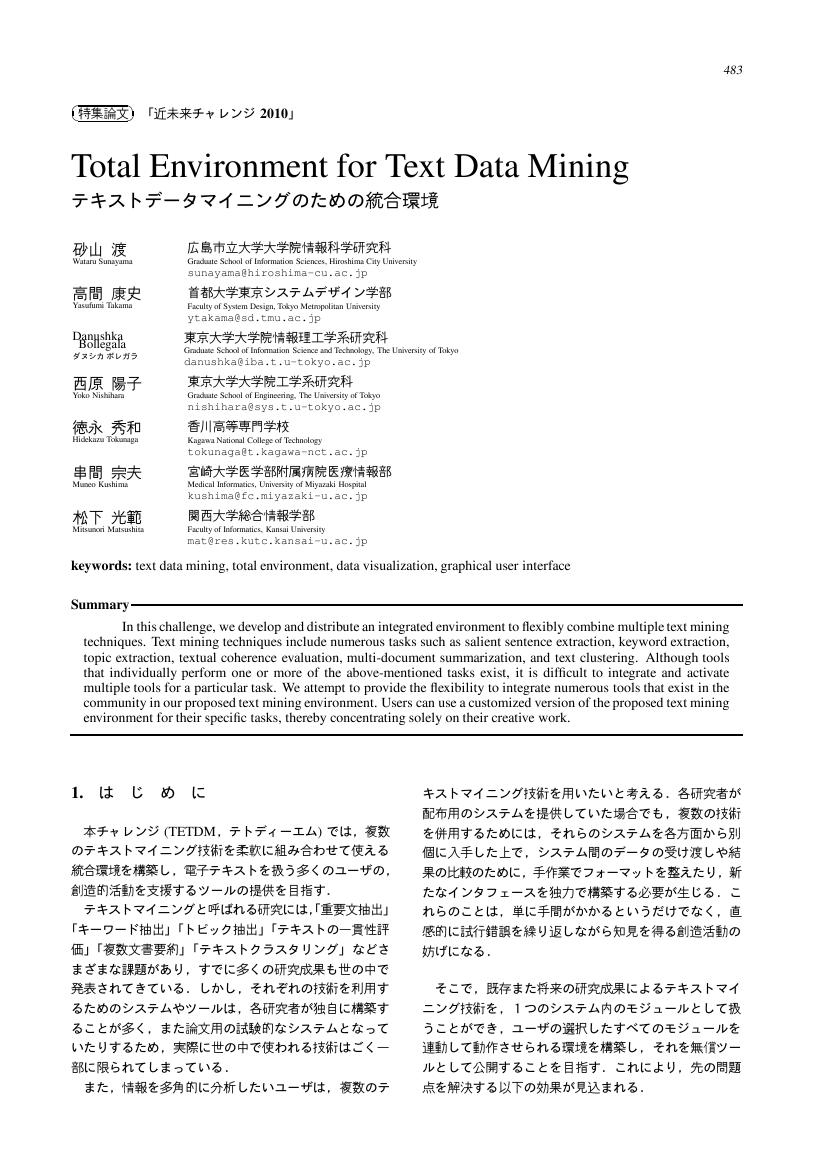2 0 0 0 OA 震災時における都心部非定住被災者の受療行動予測・対応策に関する研究
本研究の目的は、首都直下地震が発生した際に,被災者の医療を受け持つフロントライン医療サービス拠点の規模を検討するための、新宿駅周辺の非住宅の死傷者数の推定である。調査は新宿駅の東西口周辺の歩行者数を把握するものである。その結果,西口側には4-6,000人,東口側には2-10,000人の歩行者数が確認された。これを元に負傷者数を推計すると、西口側の負傷者数は一日のどの時間帯でも80人程度と安定しているが、東口の場合,午前中は35人、午後は85人,夕方は100人と変動が大きい。同様に,建物内の負傷者数も推計した。更に, 2011年3月11日東日本地震当日の行動について,アンケート調査を実施した。それらの結果から、新宿西口周辺に13箇所のフロントライン災害医療拠点を設ける場合,各所で67人程度の負傷者の治療を行うことが推定され,負傷者の分布に基づいて、東に8箇所,西に5箇所を配置することになる。
- 著者
- 近藤 則之
- 出版者
- 九州大学文学部
- 雑誌
- 哲学年報 (ISSN:04928199)
- 巻号頁・発行日
- no.41, pp.p179-203, 1982-03
2 0 0 0 OA 安定同位体的手法及び微生物生態学的手法の併用による土壌圏におけるメタン動態解析
- 著者
- 伊藤 雅之
- 出版者
- 独立行政法人農業環境技術研究所
- 雑誌
- 若手研究(B)
- 巻号頁・発行日
- 2008
メタンの吸収源としてのみ評価されてきた森林土壌について、メタンを放出しうる湿潤な地点を含めてメタン吸収・放出能の評価を行った。その結果、比較的乾いた土壌では既往研究の報告と同様にメタン吸収が主だったが、斜面下部の湿潤な土壌では、特に夏期の高温時にはメタンの放出源として機能した。また、渓畔の湿地では夏期に非常に大きなメタン放出が観測され、メタンの生成過程が降雨条件等の水文条件に規定されることが示された。
目的:individual based modelは、近年の感染症モデルとして最もパワフルなモデルであり、新型インフルエンザ対策では広く用いられている。しかしながらモデルはあくまでモデルあり、実際の人の所在、移動を表現したものではない。モデルをより現実的に近づける努力は重要であるが、それでもやはり現実性は乏しい。本研究では逆に、実際の人の所在、移動のデータからモデルを構築した。方法:1998年10-12月に実施された、首都圏在住の約88万人の1日の移動、所在が記録された抽出率約2.7%のデータを用いる。所在は、自宅、学校等の別、1648カ所のゾーンで表示され、鉄道の乗降駅、時間も記録されている。まず、このデータを用いてまず接触回数を求め、実際の社会での接触がscale freeであるかどうかを検討する。新型インフルエンザの自然史、感染性を有する期間、無症候比率、無症候の場合の感染性、受診率は先行研究によった。感染性は家庭および社会での感染性がR0=1.5になるように調整した。シミュレーションは、海外での感染者が、感染3日後に帰国、八王子の自宅に帰宅後感染性を有するとした。職場は丸の内としてJR中央線で通勤するとした。結果:無作為に抽出した638名で計測された社会,家庭,電車でのべき乗bはいずれの場合でも有意に正であった。感染者数は、最速で対応の意思決定がなされた場合の感染7日目で3032人と少ないものの、首都圏全域、特に鉄道沿線に拡散していることが明らかになった。考察:本研究で示された実際の移動データを用いての数理モデルは、現実的な対策立案に活用できるモデルを提示できたと言えよう。今後、新型インフルエンザ対策のガイドライン策定においては有用なツールになると期待される。
2 0 0 0 クラスNPの新しい特徴づけ - 確率的検査可能証明と近似問題 -
- 著者
- 太田 和夫 岡本 龍明
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理 (ISSN:04478053)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.55-68, 1994-01-15
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 3
もっとも代表的な計算機のクラスである NP 問題に対して、最近、まったく新しい特徴づけが与えられ話題になっている。この理論について解説するとともに、近似問題への応用を述べる。
2 0 0 0 電気回路のもつ自己組織化機能の解明
本研究では、広い分野で注目される自己組織化の概念を、非線形現象の研究では蓄積のある電気回路網を具体的対象として解明することを目的とした。特に、従来、自己組織化の具体例とされてきた周期現象、同期現象などの秩序化の対極にあるカオス現象に注目し、その発生条件、物理的本質を解明することにより、非線形電気回路網に生じる諸現象を統一的に理解することを目指した。本研究の主な成果は以下の通りである。(1)非線形能動素子1個、線形で正のインダクタ及びキャパシタ合わせて3個、線形抵抗1個、以上計5個の素子で構成できる11個の3次元発振器群を考えた。パラメタ値の変化に伴う平衡点の安定性の変化とカオス発生との関係を明らかにし、これらの発振器群をカオスの発生に関して分類することに成功した。これにより、3次元発振器におけるカオス発生の必要条件を得ることができ、従来、試行錯誤的にしか求められなかったカオスを系統的に探索することができることになる。今後、同様の考え方を、他の非線形特性素子を用いた系、あるいは4次元以上の系に対して拡張し、一般的なカオス発生条件を明らかにすることが課題である。(2)以上の結果から、カオスとは、非線形性の強さに伴い、非発振から発振状態(交流)、さらに発振停止(直流へと変化する経過で、発振状態の一つの特殊な状況として生じ得るものであることが明かとなった。今後、筆者が先に提唱した「平均ポテンシャル」を拡張し、これら一連の現象を物理的、統一的に理解する必要がある。(3)非線形素子が2個の系として、同一特性の2個の弛張振動発振器の結合系を考察し、2つ存在する同期状態の一方が、非線形性が強くなるとき不安定化する現象を見いだした。多数の非線形素子を含む系の振舞いを理解する基本として、この現象を物理的に解明することが今後の課題の一つである。
2 0 0 0 OA 茨城県つくば市における在来タンポポ及び雑種タンポポの分布と景観構造の関連解析
- 著者
- 山野 美鈴 芝池 博幸 井手 任
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.5, pp.587-590, 2004 (Released:2005-12-12)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 6 6
Relationships between landscape structures and distribution patterns for dandelions (Taraxacum) were examined in Tsukuba city, Ibaraki Pref. By using molecular analysis, collected samples were discriminated as "native dandelions", "introduced dandelions", "tetraploid hybrids", "triploid hybrids", and "androgenesis hybrids". 32 sampling sites were grouped into five landscape types according to their similarities of land uses. The native dandelions mainly occurred at satoyama landscape. In contrast, hybrid dandelions (tetraploid hybrids) mainly occurred at urbanized areas and bare lands. Vegetation survey was also conducted at 20 sampling sites, and their components were summarized by DCA analysis. Positive correlation was found between the frequency of native dandelions and vegetation of forest floor and margin, and negative correlation between the frequency of tetraploid hybrids and vegetation of open habitats. Based on the results obtained, it was suggested that native dandelions tended to exist in the landscape containing more forest margin, whereas tetraploid hybrids in landscape containing more developed and / or vacant lands. Role of dandelions as environmental indicator species was discussed.
- 著者
- 荒木 一視
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.3, pp.138-157, 2006-09-30
近年食料の安全性や食料の質に対する関心が高まっている.本研究もそのような立場から,現代のわが国の食料供給体系を論じるものである.その際,2004年1月に山口県阿東町で発生した鳥インフルエンザを取り上げ,実際に食料の安全性が脅かされるという事態において,食料供給の現場を担うスーパーがどのような対応をとったか,さらにそのような状況を理解するにはどのような観点が有効であるかに焦点を当てた.スーパーの対応としては,調達量や価格の調整は一般的ではなく,短期的には安全性のアピールが中心で,それに伴って阿東町や山口県内の調達先を他所に変更する事例も認められた.それはスーパーサイドにとっては商品の安全性を訴える上で意味のある対策でもあった.しかし,1年を経て,調達先は山口県内に回帰するとともに,調達先の多元化も認められた.このような一連の対策を講じた背景には,リスクへの対応という側面に加えて,安全というイメージをどのようにして構築するのかという点が重要になっていることを指摘できる.実際の安全性よりもイメージとしての安全性がスーパーの調達戦略に大きく関与している側面が浮かび上がった.このように今日の食料供給体系を稼働させていく上で,食品のイメージが大きな役割を果たしていることが明らかになり,時にそれは食料供給体系そのものを再編成するほどの影響力を有している.
2 0 0 0 OA インターネット環境に適した構造化P2Pネットワークソフトウェアの設計と実装
- 著者
- 高野 祐輝
- 巻号頁・発行日
- 2011-03
Supervisor:篠田陽一
2 0 0 0 月深発地震による月深部構造の再検討
本年度は昨年度に引き続き当初の研究計画どおり月深発地震とくにA1震源、A33震源からの地震波を利用して月の深部構造に関するデータを得ることを試みた。当初の予定通り、これらの震源からの地震波を多数スタッキングすることにより、これまで気づかれていなかった多くの後続波のフェーズを発見することが出来た。これらの中にはPKP、PKKPフェーズと思われるものがあり、これらが本当にそうであれば、月の中心部に約450kmの鉄のコアが存在することが推定される。この結論はきわめて重要な結論であるので、さらにこの後続波の一般性を確認する必要があると考えている。そのためにA1、A33震源以外の震源からの波についても同様な研究を開始したが、そのためにはアポロ地震波データの使いやすいデータベースを構築する事が効果的であると考えられるようになってきた。これはデータ処理を多数、迅速に行うためにどうしても必要になることであると同時に、将来の月探査計画、LUNAR-Aの準備的研究としても緊急を要する課題であると認識されたためである。このために本研究のかなりの時間を、この研究をさらに発展させるために必要なデータベース形態、仕様を決定するために使った。現在ではこのデータベースの仕様に基づきそれをimplementする作業に入っており、ほぼ80%の作業が終了した段階である。このデータベースは広く関連研究者に利用できるようにする予定であり、本研究が完成した暁には月地震学にとって大きな貢献をすることが出来るものと信じている。
2 0 0 0 IR 月の学習における関連事項[III]
- 著者
- 中村 泰久
- 出版者
- 福島大学
- 雑誌
- 福島大学教育実践研究紀要 (ISSN:02871769)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, pp.31-38, 2000-06
2 0 0 0 OA ピーターバラ年代記で天体の記録を読む(月食)
- 著者
- 加島 巧
- 出版者
- 長崎外国語大学
- 雑誌
- 長崎外大論叢 (ISSN:13464981)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.41-50, 2005-12-30
2 0 0 0 教師のデジタル教材評価の重要性に対する意識調査
- 著者
- 亀井 美穂子 稲垣 忠
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会研究報告集
- 巻号頁・発行日
- vol.2007, no.5, pp.85-88, 2007-12-22
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 教員養成課程における情報教育の教材について
- 著者
- 年森 敦子
- 出版者
- 一般社団法人 日本科学教育学会
- 雑誌
- 日本科学教育学会研究会研究報告
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.5, pp.9-12, 2007
- 参考文献数
- 6
近年,コンピュータの高性能化やアプリケーションの充実により,小学校や中学校においてデジタル教材を授業で利用する機会は増加する傾向にある。情報機器の利用という授業環境の変化に伴い,教員にはデジタル教材の作成能力と活用能力も要求されてきている。一方,平成15年度からの高等学校における教科「情報」の実施により,大学における情報教育は,高等学校の「情報」との接続性の面からも,これまでの汎用的なアプリケーションソフト操作教育から,専門分野での活用や,将来の職域において活用できるようなコンピュータ操作技術の習得を目指すなど,高度な内容への変化が望まれてきている。そこで,本研究では,教員養成課程の学生を対象としたデジタル教材作成技術の育成,およびその効果の調査に関する研究の一環として,情報教育科目の中でのデジタル教材作成演習を取り上げ,実施結果について報告する。
2 0 0 0 無限混合分布を用いたクラスタリング
- 著者
- 栗原 賢一
- 出版者
- 一般社団法人電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会誌 = The journal of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (ISSN:09135693)
- 巻号頁・発行日
- vol.93, no.9, pp.770-773, 2010-09-01
- 参考文献数
- 6
近年,教師なし学習の分野で無限混合分布等のノンパラメトリックベイズと呼ばれる手法が盛んに研究されている.本稿では無限混合分布のクラスタリングに対する応用を紹介する.特に有限混合分布との違いを解説し,推論方法の紹介と,画像データに対する応用を紹介する.
2 0 0 0 OA Total Environment for Text Data Mining
2 0 0 0 第一次大戦期日本の山東経営をめぐる総合的研究
第1次大戦時、ドイツの膠州湾租借地を攻略した日本は、青島守備軍を編成して占領地統治を行い、青島及び山東鉄道を中心に諸権益の拡張を図った。そのために青島守備軍などが行った山東地域の実態調査を通して日本の山東経営を検討すること、及びそれらの調査資料を利用しつつ山東地域を中心に当時の中国の政治・経済・社会について総合的な考察を行うことを目的とした。外務省外交史料館・防衛省防衛研究所図書館・山口大学東亜経済研究所を中心に10ヶ所の諸機関で資料調査を行い、青島守備軍民政部鉄道部の『調査資料』シリーズや『山東鉄道調査報告』シリーズなどを含め、約160点の資料を明らかにすることができた。その結果を「青島守備軍編刊書・報告書目録 附・解題」にまとめ、『研究成果報告書』に収録した。これらの資料は、従来あまり利用されていないが、山東地域を勢力範囲として中国大陸進出を狙った日本の企図を具体的に分析するうえで重要な資料であり、また中国の地方志や経済史の資料としても役立つものである。日本軍の占領体制、ドイツの青島経営、山東鉄道をめぐる諸問題、山東省農民の移民、山東の農産物・工鉱業など、個別のテーマを設けて研究を進めた。その成果をまとめて、第3年度に論文集『日本の青島占領と山東の社会経済 1914-22年』を刊行した。同時に山東社会科学院・青島市社会科学院との学術交流を進め、論文集には山東の研究者からの寄稿も収めることができた。第4年度には、上記の論文集を基礎に、山東の研究者と国内の日本史研究者を招いて国際シンポジウムを開催した。そこでは、実証的な研究の領域において日中の中国史研究者間、また山東地域に関する研究で日本経済史研究者と中国近代史研究者の交流を図ることができた。以上を通して、従来研究の手薄であった日本の青島占領の諸相と、それが1930年代の華北進出に意味をもった点を明らかにすることができた。
2 0 0 0 自然災害研究の統合化と災害知識伝達
- 著者
- 春山 成子 WEICHSELGARTNER J. JUERGEN Wisergartner
- 出版者
- 東京大学
- 雑誌
- 特別研究員奨励費
- 巻号頁・発行日
- 2004
今年度は、アジア太平洋地域で発生している自然災害の研究事例を統合化することを中心に研究を行った。また、2004年度では日本で異常な洪水・台風災害が発生していることもあり、自然災害のなかでも洪水事例を多く取り上げることにした。さらに、アジア太平洋地域で発生した自然災害についても、統計資料、及び、データなどを収集して、統計的な処理を行い、分析を行った。この際、ことに社会的な見地、人文科学的な研究視点に立脚して、自然災害の研究を行っている研究者に面会することにした。自然災害の研究概況を掌握するために、岐阜大学工学部の高木先生に面会して、工学部における日本人研究者の災害研究の蓄積と現在の研究動向を探るとともに、岐阜大学においてジョイント講義を行い、岐阜大学の研究者との研究連絡の輪を作り、今後の研究の展望を話しあうとともに、ヨーロッパにおける自然災害研究者との知識を共有するために数回の討議を行った。また、アジア各国からの研究者との面会を行い、欧米とアジアの自然環境認識の違いについて話し合った。さらに、つくばの防災科学研究所佐藤研究室を訪問し、日本で試みている「統合的な自然災害研究の将来的な方針」を聴取するとともに、ドイツの防災システムについてのユルゲンが報告し、意見交換を行った。さらに、神戸市で開催された「地震災害10年」の企画による国際会議(自然災害会議)に参加して、各国からの来日している研究者および行政、研究機関の事務官、国連の各機関の実務担当官との個別の会合を持ち、2004年度及び2005年度始めの災害研究のあり方、及び、実務としての自然災害・防災・警報システムに関わる手法、技術などの討議を行った。学内においては、水曜日午後にサイエンスコミュニケーショの講義を行い、日本人学生に向けた災害研究の知識の共有に関する自主ゼミの中で、科学知識の統合化に関わるゲーミング理論を構築するとともに実践した。また、これらの研究を通して、4月2日には弥生講堂において研究成果の一部を発表した。
2 0 0 0 原子力発電所をめぐる社会学的問題の研究
当初より、本研究は、第1に原発問題をとらえる枠組みの構成、第2に島根原発をめぐる地域問題の分析、という2つの課題を設定していた。研究ではまず第1の課題を達成するため、(1)関連の先行業績を検討するとともに、(2)全国紙における原発関連の記事を収集し、また(3)世論関係の資料を収集することによって、原発問題をとらえる基本的な枠組みを構成した。そこで明らかになったことは、原発問題をとらえる際には、社会学の各分野のうち、社会問題論、社会運動論、生活構造論という3つの分野からのアプローチが有用であり、それらを総合した視点が必要であるということである。同時にまた意思決定の過程についての考察が重要であり、政治社会学的な観点からの接近も欠くことはできないということも明らかになった。第2の研究課題である、島根原発の研究は、これら4つの研究分野(政治社会学、社会問題論、社会運動論、生活構造論)との関連で進められていった。具体的には、政治社会学の枠組みをもとに地域政治における意思決定のありようを探るため、地方政治家や議会議事についてのデータが収集された。社会問題論との関連では反原発団体の活動を、主として地方紙を中心に検討した。原発問題をどう考えるかということにかんしては、住民全体が決して一様な意見を保持しているわけではない。商工会と漁民の見解の相違などは顕著なものであるが、そこには当事者の生活のありようが反映している。そして、生活は地域の長い歴史と関連している。したがって、原発所在地である鹿島町の歴史について考察することも重要であると判断し、資料収集を試みた。以上の基礎的な資料をもとに、今後さらに分析を進めていく予定である。
2 0 0 0 IR 「イサワ教育こんわ会」の憲法科特設論について
- 著者
- 土屋 直人 TSUCHIYA Naoto
- 出版者
- 岩手大学教育学部
- 雑誌
- 岩手大学教育学部研究年報 (ISSN:03677370)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, pp.23-44, 2010-02-26
われわれは「憲法を教える(はずの)社会科教育」の在るべき姿について、どのように考えていけばよいのであろうか。果たしてわれわれは、<憲法と教育とのつながり>をどのようにとらえ、憲法学習、憲法教育というものを、学校教育・生涯教育の中で、主権者教育の視点からどのように実現し、実践してゆけばよいのであろうか。去る2006年12月、時の国会が(そして、われわれが)、「改正」と称して、1947年教育基本法から、憲法の「理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」という重大な文言を削除し、消し去ってしまったことの歴史的・実質的意味は大きい。21世紀に入って、2005年10月に自由民主党が「新憲法草案」を提起し、正面から憲法「改正」が論じられるようになり、2007年5月には国民投票法が成立し、明文改憲の動きが進行しようとしている状況がある。そして2006年12月、教育基本法が「改正」されることによりその憲法との関係が弱められた。無論1950年代以降、時々の政府・与党によって憲法「改正」が繰り返し企図され続けてきたことは周知の通りであり、改憲論の潮流は冷戦崩壊後のここ数年に始まったというものではない。ただ、もし万が一でも、現憲法が変わった(変えられた)その時、われわれの憲法教育、憲法に基づく教育の方向は、一体どうあればよいのか。こうした現況、大きな岐路に臨む現在ほど、憲法学習、憲法教育の重要性と必要性が高まっている時はない、といえる。今、この国の教師と子どもたち、市民が一層じっくりと憲法の歴史的意義と価値を生活の中で学び、立憲主義の精神を以て生活を高め、実践しようとする広義の憲法教育の意義が再々度確認される必要があるのではないか(1)。今から約50年前の1957(昭和32)年頃、岩手の胆沢地域において、独立した一つの教科「憲法科」の創設(特設)を提唱し、議論していた教師たちがいた。「イサワ教育こんわ会」(胆沢教育懇話会)の教師たちである。教育科学研究会機関誌『教育』の復刻版冊子に所収の、教育科学研究会『教科研ニュース』第19号(1957年10月10日発行)の中に、「サークル機関紙(ママ)から」欄(謄写刷)がある。そこには「イサワ(ママ)教育こんわ(ママ)会」の「なぜ 憲法科の特設を 主張するのか―いまの日本で ぜひ まなばなければならない 憲法―」というタイトルの稿が収められている(2)。この記事「なぜ憲法科の特設を主張するのか」の記載は、当時の「イサワ教育こんわ会」の機関誌『なかま』からの抜粋(転載)であろうと思われる(3)。なお、おそらく、この稿をその中心となって考え、文を執筆したうちの一人は、その文体や内容からして、ナガイショーゾー(永井庄蔵、1911 ~ 1998)であったと推測される(4)。ナガイはその後、全国刊行されていた教育雑誌『教師の友』1960年5月号に、「永井庄蔵」の名で論稿「憲法科を創設することの提案」を書いていた(5)。ここでは前者、「イサワ教育こんわ会」の「なぜ憲法科の特設を主張するのか」の文章を参照し、永井らが、今から約50年前(1957年、あるいはそれ以前)の当時の時点で、何故「憲法科」の特設を主張したのか、そして彼らは何を主張しようとしていたのか、その教育実践運動の歩みの一端とあわせて、彼らの「憲法科」特設論の内実を読み直し、吟味し、その問題提起の歴史的・今日的意義を問い直してみたい。(以下、引用文中の下線及び傍点、記号は原文のママ。)