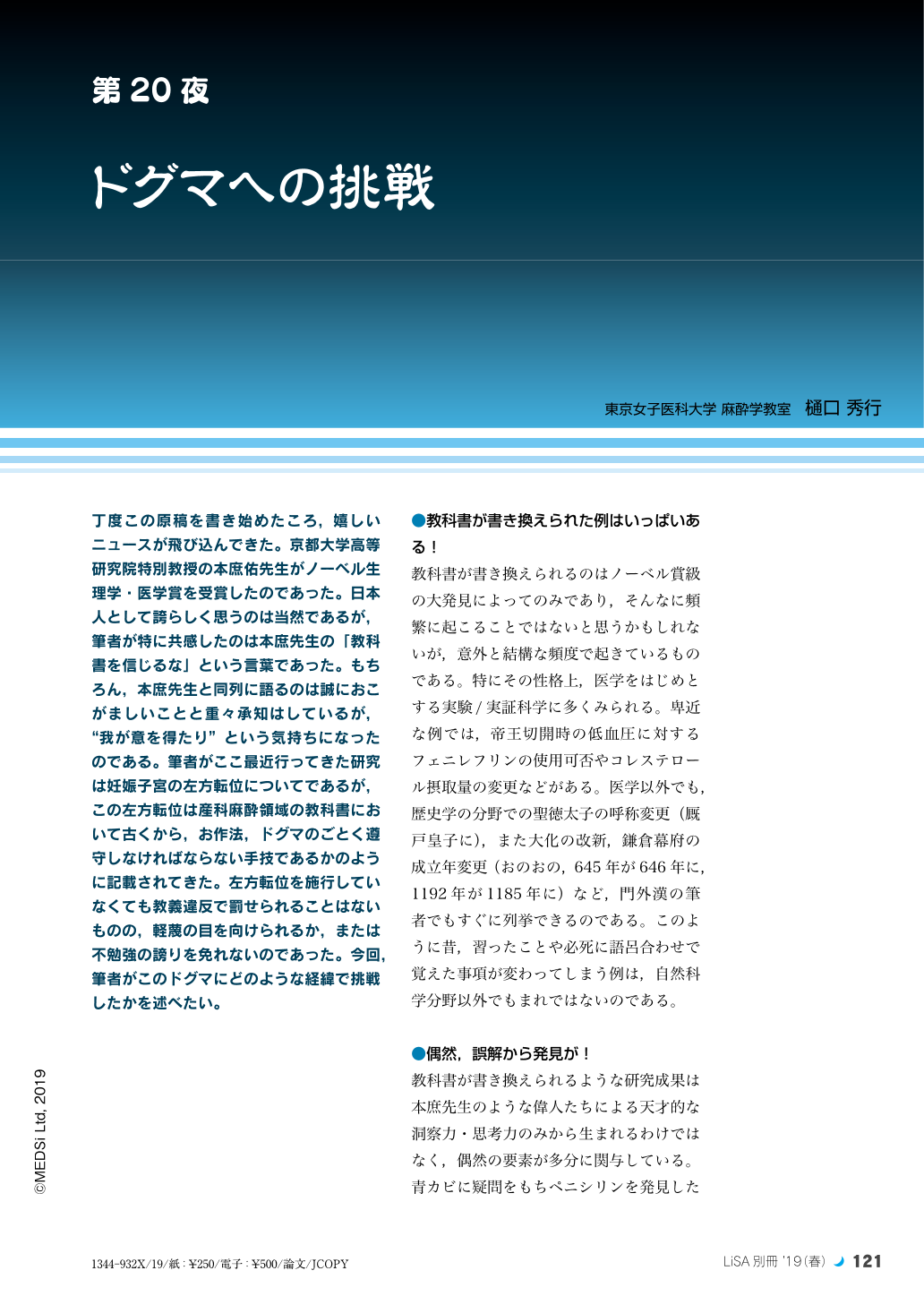1 0 0 0 OA 女子大学生の日常食における魚類と肉類の利用状況および利用におよぼす要因
- 著者
- 根立 恵子 石井 幸江 米田 泰子 由比 ヨシ子
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.3, pp.215-222, 2012 (Released:2014-02-28)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 4
食生活管理者を目指している女子大学生224名を対象として,魚類や肉類の利用状況と,食経験や居住環境がその利用状況にどのように影響するかを調べた。 育った環境が海から離れていても,新鮮な魚類を食べて育つという食経験が,魚類に対する嗜好を高めていた。調理技術の伝承は家庭が多くの役割を担い,魚料理では53.6%,肉料理は62.9%の学生が母・祖母から伝承されていた。学校教育の関与も見られ,魚料理は27.7%,肉料理は18.8%の学生が学校からと答えた。 魚類や肉類の摂取頻度に居住形態が影響し,1人暮らしの学生は豚肉と鶏肉を多く食べる傾向にあった。自宅生は比較的魚類,牛肉の利用が多かった。居住形態によって使われる調理操作も多少異なり,自宅生は魚類では生,牛肉では焼く,鶏肉では揚げる操作を比較的多く使っていた。1人暮らしの学生は魚類,肉類ともにフライパンがあれば調理が可能なソテーを多く使い,揚げる操作の利用は少なかった。
1 0 0 0 「盂蘭盆(うらぼん)」の本当の意味 : 千四百年間の誤解を解く
- 著者
- 久恒 彩子
- 出版者
- 金沢工業大学
- 雑誌
- KIT progress : 工学教育研究 (ISSN:13421662)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.49-61, 2004-03
金沢工業大学では、入学後の春学期に、全ての学生がプレースメント英語を履修する。約千七百名の学生が、二回にわたって行われるレベル分けテストによって英語I、II、IIIに、それぞれ分けられる。自分のレベルにあった英語の課程が始まると、語学学習法を紹介する時間は、授業中にはほとんど無い。春学期のうち二週間だけがレベル分けテストに割り当てられているので、残りの学期は学生にとって、いろいろな語学学習法を学ぶことに専念できる最適な機会だと言える。本論説は、外国語としての英語をまなぶ授業で、学習する者がどのように効率的な学習法を見につけ自立していくか、その方法を紹介する。学生にとって語学学習法を習得することは大切だが、語学教育者にとっても学生の経歴、学習様式、動機レベルなど、語学を教える前に把握しておくことも、同じく、或いはそれ以上に重要である。学期の最初に行ったアンケートにより、学生が既にどのような語学学習法を使っているかを調べた。学期中には様々な学習法が紹介され、学期の最後には、語学学習法と英語に対する意識がどのように変化したかを調べるために再度アンケートを行った。計493人の学生が、著者が担当したプレースメント英語の授業を履修した。そのうち学期の最初と最後に行ったアンケートの双方に答えた463名のデータが本研究に使われている。本研究は、次の三つの答えを模索する。(1)学生の言語運用能力を向上させる語学学習法/(2)学生の英語に対する意識が語学学習法の習得後に変わるかどうか/(3)レベルが著しく異なる学生に対しての有効な語学学習法の教え方 t分布の結果は、語学力、動機共に低い学生の英語に対する意識が、語学学習法を学ぶことによってどれだけ変わったかを表している。自分に適した語学学習法を認識し、今後に生かす学習法を理解したことにより、学生は進んでそれらを使うようになった。様々な学習法を習得することは、学生が人生の早い時期に自立した学習者になるために、必要不可欠な道具になりえると言える。
1 0 0 0 IR 旅行商品取引のグローバル化進展と豪州における制度の変化
- 著者
- 野村 尚司
- 雑誌
- 玉川大学観光学部紀要 (ISSN:21883564)
- 巻号頁・発行日
- vol.2014, no.2, pp.1-12, 2015-03-31
本稿は,旅行商品取引のグローバル化進展に伴う日本の旅行業がおかれた状況を踏まえ,今後のあるべき姿について考察するための準備段階として,これまで旅行業法で規定されてきた公的な旅行業ライセンス制度や旅行業者破綻に対する弁済制度の廃止といった大胆な政策改革を推進する豪州の事例を紹介し,その考察から得た含意を特定することを目的とする。 2012年12月に,豪州連邦政府・各州政府は消費者を統括する大臣会議を行い,旅行業法の見直しやTravel Compensation Fund(以下,TCF)廃止などを柱としたTravel Industry Transition Plan(以下,TITP)を推進することで合意した。豪州政府はその合意に関するコミュニケで,「旅行業のライセンス制度を維持することはもはや困難であり,品質保証としての認証制度が国の手を離れる流れに変化させざるを得なかった」との理由を述べている。豪州旅行業協会(以下,AFTA)ではこの政府決定を歓迎するコメントを発表。同協会内でワーキンググループを発足させ,TITPの趣旨に沿った新たな業界主導の旅行業認証制度や消費者保護策の策定作業に入ったのである。これは,公的な旅行業ライセンス廃止といった,極めて大きな変革であり,2012年年末の決定から約3年を掛け2015年にはTITPが完了することとなる。 そもそもグローバル展開を行うオンライン・トラベル・エージェンシー(以下,OTA)はインターネットという情報通信技術を最大限に活用することでその強みを発揮させる事業モデルである。それは,容易に世界市場へアクセスできる技術力のみならず,各国で定めた法制の枠組みを「すり抜ける」力も具有している。また地球上のどこかに顧客が存在し自社商品の競争力があると見るや即市場参入し,収益が上がらない場合は即撤退を決断する身軽さも有している。OTAの事業モデルが世界で市場シェアを増大させるにつれ,「国」の枠組みで構築されてきた各国の旅行業法制は次第に綻びが出てくる可能性があり,本稿で取り上げた豪州の事例と同様わが国においてもその見直しは避けられないのではないだろうか。
- 著者
- 安倉 良二
- 出版者
- 経済地理学会
- 雑誌
- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.2, pp.173-197, 2007-06-30 (Released:2017-05-19)
- 被引用文献数
- 5
本研究は,地方中小都市における中心商店街の再生について,愛媛県今治市の仲間型組織である「今治商店街おかみさん会」(以下,今治おかみさん会)を事例に選び,その設立背景となる商業環境の変化と活動実態の分析から考察を進めた.高度経済成長期に工業の好況を背景に隆盛を極めた今治市の中心商店街は,1990年代後半以降,大店法の運用緩和に伴う郊外地域での大規模な商業集積の形成としまなみ海道開通の影響を受け,その衰退が決定的となった.今治商工会議所,今治市役所,今治商店街協同組合は大規模な再開発構想や空店舗対策など,様々な再生策を打ち立てたが,その多くは不調に終わり,中心商店街の再生は行き詰まりをみせていた.このような状況からの打開策として,松山市で女性による商店街のまちづくりに関する実践を知った今治市役所商工労政課の提案を受けて2000年11月に設立されたのが今治おかみさん会である.今治おかみさん会は,既存の商店街組織である今治商店街協同組合とは独立しており,話題性の高い共同事業を独自で継続的に展開することで中心商店街の再生に寄与する組織のひとつとなっている.しかし,行政からの補助金削減と会員店舗の減少により,今治おかみさん会の運営は厳しい状況にある.今治市の事例からは,商業活動の衰退が進む地方中小都市の中心商店街では,規模の縮小を前提に,既存の枠にとらわれない仲間型組織が再生の一翼を担う可能性をもつことが明らかになった.
1 0 0 0 第20夜 ドグマへの挑戦
- 著者
- 樋口 秀行
- 出版者
- メディカル・サイエンス・インターナショナル
- 巻号頁・発行日
- pp.121-125, 2019-04-19
丁度この原稿を書き始めたころ,嬉しいニュースが飛び込んできた。京都大学高等研究院特別教授の本庶佑先生がノーベル生理学・医学賞を受賞したのであった。日本人として誇らしく思うのは当然であるが,筆者が特に共感したのは本庶先生の「教科書を信じるな」という言葉であった。もちろん,本庶先生と同列に語るのは誠におこがましいことと重々承知はしているが,“我が意を得たり”という気持ちになったのである。筆者がここ最近行ってきた研究は妊娠子宮の左方転位についてであるが,この左方転位は産科麻酔領域の教科書において古くから,お作法,ドグマのごとく遵守しなければならない手技であるかのように記載されてきた。左方転位を施行していなくても教義違反で罰せられることはないものの,軽蔑の目を向けられるか,または不勉強の謗りを免れないのであった。今回,筆者がこのドグマにどのような経緯で挑戦したかを述べたい。
1 0 0 0 OA 発語失行の用語・症状・訓練に関する諸問題
- 著者
- 小嶋 知幸
- 出版者
- The Japan Society of Logopedics and Phoniatrics
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.4, pp.293-299, 2004-10-20 (Released:2010-06-22)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
シンポジウムの主題である発語失行に関して, 本稿では用語・症候・訓練をめぐる諸問題について, 筆者の臨床的知見に基づいて論じた.まず, 本症候を“失行”のなかに位置づける根拠としてDarleyらが挙げている (1) 音の誤りの非一貫性, (2) 随意運動/自動運動の乖離の2点について検証し, 本症候を“失行”の範疇で捕らえることの問題点について述べた.次に, 構音 (発話) 動作の拙劣を本態とする本症候の音の誤りを分類する際に, 音韻レベルの誤りにも用いられている「置換」という同一の用語を用いることの問題点について論じた.最後に, 本症候への訓練に関して, Squareらのトップダウン・マクロ構造アプローチとボトムアップミクロ構造アプローチという分類を参照しつつ, 筆者の考える訓練の基本的コンセプトについて論じた.
1 0 0 0 IR <論文>「手巾」と「武士道」ブーム : 〈擬-普遍〉主義的主体化のメカニズム
- 著者
- 竹内 里欧
- 出版者
- 京都大学大学院文学研究科社会学研究室
- 雑誌
- 京都社会学年報 : KJS = Kyoto journal of sociology
- 巻号頁・発行日
- no.17, pp.29-42, 2009-12-25
In this paper I intend to reconsider the boom of bushido (spirit of warrior) in modern Japanese society by analyzing the short story "Hankechi" written by Akutagawa Ryunosuke (1892-1927) in 1916. In modern Japan, the bushido boom began around the end of the nineteenth century. Since the Sino-Japanese War (1894-5) bushido became popular in Japanese discourse. Of course bushi (warrior) as a social class had been abolished before this era. However, it was this boom that made the moral of bushi popular to people from all walks of life. The symbolic work of this boom was Bushido: The Soul of Japan written by Nitobe Inazo (1862-1933) in 1899. It was first published in the United States in 1899, and translated into Japanese in 1908. Nitobe was a famous thinker and educator who had a strong influence on the bushido boom. He had an ambition to be "a bridge between the East and the West". In his book, Nitobe tried to explain bushido as a spirit of Japanese society. He emphasized that bushido was a civilized and refined moral which could be equal to Western ethics. In order to reconsider the bushido boom, I would like to take up one story "Hankechi (Handkerchief)" written by Akutagawa. In the story Akutagawa caricatured Nitobe's ideas of bushido cynically. Even though it is only a short story, it succeeds in grasping the essence of the problem in civilization process of Japan, which was reflected well in the bushido boom. Therefore, it seems reasonable to examine this story as a clue to understand the aporia of the modernization and civilization process of Japan. Especially, I will focus on the "uneasiness" that came over the main character in the last scene of this story. I shall explain why he felt "uneasy" and how that kind of feeling was connected to the identities of intellectuals in modern Japanese society. For this purpose, I would like to use Louis Althusser's theory. Especially I pay attention to his theory about subjectivization. I shall discuss the difficulties embedded in the process in which modern Japanese intellectuals became subjects as represented by Nitobe Inazo's case.
1 0 0 0 IR 古代のシュメールと中国における初期の貸借考 (黒木龍三教授記念号)
- 著者
- 水谷 謙治 ミズタニ ケンジ Kenji Mizutani
- 出版者
- 立教大学経済学研究会
- 雑誌
- 立教経済学研究 (ISSN:00355356)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.229-254, 2019-10
1 0 0 0 IR 清朝末期における裁判制度について : 刑事裁判手続きを中心として
- 著者
- 娜 鶴雅
- 出版者
- 東京大学東洋文化研究所
- 雑誌
- 東洋文化研究所紀要 (ISSN:05638089)
- 巻号頁・発行日
- vol.160, pp.392-377, 2011-12
清朝司法制度, 即逐級審轉覆核制, 沿襲了傳統中國行政兼理司法的重要特徵。但自鴉片戰爭以来, 清朝政府被迫與各國簽訂了一系列不平等條約, 國家主權遭受到前所未有的重創。為了維持現有統治秩序, 改正不平等條約, 廢除治外法權, 清朝政府決定學習西方, 開展立憲運動, 進行司法改革。光緒32年(1906), 清朝政府仿照日本司法制度在全國建立了四級三審制, 始設新式審判機關--審判廳。但至民國元年為止, 全國除高等審判廳基本設立外, 地方審判廳和初級審判廳只完成了計畫的1/3和1/5。審判廳設置的不完全, 使得當時的審判程序也大不相同。(1)在審判廳完全設置地區(如京師), 審判程序按照四級三審制進行。(2)在審判廳未完全設置地區(如順天府), 州縣仍按逐級審轉覆核制兼理司法審判, 但自第二審開始, 原審判機關府、按察使司、督撫均被排除在審判程序之外, 為高等審判廳所取代。(3)在審判廳未設置地區, 仍採用逐級審轉覆核制, 但審判程序有所簡化。行政兼理司法的存在也威脅著司法的公正性, 於是清朝政府規定, 除州縣自理案件以外的案件都要經過審判廳複審, 並創設了針對死刑案件的覆判制度, 從而達到彌補行政兼理司法弊端,制約行政官司法權限的目的。
1 0 0 0 地下鉄銀座線および丸ノ内線の研究
- 著者
- 柴山 孝一
- 出版者
- 東京学芸大学
- 雑誌
- 学芸地理 (ISSN:09112693)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, pp.20-22, 1960-03-19
1 0 0 0 OA 明治期の大磯「禱龍館」及び稲毛「海氣館」にみる海浜リゾート計画思想に関する比較研究
- 著者
- 十代田 朗 渡辺 貴介
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.19-24, 1995-10-25 (Released:2018-12-01)
- 参考文献数
- 20
THIS STUDY TRIES TO CLARIFY THE PLANNING CONCEPTS OF TYPICAL SEASIDE RESORTS IN THE MEIJI ERA ;'TORYUKAN' HOTEL BY JUN MATSUMOTO IN OISO AND 'KAIKIKAN' HOTEL BY NOBORU HAMANO IN INAGE. FOR THIS PURPOSE, BASED ON HISTORICAL DOCUMENTS, PICTURES AND PHOTOGRAPHS, INTERVIEW SURVEY, ETC., CHRONOLOGICAL INFORMATION ON THE INTRODUCTION OF SEA-BATHING INTO JAPAN, THE LOCATION OF THOSE HOTELS, AND THEIR CHANGE OF LAND USE WERE ANALYZED. THE COMPARATIVE STUDY WAS CONDUCTED AND THE MAIN FINDINGS ARE AS FOLLOWS; DR. MATSUMOTO AIMED AT MEDICAL EFFECTS PRODUCED BY THE WAVES DASHING AGAINST THE BODY, AND SO HIS HOTEL WAS LOCATED CLOSE BY THE SEASIDE TO APPROACH THERE EASILY. ON THE OTHER HAND, DR. HAMANO AIMED AT MEDICAL EFFECTS PRODUCED BY BREATHING OZONIC AIR, AND SO HIS HOTEL WAS LOCATED IN THE PINE WOODS.
1 0 0 0 OA 明治期におけるリゾートの形成 : 海水浴の普及過程に着目して
- 著者
- 東 美晴 アズマ ミハル
- 雑誌
- 流通経済大学社会学部論叢
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.23-37, 2004-10
- 著者
- 野瀬 元子
- 出版者
- 東洋大学大学院
- 雑誌
- 東洋大学大学院紀要 = Bulletin of the Graduate School, Toyo University (ISSN:02890445)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.31-56, 2008
1 0 0 0 Covid-19と「ホーム」
- 著者
- 倉光 ミナ子 福田 珠己
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, 2020
<p><b>1. はじめに</b></p><p> アジア女性資料センター(2020)はCovid-19と呼ばれる新型ウィルスの感染拡大が社会において、より弱い立場に置かれている女性や子どもたちに多大な負の影響を及ぼす可能性を指摘し、ジェンダー視点に基づいたCovid-19の影響を分析・考察し、それに基づいた提言を行う重要性を論じている。Covid-19のさらなる感染拡大を防ぐために、多くの先進諸国では「Stay at home」(日本では「#Stay home」や「#うちで過ごそう」)という呼びかけが行なわれ、それに基づき、様々な政策が展開されてきた。「ホーム(home)」の重要性については、1970年代には人文主義地理学の立場から主張されていたが、学際的な潮流ともかかわりながら「ホーム」の地理学研究が本格化したのは、1990年代以降、フェミニズムの影響を受けてからのことである。Covid-19の下で突如として現れた「ステイホーム」は何をもたらすのか。フェミニスト地理学の視点から考察・分析することは必要不可欠であると考える。</p><p><b>2.Covid-19によって再確認された点</b></p><p> 2011年の東日本大震災の折に、災害や危機というものが、第一に「平常時からの意思決定における女性の不在や、社会的・経済的なジェンダー不平等が、危機への対応において強く現れ、危機が過ぎ去ったあとにも、女性・少女の権利に長期的に影響をおよぼすこと」(アジア女性資料センター 2020)、第二にもともとそこの地域が抱えていた問題を先鋭化あるいは深刻化させることが指摘されている。同様のことは「ステイホーム」においても確認される。</p><p> まず、先進諸国政府等が「ステイホーム」と呼びかけた際には、フェミニスト地理学が批判してきたように、「ホーム」に暗黙のうちに「両親と子どものそろっている温かい家庭」(異性愛カップルによる家庭、近代家族)や「居心地のよい空間」というイメージが付与されていた。イメージの一面性や、これらがもたらす違和感は、企業やインターネットが使用したロゴ、特別定額給付金が世帯主に支給されたこと、そして、ホームレスや非正規就労者で仕事ともに住処を失った人や、家に帰ることのできない少女たちが行き場を失う報道からも明らかだろう。</p><p> 次に、先進諸国、とりわけ都市の「ホーム」が公私二元論に基づく、「プライベート」、「ケア」の空間であり、その管理・維持がたいてい女性によって成り立っていることである。2020年2月末の日本政府による全国一律の一斉休校や在宅勤務により「ケア」を一手に引き受けざるをえなかった女性たちの嘆きや怒りは様々なところで報道された(その一方で、狭い自宅では仕事ができず、車の中でオンライン会議に参加する夫の話もある)。</p><p> さらに、フェミニスト地理学が指摘してきたように、「ステイホーム」は、ホームが誰にとっても等しく安全な場所でないことも明らかにした。</p><p><b>3.さらなる「ホーム」の展開へ向けて</b></p><p> 「ステイホーム」はすでにフェミニスト地理学が論じてきた点だけでなく、さらなる「ホーム」の展開の可能性を示している。「ステイホーム」を通して、だれもが「ホーム」の意義を再考し、これまでの公私二元論や異性愛規範に基づいた「ホーム」とは別の次元の「ホーム」が想像され、つくられるのか、今後に期待したい。</p><p><参考文献リスト></p><p>アジア女性資料センター 2020.COVID-19とジェンダー: 分断と差別ではなく権利と連帯にもとづく対応を.http://jp.ajwrc.org/3808(最終閲覧日2020年7月17日)</p>
- 著者
- 小松 孝徳 森川 幸治
- 出版者
- 一般社団法人情報処理学会
- 雑誌
- 情報処理学会研究報告. ICS, [知能と複雑系] (ISSN:09196072)
- 巻号頁・発行日
- vol.137, pp.71-78, 2004-10-28
- 参考文献数
- 7
円滑なコミュニケーションを行っている二者間には,自ら表出した情報が相手のそれに対して相互的に同調していく「引き込み現象」がよく観察される.そこで本研究では,人間が簡便に表出できる音声の「発話速度(話速)」に注目し,人間同士の対話状況において話速に関する引き込み現象が観察されるのか,また,インタラクションの相手が人工物となった場合で観察されるのかを確認する実験を行った.まず,人間同士の対話における話遠の引き込み現象の有無を観察するために,英会話の教材のような10種類の原稿を10人の被験者同士で交互に読みあっている際の話遠を計測した.その結果,録音された計90発話の約63%にあたる57発話において,相手の話速に自分の話速を合わせようという『話遠の引き込み現象』が観察された.続いて,あらかじめ録音された様々な話速の音声を再生する自動応答システムと被験者とが同様の対話文を読みあう実験を行った結果,27人の被験者の計243発話のうち約76%における186対話において,話速の引き込み現象が観察された.
- 著者
- 関 正樹
- 出版者
- 日本精神科病院協会
- 雑誌
- 日本精神科病院協会雑誌 = Journal of Japanese Association of Psychiatric Hospitals (ISSN:13474103)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.11, pp.1174-1180, 2020-11
1 0 0 0 IR 高等学校化学におけるオンライン授業の試み : オンデマンド型教材の開発と配信
- 著者
- 沓脱 侑記 内海 良一 平松 敦史
- 出版者
- 広島大学附属中・高等学校
- 雑誌
- 中等教育研究紀要 (ISSN:13497782)
- 巻号頁・発行日
- no.67, pp.61-66, 2021-03-31
コロナ禍による全国一斉休校のなか,化学のオンライン授業の試みとして,授業動画の作成と配信を行った。本稿では対面授業とオンライン授業の違いを踏まえながら,オンデマンド型教材の開発過程や視聴した生徒の反応などについてまとめ,化学におけるオンライン授業のあり方について考察したい。
1 0 0 0 OA トライボロジー (摩擦・摩耗)
- 著者
- 似内 昭夫
- 出版者
- マテリアルライフ学会
- 雑誌
- マテリアルライフ (ISSN:09153594)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.2, pp.75-78, 2000-04-30 (Released:2011-04-19)
- 参考文献数
- 11
1 0 0 0 OA スギ花粉飛散量の変動に伴うスギ特異的IgE抗体価の経年的変化
- 著者
- 荻野 敏 入船 盛弘 有本 啓恵 岩田 伸子 荻野 仁 菊守 寛 瀬尾 律 竹田 真理子 玉城 晶子 馬場 謙治
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.4, pp.247-251, 2006-07-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 5
73名のスギ花粉症患者を対象に、スギ、ヒノキ花粉の飛散量にかなりの変動が認められた2001年1月からの3年間、特異的IgE抗体価の経年的変化を検討した。スギ、ヒノキの大量飛散によりスギ、ヒノキ特異的IgE抗体価は翌年の1月には有意に上昇し、飛散少量年の翌年には有意に低下する経年的な変化が見られた。それに対し、HD、カモガヤでは同様の変動は見られなかった。この変動は年齢にかかわらず認められた。以上のように、特異的IgE抗体価はアレルゲンの曝露量に極めて大きな影響を受け、スギ、ヒノキ花粉の大量飛散後には、特異的IgE産生が亢進し、翌年まで高抗体価を持続することから、少量飛散年と予測されても被曝量を減らすことを考慮した生活指導が必要と思われた。