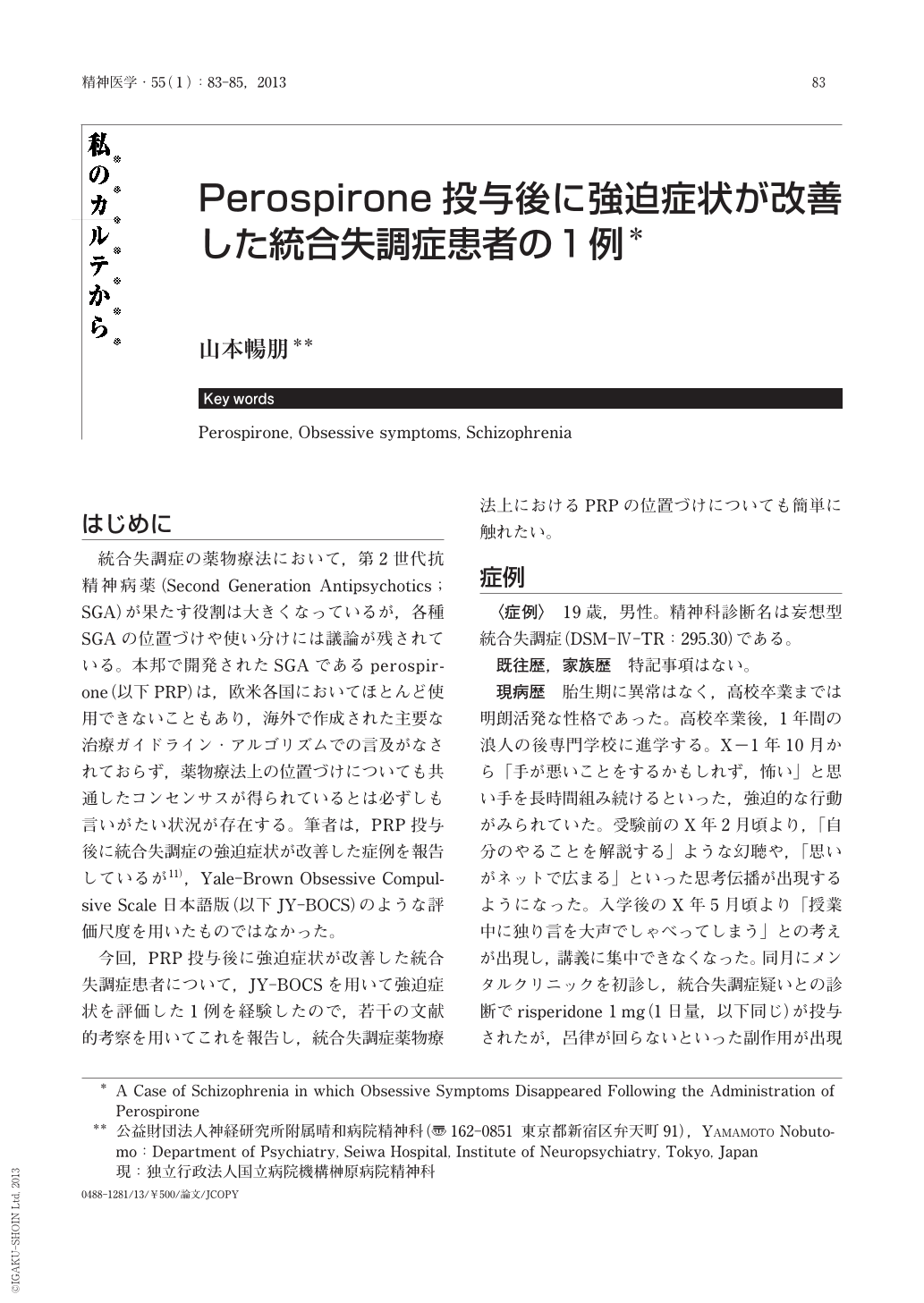- 著者
- 大塚 直彦 河野 俊彦 国枝 賢 大澤 孝明
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.2, pp.101-105, 2018 (Released:2020-04-02)
- 参考文献数
- 3
IAEA核データセクション(NDS)は,核データの収集・整備・配布・教育を通じて,原子力・非原子力分野における核物理の成果の平和利用を半世紀以上にわたり支援している。これらはいずれも国際協力事業であり,核データの先進国である我が国の大学・研究機関の核データ研究者が長年にわたって貢献している。本稿ではセクションの概要と実施事業を紹介する。
- 著者
- 須山 賢也 国枝 賢 深堀 智生 千葉 豪
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.10, pp.598-602, 2017 (Released:2020-02-19)
- 参考文献数
- 5
核データとは狭義には原子核と中性子の反応の確率であるが,一般的に言えば,原子核の物理的変化や反応の様子を表現するデータの事である。我が国が原子力開発に着手して以来,核データの開発は重要な技術開発のテーマであり,現在我が国の核データライブラリJENDLは世界で最も高い精度と完備性を兼ね備えた核データファイルの一つとして国際的に認知されている。本連載講座では,原子力開発に関係している方々を対象とし,シグマ特別専門委員会の監修を経て,核データ開発の意義,核データの開発の最新の状況,国際的な動向,そして今後の開発の方向性を解説する。
1 0 0 0 IR 特定保健指導の展開過程における課題と対応方法
- 著者
- 杉田 由加里 山下 留理子
- 出版者
- 千葉大学大学院看護学研究科
- 雑誌
- 千葉大学大学院看護学研究科紀要 (ISSN:21859698)
- 巻号頁・発行日
- no.37, pp.47-56, 2015-03
本研究の目的は,特定保健指導の展開過程(保健指導の準備,対象との信頼関係の構築,アセスメント,気づきの促し,対象者の自己の健康行動と科学的根拠のある方法の理解の促進及び教材の選定,目標の設定,継続フォロー,評価)における困難だと感じた状況(以下,課題)と課題への対応方法を明らかにすることである.研究参加者は,自治体5か所,全国健康保険協会3か所,委託業者1か所の9か所に所属する,特定保健指導の熟練者計11人(保健師9人,管理栄養士2人)とした.団体ごとのグループでの半構成的インタビューを実施した(平成25年2~3月).調査内容は先行研究から作成した特定保健指導における課題に対しどのように対応しているか,保健指導の場面を想起し語ってもらった.分析方法は,調査項目ごとに要約を作成し,各要約の同質性を判断しカテゴリとし,対応方法としてまとめた.特定保健指導の展開過程における課題として25項目に整理でき,課題への対応方法として計123項目が明らかとなった.アセスメントにおける多様な課題に対する対応方法を示せたことは,実践において有益であり,活用可能性が高いと考える.保健指導の評価の段階における対応方法に関して全部の種別の団体から抽出することができず,実践されている状況が少ないとも考えられる.保健指導スキルを向上させていくには重要な段階と考えられ,人材育成を充実させていく方向性が示唆された.
はじめに 統合失調症の薬物療法において,第2世代抗精神病薬(Second Generation Antipsychotics;SGA)が果たす役割は大きくなっているが,各種SGAの位置づけや使い分けには議論が残されている。本邦で開発されたSGAであるperospirone(以下PRP)は,欧米各国においてほとんど使用できないこともあり,海外で作成された主要な治療ガイドライン・アルゴリズムでの言及がなされておらず,薬物療法上の位置づけについても共通したコンセンサスが得られているとは必ずしも言いがたい状況が存在する。筆者は,PRP投与後に統合失調症の強迫症状が改善した症例を報告しているが11),Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale日本語版(以下JY-BOCS)のような評価尺度を用いたものではなかった。 今回,PRP投与後に強迫症状が改善した統合失調症患者について,JY-BOCSを用いて強迫症状を評価した1例を経験したので,若干の文献的考察を用いてこれを報告し,統合失調症薬物療法上におけるPRPの位置づけについても簡単に触れたい。
- 著者
- 岩田 康之
- 出版者
- 日本教育行政学会
- 雑誌
- 日本教育行政学会年報 (ISSN:09198393)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.153-156, 2017
- 著者
- Ryutaro Kasedo Atsuhiko Iijima Kiyoshi Nakahara Yusuke Adachi Isao Hasegawa
- 出版者
- Japanese Society for Medical and Biological Engineering
- 雑誌
- Advanced Biomedical Engineering (ISSN:21875219)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, pp.26-31, 2021 (Released:2021-02-11)
- 参考文献数
- 15
The rhythm of vocalizing a written language depends on a merge process that combines meaningless linguistic units into a meaningful lexical unit, word, or Bunsetsu in Japanese. However, in most previous studies, written language was presented to the participants in lexical units (word-by-word) with explicit inter-word (or inter-Bunsetsu) marks or spacing. Therefore, it has been difficult to conduct psychophysical assessment of the participants' own speed in segmenting meaningful units from unstructured written language when reading. Here, we hypothesized that the spontaneous reading speed of Japanese readers reflects their own punctuation process, even when sentences are written without punctuation marks or spaces. To test this hypothesis, we developed a new “self-paced sequential letterstring reading task,” which visually presents sentences letter-by-letter. The task required participants to push a button to proceed to the next letter at their own pace, hence allowing evaluation of the reaction time (RT) to individual letters. We found that the average RT decreased parametrically as the position of the letter approached the end of a Bunsetsu. Moreover, the RT increased drastically at the last letter completing the Bunsetsu. Participants were not shown any punctuation marks and not instructed to explicitly recognize the punctuations during reading. Therefore, these effects strongly suggest that the implicit and spontaneous punctuation is the origin of the rhythm in reading. These results show that spontaneous punctuation of letterstring affects the reading speed. The task we have developed is a promising tool for revealing the temporal dynamics of natural reading, which opens a way to shape the fluency of script-to-speech human interfaces.
1 0 0 0 OA 都市中心駅の駅前広場における容量不足の要因及び課題に関する研究
- 著者
- 小滝 省市 高山 純一 中山 晶一朗 埒 正浩
- 出版者
- 公益社団法人 土木学会
- 雑誌
- 土木学会論文集D3(土木計画学) (ISSN:21856540)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.5, pp.I_723-I_733, 2014 (Released:2015-05-18)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 2
本研究では,地方都市の中心駅の駅前広場を対象として,都市計画現況調査1)のデータや都市計画部局職員へのアンケート調査,実地調査の結果を元に,駅前広場の整備の実態と容量不足の要因について分析し,面積算定基準において具体的な方針が示されていない一般車用施設の規模算定方法に関する課題を明らかにした.その結果,中心駅の駅前広場の約89%が整備中または整備済であり,内,約67%が混雑し,約51%が一般車用施設が不足するとしている.また,駅前広場における一般車用施設の容量不足の要因は,経年などによる想定以上の交通量の増加や,待合車両の対応を計画に見込んでいないことから,平均停車時間の計画値と実態値の乖離にあることを明らかにした.
1 0 0 0 OA 2007年2月14日に八甲田山系前岳で発生した雪崩
- 著者
- 阿部 修 力石 國男 石田 祐宣 小杉 健二 上石 勲 平島 寛行
- 出版者
- The Japanese Society of Snow and Ice
- 雑誌
- 雪氷 (ISSN:03731006)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.513-518, 2007-07-15 (Released:2009-08-07)
- 参考文献数
- 5
2007年2月14日午前11時過ぎに八甲田山系前岳の北東斜面で発生した表層雪崩について,現地調査および周辺の気象・積雪観測からその発生要因を考察した.その結果,この雪崩は強風により生じた吹きだまりの一部が崩落した可能性があることがわかった.また,今回雪崩があった沢は,典型的な雪崩地形であることがわかった.
1 0 0 0 OA ホワイト・ライノ計画概要
- 著者
- 藤井 明 槻橋 修
- 出版者
- 東京大学生産技術研究所
- 雑誌
- 生産研究 (ISSN:0037105X)
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.7, pp.332-335, 2001 (Released:2008-06-16)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 IR 労働分配率の決定メカニズム : 賃金率と経済成長
- 著者
- 日隈 健壬
- 出版者
- 広島経済大学経済学会
- 雑誌
- 研究論集 (ISSN:03871401)
- 巻号頁・発行日
- no.5, pp.43-56, 1972-01
Ⅰ.はじめに Ⅱ.相対的分け前の理論の史的展開とモデル化 (1) 古典派分配理論 (2) 新古典派分配理論 (3) ケインズ派分配理論 (4) 総合理論…(以上,福岡大学既刊)Ⅲ.相対的分け前の決定因としての集計的需要と独占(1) 集計的需要と総合理論 (2) 独占度理論と総合理論…(以上,福岡大学既刊)Ⅳ.相対的分け前に関する統計的実証 (1) 労働分配率の決定メカニズム-賃金率と経済成長-…(以上,本稿)(2) 利潤分配率の決定メカニズム-投資と利潤率- Ⅴ.相対的分け前に関する計量分析Ⅵ.結び
1 0 0 0 OA Dempster-Shafer 理論を用いた意思決定問題における証拠優位則
- 著者
- 乾口 雅弘 白井 正志 坂和 正敏
- 出版者
- The Society of Instrument and Control Engineers
- 雑誌
- 計測自動制御学会論文集 (ISSN:04534654)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.6, pp.720-728, 1994-06-30 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1
In this paper, the concept of stochastic dominance is introduced to Dempster-Shafer theory of evidence and several kinds of evidential dominance are proposed. In Dempster-Shafer theory of evidence, the expected utility is obtained as an interval. The seven kinds of inequalities between intervals are defined. The relationships among these seven inequalities are investigated. Using these inequalities, seven kinds of evidential dominance are defined. A necessary and sufficient condition for each evidential dominance is discussed. The usefulness of each evidential dominance is examined by a numerical simulation.
1 0 0 0 言語の錯乱
- 著者
- 楜沢 健
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.11, pp.23-33, 2014
<p>一九二六年に刊行がはじまった「円本」は、「標準語=文学」とみなす日本語規範の見本となった。以後、「正しい」「美しい」日本語の名のもとに、「文学」の序列と差別、検閲と言葉狩り、言語の矯正と調教が猛威をふるう。労働者や農民や女性や異民族の「汚い」「間違った」日本語を記述することから出発したプロレタリア文学は、標準語の序列や矯正や調教に抗い、その規範に錯乱をもたらす、反日本語、反標準語、反文学、反国語の運動にほかならなかった。本論では、プロレタリア文学における日本語批判の諸相に光をあてた。</p>
- 著者
- Sarah Helene AARESTAD Anette HARRIS Ståle V. EINARSEN Ragne G. H. GJENGEDAL Kåre OSNES Marit HANNISDAL Odin HJEMDAL
- 出版者
- National Institute of Occupational Safety and Health
- 雑誌
- Industrial Health (ISSN:00198366)
- 巻号頁・発行日
- pp.2020-0064, (Released:2021-01-28)
- 被引用文献数
- 3
The study investigated relationships between exposure to bullying behaviours, return to work self-efficacy (RTW-SE) and resilience, and if resilience moderates the bullying-RTW-SE relationship among patients on sick leave or at risk of sick leave due to common mental disorders (CMD). A sample of 675 patients treated in an outpatient clinic was analysed using regressions and moderation analyses by employing SPSS and the Process macro SPSS supplement. The results showed a negative relationship between exposure to bullying behaviours and RTW-SE. There was also a positive main effect for resilience, as patients with high resilience score significantly higher on RTW-SE than patients with low resilience irrespective of levels of bullying. Further, the resilience sub-dimension personal resilience moderated the bullying-RTW-SE relationship, while the sub-dimension interpersonal resilience did not. Patients high on personal resilience showed relatively lower RTW-SE scores when exposed to bullying behaviours, compared to those that were not bullied with high personal resilience levels. Hence, one should take note of the fact that even if resilience may strengthen RTW-SE, bullying is an adverse event which particularly affects individuals who present with relatively high levels of resilience resources, at least when it comes to RTW-SE.
- 著者
- HIDEO UEDA CHICHIBU NAMEKI HARUHIKO SARUTA HIROTOSHI KAWAMURA AKIRA YOSHIDA AKIJI TSUZUKU
- 出版者
- THE JAPANESE CIRCULATION SOCIETY
- 雑誌
- 日本循環器學誌 (ISSN:00471828)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.8, pp.361-375, 1957-11-20 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 8 11
1 0 0 0 OA 韓国における大豆利用発酵食品
- 著者
- 島田 彰夫
- 出版者
- 公益財団法人 日本醸造協会
- 雑誌
- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, no.2, pp.103-108, 1986-02-15 (Released:2011-11-04)
- 参考文献数
- 3
日本の味噌, 醤油の歴史を顧みるとき, 韓国における大豆発酵食品を無視することはできない。味噌・醤油のような発酵食品の起源は遠く3千年の昔, 中国にあったといわれ, そのプロトタイプが日本に伝来する道として, 朝鮮半島を経由するものと, 直接東支那海を渡来するものがあった。韓国におけるテンジャン, カンジャンのジャンは中国の「醤」に由来するとみられる。そして, 韓国のメジュは日本の味噌玉へと伝わる。今日テンジャン, カンジャンの姿は, 豆味噌地帯の溜り味噌と溜りに見られる。最近韓国における食生活を調査された著者に最近の大豆発酵食品について執筆願った。
1 0 0 0 OA タイとミャンマーにおける無塩発酵大豆食品の製法と植物利用の特徴
- 著者
- 横山 智
- 出版者
- 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理学会大会 研究発表要旨 2010年 人文地理学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.38, 2010 (Released:2011-02-01)
1.はじめに 発表者は、東南アジアのナットウに興味を持ち、これまで研究報告が存在しなかったラオスのナットウを調査し、中国雲南省からの伝播ルートとタイからの伝播ルートが混在していることを明らかにした。しかし、先行研究では、タイのナットウ(トゥア・ナオ)は、ミャンマーのナットウ(ペポ)と同じグループと論じられている。 そこで本研究では、2009年に実施した北タイとミャンマーの市場調査とナットウ製法調査をもとに、発酵の際に菌を供給する植物に着目して、ミャンマーおよび北タイのナットウの類似点と相違点を解明することを目的とする。 2.販売されているナットウの種類 北タイで製造されるナットウは、(1)粒状、(2)ひき割り状、(3)乾燥センベイ状の3種類に大別することができる。ただし、日本の「納豆」と同じ「粒状」ナットウは、現地の市場で見かけることはほとんどない。北タイでは、タイ・ヤーイと称されるシャン人(ミャンマーのシャン州出身)の村では見ることができるが、それ以外の市場では、「ひき割り状」か「乾燥センベイ状」しか売られていない。 一方、ミャンマーで製造されているナットウは、多様性に富んでいる。北タイに多い「ひき割り状」と「乾燥センベイ状」以外に、シャン州のムセーの市場では、油で揚げて甘い味付けをしたもの、豆板醤のようなソースをからめたもの、そして乾燥したものなど、「粒状」を加工したナットウが多く売られていた。さらに「ひき割り状」を一度乾燥させた後に蒸かして円筒状に形を整えた珍しいナットウも売られていた。しかし、日本の「納豆」のような糸引きナットウは、2009年の調査で訪れたシャン州内の市場では少なかった。ところが、バモーより北のカチン州に入ると、シャン州で見られたような加工された「粒状」ナットウよりも、糸が引く日本の「納豆」と同じ「粒状」ナットウの比率が高くなり、カチン州都のミッチーナ市場では、強い糸が引く「粒状」ナットウがほとんどであった。 3.ナットウの製法と地域的特徴 北タイとミャンマーのナットウの製法は基本的に同じである。大豆を水に浸した後、柔らかくなるまで煮て、その後、プラスチックバックや竹カゴに入れて数日間発酵させれば、「粒上」のナットウができあがる。なお、どの地域でも発酵のために種菌を入れることはない。その後、粒を崩し、塩や唐辛子などの香辛料を混ぜて「ひき割り状」のナットウとし、さらに「乾燥センベイ状」の場合は、形を整えて天日干しする。この製造工程のなかで、地域的な差異が見られるのが、菌の供給源となる植物の利用である。 シダ類(未同定)とクワ科イチジク属は、ヒマラヤ地域で製造されているナットウの「キネマ」でも利用されていることが報告されており、カチン州との類似性が見られた。またシダ類は、シャン州でも利用されているため、ヒマラヤ地域の「キネマ」とミャンマー全域の「ペポ」との類似性も見いだすことができよう。そして、チークの葉およびフタバガキ科ショレア属の利用という視点からは、シャン州と北タイに類似性があることが判明した。 本研究の結果は、以下のようにまとめることができる。北タイとミャンマーのシャン州で大規模に「乾燥センベイ状」ナットウを生産している世帯では、発酵容器に竹カゴは用いられず、肥料袋のようなプラスチックバックに煮た大豆を数日間保存するだけであり、菌の供給源となる植物も入れない。 形状と糸引きの強弱に関しては、シダ類やイチジク属を用いているヒマラヤ地域とカチン州は「粒状」が多く、糸引きも強い傾向がある。チークやショレア属の葉を用いるシャン州や北タイは、多くが「乾燥センベイ状」で、粒状の場合でも糸引きが弱いことが明らかになった。 4.おわりに 本研究では、これまでの議論とは視点を変えて、菌を供給する植物に焦点をあて、植物利用からナットウ製法の地域区分を実施することを試みた。それの結果、これまで全く議論されていなかった、ミャンマーとタイでの類似点と相違点、そしてミャンマー内での類似点と相違点を解明できた。これらの結果をもとに、未だ達成できていない中国側での植物利用調査を進めることが出来れば、東南アジアのナットウが中国からの伝播かどうかを議論する際の重要な手がかりになると思われる。
1 0 0 0 OA ネパールの発酵食品 ―ネパールの麹「マーチャ」と納豆様大豆発酵食品「キネマ」―
- 著者
- 新国 佐幸
- 出版者
- 一般社団法人 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.3, pp.234-239, 1996-08-20 (Released:2013-04-26)
- 参考文献数
- 32
1 0 0 0 ペルゲル・フェット異常のノルウェージャンフォレストキャットの1例
- 著者
- 酒井 秀夫 阿野 仁志 久世 法子 酒井 聖花
- 出版者
- 動物臨床医学会
- 雑誌
- 動物臨床医学 (ISSN:13446991)
- 巻号頁・発行日
- vol.26, no.4, pp.182-185, 2017
<p>9歳の去勢雄のノルウェージャンフォレストキャットが健康診断のため来院した。一般血液検査では変性性左方移動が認められた。 血液塗抹では好中球,好酸球,好塩基球および単球に核の低分葉が認められ,それらは1年以上継続してみられた。血液化学検査,画像診断,微生物検査(FIV, FeLVなど)および,骨髄検査の結果から偽ペルゲル・フェット異常を除外し,ペルゲル・フェット異常と診断した。</p>
1 0 0 0 OA 食品トレースの実態と課題 —食品表示偽装は防げるか—
- 著者
- 吉松 惠子
- 出版者
- 一般社団法人 画像電子学会
- 雑誌
- 画像電子学会誌 (ISSN:02859831)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.200-204, 2009-03-25 (Released:2011-08-25)
- 参考文献数
- 3
1 0 0 0 IR 闇の深さ・陰の濃さを知る教育--大学教育における教職科目・道徳教育の位置づけ
- 著者
- 弘田 陽介
- 出版者
- 徳島大学
- 雑誌
- 大学教育研究ジャーナル (ISSN:18811256)
- 巻号頁・発行日
- no.7, pp.152-158, 2010-03