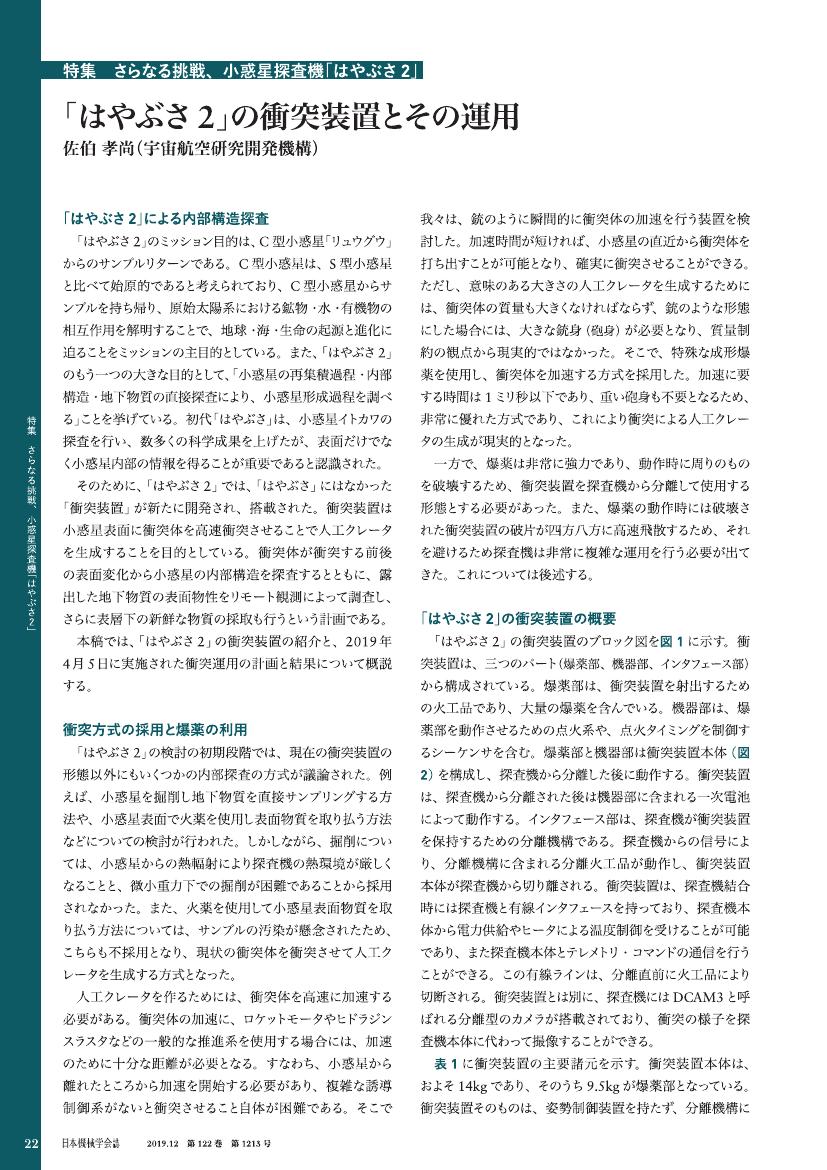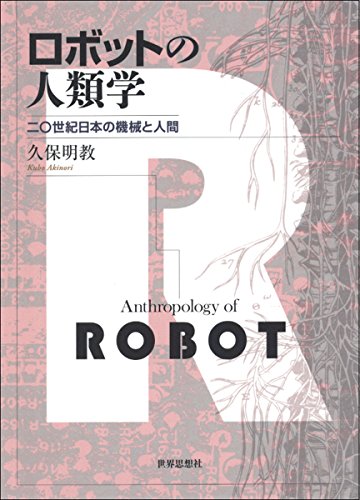1 0 0 0 OA 寒冷刺激時の自律神経系に及ぼす香りの効果
- 著者
- 濱谷 章史 真栄城 敦 寺井 明喜子 山田 弘司 島田 浩次 金木 則明
- 出版者
- Japan Ergonomics Society
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.Supplement, pp.286-287, 2001-09-04 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 4
- 著者
- Sayaka Tomatsu Masaki Takahashi Masakazu Kakuni Gen Toshima Fumiko Kimura Junichiro Takahashi Yui Umekawa Akira Sasaki Keishi Hata
- 出版者
- Japan Science Society of Biological Macromolecules
- 雑誌
- Journal of Biological Macromolecules (ISSN:13472194)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.1, pp.51, 2021 (Released:2021-01-20)
- 参考文献数
- 6
1 0 0 0 OA 性同一性障害に対する手術後音声障害の1例
- 著者
- 目須田 康 西澤 典子 松村 道哉 古田 康 福田 諭
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.5, pp.358-361, 2005-09-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 11
性同一性障害は過去8年の間に本邦にても診断・治療が施行されるようになったが、音声の変化を望む症例に対する治療、特にMTF (male to female) に対するピッチ上昇手術はこれまでガイドラインに明確な定義がされていなかったこともあり、本邦における報告は極めて少なく、手術を強く希望する場合海外の施設を訪れている例があると推測される。今回われわれは東南アジアの某国でピッチ上昇手術を受け、帰国後発声開始後に高度の気息性発声を呈した例を経験した。肉芽切除と各種保存的治療が施行されたが手術後約5カ月の時点で患者の満足は得られていない。今後本邦でも各地で性同一性障害で音声変更を望む例が出現すると予想されるため、ピッチ上昇手術の適応の検討、またこの問題における関係各科との連携の重要性について改めて認識することが必要であると考えられた。
- 著者
- 佐伯 孝尚
- 出版者
- 一般社団法人 日本機械学会
- 雑誌
- 日本機械学会誌 (ISSN:24242675)
- 巻号頁・発行日
- vol.122, no.1213, pp.22-25, 2019-12-05 (Released:2020-04-01)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 橘 寿好 長谷川 泰子 村口 喜代
- 雑誌
- 思春期学 = ADOLESCENTOLOGY (ISSN:0287637X)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.200-206, 2003-06-25
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 3
1 0 0 0 OA 田山花袋作「少女病」を読む : メディア都市TOKIOの誕生(1)
- 著者
- 勝又 正直
- 雑誌
- 名古屋市立大学看護学部紀要 = Bulletin of Nagoya City University School of Nursing (ISSN:13464132)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.95-98, 2002-03
1 0 0 0 OA 『福翁自伝』の英学史関連記述について 幕末英学者たちの研究から
- 著者
- 石原 千里
- 出版者
- 日本英学史学会
- 雑誌
- 英学史研究 (ISSN:03869490)
- 巻号頁・発行日
- vol.1995, no.27, pp.179-192, 1994 (Released:2009-10-07)
- 参考文献数
- 30
Fukuzawa's visit to Yokohama, one of the ports newly opened on July 1, 1859, has been regarded as one of the most important events in his life. His experiences at the open port made him decide to begin learning English, giving up Dutch which he had learned desperately for many years. His great achievements in westernization of Japan in his later years implicit in this event.The present article presents evidence enough to prove that this impressive episode, however, is a fiction. In reality he had started his English study certainly before the opening of Yokohama.The other episodes on his efforts of studying English, the persons from whom he learned English, his three visits abroad and a number of English books he brought back on each occasion contain several points seriously out of accord with the actual facts.It seems to be most unfortunate that Fukuzawa paid no respects to numerous pioneers of English studies in Japan many years before him, as a result of giving himself the position as such in his autobiography.Conscious and unconscious fictionalization is a destiny of an autobiography, and this masterpiece by Fukuzawa the great cannot be an exception.
- 著者
- 田中 直人 老田 智美
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 学術講演梗概集. E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎 (ISSN:13414518)
- 巻号頁・発行日
- no.2004, pp.895-896, 2004-07-31
- 被引用文献数
- 1
1 0 0 0 OA 乾燥ワカメ表面の白い斑点
- 著者
- 伊藤 龍星
- 出版者
- 大分県農林水産研究指導センター水産研究部
- 巻号頁・発行日
- no.1, pp.7-10, 2011 (Released:2012-12-06)
2009年3月下旬に大分県杵築市で採集され、素干し乾燥されたワカメの表面に、白い斑点を多数生じたものがあったので、原因について調査した。1 乾燥ワカメを海水に戻して顕微鏡観察したところ、藻体表面にある毛巣から伸長している毛に、大量のリクモフォラ属珪藻が付着していることが判明した。2 この珪藻が乾燥により白く変色し、斑点として見えたものと判断された。
本研究では、テロメラーゼ依存性アデノウイルスOBP-301(Telomelysin)に多機能がん抑制遺伝子であるp53を搭載した次世代型武装化ウイルス製剤 OBP-702(Pfifteloxin)の膵癌間質細胞による免疫抑制機構への効果を検証し、臨床試験用ロットの大量製造が進む本製剤の難治性膵癌を対象とした実用化を目指す。特に、がん関連線維芽細胞(cancer-associated fibroblast; CAF)の免疫抑制分子であるTGF-β発現調節や免疫活性化に繋がるPTENがん抑制遺伝子の膵癌細胞での発現調節に着目してin vitroおよびin vivoでの解析を進める。
1 0 0 0 ロボットの人類学 : 二〇世紀日本の機械と人間
1 0 0 0 OA 社会福祉におけるスピリチュアリティ : 宗教と社会福祉の対話
- 著者
- 木原 活信 Katsunobu Kihara
- 出版者
- 基督教研究会
- 雑誌
- 基督教研究 = Kirisutokyo Kenkyu (Studies in Christianity) (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.1, pp.17-41, 2016-06-21
社会福祉とキリスト教の関係について、福祉国家以前の慈善時代と、福祉国家下の措置制度時代、そしてポスト福祉国家としての現代の市民的契約の時代の3つに分類しつつ、そこでの宗教の役割の変遷についてキリスト教を例にスピリチュアリティの概念をもとに分析した。そのなかで市民契約の時代の宗教と社会福祉の在り方に着目し、市民的公共圏における社会福祉とスピリチュアリティについてEdward Candaの理論を踏まえつつ、議論した。
1 0 0 0 OA 兵庫県下の鉱物資源
- 出版者
- 兵庫県立人と自然の博物館
- 雑誌
- 人と自然 (ISSN:09181725)
- 巻号頁・発行日
- vol.6, pp.197-243, 1995 (Released:2019-10-31)
Hyogo Prefecture has been known as one of prominent prefectures for metallic and nonmetallic mineral resources in Japan. There are variety of types of (1) metallic deposits and (2) non-metallic deposits in Hyogo Prefecture as shown below: (1) metallic deposits: polymetallic (Cu ・ Zn ・ Pb) vein deposits, Zn ・ Pb skarn deposits, bedded cupriferous pyrite deposits (Kieslager deposits), Au-Ag vein deposits, Ni deposits, podiform Cr deposits, bedded Mn deposits, Mo deposits and Fe skarn deposits, and (2) non-metallic deposits: strata-bound brick-silic astone (Keiseki) deposits, talc deposits, feldspar deposits, pottery stone (Toseki) deposits, and Roseki (pyrophyllite-, kaolin-, or sericite-clay )deposits. Especially, the Ikuno and Akenobe mining region has been famous as one of the largest and significant metallogenic regions in Japan and the large-scale Sn-W-bearing polymetallic vein deposits has been mined for copper, zinc, lead and tin. In this paper, location and type of ore deposit, geological setting, host rock of ore deposit, grade and constituent minerals of ore, metallogenic period and history of mining are briefly reviewed and summarized for each metallic and non-metallic mine in Hyogo Prefecture.
1 0 0 0 IR サルタ-ティの人文主義と「僣主論」--バロン史学への疑問と考察
- 著者
- 石坂 尚武
- 出版者
- 史学研究会 (京都大学文学部内)
- 雑誌
- 史林 (ISSN:03869369)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.4, pp.p585-612, 1985-07
個人情報保護のため削除部分あり十五世紀のフィレンツェの人文主義に対して、「市民的人文主義」という歴史概念をもって分析を展開したバロンのルネサンス史学は、一定評価されている。彼は、十四世紀の人文主義から十五世紀のそれへの移行を、中世的なものから近代的なものへの発展として捉え、サルターティはそこで過渡的役割を果したとされる。すなわちサルターティは、市民的、共和主義的立場を明言して十五世紀の新しい人文主義を示唆するところがあったが、結局、晩年における借主の台頭の中で、宗教的、君主主義的な十四世紀の人文主義に回帰したとされる。このバロンの判断は『僭主論』の解釈による。しかしその解釈は、文献の客観的読解、著作の書かれた背景の認識、そして人文主義的著作へのアプローチにおいて疑問が残る。特に人文主義者における修辞学的志向に配慮すべきである。『僭主論』の解釈に問題がある以上、それを前提とした彼のサルターティ観、「市民的人文主義」も再検討されるべきであろう。
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経情報ストラテジ- (ISSN:09175342)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.10, pp.42-44, 2007-11
企業による不祥事が後を絶たない。謝罪会見を開きながら、「調査中」などを理由に核心を隠す光景は日常茶飯事だ。しかし、これまでにない新しい動きもある。大和総研経営戦略研究所の大村岳雄・主任研究員は「信頼回復のために"ネガティブ情報"を積極的に出す企業が増えている」と指摘する。
1 0 0 0 サモアにおける地理教育の特色
- 著者
- 新井 教之
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- 日本地理学会発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, 2019
<p>サモアの地理教育の特色について,サモアの社会科,地理のシラバスや教科書をもとに分析を行った。サモアの地理教育はニュージーランドやオーストラリアの影響を受けていること,地球温暖化の対応など理科的な要素も強い特徴があった。</p>
- 著者
- 泉 貴久
- 出版者
- 日本ニュージーランド学会
- 雑誌
- 日本ニュージーランド学会誌 (ISSN:18839304)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, pp.28-43, 1995
1 0 0 0 OA 夜刀の神 口訳風土記別記三(帯短襷長録)
- 著者
- 吉野 裕
- 出版者
- 日本文学協会
- 雑誌
- 日本文学 (ISSN:03869903)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.2, pp.35-42, 1970-02-01 (Released:2017-08-01)
- 著者
- 野田 知子 伊深 祥子
- 出版者
- 日本家庭科教育学会
- 雑誌
- 日本家庭科教育学会大会・例会・セミナー研究発表要旨集
- 巻号頁・発行日
- vol.53, pp.82, 2010
家庭科教育学会課題研究1-1のグループでは、「食に関する教育 ―行動変容を目指した授業の検討―」という課題に取り組んだ。課題研究では、授業において、生徒が自己効力感をもつことが、意識と行動の変容を起こすことになるのではないかという仮説を立てた。 <br>研究の目的<br> 自己効力感を高める授業の要素は何か、を明らかにする。<br>研究の方法<br> 授業後の自由記述調査により、自己効力感が高まったという結果を得た、授業「なぜひとりで食べるの」(授業者:伊深祥子)を研究対象として、授業内容を録音、文字化して、次の二つの方法で分析した。<br>A.授業後、5人の教師・研究者で構成される研究会で、授業内容を共有した上で、授業者が省察し、検討をした。その内容を授業記録の「教師の思い・判断」に記入、また、その時の「教室の雰囲気」、授業の中での生徒の発言に対して教師が「発言の意味を推測」して記入して検討した。<br>B.授業記録から、教師と生徒の対応の仕方の特徴を探った。<br>省察(reflection)を協同でおこなう意味<br> 「教師の思い・判断」について、授業者は「研究会で言葉にして初めて認識した」と述べている。授業の中で、教師はその瞬間にとっさの判断で生徒の言葉に応えたり質問したりしている。その時の思いは記録には残らない。そこで複数の教師・研究者との協議の中で、その時、なぜそのような言葉を発したのかを思いだし言葉にすることで、「教師の思い・判断」が明確になる。また同時に、そのことが授業者・協議参加者の学びになる。<br>授業の流れ<br> 【_丸1_自分の食卓の絵を描く _丸2_VTR「なぜ一人で食べるの」(NHK1999年)を視聴する _丸3_「一人で食べる子どもたち」について考えたことを書く _丸4_皆の書いた考えを印刷して配り、その中からふたつ選んで、共感・批判の意見を述べる】 分析した授業は_丸4_の授業である。<br>結果<br>1.参加型の授業である<br> 授業は、生徒の声が交流する授業、教師と生徒が応答する授業である。・「なんで?」という言葉が13回以上記録されている。・「こんなこと話し合っても意味ないじゃないの。何も変わらないんじゃないの」というような授業の意味を否定する意見も言える。<br> 生徒が主体的に自分の言葉で発言できることは自己効力感を高めることの土台となると考える。 参加型の授業ができる要素として下記の3点があげられる。<br> _丸1_積極的に考える生徒(「考える授業」に取り組む)<br> _丸2_意見・批判・共感等をじっくり考えさえ述べることの出来る時間<br> _丸3_入学時から取り組んだ教室の風土など<br>2.共感を示す教師・発言する生徒の存在をまるごと受け止める教師<br> ・・授業者は「一人で食べる事が多いので、全員で食べたら疲れちゃったんだね」など、生徒の発言に共感を示す対応をしている。「共感」という言葉が、1コマの授業の中で、教師13回、生徒5回記録されている。<br>・発言している生徒に対して、「Kの家は複雑な家庭だ。大丈夫かな?」<br> 「ちょっとKを助けよう」など、生徒の背後にある家庭状況なども考慮して応答している。<br> 生徒の多様な意見や生徒の存在を丸ごと受け止める教師、価値観の一方的な押しつけはしない教師の姿勢が、生徒の発言意欲につながり、生徒の声が交流する授業を成立させ、生徒の自己効力感を高めることにつながると考える。