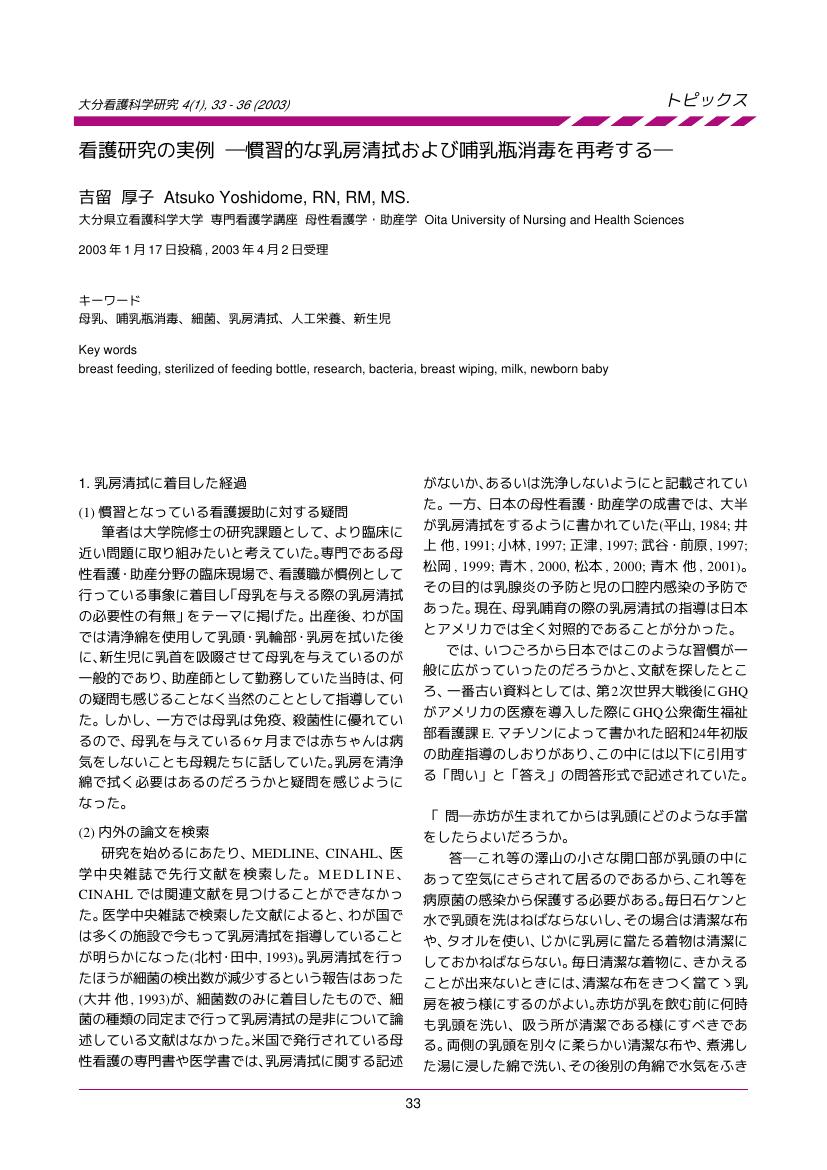1 0 0 0 OA 小学校2年生国語科における季語さがしと俳句づくり : 生活科学習との連繋の試み
- 著者
- 島本 政志 皆川 直凡
- 出版者
- 鳴門教育大学
- 雑誌
- 鳴門教育大学授業実践研究 : 授業改善をめざして = Naruto University of Education forum for classroom research (ISSN:13471120)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.137-143, 2019-07
Ⅲ大学以外の授業実践研究
1 0 0 0 OA 古墳社会の成立
- 著者
- 友廣 哲也
- 出版者
- 一般社団法人 日本考古学協会
- 雑誌
- 日本考古学 (ISSN:13408488)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.16, pp.71-91, 2003-10-20 (Released:2009-02-16)
- 参考文献数
- 128
群馬県域の遺跡からは弥生時代終末から古墳時代前期にかけて多数の外来土器が出土する。このため群馬県域における古墳時代の成立は外からのインパクト・圧力によるところが大きいとされている。1952年群馬県太田市石田川改修工事で偶然発見された土師器の中に,当時は出自が分からなかったS字状口縁台付甕が含まれていた。発見当初より群馬県内の土師器は,どこかから分からないが人が土器を持って移動してきたと考えられてきた。その後S字状口縁台付甕が東海に出自を持つことが分かってからは,東海地方の人々が集団で移動してきたとされるようになった。これが現在県内では大多数の支持を受けている入植民説である。そして最初の入植の候補地には,東海様式にいち早く変換したことを理由に,高崎市井野川流域が比定されている。入植民説に従えば東海の人々はなぜ群馬県域を目指したのか,どのくらいの人が来たのか,入植民と在地の人々との軋轢は無かったのか,さらに当時の群馬に住んでいた人々の社会・文化は壊滅・崩壊したのか等々の問題を解決しなければならない。しかし,一方外来土器の出土することを人の移動に連動させないする解釈もある。交易や交流によって様々な地方の土器が行き来した結果と考える解釈である。外来土器が出土する現象は,弥生時代終末期から古墳時代前期に限った特徴では無く,たとえば沖縄の貝が九州や北海道でも確認される事例や,古墳時代後期の土器が他地域で確認される例もあり,時代を限らず交易や交流の存在を指摘されるものも少なくない。したがって筆者は外来土器の出土が即ち人の移動に連動するという理解では無く,交流があったとの視点で理解したいと考えている。群馬県内では弥生時代中期の遺跡から多くの外来土器が出土する。そのような遺跡は低湿地に占地し,水田耕作を開始したと考えられる遺跡である。その中には弥生時代中期から古墳時代へと途切れることなく継続する遺跡も少なくない。そうなれば入植民説では説明できない。そこで筆者は外来土器が出土することは,外来の文化との接触・交流があったとの視点に立ち,再度弥生時代終末から古墳時代前期にかけての遺跡を検討したいと考えている。井野川流域には東海からの入植地とされ東海の土器様式を持つとされる多くの遺跡がある。その中で弥生時代中期に始まり古墳時代へと継続した新保遺跡(大量の土器・木器・骨角器を出土している)を取り上げ交流の視点から検討をしたい。
1 0 0 0 OA モザイク型AI普及社会への「備え」の必要性
- 著者
- 鷲田 祐一 七丈 直弘
- 出版者
- 日本マーケティング学会
- 雑誌
- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.42-59, 2017-06-30 (Released:2020-03-10)
- 参考文献数
- 23
本論ではホライゾン・スキャニング法を援用した未来洞察ワークショップを用いて,AIやIoTの普及に関して,2025年ごろに発生が懸念される想定外事象に関する仮説を検証した。その結果,AIやIoTの普及に関しても,2025年から2030年ごろに,現段階の国を挙げての開発ビジョンでは想定されていない「モザイク型」普及,すなわち技術導入の進捗度が相分離する状況が想定されると結論された。AIやIoTの開発に実際に携わる特に技術系の研究者はこのような「モザイク型」普及に対する「備え」を持つことが重要である。AIやIoTは人を排除し,人の知的作業を代替してしまうものというよりも,人と共存し人の知的作業を縁の下の力持ち的に補助するもの,という人間中心的ビジョンを明確化することで,より現実的な近未来のマーケティングが想定できるだろう。幅広いマーケティング実務者にとって,AIやIoTのインパクトをもっと身近に理解できるようになる一助になると思われる。
1 0 0 0 OA 発作性片側頭痛と群発頭痛の鑑別に苦慮した1症例
- 著者
- 柏木 航介 野口 智康 中村 美穂 半沢 篤 半田 俊之 福田 謙一
- 出版者
- 日本口腔顔面痛学会
- 雑誌
- 日本口腔顔面痛学会雑誌 (ISSN:1883308X)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.1, pp.37-41, 2018 (Released:2019-12-04)
- 参考文献数
- 6
症例の概要:37歳男性.上顎左側第二大臼歯および眼窩部の疼痛のため,眼科を受診するも改善しなかった.その後近歯科医院を受診したところ急性上顎洞炎と診断され,クラリスロマイシンとロキソプロフェンナトリウムを処方されたが症状改善せず,当科受診.当該歯に齲蝕が認められたため齲蝕除去を行ったが症状は改善せず,1日に5回以上生じる歯痛と眼窩から側頭部にかけての拍動性の激痛は残存した.また結膜充血,鼻汁を伴い,症状が生じると診療室内を落ち着きなく動き回っていた.症状から群発頭痛を疑い,酸素投与を行ったところ症状の緩和が認められた.そのため当院内科へ対診し,スマトリプタンコハク酸塩100mgを頓服処方されたが,症状は再発し再度来院した.そこで発作性片側頭痛(Paroxysmal Hemicrania:PH)を疑い,インドメタシン50mgを処方したところ,歯痛・頭痛ともに症状が改善し,現在疼痛の再発はなく,経過良好である. 考察:PHを発症している患者の15%は歯痛を感じており,発作性の歯痛,顔面痛を訴え歯科に来院することも少なくない.今回の症例も歯痛を主訴として来院しており,診断に難渋したものの自律神経症状から神経血管性歯痛と診断しインドメタシンで除痛することが出来た. 結論:今回私達はPHによる上顎臼歯部と眼窩部の痛みに対する治療を経験した.鑑別に苦慮する神経血管性歯痛を訴える患者が来院することもあるため,歯科医師にも頭痛の知識は必須だと考えられた.
1 0 0 0 フランスの硝酸アンモニウム爆発事故について
1 0 0 0 OA 配位触媒の構造と規則性制御
- 著者
- 古川 淳二
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.122-130, 1973-03-01 (Released:2011-09-21)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 1
配位触媒による重合では, 立体規則性, シスートランス規則性のほか共重合の規則性なども制御できるようになってきた。触媒への配位とそれによるポリマー末端や配位モノマーの反応性,極性,立体障害の変化が重要である。また,触媒の配位座が制限されて, ジエン末端のπ-アリルとモノマーのシス配位が交互に起こり, ジエンとα - オレフィンの交互重合が可能になった。統計論的にはベルヌーイ型とマルコフ鎖型とがある。
1 0 0 0 OA 看護研究の実例 ー慣習的な乳房清拭および哺乳瓶消毒を再考するー
- 著者
- 吉留 厚子
- 出版者
- 大分県立看護科学大学看護研究交流センター
- 雑誌
- 大分看護科学研究 (ISSN:13456644)
- 巻号頁・発行日
- vol.4, no.1, pp.33-36, 2003 (Released:2018-12-28)
- 参考文献数
- 18
1 0 0 0 OA イモータル重合分子量のそろった高分子の合成
- 著者
- 相田 卓三 井上 祥平
- 出版者
- 公益社団法人 高分子学会
- 雑誌
- 高分子 (ISSN:04541138)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.11, pp.1014-1017, 1986-11-01 (Released:2011-10-14)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
1 0 0 0 OA クラスの雰囲気を良くする特殊エージェントの行動特性の分析
- 著者
- 五十嵐 響 内田 君子 奥田 隆史
- 雑誌
- 第81回全国大会講演論文集
- 巻号頁・発行日
- vol.2019, no.1, pp.503-504, 2019-02-28
クラスの雰囲気は,クラスが編成され活動が続けられるうちに,構成員である児童・生徒の相互作用により,自然に生み出されていく風土のことである.クラスの雰囲気を良くすれば,いじめ・校内暴力・不登校など学校での問題が解決できることが知られている.クラスの雰囲気は,クラスに外部から適切なアクションを加えると良くなるが,どのようなアクションが有効であるかは明らかにされていない.本研究では,まず外部からのアクションとしてムードチェンジャー(特殊エージェント)をクラスに加入させることを提案する.次にクラスの雰囲気を良くする特殊エージェントの行動特性をマルチエージェントシミュレーションにより明らかにする.
1 0 0 0 OA グリコサーマル法による修飾チタニアの合成とその光触媒能
- 著者
- 岩本 伸司
- 出版者
- 公益社団法人 石油学会
- 雑誌
- 石油学会 年会・秋季大会講演要旨集 第37回石油・石油化学討論会 (札幌)
- 巻号頁・発行日
- pp.54, 2007 (Released:2007-12-25)
チタンテトライソプロポキシドと少量のオルトケイ酸エチルを1,4-ブタンジオール中に加え、これをオートクレーブ中で加熱すること(グリコサーマル法)により、高表面積を持ち、熱安定性に優れたアナタース型シリカ修飾チタニアのナノ結晶を得た。この試料に窒化処理を行うと、窒素を安定にドープすることができ、得られた窒素ドープシリカ修飾チタニアは可視光照射下でも高い光触媒活性を示した。
1 0 0 0 OA 死はdeathより重い ~日本語話者における道徳的判断に対する異言語効果の分析~
- 著者
- 中村 國則
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第79回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.1AM-087, 2015-09-22 (Released:2020-03-27)
- 著者
- 金谷 翔子 石渡 貴大 横澤 一彦
- 出版者
- 日本基礎心理学会
- 雑誌
- 基礎心理学研究 (ISSN:02877651)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.1, pp.11-18, 2011-09-30 (Released:2016-12-01)
- 被引用文献数
- 3
A tactile stimulus generates different sensations, depending on the delivery source. The rubber hand illusion (RHI), a phenomenon where a touch to one's hand is perceived to come from a fake hand, reflects the role of a multisensory interaction in a coherent body representation. Although this phenomenon has been mostly studied with an experimenter providing tactile stimuli, here we investigate whether a tactile stimulus must be externally produced for RHI to occur. By introducing the condition where a participant touches an artificial hand and his/her own hand simultaneously, the results demonstrate that illusion still occurs, but the perceived amplitude is smaller than that in the ordinal externally produced touch condition. Our results suggest that the externally produced tactile sense is not required for RHI. Further studies are necessary to elucidate the cause of the decreased illusion with the self-produced tactile stimulation.
1 0 0 0 OA 光触媒の材料開発と産業応用への展開
- 著者
- 峠田 博史
- 出版者
- 公益社団法人 日本金属学会
- 雑誌
- まてりあ (ISSN:13402625)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.10, pp.738-744, 2006-10-20 (Released:2011-08-11)
- 参考文献数
- 12
1 0 0 0 OA ゾル-ゲル法による光触媒の作製と応用
- 著者
- 垰田 博史
- 出版者
- 一般社団法人 表面技術協会
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.6, pp.406, 2006 (Released:2006-12-18)
- 参考文献数
- 10
- 著者
- 飯田 弘之 Hiroyuki Iida
- 雑誌
- 人工知能学会誌 = Journal of Japanese Society for Artificial Intelligence (ISSN:09128085)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.6, pp.846-852, 1995-11-01
1 0 0 0 OA 光触媒の固定化法
- 著者
- 吉本 哲夫
- 出版者
- The Surface Finishing Society of Japan
- 雑誌
- 表面技術 (ISSN:09151869)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.242-246, 1999-03-01 (Released:2009-10-30)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 7 4
1 0 0 0 OA キリスト教,ユダヤ教と近代絵画 : ゴッホ,シャガール,バーネット・ニューマン
- 著者
- 吉松 純 Jun Yoshimatsu
- 出版者
- 金城学院大学キリスト教文化研究所
- 雑誌
- 金城学院大学キリスト教文化研究所紀要 = Bulletin of Christian culture studies Kinjo Gakuin University
- 巻号頁・発行日
- vol.23, pp.1-31, 2020-03-31
フィンセント・ファン・ゴッホもマルク・シャガールも世代を超えて愛されている画家。バーネット・ニューマンは戦後のニューヨークの抽象芸術の一線で活躍した画家です。しかし,この3人の表現法はとても違います。何か共通することはあるのでしょうか。それは彼らの信仰にあります。ゴッホはオランダ改革派教会に生まれ育ち,聖書や教会などを作品の中に描いています。ユダヤ教はシャガールやニューマンに影響を及ぼしました。何世紀にもわたり十戒,とりわけ偶像礼拝につながる創作活動を禁じた第二戒はユダヤ人が芸術家を志す夢を打ち砕いてきました。シャガールもニューマンもそれと対峙して自分の絵を完成しました。この講演では,聴衆者に3人の芸術への思い,信仰をご紹介し,作品をより深く堪能する切っ掛けとなければと願っております。
1 0 0 0 OA 触媒的不斉合成
- 著者
- 野依 良治
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.12, pp.1131-1139, 1992-12-01 (Released:2009-11-16)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 8 8
Homogeneous catalysis using chiral metal complexes provides a general principle for chemical multiplication of chirality. A wide range of optically active substances can be synthesized catalytically by the appropriate combination of transition metals or main group elements and suitably designed chiral organic elements. This chemistry is useful not only for stereoselective preparation of chiral compounds in laboratories but also even on industrial level. The recent progress in this field greatly raised the potential of organic synthesis in general. The current status is discussed.
1 0 0 0 OA 産婦人科領域における3 次元超音波
- 著者
- 馬場 一憲
- 出版者
- バイオメカニズム学会
- 雑誌
- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.28-35, 2012 (Released:2016-04-15)
- 参考文献数
- 10
産婦人科では,超音波(断層)診断装置が無いと診療ができないといえるほど,超音波が活用されている.大半の症例は超音波断層法だけで診断がつくが,3 次元超音波を用いて,超音波断層法では得ることができない断面を表示したり多彩な3 次元像を表示したりすることで,診断が可能になったり診断が確定されたりする症例もある.特に,胎児の顔の形態,耳の位置や形態,四肢の形態異常の診断に,胎児体表の3 次元像が有用である. 形態だけでなく,3 次元走査と3 次元画像構築を繰り返すことで胎児の動きを立体的に捉えることができる.また,血流をカラー表示する超音波ドプラ法を3 次元超音波に応用すると血流(血管)分布を3 次元的に捉えることができる.
1 0 0 0 『管絃音義』に見られる図について
- 著者
- 高瀬 澄子
- 出版者
- 沖縄県立芸術大学音楽学部音楽学専攻
- 雑誌
- ムーサ : 沖縄県立芸術大学音楽学研究誌 (ISSN:13455443)
- 巻号頁・発行日
- no.13, pp.41-51, 2012-03