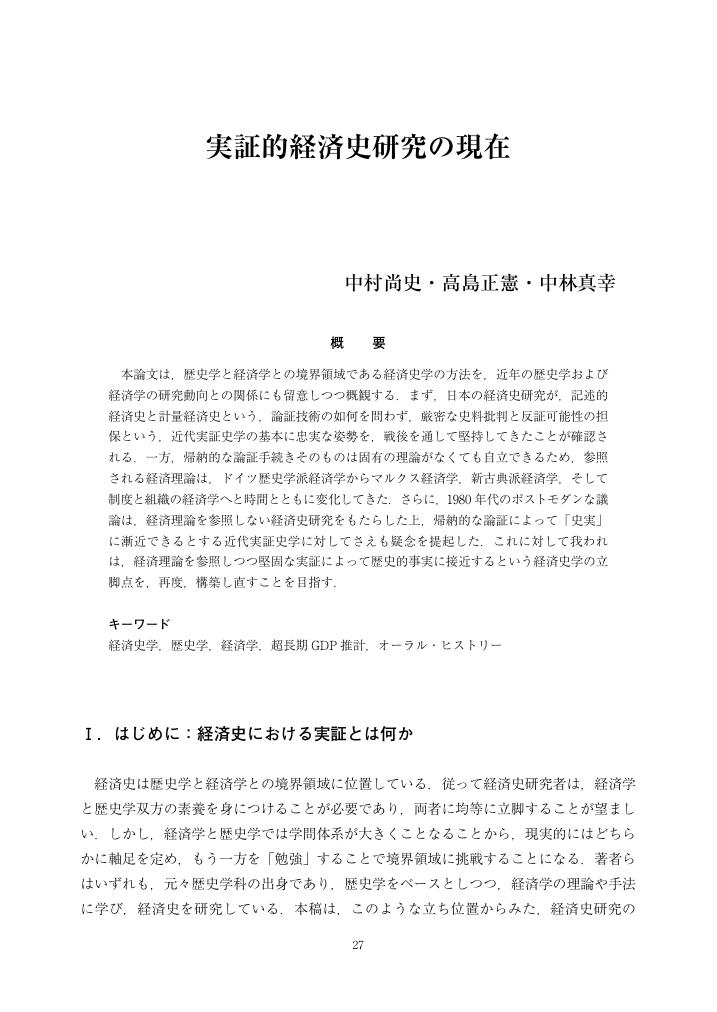25 0 0 0 OA 日本におけるバリアフリーの歴史
- 著者
- 髙橋 儀平
- 出版者
- 日本義肢装具学会
- 雑誌
- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.1, pp.62-67, 2020-01-01 (Released:2021-01-15)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
本稿は日本における1960年代後半のバリアフリーの発祥から今日までの展開を概観したものである.日本のバリアフリーの動きは1970年初頭に始まっているが,当初から欧米諸国からの学びが多く,同時にその経験をいち早く実行に移した,障害者自身の行動力によるところが大きい.一方,研究者らはそれらへの技術的情報提供を怠らなかったともいえる.その後80年代の福祉のまちづくりの取り組みを経て,90年代以降のバリアフリー関連法制度の時代が始まる.そして2020年の東京オリンピック·パラリンピックの開催決定を向け,多様な市民の共生を謳うインクルーシブな社会環境への創出に向かっている.ユニバーサルデザインはこれらをハード·ソフトの両面から具体化する技術的プロセスとして今や十分な市民権を有したといえる.バリアフリーの新たな展開に対応した重要なキーワードの1つである.
25 0 0 0 OA 四国初記録となるトガリエビスと成長に伴う形態変化に関する新知見
- 著者
- 松永 翼 遠藤 広光
- 出版者
- 国立大学法人 鹿児島大学総合研究博物館
- 雑誌
- Ichthy, Natural History of Fishes of Japan (ISSN:24357715)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, pp.9-14, 2023-07-07 (Released:2023-07-08)
25 0 0 0 OA 日本における国内テロ組織の犯行パターン
- 著者
- 大上 渉
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 心理学研究 (ISSN:00215236)
- 巻号頁・発行日
- vol.84, no.3, pp.218-228, 2013-08-25 (Released:2013-11-01)
- 参考文献数
- 35
- 被引用文献数
- 1 1
This study examined the behavioral patterns of Japanese extremist groups, based on 377 terror incidents that occurred in Japan between 1990 and 2010. These incidents included bombings, rocket attacks, hostage taking, and vehicle assaults. Information was drawn primarily from on-line newspaper databases. A multiple correspondence analysis was performed using five categories: extremist group identity, time of attack, target of attack, attack strategy, and method of claiming responsibility. Extremist group characteristics varied along two dimensions: the interaction level between terrorist and victim, and the indiscriminate level of use of force. We categorized multiple far-left, far-right, and religious extremist groups based on these two dimensions. Our findings may help prevent terror attacks, and help identify the group responsible for a given incident.
25 0 0 0 OA 電子レンジのしくみ
- 著者
- 清水 聡
- 出版者
- 一般社団法人 電子情報通信学会
- 雑誌
- 電子情報通信学会 通信ソサイエティマガジン (ISSN:21860661)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, no.1, pp.4-5, 2019-06-01 (Released:2019-06-01)
- 著者
- 西井 貴美子 山田 秀和 笹川 征雄 平山 公三 磯ノ上 正明 尾本 晴代 北村 公一 酒谷 省子 巽 祐子 茶之木 美也子 寺尾 祐一 土居 敏明 原田 正 二村 省三 船井 龍彦
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.119, no.14, pp.3037-3044, 2009-12-20 (Released:2014-11-28)
大阪皮膚科医会は学校における水泳プール授業時のサンスクリーン剤使用の実態調査を大阪府下の公立学校1,200校を対象に実施したが,結果は約3割以上の学校がサンスクリーン剤使用を禁止または不要としていた.禁止の理由として水質汚染の心配が多数をしめたため,2007年夏に大阪府内の公立中学校14校の協力を得てワンシーズン終了後の水質検査を実施し,プール授業開始直後の水質と比較した.結果は文部科学省の学校環境衛生の基準に定められている6項目(pH,濁度,遊離残留塩素,過マンガン酸カリウム消費量,大腸菌,トリハロメタン)のうち濁度,過マンガン酸カリウム消費量,大腸菌,トリハロメタンに関しては基準値からはずれた項目はなかった.遊離残留塩素,pHについてはサンスクリーン剤使用を自由または条件付許可の学校で基準値より低値を示す傾向にあった.統計的検討はサンプル数,各校の条件の違いでむずかしいが,定期的にプール水の残留塩素濃度を測定,管理し,補給水の追加をすれば紫外線の害を予防する目的でサンスクリーン剤を使用することに問題はないと考える.
25 0 0 0 OA 煙硝づくりの歴史的経緯と古土法による再現実験の検証─江戸時代の火薬原料製造の実験的検証─
- 著者
- 野澤 直美
- 出版者
- 日本薬史学会
- 雑誌
- 薬史学雑誌 (ISSN:02852314)
- 巻号頁・発行日
- vol.54, no.2, pp.77-82, 2019 (Released:2020-07-11)
Gunpowder happened to be produced while seeking the elixir of life. Saltpeter (i.e., potassium nitrate) is an essential substance required to produce gunpowder. There are no saltpeter lodes in Japan. So an aged-soil method called Kodo-hou, which was developed to make saltpeter using the soil from underfloors of houses, was used after guns were introduced. It is not clear where and how this method was invented. The only culture-related method, called Baiyou-hou, was adopted in the Gokayama region of Kaga-han, now Ishikawa. The Edo period was so peaceful that the demand for making saltpeter subsided, and the production technology fell into decline. The Chichibu area, now Saitama, thrived in the production of gunpowder when under the control of Oshi-han. Especially, at the end of the Edo period, much gunpowder was required to defend Edo Bay following the arrival of Admiral Perry. Oshi-han was ordered to defend Edo Bay and bought the gunpowder used from the Chichibu territory. By that time, the materials used for the Kodo-hou method became more available, leading to a familiarized way to make saltpeter. The author succeeded in producing saltpeter applying the Kodo-hou method and using the same material as in the Edo period, confirming the correctness of that material. It was personally experienced how hard it was to make saltpeter in those days. In Chichibu, nearly 400 festivals are held each year, and people set off fireworks as a sign of dedication to not only big shrines, but also small shrines. This suggests that there used to be abundant gunpowder in this area.
25 0 0 0 OA 愛知県におけるアライグマ野生化の過程と今後の対策のあり方について
- 著者
- 揚妻-柳原 芳美
- 出版者
- 日本哺乳類学会
- 雑誌
- 哺乳類科学 (ISSN:0385437X)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.2, pp.147-160, 2004 (Released:2008-03-05)
- 参考文献数
- 84
- 被引用文献数
- 9
愛知県犬山市および岐阜県可児市を中心に分布しているアライグマ(Procyon loter)の導入から定着,分布拡大までの過程を,新聞記事や聞き取り情報などから分析した.その結果,1962年に犬山市で起きた日本モンキーセンターからのアライグマ12頭の脱走,1982年可児市でのアライグマ約40頭の放逐などが,この地域にアライグマを定着させた要因と考えられた.また,アライグマの分布が急速に拡大したのはゴルフ場や道路建設および宅地開発が影響していることが示唆された.その後,アライグマは愛知·岐阜県境に広がる丘陵地を中心に定着し,徐々に南東へと分布域を拡大してきたと考えられる.野生化アライグマの問題点は様々に指摘されているが,本稿ではその対策のあり方についても検討を加えた.
25 0 0 0 OA Superiority of Long-Acting to Short-Acting Loop Diuretics in the Treatment of Congestive Heart Failure
- 著者
- Tohru Masuyama Takeshi Tsujino Hideki Origasa Kazuhiro Yamamoto Takashi Akasaka Yutaka Hirano Nobuyuki Ohte Takashi Daimon Satoshi Nakatani Hiroshi Ito
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.4, pp.833-842, 2012 (Released:2012-03-23)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 46 49
Background: Diuretics are the most prescribed drug in heart failure (HF) patients. However, clinical evidence about their long-term effects is lacking. The purpose of this study was to compare the therapeutic effects of furosemide and azosemide, a short- and long-acting loop diuretic, respectively, in patients with chronic heart failure (CHF). Methods and Results: In this multicenter, prospective, randomized, open, blinded endpoint trial, we compared the effects of azosemide and furosemide in patients with CHF and New York Heart Association class II or III symptoms. 320 patients (160 patients in each group, mean age 71 years) were followed up for a minimum of 2 years. The primary endpoint was a composite of cardiovascular death or unplanned admission to hospital for congestive HF. During a median follow-up of 35.2 months, the primary endpoint occurred in 23 patients in the azosemide group and in 34 patients in the furosemide group (hazard ratio [HR], 0.55, 95% confidence interval [CI] 0.32-0.95: P=0.03). Among the secondary endpoints, unplanned admission to hospital for congestive HF or a need for modification of the treatment for HF were also reduced in the azosemide group compared with the furosemide group (HR, 0.60, 95%CI 0.36-0.99: P=0.048). Conclusions: Azosemide, compared with furosemide, reduced the risk of cardiovascular death or unplanned admission to hospital for congestive HF. (Circ J 2012; 76: 833-842)
25 0 0 0 OA 観察可能なものと観察不可能なもの
- 著者
- 田村 哲樹
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.1, pp.1_37-1_60, 2015 (Released:2018-06-10)
- 参考文献数
- 37
Scholars of politics have been familiar with normative-empirical distinction. Yet this article reconsiders this divide through exploring another classification in terms of the “observable” and the “unobservable”. According to this new classification, we can assume two types of politics research. Firstly, there are researches which are based on the positivist epistemology and, therefore, deal with the observable. In these cases, the cooperation between positivist, empirical analyses and the normative political philosophy focusing on moral values such as justice, equality and freedom would be feasible. Secondly, there are researches which are based on the non-positivist epistemologies including both interpretivism and realism, and, therefore, deal with the unobservable in some senses. In these cases, the cooperation between non-positivist empirical analyses and the “politics-political” political theory focusing on topics about the nature and the role of politics and the political would be feasible. Consequently, this article contends that we can rethink the existing distinction between the normative and the empirical in political science; the distance either between normative political philosophy and “politics-political” political theory or between positivist empirical analysis and non-positivist one might be farther than what is ordinarily drawn between normative political theory and empirical analysis.
25 0 0 0 OA ポピュリスムの民主主義的効用
- 著者
- 山本 圭
- 出版者
- 日本政治学会
- 雑誌
- 年報政治学 (ISSN:05494192)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.2, pp.2_267-2_287, 2012 (Released:2016-02-24)
- 参考文献数
- 39
This paper aims to re - think the relationship between populism and democracy, and clarify that populism can hold some advantages for democratic societies. In order to do this I shall, first of all, make a survey of some arguments that have dealt with this relationship, and show that they face a difficult antinomy. I will then argue that the primary reason for this dilemma resides in “two strand theory” in the concept of modern democracy. Secondly, this paper focuses on theories of “radical democracy” to indicate how and why recent democratic theories move closer to populism. After reviewing some representative theories of radical democracy, I shall pick up Ernesto Laclau's political theory on populism, as his thought provides an appropriate example of the encounter between democracy and populism. Finally, through these considerations, I will attempt to clarify “the democratic utilities of populism.”
25 0 0 0 OA 実証的経済史研究の現在
- 著者
- 中村 尚史 高島 正憲 中林 真幸
- 出版者
- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所
- 雑誌
- 社会科学研究 (ISSN:03873307)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.2, pp.27-53, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)
- 著者
- 吉村 大輔 吉村 理江 水谷 孝弘
- 出版者
- 一般社団法人 日本消化器内視鏡学会
- 雑誌
- 日本消化器内視鏡学会雑誌 (ISSN:03871207)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.5, pp.469-477, 2023 (Released:2023-05-22)
- 参考文献数
- 27
Helicobacter pylori(Hp)の感染率の低下を反映し従来稀とされたHp未感染胃癌の増加が報告されている.自験例の解析ではHp未感染胃癌は(1)噴門部(食道胃接合部)腺癌,(2)胃底腺領域とくにU,M領域に好発する胃型形質の低異型度腺癌,(3)胃角前庭部の胃底腺と幽門腺境界領域に好発する印環細胞癌,(4)幽門腺領域に好発ししばしば腸型形質を呈する分化型腺癌,に分類可能であった.噴門部腺癌の多くが進行癌であったのに対して,その他の領域は大部分がESDによる治療が可能であった早期癌で,その進行が緩徐である可能性も示唆された.Hp未感染胃においては部位,腺領域ごとの癌の好発部位と形態および組織型の特徴をふまえた観察が効率的と考える.
- 著者
- Takashi Muramatsu Shinichiro Masuda Nozomi Kotoku Ken Kozuma Hideyuki Kawashima Yuki Ishibashi Gaku Nakazawa Kuniaki Takahashi Takayuki Okamura Yosuke Miyazaki Hiroki Tateishi Masato Nakamura Norihiro Kogame Taku Asano Shimpei Nakatani Yoshihiro Morino Yuki Katagiri Kai Ninomiya Shigetaka Kageyama Hiroshi Takahashi Scot Garg Shengxian Tu Kengo Tanabe Yukio Ozaki Patrick W. Serruys Yoshinobu Onuma
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-23-0051, (Released:2023-03-11)
- 参考文献数
- 36
- 被引用文献数
- 6
Background: P2Y12 inhibitor monotherapy without aspirin immediately after percutaneous coronary intervention (PCI) has not been tested in East Asian patients, so in this study we aimed to assess the safety and feasibility of reduced dose (3.75 mg/day) prasugrel monotherapy in Japanese patients presenting with chronic coronary syndrome (CCS).Methods and Results: ASET-JAPAN is a prospective, multicenter, single-arm pilot study that completed enrolment of 206 patients from 12 Japanese centers in September 2022. Patients with native de-novo coronary lesions and a SYNTAX score <23 were treated exclusively with biodegradable-polymer platinum-chromium everolimus-eluting stent(s). Patients were loaded with standard dual antiplatelet therapy (DAPT) and following successful PCI and optimal stent deployment, they received low-dose prasugrel (3.75 mg/day) monotherapy for 3 months. The primary ischemic endpoint was a composite of cardiac death, spontaneous target-vessel myocardial infarction, or definite stent thrombosis. The primary bleeding endpoint was Bleeding Academic Research Consortium (BARC) type 3 or 5. At 3-month follow-up, there were no primary bleeding or ischemic events, or any stent thrombosis.Conclusions: This pilot study showed the safety and feasibility of prasugrel monotherapy in selected low-risk Japanese patients with CCS. This “aspirin-free” strategy may be a safe alternative to traditional DAPT following PCI.
25 0 0 0 OA 露ウ戦争におけるロシアの目的―政権打倒、征服、そして領土整理へ―
- 著者
- 松里 公孝
- 出版者
- ロシア・東欧学会
- 雑誌
- ロシア・東欧研究 (ISSN:13486497)
- 巻号頁・発行日
- vol.2022, no.51, pp.1-20, 2022 (Released:2023-04-21)
- 参考文献数
- 30
This paper investigates the endeavors to solve the Donbas Conflict typologically. The first and most consistent policy was the Minsk Accord belonging to the category of federalization. As has been the case with other post-Soviet secession conflicts, federalization was a hopeless policy, which produced serious commitment problems, while contradicting the real interests of both the parent state (Ukraine) and the secession polities (the DPR and LPR). In the context of the Donbas War none proposed the second type of solution, that is, land-for-peace. Ineffective diplomatic endeavors induced both Ukraine, Russia, and the DPR/LPR to solve the situation in a military way. Azerbaijan’s victory in the Second Karabakh War in 2020 disposed Ukraine for a coercive solution of the Donbas problem (the reconquest policy). The Russian political and military leadership split into two groups: one supporting the policy to make the secession polities (the DPR and LPR) Russia’s protectorates and another supporting the policy to destroy the parent state (Ukraine). The unsatisfactory results of Russia’s choice in 2008 of the protectorate policy vis-à-vis South Ossetia and Abkhazia and underestimation of Kyiv’s defense capacity made the Russian leaders opt for the destruction of Ukraine itself.
25 0 0 0 OA 形状の異なる計量スプーンの精度の比較
- 著者
- 伊藤 知子 上野 龍司
- 出版者
- 日本調理科学会
- 雑誌
- 日本調理科学会大会研究発表要旨集 平成24年度日本調理科学会大会
- 巻号頁・発行日
- pp.113, 2012 (Released:2012-09-24)
【目的】計量は調理の基本操作であり、特に塩分制限食など治療食の調理において計量操作の持つ意味は大きい。家庭においては、計量には計量カップ、計量スプーンなど、容積を測定する器具が用いられることが多いと考えられるが、市販されているそれらの形状は様々であり、精度についても不明である。これらは計量法で定められている「ます」ではないため検定検査の対象とはならないが、その測定値について一定以上の再現性は必要である。本研究では計量スプーンに着目し、形状の異なる計量スプーンの精度の比較を行った。【方法】計量スプーン(大さじおよび小さじ)12種について、その長径、短径、深さを測定した。これらの計量スプーンを用いて、水、小麦粉、塩、サラダ油等を測り取り、その重量を測定し、比較した。さらに「標準計量カップ・スプーンによる重量表(g)」(以下、重量表)の値との比較を行った。【結果】最初に大学生12名を被験者とし、2種類の計量スプーンを用いて、水・小麦粉を測りとってもらい、その重量を測定した。大さじを用いて測定した場合に有意差が見られた。次に計量スプーン12種を用いて様々な試料を測り取って重量を測定したところ、その値は有意に異なることが明らかとなった。特に半径(短径)よりも深さの値が小さい浅型の計量スプーンの測定値は、重量表の値の80%未満であった。浅型のものを除いた8種の計量スプーンの測定値を比較したところ、粒形状の試料よりも液状の試料の方が測定値のばらつきが大きかった。家庭における少人数用の治療食の調理や、味の再現性を重視する場合においては、少量の調味料の計量における計量誤差を小さくする計量方法の習得が必要であると考えられる。
25 0 0 0 OA 酵素免疫測定法による食物・生薬中のフラノクマリン類含量のスクリーニング
- 著者
- 齋田 哲也 藤戸 博
- 出版者
- 一般社団法人日本医療薬学会
- 雑誌
- 医療薬学 (ISSN:1346342X)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.7, pp.693-699, 2006-07-10 (Released:2007-11-09)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 4 3
Furanocoumarin derivatives such as bergamottin and 6',7'-dihydroxybergamottin are inhibitors of CYP3A4 and have been isolated from grapefruit juice. We developed a sensitive and specific enzyme-linked immunosorbent assay for these furanocoumarin derivatives and used it for screening a large number of citrus fruits, vegetables and crude drugs for them. On testing the juice and peel of 25 citrus fruits, significant reactivity was observed with the juice of 4 of them : sweetie, melogold, banpeiyu pummelo and red pummelo and in the case of peel, significant reactivity was observed for 4 fruits : sweetie, melogold, sour pummelo and natsudaidai. For most of the citrus fruits, the peel showed a stronger reaction than the juice. Seven vegetables were tested and only slight reactivity was observed for 4 of them : parsley, celery, Italian parsley and mitsuba. Among the twenty crude drugs tested, significant reactivity was observed for 2 : angelica dahurica root (byakushi) and bitter orange peel (touhi). These findings suggest that 4 of the citrus fruits and 2 of the crude drugs tested would exhibit strong drug interactions.
25 0 0 0 OA 位相変換による複素スペクトログラムの表現
- 著者
- 矢田部 浩平 升山 義紀 草野 翼 及川 靖広
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.3, pp.147-155, 2019-03-01 (Released:2019-09-01)
- 参考文献数
- 54
25 0 0 0 OA 改正臓器移植法をめぐる投票行動
- 著者
- 加藤 英一
- 出版者
- 学校法人 北里研究所 北里大学一般教育部
- 雑誌
- 北里大学一般教育紀要 (ISSN:13450166)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, pp.111-131, 2010-03-31 (Released:2017-09-29)
2009年、 ⌈ 臓器移植に関する法律⌋の改正案が国会において採決された。日本共産党を除いた 各政党は、改正案の特性から投票に際して党議拘束を外した。投票の結果、原案通りに改正案は 成立した。これによって日本では、法的に脳死が人の死として認められることになった。衆・参両議院での投票行動は、党議拘束を外したにも拘らず、政党による影響を否定できない結果となった。それは1997年の ⌈ 臓器の移植に関する法律⌋が可決された際と同じである。これは R.K.マートンの準拠枠組みの理論によって、ある程度は説明が可能である。しかし今回の法改正における投票行動では、それ以外の要因である、衆・参議院のねじれ状態や小泉チルドレンの影響をも考慮しなければならない。
25 0 0 0 OA 西南日本におけるスラブ起源深部流体の分布と特徴
- 著者
- 風早 康平 高橋 正明 安原 正也 西尾 嘉朗 稲村 明彦 森川 徳敏 佐藤 努 高橋 浩 北岡 豪一 大沢 信二 尾山 洋一 大和田 道子 塚本 斉 堀口 桂香 戸崎 裕貴 切田 司
- 出版者
- 日本水文科学会
- 雑誌
- 日本水文科学会誌 (ISSN:13429612)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.1, pp.3-16, 2014-02-28 (Released:2014-05-28)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 13 20
近年のHi-netによる地震観測網により,我が国の沈み込み帯における地殻・マントル中の熱水流体の不均質分布による三次元地震波速度構造の異常や深部流体に関連する深部低周波地震の存在などが明らかになってきた。地球物理学的な観測結果に基づく岩石学的水循環モデルは,固体地球内部の水収支を定量化し,滞留時間の長い深層地下水中には検出可能な濃度でスラブ脱水起源の深部流体が流入していることを示す。また,内陸地震発生における深部流体の役割も,近年重要視されている。モデルは主に地球物理学的観測やシミュレーション等の結果に基づいたものであるため,地球化学的・地質学的な物質科学的証拠の蓄積はモデルの高度化にとって重要である。そこで,我々は西南日本の中国–四国–近畿地方において深層地下水の同位体化学的特徴の検討を行い,地下水系に混入する深部流体の広域分布について明らかにした。その結果,マグマ水と似た同位体組成をもつ深部流体,すなわち,スラブ起源深部流体のLi/Cl比(重量比)が0.001より高いことを示した。Li/Cl比は,天水起源の淡水で希釈されても大きく変化しないことが期待されるため,深部流体の指標に最適である。Li/Cl比の広域分布は,スラブ起源深部流体が断層・構造線および第四紀火山近傍で上昇していることを示した。また,深部低周波 (DLF) 地震が起きている地域の近傍に深部流体が上昇している場合が多く見られ,DLF地震と深部流体の関連性を示唆する。
25 0 0 0 OA イスラームとムスリムについて教える/学ぶ人のために―ムスリマのフィールドワーカーからの提案―
- 著者
- 杉江 あい
- 出版者
- 公益社団法人 日本地理学会
- 雑誌
- E-journal GEO (ISSN:18808107)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.102-123, 2021 (Released:2021-03-31)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 2
本稿では,バングラデシュを主なフィールドとするムスリマとしての立場から,イスラームとムスリムに関する学習のために次の3点を提案する.第1に,イスラームとムスリムに接する上で必要なリテラシーを高めること.ここでいうリテラシーとは,クルアーンなどの章句の理解にはアラビア語やイスラーム学の深い知識が必要であり,西洋のバイアスがかかった生半可な知識では誤解しやすく,一部の研究者やムスリムの間でも誤った解釈や恣意的な章句の引用などがなされていることに注意することである.第2に,イスラームとムスリムを切り離してとらえること.イスラームをムスリムの言動のみから解釈し,またムスリムの生活文化をイスラームに還元するアプローチは誤りである.第3に,イスラームにおいて重視される信仰や人格,現世での利点について説明すること.義務や禁忌を表面的に教えるだけでは,イスラームを特異視するステレオタイプから脱却できない.