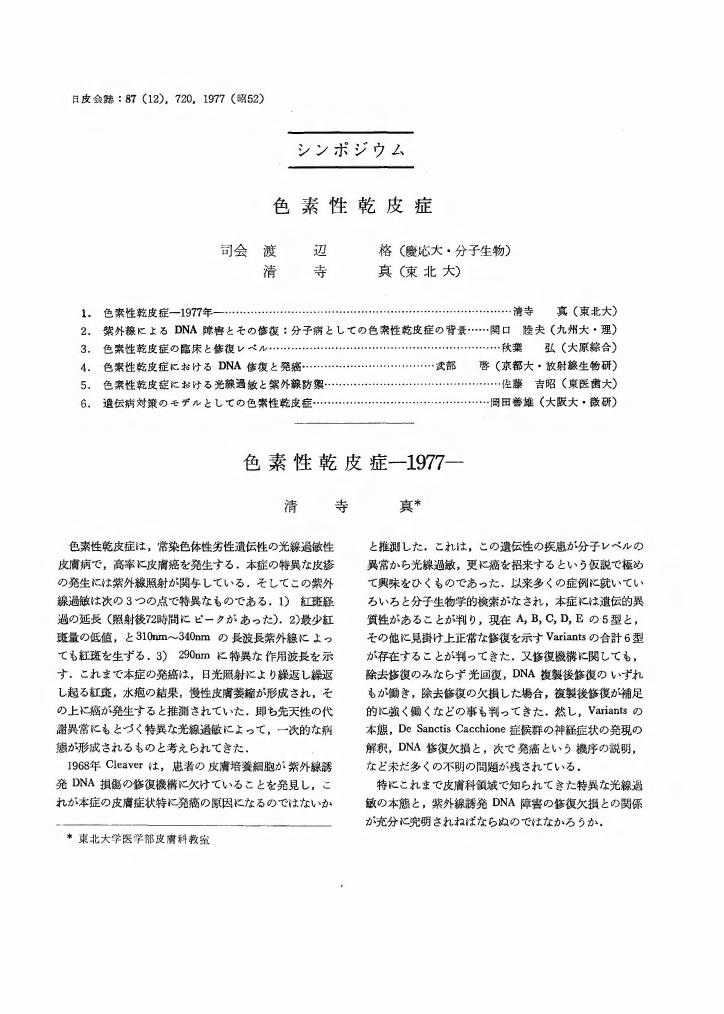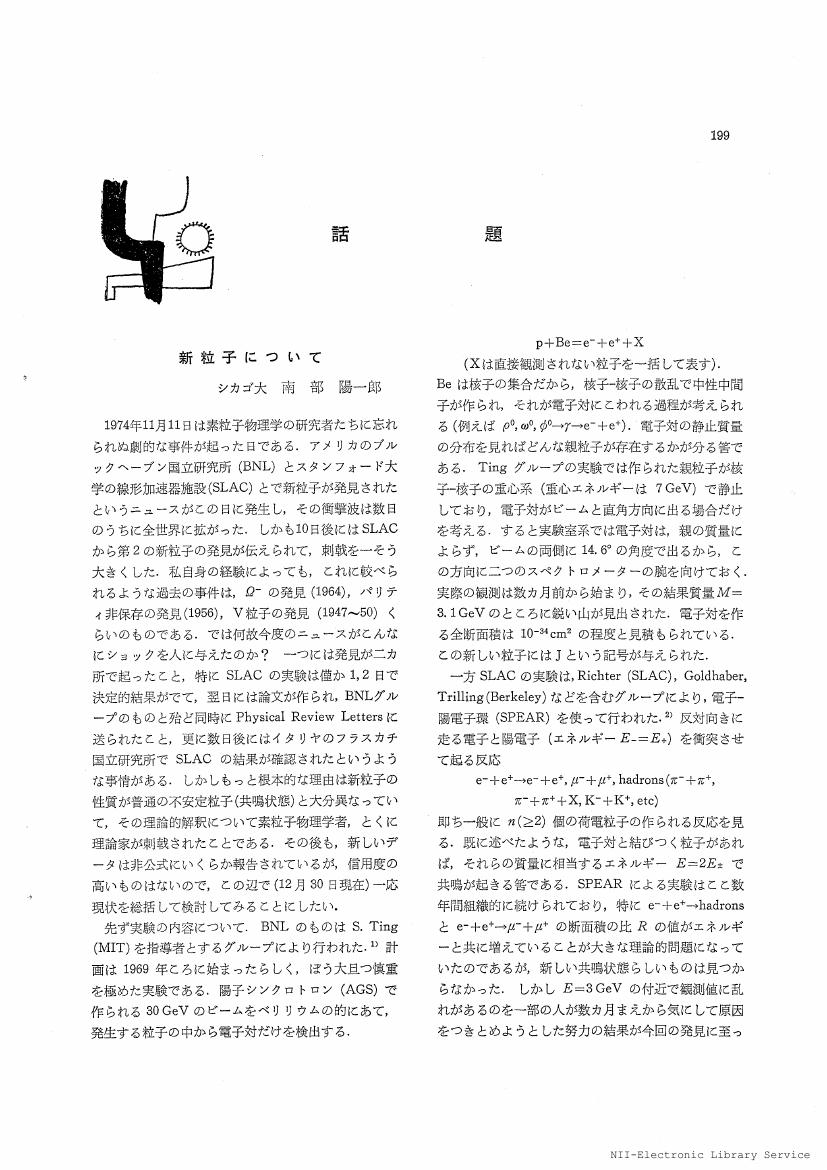- 著者
- 丹羽 英之
- 出版者
- 一般社団法人 日本生態学会
- 雑誌
- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, no.1, pp.2113, 2022-04-15 (Released:2022-06-28)
- 参考文献数
- 16
水生植物の生育域は人為的な影響を受けやすいエリアであり、外来生物の侵入が顕著になっている。水生植物の動態を理解し保全していくためには、空間スケールに応じたリモートセンシング技術の確立が重要となる。そこで、 Pole photogrammetryを応用した水生植物の詳細な植生図作成方法を提案し、湧水域で水生植物分布を定量的に把握することで、その有効性を実証することを目的とした。淀川水系桂川の犬飼川の合流点上流の河道内にみられる湧水流を調査対象地とした。カメラスタビライザーに取り付けたカメラで水域を撮影した。撮影した動画を SfM-MVS Photogrammetryで処理し、オルソモザイク画像を作成し、目視判読により種ごとのパッチポリゴンを作成した。作成したオルソモザイク画像の地上分解能は高く混生する種を識別することができた。オルソモザイク画像の判読により植生図データを作成することで、種ごとの分布面積が算出でき、定量的な分析が可能になる。さらに区間に分割して分析することで水生植物の流程分布を把握することができた。調査対象とした湧水流は出現種数が多く希少な湧水域の 1つだといえる。しかし、同時に外来種の侵入もみられることから、流程分布を考慮した生態系管理を実践していくことが重要である。
- 著者
- Yasuko Okamoto Takanori Sakaguchi Yoshito Ikematsu Toshikazu Kanai Kazuhisa Hirayama Hiroaki Tamura Tadataka Hayashi Yoshiro Nishiwaki Hiroyuki Konno Katsunori Aoki
- 出版者
- The University of Tokushima Faculty of Medicine
- 雑誌
- The Journal of Medical Investigation (ISSN:13431420)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3.4, pp.325-333, 2023 (Released:2023-11-09)
- 参考文献数
- 37
- 被引用文献数
- 1
The effects of early enteral arginine-rich nutrition (EAN) were analyzed among patients undergoing curative-intent total gastrectomy for gastric cancer. There were 19 patients in this prospective study, all randomly assigned to either a parenteral nutrition (PN) group or an EAN group for the first seven days after surgery. The EAN group received 1.8-fold greater arginine (10.1 g/day) compared with the PN group, which was administered through an enteral tube inserted into the jejunal loop. Both groups were provided almost identical amounts of total amino acids (54 g/day), and the total energy was set at 65% of the total requirement (25 kcal/kg/day). No significant differences were observed between the two groups in postoperative complications, length of hospital stay, oral intake, nutritional status, or body weight. The serum arginine profile was similar in the two groups, as it decreased significantly on postoperative day (POD) 1, and gradually returned to preoperative levels by POD 7. The nitrogen balance remained negative until POD 7 in the PN group, but turned neutral at POD 7 in the EAN group. While we could not confirm body weight loss improvement, these results suggested that early arginine-rich enteral nutrition could improve the nitrogen balance after total gastrectomy. J. Med. Invest. 70 : 325-333, August, 2023
2 0 0 0 OA DNA修復と進化論的考察
- 著者
- 近藤 宗平
- 出版者
- 一般社団法人 日本生物物理学会
- 雑誌
- 生物物理 (ISSN:05824052)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.3, pp.118-126, 1974-05-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 45
- 被引用文献数
- 1 1
Recent knowledge of DNA repair is reviewed in perspective with emphasis on Escherichia coli. Enzymatic phtoreactivation is the simplest and the most general among the three major DNA repair systems. Excision repair is also common from microorganisms to human and yet its molecular mechanism is not universal. Tolerance repair, i.e., post-replication repair, is effective for the widest variety of DNA damage and rather different between lower and higher forms. From these characteristics, it is proposed that DNA repair mechanisms evolved in the order of photoreactivation, excision repair and tolerance repair after the primary living systems were created by solar ultraviolet.
2 0 0 0 OA シンポジウム 色素性乾皮症
- 出版者
- 公益社団法人 日本皮膚科学会
- 雑誌
- 日本皮膚科学会雑誌 (ISSN:0021499X)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.12, pp.720, 1977 (Released:2014-08-22)
2 0 0 0 OA P・シュミットによる「ゲーテの色彩象徴」覚書
- 著者
- 岸 繁一
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.1983, no.5, pp.82-93, 1983-11-03 (Released:2010-02-26)
- 著者
- HIROKI SEIKE SHINYA WATANABE
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- Anthropological Science (ISSN:09187960)
- 巻号頁・発行日
- vol.129, no.2, pp.151-164, 2021 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 1
South American camelids, which were domesticated in the Central Andes, have been emphasized for their secondary uses (e.g. llamas as pack animals and alpacas for their wool). In modern pastoral societies the use of mature animals for meat is not efficient. However, it is interesting that cut marks have often been found on archaeological animal bones. This study aimed to describe butchering of camelids through macroscopic observation of cut marks in the Middle Horizon period, during the Wari Empire (600–1000 CE), when the use of camelids reached its peak, and to test whether these activities are consistent with ethnoarchaeological and ethnographic findings. The materials used here are camelid bones with cut marks from El Palacio in the northern highlands of Peru. They were assigned to Middle Cajamarca Phases B and C, and a part of the Late Cajamarca Phase (800–1000 CE). In this study, cut marks on animal bones were observed by macroscopy, and analyses were focused on their distribution, frequencies, and direction. Cut marks on camelid bones from El Palacio were observed over the entire body, suggesting that these marks were caused by dismembering, skinning, and extraction of meat, fat, and marrow. The frequencies of cut marks on camelid bones at El Palacio was 1.3%, lower than that in the Formative Period. This lower frequency might have been caused by more fragmented bones in the former. Furthermore, it is possible that the use of secondary products was emphasized at El Palacio. Cut marks were concentrated on the ventral side of each bone. This can be attributed to the butchering procedure described from ethnoarchaeology and ethnography, in which animal was turned on its back for dismemberment and removal of its internal organs from the ventral side, being careful not to soil the earth for ritual considerations.
2 0 0 0 OA 新粒子について
- 著者
- 南部 陽一郎
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.3, pp.199-201, 1975-03-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 4
2 0 0 0 OA 寝室内環境が睡眠の質に与える影響 (第4報)空気質を考慮した寝室内環境が睡眠に及ぼす影響
- 著者
- 井上 莉沙 都築 和代 竹内 悠香 秋山 雄一 尾方 壮行 田辺 新一
- 出版者
- 公益社団法人 空気調和・衛生工学会
- 雑誌
- 空気調和・衛生工学会大会 学術講演論文集 平成30年度大会(名古屋)学術講演論文集 第6巻 温熱環境評価 編 (ISSN:18803806)
- 巻号頁・発行日
- pp.93-96, 2018 (Released:2019-10-30)
寝室内環境が睡眠に及ぼす影響の調査のため、窓の開閉条件を設定した自宅寝室における睡眠実測調査を行った。睡眠の評価は脳波計を用い、睡眠前後のアンケート調査も行った。結果として、窓開け条件で睡眠の質が向上し、良い寝室内空気質が睡眠を改善する可能性が示された。さらに、音環境、温熱環境、空気質が睡眠に与える複合影響を調査するため、マルチレベル分析を行った。
2 0 0 0 OA 肛門管内低周波電気刺激による慢性直腸肛門痛に対する効果
- 著者
- 宇都宮 高賢 柴田 興彦 菊田 信一 堀地 義広
- 出版者
- The Japan Society of Coloproctology
- 雑誌
- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.169-174, 2005 (Released:2009-06-05)
- 参考文献数
- 26
難治性の慢性直腸肛門痛症例,男性19人,女性42人について肛門管内を双極刺激電極を挿入し低周波電気刺激を週1~2回,一回5分間行いその効果について検討した.これら症例のうち男性9人,女性12人について低周波電気刺激前後における左側肛門管組織血流量の測定を行った.症例の肛門内圧検査を行い随意最大収縮圧100mmHg以上の症例(機能正常群)と100mmHg以下(機能低下群)に分けて検討した.男性では,機能正常群が多く,女性では機能低下群が多かったが,慢性直腸肛門痛との関連はなかった.痛みが消失するまでの刺激回数は平均3.5±1.6回であり,98%に効果を認め,59%に痛みの完全消失が得られた.肛門管組織血流量,血流速度は低周波電気刺激により男性で64%,女性で33%の有意な増加がみられた(p<0.Ol).肛門管内低周波電気刺激は,慢性直腸肛門痛症例に対して簡便有効な治療方法であった.
2 0 0 0 OA 韓国産マムシと北海道様似産ニホンマムシ 屋外飼育場における生態
2 0 0 0 OA マターナル・ブレイン― その適応的メカニズム ―
- 著者
- 則内 まどか 菊池 吉晃
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.4, pp.135-140, 2016 (Released:2017-10-31)
Parenting plays a critical role in the infant’s survival and optimal development, as well as in the parent-infant attachment. The parent-infant relationship provides infants with their first social environment, forming templates to interact with others. In this review, we focus on neuroimaging studies of human maternal brain associated with the development of mother-infant relationship. First, we review the functional and structural changes in the mother’s brain during the early postpartum period. Second, we discuss the neural basis of maternal love, in which the orbitofrontal cortex integrates the reward and interoceptive processing systems, which suggests that a mother’s infant is not only a reward, but also functions to protect the mother's life through the production of homeostatic emotions in the mother. Third, we discuss the maternal brain including how the orbitofrontal cortex might possibly regulate maternal stress during the “terrible twos”. Maternal stress adaptations are important not only for the maternal behavior, but also for the mother’s well-being and mental health. Finally, we focus on the long-term effects of the early experience of parental care on the infant’s brain function, including those associated with later parenting and how maternal brain might shape the infant’s current and future brain.
2 0 0 0 OA 日本語の「すみません」の特徴について どのような場面で使用されるのか
- 著者
- 辻 周吾
- 出版者
- 学校法人 京都外国語大学国際言語文化学会
- 雑誌
- 国際言語文化学会日本学研究 (ISSN:2424046X)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, pp.19-38, 2022 (Released:2022-04-30)
The purpose of this study is to clarify the situations in which the Japanese word “sumimasen” is used and to help foreigners understand this word. From the example sentences in the corpus, I analyzed these situations and I could identify nine different cases: “a situation in which the speaker negatively influences the listener”, “a situation in which the speaker is not able to perform the expected action”, “a situation in which the speaker's behavior can be detrimental to the listener”, “a situation that is undesirable for the listener”, “a situation in which the speaker forces the listener to perform an action”, “a situation in which the speaker greets the listener formally and politely”, “a situation in which the speaker draws the listener's attention as a call to action”, “a situation in which the speaker greets the listener formally and politely”, and “a situation in which the speaker searches for words as fillers in conversations”. Thus, there is a wide range of situations in which the Japanese word “sumimasen” is used in everyday communication.
2 0 0 0 OA 鳥類の目と科の新しい和名(2)鳴禽類
- 著者
- 山崎 剛史 亀谷 辰朗
- 出版者
- 公益財団法人 山階鳥類研究所
- 雑誌
- 山階鳥類学雑誌 (ISSN:13485032)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.2, pp.138-143, 2020-12-15 (Released:2020-12-16)
- 参考文献数
- 14
Japanese names are a useful tool for Japanese speakers to communicate scientifically about birds. However, over 30 years have already passed since the most influential book treating Japanese names for all modern birds (Yamashina 1986) was published. During that time, the classification of birds has undergone major changes. Here we provide a revised list of Japanese names for family-level taxa of oscines, which adopts the latest classification system (Gill & Donsker 2018).
- 著者
- 井上 昌善
- 出版者
- 全国社会科教育学会
- 雑誌
- 社会科研究 (ISSN:0289856X)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, pp.1-12, 2021-11-30 (Released:2022-10-27)
本研究は,外部人材と子どもの熟議を促す社会科授業構成の原理と方法を,外部人材を活用した中学校社会科地理的分野の単元開発と実践を通して検討することを目指すものである。本研究の成果は,他者との協働的な関係性としての共通善を形成するためには,学校に公共空間を創出させ外部人材と子どもの熟議を促す指導が必要になることを開発単元の結果に基づいて示したことである。外部人材と子どもの熟議を促すためには,次の三点をふまえた指導が有効である。①課題解決のための共通基盤となる社会認識の形成を通して,子どもの思考の次元を変容させること。② 外部人材によるフィードバックを通して,子どもの自尊感情を高め意見表明に対する抵抗感を解消すること。③外部人材もまだ取り組んでいない現実社会の課題を中心教材として設定すること。 本研究の成果は,外部機関との連携を重視する学校教育のあり方を検討する際の一助になる。今後の課題は,消防士以外の外部人材や関係機関と連携した単元開発を行い地域と学校の連携方法のあり方を検討すること,地域社会と連携する社会科学習を推進する教師の教科観や学力観について明らかにすることの二点である。
2 0 0 0 OA 男性介護者の語りにみる「男性ゆえの困難」
- 著者
- 松井 由香
- 出版者
- Japanese Council on Family Relations
- 雑誌
- 家族研究年報 (ISSN:02897415)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.55-74, 2014 (Released:2015-03-31)
- 参考文献数
- 25
- 被引用文献数
- 2
本稿は、従来の家族介護研究において不可視化される、あるいは問題化される傾向にあった男性介護者に注目し、彼らが語る「男性ゆえの困難」について考察することを目的とする。具体的には、彼らが日々直面している介護をめぐる困難について、自らを「男性」あるいは「夫/息子」であることに関連づけて言及したトピックスを抽出し、彼らにとっての「男性ゆえの困難」の内実と意味づけを分析することをとおして、家族介護をめぐるジェンダー規範のありようについて考察した。調査対象者は、「仕事と介護の両立困難」「家事役割遂行の困難」「身体接触をともなう介護の困難」「介護の『仕事化』とそれにともなう困難」を「男性ゆえの困難」として語った。それらの困難は、彼らが介護や家事を女性が担うべきジェンダー化された役割として捉えていることを逆説的に示した。
2 0 0 0 OA 原子核のクラスター模型
- 著者
- 堀内 昶 池田 清美
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.11, pp.836-844, 1983-11-05 (Released:2008-04-14)
- 参考文献数
- 52
原子核のクラスター模型は, はじめは殻模型を補完するものとして, 最近では広い質量数及びエネルギー領域に適用しうるものとして用いられ, 軽い核の構造とその動的性質を記述するに不可欠な模型の一つとなっている. クラスター模型は"原子核内で核子が局所的に強く相関しあう部分的小集団"であるクラスターを単位とし, そのクラスターの集合体で取扱う模型である. それ故クラスター相関が強く現れる際には, クラスター間相対運動が原子核の運動様式の基本となるとする立場の模型である. この意味で, 殻模型とは立脚点が質的に異なる模型である. この解説は, 原子核の分子的 (クラスター) 構造の我国を中心とする研究について概説し, 近年活発となって来ている周辺研究分野との結びつきについて紹介するものである.
- 著者
- 堀口 康太
- 出版者
- 日本老年行動科学会
- 雑誌
- 高齢者のケアと行動科学 (ISSN:18803474)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.66-81, 2022 (Released:2022-12-30)
本研究の目的は,組織公平性,組織からのサポート,役割葛藤および役割のあいまいさという3つの職場要因と高齢労働者の仕事への自律的動機づけとの関連を検討することであった。本研究では,組織公平性と組織からのサポートは,自律的動機づけと正の関連を示し,役割葛藤および役割のあいまいさと自律的動機づけは負の関連を示すという仮説を検証した。調査は,企業に勤務する高齢労働者771名に対して行い,558名から回答を得た(Mage=62.00歳, SD=1.35歳,男性93.7%[n=523],女性4.3%[n=24],不明2.0%[n=11])。重回帰分析の結果,組織からのサポートが自律的動機づけ(「内発・貢献・自己発揮」,「獲得・成長」)と正の関連を示し,組織公平性は「内発・貢献・自己発揮」と正の関連を示した。一方,役割葛藤は自律的動機づけと負の関連を示した。したがって,本研究の仮説はおおむね支持された。本研究から高齢労働者の仕事への自律的動機づけの維持・向上のためには,上司からの公平な人事評価,上司・同僚との間の支援的な関係性,そして,業務上の役割を明確にできるようなサポート等,支援的な組織づくりをしていくことの重要性が示唆された。
2 0 0 0 OA NPMの展開とその帰結 評価官僚制と統制の多元化
- 著者
- 南島 和久
- 出版者
- 特定非営利活動法人 日本評価学会
- 雑誌
- 日本評価研究 (ISSN:13466151)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.3, pp.3_17-3_27, 2009 (Released:2014-05-21)
- 参考文献数
- 43
本稿はNPM(New Public Management)1と評価との関係に論及する。ここでいうNPMは、政治学的にいえば20世紀最終四半期に展開した世界的な行政改革の思潮である。具体的にはイギリスのサッチャー政権下のサッチャリズムやアメリカのレーガン政権下のレーガノミクス、あるいはニュージーランドのロンギ政権下のロジャーノミクスがその源流である。とりわけ日本では、行政改革のみならず政策評価の理論的背景として紹介されることもおおい。本稿は、これらをふまえながら公的部門における「評価」についてNPMの理論的影響があったのか、あったとすればどのような意味であったといえるのかという点を検討する。またこのことを明らかにした上で本稿は、NPM論者として著名なHoodの所説に寄り添いながらNPMが惹起するもうひとつの論点、すなわち「統制の多元化」現象を指摘する。
- 著者
- Bonpei Takase Katsumi Hayashi Satoko Takei Tetsuya Hisada Nobuyuki Masaki Masayoshi Nagata
- 出版者
- The Japanese Society of Internal Medicine
- 雑誌
- Internal Medicine (ISSN:09182918)
- 巻号頁・発行日
- pp.9318-21, (Released:2022-05-14)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 7
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) has become a pandemic, and vaccines remain the only effective tools available for ending it. However, their side effects, such as syncope, which mimics sudden cardiac death, are serious concerns. We herein report 6 cases of delayed vasovagal syncope and presyncope (VVR) caused by COVID-19 vaccination among 25,530 COVID-19 patients. The prevalence of delayed VVR due to COVID-19 vaccination was 0.026%. In addition, no delayed VVR was found among 17,386 patients who received the influenza vaccine. Delayed VVR is likely to be overlooked if medical staff are not aware of this symptom. This report provides significant information regarding effects of COVID-19 vaccination.
2 0 0 0 OA コントロール感の操作に基づくコントロール欲求が心理的所有感に与える影響の検討
- 著者
- 井関 紗代 北神 慎司
- 出版者
- 日本消費者行動研究学会
- 雑誌
- 消費者行動研究 (ISSN:13469851)
- 巻号頁・発行日
- pp.202303.003, (Released:2023-12-20)
- 参考文献数
- 34
補償的コントロール理論(compensatory control theory)によると、何らかの状況的要因によって、コントロール感が低下した場合、そのコントロール感をベースラインまで戻そうと動機づけられ、一時的にコントロール欲求が高まる。しかし、日本人のコントロール欲求はもともと低いことが指摘されている。したがって、日本人の場合、コントロール感が低下しても、それを補完しようとする動機が弱い可能性が示唆される。そこで、研究1では、日本人を対象に、コントロール感(高、低)を操作し、一時的にコントロール欲求が高まるのか検討したところ、その再現に成功した。研究2では、低下したコントロール感を補完する方略としてカスタマイズに着目した。コントロール感の低下により、一時的にコントロール欲求が高まっている場合、カスタマイズ商品に対する心理的所有感が高くなるという予測に基づき検討したが、コントロール感の操作による違いは確認されなかった。さらに、カスタマイズの有無にかかわらず、コントロール感高条件(vs低条件)で心理的所有感が高くなることが示された。