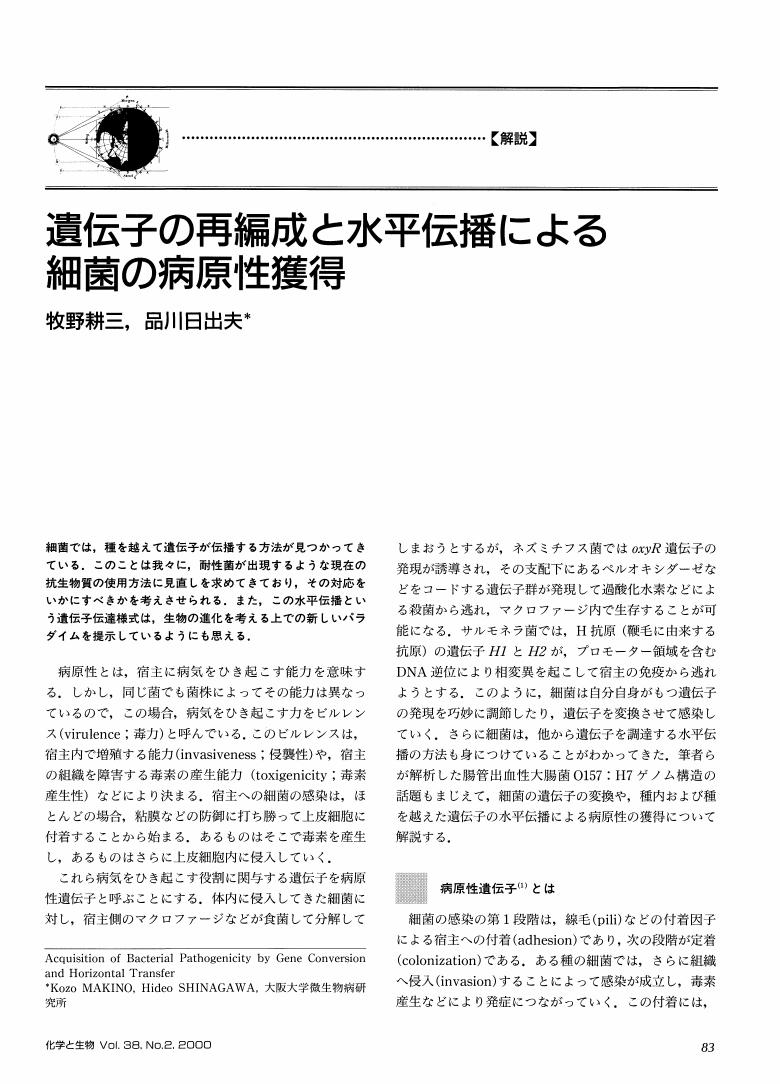2 0 0 0 OA 有毒化学物質の真の危機とは何か-「環境ホルモン騒ぎ」をこえて
- 著者
- 水口 憲哉
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.47-52, 1999-01-01 (Released:2009-11-16)
2 0 0 0 OA 適温での食事提供による患者満足度の改善
- 著者
- 増渕 吉一 杉田 恵 茅原 修 蛇沼 俊枝 梶 由依子 佐野 渉
- 出版者
- 一般社団法人 日本農村医学会
- 雑誌
- 日本農村医学会学術総会抄録集 第59回日本農村医学会学術総会 (ISSN:18801749)
- 巻号頁・発行日
- pp.392, 2010 (Released:2010-12-01)
目的:適温での食事提供は温冷配膳車を使用する施設が約半数に達しているが、当院では保温食器利用の為、現状設備において適温での食事提供には問題がある。そこで今回、料理の仕上がり時刻や盛付・配食時間の設定(以下配膳管理)等の工夫により、さらに美味しく食べてもらえる事を目的に適温サービスを行い患者満足度の向上を目指したので報告する。〈BP〉方法:_I_2009年9月から1カ月間の料理の温度計測_II_常食喫食者47名を対象とした適温アンケートの実施_III_喫食時温度が主食60~75℃、主菜60~75℃、副菜10~15℃と料理別に適温の目安を設定_IV_配膳管理徹底後、配膳時間・喫食時間の時差による満足度の変化を調査_V_温冷配膳車のデモ機による食事提供時のアンケート調査〈BP〉結果:_I_料理の温度計測では、主食が盛付時66.5℃から喫食時52.2℃、主菜が63.9℃から39.3℃、副菜が17.5℃から19.5℃となった。_II_現状の温度に「不満」は36%の回答があった。_III_喫食時温度は、主食(米飯)が実施前平均54.6℃実施後平均62.9℃、主菜(シチュー類)が39.3℃から65.3℃、副菜(和え物類)が19.5℃から10.5℃と適温の目安に近づく事が出来た。_IV_配膳管理の改善後は、時差に関係なく90%「満足」との回答が得られた。_V_温冷配膳車デモ機を使用時の満足度は良好であった。「温かい物は温かく、冷たい物は冷たく食べられる事が嬉しい」との意見が得られた。〈BP〉考察:現状把握により盛付時温度と喫食時温度の変化が著しい事が分かり、適温サービス意識が強化した。適温の目標設定により配膳管理が充実し患者満足度が向上したが、気温の変化や病棟による配膳時間の時差等の影響を考慮すると、温冷配膳車の利用が安定した適温サービスに非常に効果的であった。今後も、適温での食事提供には機械に頼るだけでなく常に配膳管理の意識・改善を継続する事の重要性が示唆された。
2 0 0 0 OA 鮮やかな光色で照明された食品に対する食欲
- 著者
- 小林 茂雄
- 出版者
- 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)
- 巻号頁・発行日
- vol.74, no.637, pp.271-276, 2009-03-30 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 5 7
The purpose of this research is to examine the effects of vivid colored lighting on appetite for food. The experiments were carried out to observe subjects' evaluations of various dishes illuminated with vivid colored lights in a room assumed to be a restaurant. The results of the experiments are summarized as follows.1. Appetite tended not to decrease when the food was illuminated with colors similar to those of the food. It was thought that this was because the food color did not change to any great extent.2. Appetite for food with plural colors tended to decrease more than was the case for monochrome foods. It was thought that this was because the color balance of the food with plural colors was easily changed by the colored lights.3. Appetite tended to be maintained at a constant level when the temperature of the food corresponded to the warm/cool image of the colored lights. On the other hand, appetite tended to decrease when the above two factors did not correspond.4. When the food was illuminated with blue and green lights, the appetite of women tended to be lower than that of men.
2 0 0 0 OA パラケルススの物質観 : 四元素と三原基の構造関係について
- 著者
- 菊池原 洋平
- 出版者
- 日本科学史学会
- 雑誌
- 科学史研究 (ISSN:21887535)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.217, pp.24-34, 2001 (Released:2021-08-17)
As a physician and a natural philosopher in the Renaissance, Paracelsus discusses in his works the structure of this world and individual things as well as the human body. All things in this world consist not only of four elements which Aristotle and his followers advocated, but also of three substances (sulfur, mercury and salt) which can be regarded as the offspring from the Arabic alchemical tradition. The aim of this paper is to consider a structural relationship between four elements and three substances form the viewpoint of the "life" concept, which was prominent in the Renaissance. My paper puts emphasis on the following items : 1. Every thing is given material body by just one element, not by four elements, in which qualitative difference can be discerned; four elements do not mutually transform as they do in the Aristotelian theory. 2. Four elements are the mother's womb bearing all things, and give to each of them nourishments for its activity. 3. Three substances are vital activities in the body, not a soul as assumed in the traditional Western thought. 4. An individualization of a thing is determined by both the activity of inherent three substances as a seed and their quantitative and qualitative differences. 5. A creation of this world is a process in which four elements are so fertilized by three substances as in biological fertilization. Therefore, a structural relationship between four elements and three substances is derived from an idea of the generative function based on the "life" concept. Accordingly we can safely say that four elements and three substances are theorized by his empirical thought which has "life" concept as an indispensable ingredient. It is not until four elements and three substances are combined each other that all things become of matter and life. In regard to the organization of a thing, it is not composed of just three substances; three substances do not in turn dominate four elements; rather, both need each other.
2 0 0 0 OA ぶっくしぇるふ より理解を深める! 体液電解質異常と輸液
- 著者
- 樋口 誠
- 出版者
- 信州医学会
- 雑誌
- 信州医学雑誌 (ISSN:00373826)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.2, pp.82, 2007-04-10 (Released:2013-08-07)
2 0 0 0 OA 高齢者の大腿骨頸部・転子部骨折とリハビリテーション
- 著者
- 加賀谷 斉
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.10, pp.677-685, 2008-10-18 (Released:2008-10-24)
- 参考文献数
- 75
- 被引用文献数
- 3 1
Femoral neck and intertrochanteric fractures are common in the elderly. These types of fractures affect about 90,000 people each year in Japan. At present, most such fractures are operated on. Immediate unrestricted weight-bearing after surgery is usually allowed. Conservative treatment may be considered if a patient can bear long-term bed rest and accept the risk of having a less functional outcome. Isometric quadriceps muscles and ankle range of motion exercises are important therapies to use before surgery. The appropriate intensity for rehabilitation is still controversial. The majority of the functional recoveries occur within the first 6 months, but further outpatient rehabilitation is still effective in patients without severe physical or cognitive impairments. About half of all patients recover their prefracture activities of daily living. Patients who are older or who are disoriented after surgery recovered least in terms of instrumental activities of daily living. In this group, even patients with uneventful healing courses did not regain their prefracture health-related quality of life level. Deep vein thrombosis, pulmonary infarction, palsy of the common peroneal nerve, fall, avascular necrosis of the femoral head, screw dislodging and removal, dislocation and infection are all possible risks factors after femoral neck and intertrochanteric fractures.
2 0 0 0 OA 当院救命救急センターに搬送された重症外国人患者診療の検討
- 著者
- 下山 京一郎 東 一成 織田 順
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.23, no.1, pp.19-26, 2020-02-29 (Released:2020-02-29)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
2017年度訪日外国人観光客は2,869万人であった。東京オリンピックが迫り,増加する外国人観光客に対する医療体制の構築が急務である。東京医科大学病院救命救急センターは三次救急症例のみが搬送される救命救急センターであり,比較的多数の外国人患者が搬送される施設である。そこでわれわれは,訪日外国人観光客を含む重症外国人患者87例についてその傾向,診療上の障壁について検討した。男女比は2:1で,国籍別割合はアジア人で74%を占め中国人が33%と最多であった。54%に何らかの形で通訳が必要で,51%の患者が入院した。 傷病としては心肺停止が最多であり25%を占めた。未収者の割合は14.9%に及んだ。診療上の障壁としては大使館,国際搬送サービスなど他機関との連携に難渋することが多かったが,言語面,文化面での問題に難渋した例は少なかった。通訳者のなかに専門職はほとんど含まれておらず,医療安全面でのリスクが高い状態で重症外国人患者診療が行われていることがわかった。
2 0 0 0 OA パーキンソン病の栄養療法の確立に向けて
- 著者
- 橋本 幸亜
- 出版者
- 一般社団法人 日本静脈経腸栄養学会
- 雑誌
- 日本静脈経腸栄養学会雑誌 (ISSN:21890161)
- 巻号頁・発行日
- vol.32, no.5, pp.1453-1455, 2017 (Released:2017-12-20)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
パーキンソン病(Parkinson's Disease;以下、PDと略)患者は、手足が震える、動きが緩慢になる、筋肉が硬直する、体のバランスが悪くなる等の症状がみられ、進行の速さは患者によって異なる。さらに、手足の筋肉だけではなく、舌の筋肉や口の周りの筋肉等、すべての筋肉の動きが悪くなるため、食べ物を噛むことも飲み込むことも難しくなる。PD 患者の栄養管理は、病勢に応じた食事形態への配慮や、薬との相互作用に注意することが大切である。
2 0 0 0 OA 日本語の否定命令文をめぐって : 「スルナ」を述語とする文の特性と機能
- 著者
- 尾崎 奈津
- 出版者
- 日本語学会
- 雑誌
- 日本語の研究 (ISSN:13495119)
- 巻号頁・発行日
- vol.3, no.1, pp.65-79, 2007-01-01 (Released:2017-07-28)
本稿は否定命令文の機能と特異性,さらに命令文と否定の関わりについて記述したものである。従来,叙述の否定文は先に肯定的想定があってはじめて使用されることが知られているが,否定命令文も叙述の文と同様,肯定的な事態,すなわち命令文の対象となる行為が先にあって使用される。そしてその行為の成立する時間および意志性という二つの要因により,文の機能が,事態の実現を要求する《命令》から,〈不満の表明〉・〈当為的判断〉・対象となる行為に対する〈評価〉・〈願望〉に変化する。実例では後者の《命令》以外のもののうち,叙述文的な機能を担う〈不満の表明〉〈当為的判断〉〈評価〉の例が非常に多く出現する。しかもその中で〈評価〉は否定命令文に特有のものである。こうしたことから,否定命令文は肯定命令文に比べて叙述文に傾く傾向が強いといえる。
2 0 0 0 すべり台の動摩擦係数の実測研究
- 著者
- 村田 次郎 塩田 将基
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.2, pp.95-100, 2023-06-06 (Released:2023-06-10)
- 参考文献数
- 7
「重い人ほどすべり台を速く滑るのは何故か」という疑問を動機とした,すべり台の摩擦に関する大学生の探究学習の実践例を報告する。一様重力場中の落下加速度は質量によらず一定であり,これは動摩擦がはたらく状況でも同じであると学習するが,これと生活経験が矛盾する事から生じる疑問である。物体が滑る加速度を実測し,空気抵抗の寄与,動摩擦係数の質量依存性,速度依存性を調べた。ローラー式すべり台では動摩擦係数が一定ではない事が示された一方,金属板式すべり台では一定値からずれる有意な結果は得られなかった。
2 0 0 0 OA 不妊クリニックにおける鍼灸治療導入の実態に関するアンケート調査
- 著者
- 池田 朋子 田口 玲奈 北小路 博司
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.3, pp.230-241, 2020 (Released:2021-10-28)
- 参考文献数
- 13
【目的】全国の不妊クリニックを対象に、不妊治療における鍼灸の認識やその導入の実態を明らかにし、今後の不妊鍼灸における問題点を考察する。 【対象と方法】2015年9月現在、(公社)日本産科婦人科学会ホームページ上で「体外受精・胚移植の臨床実施に関する登録施設」、「ヒト胚および卵子の凍結保存と移植に関する登録施設」、「顕微授精に関する登録施設」の全てに該当する547施設を対象に、郵送による無記名のアンケート調査を行った。 【結果】有効回収率は28.5% (156/547通) で、回答者の82.7%を医師が占めた。不妊治療における鍼灸は55.1%で認知されていた。しかし、実際に鍼灸を導入している施設は8.3%で、72.0%では今後も導入予定はなかった。鍼灸を導入している施設は婦人科医院が最も多く、鍼灸導入状況と病院形態に関連性がみられた(p=0.037)。また、鍼灸導入と情報源の有無には関連性がみられた(p=0.0009)。鍼灸の導入目的には、「精神的ストレスの緩和」が75.9%と最多であったが、導入しない理由としては、「鍼灸治療に十分なエビデンスがあると感じられないため」が59.3%と多かった。 【結論】現在、鍼灸を導入しているクリニックは少数であるが、今後、比較研究などエビデンスに基づいた、医師や患者にも分かりやすい鍼灸治療の有効性を示す必要があると考えられた。また、鍼灸師が他の医療従事者と同等のレベルで不妊治療について意見・情報交換ができるようになれば、クリニック内での導入や、クリニックと提携して治療を行う鍼灸院が増える可能性があり、鍼灸師のレベル向上が求められる。
2 0 0 0 OA 遺伝子の再編成と水平伝播による細菌の病原性獲得
- 著者
- 牧野 耕三 品川 日出夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本農芸化学会
- 雑誌
- 化学と生物 (ISSN:0453073X)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.83-92, 2000-02-25 (Released:2009-05-25)
- 参考文献数
- 7
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 日本語教育における学習者音声の研究と音声教育実践
- 著者
- 戸田 貴子
- 出版者
- 公益社団法人 日本語教育学会
- 雑誌
- 日本語教育 (ISSN:03894037)
- 巻号頁・発行日
- vol.142, pp.47-57, 2009 (Released:2017-04-25)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
本稿では,近年の学習者音声に関する研究成果を紹介し,音声教育実践について述べる。 三つの調査の結果から,1)発音上の問題がコミュニケーションの弊害になっているとの認識を学習者が示していることが明らかになった。一方,2)大人になってから学習を開始した場合でも,学習次第でネイティブレベルの発音習得が可能であることがわかった。また,3)学習成功者は発音学習に対する意識・学習方法・インプットの量などの理由に支えられて高い発音習得度を達成したことが示唆された。 これらの研究成果を踏まえ,教室内外において発音練習ができる学習環境を整備し,学習機会を提供することにより,自律学習を促していくことを提案した。具体例としては,1)シャドーイング練習用DVD教材,2)オンデマンド日本語発音講座,3)日本語発音練習用ソフトウェアの開発について述べた。
2 0 0 0 OA 気管支喘息と副腎機能低下症
- 著者
- 灰田 美知子
- 出版者
- 一般社団法人 日本心身医学会
- 雑誌
- 心身医学 (ISSN:03850307)
- 巻号頁・発行日
- vol.62, no.2, pp.132-138, 2022 (Released:2022-03-01)
- 参考文献数
- 16
気管支喘息(以下,喘息)は心理社会的要因の影響が多い疾患であるが,そのさまざまな不定愁訴は心理社会的要因のみならず背景に存在する副腎機能低下症(adrenal insufficiency:AI)の関与も否定できない.本来の喘息の重症度に加え,過去の副腎皮質ホルモン使用による続発性のAIがあれば,それは不定愁訴の関与因子として疑う必要がある.AIは個人差も大きく実臨床での確定診断は困難である.今回,128例の喘息患者の副腎機能検査として①コルチゾールの日内変動,②24時間尿中コルチゾール,③ACTH負荷試験を実施し,その解析を行った.喘息患者の約15.6%にきわめて重症な副腎機能低下を認めたほか,CMI,YG性格検査,TEGなどを実施したところ,AIの重症度に応じて身体的自覚症状,疾病頻度などが高く,AIが,このような不定愁訴の背景にある可能性も考慮する必要があると考えられた.
2 0 0 0 OA ある抄録者のためらい ――気の想像観から元子論的想像観へ――
- 著者
- 甘露 純規
- 出版者
- 日本近代文学会
- 雑誌
- 日本近代文学 (ISSN:05493749)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, pp.16-31, 2019-11-15 (Released:2020-11-15)
江戸期、抄録は読書の際に、気に入った文章を抜き書きし記憶する行為だった。こうした抄録は読者にとって単に文章表現を記憶するだけでなく、気の概念を媒介として、自らの作文のための想像を掻き立てた。本稿では、明治二一年の吉田香雨『小説文範』を手掛かりに、抄録物を生み出した文化的背景、具体的には明治期以前の記憶と想像の関係を明らかにした。また、こうした明治以前の記憶・想像についての言説が、明治期の心理学の移入の中でどのように解体されていくかを示した。
2 0 0 0 OA 現代における承認の諸相
- 著者
- 入江 幸男
- 出版者
- 日本ヘーゲル学会
- 雑誌
- ヘーゲル哲学研究 (ISSN:13423703)
- 巻号頁・発行日
- vol.2000, no.6, pp.28-40, 2000-12-16 (Released:2010-07-27)
- 参考文献数
- 12
2 0 0 0 OA ケタミン・キシラジン混合液による野生ニホンツキノワグマの不動化
- 著者
- 大原 佳世子 川西 秀則 伊藤 大 正岡 亮太 藤井 光子 福本 幸夫
- 出版者
- 日本野生動物医学会
- 雑誌
- 日本野生動物医学会誌 (ISSN:13426133)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.99-104, 2000 (Released:2018-11-03)
- 参考文献数
- 10
広島県(農林水産部)が1994年から実施したツキノワグマ保護管理計画に基づいて捕獲された野生ニホンツキノワグマの, 薬物による不動化を実施した。不動化の方法は, 箱罠またはくくり罠で捕獲された個体に対して, 20%塩酸ケタミンと2%あるいは5%塩酸キシラジンの混合液を, 吹き矢, 麻酔銃または注射器によって筋肉内注射した。実施した26例のうち, オス12例, 雌3例の合計15例で, 初回の注射で不動化することができた。基準投与量は体重1kg当たりケタミン10mg, キシラジン1mgとし, 推定体重に基づいて投与量を計算し, 不動化後に実測した体重から体重1kg当たりの投与量を逆算した。実際の投与量は体重1kg当たり, 最低ケタミン6.25mg+キシラジン0.625mgから, 最高ケタミン20.00mg+キシラジン2.00mgで, 注射後3〜11分で不動化した。また, この不動化に要した注射液の注入量は, 最少が体重26kgの個体に対する1.75ml(20%ケタミン液+5%キシラジン注射液使用), 最多が体重75kgの個体に対する15ml(20%ケタミン液+2%キシラジン注射液使用)であった。不動化薬投与による副作用と思われる症状は, 1頭において軽度の全身性痙攣と唾液分泌昂進を認めたが, 無処置で覚醒した。
2 0 0 0 OA 雑誌『太陽』による風景写真の流通が風景の見かたにもたらした影響
- 著者
- 水谷 知生
- 出版者
- 公益社団法人 日本造園学会
- 雑誌
- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)
- 巻号頁・発行日
- vol.80, no.5, pp.405-408, 2017-03-31 (Released:2017-09-13)
- 参考文献数
- 28
It has been indicated that “The Japanese Landscape Theory” by Shiga shigetaka, which was published in 1894, was the key to change the way Japanese see natural landscape. The change occurred during this period seems to have resulted in the designation of National Parks in 1930s, and further investigation of the background is required. This paper examines the transition of landscape photographs published in the “Taiyo” magazine, which is considered to be one of the factors influencing the way of seeing natural landscapes in Japan by distributing a large quantity of printed landscape photographs to the public. As the “Taiyo” magazine started to publish photographs selected by competitions, photographs of unidentified landscape increased in number after 1902, whereas “Meisyo” had been mainly featured before around 1900. This paper suggests that the distribution of photographs which had been influenced by landscape painting, hence emphasizing artistic beauty of landscapes, had changed the way general readers see natural landscapes.
2 0 0 0 OA 脱髄性末梢神経障害の電気診断と末梢神経エコーの有用性
- 著者
- 野寺 裕之
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床神経生理学会
- 雑誌
- 臨床神経生理学 (ISSN:13457101)
- 巻号頁・発行日
- vol.44, no.4, pp.203-211, 2016-08-01 (Released:2017-08-09)
- 参考文献数
- 24
脱髄性末梢神経疾患は免疫療法による治療が可能であるため, 見逃し無く診断することが重要である。神経伝導検査をはじめとする神経生理検査は多くの末梢神経の病態をベッドサイドで明らかにできるため特に重要な検査であるが, 診断基準が複雑であることから, 項目を丸覚えするのではなく, 検査異常を示す電気生理学的メカニズムを理解することが正確な診断と病態の把握に必須である。さらに, 電気生理学的検査に加え, 末梢神経の画像検査が有用とされ, 脱髄を示唆する神経腫大を画像的に検出することができれば診断精度が向上する。MRIとエコーなどを用いた画像検査と神経生理検査を組み合わせた病態の把握が進んでいる。
2 0 0 0 OA アホウドリと「帝国」日本の拡大
- 著者
- 平岡 昭利
- 出版者
- 地理空間学会
- 雑誌
- 地理空間 (ISSN:18829872)
- 巻号頁・発行日
- vol.1, no.1, pp.53-70, 2008 (Released:2018-04-12)
行為論で人間行動を解釈する視点から,明治期,日本人の南洋進出の行為目的は,アホウドリであったと想定し,それを追った行動が「帝国」日本の領域拡大につながったことを検討した。アホウドリは小笠原諸島では早くから認識され,1885 年頃には羽毛が外国に輸出されていた。鳥島でアホウドリ撲殺事業を始めた玉置半右衛門は,巨利を得て実業家となり榎本武揚などの南進論者と深くかかわっていた。当時,無人島開拓などの新聞小説が広く読まれるなか,開拓事業に成功した玉置は数々の書物に取り上げられ,無人島探検ブームの一因となった。このブームの中,アホウドリから莫大な利益がもたらされることを認識した人々は,当時の地図に数多く描かれていた疑存島の探検に競って乗り出し,権利獲得競争の果てというべきガンジス島問題も発生した。このようにアホウドリから一攫千金を目論む山師的な人々の行動が,「帝国」日本の領域を東へ,南へと拡大したことを明らかにした。