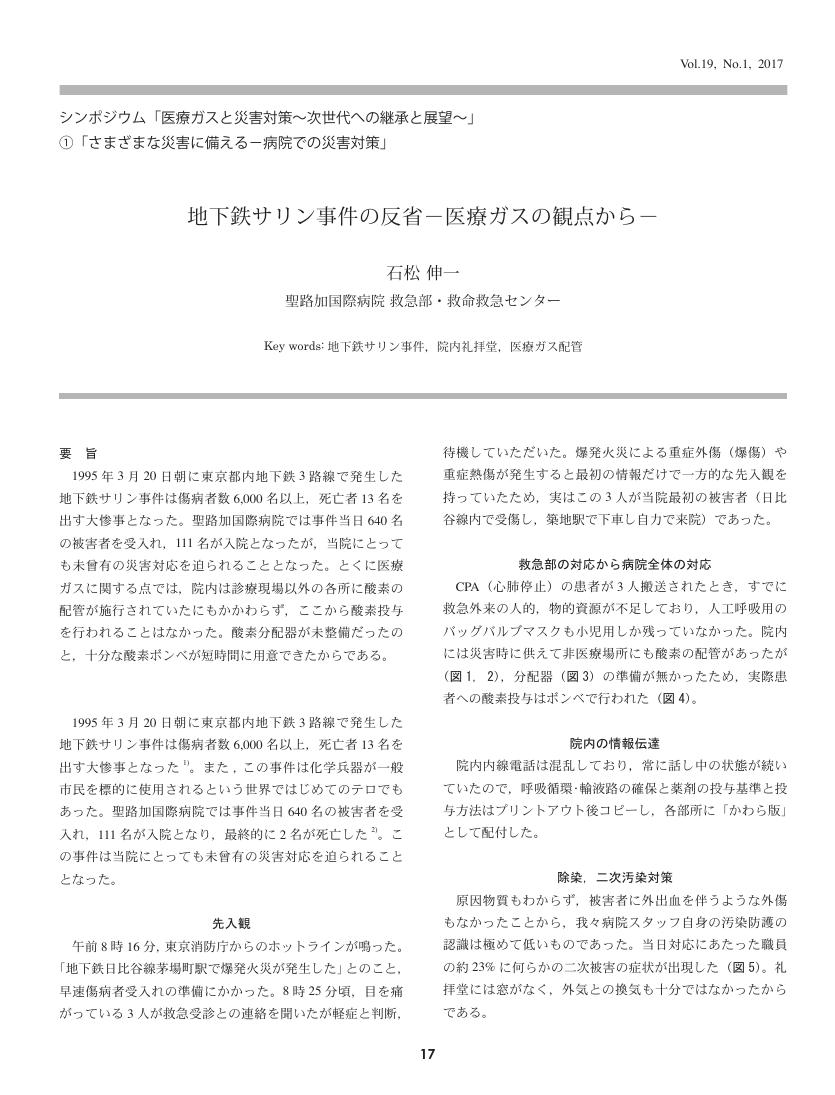- 著者
- Tomoka Shimizu Tasuku Miyoshi
- 出版者
- Society of Aero Aqua Bio-mechanisms
- 雑誌
- Journal of Aero Aqua Bio-mechanisms (ISSN:21851522)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.1, pp.6-12, 2019 (Released:2019-02-23)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
The aim of this study was to clarify postural control in the pitch direction using a combination of the flexion angles of the root and fin tip of the pectoral fin in Mobula japanica using Three-D-Computational fluid dynamics analysis. We made Mobula models that allow flexion of the tip of the fin and the root of the fin independently. It was revealed that independent pectoral fin flexion promotes a change in the velocity distribution around the body and, as a result, the pitch moment is generated.
- 著者
- Mitsunori MATSUMAE Kagayaki KURODA Satoshi YATSUSHIRO Akihiro HIRAYAMA Naokazu HAYASHI Ken TAKIZAWA Hideki ATSUMI Takatoshi SORIMACHI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.4, pp.133-146, 2019 (Released:2019-04-15)
- 参考文献数
- 120
- 被引用文献数
- 14 31
The “cerebrospinal fluid (CSF) circulation theory” of CSF flowing unidirectionally and circulating through the ventricles and subarachnoid space in a downward or upward fashion has been widely recognized. In this review, observations of CSF motion using different magnetic resonance imaging (MRI) techniques are described, findings that are shared among these techniques are extracted, and CSF motion, as we currently understand it based on the results from the quantitative analysis of CSF motion, is discussed, along with a discussion of slower water molecule motion in the perivascular, paravascular, and brain parenchyma. Today, a shared consensus regarding CSF motion is being formed, as follows: CSF motion is not a circulatory flow, but a combination of various directions of flow in the ventricles and subarachnoid space, and the acceleration of CSF motion differs depending on the CSF space. It is now necessary to revise the currently held concept that CSF flows unidirectionally. Currently, water molecule motion in the order of centimeters per second can be detected with various MRI techniques. Thus, we need new MRI techniques with high-velocity sensitivity, such as in the order of 10 μm/s, to determine water molecule movement in the vessel wall, paravascular space, and brain parenchyma. In this paper, the authors review the previous and current concepts of CSF motion in the central nervous system using various MRI techniques.
2 0 0 0 OA 北部九州における縄文海進以降の海岸線と地盤変動傾向
- 著者
- 下山 正一
- 出版者
- Japan Association for Quaternary Research
- 雑誌
- 第四紀研究 (ISSN:04182642)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.5, pp.351-360, 1994-12-31 (Released:2009-08-21)
- 参考文献数
- 17
- 被引用文献数
- 1 3
海成層の最大分布に基づき, 北部九州各地の縄文海進ピーク時期の海域と海岸線が明らかになった. 縄文時代以降の海岸線は前進傾向にあるので, 海成層の分布限界, 弥生時代の遺跡分布, 江戸時代初期の国絵図の3つの情報が十分得られれば, 佐賀・筑後両平野の例に示すように, 縄文前期の海岸線, 弥生時代末の海岸線, 江戸時代初期の海岸線をそれぞれ描くことができる.北部九州のうち, 玄界灘・響灘沿岸地域の海成層上限高度は一様ではなく, +0.4から+4.5mまでの値が見積られる. 有明海沿岸の佐賀平野と筑後平野の縄文海進ピーク時期の海成層の上限高度差は-1.9mと+4.8mで, 隣接地域としては最も大きい. これらの上限高度の差は過去5~6,000年間に生じた垂直変動量とみなせる.北部九州各地の下末吉海進ピーク時期の海成層が現海面下にのみ存在することから, 北部九州は全体に緩やかな沈降地域と考えられる.
2 0 0 0 OA 新しい聴覚検査 補聴器適合に役立つ検査 ―実耳測定とワイドバンドティンパノメトリ―
- 著者
- 水足 邦雄
- 出版者
- 一般社団法人 日本聴覚医学会
- 雑誌
- AUDIOLOGY JAPAN (ISSN:03038106)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.3, pp.174-180, 2020-06-30 (Released:2020-07-16)
- 参考文献数
- 11
- 被引用文献数
- 1 1
要旨: 適切な補聴器フィッティングの評価をする上で, 補聴器適合検査は不可欠である。実耳測定は補聴器適合検査の指針にも掲載されているが, 充分に普及しているとは言えない。本稿では実耳測定の実際と特に小児とオープンフィッティングでの活用方法を紹介する。また, 新しい中耳機能測定装置であるワイドバンドティンパノメトリについて解説し, その補聴器適合での活用の可能性について具体例を提示した。従来の補聴器適合検査では不安が残る症例では, これらの検査を追加することでよりよいフィッティングを行うことができる。
2 0 0 0 OA アニメキャラクターの分類と女性タレントとの類似性
- 著者
- 太田 碧 越智 啓太
- 出版者
- 公益社団法人 日本心理学会
- 雑誌
- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第78回大会 (ISSN:24337609)
- 巻号頁・発行日
- pp.2EV-1-022, 2014-09-10 (Released:2021-03-30)
2 0 0 0 OA 視野と内声化のトレーニングが読み速度に与える影響
- 著者
- 森田 愛子 小澤 郁美
- 出版者
- 日本教育工学会
- 雑誌
- 日本教育工学会論文誌 (ISSN:13498290)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.Suppl, pp.45-48, 2016-01-25 (Released:2016-02-12)
- 参考文献数
- 11
本研究の目的は,読み手のニーズに合うような,簡易で科学的根拠が明確であり,十分な効果をもたらす速読トレーニングを開発し,その効果を実証することであった.本研究で実施したトレーニングは,いずれも,1日約5分のトレーニングを1週間行うものであった.視野のトレーニングについては,既に,1週間で約30%の読み速度上昇効果があることが実証されているが,先行研究のトレーニングを改定したところ,読み速度を約50%上昇させることができた.また,黙読時に頭の中で文章を音声化するという内声化を減少させるトレーニングを追加したところ,読み速度を約60%上昇させることに成功した.
2 0 0 0 OA 向社会的行動の対象による向社会的動機づけの差異――青年期初期の子どもを対象に
- 著者
- 山本 琢俟 上淵 寿
- 出版者
- 日本パーソナリティ心理学会
- 雑誌
- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, no.2, pp.86-96, 2021-09-15 (Released:2021-09-15)
- 参考文献数
- 28
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的は,関係性アプローチに則り対象ごとの向社会的行動と関連する向社会的動機づけの差異を多面的に検討することである。動機づけは,自己決定理論の観点から自律的な向社会的動機づけと統制的な向社会的動機づけを扱った。インターネットを通じて小学5年生から中学3年生の子ども1,998名に自記式調査を実施した。変数中心的なアプローチと人間志向的なアプローチによって,対象別の向社会的行動と向社会的動機づけとの関連が検討された。その結果,向社会的行動はその対象によらず自律的な向社会的動機づけと関連していること,見知らぬ人に対する向社会的行動については自律的な向社会的動機づけと統制的な向社会的動機づけが共に関連していることが示された。本研究の結果は,向社会的行動の対象ごとにその動機づけが異なることを実証的に示したものであり,向社会的行動の対象による生起頻度の違いが向社会的動機づけに起因することを示唆するものである。
2 0 0 0 OA ビタミンKの生体内活性化とその意義
- 著者
- 中川 公恵
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.133, no.12, pp.1337-1341, 2013-12-01 (Released:2013-12-01)
- 参考文献数
- 20
Natural vitamin K is found in two forms: a plant form, phylloquinone (PK) and bacterial forms, menaquinones (MKs). PK is a major form of dietary vitamin K; however, the most prevalent form of vitamin K in animals and humans is menaquinone-4 (MK-4). Despite its high concentrations, the origin of MK-4 is yet to be defined. It is postulated that PK is converted into MK-4 and accumulates in extrahepatic tissues. The molecular mechanisms for these conversion reactions have been unclear. To identify the MK-4 biosynthetic enzyme, we screened the human genome database for prenylation enzyme. We found UbiA prenyltransferase domain containing 1 (UBIAD1), a human homologue of Escherichia coli prenyltransferase menA. The short interfering RNA against the UBIAD1 gene inhibited the conversion of deuterium-labelled vitamin K derivatives into deuterium-labelled-MK-4 (MK-4-d7) in human cells. We confirmed that the UBIAD1 gene encodes an MK-4 biosynthetic enzyme through its expression and conversion of deuterium-labelled vitamin K derivatives into MK-4-d7 in insect cells infected with UBIAD1 baculovirus. UBIAD1 was localized in endoplasmic reticulum. Our results show that UBIAD1 is a human MK-4 biosynthetic enzyme. This identification will permit more effective decisions to be made about vitamin K intake and bone health.
- 著者
- 吉田 悠記子
- 出版者
- 日本経営学会
- 雑誌
- 日本経営学会誌 (ISSN:18820271)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, pp.29-42, 2020 (Released:2021-09-01)
- 参考文献数
- 38
What value can startups derive from investment by non-financial companies? It has been revealed that venture capital (hereinafter VC) provides not only capital but also various supports for early growth of startups (Carpenter and Petersen, 2002). Financial companies including banks are also analyzed as the source of capital for startups, especially in terms of their differences from VC (Winton and Yerramilli, 2008; Marcus et al, 2013). In addition, the importance of open innovation is increasing (Chesbrough, 2003). Because of non-financial company’s benefits by collaborating with startups, the investment ratio of non-financial companies is still high. However, the impact caused by non-financial companies on the growth of startups has not been fully clarified in previous research. Based on the institutional logic and the resourced-based view, this study analyzed the impact caused by non-financial companies as well as VC and financial companies on initial public offerings (hereinafter IPOs) of startups. This study analyzes the data of startups that went public on the Japanese stock exchange from 2007 to 2009. The dependent variable is the period up to IPO, which is an indicator of the speed of growth of startup. The independent variables are the investment ratios of five types of investors before IPO, non-financial companies, financial companies, corporate venture capital (hereinafter CVC) by non-financial companies, CVC by financial companies and independent VC, which are indicators of impact caused by investors. As a result, it is confirmed that the period until IPO is shortened when the investment ratio of non-financial company is high. This means that the growth of the startup up to IPO was promoted earlier because of the investment by non-financial companies. The contribution of this research is that it has clarified the impacts for the growth of startup caused by non-financial companies, under the situation with several types’ investors.
2 0 0 0 OA 地下鉄サリン事件の反省−医療ガスの観点から−
- 著者
- 石松 伸一
- 出版者
- 日本医療ガス学会
- 雑誌
- Medical Gases (ISSN:24346152)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.1, pp.17-18, 2017 (Released:2019-09-17)
- 参考文献数
- 2
2 0 0 0 OA 少量のヒドロモルフォン投与中に神経毒性を呈した腎機能障害を有する2例
- 著者
- 鷹津 英 八木 佑加子 大前 隆仁 山口 崇
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.3, pp.267-270, 2021 (Released:2021-09-16)
- 参考文献数
- 12
本邦では腎不全患者に対してヒドロモルフォンを使用し,神経毒性を呈した報告は多くはない.この度,腎機能障害患者に対してヒドロモルフォンを開始または増量したところ,せん妄を呈した症例を2例経験した.症例1ではがん性疼痛に対してヒドロモルフォン持続注射を2.4 mg/日から3.6 mg/日に増量する過程でせん妄が出現した.減量後,せん妄は改善した.症例2では咳嗽・呼吸困難に対してヒドロモルフォン2 mg/日の内服を開始したところせん妄が出現し,中止後改善した.それぞれヒドロモルフォンによりがん性疼痛や咳嗽・呼吸困難は改善されていたが,有害事象によりヒドロモルフォンの継続が困難なため,オピオイドスイッチングを要した.腎不全患者に高用量,長期間のヒドロモルフォンを使用することで神経毒性を呈する報告はあるが,少量・短期間の投与でも神経毒性を呈することを経験した.
- 著者
- 高柳 匡 西岡 辰磨 笠 真生
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.6, pp.361-369, 2014-06-05 (Released:2019-08-22)
重力を含む全ての力を統一すると期待される超弦理論は,AdS/CFT対応と呼ばれる重力理論と場の理論の等価性(ホログラフィー原理)を予言する.近年,この考え方を量子多体系の物理や物性物理学へ応用する動きが高まっており,高温超伝導体などに代表される強相関量子多体系において,普遍的と期待される性質が重力理論を用いて盛んに解析されている.その中でも特に「エンタングルメント・エントロピー」と呼ばれる,量子多体系の量子状態の量子的なもつれを測る指標が注目を集めている.ホログラフィー原理に基づくと,量子臨界点にある量子多体系のエンタングルメント・エントロピーは,反ド・ジッター空間中の「曲面の最小面積」で与えられる.従来の複雑な計算方法と異なり,このホログラフィック公式は相互作用する系に適用可能な新たな解析方法である.一方,量子情報理論および数値物性理論では,量子系の波動関数を,しばしばテンソルネットワークと呼ばれる形式で表示し,波動関数に含まれるエンタングルメントの見積もりが行われる.ホログラフィー原理とテンソルネットワークは,一見何の関係もないように見える.ところが最近の研究では,テンソルネットワークを用いて異なったエネルギースケールでのエンタングルメントの記述を考えると,自然に反ド・ジッター空間中の曲面の構造が現れることがわかってきた.このように,エンタングルメント・エントロピーを通じて,量子多体系,量子重力理論,量子情報理論の間の関係性が明らかになりつつある.特に,ホログラフィック公式とテンソルネットワークの類似性は,重力理論における時空そのものが量子エンタングルメントの集合体であるという,全く新しい見方を提起している.本記事では,ホログラフィック公式を中心に,この3つの分野におけるエンタングルメント・エントロピーに関する最近の発展を解説する.まず2節では量子多体系のエンタングルメント・エントロピーを導入し,強劣加法性などの基本的性質について述べる.また,エンタングルメント・エントロピーのスケーリングが,量子多体系の種々の相を区別するのに有効な指標であることを見る.次の3節では系のエネルギースケールを変えたときのエンタングルメントの変化を考察する.特に系が持つ「有効自由度」はエネルギーが低くなるにつれ減少するはずだが,そのような有効自由度を測る関数が,エンタングルメント・エントロピーを用いることで具体的に構成できることを示す.4節ではまずホログラフィー原理の具体例であるAdS/CFT対応を解説し,重力理論を用いたエンタングルメント・エントロピーのホログラフィック公式を導入する.その後,この公式が重要な性質である強劣加法性を満たすことを確認し,AdS/CFT対応で記述される非フェルミ流体に触れる.最後に5節ではMERAと呼ばれる,繰り込み群の考え方に基づいた量子多体系のテンソルネットワーク波動関数を紹介し,MERAとAdS/CFT対応におけるホログラフィック公式の類似性を考察する.
2 0 0 0 OA 断層心エコー図法によるウシの心奇形の診断
- 著者
- 萩尾 光美 村上 隆之 大塚 宏光
- 出版者
- Japanese Society of Veterinary Cardiology
- 雑誌
- 動物の循環器 (ISSN:09106537)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.19, pp.1-10, 1986 (Released:2009-09-17)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
2 0 0 0 OA 地震学のオープンサイエンス―地震観測所のサイエンスミュージアム・プロジェクトをめぐって―
- 著者
- 矢守 克也 飯尾 能久 城下 英行
- 出版者
- 日本グループ・ダイナミックス学会
- 雑誌
- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)
- 巻号頁・発行日
- pp.2009, (Released:2020-12-24)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 3
巨大災害による被害,新型感染症の世界的蔓延など,科学(サイエンス)と社会の関係の問い直しを迫られる出来事が近年相次いでいる。本研究は,このような現状を踏まえて,地震学をめぐる科学コミュニケーションを事例に,「オープンサイエンス」を鍵概念として科学と社会の関係の再構築を試みようとしたものである。本リサーチでは,大学の付属研究施設である地震観測所を地震学のサイエンスミュージアム(博物館施設)としても機能させることを目指して,10年間にわたって実施してきたアクションリサーチについて報告する。具体的には,「阿武山サポーター」とよばれる市民ボランティアが,ミュージアムの展示内容に関する「解説・観覧」,地震活動の「観測・観察」,および,その結果得られた地震データ等の「解析・解読」,以上3つの側面で地震学に「参加」するための仕組みを作り上げた。以上を踏まえて,「学ぶ」ことを中心とした,従来,「アウトリーチ」と称されてきた科学コミュニケーションだけでなく,科学者と市民が地震学を「(共に)なす」ことを伴う,言いかえれば,「シチズンサイエンス」として行われる科学コミュニケーションを実現することが,地震学を「オープンサイエンス」として社会に定着させるためには必要であることを指摘した。
2 0 0 0 OA 職業性ストレスとワーク·エンゲイジメント
- 著者
- 島津 明人
- 出版者
- 公益財団法人 パブリックヘルスリサーチセンター
- 雑誌
- ストレス科学研究 (ISSN:13419986)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.1-6, 2010 (Released:2010-06-01)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 10 17
This article gives an overview of the recently introduced concept of work engagement: a positive, fulfilling, affective motivational state of work-related well-being. I first define engagement as a state including vigor, dedication, and absorption, and then refer to how engagement differs from related concepts (i.e., burnout and workaholism). Work engagement is a unique concept that is best predicted by job resources (e.g., autonomy, supervisory coaching, performance feedback) and personal resources (e.g., optimism, self-efficacy, self-esteem) and is predictive of psychological/physical health, proactive organizational behavior, and job performance. The most often used instrument to measure engagement is the Utrecht Work Engagement Scale, a self-report instrument that has been validated in many countries across the world. The paper closes with practical implications to improve work engagement in terms of job and personal resources.
2 0 0 0 OA オーダー履歴による待ち時間の分析
- 著者
- 津本 周作 木村 知広 河村 敏彦 平野 章二
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会第二種研究会資料 (ISSN:24365556)
- 巻号頁・発行日
- vol.2018, no.AIMED-006, pp.12, 2018-11-21 (Released:2021-08-28)
病院情報システム蓄積された実行オーダー歴に系列マイニング・クラスタリングを適用して,外来診療におけるクリニカルパスを構成する方法の開発と検証について報告する。
- 著者
- Takafumi TANEI Yasukazu KAJITA Shigenori TAKEBAYASHI Kosuke AOKI Norimoto NAKAHARA Toshihiko WAKABAYASHI
- 出版者
- The Japan Neurosurgical Society
- 雑誌
- Neurologia medico-chirurgica (ISSN:04708105)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.6, pp.213-221, 2019 (Released:2019-06-15)
- 参考文献数
- 38
- 被引用文献数
- 6 17
The efficacy and predictive factors associated with successful spinal cord stimulation (SCS) for central post-stroke pain (CPSP) have yet to be definitively established. Thus, this study evaluated the rates of pain relief found after more than 12 months and the predictive factors associated with the success of SCS for CPSP. The degree of pain after SCS in 18 patients with CPSP was assessed using the Visual Analog Scale preoperatively, at 1, 6 and 12 months after surgery, and at the time of the last follow-up. After calculating the percentage of pain relief (PPR), patients were separated into two groups. The first group exhibited continuing PPR ≥30% at more than 12 months (effect group) while the second group exhibited successful/unsuccessful trials followed by decreasing PPR <30% within 12 months (no effect group). Pain relief for more than 12 months was achieved in eight out of 18 (44.4%) patients during the 67.3 ± 35.5 month follow-up period. Statistically significant differences were found for both the age and stroke location during comparisons of the preoperative characteristics between the two groups. There was a significantly younger mean age for the effect versus the no effect group. Patients with stoke in non-thalamus were significantly enriched in effect group compared with those with stoke in thalamus. Multivariable analysis using these two factors found no statistical differences, suggesting that these two factors might possibly exhibit the same behaviors for the SCS effect. These results suggest that SCS may be able to provide pain relief in young, non-thalamus stroke patients with CPSP.
2 0 0 0 OA 2.高齢者の手足しびれ感の診断のポイント
- 著者
- 吉村 道由 荒田 仁 出口 尚寿 髙嶋 博
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.103, no.8, pp.1876-1884, 2014-08-10 (Released:2015-08-10)
- 参考文献数
- 5
しびれは個々でその定義が異なり,鑑別も非常に多い.高齢者においては,年齢に伴う動脈硬化性変化や骨性変化によりきたす疾患も多くみられる.診断をするにあたっては既往症や基礎疾患などの背景と伴に,発症様式,性状,部位なども重要となる.しびれのメカニズムを述べるとともに,末梢性,中枢性,部位別に分類してそれぞれの代表的な疾患の特徴や,診断をすすめるうえでの検査について述べる.
2 0 0 0 OA 事実認定の論理に関する一考察
- 著者
- 小林 公
- 出版者
- 日本法哲学会
- 雑誌
- 法哲学年報 (ISSN:03872890)
- 巻号頁・発行日
- vol.1974, pp.103-135, 1975-10-30 (Released:2008-11-17)
- 参考文献数
- 54
2 0 0 0 OA アイシングによる遅発性筋痛の軽減効果 ―無作為化比較対照試験による検討―
- 著者
- 甲斐 太陽 永井 宏達 阪本 昌志 山本 愛 山本 ちさと 白岩 加代子 宮﨑 純弥
- 出版者
- 公益社団法人 日本理学療法士協会
- 雑誌
- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)
- 巻号頁・発行日
- pp.0792, 2014 (Released:2014-05-09)
【はじめに,目的】運動場面におけるアイシングを用いた寒冷療法は,これまで広く行われており,運動後の疼痛の制御や,疲労の軽減,その他急性外傷による炎症や腫脹の軽減などが目的となっている。運動後のアイシングについては,オーバーユーズによる急性炎症反応の抑制や,組織治癒の際に伴う熱,発赤などを減少させる効果が確認されている。具体例としては,投球後の投手が肩をアイシングすることがあげられる。一方で,筋力トレーニング実施後に生じる副次的作用として遅発性筋痛があるが,トレーニングした筋そのものに対してのアイシングは,その効果に関する報告が少なく,また統一した見解が得ているわけではない。アイシングによる遅発性筋痛への影響を明らかにすることは,運動療法を効率よく行う上でも重要な知見となる。本研究では,アイシングによる寒冷療法は,遅発性筋痛の軽減に関与するのかを検証することを目的とした。【方法】対象は健常若年者29名(男14名,女15名18.6±0.9歳)とした。層化ブロックランダム割り付けにより,対象者を介入群14名,対照群15名に分類した。研究デザインは無作為化比較対照試験とし,両群に対して遅発性筋痛が生じうる負荷を加えた後に,介入群にのみアイシングを施行した。対象者の非利き手側の上腕二頭筋に遅発性筋痛を生じさせるため,ダンベル(男性5kg,女性3kg)を用いた肘関節屈曲運動を動作が継続できなくなるまで実施した。運動速度は屈伸運動が4秒に1回のペースになるように行い,メトロノームを用いて統制した。運動中止の判断は,肘関節屈曲角度が90°未満なる施行が2回連続で生じた時点とした。3分間の休憩の後,再度同様の運動を実施し,この過程を3セット繰りかえした。その後,介入群には軽度肘関節屈曲位で上腕二頭筋に氷嚢を用いてアイシングを20分間実施した。対照群には,介入群と同様の姿勢で20分間安静をとるよう指示した。評価項目はMMT(Manual Muscle Test)3レベル運動時のVAS(Visual Analog Scale),および上腕二頭筋の圧痛を評価した。圧痛の評価には徒手筋力計(μ-tas)を使用した。圧痛の測定部位は肩峰と肘窩を結んだ線の遠位3分の1を基準とし,徒手筋力計を介して上腕二頭筋に検者が圧追を加え,対象者が痛みを感じた時の数値を測定,記録した。VASは介入群,対照群ともに課題前,課題直後,アイシング直後,その後一週間毎日各個人で評価した。圧痛は課題前,課題直後,アイシング直後,実験一日後,二日後,五日後,六日後,七日後に評価した。圧痛の評価は同一の検者が実施し,評価は同一時間帯に行った。実験期間中は介入群,対照群ともに筋力トレーニング等を行わず,通常通りの生活を送るよう指導した。統計解析には,VAS,圧痛に関して,群,時間を要因とした分割プロットデザイン分散解析を用いた。交互作用のみられた項目については事後検定を行った。なお,圧痛の評価は,級内相関係数(ICC)を算出し信頼性の評価を検討した。【倫理的配慮,説明と同意】本研究はヘルシンキ宣言に沿って,対象者には研究の内容,身体に関わる影響を紙面上にて説明した上,書面にて同意を得た。【結果】今回の研究では,最終評価まで脱落者はおらず,全参加者が解析対象となった。圧痛検査のICC(1,1)は0.83であり,良好な信頼性を有していた。VASに関しては,介入群において,疼痛が有意に抑制されていた(交互作用:p<0.05)。VASにおける群間の差が最も大きかったのは,トレーニング三日後であり,介入群4.8±3.1cm,対照群6.8±1.7cmであった。圧痛に関しては,有意ではないものの中程度の効果量がみられた(交互作用:p<0.088,偏η2=0.07)。圧痛における群間の差が最も大きかったのはトレーニング二日後であり,介入群76±55N,対照群39±28Nであった。【考察】本研究の結果,筋力トレーニング後にアイシングを用いることによって,その後の遅発性筋痛の抑制に影響を与えることが明らかになった。遅発性筋痛が生じる原因としては,筋原線維の配列の乱れや筋疲労によって毛細血管拡張が生じることによる細胞間隙の浮腫および炎症反応などが述べられている。一方,アイシングの効果としては血管が収縮され血流量が減少し,炎症反応を抑えることができるとされている。今回の遅発性筋痛の抑制には,アイシングにより血流量が減少され,浮腫が軽減されたことが関与している可能性が考えられた。【理学療法学研究としての意義】運動療法後のアイシングにより遅発性筋痛を抑制することができれば,その後のパフォーマンス低下の予防や,よりスムーズなリハビリテーション介入につながる可能性がある。今後,これらの関係性を明らかにしていくことで,理学療法研究としての意義がさらに高くなると考える。