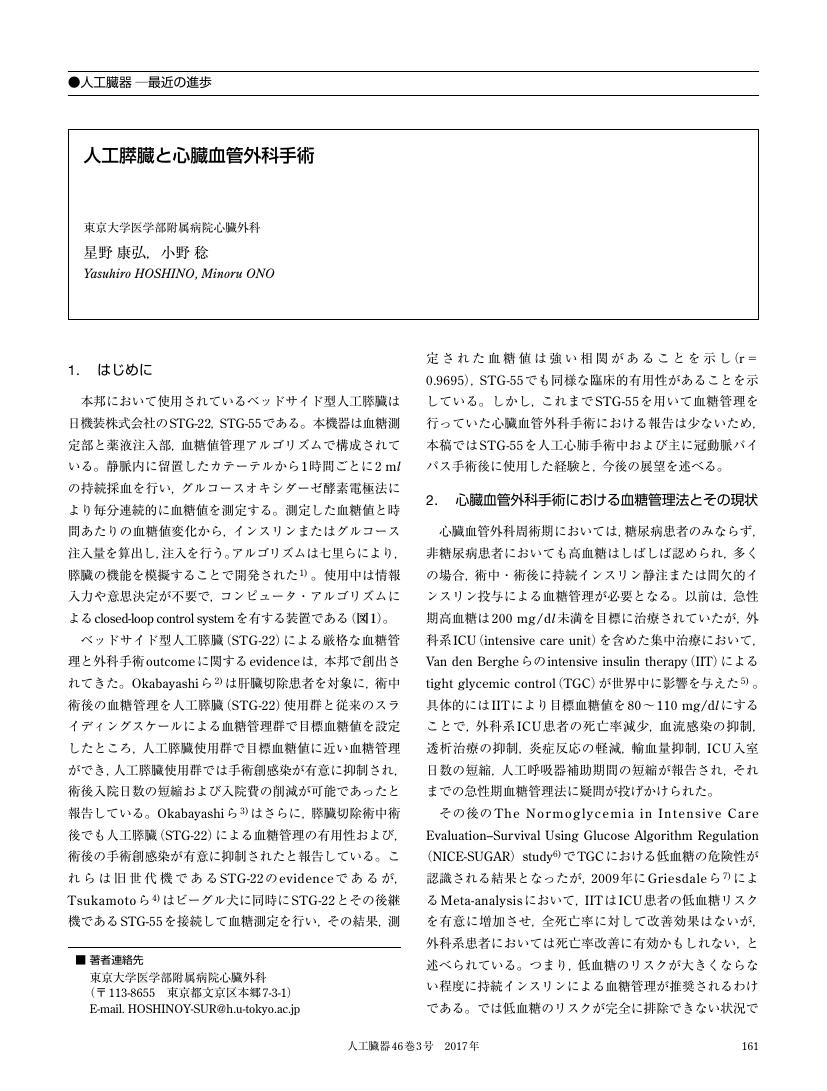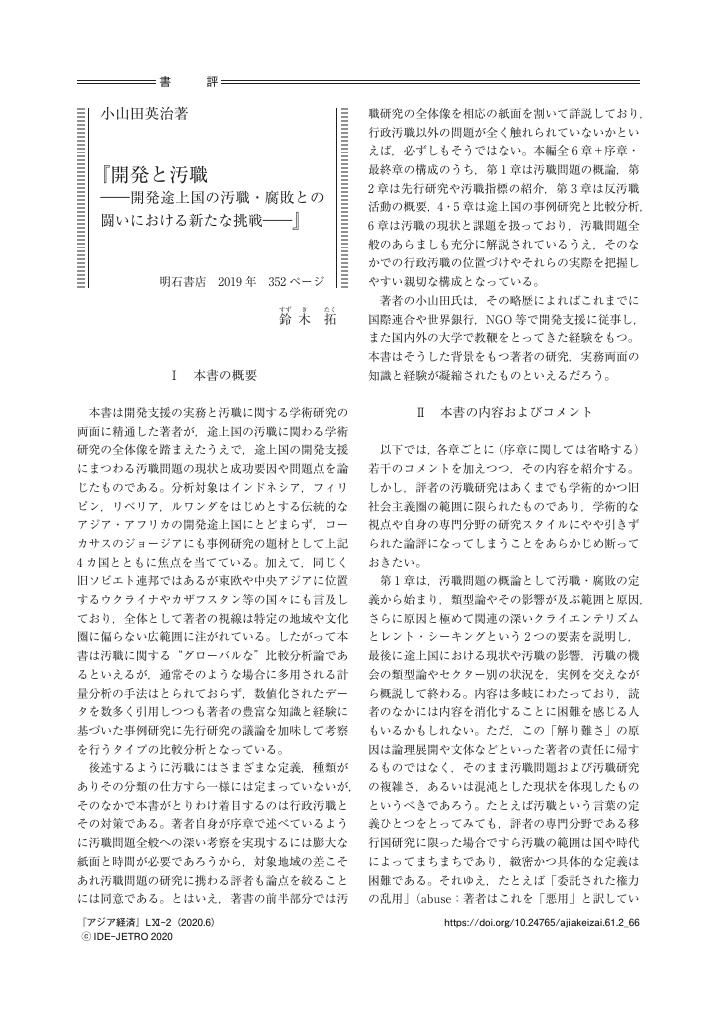- 著者
- 小野 英哲 吉岡 丹
- 出版者
- 一般社団法人 日本建築学会
- 雑誌
- 日本建築学会論文報告集 (ISSN:03871185)
- 巻号頁・発行日
- vol.188, pp.1-10,115, 1971-10-30 (Released:2017-08-22)
- 被引用文献数
- 1 1
The pupose of this paper is to relate the athlete's sense on resilieucy to factors being extracted from measuring the resibiency. The result are obtained from the inquiry about the athlete's sense on resiliency as follows. ・Almost athletes are sensible the difference of resiliency. ・We could extract several gymnasiums which was typical type of resiliency. The results are obtained from the experiment of measuring resiliency with the apparatus being planned and manufactured by way of trial as follows. ・We could obtain dyynanic load-deflection courves of gymnasium floor. ・The relation of gymnasium floor's deflection energy and athlete's sense on resiliency is very intimate. ・The efficiency of vibration damping and the stability of the floor's deflection have influence upon the athlete's sense on resiliency.
2 0 0 0 OA 繊毛運動の機構とその制御
- 著者
- 村上 彰
- 出版者
- 耳鼻と臨床会
- 雑誌
- 耳鼻と臨床 (ISSN:04477227)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.2Supplement4, pp.555-562, 1979-05-20 (Released:2013-05-10)
- 参考文献数
- 6
- 著者
- 塩野 宏之 齋藤 寛 今野 陽一 熊谷 勝巳 永田 修
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.87, no.2, pp.101-109, 2016-04-05 (Released:2017-06-17)
- 参考文献数
- 33
- 被引用文献数
- 4
In cold regions of Japan, rice straw residues cut and scattered in late autumn are often incorporated into paddy soils the next spring. Generally, emissions of methane (CH4) from such paddy fields are very high owing to rapid anaerobic decomposition of the straw under flooding. We investigated the effects of incorporating straw by shallow tillage in autumn to decompose under aerobic conditions for reducing emissions of the greenhouse gases CH4 and nitrous oxide (N2O). Three plots were prepared: shallow tillage in autumn by plowing at 5–8 cm depth (STA), conventional tillage in autumn by plowing at 18–20 cm depth (CTA), and conventional tillage in the next spring by plowing at 18–20 cm depth (CTS). The study was conducted from 2010 to 2013. In the STA and CTA plots, the straw was incorporated in October, and the plots were plowed the next April. In the CTS plot, the straw was incorporated at plowing in April. All plots were irrigated and rice seedlings were transplanted in late May. CH4 and N2O fluxes were measured by the closed chamber method throughout the cropping period. Tiller number, grain yield, and brown rice quality were also measured. The cumulative CH4 emissions increased in the order of STA (19.9–85.6 g CH4 m-2) < CTA (24.8–107.6 g CH4 m-2) < CTS (45.6–134.1 g CH4 m-2). N2O emissions in all plots were negligible. Tiller number was higher in the STA plot than in the other plots. There were no significant differences in grain yield or brown rice quality. From the time of snowmelt in March to plowing in April, the soil moisture and the concentration of ferrous iron (Fe2+) in soil were lower in the STA plot than in the CTA plot. Consequently, shallow tillage in autumn by plowing at 5–8 cm was the most effective technique for reducing emissions of greenhouse gases from paddy fields with incorporated rice straw in a cold region of Japan.
- 著者
- Yabin Guan Peng Qu Shugang Lu M. James C. Crabbe Ticao Zhang Yupeng Geng
- 出版者
- The Genetics Society of Japan
- 雑誌
- Genes & Genetic Systems (ISSN:13417568)
- 巻号頁・発行日
- pp.20-00025, (Released:2020-11-11)
- 参考文献数
- 61
- 被引用文献数
- 4
Thlaspi arvense (field pennycress) is widespread in temperate regions of the northern hemisphere. We estimated the genetic and epigenetic structure of eight T. arvense populations (131 individuals) in China using amplified fragment length polymorphism and methylation-sensitive amplified polymorphism molecular-marker techniques. We detected low diversity at both genetic (mean = 0.03; total = 0.07) and epigenetic (mean = 0.04; total = 0.07) levels, while significant genetic (FST = 0.42, P < 0.001) and epigenetic (FST = 0.32, P < 0.001) divergence was found across the distribution range. Using Mantel testing, we found spatial genetic and epigenetic differentiation, consistent with isolation-by-distance models. We also identified a strong correlation between genetic and epigenetic differentiation (r = 0.7438, P < 0.001), suggesting genetic control of the epigenetic variation. Our results indicate that mating system, natural selection and gene flow events jointly structure spatial patterns of genetic and epigenetic variation. Moreover, epigenetic variation may serve as a basis of natural selection and ecological evolution to enable species to adapt to heterogeneous habitats. Our study provides novel clues for the adaptation of T. arvense.
2 0 0 0 OA 陳述記憶における再固定化過程
2 0 0 0 OA 日本産コガネグモダマシ属のクモ類
- 著者
- 谷川 明男
- 出版者
- Arachnological Society of Japan
- 雑誌
- Acta Arachnologica (ISSN:00015202)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.31-47, 1989 (Released:2007-03-29)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 7 9
現在まで, 日本産の Larinia 属としては, コガネグモダマシ L. argiopiformis BÖSENBERG et STRAND のみが知られていたが, 新たにネッタイコガネグモダマシ (新称) L. fusiformis (THORELL), ミナミコガネグモダマシ (新称) L. phthisica (L.KOCH), キタコガネグモダマシ (新称) L. jeskovi MARUSIK の3種の分布を確認し, ムネグロコガネグモダマシ (新称) L. onoi とセキグチコガネグモダマシ (新称) L. sekiguchii の2新種を記載した。これにより日本産の Larinia 属は6種となった。
2 0 0 0 OA 心的現実と想像界をめぐって : 世界空間論への歩み
- 著者
- 菅原 浩
- 出版者
- 人体科学会
- 雑誌
- 人体科学 (ISSN:09182489)
- 巻号頁・発行日
- vol.10, no.2, pp.1-10, 2001-10-31 (Released:2018-03-01)
2 0 0 0 OA 産後女性の身体症状─育児中の女性に対するアンケート調査より─
- 著者
- 永見 倫子
- 出版者
- 日本保健科学学会
- 雑誌
- 日本保健科学学会誌 (ISSN:18800211)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.1, pp.16-21, 2019 (Released:2019-12-25)
- 参考文献数
- 9
3 歳以下の乳幼児を育児中の女性115 名に対しアンケート調査を行い,産後,特に 産褥期以降の乳幼児の育児にあたる時期の不調・疼痛の実態把握を目的に調査を行った. 産後の疼痛は腰部71.3%で最も多かった.また頸部38.3%,肩56.5%,手首31.3%など では妊娠中と比較し有意に増加していた(P < 0.01).最も疼痛の強い時期は子の定頚前 33.0%が最多で,疼痛の出る動作は抱っこや授乳など育児関連の動作が選択された.産後 の身体のケアについての指導は産科で行われることが多く,理学療法士の介入は0%だっ た.一方,正しい身体の使い方や疼痛予防のための運動指導などの希望は多かった. 産褥期のみならず育児期にかけて多くの女性が疼痛に悩まされていること,介入や対策 は不十分であることが明らかとなった.疼痛は特に乳児を支える時期や動作で多く,育児 の負荷が原因である可能性が高い.疼痛予防のための運動指導や育児の動作指導など,理 学療法士介入の必要性が示唆された.
2 0 0 0 OA 人工膵臓と心臓血管外科手術
- 著者
- 星野 康弘 小野 稔
- 出版者
- 一般社団法人 日本人工臓器学会
- 雑誌
- 人工臓器 (ISSN:03000818)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.161-163, 2017-12-15 (Released:2018-03-15)
- 参考文献数
- 14
2 0 0 0 OA 16 計算機シミュレーションによる放射線生物作用の初期過程の研究
- 著者
- 渡邊 立子 甲斐 健師 服部 佑哉
- 出版者
- 公益社団法人 日本アイソトープ協会
- 雑誌
- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)
- 巻号頁・発行日
- vol.66, no.11, pp.525-530, 2017-11-15 (Released:2017-11-15)
- 参考文献数
- 9
放射線による生物影響のメカニズムの解明には,モデルやシミュレーションを用いた研究は重要な役割を持つ。特に,メカニズムに関する仮定や生体の異なるレベルで得られた実験データの間の関係を評価するためにはシミュレーションは有効な手段である。本稿では,DNAと細胞への放射線影響のシミュレーションによる研究の概要について述べる。この中で,DNA損傷生成に関わる物理化学過程の詳細を推定する理論的アプローチと,DNA損傷と細胞応答のダイナミクスを推定する数理モデルも紹介する。
2 0 0 0 OA デジタル時代の新聞社 読者を知り,自らを変える
- 著者
- 藤谷 健
- 出版者
- 日本マス・コミュニケーション学会
- 雑誌
- マス・コミュニケーション研究 (ISSN:13411306)
- 巻号頁・発行日
- vol.96, pp.47-60, 2020-01-31 (Released:2020-06-17)
- 参考文献数
- 1
Recent years have seen the emergence and continued evolution of anunprecedented landscape of digital media products and platforms, mobiledevices, and distribution and consumption patterns. Triggered and acceleratedby digital innovation, these changes have given rise to new challenges for legacy media organizations, such as newspaper publishers. A transformation of thenewsroom has been underway in major publishers around the world. The AsahiShimbun, the second largest national daily in Japan, is no exception. This paperis in the process of transforming itself into an integrated news organization( i.e.,one that publishes in both digital and print formats). Reporters and editors areexpected to adapt their mindset and workflow and adopt new skills and roles inline with audience-first journalism. Given this, we have set three goals: ⑴ toserve targeted audiences with targeted content; ⑵ to publish on the platformsused by the target audience; and ⑶ to produce and publish continuously tomeet audience needs. This requires a deeper, broader understanding of the targetaudience, so the paper has developed Hotaru, a new editorial analytics dashboardfor the newsroom in 2016. An abbreviation of “in-HOuse Tool for Analyzingand Reporting Users’ Activities,” Hotaru provides reporters and editorswith access to a rich source of real-time data, thereby helping them to developa better understanding of the impact of stories and the importance of audienceengagement. This new habit of looking at data is clearly helping to encourageeditorial experiments in the newsroom. For instance, if journalists want toreach out to mothers for stories on parenting, they can strategically use LINE,a messaging app that is popular among mothers. In this case, such stories areshared and spread effectively through the mothers’ networks. In another successfulcase, a reporter can, based on single coverage, file two types of storiesto meet the needs of two different target audience groups.
2 0 0 0 OA 気柱を伝わる音速の温度変化
- 著者
- 恵下 斂 川北 一彦
- 出版者
- 日本物理教育学会
- 雑誌
- 物理教育 (ISSN:03856992)
- 巻号頁・発行日
- vol.41, no.1, pp.9-11, 1993-03-01 (Released:2017-02-10)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
高校物理あるいは大学の基礎課程の教材として活用することを目的として,気柱を伝わる音速の温度変化を測定するシステムを組み立てた。温度を変えながら,気柱の共鳴を利用して音速を測り,大気中を伝わる音速の理論式と比較した。その結果,温度範囲をあまり広くとらないかぎり,気柱を伝わる音速は理論式と比べてわずかに小さく,温度が高くなるにしたがってその差が大きくなることがわかった。
2 0 0 0 OA 7-メトキシセファロスポリンの合成とその応用
- 著者
- 中尾 英雄 柳沢 宏明 杉村 征夫 平岡 哲夫
- 出版者
- The Society of Synthetic Organic Chemistry, Japan
- 雑誌
- 有機合成化学協会誌 (ISSN:00379980)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.7, pp.563-574, 1977-07-01 (Released:2009-11-13)
- 参考文献数
- 36
Synthetic studies on 7-methoxycephalosporins are reviewed under the following subjects : 1. synthesis of cephamycin derivatives 2. chemical methoxylation a) direct methods b) indirect methods 3. author's work a) synthesis by oxidation of novel Schiff bases b) synthesis from 7-haloacetamidocephalosporins 4. synthesis of new antibacterial derivatives.
2 0 0 0 OA 片脚着地動作時の足部運動と膝関節外反運動の関係
- 著者
- 木下 恵美 浦辺 幸夫 前田 慶明 藤井 絵里 笹代 純平 岩田 昌 河原 大陸 沼野 崇平
- 出版者
- 理学療法科学学会
- 雑誌
- 理学療法科学 (ISSN:13411667)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.2, pp.227-231, 2016 (Released:2016-04-29)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 2
〔目的〕本研究の目的は,片脚着地動作時の前・後足部運動と膝関節外反運動の関係を明らかにすることである.〔対象〕対象は健常成人女性13名とした.〔方法〕課題動作は高さ30 cm台からの非利き脚での片脚着地動作とし,台より30cm前方に着地させ,片脚立位を保持させた.課題動作中の膝関節外反角度,前足部回内角度,後足部外反角度,アーチ高を算出し,膝関節外反角度と各足部角度,アーチ高との相関関係を調べた.〔結果〕片脚着地動作時の前足部回内運動と膝関節外反運動に有意な相関関係は認められなかった.一方,後足部外反運動と膝関節外反運動には有意な正の相関が認められた.〔結語〕片脚着地動作での膝関節外反運動を予防するためには,後足部外反運動を少なくすることが重要であることが示唆された.
2 0 0 0 OA 薬学基礎教育を考える:生化学教育に携わった老教師の思い
- 著者
- 後藤 佐多良
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.140, no.3, pp.407-410, 2020-03-01 (Released:2020-03-01)
- 参考文献数
- 6
As a teacher of biochemistry in a school of pharmacy, a basic subject in pharmacist education, I try to include applied topics such as the biochemical mechanisms of diseases and side effects of medicines in relation to basic knowledge of biochemistry for advanced subjects that students will learn in later years. In aging societies, many people visiting community pharmacies are elderly who tend to have health concerns other than diseases diagnosed by physicians. If asked, community pharmacists should be able to give advice on potential problems patients might have, in addition to giving explanations of medicines prescribed. Basic subjects covered in university pharmacy courses should be the most useful in such community settings.
2 0 0 0 OA 根管充填後のコロナルリーケージ〜歯内療法と歯冠修復との密接な関係〜
- 著者
- 木ノ本 喜史
- 出版者
- 公益社団法人 日本補綴歯科学会
- 雑誌
- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.2, pp.126-131, 2017 (Released:2017-05-30)
- 参考文献数
- 19
良好な根管充填が完了した歯であっても歯冠側から根管内に漏洩が生じると,修復前には認めなかった根尖性歯周炎が発症する.この現象はコロナルリーケージと呼ばれており,修復の再治療が必要となる原因の一つである.最終修復までの仮封の期間や支台築造装着までの根管の汚染,修復後の二次う蝕等がコロナルリーケージに影響を及ぼす.根管充填がしっかり達成されていれば,根尖へ感染は波及しないわけではなく,修復後にも根尖に感染が生じる可能性がある.歯内療法においては当然のことであるが,修復処置においても根管の感染を意識した処置が必須である.
- 著者
- 実重 真吾 片山 茂裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.7, pp.548-554, 1997-07-25 (Released:2009-11-24)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
インスリン及びIGF-1の培養血管平滑筋細胞 (以下VSMCと略) に対する増殖効果及び細胞外基質のコラーゲン合成能とI型コラーゲンα1鎖の遺伝子発現に及ぼす影響を検討した. ブタの腹部大動脈より採取したVSMCに, インスリンを0, 16, 160nM, IGF-1を0, 1.31, 13.1nMの濃度で添加し, 細胞数・DNA合成能 ([3H]-thymidine) を, またインスリン0, 1,600, 16,000nMを加えて, 蛋白合成能 ([3H]-proline)・総コラーゲン蛋白合成能を調べた結果, 細胞数は1.4倍 (IGF-1) ~1.5倍 (インスリン) に, DNA合成能は3倍 (IGF-1) ~3.8倍 (インスリン) に, 蛋白合成能は1.8倍 (IGF-1) ~3倍 (インスリン) に濃度依存性に有意に増加した. 総コラーゲン蛋白合成は, インスリン16,000nM, IGF-113.1nMの濃度で, それぞれ26.5倍, 2.3倍に増加した. I型コラーゲンα1鎖mRNAは, IGF-1では濃度依存性に増大し, インスリンではIGF-1と比較して弱いが, 増大傾向を認めた. 以上, インスリンやIGF-1が, VSMCの増殖の情報伝達及び細胞外マトリックスの合成に密接に関連している可能性が示唆された.
2 0 0 0 OA 着色と変形を伴う弥生前期人の頭蓋
- 著者
- 金関 丈夫 小片 丘彦
- 出版者
- The Anthropological Society of Nippon
- 雑誌
- 人類學雜誌 (ISSN:00035505)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.3-4, pp.177-182, 1962-03-30 (Released:2008-02-26)
- 参考文献数
- 10
- 被引用文献数
- 1
A description and a discussion are given by the authors on a round shaped greenish coloring, seemingly caused by a decorative bronze disc on the squamal surface in the supraglabellar region of a male human skull from the Koura-site of the Earlier Yayoi-period together with an unnatural flatness of the bone surface in the supraasterional region on both sides of the same skull. According to the authors, these seem to have been caused by an incessant use, from an early age onward, of a headband with a copper disc fastened to it in front. This, being an unique instance among the Koura skulls, appears to indicate that the individual in question might have been of a special duty, presumably of a religious one.
2 0 0 0 OA 種々の堆肥中における大腸菌群等の生残
- 著者
- 〓 春明 越田 淳一 森山 典子 王 暁丹 有働 武三 井上 興一 染谷 孝
- 出版者
- 一般社団法人 日本土壌肥料学会
- 雑誌
- 日本土壌肥料学雑誌 (ISSN:00290610)
- 巻号頁・発行日
- vol.76, no.6, pp.865-874, 2005-12-05 (Released:2017-06-28)
- 参考文献数
- 34
- 被引用文献数
- 3
九州各地の堆肥化施設23カ所から,牛糞,鶏糞,生ゴミおよび下水汚泥を原料とした堆肥計29点を採取し,糞便汚染指標菌(大腸菌群,大腸菌およびサルモネラ菌)について培養検査した。1)これら堆肥試料のCECは31.4〜79.0cmol_ckg^<-1>の範囲(平均55.4cmol_ckg^<-1>)で,炭素率(C/N比)は7.6〜25.4の範囲(平均15.3)にあり,他の性状と合わせ,多くが完熟堆肥であると判断された。2)デスオキシコーレイト寒天培地により大腸菌群が29点中11点(38%)から検出され10^2〜10^6cfug^<-1> dry matterの菌数レベルであった。大腸菌群陽性堆肥試料4点のうち3点からの分離株は,大腸菌群に属するE. coli, E. vulneris, Pantoea sp., Buttiauxella agrestisと同定された。しかし,Serratia marcescensのみが分離された試料が1点,本菌とE. coliが分離された試料が1点あった。大腸菌群には属さない腸内細菌科の細菌であるS. marcescensは赤色色素を生産するため,分離培地上で大腸菌群の赤いコロニーと誤認されたものと推察された。一方,得られたE. coli5株は,病原大腸菌免疫血清試験ですべて陰性であった。3)堆肥試料12点についてクロモカルト・コリフォーム培地による大腸菌の直接培養検査およびMLCB寒天培地によるサルモネラ菌の検出を試みた結果,大腸菌はいずれの試料からも検出されず,サルモネラ菌は2点(17%)から検出され,その菌数は10^3cfug^<-1> dry matterのレベルにあった。4)堆肥原料(牛糞,鶏糞,生ゴミ等)8点のうち大腸菌群およびサルモネラ菌がいずれも6点(75%)から,大腸菌が5点(63%)から検出され,菌数はいずれも10^2〜10^8cfug^<-1> dry matterであった。5)堆肥製造施設6カ所における堆肥化過程での糞便汚染指標菌の消長を7例について追跡した結果,糞便汚染指標菌が減少して製品中で消失する場合,いったん消失するが製品で再度検出される場合,全く消失しない場合,原料から製品まで検出されない場合の4通りが観察された。発酵温度が高くてもサルモネラ菌などが生残する場合があり,その原因について,再増殖や交叉汚染の可能性を考察した。6)上記の諸結果に基づき,堆肥の製造過程における温度管理や交叉汚染防止などの適切な衛生管理の重要性を指摘した。
- 著者
- 鈴木 拓
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- アジア経済 (ISSN:00022942)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.66-69, 2020-06-15 (Released:2020-07-01)
- 参考文献数
- 1