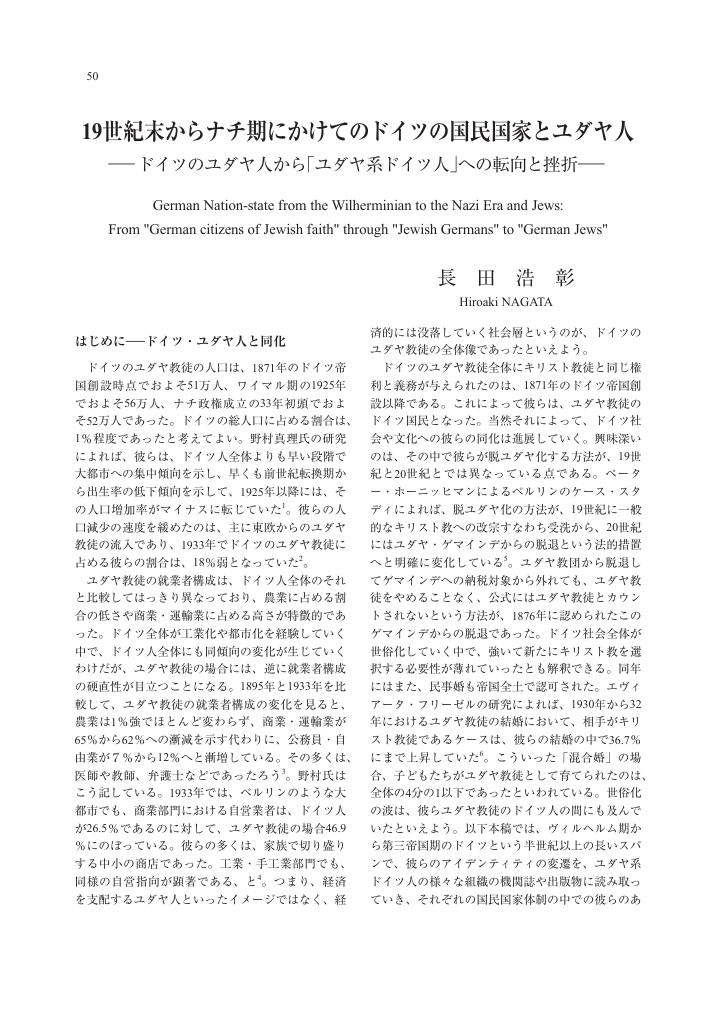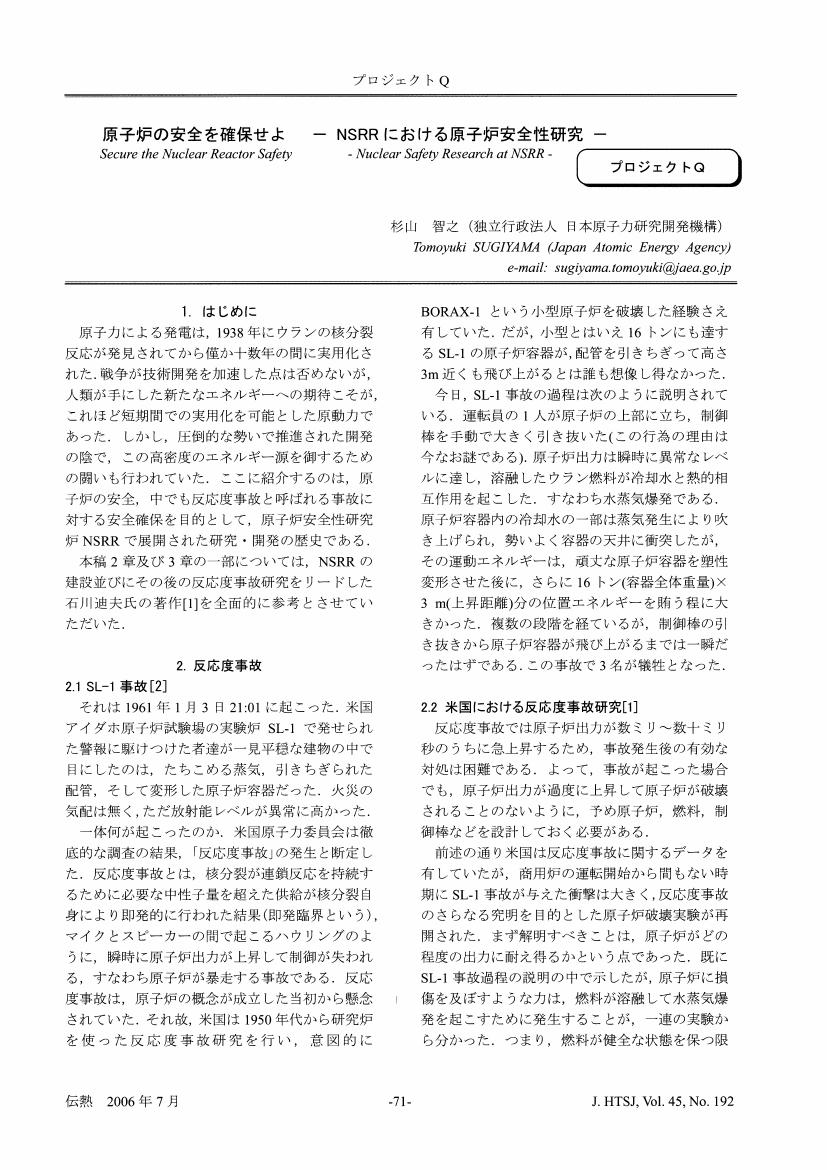- 著者
- 神谷 哲司
- 出版者
- 一般社団法人 日本発達心理学会
- 雑誌
- 発達心理学研究 (ISSN:09159029)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.3, pp.238-249, 2013 (Released:2015-09-21)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 4
本研究は育児期夫婦における家庭内の役割に着目し,その類型化を元に,家庭内役割観が相互に調整されていない(異なる)夫婦の関係性を明らかにすることを目的とした。具体的には,「相手にとっての自分の役割」と「自分にとっての相手の役割」という夫婦双方の家族成員としての役割観に基づき夫婦をペアとした家庭内役割観タイプを抽出し,夫婦関係満足度や情緒的なかかわりとの関連を検討した。質問紙による183組の夫婦のペアデータが分析された結果,家庭内役割観タイプとして,夫婦双方ともにすべての役割を重要であると認識する相互役割高群,反対に重要ではないとする相互役割低群と,役割観が異なるタイプとして,妻が夫を重要だと認識する一方で夫は自分もパートナーも重要でないと認識する視点格差群が抽出された。この視点格差群は相互役割高群と同様,妻の夫婦関係満足が高く,また情緒的なかかわりが夫婦ともに相互役割低群よりも高かった。これらの結果から,視点格差群について先行研究との関連で討議され,家庭内役割観のギャップを夫からの情緒的なかかわりによって補償している可能性が示唆された。
4 0 0 0 OA 寒冷期の避難生活を想定した就寝資材の検討
- 著者
- 根本 昌宏
- 出版者
- 日本衣服学会
- 雑誌
- 日本衣服学会誌 (ISSN:09105778)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, no.2, pp.59-63, 2021 (Released:2023-12-12)
- 参考文献数
- 7
- 著者
- 伊地知 紀子
- 出版者
- 日本オーラル・ヒストリー学会
- 雑誌
- 日本オーラル・ヒストリー研究 (ISSN:18823033)
- 巻号頁・発行日
- vol.2, pp.40-51, 2006-09-23 (Released:2018-12-10)
So many Korean people live in Osaka and most of the people have been from Jeju Island. Because the liner route was established between Osaka and Jeju in 1920's, a lot of Jeju people have been to Osaka to get their daily bread. Though a lot of people returned to Jeju before and after liberating from the colonization, not a few people have gone to Japan again to avoid the political turmoil due to Jeju 4.3 affair afterwards. The existent research is not necessarily much accumulated about lives of Korean people in this period. So we considered reconstructing the present age life-size history of the East Asia by oral history of the Jeju people in Japan.
4 0 0 0 OA 郵政省における為替貯金業務のオンライン概要
- 著者
- 川添 隆公
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.22, no.3, pp.200-210, 1979-06-01 (Released:2016-03-16)
郵政省における為替貯金業務のオンライン化についてその経緯と現状を紹介するとともに,システムの概要を解説した。本システムは,全国約2万の郵便局と計算センタ(9か所)を特定通信回線でオンライン・ネットワークを構成する一方,各計算センタ相互のセンタ間処理を可能とするために,東京計算センタ内に交換設備を設置し,交換機能を持たせた,他に類例のない大規模なオンライン・バンキングシステムである。また,後方処理として地方貯金局に事務センタを設置し,オフ扱処理,計数確査,事故処理等の関連事務処理を行っている。
4 0 0 0 韓国勒島出土人骨に関する形質人類学的研究
現在まで、韓国の古人骨研究でまとまったものは、日本の古墳時代初期に相当する礼安里人骨の報告があるのみと言って良いだろう。しかし、礼安里人骨は個体数こそ70個体を数えるが、保存状態が良好なものはごくわずかであった。しかし、平成16年度から調査研究を行った勒島人骨は、礼安里人骨の時代をさかのぼること約400年。日本の弥生時代の中期初頭に相当し、しかも極めて保存状態が良好な個体が数多くある人骨群であった。また、当時の韓国にどのような疾病が存在したかと言う観点での研究は、現在まで全くなされていない。結核の起源など、渡来人によって日本に持ちこまれた疾病を解き明かすことは、昨今の古病理学の大きな課題であり、日本、韓国を始めとする、東アジアの疾病史の研究においても、非常に価値が高いものであった。以上のように、平成16年度より、基盤研究(C)「韓国勒島出土人骨に関する形質人類学的研究」を行い、日本の弥生時代中期相当の、韓国南部の人骨の形質や古病理学的分析を進めてきた。その結果、当時の日本と韓国は、文化的・人的交流が非常に盛んであったことが、明らかとなった。一例を挙げれば、勒島遺跡からは、日本の弥生土器(須玖I式、II式土器など)が多数出土し、恐らくは、日本の土器が搬入されたのではなく、「日本人が移住していた」と考えられる。人骨の形質は、概ね北部九州地方から出土する「渡来系弥生人」に類似するが、男性で変異が大きく、女性で変異が小さいという特徴を持つ。この傾向は、礼安里人骨、土井ヶ浜人骨には共通するが、金隈人骨の女性は変異が大きく、違った傾向を持つ。
4 0 0 0 OA 月経困難症に対する漢方別年齢的解析
- 著者
- 川口 惠子
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.5, pp.869-876, 2000-03-20 (Released:2010-03-12)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
10代から40代までの月経困難症患者 (器質性月経困難症20例, 機能性月経困難症例36例) に対して, 東洋医学的診断に水基づいて決定された漢方エキスを投与し, 効果判定を2ヵ月後に行った。器質性月経困難症例では著効6例, 有効6例, 無効5例, 脱落3例であった。機能性月経困難症例では著効15例, 有効7例, 無効1例, 脱落13例であった。10代, 20代の若年者では器質性よりも機能性月経困難症が多く, 漢方薬を服用し続けた20例中17例に効果がみられた。30代, 40代になるにつれて器質性月経困難症の占める割合が増加したが, 服用し続けた22例中19例に効果がみられた。漢方療法は服用を続ければ器質性機能性いずれの月経困難症に対しても有効な治療法と言えよう。
4 0 0 0 OA 佐賀クリーク網の歴史的変遷と住民意識
- 著者
- 荒木 宏之 古賀 憲一 荒牧 軍治 二渡 了
- 出版者
- Japan Society of Civil Engineers
- 雑誌
- 環境システム研究 (ISSN:09150390)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, pp.32-37, 1990-08-10 (Released:2010-03-17)
- 参考文献数
- 9
The water management systems in channel network in the Saga Plains have a long history. The functions, drainage and irrigation etc., are gradually changing for 400 years with social systems such as modernizing of agriculture and urbanization etc. An integrated water management based on inhabitants' consciousness and water quality is necessary for environmental conservation. For the sake of appropriate environmental conservation of the creeks, 1) historical change of the water management is classified, 2) relationships between the change of water management and social systems are revealed, 3) inhabitants' consciousness is surveyed by the questionnaire. As a result, the change of water management is classified into three processes, that is, the developing process (-1600), the completion process (1600-1940), and the declining process due to water pollution (1940-present). From the result of the questionnaire, important experiences during childhood, such as drinking the water of creeks and swimming, influence inhabitants' consciousness viz, familiarity to the creeks. Especially, the influence appeared strongly on middle-aged inhabitants who were in childhood earlier in the third process. It is necessary to sustain the traditional experiences for conserving the environment.
- 著者
- 長田 浩彰
- 出版者
- 日本ユダヤ学会
- 雑誌
- ユダヤ・イスラエル研究 (ISSN:09162984)
- 巻号頁・発行日
- vol.27, pp.50, 2013 (Released:2020-09-16)
4 0 0 0 OA ユールストロームダイアグラム―流水による砕屑物からなる地層の形成の理解―
- 著者
- 廣木 義久
- 出版者
- 日本地学教育学会
- 雑誌
- 地学教育 (ISSN:00093831)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.3, pp.97-107, 2019-02-28 (Released:2019-11-13)
- 参考文献数
- 42
- 被引用文献数
- 5
流水による砕屑物からなる地層の形成を理解する上で非常に重要なユールストロームダイアグラムを解説した.ユールストロームダイアグラムは今から約80年前の1939年に発表されたダイアグラムであるが,水中における砕屑物の堆積を理解するのに,今でも有効である.このダイアグラムは堆積や侵食が起こるときの流速と堆積物の粒径との関係を示している.地層は流速が変化する中で,異なる粒径の粒子が堆積するために形成される.それぞれの堆積環境は特有の水理学的エネルギーを持っており,その環境の中で,流速変化が特有の範囲で起こるため,特有の粒径からなる地層が形成される.すなわち,粗粒(細粒)の堆積物からなる地層は高い(低い)水理学的エネルギーを持つ堆積環境において堆積される.
4 0 0 0 OA 飯田隆著『言語哲学大全IV:真理と意味』(勁草書房,2002年)
- 著者
- 山田 友幸
- 出版者
- 日本科学哲学会
- 雑誌
- 科学哲学 (ISSN:02893428)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.77-89, 2004-07-25 (Released:2009-05-29)
This book is the last book of Iida's celebrated series, "Summa". It includes a detailed argument for homophonic semantics and an equally detailed exposition of his truth-conditional semantics for three fragments of Japanese, the third of which contains indexical expressions and tensed verbs. As one might expect, the semantics given for this fragment is far from being homophonic. I will examine what role his argument for homophonic semantics plays in his defense of his non-homophonic semantics. I will also examine how Iida avoids treating moods in his semantics, and point out the need to treat illocutionary acts within semantics.
4 0 0 0 OA 共生思想 VS 優生思想 ――共生教育の哲学的基礎のために
- 著者
- 山脇 直司
- 出版者
- 日本共生科学会
- 雑誌
- 共生科学 (ISSN:21851638)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, no.9, pp.76-81, 2018 (Released:2019-06-17)
This article aims at clarifying and enriching the philosophy for inclusive society, opposing eugenic thought, which discriminates human beings by the inequality of ability. For that purpose, I emphasize first the value of fundamental human rights for all people, which Utilitarianism tends to neglect, and second other public values such as cohappiness, compassion and WA that includes the idea of restorative justice.
4 0 0 0 OA 経済学徒としての半世紀 --マクロ経済学・金融理論についての個人的体験--
- 著者
- 髙橋 亘
- 出版者
- 大阪経大学会
- 雑誌
- 大阪経大論集 (ISSN:04747909)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.155-174, 2022-07-15 (Released:2022-08-01)
経済学書に最初に出会ってからいつの間にか50年以上たった。この半世紀,私的体験に過ぎないが,それでも経済学の変遷は著しい。この間,経済学を学び続けてこられたのには,家族や職場のサポートとともに,大学・留学で受けた教育や恩師・先輩・友人に恵まれたこともある。本稿では,退官を契機にケインズ経済学の危機から始まるマクロ経済学の変遷を,私自身が受けた教育などと重ね合わせて,振り返った。
4 0 0 0 OA 永田大輔・松永伸太朗著 『産業変動の労働社会学―アニメーターの経験史』
- 著者
- 阿部 真大
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.73, no.2, pp.188-190, 2022 (Released:2023-09-30)
4 0 0 0 OA 原子炉の安全を確保せよ NSRRにおける原子炉安全性研究
- 著者
- 杉山 智之
- 出版者
- 社団法人 日本伝熱学会
- 雑誌
- 伝熱 (ISSN:13448692)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.192, pp.71-76, 2006 (Released:2010-12-16)
- 参考文献数
- 7
4 0 0 0 OA 軍事作戦とフェミニニティ 第二次世界大戦期イギリスの男女混成防空部隊
- 著者
- 林田 敏子
- 出版者
- 公益財団法人 東海ジェンダー研究所
- 雑誌
- ジェンダー研究 (ISSN:13449419)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, pp.63-81, 2023 (Released:2023-12-08)
4 0 0 0 OA ネオニコチノイド系農薬の環境と食品汚染の現状と課題
- 著者
- 上浦沙友里・伏脇 裕一
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.2, pp.137-144, 2018-04-15 (Released:2018-04-15)
- 参考文献数
- 43
- 被引用文献数
- 1
近年,我が国および欧米諸国において大量に殺虫剤として使用されているネオニコチノイド系農薬について,その種類,生産量,環境汚染および食品汚染例,毒性とヒトおよび生態系に与える影響などについて考察した.特に,世界各地において,ネオニコチノイド系農薬の散布に伴い,ミツバチの大量死とミツバチの減少による農産物への被害が深刻化している現象についても問題点として指摘し,ネオニコチノイド系農薬散布についての課題について言及した.
4 0 0 0 OA タンザニアにおける路上商人の組合化とインフォーマル性の政治 抗争空間論再考
- 著者
- 小川 さやか
- 出版者
- 日本文化人類学会
- 雑誌
- 文化人類学 (ISSN:13490648)
- 巻号頁・発行日
- vol.82, no.2, pp.182-201, 2017 (Released:2018-04-13)
- 参考文献数
- 30
グローバリゼーションや都市の近代化と深く関連したジェントリフィケーションやゲーテッドコミュニティの出現、非-場所的な空間の拡大により、都市公共空間をめぐるアクター間の緊張関係が問われるようになった。これを受けて、路上商人問題を、国家や路上商人、市民社会のあいだで路上という資源をめぐり「働く権利」、「公平な労働のための権利」、「通行/運送の権利」、「移送/賃貸権」、「管理・運営権」など様々な権利の拮抗として位置づけ、路上商人による組合化とそれを通じた集合的行為に注目する研究が台頭している。本稿では、これらの研究が期待するインフォーマルセクターによる組織化とは、既存の都市公共空間の管理運営に迎合的なかたちにインフォーマルセクターの経済実践を埋め込むことを目指すものであることを指摘し、タンザニアの路上商人マチンガによる組合形成の過程および組合運営の特徴を、現実の路上空間とパラレルに存在する「イ フォーマルな政治空間」の拡大としてみる視点を提示することで、路上商人が都市公共空間を管理・統制する国家と取り結び始めた新たな関係をめぐる先行研究の議論を再考する。
- 著者
- 内布 敦子
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, no.9, pp.9_60-9_65, 2014-09-01 (Released:2015-01-02)
- 参考文献数
- 12
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 新型コロナウイルス感染症の小児重症・中等症例発生数と重症小児の診療体制
- 著者
- 日本集中治療医学会小児集中治療委員会日本小児集中治療連絡協議会COVID-19 ワーキンググループ 日本集中治療医学会小児集中治療委員会
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.177-180, 2022-03-01 (Released:2022-03-15)
- 参考文献数
- 11
日本集中治療医学会小児集中治療委員会日本小児集中治療連絡協議会COVID-19ワーキンググループは,新型コロナウイルスの国内流行のいわゆる第5波で,その初期の段階で20 歳未満の患者数が増加していることを把握した。小児科学会との協力体制のもと,小児重症・中等症例発生状況をまとめた。登録症例数は46例。COVID-19肺炎は20例であり,その他の入室理由が過半数を占めた。また,重症症例の診療体制について整理した。
4 0 0 0 OA 非線形力学系のクープマン作用素 —最近の研究から
- 著者
- 薄 良彦
- 出版者
- 一般社団法人 システム制御情報学会
- 雑誌
- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.8, pp.324-329, 2021-08-15 (Released:2022-02-15)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 1