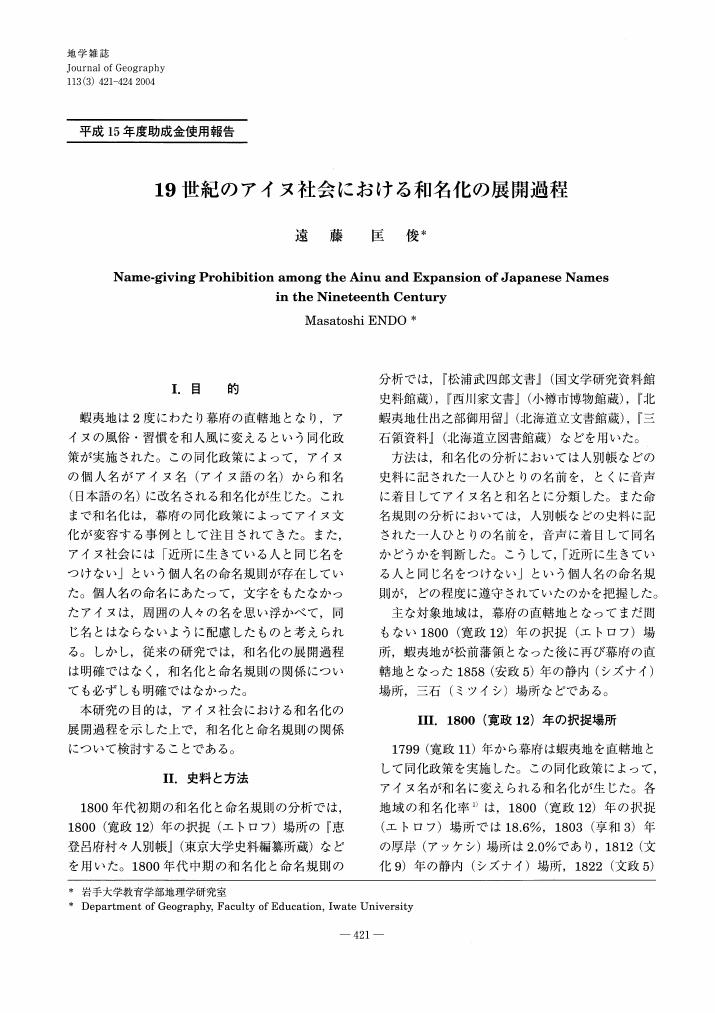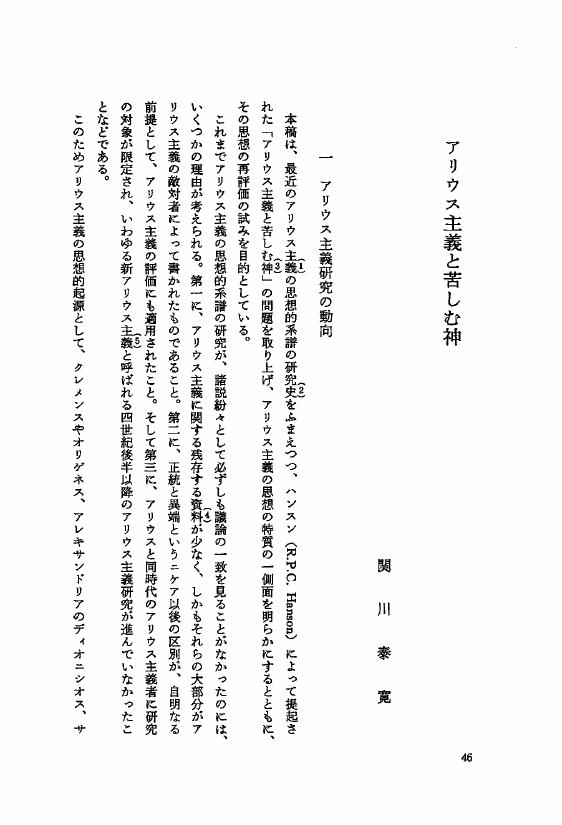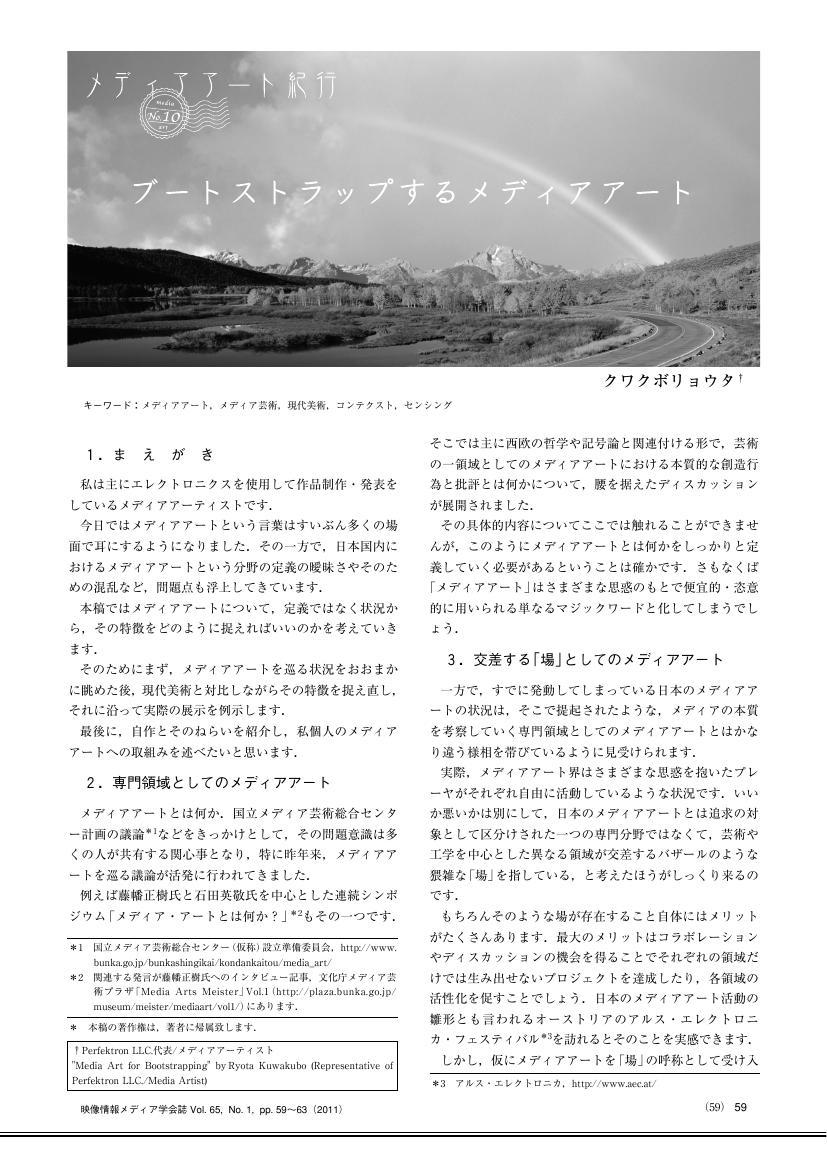4 0 0 0 OA 彰考館旧蔵アイヌ語テキスト「蝦夷チヤランケ並浄瑠理言」について
- 著者
- 佐藤 知己
- 出版者
- 北海道大学文学研究科
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.109, pp.31-58, 2003-02-28
4 0 0 0 OA 口腔がんと細菌・真菌・ウイルス
- 著者
- 中西 康大 田村 優志 高橋 美穂 唐木田 一成 坂本 春生
- 出版者
- 公益財団法人 腸内細菌学会
- 雑誌
- 腸内細菌学雑誌 (ISSN:13430882)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.4, pp.197-208, 2020 (Released:2020-10-26)
- 参考文献数
- 132
口腔内をはじめ,生体内には多くの細菌が存在しており,細菌同士同菌種・異菌種問わず,細菌間コミュニケーションをしている.近年細菌は,生体に様々な影響を与えていることが研究されてきている.胃がんのピロリ菌に代表されるように,細菌が全身の「がん」に関与することが研究されるようになってきた.口腔がんにおいても,細菌の関与について研究されてきている.細菌が「がん」に関与する際は,大きく分けて三つの関与方法があると考えられている.一つ目は,「慢性炎症による刺激」である.慢性炎症による持続的な炎症性メディエーターなどの放出は,細胞増殖や変異誘発,がん遺伝子の活性化などを引き起こす.細胞の増殖に影響するということは,がん細胞の増殖にも影響することを意味する.二つ目は,「アポトーシスの阻害」である.アポトーシスの阻害により,細胞の長期生存が可能になる.三つ目は細菌が「発がん性」物質の産生することによる,直接的ながん化への関与になる.このレビューでは,Fusobacterium nucleatum,Prophyromonas gingivalis,および,そのほかの微生物Candida,virusesが口腔がんにどう影響するかについて概説する.
4 0 0 0 OA 19世紀のアイヌ社会における和名化の展開過程
- 著者
- 遠藤 匡俊
- 出版者
- Tokyo Geographical Society
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.113, no.3, pp.421-424, 2004-04-25 (Released:2009-11-12)
4 0 0 0 OA アリウス主義と苦しむ神
- 著者
- 関川 泰寛
- 出版者
- The Japan Society of Christian Studies
- 雑誌
- 日本の神学 (ISSN:02854848)
- 巻号頁・発行日
- vol.1991, no.30, pp.46-62, 1991-09-05 (Released:2009-10-23)
- 参考文献数
- 47
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA ブートストラップするメディアアート
- 著者
- クワクボ リョウタ
- 出版者
- 一般社団法人 映像情報メディア学会
- 雑誌
- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)
- 巻号頁・発行日
- vol.65, no.1, pp.59-63, 2011 (Released:2013-01-01)
- 参考文献数
- 1
4 0 0 0 OA 宗教多元主義モデルに対する批判的考察 : 「排他主義」と「包括主義」の再考
- 著者
- 小原 克博 Katsuhiro Kohara
- 出版者
- 基督教研究会
- 雑誌
- 基督教研究 = Kirisutokyo Kenkyu (Studies in Christianity) (ISSN:03873080)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.23-44, 2007-12-12
宗教の神学あるいは宗教間対話において広く用いられてきた類型に、排他主義、包括主義、多元主義がある。宗教多元主義の立場からは、しばしば、排他主義や包括主義は克服されるべき前時代的なモデルとして批判されてきた。本稿では、このような宗教多元主義モデルが前提としている進歩史的な価値観を「優越的置換主義」として批判すると共に、その問題は現実の宗教界や政治の世界などにおいても反映されていることを、西洋および日本における事例を通じて考察する。その上で、排他主義や包括主義に分類される宗教や運動の中にも、評価すべき要素があることを指摘する。また、これまでもっぱら西洋の神学サークルの中で議論されてきた多元主義モデルが、非西洋世界において、どのような有効性を持つのかを、イスラームや日本宗教の視点を適宜織り交ぜながら、批判的に検討する。最後に、西洋的価値を中心とする宗教多元主義を積極的に相対化していくためには、宗教の神学と文脈化神学を総合する必要があることを示唆する。
4 0 0 0 OA 意識の神経基盤と複雑性
- 著者
- 小野田 慶一
- 出版者
- 日本生理心理学会
- 雑誌
- 生理心理学と精神生理学 (ISSN:02892405)
- 巻号頁・発行日
- pp.2204si, (Released:2022-08-27)
- 参考文献数
- 136
- 被引用文献数
- 1 1
意識は長らく哲学や心理学において扱われてきたが,近年漸く神経科学の正当な研究対象として扱われるようになってきた。そこでは意識を科学的に扱うための実験的アプローチや情報理論に基づく数理的研究が進展してきた背景がある。本稿では神経科学における意識研究がどのように意識の問題に取り組んできたかを概観する。さらに意識と脳の複雑性の連関を踏まえた上で,統合情報理論に基づき意識の神経基盤を探求した自身の研究を紹介する。
- 著者
- 櫻井 勝康
- 出版者
- 筑波大学
- 雑誌
- 新学術領域研究(研究領域提案型)
- 巻号頁・発行日
- 2019-04-01
目的1. オーガズムを視覚的に捕える-オーガズムの脳内表現 -1-1. Cat-FISHによるオーガズムをコードする神経細胞群の探索1-2. in vivoイメージングによるオーガズムをコードする神経細胞群の神経活動の計測目的2. オーガズムを機能的に捕える-オーガズムのコントロール -2-1. CANEシステムによるオーガズムをコードする神経細胞群の操作
4 0 0 0 OA 転換期にある筑波研究学園都市の地区計画が空間資源継承に果たす役割と課題
- 著者
- 瀬川 遥子 島田 由美子 藤井 さやか
- 出版者
- 公益社団法人 日本都市計画学会
- 雑誌
- 都市計画論文集 (ISSN:09160647)
- 巻号頁・発行日
- vol.58, no.3, pp.1187-1194, 2023-10-25 (Released:2023-10-25)
- 参考文献数
- 20
筑波研究学園都市では、1980年の概成から40年が経ち、国家公務員宿舎の廃止や事業予定地の売却に伴う民間事業者による開発が相次ぎ、住宅地開発が加速している。従前の公務員宿舎地区では、エリア全体に適用される「計画標準」という開発ルールによって、空間デザインの統一や敷地間の連続性が図られ、研究学園都市の空間資源を創出していた。計画標準に代わる誘導策として、2010年より宿舎跡地に「地区計画」が策定されている。本研究ではこの地区計画に着目し、規定内容及び形成された空間の質に対する評価から、地区計画が研究学園都市の空間資源の継承に果たす役割と課題を明らかにすることを目的とする。地区計画作成内容、現地調査、規定項目と実際の開発状況の分析から、現行の地区計画では開発ボリュームの増大はコントロールできていないが、反対に、かきやさくの構成と緑については、一定の誘導効果をあげていることが明らかになった。
4 0 0 0 IR "熱帯"の幻影--林芙美子『浮雲』について--屋久島、仏領インドシナと戦後日本
- 著者
- 牧野 陽子
- 出版者
- 成城大学
- 雑誌
- 成城大学経済研究 (ISSN:03874753)
- 巻号頁・発行日
- no.158, pp.454-431, 2002-11
4 0 0 0 OA 津波に対する島のレンズ効果 その2. 1983年日本海中部地震津波
- 著者
- 阿部 邦昭
- 出版者
- 公益社団法人 日本地震学会
- 雑誌
- 地震 第2輯 (ISSN:00371114)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.1, pp.11-17, 1996-05-24 (Released:2010-03-11)
- 参考文献数
- 8
Focusing effect of islands on the 1983 Nihonkai-chubu (central part of the Japan Sea) earthquake tsunami was identified at eight coasts facing to islands from peak formations of the maximum inundation heights. Defining parameters of the peak height (H) at a coastal focus, the background average height (H0), the peak width (Wd), the coastal focus distance from the island (L) and the island size (L0), we discussed relations among them. As the result peak width Wd is approximated asWd/L0=0.43 (L/L0)1.0Amplification ratio H/H0 is about 1.5 for islands of epicentral distances smaller than 400km and shows an increase with the epicentral distance for islands of epicentral distances larger than 400km. These facts are explained as a focusing effect of islands on tsunamis, in which incident wave, refracted in a sloped region around the island after divided into two, superposes on each other in the back side. In islands distant from the source the incident wave is coherent and the amplification ratio increase. The amplification ratio and relative peak width are compared with those in the another focusing effect, previously found on the 1993 Hokkaido nansei-oki earthquake tsunami. The similar proportionality of peak width and amplification ratio between two tsunamis suggest that the amplification is caused by the same mechanism.
4 0 0 0 OA T-2CCVの開発概要
- 著者
- 山田 秀次郎 菅野 秀樹 竹腰 昭弘 日根野 穣 加藤 明夫
- 出版者
- 一般社団法人 日本航空宇宙学会
- 雑誌
- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.405, pp.475-481, 1987-10-05 (Released:2010-12-16)
- 被引用文献数
- 4 4
- 著者
- Emi Kameoka Shiro Mitsuya Roel R. Suralta Akira Yamauchi Amelia Henry
- 出版者
- Japanese Society for Root Research
- 雑誌
- Plant Root (ISSN:18816754)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.45-58, 2023 (Released:2023-08-14)
- 参考文献数
- 44
- 被引用文献数
- 1
In this study, two experiments were conducted to evaluate the genotypic variation of rice root system distribution and root activity in response to short-term drought conditions. Seven rice genotypes were used, of which one (Rexmont) showed the greatest reduction in shoot biomass under drought, and two (Swarna and KDML105) showed the least reduction in shoot biomass under drought in both experiments. In a phytotron experiment (Experiment 1) in which root hydraulic conductivity (Lpr) of 21-day-old rice plants was evaluated in well-watered (control) and dry down (drought) conditions, the Lpr of Swarna, KDML105, and IRAT109 were significantly lower under drought compared to the control. In a field experiment (Experiment 2) conducted in the 2013 wet season at IRRI, stomatal conductance, bleeding rate, and root surface area density (RSAD) at 0-15, 15-30, 30-45, and 45-60 cm soil depths were measured in an irrigated (control) and rainfed (drought) treatments. Swarna, KDML105, and FR13A showed significant reductions in RSAD at 0-30 cm depth under drought in the field compared to the control, while Rexmont and IRAT109 showed no significant changes. In addition, Rexmont and Swarna both maintained higher bleeding rates than the other genotypes. Based on the root hydraulic and architectural traits of contrasting genotypes, we conclude that the bleeding rate did not explain the genotypic variations in the maintenance of shoot biomass, and that reducing shallow root growth and Lpr in response to drought conferred the best ability to maintain shoot biomass under short-term drought conditions.
4 0 0 0 奥州藤原氏と蝦夷ヶ島の砂金、その学際的研究
4 0 0 0 OA 人と生きるイヌ-イヌの起源から現代人に与える恩恵まで
- 著者
- 大森 理絵 長谷川 寿一
- 出版者
- 日本動物心理学会
- 雑誌
- 動物心理学研究 (ISSN:09168419)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.3-14, 2009 (Released:2009-07-28)
- 参考文献数
- 48
- 被引用文献数
- 1 1
Based on results of molecular phylogenetic analyses and archaeological evidences, most researchers believe that the dog is descended from the wolf and that east Asia was the central place for the early events of domestication around 15,000-20,000BP. Many different theories of domestication have been proposed in respect of the evolutionary mechanism, and each theory can explain a particular aspect of the process which has different evolutionary backgrounds by its stage and phase. The dog is established in modern society as a companion animal. It has physiological and psychological benefits to human, which include facilitating therapy, reducing stress, and socialization. In addition to that, the dog has positive effects on child development and elderly people.
4 0 0 0 OA 行儀良く座れる通勤電車用ロングシートの提案
- 著者
- 安中 成樹 山崎 信寿
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 日本人間工学会大会講演集 日本人間工学会第50回記念大会
- 巻号頁・発行日
- pp.312-313, 2009 (Released:2011-05-20)
4 0 0 0 OA 『明星』60余年の歩み ―雑誌メディアの細分化
- 著者
- 田島 悠来
- 出版者
- 日本出版学会
- 雑誌
- 出版研究 (ISSN:03853659)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, pp.41-61, 2016-03-20 (Released:2019-03-31)
- 参考文献数
- 15
本稿は,集英社が刊行する雑誌『明星』の60余年の歩みを,①黎明期:大衆娯楽誌②黄金期:アイドル誌③転換期:「ジャニーズ」専門誌という三つに区分し紐解くものである.特に,70年代までに日本に到来した戦後の大衆社会と,80年代以降の雑誌の細分化に見られるその解体のプロセスを,一つの雑誌のなかで体現しているという意味において重要な媒体として『明星』を位置づけ論じる.
4 0 0 0 OA 愛知県で救急救命士が対応した施設外分娩症例の検討
- 著者
- 田島 典夫 井上 保介
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床救急医学会
- 雑誌
- 日本臨床救急医学会雑誌 (ISSN:13450581)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.562-567, 2022-06-30 (Released:2022-06-30)
- 参考文献数
- 5
救急救命士が対応した施設外分娩症例を調査し,その頻度や母体と児の状態について検討した。県内で現場活動に従事している救急救命士のうち,52%の者が過去救急出動で施設外分娩に遭遇した経験があると回答した。回答があった施設外分娩症例のうち,457件について検討したところ,調査から直近1年間の施設外分娩は87件であり,県全救急件数の0.025%であった。また,救急隊が現場到着時にすでに分娩済みであったのは75.9%であり,救急隊接触後および搬送中に分娩に至った事案は21.9%であった。さらにすでに分娩していた事案の分娩場所については,自宅内が82%を占め,なかでもトイレでの分娩が37.2%ともっとも多かった。これらの結果から,救急救命士が対応した施設外分娩の頻度や母体と児の状態が明らかとなったが,不明な点も多かった。今後は,統一したフォーマットによる全国規模でのデータ収集とその分析が望まれる。
4 0 0 0 OA ナショナルフットボールリーグを目指す日本人アメリカンフットボール選手の課題
- 著者
- 松尾 博一 松元 剛
- 出版者
- 日本コーチング学会
- 雑誌
- コーチング学研究 (ISSN:21851646)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.2, pp.285-294, 2022-03-20 (Released:2022-05-09)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 2
The purpose of this study was to clarify the issues that Japanese American football players need to overcome in trying to sign a contract with an NFL team through interviews. The subjects were four Japanese American football players who had participated in the training camp of an NFL team in the past. Interviews were conducted in person. The content of the interviews was recorded with the subjects' permission, and the recorded audio was transcribed. The content related to each issue was coded and classified. As a result, three main issues were identified: issues related to competition, issues outside of competition, and issues related to the athletic experience in the United States. When Japanese players aspire to play in the NFL, they must deal with the athletic challenges they face at each football position and overcome the non-athletic challenges they face by learning the language and receiving support from various people. In addition, they need to adapt to the competitive environment in the United States by gaining football playing experience as soon as possible.
4 0 0 0 OA 線維筋痛症患者をよりよく理解するには ~患者相談を通じて気付いたこと~
- 著者
- 橋本 裕子
- 出版者
- 公益財団法人 国際全人医療研究所
- 雑誌
- 全人的医療 (ISSN:13417150)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, no.1, pp.33-40, 2017-12-25 (Released:2019-04-19)
- 参考文献数
- 9
線維筋痛症患者を理解するのは難しいと言われることが多々あるが,その原因の一つは,医療現場では時間がないこと,もう一点は,医療者と患者の立場,目指すものの違いであろう.患者は一刻も早く「この痛みから解放されたい」「今度こそこの医師に分かって欲しい」と強く思っている.「治るのか,一生治らないのか」「特効薬はないのか」「誰なら治せるのか」などの性急な相談がたくさんある.患者の気持ちとしては当然だろう.耐え難い痛みと不安,早く職場に復帰しなければ失職する,長期間医療費を負担する困難,家族に対する遠慮.発症に至る経緯,話したいライフストーリーが積もり積もっている.これを紐解くにはかなりの時間と聞き出す側のゆとりが必要である.治療には長期間かかるが,じっくり取り組む環境をまず作らなければならない.患者が現実に直面する困難や不安,治りたいと苦悩する気持ちを日頃の電話相談から紹介したい.