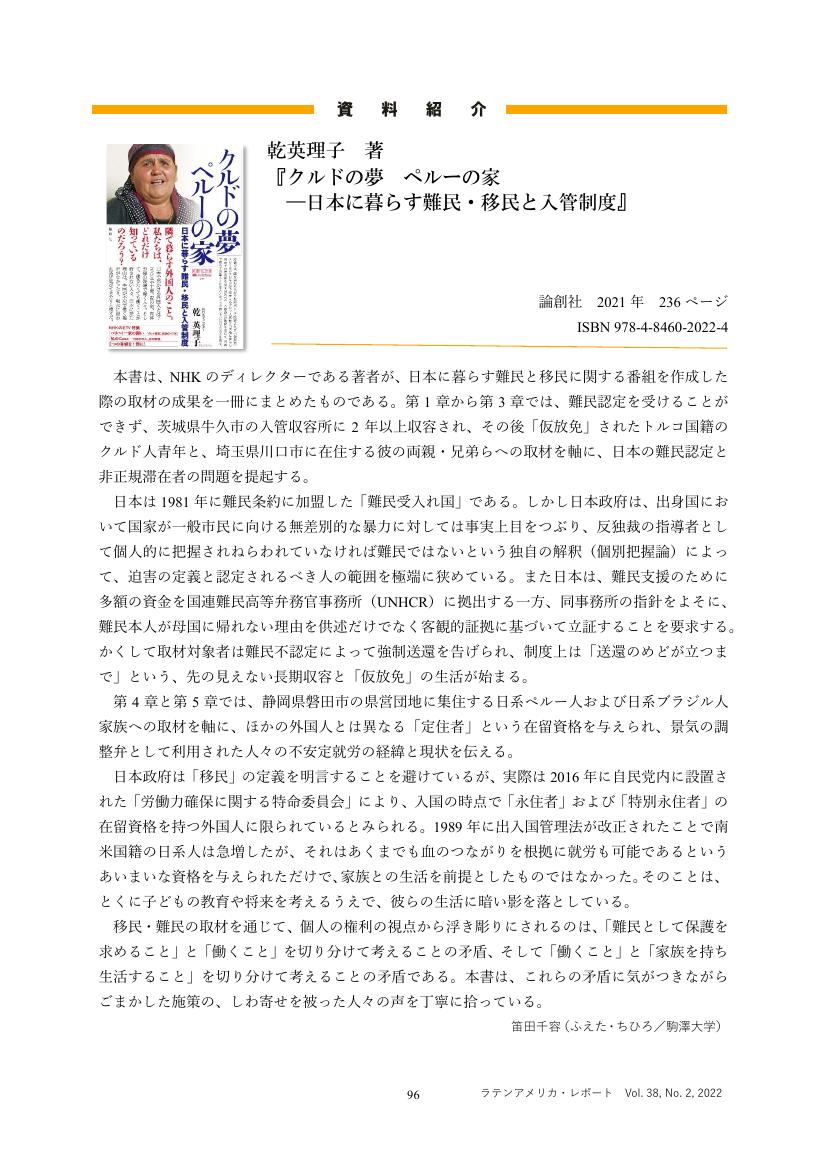4 0 0 0 OA アイルランドの哲学・思想 ( 芸術・宗教・科学を含む )
4 0 0 0 OA いわゆる「部分社会の法理」の再構成
- 著者
- 渡邊 亙
- 出版者
- 関西法政治研究会
- 雑誌
- 法政治研究 (ISSN:21894124)
- 巻号頁・発行日
- vol.First, pp.229-264, 2015-03-29 (Released:2017-07-06)
Die in Deutschland unter dem Thema "Selbstverwaltung" behandelte Frage wird in Japan in zwei wesentlich unterschiedlichen dogmatischen Bereichen betrachtet. Die hier zu behandelnde Lehre, welche die Autonomie der nicht kommunalen Korperschaften zum Gegenstand hat, wird in Japan als Lehre der "Teilgesellschaft" bezeichnet. Der Begriff "Teilgesellschaft" stammt urspriinglich aus dem rechtsphilosophischen Kontext. Heute bildet dieser Begriff den Kern der Lehre der Rechtsprechung uber die Autonomie der Korperschaften im offentlichen und privaten Bereich. In der folgenden Untersuchung ist zunachst die Entwicklung dieses Begriffs in Literatur und Rechtsprechung zu beschreiben. Anschliessend soil auf ihre Charakteristika sowie die daraus folgende Problematik hingewiesen werden.
4 0 0 0 OA 五月女颯著『ジョージア近代文学のポストコロニアル・環境批評』
- 著者
- 貝澤 哉
- 出版者
- 日本ロシア文学会
- 雑誌
- ロシア語ロシア文学研究 (ISSN:03873277)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, pp.173-185, 2023-10-15 (Released:2023-12-20)
4 0 0 0 OA 直観像素質者における視空間記憶過程の特性 : 定性的研究および定量的研究からの示唆
- 著者
- 新原 理津子
- 出版者
- 若手イメージ研究者のためのブラッシュアップセミナー運営委員会
- 雑誌
- 若手イメージ研究者のためのブラッシュアップセミナー予稿集
- 巻号頁・発行日
- pp.18-23, 2013-03-14
若手イメージ研究者のためのブラッシュアップセミナー(Brush up seminar for young researchers on mental imagery).2013年3月16日(土)〜17日(日).北海道大学学術交流会館,札幌市.
4 0 0 0 OA 済州4・3を語る、済州4・3から語る
- 著者
- 伊地知 紀子
- 出版者
- 関西社会学会
- 雑誌
- フォーラム現代社会学 (ISSN:13474057)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, pp.127-136, 2018 (Released:2019-05-11)
- 参考文献数
- 15
本シンポジウムのテーマである「歴史経験の語られ方、記憶のされ方」について、済州4・3を事例として報告した。済州4・3をめぐる語りは、語り手である個人、その家族あるいは親戚姻戚が何をしていたのか、どこにいたのか、どのように犠牲となったかといった事件当時だけではなく、事件後にこれらの人びとがどこでどのように暮らしたのかによっても規定される。他二本の報告は、東北大震災(金菱報告)と三池炭鉱報告(松浦報告)であった。各報告と合わせて議論することにより、歴史経験の語られ方、記憶のされ方についての論点として気づいたことがある。それは、歴史経験や記憶を開いていく場をどのように設定するのか、別の表現をとるとすればpublic memoryの時間軸をどう設定するのか、空間をどこまで広げるのか、つまりpublicと形容する時どのような枠組みを前提として論ずるのかということだ。この問いは、ある地域のある時期における歴史経験が、後の生活にいかなる影響を及ぼすのかという視点を複眼的に置くことなくしては深めることが困難なものである。この気づきを踏まえて、済州4・3とはいかなる歴史経験であり、体験者や遺族などがどのように語り、さらに済州4・3から何を語りうるのか、本稿は在日済州島出身者の生活史調査からの試論である。
- 著者
- 境野 高資 本間 多恵子 辻 聡 石黒 精 阪井 裕一
- 出版者
- 一般社団法人 日本救急医学会
- 雑誌
- 日本救急医学会雑誌 (ISSN:0915924X)
- 巻号頁・発行日
- vol.24, no.5, pp.241-246, 2013-05-15 (Released:2013-07-24)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 1
【背景】東京都では年に約4万件発生していた搬送先の選定困難を改善するため,平成21年9月より東京ルールを開始した。東京ルールでは,5つの医療機関に照会または連絡時間20分以上を要しても搬送先が決定しない中等症以下の救急搬送事案に関し,地域救急医療センターなどが調整・受入を行うと定められた。【目的】東京ルール制定以後,小児の搬送先選定先困難事案の発生状況を調査し,その要因を検討する。【対象】平成21年9月から平成22年12月に,東京ルールに該当した15歳未満の事案。【方法】東京都福祉保健局資料をもとに後方視的に検討した。【結果】東京ルールに該当した事案は,15歳未満の小児では119,486件中224件(0.2%)であり,15歳以上の702,229件中16,104件(2.3%)に比べて有意に少なかった。小児例では男児が153件(68.3%)を占め,年齢は隔たりなく分布していた。該当事案の発生は土日祝日1.2件/日,平日0.3件/日で,準夜帯が143件(63.8%)を占めた。傷病種別では外傷が180件(80.4%)を占め,うち177件(79%)は骨折・打撲・挫創などであった。【考察】東京都における搬送先選定困難事案の中に少ないながら小児例が含まれていた。小児例は土日祝日および準夜帯に多く発生し,多くが整形外科領域を中心とした外傷症例であった。小児の搬送先選定困難事案を改善するため,救急告示病院における準夜帯の小児整形外科救急診療体制の再構築が必要であると考えられた。【結語】東京都における小児の搬送先選定困難事案は土日祝日および準夜帯の整形外科領域に多く,対応した医療システムの構築が求められる。
- 著者
- 中井 好男
- 出版者
- 一般社団法人 言語文化教育研究学会:ALCE
- 雑誌
- 言語文化教育研究 (ISSN:21889600)
- 巻号頁・発行日
- vol.19, pp.52-73, 2021-12-24 (Released:2022-02-14)
- 参考文献数
- 41
- 被引用文献数
- 2
本研究は,ろうの両親を持つ聴者(コーダ:Children of Deaf Adults)である筆者が,中国出身のコーダとの対話を通して,自身の経験の内省と異なる社会での経験の比較を行うことによって,日本手話の継承に関する問題について考察する当事者研究である。分析方法として,当事者同士の対話的自己エスノグラフィを用い,継承語という視点から日本手話を捉え,その課題の外在化を目指した。分析の結果,筆者らは両親から継承するろう文化と音声言語を基軸とする生活圏の文化との間に第三の文化を有しているが,周囲からの蔑視や社会から押し付けられる障害者家族の一員という社会的アイデンティティによって障害者家族の文化として形成されているため,それを拒絶してきたことがわかった。また,この第三の文化を受容可能なものにするためには,コーダとしての能動的な社会的アイデンティティの構築に加え,第三の文化の基盤をなす日本手話の継承も必要となることが指摘できた。
4 0 0 0 OA 進行がん患者のせん妄に対するアセナピン舌下錠の有用性に関する後方視的研究
- 著者
- 前倉 俊也 相木 佐代 田宮 裕子 久田原 郁夫 櫻井 真知子 吉金 鮎美
- 出版者
- 日本緩和医療学会
- 雑誌
- Palliative Care Research (ISSN:18805302)
- 巻号頁・発行日
- vol.18, no.3, pp.177-182, 2023 (Released:2023-07-19)
- 参考文献数
- 13
【目的】進行がん患者のせん妄に対するアセナピン舌下錠の有用性について評価する.【方法】2019年10月1日から2022年9月30日までに当院に入院し,せん妄に対する治療としてアセナピン舌下錠を投与された進行がん患者を対象に,その有用性に関して電子カルテを用いて後方視的に調査を行った.せん妄による興奮症状の改善度を評価するためにAgitation Distress Scale(ADS)を用いて評価した.【結果】解析対象となった患者は20例であった.対象となった患者の投与前のADS値の平均値(範囲)は12(4–17),投与後の平均値(範囲)は7.9(0–18),p値<0.001であり投与前後で有意な低下が認められた.【結論】アセナピン舌下錠はせん妄に対する薬物治療の選択肢の一つとして有用な可能性が示唆された.
4 0 0 0 OA ヒト腸内マイクロバイオーム解析のための最新技術
- 著者
- 服部 正平
- 出版者
- 日本臨床免疫学会
- 雑誌
- 日本臨床免疫学会会誌 (ISSN:09114300)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.5, pp.412-422, 2014 (Released:2015-01-06)
- 参考文献数
- 26
- 被引用文献数
- 4
近年のDNAシークエンシング技術の革新的進歩(いわゆる,次世代シークエンサー; NGS)により,数百兆個の細菌から構成されるヒト腸内細菌叢の集合ゲノム(マイクロバイオーム)の網羅的で高速な解析が可能となった.また,細菌叢の生物学的あるいは生態学的知見を正確に得るための解析技術の開発や改良もなされ,細菌叢の包括的な研究が世界的に進められるようになった.その結果,ヒト腸内細菌叢の基本的な全体構造や機能,食事等の外的因子による影響,さらには様々な疾患における腸内細菌叢の異常(dysbiosis)等が明らかとなり,腸内細菌叢と宿主ヒトの生理現象がこれまでの想像を越えて密接な関係にあることが示唆された.一方で,サンプルの保存や搬送法,DNA抽出法,用いるシークエンサーの種類等の解析プロトコールによる影響についての詳細な精査も必要になっている.本稿では,NGSを用いたヒト腸内マイクロバイオームの解析法について解説する.
4 0 0 0 OA フランスにおける女性史・ジェンダー史 ──新しいアプローチ、新しい対象、新しい問題──
- 著者
- テボー フランソワーズ 北原 零未
- 出版者
- ジェンダー史学会
- 雑誌
- ジェンダー史学 (ISSN:18804357)
- 巻号頁・発行日
- vol.9, pp.79-91, 2013 (Released:2015-12-29)
4 0 0 0 OA 第一次世界大戦と日本陸軍の近代化 ―その成果と限界―
- 著者
- 服部 聡
- 出版者
- 国際安全保障学会
- 雑誌
- 国際安全保障 (ISSN:13467573)
- 巻号頁・発行日
- vol.36, no.3, pp.25-50, 2008-12-31 (Released:2022-04-20)
4 0 0 0 OA 改正薬事法と研究倫理―中絶胎児研究のリスク・ベネフィット評価―
- 著者
- 栗原 千絵子 松本 佳代子 石光 忠敬
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- YAKUGAKU ZASSHI (ISSN:00316903)
- 巻号頁・発行日
- vol.123, no.3, pp.91-106, 2003-03-01 (Released:2003-03-26)
- 参考文献数
- 102
- 被引用文献数
- 1 1
The Japanese Pharmaceutical Law was revised at the end of July 2002. The important features of this revision are the postmarketing safety scheme, especially for biological products, and reconstruction of the legislation for effective pharmaceutical development. This is based on the national policy to foster life sciences such as genetic research and regenerative medicine for both healthcare improvement and industrial promotion. Such research requires study participants who donate human tissue including abandoned embryos or aborted fetuses, which may touch the human dignity. In particular, fetal stem cell research appears to have unpredictable risks not only to women who undergo abortions but also to societal epistemology. The authors conducted risk-benefit assessment of fetal stem cell research, reviewing the scientific, ethical, legal, and social aspects, including a case study of critical appraisal on a report of the double-blind, sham surgery-controlled trial of implantation of fetal tissues in patients with Parkinson's disease conducted in the USA. It is concluded that risk-benefit assessment with a wide, profound perspective is necessary for advanced biotechnology. Some types of research should not be assessed based only on such utilitarian viewpoints as risk and benefit. Conscientious reflection is necessary to reach a public consensus on which types of human material can be utilized as research or pharmaceutical resources.
- 著者
- 鹿野 祐介 肥後 楽 小林 茉莉子 井上 眞梨 永山 翔太 長門 裕介 森下 翔 鈴木 径一郎 多湖 真琴 標葉 隆馬 岸本 充生
- 出版者
- 研究・イノベーション学会
- 雑誌
- 研究 技術 計画 (ISSN:09147020)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.3, pp.279-295, 2022-11-01 (Released:2022-11-14)
- 参考文献数
- 35
The Research Center on Ethical, Legal, and Social Issues (ELSI) at Osaka University and mercari R4D started a practical joint research project in 2021 to innovate based on the concept of ELSI and responsible research and innovation (RRI). This paper describes the research and practice conducted in this joint project on (A) upgrading the ethics review process for research and development, (B) assessing AI-based solution technologies and strengthening AI governance, and (C) conducting a feasibility study for participatory technology assessment on quantum technology, respectively. In this paper, we illustrate the methods and processes of this project, as well as the results of these individual studies, and share critical reflections on the ELSI/RRI knowledge production processes from the perspectives of both ELSI researchers and members of the private sector. Our results provide evidence of the contribution to innovation governance in science and technology from ELSI/RRI research and the knowledge of the humanities and social sciences.
4 0 0 0 OA 性欲中枢,性的興味に関する画像的解析
4 0 0 0 OA 人新世における環境教育
- 著者
- 野村 康
- 出版者
- 一般社団法人 日本環境教育学会
- 雑誌
- 環境教育 (ISSN:09172866)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.4, pp.4_56-63, 2022 (Released:2022-08-04)
- 参考文献数
- 49
This paper aims to stimulate a discussion on environmental education (EE) in the context of the Anthropocene era. Therefore, the author first reviews research on EE in/for the Anthropocene era under the headings of “(re) conceptualizing nature/the environment,” “criticizing anthropocentric views,” and “epistemological discussion.” The author then suggests that EE should emphasize the agentic capacity of nature and non-humans, multidisciplinary and participatory approaches, environmental justice and indigenous knowledge for the purpose of managing Anthropocene challenges, such as uncertainty, complexity, and human responsibility for environmental issues. Furthermore, the author finds that non-positivist yet foundationalist epistemologies, such as critical realism and new materialism, are particularly emphasized in the literature that was reviewed, as this can encourage the reflexivity and transformation necessary in the Anthropocene era. This paper then compares this emerging Anthropocene discourse with the currently dominant discourse of sustainable development (SD), which requires critical examination of both education for SD (ESD) and SD goals (SDGs). The inherent anthropocentricism and lack of reflexivity and transformative capacity of SD are highlighted as drawbacks of ESD and SDGs as guiding concepts in the Anthropocene era. These shortcomings present a challenge for future EE research.
4 0 0 0 OA 乾英理子 著 『クルドの夢 ペルーの家―日本に暮らす難民・移民と入管制度』
- 著者
- 笛田 千容
- 出版者
- 独立行政法人 日本貿易振興機構アジア経済研究所
- 雑誌
- ラテンアメリカ・レポート (ISSN:09103317)
- 巻号頁・発行日
- vol.38, no.2, pp.96, 2022 (Released:2022-01-31)
- 著者
- 村岡 敬明
- 出版者
- 日本法政学会
- 雑誌
- 法政論叢 (ISSN:03865266)
- 巻号頁・発行日
- vol.59, no.1, pp.41, 2023 (Released:2023-12-15)
4 0 0 0 OA 乳児期における社会的学習:誰から,どのように学ぶのか
- 著者
- 奥村 優子 鹿子木 康弘
- 出版者
- 心理学評論刊行会
- 雑誌
- 心理学評論 (ISSN:03861058)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, no.2, pp.191-203, 2018 (Released:2019-11-06)
- 参考文献数
- 67
How do infants extract useful information from a world of distractions? Social learning from others enables infants to acquire information rapidly and efficiently that otherwise would require more time and cognitive resources. In this paper, we aimed to clarify the social learning mechanism of infants by focusing on from whom and how they learn. First, we introduced the theory of natural pedagogy, which argues that young infants can acquire knowledge from ostensive signals. Second, we reviewed recent studies on infant social learning from the viewpoint of two critical factors: agents and ostensive signals. In particular, we provided studies that focused on what type of agent is appropriate as an information source for infant learning and how ostensive signals work effectively for infant learning. Third, we provided tentative suggestions on how the foundations of infant social learning are generated, maintained, and formed in early development.
4 0 0 0 OA カネの結合体とヒトの結合体の二面性
- 著者
- 伊丹 敬之
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.1, pp.4-17, 2023-09-20 (Released:2023-09-30)
- 参考文献数
- 3
人的資本が注目されているが,その本当の理由は株主傾斜が上場企業で行き過ぎたことへの警戒感ではないか. 日本の大企業は,カネの結合体として株主への分配を増やすことに忙しく,ヒトの結合体の中核である従業員への分配を軽視している.その上,設備投資まで抑制している.それでは,日本企業に成長の未来図は描けないだろう. 企業はカネとヒトの二面性を本質的にもっていることを,もっと深く考えるべきである.
4 0 0 0 OA 双生児と一般児による遺伝因子分析 Y-G性格検査への適用
- 著者
- 豊田 秀樹 村石 幸正
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)
- 巻号頁・発行日
- vol.46, no.3, pp.255-261, 1998-09-30 (Released:2013-02-19)
- 参考文献数
- 16
双生児と一般児のデータを同時に分析する遺伝因子分析モデルが, Y-G性格検査の研究に適用される。構造方程式モデルの1つであるこのモデルによって, 187組の一卵性双生児と43組の二卵性双生児と1309 人の一般児の標本を分析した。一般児のデータは, 因子の共分散構造を安定させるために利用することができる。遺伝的影響・共有環境・非共有環境は, 適応性因子の分散を, それぞれ2.5%, 32.5%, 65.0% 説明していた。またそれらは, 外向性因子の分散を, それぞれ49.8%, 10.3%, 39.9%説明していた。外向性よりもむしろ適応性の因子の分散に対して, 環境がより大きく影響することを遺伝因子分析の結果は示した。