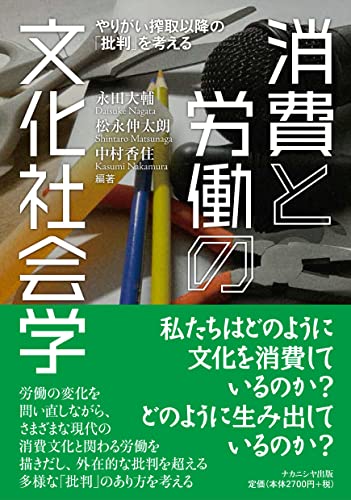- 著者
- Kei SAKAMOTO Masaaki TAKAHASHI
- 出版者
- Meteorological Society of Japan
- 雑誌
- 気象集誌. 第2輯 (ISSN:00261165)
- 巻号頁・発行日
- vol.83, no.5, pp.817-834, 2005 (Released:2005-11-19)
- 参考文献数
- 16
- 被引用文献数
- 23 23
Near the tropopause over the North Pacific in summer an isolated low pressure system (Upper Cold Low, UCL) is often generated by the deepening and cutting off of a trough in the mid-latitude westerlies. The tracks and structures of these UCLs have been investigated in previous studies, but understanding of the cut off and weakening processes remains poor. In this paper, the tracks of UCLs generated in the 1999 summer are analyzed using ECMWF data. The physical processes occurring in one ofthese systems are investigated in detail using the ECMWF data, and the meso-scale model MM5. We focus particularly on cut off and weakening processes, and on the structure of the vertical velocity in the UCL.The summer of 1999 was hot over Japan, and part of the Tibetan high pressure, around 200 hPa, was shifted northward. This allowed some UCLs to approach Japan in July and August. A UCL on August 19th is selected for detailed analysis, and was generated in the following process. Positive vorticity in a westerly wave at 200 hPa was extended by a northeast wind in the upper layer only. The positive vorticity was cut off by non-liner effects and upper level divergence, associated with convective clouds, generating the isolated UCL. The structure of the cyclonic circulation and the warm and cold cores were similar to those in previous studies. The structure of the vertical motion of the moving UCL was explained by dry dynamics and there was upward motion on the front side of the UCL, in the direction of movement. Upper level clouds in the UCL strengtJhened this upward motion. Convective clouds were seen in the system. The latent heat of these convective clouds played an important role in weakening the cold core of the UCL.
4 0 0 0 OA ロケットにおける測定技術
- 著者
- 前村 孝志 神谷 卓伸
- 出版者
- 一般社団法人 スマートプロセス学会 (旧高温学会)
- 雑誌
- 高温学会誌 (ISSN:03871096)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.5, pp.220-226, 2008-09-21 (Released:2012-10-16)
- 参考文献数
- 15
4 0 0 0 OA 養殖現場を視野に入れた魚類ウイルスRNAワクチンの実用化
本研究で実用化を目指した「ds-RNA型」ワクチンは,申請者らが開発してきた「mRNA型」ワクチンを発展させたものであり,ds-RNA接種により産生されるインターフェロンを利用した簡便かつ実用的な魚類ウイルスに対する免疫方法である。Poly(I:C)をニジマス,マハタ,ヒラメに投与し,魚を一過性の抗ウイルス状態とし,それぞれ伝染性造血器壊死症,ウイルス性神経壊死症,ウイルス性出血性敗血症原因ウイルスで攻撃して生存率を対照と比較した。3例共にワクチン効果が確認でき,この間に養殖環境中に存在する病原ウイルスに暴露させることでウイルスに対する特異免疫を誘導することもできた。さらに実用化に向け,魚毒性の心配がない用法・容量を定めることができた。
4 0 0 0 IR 平安時代中期における紀伝道文人の研究
- 著者
- 出口 誠
- 出版者
- 筑波大学 (University of Tsukuba)
- 巻号頁・発行日
- 2022
【要旨】
4 0 0 0 OA 遷音速機の設計について(座談会)
4 0 0 0 OA 睡眠時間は主観的健康観及び精神神経免疫学的反応と関連する
- 著者
- 岡村 尚昌 津田 彰 矢島 潤平 堀内 聡 松石 豊次郎
- 出版者
- 日本行動医学会
- 雑誌
- 行動医学研究 (ISSN:13416790)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.33-40, 2010 (Released:2014-07-03)
- 参考文献数
- 28
大学生の睡眠時間と心身の健康との関連性を明らかにするために、GHQ-28による主観的評定と精神神経免疫学的(PNI)反応[3-methoxy-4-hydroxyphenylglychol(MHPG)含有量、免疫グロブリン(Ig)A抗体産生量]を用いた客観的評価から、睡眠時間の長さによって、心身のストレスの自覚とノルアドレナリン神経系と免疫系の活性がどのように異なるのか検討した。研究参加の同意が得られた健康な大学生205名(男性110名、女性95名、年齢18.6±1.0)を対象に睡眠時間を調査し、最適睡眠時間群(AS:Adequate Sleep)(6〜8時間睡眠)を35名、短時間睡眠群(SS: short sleep)(5時間以下の睡眠)33名と長時間睡眠群(LS: long sleep)(9時間以上の睡眠)28名をそれぞれ抽出した。講義時に、集団一斉法にてGHQ-28への記入を求め、PNI反応を測定するために唾液の採取を行った.LS群のGHQ-28得点は、「社会的活動障害」および「うつ傾向」下位尺度でAS群とSS群に比較して有意に高値であった。一方、SS群はASに比較して「身体症状」下位尺度得点が有意に高かった。SS群の唾液中free-MHPGは、AS群と異ならなかったが、LS群に比較して有意に高く、s-IgAは有意に低かった。ロジスティック回帰分析の結果は、中等度以上の「身体的症状」、「社会的活動障害」と「うつ傾向」症状が短時間もしくは長時間睡眠と有意に関連していることを明らかにした。以上の知見から、6〜8時間睡眠が最も心身の健康と関連していることが示された。また、睡眠時間いかんによって唾液を指標にして得られたPNI反応が異なったことは、今後、大学生のストレス関連疾患の予防や健康増進活動のために、睡眠の重要性を示す客観的証拠となると考える。
4 0 0 0 OA 企業ドメインの歴史性:ウェスチングハウス社の企業転換に関する事例研究
- 著者
- 宮田 憲一
- 出版者
- 特定非営利活動法人 組織学会
- 雑誌
- 組織科学 (ISSN:02869713)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.4, pp.27-38, 2022-06-20 (Released:2022-09-17)
- 参考文献数
- 60
企業ドメインに関する既存研究は,ドメインの階層性や時間的展開とその変化要因に焦点を当ててきたが,本稿では,過去の経営者から継承した企業ドメインの歴史的側面が現経営者のドメイン定義に経路依存的な影響を及ぼすことを指摘する.電機からメディアへと事業転換して消滅した米国企業のウェスチングハウス社を事例にして,113年にわたる超長期間の考察から,戦略構想プロセスにおける歴史的要因を分析する必要性が示される.
4 0 0 0 OA 煎茶の1煎,2煎,3煎液の成分組成に基づく溶出特性
- 著者
- 坂本 彬 中川 致之 杉山 弘成 堀江 秀樹
- 出版者
- Japanese Society of Tea Science and Technology
- 雑誌
- 茶業研究報告 (ISSN:03666190)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.94, pp.45-55, 2002-12-31 (Released:2009-07-31)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 1 1
1. 煎茶の標準的な入れ方に近い湯温50℃,60℃,70℃,90℃(遊離アミノ酸類は90℃を除く),浸出時間は1煎目が60秒,2煎目,3煎目が10秒間の条件で,主要カテキン類4種,カフェイン,主要遊離アミノ酸類6種がどのように溶出するかを調べた。(1)カテキン類,カフェインは,ともに温度の上昇に伴って溶出量が増加した。カテキン類のうちで遊離型カテキン類は比較的溶出しやすく,エステル型カテキン類は溶出が遅かった。90℃3煎目で前者が90%以上溶出されたのに対し,後者は50%台であった。カフェインは遊離型カテキン類に近い溶出性を示した。(2)アミノ酸類はきわめて溶出されやすく,50~70℃の1煎目で半分近く溶出し,3煎目には,ほとんど100%溶出した。ただし, アルギニンは他のアミノ酸より溶出が遅い傾向にあった。2. 温度を変える入れ方,すなわち1煎目を5℃,10分,2煎目を50℃,1分,3煎目を95℃1分の条件で主要カテキン類4種,カフェイン,主要遊離アミノ酸類6種,ペクチン,カリウム,マグネシウム,カルシウム,リン酸がどのように溶出するかを調べた。(1)遊離型カテキン類は冷水でも比較的溶出しやすく,3煎目までで80~90%が溶出した。一方,エステル型カテキン類は低温では溶出されにくく,熱湯を用いた3煎目で急激に溶出したが,それでも50%程度であった。カフェインは低温でも1煎目で36%程度溶出し,熱湯を用いた3煎目までで84%に達した。(2)アミノ酸類は冷水でもよく溶出したが,アルギニンは他のアミノ酸類より溶出が遅かった。1煎目に冷水を使用する条件でも,アルギニンを除いて2煎目で70~80%が溶出した。(3)ペクチンは溶出しやすく,いずれの形態のものも煎を重ねるに従って段階的に溶出が減少した。(4)カリウムは溶出されやすく,3煎でほとんどが溶出した。マグネシウム,リン酸は煎を重ねるに従って溶出が減少した。ただし,カルシウムは1煎から3煎まで同程度の溶出量であり,溶出割合も3煎までで4%に満たなかった。(5)1煎液の濃厚な甘味,旨味にはアミノ酸類の濃度が高く,ペクチンを多く含むことが,また3煎液の強い苦味にはエステル型カテキン類の濃度の高いことが寄与していると推察される。
- 著者
- 石川 洋子
- 出版者
- 北海道大学大学院文学研究科応用倫理研究教育センター
- 雑誌
- 応用倫理 (ISSN:18830110)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, pp.64-74, 2011-11
4 0 0 0 OA 『論理哲学論考』における「形式」の意味とその問題性
- 著者
- 奥 雅博
- 出版者
- 科学基礎論学会
- 雑誌
- 科学基礎論研究 (ISSN:00227668)
- 巻号頁・発行日
- vol.8, no.3, pp.97-101, 1967-11-30 (Released:2009-09-04)
4 0 0 0 OA 詩に浄化される身体 ―余秀華という現象とその詩―
- 著者
- 小笠原 淳
- 出版者
- 愛知大学現代中国学会
- 雑誌
- 中国21 = China 21 (ISSN:13428241)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, pp.173-188, 2015-08-20
4 0 0 0 OA 臨床試験の実施の基準(GCP)
- 著者
- 竹澤 正行
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.138, no.5, pp.205-208, 2011 (Released:2011-11-10)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 4 4
臨床試験の実施の基準(GCP: Good Clinical Practice)は,医薬品として承認を得るために必要な臨床試験(治験)や医薬品の市販後に再審査,再評価を受けるために必要な臨床試験(製造販売後臨床試験)を実施する際に遵守しなければならない基準である.このGCPは,厚生労働省令として定められており,薬事法で「当該資料は,厚生労働大臣の定める基準に従って収集され,かつ,作成されたものでなければならない.」と規定されている「厚生労働大臣の定める基準」の1つである.なお,GCPは,治験などの対象となるヒト(被験者)の人権と安全性の確保,臨床データの信頼性の確保を図り,治験などが倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されることを目的として定められている.
4 0 0 0 OA トクヴィルの刑罰思想
- 著者
- 梅澤 礼
- 出版者
- 日仏哲学会
- 雑誌
- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.85-101, 2023-09-01 (Released:2023-10-01)
4 0 0 0 OA ジョルジュ・カンギレムの医学哲学における存在と価値
- 著者
- 宇都 広樹
- 出版者
- 日仏哲学会
- 雑誌
- フランス哲学・思想研究 (ISSN:13431773)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.177-188, 2023-09-01 (Released:2023-10-01)
4 0 0 0 消費と労働の文化社会学 : やりがい搾取以降の「批判」を考える
- 著者
- 永田大輔 松永伸太朗 中村香住編著
- 出版者
- ナカニシヤ出版
- 巻号頁・発行日
- 2023
4 0 0 0 OA 踏切の安全対策
- 著者
- 古川浩太郎
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.789, 2016-10
4 0 0 0 OA 歩行運動とリズム生成
- 著者
- 伊藤 宏司
- 出版者
- The Robotics Society of Japan
- 雑誌
- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, no.3, pp.320-325, 1993-04-15 (Released:2010-08-25)
- 参考文献数
- 30
- 被引用文献数
- 4 5
4 0 0 0 OA エストロゲンの心筋保護作用
- 著者
- 野出 孝一
- 出版者
- 一般社団法人 日本老年医学会
- 雑誌
- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)
- 巻号頁・発行日
- vol.42, no.6, pp.630-632, 2005-11-25 (Released:2011-03-02)
- 参考文献数
- 8
心筋細胞にもエストロゲン受容体, 両方が局在し, 女性ホルモンであるエストロゲンが心筋の肥大・炎症に抑制効果を有することが明らかになった. 臨床例でも, 高齢女性が高血圧による心肥大・心不全を合併しやすいことや, ホルモン補充療法が心肥大を抑制することが報告されている. エストロゲンが心筋細胞肥大を抑制するメカニズムとしては, ERK・AP-1活性化の抑制作用やカルシニューリン・NFAT3の活性化抑制作用, さらにその上流にあるGqに対する直接作用がわかってきた. 本稿では, エストロゲンの心筋細胞について自験例も含めて概説する.
4 0 0 0 OA 頭蓋内血管狭窄病変アップデート
- 著者
- 菱川 朋人 伊達 勲
- 出版者
- 一般社団法人日本脳神経外科コングレス
- 雑誌
- 脳神経外科ジャーナル (ISSN:0917950X)
- 巻号頁・発行日
- vol.31, no.12, pp.758-763, 2022 (Released:2022-12-25)
- 参考文献数
- 22
頭蓋内血管狭窄病変は多様な病態に起因する. 動脈硬化性病変において抗血栓療法, 抗動脈硬化治療の進歩は内科治療の成績向上をもたらしている. バイパス術においては定量的脳血流評価と低い周術期合併症率が重要である. もやもや病では虚血型, 出血型ともに新たな知見が報告され手術適応がより具体化される可能性がある. 脳卒中治療ガイドライン2021では小児の脳血管障害の項が新設されている. Focal cerebral arteriopathyはガイドラインにも記載されており, 小児の動脈性虚血の原因として重要である.