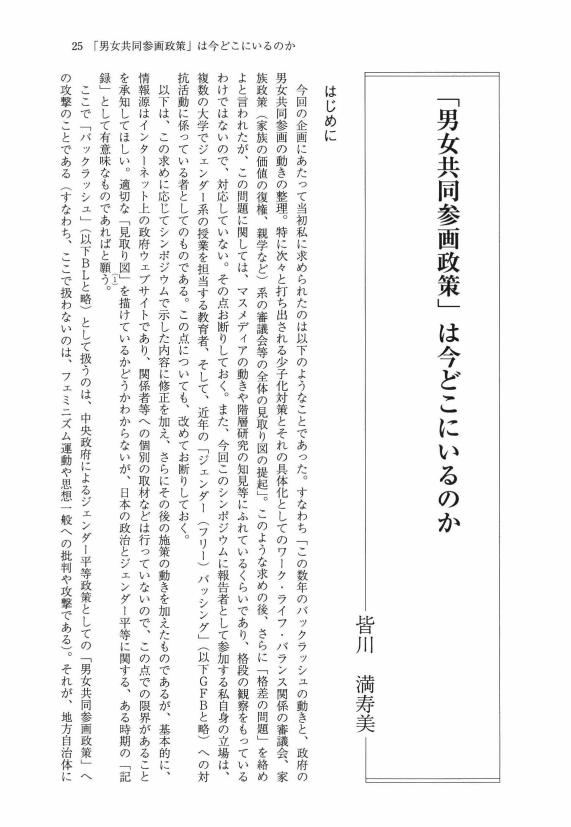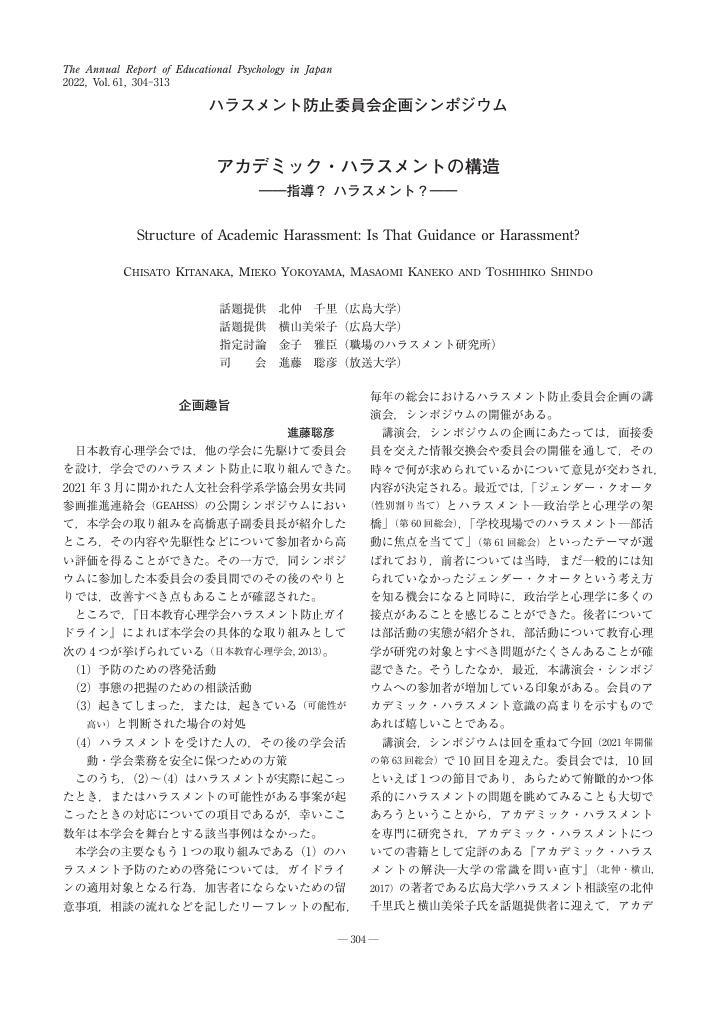4 0 0 0 IR 「古今集」の「うた」における形成と展開
4 0 0 0 IR 危機の時代を生きる料理家の群像 : 田中米・香川綾・近藤とし子・東佐与子
- 著者
- 西川 和樹 Kazuki Nishikawa
- 出版者
- 同志社大学
- 巻号頁・発行日
- 2022
source:https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB13194889/?lang=0
4 0 0 0 IR アジア系アメリカ人の映画制作/上映活動 : 芸術的労働をめぐって
- 著者
- 高橋 侑里 Yuri Takahashi
- 出版者
- 同志社大学
- 巻号頁・発行日
- 2022
source:https://doors.doshisha.ac.jp/opac/opac_link/bibid/BB13194890/?lang=0
4 0 0 0 IR ルソーにおける政治的身体と一般意志
- 著者
- 平 光佑 Kosuke Taira
- 出版者
- 同志社大学
- 巻号頁・発行日
- 2022
Doshisha University
4 0 0 0 OA 若者のデジタルゲームに対するイメージ尺度の開発と信頼性・妥当性の検討
- 著者
- 福井 昌則 黒田 昌克 野村 新平 山下 義史 森山 潤
- 出版者
- 日本デジタルゲーム学会
- 雑誌
- デジタルゲーム学研究 (ISSN:18820913)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.1, pp.1-11, 2022 (Released:2023-09-24)
本研究の目的は,若者(高校生,大学生)のデジタルゲームに対するイメージ尺度を開発し,その信頼性と妥当性 を検討することである.予備調査として,デジタルゲーム開発を専門とする大学生 112 名に予備調査を行い,デジタルゲ ームに対するイメージを測定する項目として 115 項目を抽出した.その 115 項目を用いて,関西圏の高校生,大学生 360名を対象に調査を実施した.その結果,デジタルゲームに対するイメージとして,「個人的・社会的悪印象」,「特別体験・肯定的印象」,「スキル向上」,「広範的コミュニケーション」,「健康被害・依存誘発」,「思想的悪影響」,「運動不足」の 7因子(74 項目)が抽出された.
4 0 0 0 OA 「男女共同参画政策」は今どこにいるのか
- 著者
- 皆川 満寿美
- 出版者
- 日本女性学会
- 雑誌
- 女性学 (ISSN:1343697X)
- 巻号頁・発行日
- vol.16, pp.25-39, 2009-03-31 (Released:2021-12-05)
4 0 0 0 OA 肢体不自由児の療育—三人の夢
- 著者
- 高取 吉雄
- 出版者
- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会
- 雑誌
- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.2, pp.67-72, 2012-02-18 (Released:2012-03-07)
- 参考文献数
- 15
- 被引用文献数
- 1 3
- 著者
- Daigo Kachi Tetsumin Lee Michihito Naito Kazuki Matsuda Kodai Sayama Yuki Odanaka Mao Terui Tomoki Horie Shinichiro Okata Masashi Nagase Yuta Taomoto Toru Misawa Ryoichi Miyazaki Masakazu Kaneko Yasutoshi Nagata Toshihiro Nozato Takashi Ashikaga
- 出版者
- The Japanese Circulation Society
- 雑誌
- Circulation Journal (ISSN:13469843)
- 巻号頁・発行日
- pp.CJ-23-0391, (Released:2023-09-09)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 林 日出男
- 出版者
- The Japan Association of College English Teachers
- 雑誌
- 大学英語教育学会紀要 (ISSN:02858673)
- 巻号頁・発行日
- vol.64, pp.39-55, 2020 (Released:2021-04-01)
- 参考文献数
- 43
Drawing on the distinction between societal and educational motivations in L2 learning suggested by Gardner (2010) and extending this duality to learners’ perceived needs for English (PNE), this study explores the causal relationship involving dual motivation types and dual senses of need for English with EFL learners. Data collection from Japanese and Korean college English learners followed by SEM analyses (with 310 Japanese and 330 Korean participants) found that intrinsic reasons for learning English and societal PNE impact both societal and educational motivations significantly across the two groups. Educational PNE, in contrast, showed only negligible impact on either type of motivation, casting doubt on the motivational effectiveness of classroom-generated need for English. A subsequent multi-group SEM analysis found that intrinsic reasons play a significantly greater motivational role with the Japanese than with the Korean participants. The Korean participants, on the other hand, demonstrated a greater role of societal PNE than the Japanese counterparts. These are discussed to reflect the enjoyment-based English learning and teaching in the Japanese university and the relatively large social demand for English competence in Korean culture.
4 0 0 0 OA ユーザーの長期観察によるハッシュタグの分類と非科学的言説の拡散過程の解明
- 著者
- 三浦 大樹 浅谷 公威 坂田 一郎
- 出版者
- 一般社団法人 人工知能学会
- 雑誌
- 人工知能学会全国大会論文集 第36回 (2022) (ISSN:27587347)
- 巻号頁・発行日
- pp.3M4GS402, 2022 (Released:2022-07-11)
今日の社会において,ソーシャルメディアは情報拡散に重要な役割を果たしている.しかし拡散されていく情報には誤っているものも多くあり,社会的な問題となっている.SNS上における誤った情報の拡散に関しての研究は多くなされており,その拡散力の強さなどが知られている.しかし既存の研究は情報拡散時点のユーザーの行動に焦点を当てており,情報拡散を引き起こすユーザーの内在的な特性については幅広く分析されていない.本研究ではユーザの過去にも焦点を当てることで陰謀論に取り込まれるユーザの本来の特性と彼らに生じる変化について新たな知見を得ることを目指す. そこで本研究ではコロナ禍だけでなく過去のユーザ間のリプライ・リツイートネットワークにもクラスタリングを施し,コロナ禍においてTwitterで多く使われたハッシュタグについて網羅的に分析を行った.その結果,コロナは実は存在しないと考えるようになった人々がコロナ禍に入ってから急速に集まり独自のコミュニティを作って孤立化したことが明らかになった.
4 0 0 0 OA 産科出血に対する子宮動脈塞栓術後の生殖能に関する追跡調査
- 著者
- 北村 亜也 田中 啓 松島 実穂 松澤 由記子 谷垣 伸治 小林 陽一
- 出版者
- 一般社団法人 日本周産期・新生児医学会
- 雑誌
- 日本周産期・新生児医学会雑誌 (ISSN:1348964X)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.1, pp.101-105, 2020 (Released:2020-05-13)
- 参考文献数
- 13
産科出血は妊産褥婦死亡の主要な原因を占め,速やかな対応を必要とする.近年,子宮動脈塞栓術(UAE)は産科出血に対する治療法として頻用されているが,生殖能への影響は十分に評価されていない.産科出血に対するUAEが月経再開,妊孕性,妊娠合併症に与える影響について後方視的に調査した.産科出血に対してUAEを行った78例のうち,追跡できた53例の月経再開率は98.1%(52/53例)であった.月経再開した52例中,挙児希望があった15例のうち,11例が妊娠成立し,8例が分娩に至った.そのうち3例が前置胎盤となり,その全例で癒着胎盤を認め帝王切開同時子宮全摘術を実施した.本検討により,UAEは月経再開や妊孕性には概ね影響を与えないが,妊娠例では癒着胎盤の発生率を高める可能性があることが明らかになった.UAE後の妊娠については,ハイリスク妊娠としての慎重な管理と十分な患者説明が必要である.
- 著者
- 工藤 遥
- 出版者
- 北海道社会学会
- 雑誌
- 現代社会学研究 (ISSN:09151214)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.61-84, 2022 (Released:2022-08-01)
- 参考文献数
- 7
本稿では,コロナ禍初期に北海道札幌市で「子ども宅食」活動を展開した子育て支援NPO が実施したアンケート調査のデータから,一斉休校や登園・外出自粛要請が子育て家庭に与えた影響について考察した。休校・自粛要請により,家庭内で母子だけで過ごす時間が長時間化する中,幼い子どもを持つ母親たちは,子どもの食事作りや家庭学習,生活習慣や健康面への配慮など,普段よりも多くのケアや教育,家事負担を抱え,就業面や経済的な面でも困難に直面していた。本調査では,母親回答者の9割以上が休校・自粛の影響で「困った」と回答し,特に就園・就学期の子どもがいる親でその割合が高かった。また,ストレス程度が高い回答者は普段よりも休校中ほど多く,特に普段からストレスが強い層ほど休校中のストレスや困り感も強いことが確認された。保育・子育て支援の利用が一般化した社会で,「子育ての社会化」機関がその機能を一斉に停止・縮小したことの影響は大きく,また,コロナ禍では家族ケアや女性の就労に関する平時からの問題もより深刻な形で顕在化した。こうした中で本調査では,食事提供型の支援が家事負担や食費の軽減にとどまらず,孤立感の緩和や精神的支援としても有用であることが示唆された。子育て問題の予防と解消のためには,緊急時も含めて「子育ての社会化」体制を機能させることとともに,公的支援の「切れ目」を埋める民間の活動に対する支援の拡充も重要である。
4 0 0 0 地球環境の変動と文明の盛衰ー新たな文明のパラダイムを求めてー
平成2年9月14日に平成3年度より出発する重点領域研究「地球環境の変動と文明の盛衰」(104 文明と環境)の第1回研究打合わせ会を京都市で実施した。出席者は研究代表者伊東俊太郎ほか13名。全体的な研究計画の打合わせと,今後の基本方針の確認ならびにニュ-スレタ-用の座談を実施した。平成2年12月1日,雑誌ニュ-トン12月号(教育社刊)誌上にて本重点領域研究にかかわる特集を組み,発表した。重点領域研究の広報活動の一環として研究計画の概要を朝日新聞11月6日付,毎日新聞1月3日付,日本経済新聞2月11日付に発表した。平成3年2月21日,ニュ-スレタ-「文明と環境」出発準備号を刊行し,関係者に配布した。内容は対談梅原猛・伊東俊太郎,座談安田喜憲ほか5名,特集,速水融ほかで31ペ-ジの構成である。大変好評で,日本経済新聞3月21日付にも紹介され,多くの研究者,企業関係者から問い合わせが殺到した。平成3年2月28日,第2回研究打合わせ連絡会を京都市で開催した。出席者は伊東俊太郎ほか重点領域計画研究関係者58名であった。午前中全体集会を実施し,午後分科会に分かれて,今後の研究方針について話し合った。今回の研究打合わせにより,58名もの参加者を得たことは,4月以降の本格的な出発に明かるい希望を抱かせた。平成3年3月8日,文部省にて重点領域研究審査会を実施し,公募研究の候補を選定した。
- 著者
- 町田 昌彦 岩田 亜矢子 山田 進 乙坂 重嘉 小林 卓也 船坂 英之 森田 貴己
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会和文論文誌 (ISSN:13472879)
- 巻号頁・発行日
- pp.J20.036, (Released:2022-01-26)
- 参考文献数
- 53
- 被引用文献数
- 4
We estimate the monthly discharge inventory of tritium from the port of Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant (1F) from Jun. 2013 to Mar. 2020 using the Voronoi tessellation scheme, following the tritium monitoring inside the port that started in Jun. 2013. As for the missing period from the initial month, Apr. 2011 to May 2013, we calculate the tritium discharge by utilizing the ratio of tritium concentration to 137Cs concentration in stagnant contaminant water during the initial direct run-off period to Jun. 2011 and the discharge inventory correlation between tritium and 137Cs for the next-unknown continuous-discharge period up to May 2013. From all the estimated results over 9 years, we found that the monthly discharge inventory sharply dropped immediately after closing the seaside impermeable wall in Oct. 2015 and subsequently coincided well with the sum of those of drainage and subdrain etc. By comparing the estimated results with those in the normal operation period before the accident, we point out that the discharge inventory from the 1F port after the accident is not very large. Even the estimation for the year 2011 is found to be comparable to the maximum of operating pressurized water reactors releasing relatively large inventories in the number of digits. In the national level, the total domestic release inventory in Japan significantly decreased after the accident owing to the operational shutdown of most plants. Furthermore, 1F and even the total Japanese discharge inventory are found to be minor compared with those of nuclear reprocessing plants and heavy-water reactors on a worldwide level. From the above, we suggest that various scenarios can be openly discussed regarding the management of tritium stored inside 1F with the help of the present estimated data and its comparison with the past discharge inventory.
4 0 0 0 OA 師範学校編纂『地理初歩』とその底本
- 著者
- 齋藤 元子
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.78, no.6, pp.413-425, 2005-05-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 23
学制公布の翌年1873(明治6)年に文部省の指示を受けて,師範学校が編纂した最初の官製地理教科書『地理初歩』は,アメリカ人コーネルの地理書を底本にしたといわれている.コーネルの地理書は,5段階のシリーズ教科書と自然地理書の6種類がある.これまでCornell's Primary Geographyを底本に, Cornell's High-School Geographyを補足本に用いたという説と, Cornell's First Steps in Geographyを底本にしたという説が提示されているが,詳細な検証はなされていない.本稿は,『地理初歩』の底本を明らかにすることを目的として,『地理初歩』の本文ならびに挿入図のすべてを, 6種類のコーネルの地理書と対比させ,文章の引用関係を調査した.その結果,『地理初歩』の底本はCornell's Primary Geographyであり, Cornell's First Steps in Geography, Cornell's lntermediate Geography, Cornell's Grammar-School Geographyを補足に用いたことが明らかになった.
4 0 0 0 OA 明治期~昭和期に活躍した江藤春代の編物普及活動と日本における編物の変遷
- 著者
- 北川 ケイ
- 出版者
- 一般社団法人 日本家政学会
- 雑誌
- 日本家政学会誌 (ISSN:09135227)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.12, pp.783-799, 2020 (Released:2020-12-19)
- 参考文献数
- 188
江藤春代は, 1924年に編物記号である「合理的符号」を考案した編物講師である. 明治期~昭和期に渡る彼女の人生は, 明治維新後の秩禄処分, 日露戦争, 第一次世界大戦, 関東大震災, 日中戦争, 第二次世界大戦と幾度となく政策の変更と戦争や災害に見舞われた. 家族, 特に男手を失う環境が常にあった. 彼女は, 編物で自立 (精神的な自立も含む) すること, 家族の為に編むことに焦点を合わせて正しい編物技術の普及活動を多種多様に行った. 災害や戦争後の復興時における経験を活かした江藤春代の編物普及活動に着目して変遷にまとめた. 江藤春代の編物普及活動を辿ることによって見えてきたことは, 日本女性が生業としての副業を願い, 家庭の平和を願い, 生きる為に編物技術を取得し内職を得ようとしていたことがわかる. 正しい編物技術を身に着ければ, 災害戦争の影響下にある毛糸, 綿糸等様々な糸を使いこなすことが可能になり, 生計を助ける手立てになったのである. 編物は, 欧米では, 教養としての技術であったが, 日本にとっては生きる為の技術であったのである.
4 0 0 0 OA アカデミック・ハラスメントの構造 ―指導?ハラスメント?―
- 著者
- 北仲 千里 横山 美栄子 金子 雅臣 進藤 聡彦
- 出版者
- 一般社団法人 日本教育心理学会
- 雑誌
- 教育心理学年報 (ISSN:04529650)
- 巻号頁・発行日
- vol.61, pp.304-313, 2022-03-30 (Released:2022-11-16)
- 参考文献数
- 2
- 被引用文献数
- 1
4 0 0 0 OA 日本語の量を表す形容詞の意味体系と量カテゴリーの普遍性
- 著者
- 久島 茂
- 出版者
- The Linguistic Society of Japan
- 雑誌
- 言語研究 (ISSN:00243914)
- 巻号頁・発行日
- vol.1993, no.104, pp.49-91, 1993-09-25 (Released:2007-10-23)
- 参考文献数
- 27
This paper argues that basic dimension adjectives are divided into two classes according to whether they refer to “object” or “place”. The former are systematized according to the feature of the shape of the object, and the latter the relation of the place to its surroundings.There are conceptually six dimension categories of objects. We will use the following signs analogized to phonetic signs: [A] stands for the volume of a box, [I] the length of a rod, [U] the thickness of a board, [E] the extension of a board, [O] the thickness of a rod, and [_??_] the width of a belt.The six categories have the following system and hierarchy which are based on the developement of visual perceptions and oppositions between categories: (As to the length of sides, let longest_??_intermediate_??_shortest).[P] → [Q] means that if a language contains words /Q/ (=a pair of antonyms), it must also contain words /P/. (The kernal meaning of words /p/ (/Q/) is [P] ([Q]).) Some dialects in Kyusyu have only /A/ /I/ /U/, which correspond to [A•E•0•_??_], [I], [U] respectively. Standard Japanese has /A/ / I / /U/ /0/ corresponding to [A•E], [I] [U], [O•_??_] respectively.