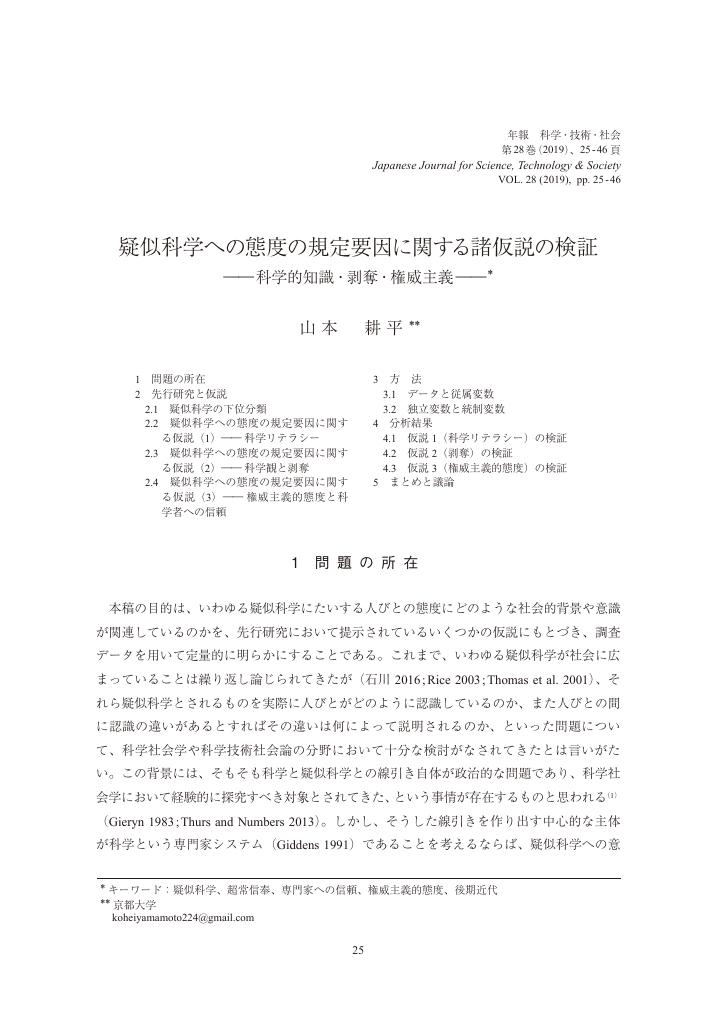4 0 0 0 OA 授業方法が学力と学力の階層差に与える影響 ――新学力観と旧学力観の二項対立を超えて――
- 著者
- 須藤 康介
- 出版者
- 日本教育社会学会
- 雑誌
- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)
- 巻号頁・発行日
- vol.81, pp.25-44, 2007-11-30 (Released:2015-07-14)
- 参考文献数
- 24
- 被引用文献数
- 3
The purpose of this paper is to grasp how science is taught in Japanese junior high schools, and to show the influences of teaching methods on academic achievement and differences between social classes, using the data of TIMSS2003.It is found that science lessons in junior high schools are taught using four teaching methods: the experiment-investigation method, society-daily life method,homework-examination method, and hearing-practice method, as well as combinations of these methods. They are not trade-offs, but are linked to one another. In this paper, the author emphasizes the following three points regarding the influence of these four teaching methods.Firstly, looking at two of the “Traditional Views on Academic Achievement,” the hearing-practice method tends to improve academic achievement, while the homework-examination method may degrade it. Thus, a return to the “Tradi tional Views on Academic Achievement” could potentially lead to an unintended further decline in academic achievement. Secondly, the society-daily life method, which is based on the “New Views on Academic Achievement,” may promote increased differences of academic achievement between social classes, but does not bring about a decline of academic achievement. Thirdly, an addi tional effect takes place on academic achievement when the hearing-practice method and society-daily life method are combined.Based on these findings, the author suggests that we should not regard “New Views on Academic Achievement” and “Traditional Views on Academic Achievement” as being in binary opposition. Rather, we should discover effective teaching methods (and a combination of them) among many kinds of “new” and “traditional” teaching methods.
4 0 0 0 OA 疑似科学への態度の規定要因に関する諸仮説の検証 科学的知識・剥奪・権威主義
- 著者
- 山本 耕平
- 出版者
- 科学社会学会
- 雑誌
- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, pp.25-46, 2019 (Released:2020-09-30)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 小林 庸平 中田 大悟
- 出版者
- 日本財政学会
- 雑誌
- 財政研究 (ISSN:24363421)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.147-169, 2016 (Released:2021-08-28)
- 参考文献数
- 24
社会保険料負担の増加は,日本国内の投資を阻害し,空洞化を促進しているのではないかとの指摘があるが,それを実証的に分析した研究は,国内外を問わず非常に乏しい。本稿では,健康保険料データと企業データをマッチングさせた個票データを用いて,企業の健康保険料負担が,設備・研究開発・対外直接投資にどのような影響を与えているかを実証的に分析した。分析の結果,健康保険料負担の増加は,⑴企業の国内投資を一定程度抑制させた可能性がある,⑵研究開発投資には大きな影響は与えていない,⑶海外進出を行うかどうかの意思決定には影響を与えていないものの,既に海外進出を行っている企業の対外直接投資を増加させた可能性がある,といった結果が得られた。
- 著者
- 木村 理子
- 出版者
- 東京大学大学院総合文化研究科超域文化科学専攻表象文化論
- 雑誌
- 表象文化論研究 (ISSN:13485423)
- 巻号頁・発行日
- no.2, pp.60-94, 2003-03
4 0 0 0 OA シニア世代の社会活動継続を支えるうれしい言葉の検討
- 著者
- 有吉 美恵 錦谷 まりこ
- 出版者
- 日本社会心理学会
- 雑誌
- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)
- 巻号頁・発行日
- vol.37, no.1, pp.50-60, 2021-07-31 (Released:2021-07-31)
- 参考文献数
- 28
This study focuses on how the imbalance between efforts and rewards relates to active participation in the social and labor markets of senior citizens who retire from the front line of corporate organizations, and it aims to clarify how others’ words are related to their intention to continue in social activities. We asked 104 senior and pre-senior individuals who participated in social activities to describe the words they were happy with and asked about effort-reward imbalance and their intention to leave. Text mining and analysis using KH Coder revealed that there was a difference in characteristic words between when receiving rewards and when no rewards were received. When receiving rewards, words that evaluated work and behavior were seen as characteristic words. On the other hand, when there was no reward, words that focused on the existence of individuals were also seen as characteristic words. This suggests the importance of paying attention to and recognizing the senior generation’s attitudes and actions rather than merely providing monetary rewards.
4 0 0 0 OA 一酸化炭素中毒間歇型の病態と予防
- 著者
- 藤田 基 鶴田 良介
- 出版者
- 一般社団法人 日本集中治療医学会
- 雑誌
- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.3, pp.373-379, 2013-07-01 (Released:2013-08-09)
- 参考文献数
- 35
一酸化炭素(CO)中毒の間歇型は,CO中毒患者の亜急性期から慢性期における予後を規定する病態である。その病態は,COによる直接的・間接的な虚血による神経細胞傷害と脱髄性傷害が主体と考えられる。診断は急性CO中毒後,無症状期を経て40日以内に出現する失見当識,記銘力障害などの多彩な精神神経症状による。また積極的に複数の検査を組み合わせた評価バッテリーを行う方法がある。間歇型発症率は0~46%と報告されており,予測因子としては意識障害の有無,年齢36歳以上,血中carboxyl hemoglobin(COHb)濃度25%以上,CO曝露から治療開始まで24時間経過していること,白血球増多などが報告されているが,一定したものはない。また予防として高気圧酸素治療が有効である可能性があるが,その効果について未だ議論が分かれており,今後のさらなる症例の蓄積,検討が必要である。
- 著者
- Ikuko MAEDA Akemi K. HORIGANE Mitsuru YOSHIDA Yoshihiro AIKAWA
- 出版者
- Japanese Society for Food Science and Technology
- 雑誌
- Food Science and Technology Research (ISSN:13446606)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.2, pp.107-116, 2009 (Released:2009-06-16)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 11 16
Magnetic resonance imaging (MRI) was employed to observe water diffusion within two kinds of buckwheat noodles (marunuki, sarashina) and one kind of wheat noodle during boiling and holding. The apparent diffusion coefficients for water were statistically estimated with Fick's second law using a rectangular cylinder model, and the changes in moisture distribution in buckwheat and wheat noodles were compared quantitatively. Apparent diffusion coefficients of water in noodles during boiling were 4 to 7 × 10–6 cm2/sec. The diffusion coefficients of water in buckwheat noodles during boiling were higher than those in wheat noodles. For each noodle, the diffusion coefficient during holding after boiling was 2 to 3 × 10–7 cm2/sec and constant through the holding time, from 30 to 120 min. The diffusion coefficients in buckwheat noodles during holding were lower than those in wheat noodles. These results show that, as compared with wheat noodles, buckwheat noodles cooked more rapidly and lost favorable texture during holding.
4 0 0 0 OA 旭川アイヌの祖霊祭祀「イアレ」 (地理学特集号)
- 著者
- 小嶋 響 コジマ ヒビキ Hibiki Kojima
- 雑誌
- 史苑
- 巻号頁・発行日
- vol.53, no.1, pp.71-83, 1992-07
- 著者
- 深町 花子 荒井 弘和 石井 香織 岡 浩一朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本認知・行動療法学会
- 雑誌
- 行動療法研究 (ISSN:09106529)
- 巻号頁・発行日
- vol.43, no.1, pp.61-69, 2017-01-31 (Released:2017-10-11)
- 参考文献数
- 27
- 被引用文献数
- 1
本研究の目的はアクセプタンスおよびマインドフルネスに基づいた介入のスポーツパフォーマンス向上への効果について系統的に概観することであった。国内外の複数のデータベースにて「マインドフルネス」や「パフォーマンス」などの関連する検索語を用いて検索を行い、11件の研究を採択した。日本では該当する研究は見られなかった。ほとんどの研究では(n=8)スポーツパフォーマンスを高めるうえでポジティブな結果が得られていた。残りの3件のうち2件でもフォローアップ期にはスポーツパフォーマンスが向上していた。本研究の結果より、アクセプタンスおよびマインドフルネスに基づいた介入は、スポーツパフォーマンス向上に効果的であると思われる。ただし、国内では全く研究が実施されていない。今後は日本のアスリートにおいてもアクセプタンスおよびマインドフルネスに基づいた介入研究が必要である。
4 0 0 0 OA [名古屋逓信局]管内電気事業要覧
4 0 0 0 OA 藤野可織作品における<怪物>の系譜 -『いやしい鳥』から『ドレス』まで-
- 著者
- 磯﨑 美聡
- 出版者
- 早稲田文芸・ジャーナリズム学会
- 雑誌
- 早稲田現代文芸研究 (ISSN:21858616)
- 巻号頁・発行日
- vol.13, pp.41-54, 2023-03-13
- 著者
- 黒崎 宏貴 吉村 健佑
- 出版者
- 日本公衆衛生学会
- 雑誌
- 日本公衆衛生雑誌 (ISSN:05461766)
- 巻号頁・発行日
- vol.67, no.8, pp.501-508, 2020-08-15 (Released:2020-09-01)
- 参考文献数
- 13
- 被引用文献数
- 1
目的 第3期医療費適正化計画では「糖尿病の重症化予防」,「特定健康診査・特定保健指導の推進」,「後発医薬品の使用促進」,「医薬品の適正使用」により1人当たり外来医療費の地域差縮減を目指している。この目標を達成するためには都道府県単位での具体的な取組目標を設定することが重要となる。厚生労働省はレセプト情報・特定健診等情報データベース(NDB)を構築し公表している。これまでNDBオープンデータを活用して糖尿病医療費の地域差について解析した研究は行われていない。本研究では,NDBオープンデータを活用し,入院外糖尿病医療費について,ジペプチジルペプチダーゼ-4(DPP-4)阻害薬の処方箋料の地域差およびスルホニル尿素薬(SU薬),グリニド薬,ビグアナイド薬,α-グルコシダーゼ阻害薬,チアゾリン誘導体薬の後発医薬品の使用割合の地域差,都道府県別の糖尿病透析予防指導管理料の地域差について解析した。そして,都道府県差が示されている人口当たり糖尿病医療費との相関を解析することで地域差の要因について解析し,地域差縮減に向けたデータを提示する。方法 第2回NDBオープンデータ(集計対象:平成27年度レセプト情報および平成26年度特定健康診査情報)を使用した。本研究では,糖尿病についての入院外医療費のみを研究対象とした。NDBオープンデータより各要因を抽出し,人口当たり糖尿病医療費との関係を評価するためにピアソンの積率相関係数rを算出した。相関係数の検定にはStudentのt検定を用いてP値を算出した。P値は0.05未満の場合を有意水準とした。結果 人口当たりDPP-4阻害薬処方箋料が高い都道府県では糖尿病医療費が高い傾向にあることが明らかになった(r=0.40, P=0.0048)。また,SU薬の後発医薬品の使用割合が高い都道府県では糖尿病医療費が低い傾向にあることが分かった(r=−0.43, P=0.0023)。糖尿病の重症化予防という点について,糖尿病透析予防指導管理料は糖尿病医療費との相関は認められなかった(r=−0.096, P=0.52)。結論 本研究では,NDBオープンデータを用いることで,DPP-4阻害薬処方箋料やSU薬後発医薬品の使用割合に地域差があり,人口当たり糖尿病医療費に関与している可能性が示唆された。本研究により,糖尿病医療費の都道府県差縮小に向けた政策立案にNDBオープンデータが有用であることが示唆された。
4 0 0 0 OA 終わらない「かわいそうなぞう」問題 ―受け止めの諸相から見えてくる課題群―
- 著者
- 西山 利佳
- 出版者
- 東京学芸大学国語科教育学研究室
- 雑誌
- 学芸国語教育研究 (ISSN:09139362)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.2, 2017 (Released:2018-10-24)
4 0 0 0 OA "9時10分前"は,何時何分? 2020 年「日本語のゆれに関する調査」から(1)
- 著者
- 塩田 雄大
- 出版者
- NHK放送文化研究所
- 雑誌
- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)
- 巻号頁・発行日
- vol.70, no.12, pp.36-53, 2020 (Released:2021-04-16)
「日本語のゆれに関する調査」の結果について報告をおこなう。調査結果から、次のようなことを指摘する。 ▼「9時10分前」というのは「9時10分の数分前」であるという解釈のしかたが、若い年代になるほど多くなっている。 ▼「私情」ということばについて、20代を中心に「私的な事情」のことも指しうるという考え方が多くなっている。 ▼「船は2日おきに来ます」という言い方について、ある日に船が来たら次に来るのはその3日後になるという解釈は少なく、2日後になるという解釈が最も多かった。 ▼「言う」について、「[ユウ]と発音する」と意識している人が多かったが、文字で書かれたとおり「[イウ]と発音する」と意識している人の数も決して少なくなかった。 ▼「ぬかった道」ではなく「ぬかるんだ道」と言うという人が最も多く、この回答に集中する割合は若い年代になるほど顕著に多くなっている。 ▼「足らない」「もの足らない」ではなく「足りない」「もの足りない」と言うという人が、いずれも多い。年代が若くなるほどこの回答に集中する割合が多くなっている。 ▼「はし・はじ」(端)は、全体としては「はし」が最も多いが、若い年代になるほど「はじ」もある程度多くなるような分布になっている。
4 0 0 0 車内でのPC作業が起因となる車酔い緩和手法の提案
- 著者
- 畑山 諒太 佐藤 健哉
- 雑誌
- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020-ITS-83, no.16, pp.1-6, 2020-11-17
近年,自動運転に関する研究が盛んに行なわれいる.車が自動運転化されることにより,運転者は不要となり,車内環境は大幅に変化することが予想される.今まで必要だった運転者は一乗員となり,車内ではより自由な時間を過ごすことができるようになる.そういった状況において,車内ではPC作業をする機会が増え,車酔いが増加すると予想される.走行している車内で画面を注視すると,内耳から脳に送られてくる信号と眼球から脳に送られてくる信号に不一致が生じ,脳が「異常」と判断し,自律神経が不安定になる.そして,自律神経が不安定になった結果,吐き気や頭痛といった車酔いの症状が表れるためである.本研究は,車内でのPC作業が起因となる車酔いの緩和手法を提案する.PC利用者に,車が次の交差点で曲がる右左折方向を音声で事前に告知し,旋回方向へ頭部を傾けさせる手法である.先行研究から,運転者の旋回方向への頭部運動は車酔い緩和につながることが示されており,PC作業による車酔いの緩和が期待できる.本研究では,提案手法の事前告知による車酔い緩和を検証するため,検証実験での事前告知タイミングのパターンを以下の3つとした.「右左折のためのブレーキを踏む1秒前とハンドルを回す1秒前に2回」,「ハンドルを回す1秒前に1回」,「告知なし」の3パターンである.実験参加者には走行車内で,告知回数2回,告知回数1回,告知なしのそれぞれのパターンで,車内でPC作業を行ってもらう.そして,アンケート,心拍数,唾液アミラーゼ活性値,タイピングタスクの評価結果から提案手法の優位性を示した.
4 0 0 0 OA 高齢者の薬物治療における残薬発生・長期化の要因に関する質的研究
- 著者
- 中村 友真 岸本 桂子 山浦 克典 福島 紀子
- 出版者
- 日本社会薬学会
- 雑誌
- 社会薬学 (ISSN:09110585)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, no.1, pp.2-9, 2016-06-10 (Released:2016-07-06)
- 参考文献数
- 22
- 被引用文献数
- 6
To consider what pharmacists can do to prevent patients from having leftover prescription drugs, we conducted a qualitative study about the various causes behind the unused drugs. We interviewed one male and four female home-care patients who had leftover prescription drugs that pharmacists detected via their home visiting service. The Grounded Theory Approach was used for analysis, and two types were identified as “exogenous factors that cause confusion for the patient” and “patient’s personal thoughts and feelings.” “Exogenous factors that cause confusion” involved eight factors, including unsuitable dosing schedule for lifestyle, complex timing for taking medicine, and inadequate support for enhancing patients’ compliance. These factors were divided into [problems with prescription] and [difficult changes to manage]. In “patient’s personal thoughts and feelings,” 16 concepts were identified and their broader concepts comprised six categories: [distrust of drugs], [taking a positive view about one’s own non-compliance], [psychological distance from medical staff], and others. It was assumed that there would be a perception gap of compliance between patients and medical staff. Moreover, patients affirmed their poor compliance and they did not see the occurrence of leftover drugs as a problem. Additionally, psychological distance from medical staff prevents patients from consultation. Therefore, pharmacists should check patients’ compliance for each drug as well as any medical problems. Knowing patients’ inherent mind revealed by this study, the pharmacist can assist medication alongside patients and contribute to the early prevention of unused drugs.
4 0 0 0 OA 胎生期および小児期におけるストレスと将来の精神神経疾患
- 著者
- 周 至文 羅 聡 小山 隆太
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬理学会
- 雑誌
- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)
- 巻号頁・発行日
- vol.146, no.5, pp.263-267, 2015 (Released:2015-11-11)
- 参考文献数
- 49
胎生期および小児期は神経回路形成における重要な時期である.この時期における各種のストレスは,ストレスホルモンや炎症因子,そして神経細胞活動の異常などを介して,神経細胞の遺伝子発現や神経回路の形成に異常をもたらし,さまざまな脳疾患に罹患するリスクを上昇させると推察される.本総説では,胎生期および小児期におけるストレスと将来の精神神経疾患発症との関係性について,我々の研究成果を交えながら紹介する.特に,各疾患のモデル動物を用いた研究によって発見された神経生物学的メカニズムに着目しながら議論する.
- 著者
- 岸本 千佳司 Chikashi Kishimoto
- 雑誌
- AGI Working Papers Series
- 巻号頁・発行日
- vol.2015-08, pp.1-39, 2015-03
本研究の目的は,台湾半導体産業における垂直分業体制,とりわけファウンドリ・ビジネス(ウェハプロセスの受託製造業)の発展について,その歴史的経緯,成功要因を業界トップ企業のTSMCの事例を念頭に置き分析することである。その結果,ファウンドリの台頭は決して簡単に実現されたわけではなく,その時々に指摘された「限界」や「困難」をビジネスモデル上のイノベーションによって乗り越えてきたことが示される。ファウンドリ・ビジネスの発展史は少なくとも3段階に分けられる。①「ファウンドリ・ビジネスの初期モデル(1987年~1990年代半ば)」-専業ファウンドリの基本的な利点を活かした比較的単純なサービスの提供が特徴。当初,既存大手メーカーからのおこぼれ的仕事が主で,誕生間もないファブレス業の成長を刺激した。②「ファウンドリ・ビジネスの成長:技術・生産能力の発展(1990年代後半頃から)」-顧客ファブレスの成長(その背景にあるPC・周辺機器等の応用製品市場の成長)と連動。また,プロセス技術を体化した新式製造装置の導入で技術的キャッチアップが容易となった。工場拡充による規模の経済実現も進められた。③「ファウンドリ・ビジネスの成熟:ソリューション・ビジネスへ(2000年代以降)」-ファウンドリ・ビジネスは,専業の基本的利点,先端プロセス開発推進,大規模生産能力構築に加え,顧客への設計支援サービスを核とするソリューション提供に着手した。その内容は年々豊富になり,半導体バリューチェーン上の他の専門企業および主要顧客とのパートナーシップの構築・深化が進んだ。現在までに,専業の利点を徹底的に追求し,同時に顧客ファブレスやアライアンス・パートナーを含む他の専業企業の成長を促し,相互に支えあい,各分野でのイノベーションを刺激し,全体として半導体設計・製造のエコシステムを繁栄させる上で,ファウンドリは,IDM中心の産業システムよりも有効であったことが認められる。加えて,近年ファウンドリ業界でも企業間の格差が目立ってきている。本研究では,それをファウンドリ・ビジネスにおける成長の「正の循環」が形成された結果として捉え,この具体的状況をTSMCと台湾ファウンドリ2番手UMCとの業績比較を通して検討する。2000年代初頭まで概ね互角と看做されていた両社は,その後,収益性で差が開いていった。設備投資額や研究開発支出でも差が出ており,これが先端プロセス開発と量産立ち上げの遅速に影響を与えている。生産能力拡充と設備稼働率でもTSMCがUMCを上回っている。これがまた収益性の違いに繋がり,次第に格差が拡大していったのである。
4 0 0 0 OA 出島(長崎)における19世紀の気象観測記録
- 著者
- 財城 真寿美 塚原 東吾 三上 岳彦 コネン グンター
- 出版者
- The Association of Japanese Geographers
- 雑誌
- 地理学評論 (ISSN:13479555)
- 巻号頁・発行日
- vol.75, no.14, pp.901-912, 2002-12-01 (Released:2008-12-25)
- 参考文献数
- 42