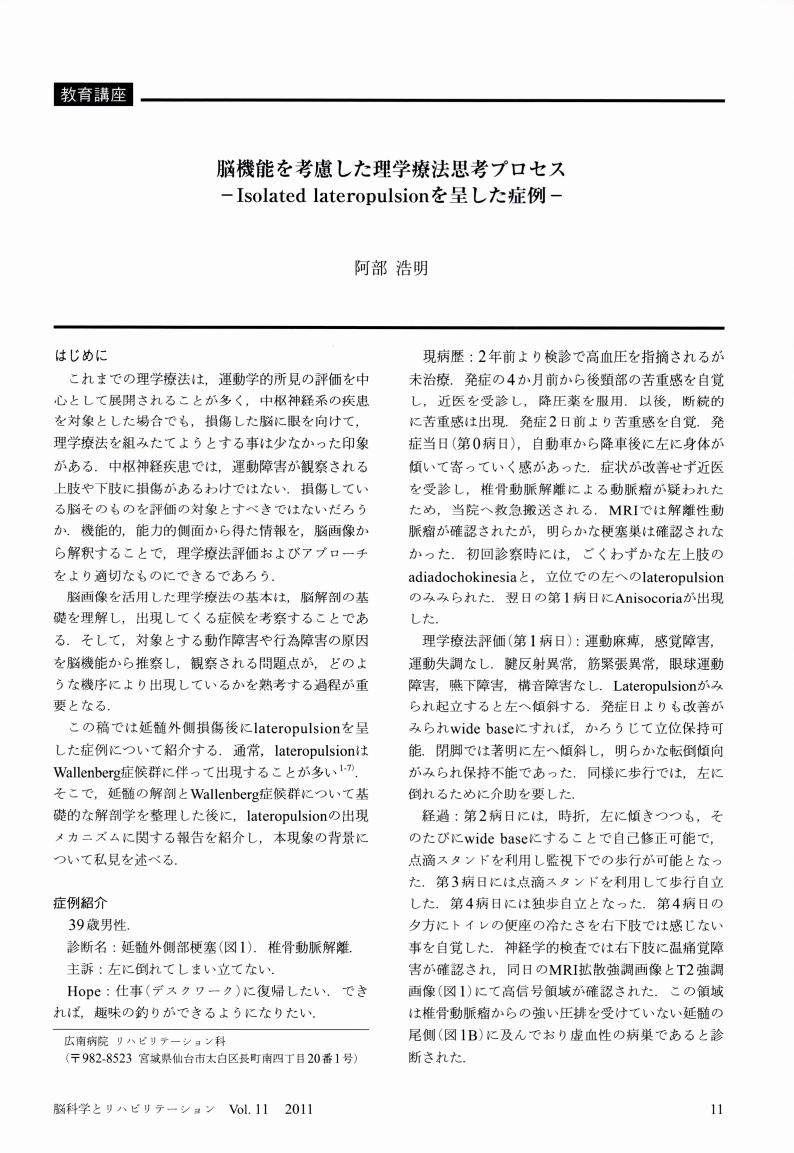3 0 0 0 OA デュアルユース研究の何が問題なのか 期待価値アプローチを作動させる
- 著者
- 片岡 雅知 河村 賢
- 出版者
- 科学社会学会
- 雑誌
- 年報 科学・技術・社会 (ISSN:09199942)
- 巻号頁・発行日
- vol.30, pp.35-66, 2021-06-30 (Released:2022-07-01)
3 0 0 0 OA NEWAGE: 方向に感度をもつダークマター直接検出実験
- 著者
- 中村 輝石 身内 賢太朗
- 出版者
- 一般社団法人 日本物理学会
- 雑誌
- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)
- 巻号頁・発行日
- vol.71, no.7, pp.469-473, 2016-07-05 (Released:2016-10-04)
- 参考文献数
- 9
- 被引用文献数
- 1
宇宙の構成要素のうちで通常の物質は5%でしかない.―宇宙マイクロ波背景輻射の観測などの結果から導かれた,最新の宇宙像である.残りの1/4は銀河や銀河団を重力的に結び付けている「暗黒物質」と呼ばれる未知の物質,3/4は宇宙の加速膨張の源として働く「暗黒エネルギー」と呼ばれる未知のエネルギーである.暗黒物質の存在は,1930年代に銀河団中での銀河の運動を説明するために,ツビッキーによって提唱された.その後1970年代になると銀河の回転曲線を説明するために,銀河を「ハロー」のように取り囲む暗黒物質の存在が示唆された.2000年代には,宇宙マイクロ波背景輻射の観測等によって,宇宙全体での暗黒物質の量が議論されるようになってきた.このように銀河,銀河団,宇宙全体という異なった階層での存在が確認されている暗黒物質であるが,その正体は全く不明である.暗黒物質の性質を解明すべく世界中で様々な実験的研究が行われている.それらは大別して 1)加速器で暗黒物質を生成し信号を検出する(加速器実験) 2)銀河中心などにとらえられた暗黒物質同士の対消滅からの信号を検出する(間接探索) 3)暗黒物質と通常の物質との反応を検出する(直接探索)の3つに分類することができる.本稿で取り扱うNEWAGE(NEw generation WIMP search with an Advanced Gaseous tracking device Experiment)実験は直接探索実験のひとつである.暗黒物質直接探索実験では,我々の住む天の川銀河にとらえられている暗黒物質と,検出器を構成する通常の物質との反応で検出器が得るエネルギーを検出する.ただし,こうした「検出器」は我々の身の回りに多く存在するガンマ線や中性子などの通常の物質に対しても反応し,バックグラウンドとなる(通常の粒子線検出器を,暗黒物質直接探索のための検出器に「借用」しているといった表現の方が近い).バックグラウンドの多くは宇宙から飛来する「宇宙線」と呼ばれる粒子線に由来するため,宇宙線を避けるために直接探索実験は地下深い実験室で行うことが一般的である.NEWAGEは,東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の地下実験環境を,共同利用により使用させて頂いている.右下の図に暗黒物質と太陽系の銀河内での運動を模式的に示す.暗黒物質は銀河内でランダムな方向に運動していると考えられており,太陽系の速度で一定の方向に運動する我々には「暗黒物質の風」が吹き付けているように感じられる.NEWAGEではこれまでの直接探索実験で得られるエネルギー情報に加えて,反跳された粒子の飛跡という情報を加えることで暗黒物質の到来方向の検出を可能とし,暗黒物質直接検出の強い証拠を得ることを目指す.NEWAGEは,国内で開発された三次元飛跡検出器を用いた実験で,方向に感度をもつ暗黒物質探索分野で世界をリードしている.今回新たに製作した検出器「NEWAGE-0.3b′」を用いて神岡地下実験室で観測を行い,これまでに得られていた制限を約一桁更新した.現在は,感度を向上して暗黒物質の検出を目指すために,検出器起源のバックグラウンド低減を進めている.
3 0 0 0 OA 精神治療対話における問題認識のための悩み文及び心情文抽出システム
- 著者
- 花房 竜馬 荒木 健治
- 出版者
- Japan Society for Fuzzy Theory and Intelligent Informatics
- 雑誌
- 知能と情報 (ISSN:13477986)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.4, pp.860-871, 2021-11-15 (Released:2021-11-15)
- 参考文献数
- 13
近年,精神疾患患者の増加に伴い,精神治療におけるカウンセリングの需要が急増している.しかし,精神治療への抵抗感や費用の高さから治療を受けられず,疾患の悪化により自ら命を絶つケースも少なくない.現時点では,心理療法士と同等の精神治療を代行できる対話システムは存在しない.本論文では,心理療法における問題の認識を自動的に行うために,相談者の発話から悩み文,心情文を自動抽出する手法を考案した.その手法を基に,ルールベースによる抽出システム,類似性による抽出システム,分類器による抽出システムを開発した.各抽出システムにより性能評価実験を行った結果,分類器による抽出システムがF値0.73と最も良い性能を示し,提案手法の有効性が示された.
3 0 0 0 OA 日本人の起源と進化-集団ゲノム学的アプローチによる縄文人由来ゲノム領域の抽出-
日本人男性345名のY染色体の全塩基配列決定を行い系統解析を行った。その結果、本土日本人男性では35.4%の頻度で観察されるが、他の東アジア人には観察されないクレードを発見した。遺伝子系図解析によって過去の人口変動を推定したところ、縄文時代晩期から弥生時代にかけて人口が急激に減少したことが示された。47都道府県の全ゲノムSNPアリル頻度データを用いて解析を行い、都道府県間の遺伝的差異は、縄文人に由来するゲノム成分の程度と地理的位置関係によって説明できることを見出した。興味深い発見の一つは、近畿地方及び四国地方の人々が遺伝的に中国・漢民族に近いことであった。
3 0 0 0 OA ロシア=ウクライナ戦争とカザフスタン ―ロシアのウクライナ侵攻には反対も、しかし……―
- 著者
- 地田 徹朗
- 出版者
- 名古屋外国語大学ワールドリベラルアーツセンター
- 雑誌
- Artes MUNDI = Artes MUNDI (ISSN:24321125)
- 巻号頁・発行日
- no.8, pp.77-86, 2023-03-31
- 著者
- 阿部浩明
- 出版者
- 脳機能とリハビリテーション研究会
- 雑誌
- 脳科学とリハビリテーション (ISSN:13490044)
- 巻号頁・発行日
- vol.11, pp.11-22, 2011 (Released:2018-10-30)
3 0 0 0 OA 富士山信仰にみる比奈赫夜姫 ― その成立と終焉 ―
- 著者
- 植松 章八
- 出版者
- 富士学会
- 雑誌
- 富士学研究 (ISSN:24330310)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, no.1, pp.17-37, 2014-12-31 (Released:2022-12-16)
- 参考文献数
- 1
- 著者
- 出口 康夫
- 出版者
- 理想社
- 雑誌
- 理想 (ISSN:03873250)
- 巻号頁・発行日
- no.689, pp.144-160, 2012
- 著者
- Megumi Hara Yuichiro Nishida Keitaro Tanaka Chisato Shimanoe Kayoko Koga Takuma Furukawa Yasuki Higaki Koichi Shinchi Hiroaki Ikezaki Masayuki Murata Kenji Takeuchi Takashi Tamura Asahi Hishida Mineko Tsukamoto Yuka Kadomatsu Keitaro Matsuo Isao Oze Mikami Haruo Kusakabe Miho Toshiro Takezaki Rie Ibusuki Sadao Suzuki Hiroko Nakagawa-Senda Daisuke Matsui Teruhide Koyama Kiyonori Kuriki Naoyuki Takashima Yasuyuki Nakamura Kokichi Arisawa Sakurako Katsuura-Kamano Kenji Wakai
- 出版者
- Japan Epidemiological Association
- 雑誌
- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)
- 巻号頁・発行日
- pp.JE20210155, (Released:2021-10-16)
- 参考文献数
- 49
- 被引用文献数
- 6
Background: Little is known about whether insufficient moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) and longer sedentary behavior (SB) are independently associated with estimated glomerular filtration rate (eGFR) and CKD, whether they interact with known risk factors for CKD, and the effect of replacing sedentary time with an equivalent duration of physical activity on kidney function.Methods: We examined the cross-sectional association of MVPA and SB with eGFR and CKD in 66,603 Japanese cohort study in 14 areas from 2004 to 2013. MVPA and SB were estimated using a self-reported questionnaire, and CKD was defined as eGFR<60 mL/min/1.73 m2. Multiple linear regression analyses, logistic regression analyses, and an isotemporal substitution model were applied.Results: After adjusting for potential confounders, higher MVPA and longer SB were independently associated with higher eGFR (Pfor trend MVPA<0.0001) and lower eGFR (Pfor trend SB<0.0001), and a lower odds ratio (OR) of CKD (adjusted OR of MVPA≥20 MET·h/day: 0.76 [95%CI: 0.68–0.85] compared to MVPA<5 MET·h/day) and a higher OR of CKD (adjusted OR of SB≥16 h/day: 1.81 [95%CI: 1.52–2.15] compared to SB<7 h/day), respectively. The negative association between MVPA and CKD was stronger in men, and significant interactions between sex and MVPA were detected. Replacing 1 hour of SB with 1 hour of physical activity was associated with about 3 to 4% lower OR of CKD.Conclusions: These findings indicate that replacing SB with physical activity may benefit kidney function, especially in men, adding to the possible evidence on CKD prevention.
3 0 0 0 OA フランスのテロリズム対策
- 著者
- 高山直也
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)
- 巻号頁・発行日
- no.228, 2006-05
3 0 0 0 OA 構文獲得における対称性バイアスの有効性
- 著者
- 的場 隆一 中村 誠 東条 敏
- 出版者
- 日本認知科学会
- 雑誌
- 認知科学 (ISSN:13417924)
- 巻号頁・発行日
- vol.15, no.3, pp.457-469, 2008 (Released:2010-02-15)
- 参考文献数
- 31
- 被引用文献数
- 3
It is well known that the symmetry bias much accelerates the process of vocabulary learning, especially in infants' first language acquisition where they easily tend to connect objects with their names. However, the grammar learning is another important aspect of language acquisition. In this study, we contended that the symmetry bias also would help to learn grammar rules. We employed Kirby's model (Iterated Learning Model; ILM) in which the parental speakers uttered sentences with their semantic representaions and children guessed the background grammar in their minds; in turn, children became new parents and generated sentences in the following generation. We revised this model to include utterances without semantics. We have shown that children could abduce the meanings from utterances by the symmetry bias, and that they acquired the same language with smaller number of learning data by computer simulation.
3 0 0 0 OA アミノ酸単独液の熱安定性
- 著者
- 後藤 泰子 柴田 ときは
- 出版者
- The Japan Society of Home Economics
- 雑誌
- 家政学雑誌 (ISSN:04499069)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.7, pp.428-431, 1970-12-20 (Released:2010-03-09)
- 参考文献数
- 1
Samples of thirteen kinds of amino acid solution (1/100 mol) were heated for 120 min. at the pressure of 1kg/cm2, making analysis of amino acids by Beckmann/Spinco Amino Acid Analyzer 120-B every 10 min. to provide their heat decomposition graph.The work has yielded the following results.Glutamic acid has the highest heat decomposition rate of 68% in 120 min. The second highest decomposition rate, 8%, is obtained with tryptophan. Other amino acids, however, have the rates of under 3%.The experimental formulae which approximate the heat decomposition curves of respective amino acids wera pursued and differences in the modes of decomposition were discussed. The periods of half decay of both glutamic acid and tryptophan were obtained.
3 0 0 0 OA 上下加速度の周波数分布と船酔いの関係に関する一考察
- 著者
- 岸本 雅裕
- 出版者
- 社団法人 日本船舶海洋工学会
- 雑誌
- 関西造船協会論文集 (ISSN:13467727)
- 巻号頁・発行日
- vol.2002, no.238, pp.238_191-238_196, 2002 (Released:2004-02-27)
- 参考文献数
- 16
O’Hanlon et al. gave a full rage data on motion sickness for single frequency sinusoidal vertical motions. When it is used for ship motion, there are some problems because ship motion distributes in wide frequency range. In this paper, motion sickness in two frequency vertical motions and ship motions distributed in wide frequency rage are studied. And it is shown that vertical acceleration components in higher frequency range may have bigger effects on motion sickness than estimated from O’Hanlon’s data
3 0 0 0 OA 日本語での音韻認識障害が認められない英語学習困難例
- 著者
- 蔦森 英史 宇野 彰 春原 則子 金子 真人 粟屋 徳子 狐塚 順子 後藤 多可志 片野 晶子
- 出版者
- 日本音声言語医学会
- 雑誌
- 音声言語医学 (ISSN:00302813)
- 巻号頁・発行日
- vol.50, no.3, pp.167-172, 2009 (Released:2010-04-06)
- 参考文献数
- 20
- 被引用文献数
- 6 2 7
発達性読み書き障害は複数の認知的要因が関与しているとの報告がある (Wolf, 2000;宇野, 2002;粟屋, 2003) . しかし, 読み, 書きの学習到達度にそれぞれの情報処理過程がどのように影響しているのかはまだ明確になっていない. 本研究では全般的な知能は正常 (VIQ110, PIQ94, FIQ103) だが漢字と英語の書字に困難を示した発達性書字障害例について報告する. 症例は12歳の右利き男児である. 要素的な認知機能検査においては, 日本語での音韻認識力に問題が認められず, 視覚的記憶力のみに低下を示した. 本症例の漢字書字困難は過去の報告例と同様に, 視覚性記憶障害に起因しているものと考えられた. 英語における書字困難の障害構造については, 音素認識力に関しては測定できなかったが, 日本語話者の英語読み書き学習過程および要素的な認知機能障害から視覚性記憶障害に起因する可能性が示唆された.
3 0 0 0 OA 喉頭組織の男性ホルモンとの関わり
- 著者
- 竹山 勇 漆畑 保 堤 康一朗
- 出版者
- 日本喉頭科学会
- 雑誌
- 喉頭 (ISSN:09156127)
- 巻号頁・発行日
- vol.5, no.1, pp.6-11, 1993-06-01 (Released:2012-09-24)
- 参考文献数
- 14
A marked difference in the incidence of laryngeal carcinoma between male and female has been widely unknown. The reason to this, however, has been unknown. In this connection, the affinity of the laryngeal tissue for androgen hormone was investigated in the present study. An auto radio-graphic study was conducted with the tissue of normal laryngeal mucosa and that of moderately differentiated squamous cell carcinoma of the larynx. 3H-T and its metabolites were found in the nuclei of epithelial cells of male vocal folds and some parts of male laryngeal carcinoma tissues. This suggest the existence of some effect of testosterone on the cell nuclei of these tissues. Quantitative analyses of the intracellular distribution of radioactivity conducted by means of the silver grain counting method showed that approximately 60-70% of 3H-T were located in the nuclear compartment of cancer cells of small size and the epithelium of the vocal fold near the basement membrane. The ABC method demonstrated a positive reaction in the nuclei of laryngeal carcinoma cells and the laryngeal muscle in males.These findings suggest that human laryngeal tissue, especially the vocal fold tissue, and laryngeal carcinoma cells may be one of the target organs for androgenic steroids and that androgen plays an important role in the carcinogenetic process of normal laryngeal tissue.
3 0 0 0 OA 副鼻腔真菌症の診断と治療
- 著者
- 吉川 衛
- 出版者
- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会
- 雑誌
- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.5, pp.629-635, 2015-05-20 (Released:2015-06-11)
- 参考文献数
- 21
- 被引用文献数
- 7
近年, 日常診療において副鼻腔真菌症に遭遇する機会が増加してきているが, その理由として, 患者の高齢化はもとより, 糖尿病患者の増加や, ステロイド, 免疫抑制薬, 抗悪性腫瘍薬などの使用により免疫機能の低下した患者の増加などが考えられる. さらに, 副鼻腔で非浸潤性に増殖した真菌に対する I 型・III 型のアレルギー反応や T 細胞応答などにより病態が形成される, アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎のような特殊な副鼻腔真菌症も報告されるようになった. 急性および慢性浸潤性副鼻腔真菌症の治療は, 外切開による拡大手術が第一選択となり, 手術による病巣の徹底的な除去と, 抗真菌薬の全身投与を行う. 慢性非浸潤性副鼻腔真菌症の治療は, 抗真菌薬の全身投与は不要で, 手術により真菌塊を除去した上で病的な粘膜上皮を切除すると予後は良好である. アレルギー性真菌性鼻副鼻腔炎の治療は, 現在のところ手術療法が第一選択で, 術後のステロイドの全身投与が有効とされている. このように, いずれのタイプにおいても副鼻腔真菌症では手術治療が中心となるため, 耳鼻咽喉科医が的確に診断し, 治療を進めていくことが求められる. 2014年4月に「深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2014年版」が刊行され, 副鼻腔真菌症について治療アルゴリズムが示されている. 非浸潤性以外の副鼻腔真菌症はどれも発症頻度の高い疾患ではないため, エビデンスレベルの高い報告は国内外を問わず存在しなかったが, これまで蓄積された報告に基づくこの治療アルゴリズムが, 今後の診療の指標となると考える.
3 0 0 0 OA ハイゼンベルクとゲーテ
- 著者
- 山崎 和夫
- 出版者
- ゲーテ自然科学の集い
- 雑誌
- モルフォロギア: ゲーテと自然科学 (ISSN:0286133X)
- 巻号頁・発行日
- vol.2004, no.26, pp.15-25, 2004-10-30 (Released:2010-02-26)
- 参考文献数
- 10
3 0 0 0 OA 熊祭りの起源
- 著者
- 春成 秀爾
- 出版者
- 国立歴史民俗博物館
- 雑誌
- 国立歴史民俗博物館研究報告 = Bulletin of the National Museum of Japanese History (ISSN:02867400)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, pp.57-106, 1995-03-31
熊祭りは,20世紀にはヨーロッパからアジア,アメリカの極北から亜極北の森林地帯の狩猟民族の間に分布していた。それは,「森の主」,「森の王」としての熊を歓待して殺し,その霊を神の国に送り返すことによって,自然の恵みが豊かにもたらされるというモチーフをもち,広く分布しているにもかかわらず,その形式は著しい類似を示す。そこで人類学の研究者は,熊祭りは世界のどこかで一元的に発生し,そこから世界各地に伝播したという仮説を提出している。しかし,熊祭りの起源については,それぞれの地域の熊儀礼の痕跡を歴史的にたどることによって,はじめて追究可能となる。熊儀礼の考古学的証拠は,熊をかたどった製品と,特別扱いした熊の骨である。熊を,石,粘土,骨でかたどった製品は,新石器時代から存在する。現在知られている資料は,シベリア西部のオビ川・イェニセイ川中流域,沿海州のアムール川下流域,日本の北海道・東北地方の3地域に集中している。それぞれの地域の造形品の年代は,西シベリアでは4,5千年前,沿海州でも4,5千年前,北日本では7,8千年前までさかのぼる。その形状は,3地域間では類似よりも差異が目につく。熊に対する信仰・儀礼が多元的に始まったことを示唆しているのであろう。その一方,北海道のオホーツク海沿岸部で展開したオホーツク文化(4~9世紀)には,住居の奥に熊を主に,鹿,狸,アザラシ,オットセイなどの頭骨を積み上げて呪物とする習俗があった。それらの動物のうち熊については,仔熊を飼育し,熊儀礼をしたあと,その骨を保存したことがわかっている。これは,中国の遼寧,黄河中流域で始まり,北はアムール川流域からサハリン,南は東南アジア,オセアニアまで広まった豚を飼い,その頭骨や下顎骨を住居の内外に保存する習俗が,北海道のオホーツク文化において熊などの頭骨におきかわったものである。豚の頭骨や下顎骨を保存するのは,中国の古文献によると,生者を死霊から護るためである。オホーツク文化ではまた,サメの骨や鹿の角を用いて熊の小像を作っている。熊の飼育,熊の骨の保存,熊の小像は,後世のアイヌ族の熊送り(イヨマンテ)の構成要素と共通する。熊の造形品は,オホーツク文化に先行する北海道の続縄文文化(前2~7世紀)で盛んに作っていた。続縄文文化につづく擦文文化(7~11世紀)の担い手がアイヌ族の直系祖先である。彼らは,飼った熊を送るというオホーツク文化の特徴ある熊祭りの形式を採り入れ,自らの発展により,サハリンそしてアムール川下流域まで普及させたことになろう。それに対して,西シベリアでは,狩った熊を送るという熊祭りの形式を発展させていた。そして,長期にわたる諸民族間の交流の間に,熊祭りはその分布範囲を広げる一方,そのモチーフは類似度を次第に増すにいたったのであろう。
3 0 0 0 OA 形態素解析における関西弁の自動認識
- 著者
- 廣川 純也 深澤 拓海 松村 冬子 原田 実
- 雑誌
- 研究報告自然言語処理(NL) (ISSN:21888779)
- 巻号頁・発行日
- vol.2016-NL-225, no.3, pp.1-7, 2016-01-15
言語処理システムの基盤技術である形態素解析では既に高い精度が実現されている.しかし,方言やネットスラングなどの標準語から外れた日本語文を解析する際,それらの表現が形態素解析で用いる辞書に登録されていないため,正しく解析ができない場合がある.本研究では方言の中でも特に関西弁を含む日本語文の形態素解析の精度向上を目指し,形態素解析器 JUMAN に関西弁特有の語の表記や活用形,連接規則を追加することで,従来は未知語として処理されていた語の正しい解析を実現する.