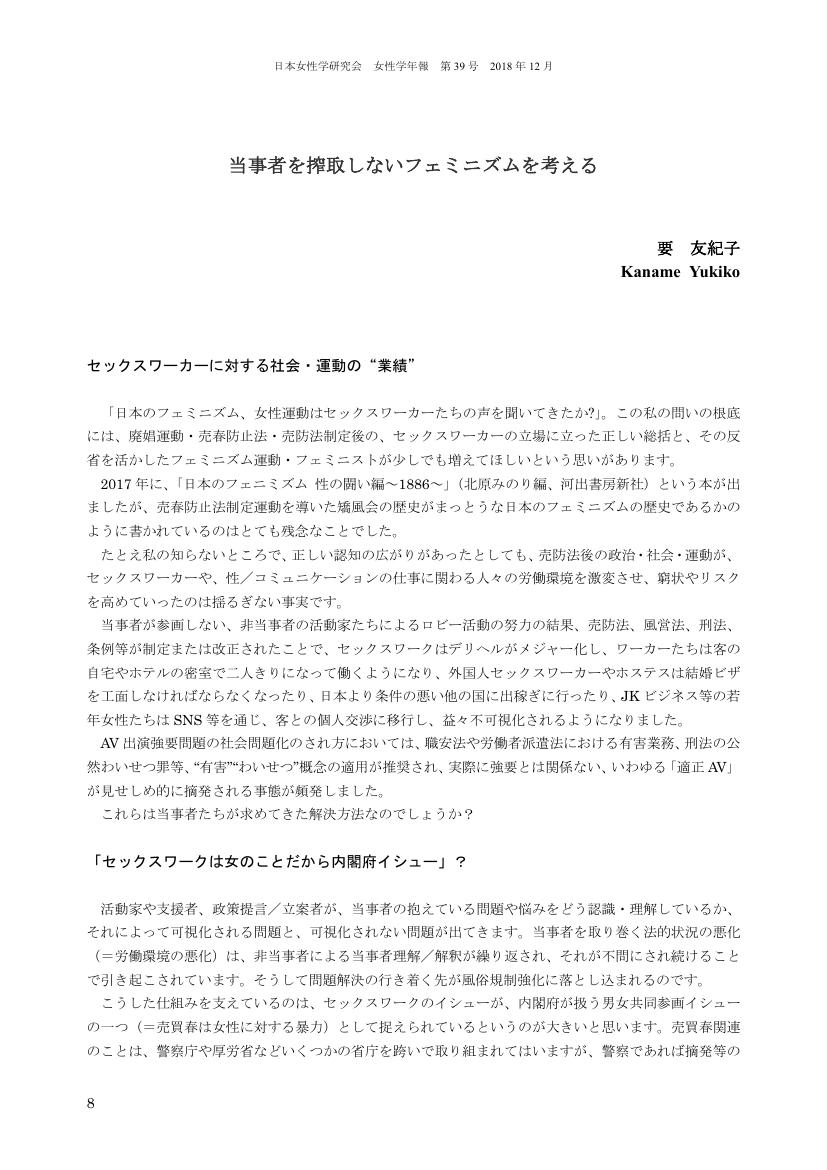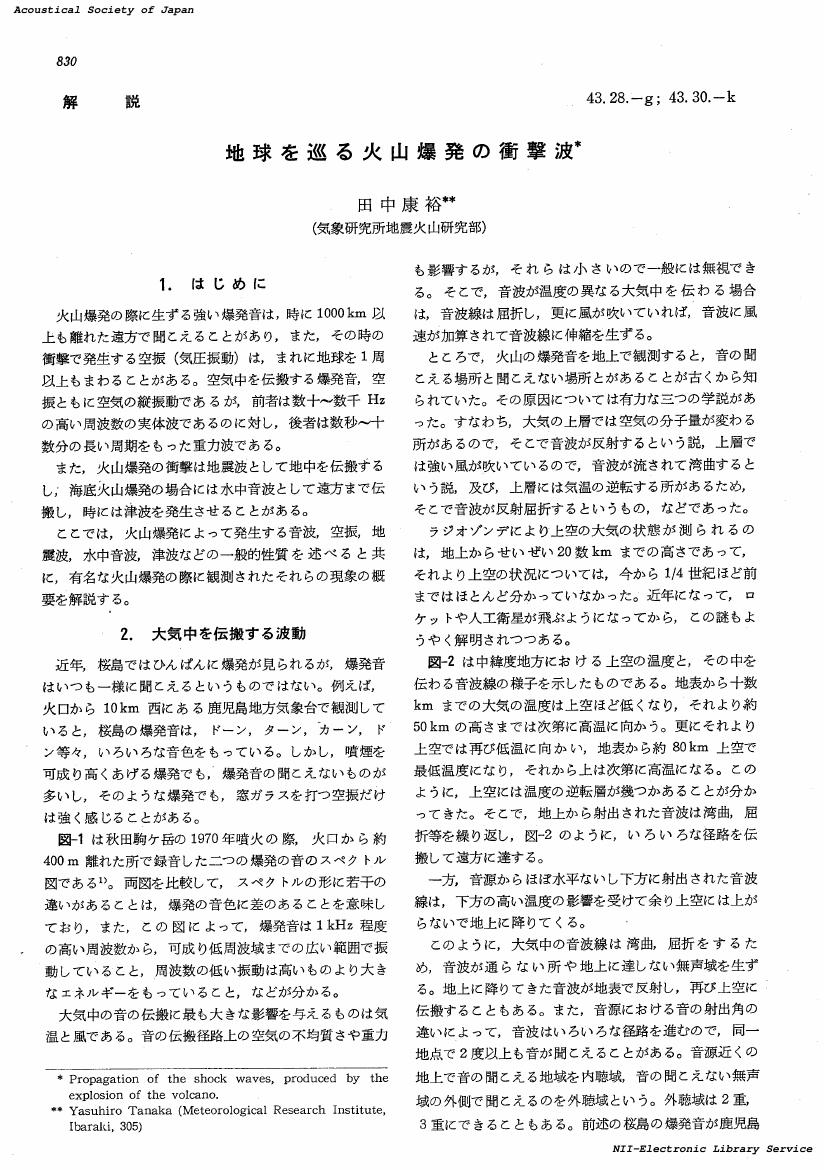79 0 0 0 OA 東日本の海跡湖 「北浦」 に流入する農業水路における遡上魚類の季節変化
- 著者
- 浜野 隼 木村 将士 加納 光樹
- 出版者
- 日仏海洋学会
- 雑誌
- La mer (ISSN:05031540)
- 巻号頁・発行日
- vol.60, no.3-4, pp.25-35, 2022-12-28 (Released:2023-01-14)
Seasonal changes in upstream movements of fishes were examined in an irrigation ditch flowing into an inland-sea lake, Kitaura, Ibaraki Prefecture, eastern Japan, from April 2020 to March 2021. A total of 1,762 individuals representing 6 families and 12 species were collected using small fyke nets throughout the study period. The most abundant species were the gobiid Rhinogobius sp. OR(70.8% of the total number of individuals collected), the gobiid Gymnogo- bius urotaenia(22. 5%), the cobitid Misgurnus anguillicaudatus(2. 7%), the gobiid Tridentiger brevispinis(1.7%)and the cyprinid Gnathopogon elongatus elongatus(1.1%). Based on the body sizes, developmental stages and seasonal occurrence patterns of fishes sampled, it is highly likely that the irrigation ditch would be used as a place of temporary growth and spawning by several fishes including amphidromous gobiids.
79 0 0 0 OA 当事者を搾取しないフェミニズムを考える
- 著者
- 要 友紀子
- 出版者
- 日本女性学研究会
- 雑誌
- 女性学年報 (ISSN:03895203)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, pp.8-11, 2018 (Released:2019-01-22)
- 参考文献数
- 2
79 0 0 0 OA 線維筋痛症は和漢診療学では瘀血病態を呈する
- 著者
- 藤永 洋 高橋 宏三 嶋田 豊
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.146-150, 2009-06-30 (Released:2016-03-31)
- 参考文献数
- 14
- 被引用文献数
- 1
Japanese Oriental (Kampo) medicine has been widely used to treat fibromyalgia. In Kampo medicine, the determination of therapy is based on “Sho” (diagnosis of Kampo medicine). However there have not been sufficient studies of the “Sho” in fibromyalgia. We therefore investigated the “Sho” in fibromyalgia by assessing the “Sho” in 27 patients with fibromyalgia: 20 females and 7 males, mean age 52.9±15.6 (27 to 89). The result showed 3 patients with “Jissho” (hyperfunction of body energy), 15 patients with “Kyojitsukansho” (medium of hyperfunction/hypofunction of body energy) and 9 patients with “Kyosho” (hypofunction of body energy). All patients showed “Kikyo” (deficiency of “Ki” (vital energy)), “Kiutsu” (insufficient circulation of “Ki” and “Ki” stasis in an organism)”, and “Oketsu” (insufficient blood-circulation and blood stasis). The “Oketsu” score of the 15 patients using Terasawa’s criteria were 27.0~67.0, mean score 43.5±10.1. Nine of the 15 patients showed severe “Oketsu”, which was indicated by a total score of more than 40 points. This finding indicated an intimate correlation with fibromyalgia and“Oketsu”.Several reports showed the presence of abnormal microcirculation in fibromyalgia. Abnormal microcirculation is considered to be related to “Oketsu”. Therefore, we considered that “Oketsu” is an important pathological condition to investigate and treat with fibromyalgia.
79 0 0 0 OA 未婚の若年女性の中絶経験 現実的制約と関係性の中で変化する,多様な径路に着目して
- 著者
- 安田 裕子 荒川 歩 髙田 沙織 木戸 彩恵 サトウ タツヤ
- 出版者
- 日本質的心理学会
- 雑誌
- 質的心理学研究 (ISSN:24357065)
- 巻号頁・発行日
- vol.7, no.1, pp.181-203, 2008 (Released:2020-07-06)
中絶を選択した女性は,生命の喪失や,社会的に容認されないというスティグマに苦しむ。そのために,自らの経験や気持ちを誰かに語ることが困難であり,孤独のうちに悲嘆のプロセスを辿る人が多い。本稿では,20 歳前後の未婚の時期に中絶を経験し,中絶手術後 2 年以上経過した女性 3 名を対象にインタビューを行い,その経験を聴きとった。そして,中絶を選択する未婚の若年女性が何に迷い苦しんでいるのかを,その経験の固有の意味を含めて,周囲の人々が理解できるように,描き出すことを目指した。分析枠組みとしては,複線径路・等至性モデル(TEM)を用いた。妊娠していることに気づき,医師の診断を受け,中絶手術をし,現在に至るまでの時間経過のなかで,社会的制約やパートナーなどの周囲の人々の影響をうけつつ変化する,中絶経験の多様性を捉えた。彼女たちは,パートナーの辛さに配慮し,また中絶したことによる罪悪感に苛まれ,それゆえ周囲の人々に話すことができず,実質的・精神的な支えを得られにくい辛い状態であった。また,中絶をすることで,元の状態に戻ることを望んでいる人もいた。しかし,時間が経過した後,彼女たちは,妊娠と中絶を,自分の人生における大事な経験として受け容れようと変化していた。
79 0 0 0 OA 「叡智」を活かす―UNSCEAR2020報告書
- 著者
- 服部 美咲
- 出版者
- 一般社団法人 日本原子力学会
- 雑誌
- 日本原子力学会誌ATOMOΣ (ISSN:18822606)
- 巻号頁・発行日
- vol.63, no.8, pp.623_2, 2021 (Released:2021-08-10)
79 0 0 0 OA ロボコンにおける妨害ロボットの歴史と今後のロボコン
- 著者
- 浜田 光誉 鈴木 新一
- 出版者
- 自動制御連合講演会
- 雑誌
- 自動制御連合講演会講演論文集 第54回自動制御連合講演会
- 巻号頁・発行日
- pp.76, 2011 (Released:2012-03-09)
妨害ロボットは,相手との駆け引きや心理戦をもたらし,手動ロボットは,操縦者の行いによっては,ドラマを生む.こういった要素は,参加者と観客を楽しませる.妨害ロボットと手動ロボットは,面白いコンテストのためには必要である.しかし,2009年にロボコンのルールが変更され,それ以降,妨害ロボットは製作できなくなった.手動ロボットだけが,ゲームに面白さをもたらすことになった.しかし,外国の二チームによって,完全に自動的に動く,「自動化された」手動ロボットを製作された.自動化された手動ロボットはミスをしない.そこにハプニングは生まれない.観客は,ハプニングを楽しめなくなってしまった.ハプニングよって作られたドラマは,テレビ番組とって,とても重要である.自動化された手動ロボットの製作を認めるべきだろうか?
79 0 0 0 OA 都市の緑と被災樹
- 著者
- 山下 脩二
- 出版者
- 日本生気象学会
- 雑誌
- 日本生気象学会雑誌 (ISSN:03891313)
- 巻号頁・発行日
- vol.45, no.1, pp.29-32, 2008 (Released:2008-06-13)
- 参考文献数
- 2
79 0 0 0 OA 計量テキスト分析およびKH Coderの利用状況と展望
- 著者
- 樋口 耕一
- 出版者
- 日本社会学会
- 雑誌
- 社会学評論 (ISSN:00215414)
- 巻号頁・発行日
- vol.68, no.3, pp.334-350, 2017 (Released:2018-12-31)
- 参考文献数
- 29
- 被引用文献数
- 13 16
筆者はテキスト型 (文章型) データの分析方法「計量テキスト分析」を提案し, その方法を実現するためのフリーソフトウェア「KH Coder」を開発・公開してきた. 現在ではKH Coderを利用した応用研究が徐々に蓄積されつつあるように見受けられる. したがって現在は, ただ応用研究を増やすのではなく, KH Coderがいっそう上手く利用され, 優れた応用研究が生み出されることを企図しての努力が重要な段階にあると考えられる. そこで本稿では, 現在の応用研究を概観的に整理することを通じて, どのようにKH Coderを利用すればデータから社会学的意義のある発見を導きやすいのかを探索する.この目的のために本稿では第1に, 計量テキスト分析およびKH Coder提案のねらいについて簡潔に振り返る. 第2に, KH Coderを利用した応用研究について概観的な整理を試みる. ここではなるべく優れた応用研究を取り上げて, 方法やソフトウェアをどのように利用しているかを記述する. また, なるべく多様なデータを分析対象とした研究を取り上げることで, 応用研究を概観することを目指す. 第3に以上のような整理をもとに, 計量テキスト分析やKH Coderを上手く利用するための方策や, 今後の展開について検討する.
79 0 0 0 OA 地球を巡る火山爆発の衝撃波
- 著者
- 田中 康裕
- 出版者
- 一般社団法人 日本音響学会
- 雑誌
- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)
- 巻号頁・発行日
- vol.40, no.12, pp.830-836, 1984-12-01 (Released:2017-06-02)
- 被引用文献数
- 1
- 著者
- 佐藤 翔 楠本 千紘 服部 亮 大菅 真季 浅井 理沙 河野 真央 久山 寮納
- 出版者
- 情報知識学会
- 雑誌
- 情報知識学会誌 (ISSN:09171436)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.3, pp.223-252, 2018-09-30 (Released:2018-10-19)
- 参考文献数
- 37
本研究では百科事典記事の信憑性判断に「情報源がWikipediaであること」が与える影響を明らかにすることを目的に,日本の大学生を対象とする調査を実施した.Wikipedia日本語版と日本大百科全書JapanKnowledge版双方に存在する6つの項目について,それぞれレイアウトをそのままにした 場合と,レイアウト情報を除去した場合を用意し,どちらの方が正確であると思うかを被験者に尋ねた.分析の結果,回答者の多くはレイアウト情報が残っており,見た目からWikipediaであることが判断で きる場合には,日本大百科全書の方がWikipedia日本語版よりも正確であると判断した.一方,レイアウト情報が除去された場合,Wikipedia日本語版の方が日本大百科全書よりも正確であると判断した者が多かった.情報源がWikipediaであること自体が,記事内容の信憑性判断に影響すると考えら れる.
79 0 0 0 OA 琉球列島の河川急流域に生息するハゼ科ヨシノボリ属魚類2新種
- 著者
- 鈴木 寿之 大迫 尚晴 木村 清志 渋川 浩一
- 出版者
- Kanagawa Prefectural Museum of Natural History (Kanagawa Prefectural Museum)
- 雑誌
- 神奈川県立博物館研究報告(自然科学) (ISSN:04531906)
- 巻号頁・発行日
- vol.2020, no.49, pp.7-28, 2020 (Released:2020-03-31)
- 被引用文献数
- 2
琉球列島の河川急流域に生息するハゼ科ヨシノボリ属魚類2 新種、Rhinogobius yaima と R. yonezawai を記載した。Rhinogobius yaima(ヤイマヒラヨシノボリ:新称)は縦列鱗数40–43、脊椎骨数26、第1 背鰭棘数6、頭部はよく縦偏し、体と尾柄は細長い、雄の第1 背鰭低く後端は倒しても第2 背鰭起部に達しない、腹鰭第5 軟条は普通最初に5 分岐する、胸鰭基底、腹鰭起部前方、腹部腹中線周辺は無鱗である、生時もしくは生鮮時に側頭部から第2 背鰭起部にかけての背面に橙色または赤色の2 縦線がある、胸鰭基底に1 暗色楕円形斑がある、雄の尾鰭に橙色の4 横点列がある、雌の尾鰭基底に垂直に並んだ1 対の長方形または円形の黒色斑があるなどの特徴で同属他種から区別できる。Rhinogobius yonezawai(ケンムンヒラヨシノボリ:新称)は縦列鱗数35–39、脊椎骨数26、雄の第1 背鰭は高く烏帽子形、その第2・3 棘が最長で糸状に伸長しないものの倒すと第2 背鰭第1 から第4 軟条基部に達する、腹鰭第5 軟条は最初に4 分岐する、胸鰭基底、腹鰭起部前方、腹部腹中線周辺もしくは腹部腹中線前半周辺は無鱗である、胸鰭基底に黒色楕円形斑がある、生時もしくは生鮮時に側頭部から第1 背鰭下方にかけての背面に橙色または赤色の2 縦線がある、胸鰭基底に1 暗色楕円形斑がある、雄の尾鰭に橙色または赤色の6–8 垂線がある、雌の尾鰭基底に横Y 字形の1 黒色斑があるなどの特徴で同属他種から区別できる。
79 0 0 0 OA 日本の子どもの貧困: 失われた「機会の平等」
- 著者
- 阿部 彩
- 出版者
- 公益財団法人 日本学術協力財団
- 雑誌
- 学術の動向 (ISSN:13423363)
- 巻号頁・発行日
- vol.14, no.8, pp.8_66-8_72, 2009-08-01 (Released:2011-03-03)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1 1
79 0 0 0 OA レニングラードの福者(ブラジェーンナヤ)クセーニヤ
- 著者
- 髙橋 沙奈美
- 出版者
- 日本宗教学会
- 雑誌
- 宗教研究 (ISSN:03873293)
- 巻号頁・発行日
- vol.91, no.3, pp.25-48, 2017-12-30 (Released:2018-03-30)
本稿はペテルブルグの聖クセーニヤに対する崇敬を事例として、人びとの日常生活の中で経験され、表現される「生きた宗教(lived religion)」が、社会主義時代にどのような主体によって維持され、いかに変容し、またいかに持続したかという問題を検討する。十八世紀末の帝都の下町に暮らしたといわれるクセーニヤは、十九世紀後半から二〇世紀にかけて、悩みや苦しみに寄り添い力を貸してくれる聖痴愚として、人びとに慕われ始めた。一九一七年の革命後、反宗教政策で教会が壊滅状態に陥り、祈?を依頼できる司祭がいなくなると、レニングラードの人びとはクセーニヤに「手紙」を書くことで崇敬を維持した。クセーニヤは過去の記憶ではなく、テロルや包囲戦の時期もレニングラードと共にある等身大の福者として意識された。また、帝政末期にすでに正教会にも認められていたクセーニヤ崇敬は、教会権力によって単なる民衆宗教として排斥されず、西側の世論を怖れたソ連政府も礼拝堂の破壊を思いとどまった。一九八八年の列聖は、信者たちにとって、革命以前の信仰生活の復活ではなく、ともに最も苦しい時代を生き抜いたクセーニヤの記念を意味したのである。
- 著者
- Kenta Ofuji Naomi Ogasawara
- 出版者
- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN
- 雑誌
- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.56-65, 2018-03-01 (Released:2018-03-01)
- 参考文献数
- 23
- 被引用文献数
- 5 5
In this paper, we study the effects of acoustic characteristics of spoken disaster warnings in Japanese on listeners' perceived intelligibility, reliability, and urgency. Our findings are threefold: (a) For both speaking speed and fo, setting them to normal (compared from slow/fast ({+}/{-}20%) for speed, and from low/high (+/- up to 36 Hz) for fo) improved the average evaluations for Intelligibility and Reliability. (b) For Urgency only, setting speed to faster (both slow to normal and normal to fast) or setting fo to higher (both low to normal and normal to high) resulted in an improved average evaluation. (c) For all of intelligibility, reliability, and urgency, the main effect of speaking speed was the most dominant. In particular, urgency can be influenced by the speed factor alone by up to 39%. By setting speed to fast (+20%), all other things being equal, the average perceived urgency raised to 4.0 on the 1–5 scale from 3.2 when the speed is normal. Based on these results, we argue that the speech rate may effectively be varied depending on the purpose of an evacuation call, whether it prioritizes urgency, or intelligibility and reliability. Care should be taken to the possibility that the respondent-specific variation and experimental conditions may interplay these results.
78 0 0 0 OA 慢性疲労症候群の病態機序とその治療
- 著者
- 渡邊 恭良 倉恒 弘彦
- 出版者
- 日本神経治療学会
- 雑誌
- 神経治療学 (ISSN:09168443)
- 巻号頁・発行日
- vol.33, no.1, pp.40-45, 2016 (Released:2016-05-20)
- 参考文献数
- 16
Chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME) is a disease characterized by chronic, profound, disabling, and unexplained fatigue. Although it is hypothesized that inflammation in the CNS is involved in the pathophysiology of CFS/ME, there were no direct evidence of neuroinflammation in patients with CFS/ME. Activation of microglia and/or astrocytes is related to neuroinflammation. Our recent PET study successfully demonstrated that neuroinflammation (activation of microglia and astrocytes) is present in widespread brain regions in patients with CFS/ME, and is associated with the severity of neuropsychological symptoms. Evaluation of neuroinflammation in patients with CFS/ME may be essential for understanding the core pathophysiology, as well as for developing the objective diagnostic criteria and effective medical treatments for CFS/ME. We here describe related pathophysiological findings and topics, and mention the diagnostic and therapeutic attempts through these findings in Japan.
78 0 0 0 OA 4~10世紀における気候変動と人間活動
- 著者
- 吉野 正敏
- 出版者
- 公益社団法人 東京地学協会
- 雑誌
- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)
- 巻号頁・発行日
- vol.118, no.6, pp.1221-1236, 2009-12-25 (Released:2010-03-23)
- 参考文献数
- 60
- 被引用文献数
- 3 2
The global climate is known to have been relatively warm during the period from the 4th to 10th centuries, although there were slightly different fluctuation patterns locally and regionally. The present article addresses these differences, analyzing the results of previous studies. The warm period is known in Europe as the Medieval Warm Period. Evidence in Japan is also found from the 4th century to the 11th century. Because historical age divisions differ between Europe and Japan, the peak of the Warm Period from the 7th to the 10th century is classified as part of the ancient period in Japan. Therefore, the Warm Period in Japan has been proposed to be called the Nara-Heian Warm Period, Heian Warm Period or Little Climatic Optimum. Based on the water level changes of Lake Shinji in Shimane Prefecture, the present article discusses the warmer climatic conditions in the Heian Period. It also examines old agricultural settlements in the Tohoku District, northern Honshu. People came from Hokkaido or northern Honshu and cultivated rice in the northeastern-most part of Honshu in the 1st century B.C. It is thought that the effect of the warm current branch flowing along the Japan Sea Coast and emerging on the Pacific side through the Tsugaru Straight had an influence on the distribution of rice cultivation at this early stage. Finally, the article shows that the northward shift of the power front of the Central Government (Yamato Chotei) during the 7th to the 9th centuries occurred about 70-80 years earlier in Dewa, an ancient state on the Japan Sea side of Tohoku District, than in Mutsu, also an ancient state on the Pacific side. It is interesting to note, however, that the speed of the northward shift was almost the same on both sides, even though there were different political powers, situations and problems on either side. It is suggested that the northward shift was affected by the warming on the broader space scale.
78 0 0 0 OA 潜水タンカーの経済性に関する研究
- 著者
- 黒田 七郎 田中 拓 上田 隆康 隆杉 憲行
- 出版者
- The Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers
- 雑誌
- 造船協會論文集 (ISSN:18842062)
- 巻号頁・発行日
- vol.1965, no.117, pp.292-309, 1965 (Released:2009-07-23)
- 参考文献数
- 15
It is well known that a submarine has the excellent propulsive performance in high speed. navigation in deeply submerged condition, but few papers have sufficiently shown economical feasibility of submarines for commercial use.The authors have studied about the feasibility of submarine tankers with a view to develop technical problems of commercial submarines. At first, the experiments on five submarine tanker models with the circular and rectangular hull sections were performed by method of three-component measurements at Mejiro No. 2 Tank.Examining the resistance, stability, floating draft and general arrangement of the submarine tankers, the authors chose the ST-2 type rectangular hull form as best for the submrine tanker. The lines of the ST-2 type hull form was shown in Fig. 3The ST-2 type submarine tankers with various dead weights and shaft horse powers were designed and their investment, operation cost, annual profit, freight rate per dead weight and capital recovery factor were calculated. The results of this study were summarized in Fig. 19 to 23. The best submarine tanker in the point of view of commercial feasibility was 40, 000 tons in dead weight and 20, 000 horse powers in shaft horse power under restrained condition within 14 meters in maximum floating draft. On the contrary to the previous opinions, was shown the fact that the submarine tankers would not be very fast than present conventional tankers. As shown in Fig. 23, the submarine tanker would not have commercial feasibility without drastically decreased cost of nuclear power plants.
78 0 0 0 OA 供用不可まで劣化した軍艦島の鉄筋コンクリート造建築物の補修・補強・保存
- 著者
- 野口 貴文
- 出版者
- 公益社団法人 日本コンクリート工学会
- 雑誌
- コンクリート工学 (ISSN:03871061)
- 巻号頁・発行日
- vol.56, no.3, pp.218-226, 2018 (Released:2019-03-01)
- 参考文献数
- 5
- 被引用文献数
- 1
長崎市からの委託により「供用不可まで劣化破損が進行したコンクリート構造物の補修・補強工法に関する研究委員会」が2015~2016年度に設置された。軍艦島は,2014年に国の史跡指定を受け,2015年に世界文化遺産の構成資産として登録されたため,委員会では,廃墟と化して残存する著しく劣化した鉄筋コンクリート造建築物群の保存方策に関して,技術的・文化財的な観点から様々な検討がなされた。特に,保存優先順位の高い3号棟,16号棟および65号南棟に対しては,具体的な補修方法,補強方法,および補修工事・補強工事の施工方法に関して具体的な検討がなされた。本稿は,それらの概要について取り纏めたものである。
78 0 0 0 OA 2. 腎不全患者に集中発症したスギヒラタケ脳症
- 著者
- 下条 文武 成田 一衛
- 出版者
- 一般社団法人 日本内科学会
- 雑誌
- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)
- 巻号頁・発行日
- vol.95, no.7, pp.1310-1315, 2006-07-10 (Released:2009-03-27)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
平成16年9月中旬以後, 新潟県北部の血液透析患者に原因不明の急性脳症が多発し, 死亡例も発生した. 私どもは, 関連病院の透析担当主治医から, 発症者のなかにスギヒラタケ摂取後に発症した症例があるとの情報を得たので, この事実に注目し, スギヒラタケ摂取との関連性について全国の日本腎臓学会員に情報提供を呼びかけた. その結果, スギヒラタケ摂取と急性脳症の発症に強い関連がある32症例の情報を得, 致死率が約30%に及ぶ重篤な臨床経過をとる脳症であることがわかった.