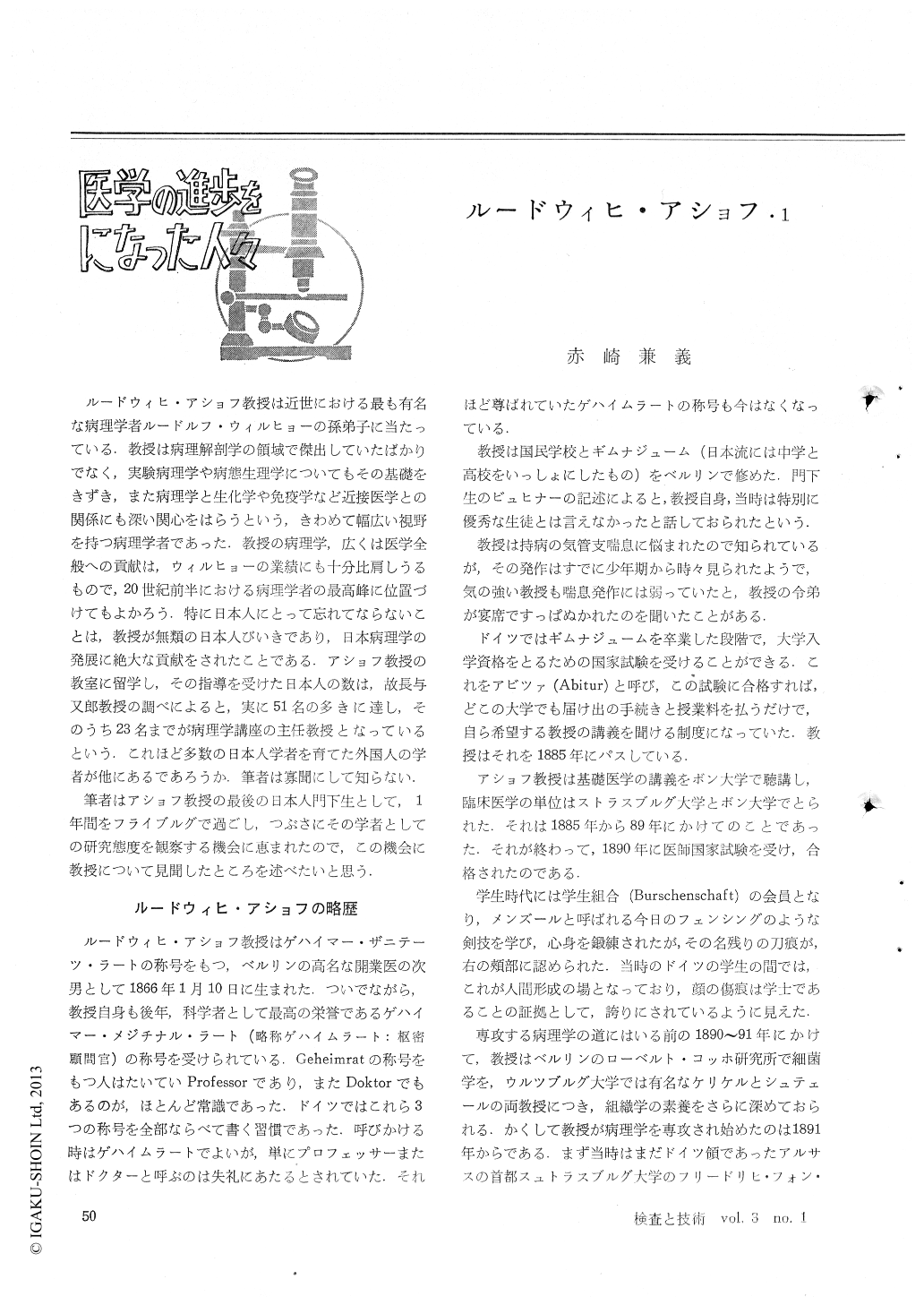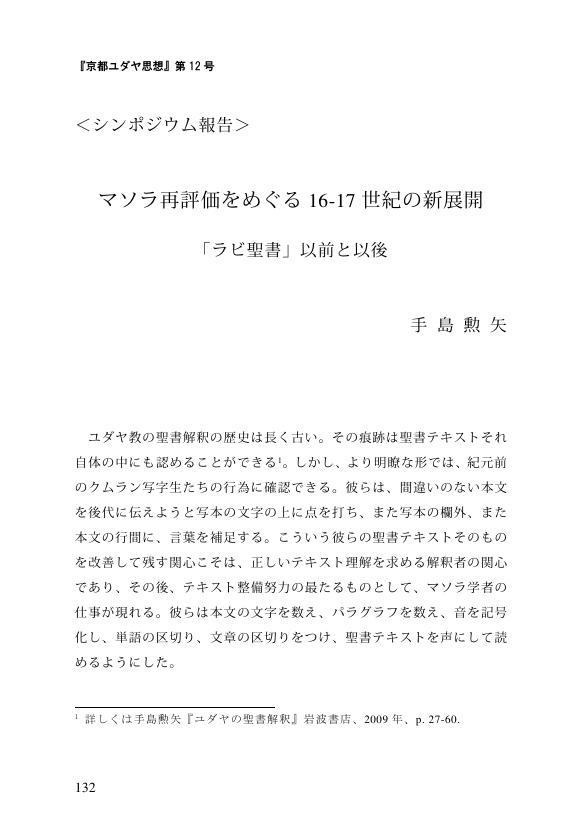2 0 0 0 ラピタ人からポリネシア人への変容過程を探る先史学的研究
南太平洋に住む人びとの祖先集団であり、ポリネシア人が生まれる直接の祖先となった先史ラピタ人の実態を解明するため、生物人類学、先史人類学、考古学、生態人類学、人類遺伝学、年代測定学、地球科学などの研究手法で多角的な研究を進めた。トンガ諸島のハアパイ・グループ、サモアのサワイイ島、フィジーのモツリキ島などで現地調査を実施して、それぞれの分野に関係する基礎資料類を収集するとともに、それらのデータ類を分析する作業を鋭意、前進させた。それと同時に、ラピタ人からポリネシア人が生まれる頃にくり広げられた南太平洋での古代の航海活動を検証すべく、ポリネシアから南アメリカの沿岸部に散らばる博物館資料を点検する調査を実施した。特記すべき研究成果は以下のごとくである。まずは、フィジーのモツリキ島にあるラピタ遺跡を発掘調査して古人骨(マナと命名)を発見し、フィジー政府の許可を得て日本に借り出し、形質人類学と分析考古学の方法で徹底的に解析することにより、古代ラピタ人の復顔模型を作成するに成功したことである。マナの骨格、ことに頭蓋骨は非常に良好な状態で遺残しており、これまでに発見されたラピタ人骨では唯一、詳細な復顔分析が可能な貴重な資料であったため、世界に先がけて古代ラピタ人の顔だちを解明することができた。それによって彼らがアジア人の特徴を有するとともに、併せて、現代のポリネシア人に相似する特徴も有することを実証できた。そのほか、一般にポリネシア人は非常に足が大きく、世界でも最大の大足グループであることを証明し、その性質がラピタ人の頃に芽生えたらしいことを推論できたこと、さらに、サモアのサワイイ島で考古学の発掘調査を実現できたこと、トンガ諸島で古代の漁労活動を類推する資料類を収集するとともに、現代人の遺伝的な関係を分析する血液試料を採集できたことなども大きな成果である。とりわけ世界で最初に復顔したラピタ人の等身模型は国内外に発信できる本研究の最大の研究実績であろう。
2 0 0 0 OA 序章 地域研究と国際政治の間
- 著者
- 大島 美穂
- 出版者
- 一般財団法人 日本国際政治学会
- 雑誌
- 国際政治 (ISSN:04542215)
- 巻号頁・発行日
- vol.2017, no.189, pp.189_1-189_16, 2017-10-23 (Released:2018-12-19)
- 参考文献数
- 22
The purpose of this volume is to review the relationship between International Politics and Regional Studies from the perspectives of each field, and to re-examine Regional Studies contribution to International Politics. It has been quite some time since Stanley Hoffmann, among others, indicated that International Relations (IR) was an American social science, and it has become commonplace to affirm that IR is not “international” at all, but is rather characterized by a pervasive Anglo-American mode of thought and resulting conceptual and spatial boundaries. Since then a limited number of studies have emerged to enhance our understanding of how IR is perceived in distinct places around the globe, and one of the most important of these is a series on “geocultural epistemologies in IR” by Arlene B. Tickner and Ole Wæver. The configuration of the JAIR membership shows that in Japanese academic circles IR has developed in a dual format with one branch focusing on theoretical research and global studies and the other on regional studies and historical research, and, moreover, that those tendencies are different from American IR. As another distinct feature, these two areas of research do not exist in an isolated manner, and more than a few members not only carry out regional studies but also incorporate a profound knowledge of theoretical research into their work, which has led to the development of significant resources and achievements. However, it is difficult to sustain this linkage as a steady process, and it seems that the majority of members, throughout their careers, study in a very narrow range of specialization with limited crossover into alternates branches of the field.It can be said that regional histories, as well as their political, economic, and social structures, have been formed in the context of international politics and that we cannot discuss regional issues without regard to international politics and vice versa. In this volume, by presenting the relationships between international politics and regional issues in the Middle East, Latin America, East Asia, South-East Asia, Russia and Europe, and by engaging in analysis of regional alliances in international conflict, we would like to try relativizing IR and the interaction of regional and international politics in evidence based research.
2 0 0 0 OA 水溶液中のカルシウムとマグネシウムに対する各種錯化剤のイオン封鎖能の測定
- 著者
- 安江 任 小澤 聡 荒井 康夫
- 出版者
- 公益社団法人 日本化学会
- 雑誌
- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)
- 巻号頁・発行日
- vol.1986, no.6, pp.767-770, 1986-06-10 (Released:2011-05-30)
- 参考文献数
- 26
水道水の軟化, ボイラーのスケール防止, 焼セッコウやボルトランドセメントの凝結遅延に関連し, 水溶液中のカルシウム, マグネシウムイオンを封鎖することを目的として, クエン酸ナトリウ, ショ糖, ブドウ糖, ジグリコール酸などの錯形成能,錯イオンの組成を比較検討した。測定方法には濁度法, 金属指示薬法, イオン選択電極電位差法, 電気伝導度法を用いた。クエン酸ナトリウムおよび糖類のイオン封鎖能は測定方法によってかなり相違し, その理由を考察した。クエン酸ナトリウムはカルシウムイオンに対する封鎖能が大であり, たとえぽpH8.5での封鎖能は26.8g であるのに対してマグネシウムのそれは17.0g であった。本研究で確認した錯イオンのほとんどは結合比が1/1であるが, ジグリコール酸のカルシウム錯イオンにかぎり結合比は1/2であった。また, 錯イオンの多くはpH8.0~9.5の水溶液中でもっとも安定である。
- 著者
- 岩崎民平 河村重治郎編集主幹 市河三喜顧問
- 出版者
- 研究社
- 巻号頁・発行日
- 1960
- 著者
- 五十嵐 里菜 馬場 悠太 平林 雅和 伊從 慶太 大隅 尊史
- 出版者
- 日本獣医皮膚科学会
- 雑誌
- 獣医臨床皮膚科 (ISSN:13476416)
- 巻号頁・発行日
- vol.25, no.3, pp.153-156, 2019 (Released:2019-09-20)
- 参考文献数
- 6
- 被引用文献数
- 1
ブリティッシュ・ショートヘアー,4歳4ヶ月齢,未去勢雄が両外耳道および耳介周囲に多発性の黒〜灰色,ドーム状の隆起性病変を呈した。病理組織学的検査によって,Feline ceruminous cystomatosisと診断された。自宅での点耳治療が困難であったため,病院での耳洗浄および1%フロルフェニコール,1%テルビナフィン,0.1%ベタメタゾン酢酸エステル配合の点耳ゲル剤による治療を計3回実施したところ,約3ヶ月以内に病変の著しい退縮を認め,最終投与の約6ヶ月後に至るまで再発を認めなかった。
2 0 0 0 OA 稀な病変を有した悪性リンパ腫合併シェーグレン症候群の剖検2症例
- 著者
- 永渕 裕子 伊藤 彦 小泉 宏隆 風間 暁男 高木 正之 山田 秀裕 尾崎 承一
- 出版者
- 一般社団法人 日本臨床リウマチ学会
- 雑誌
- 臨床リウマチ (ISSN:09148760)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.75-81, 2016-03-30 (Released:2016-05-31)
- 参考文献数
- 13
子宮腫瘍と両側副腎腫瘍を呈した悪性リンパ腫(ML)合併シェーグレン症候群(SjS)の2剖検例を経験した.症例1:関節リウマチとSjS合併の83歳女性.下腿浮腫精査で子宮腫瘍を指摘.症例2:SjSの83歳男性.発熱精査で両側副腎腫瘍を指摘.2例共生検できず.剖検でびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の診断が確定した.MLによる子宮と副腎病変は稀で,SjSでの報告はない.SjSに合併する腫瘍の鑑別として重要と考え,報告する.
2 0 0 0 OA 技術時代における退屈 郷愁と祝祭という現象をめぐって
- 著者
- 渡邉 京一郎
- 出版者
- 日本哲学会
- 雑誌
- 哲学 (ISSN:03873358)
- 巻号頁・発行日
- vol.2023, no.74, pp.240-255, 2023-04-01 (Released:2023-06-28)
- 著者
- 山本 和利
- 出版者
- 一般社団法人 日本プライマリ・ケア連合学会
- 雑誌
- 日本プライマリ・ケア連合学会誌 (ISSN:21852928)
- 巻号頁・発行日
- vol.34, no.3, pp.260-264, 2011 (Released:2015-05-30)
2 0 0 0 OA 「傷寒論」の治療諸原則について
- 著者
- 藤平 健
- 出版者
- The Japan Society for Oriental Medicine
- 雑誌
- 日本東洋醫學會誌 (ISSN:1884202X)
- 巻号頁・発行日
- vol.28, no.1, pp.1-12, 1977-11-30 (Released:2010-10-21)
2 0 0 0 OA 小学生の体力と学力の関連性
- 著者
- 新本 惣一朗 三木 由美子 山﨑 昌廣
- 出版者
- 日本生理人類学会
- 雑誌
- 日本生理人類学会誌 (ISSN:13423215)
- 巻号頁・発行日
- vol.21, no.2, pp.75-82, 2016 (Released:2017-10-31)
The purpose of this paper is to investigate the correlation between physical strength and academic performance in Japanese elementary school children while simultaneously obtaining basic data on physical strength and academic performance. Statistically significant correlations were found between various fitness scores and various academic scores with 5th and 6th grade elementary school boys. The correlations were seen between standing jump test scores, side step test scores, as well as sit-up test scores and many academic scores with 5th grade elementary school girls. With 6th grade girls, the correlations were seen between side step test scores, multi-stage fitness as well as flexibility test scores and various academic scores. These results indicate that correlations exist between physical strength and academic performance. However, it appears to be weak.
2 0 0 0 OA 食の安全性について ―その1:食の安全性とは何か―
- 著者
- 佐田 守弘
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.49, no.3, pp.161-167, 2010-06-15 (Released:2016-09-30)
- 参考文献数
- 3
2 0 0 0 ルードウィヒ・アショフ・1
ルードウィヒ・アショフ教授は近世における最も有名な病理学者ルードルフ・ウィルヒョーの孫弟子に当たっている.教授は病理解剖学の領域で傑出していたばかりでなく,実験病理学や病態生理学についてもその基礎をきずき,また病理学と生化学や免疫学など近接医学との関係にも深い関心をはらうという,きわめて幅広い視野を持つ病理学者であった.教授の病理学,広くは医学全般への貢献は,ウィルヒョーの業績にも十分比肩しうるもので,20世紀前半における病理学者の最高峰に位置づけてもよかろう.特に日本人にとって忘れてならないことは,教授が無類の日本人びいきであり,日本病理学の発展に絶大な貢献をされたことである,アショフ教授の教室に留学し,その指導を受けた日本人の数は,故長与又郎教授の調べによると,実に51名の多きに達し,そのうち23名までが病理学講座の主任教授となっているという.これほど多数の日本人学者を育てた外国人の学者が他にあるであろうか.筆者は寡聞にして知らない. 筆者はアショフ教授の最後の日本人門下生として,1年間をフライブルグで過ごし,つぶさにその学者としての研究態度を観察する機会に恵まれたので,この機会に教授について見聞したところを述べたいと思う.
2 0 0 0 IR 連合国戦争犯罪政策の形成--連合国戦争犯罪委員会と英米(上)
- 著者
- 林 博史
- 出版者
- 関東学院大学経済学部教養学会||カントウ ガクイン ダイガク ケイザイ ガクブ キョウヨウ ガッカイ||The Society of Liberal Arts Kanto Gakuin University
- 雑誌
- 自然・人間・社会 (ISSN:0918807X)
- 巻号頁・発行日
- no.36, pp.1-42, 2004-01
本稿では連合国の戦争犯罪政策の形成過程について、連合国戦争犯罪委員会に焦点をあて、同時に連合国の中小国の動向、役割に注意し、かつイギリスとアメリカ政府の動向を合わせて分析する。枢軸国による残虐行為に対してどのように対処するのかという問題を扱うために連合国戦争犯罪委員会が設置された。委員会は従来の戦争犯罪概念を超える事態に対処すべく法的理論的に検討をすすめ、国際法廷によって犯罪者を処罰する方針を示した。だがそれはイギリスの反対で潰された。その一方、委員会の議論は米陸軍内で継承されアメリカのイニシアティブにより主要戦犯を国際法廷で裁く方式が取り入れられていった。委員会における議論はその後に定式化される「人道に対する罪」や「平和に対する罪」に繋がるものであり、理論的にも一定の役割を果たすことになった。だが当初の国際協調的な方向から米主導型に変化し、そのことが戦犯裁判のあり方に大きな問題を残すことになった。
2 0 0 0 OA 国防軍免責の原点? : ニュルンベルク裁判:『将軍供述書』の成立をめぐって
- 著者
- 守屋 純
- 出版者
- 中部大学
- 雑誌
- 国際関係学部紀要 (ISSN:09108882)
- 巻号頁・発行日
- vol.35, pp.1-17, 2005-10-31
2 0 0 0 OA 臨床における経絡・経穴の意義を改めて問う
- 著者
- 和辻 直 橋本 厳 粕谷 大智 藤本 新風 篠原 昭二
- 出版者
- 公益社団法人 全日本鍼灸学会
- 雑誌
- 全日本鍼灸学会雑誌 (ISSN:02859955)
- 巻号頁・発行日
- vol.72, no.1, pp.14-27, 2022 (Released:2022-08-10)
- 参考文献数
- 15
2 0 0 0 OA マソラ再評価をめぐる16-17世紀の新展開 「ラビ聖書」以前と以後
- 著者
- 手島 勲矢
- 出版者
- 京都ユダヤ思想学会
- 雑誌
- 京都ユダヤ思想 (ISSN:21862273)
- 巻号頁・発行日
- vol.12, pp.132-160, 2021-12-20 (Released:2023-04-07)
2 0 0 0 OA 一五・一六世紀における「保内商人」団の経営形態変化と経営論理の展開
- 著者
- 鈴木 敦子
- 出版者
- 経営史学会
- 雑誌
- 経営史学 (ISSN:03869113)
- 巻号頁・発行日
- vol.29, no.2, pp.27-56, 1994-07-30 (Released:2009-11-06)
Researches on honai-shonin have been made on the assumption that they were za-shonin living in villages (sonraku-za-shonin). One of the issues that these researches have pointed out is that their assertion about monopoly changed in the sixteenth century from the monopoly of transaction (ichi-za-ken) to that of trade routes. In this paper we have inquired into this change from the viewpoint that this was the change of their organization and creed of business. The main points we have clarified are as follows : First, they asserted their monopoly of trade routes upon being recognized as a corporation. We have reached this conclusion as a result of the elucidation of the process of their getting out of the control of shoen-ryoshu (sanmon), and of the above-mentioned recognized by shugo-Rokkaku-shi.Secondly, the reason of their assertion is that the goods they dealt in increased in amount. They no longer were able to assert the monopoly with the sales method relying upon za. So they were forced to assert the monopoly of trade routes connecting suppliers and retailers. This change in the form of business was in correspondence with the emergence of a local economy on the eastern coast of Lake Biwa in Omi-no-kuni.Thirdly, the reason why they could change the form of business is that their policy was in accordance with that of shugo-Rokkaku-shiFinally, having passed through the process mentioned above, honai-shonin transformed themselves from medieval za-shonin to a new type of merchants which adapted themselves to the local economy in the sixteenth century, namely, shingi-shonin.
- 著者
- 杉江 あい
- 出版者
- 一般社団法人 人文地理学会
- 雑誌
- 人文地理 (ISSN:00187216)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.2, pp.191-211, 2017 (Released:2017-07-07)
- 参考文献数
- 45
バングラデシュの村落社会は宗教やカーストの違いに基づく多様な社会集団から構成されているにも関わらず,先行研究は被差別集団を含まないムスリムのみを主要な研究対象としてきた。また,従来の開発研究は,コミュニティを一枚岩に捉え,そこでの合意形成を無批判に民主的であるとする見方を批判してきたが,現在バングラデシュで展開されている農村開発事業では均質的なコミュニティが想定されている。本稿は,ムスリムの被差別集団が居住する地域におけるコミュニティの実態を,最も下位のインフォーマルな合意形成の単位であるショマージに着目して明らかにすることを通じて,バングラデシュ農村のコミュニティのありようを再考する。本稿が検討した事例において,ショマージは特定の村や集落を基盤として形成されていたが,ショマージのメンバーシップの条件設定とその承認はカースト的制度による不平等な権力関係に基づいてなされていた。経済,教育水準が一様に低く,政治的に従属的な被差別集団は,同じ村に居住するムスリムから成るショマージやその共同的な活動から排除されていた。そうした被差別集団から成るショマージは,紛争解決や宗教施設の建設・運営をする上で近隣住民に頼らざるを得ない状況にあった。カースト的制度に基づく不平等な権力関係はバングラデシュ農村のコミュニティを特徴づけており,そこでの合意形成は必ずしも民主的なものであるとは言えない。
2 0 0 0 OA 「地下鉄東西線転倒事故」の原因
- 著者
- 古川 浩 高橋 一雄
- 出版者
- 安全工学会
- 雑誌
- 安全工学 (ISSN:05704480)
- 巻号頁・発行日
- vol.20, no.2, pp.66-74, 1981-04-15 (Released:2018-02-28)
昭和53年2月28日に地下鉄東西線の上り電車が荒川・中川橋梁上で転倒した原因は,橋梁の下をくぐり抜けている防潮堤に事故当時西南方より吹きつけていた強風がつき当たって水平から9.17°上向きに風向きを変えて橋梁に達し,更に現場では橋梁の中間中桁に遮られて強い“吹き上げ”現象を起こした.そのため,車両の側壁に及ぼす西南風の水平分力と車両底面を突き上げる“吹き上げ”の合力によって事故が発生したことが明らかになった.本論文はこの現象の解明を調査結果を踏まえて理論及び計算によって 示したものである.