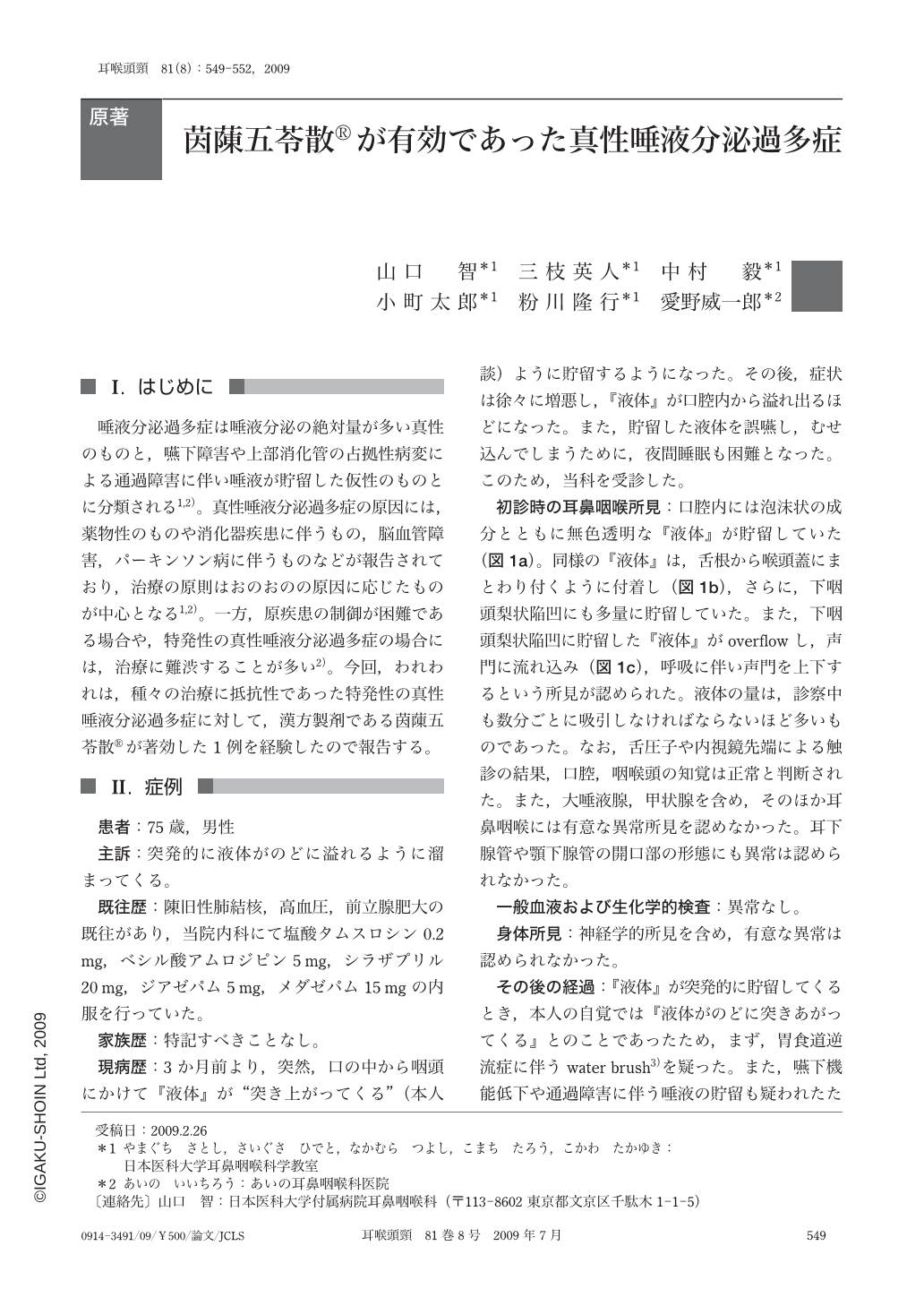2 0 0 0 OA ドイツにおける行政の電子化推進の体制と課題
- 著者
- 渡辺富久子
- 出版者
- 国立国会図書館
- 雑誌
- レファレンス (ISSN:1349208X)
- 巻号頁・発行日
- no.847, 2021-07
2 0 0 0 色彩の知覚とその心理効果
- 著者
- 大山 正
- 出版者
- The Visualization Society of Japan
- 雑誌
- 可視化情報学会誌 (ISSN:09164731)
- 巻号頁・発行日
- vol.17, no.64, pp.2-7_1, 1997
- 被引用文献数
- 2
2 0 0 0 腸内細菌が協調して脊髄の炎症反応を悪化させる
- 著者
- 天ヶ瀬 紀久子
- 出版者
- 公益社団法人 日本薬学会
- 雑誌
- ファルマシア (ISSN:00148601)
- 巻号頁・発行日
- vol.57, no.8, pp.775, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 5
自己免疫疾患の1つである多発性硬化症(multiple sclerosis: MS)は,脳および脊髄における散在性の脱髄斑を特徴とし,脱髄による神経伝達障害が視力障害,運動障害,感覚障害,認知症,排尿障害などさまざまな神経症状を引き起こすが,その発症原因は明らかでない.近年,腸内細菌叢の宿主に対する生理学および病理学的役割が注目されており,炎症性腸疾患,精神・神経疾患,免疫および代謝内分泌疾患などさまざまな疾患での研究が進められている.MSにおいても,2011年に健常人の糞便微生物移植によりMS患者の症状改善が報告され,患者の腸内細菌叢とMS発症および増悪との関係性が明らかになりつつある.現在,腸内細菌によるMSの増悪にはヘルパーT細胞のサブセットTh17細胞の分化誘導が関与すると考えられているが,その詳細は明らかでない.今回紹介する論文では,MSモデルであるマウス実験的自己免疫性脳脊髄炎(experimental autoimmune encephalomyelitis: EAE)を用い,2種の腸内細菌が協調して疾患の発症と増悪を促進することを報告している.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Borody T. J. et al., Am. J. Gastroenterol., 106, S352(2011).2) Cosorich I. et al., Sci. Adv., 3, e1700492(2017).3) Miyauchi E. et al., Nature, 585, 102-106(2020).4) Jangi S. et al., Nat. Commun., 7, 12015 (2016).5) Mangalam A. et al., Cell Rep., 20, 1269-1277(2017).
- 著者
- 大道寺 隆也
- 出版者
- 早稲田大学大学院政治学研究科
- 雑誌
- 早稲田政治公法研究 (ISSN:02862492)
- 巻号頁・発行日
- vol.110, pp.1-15, 2015-12-20
- 著者
- 角谷 詩織 Shiori SUMIYA
- 出版者
- 上越教育大学
- 雑誌
- 上越教育大学研究紀要 = Bulletin of Joetsu University of Education (ISSN:09158162)
- 巻号頁・発行日
- vol.39, no.2, pp.301-309, 2020
2 0 0 0 必修科目とした社会実装型PBLの初年度の実践とその教育的効果
- 著者
- 大塚 友彦 多羅尾 進 永井 翠 佐藤 知正
- 出版者
- 公益社団法人 日本工学教育協会
- 雑誌
- 工学教育 (ISSN:13412167)
- 巻号頁・発行日
- vol.69, no.4, pp.4_52-4_58, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 14
This paper reports the introduction of PBLs for social implementation as compulsory subjects, the efforts in first year practice, and the analysis of their effects. In the first half-year for the fourth grade students in KOSEN, “Social Implementation Project I” is placed to learn the importance of finding issues through case studies of social Implementations and to understand the relationship between technology and society. In the latter half-year, “Social Implementation Project Ⅱ” is placed, in which students work on social implementation as a team in collaboration with partners inside or outside of our campus. It shows the fact which the student’s self-evaluation of generic skills was improved by the student’s experience of PBLs. The fact that the student’s PROG scores were improved by the experience of PBLs suggests that PBLs for social implementation have the effect of improvement of the student’s competency. It shows that the analysis in this paper provides quantitative evidence for the effects of PBL for social implementation on human resource development.
2 0 0 0 輪状咽頭筋ミオパチーにサルコペニアを伴った嚥下障害例
- 著者
- 戸田 直紀 両角 遼太 東 貴弘
- 出版者
- 耳鼻咽喉科臨床学会
- 雑誌
- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, no.8, pp.615-620, 2021 (Released:2021-08-01)
- 参考文献数
- 12
Dysphagia in older persons can be of diverse causation. Herein, we report the case of a 74-year-old man with severe dysphagia caused by myopathy of the cricopharyngeal muscle.His swallowing function had begun to deteriorate 6 years before his first visit to our hospital. Videoendoscopic and video-fluorographic examinations of swallowing revealed no dilatation of the esophageal orifice. The patient was treated by cricopharyngeal myotomy. Histopathologic examination revealed myopathy of the cricopharyngeal muscle. However, no improvement of the swallowing function was observed after the surgery. This finding, along with his weight loss of 10 kg during the 6-year period suggested that the patient had sarcopenia with a loss of general muscle strength, including of the muscles related to swallowing, due to malnutrition. After nutritional management by tube feeding and swallowing rehabilitation for 3 months, he showed improvement in the swallowing function, and finally resumed oral intake. Indeed, video-fluorography after 5 months of rehabilitation revealed that the anterior movement distance of the hyoid had increased. This result indicated that anterior movement of the hyoid plays an important role in the dilatation of the esophageal orifice during swallowing.
- 著者
- 応 雄
- 出版者
- 北海道大学文学研究科
- 雑誌
- 北海道大学文学研究科紀要 (ISSN:13460277)
- 巻号頁・発行日
- vol.114, pp.41-62, 2004-11-30
- 著者
- 後 房雄
- 出版者
- 日本行政学会
- 雑誌
- 年報行政研究 (ISSN:05481570)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, pp.2-26, 2017
- 著者
- ぽむ企画
- 出版者
- 日経BP社
- 雑誌
- 日経アーキテクチュア (ISSN:03850870)
- 巻号頁・発行日
- no.820, pp.巻末2-9, 2006-04-10
秋葉原の現状を知るために、まずは近年の秋葉原の空間的変化を研究する森川嘉一郎氏(桑沢デザイン研究所特別任用教授)に、秋葉原の建築空間の特質を聞いた。 「秋葉原を構成する建物自体は、他の街とさして変わらない。大きく異なっているのは、それらのファサードの多くの面積が広告物で覆われていることと、そうした広告の趣味的な偏りだ」と森川氏は言う。
2 0 0 0 サイエンス2.0へようこそ Researchmap.jpについて
- 著者
- 新井 紀子
- 出版者
- 国立研究開発法人 科学技術振興機構
- 雑誌
- 情報管理 (ISSN:00217298)
- 巻号頁・発行日
- vol.52, no.1, pp.12-19, 2009
情報・システム研究機構国立情報学研究所では,研究者向けサイエンス2.0基盤サービスResearchmap.jpを公開する。本サービスは研究者に対して,研究ホームページを公開するための領域である「マイポータル」のほか,バーチャルなデスクトップの機能を果たす「マイルーム」,他の研究者と共同研究や委員会活動をするためのコミュニティーを提供する。マイポータルには研究者履歴(Curriculum Vitae)を公開するためのテンプレートのほか,研究ブログ,資料配布用キャビネット,動画配信ツールなどが備えられており,研究者はその中から自分を表現するためのツールを自由にチョイスし,効果的に情報発信を行うことができる。
2 0 0 0 IR 室町幕府の異国使節への応対
- 著者
- 関 周一
- 出版者
- 宮崎大学教育学部
- 雑誌
- 宮崎大学教育学部紀要 = MEMOIRS OF THE FACULTY OF EDUCATION, UNIVERSITY OF MIYAZAKI (ISSN:24339709)
- 巻号頁・発行日
- no.96, pp.100-129, 2021-03-31
2 0 0 0 IR 蓬左文庫本『日次記』の基礎的考察:書物の書写・贈与・相続をめぐる公家と武家
2 0 0 0 茵蔯五苓散®が有効であった真性唾液分泌過多症
Ⅰ.はじめに 唾液分泌過多症は唾液分泌の絶対量が多い真性のものと,嚥下障害や上部消化管の占拠性病変による通過障害に伴い唾液が貯留した仮性のものとに分類される1,2)。真性唾液分泌過多症の原因には,薬物性のものや消化器疾患に伴うもの,脳血管障害,パーキンソン病に伴うものなどが報告されており,治療の原則はおのおのの原因に応じたものが中心となる1,2)。一方,原疾患の制御が困難である場合や,特発性の真性唾液分泌過多症の場合には,治療に難渋することが多い2)。今回,われわれは,種々の治療に抵抗性であった特発性の真性唾液分泌過多症に対して,漢方製剤である茵蔯五苓散®が著効した1例を経験したので報告する。
- 著者
- 秋山 晋吾
- 出版者
- 千葉大学大学院社会文化科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書 (ISSN:18817165)
- 巻号頁・発行日
- no.95, pp.43-72, 2004-02
千葉大学社会文化科学研究科研究プロジェクト報告書第95集『近代ヨーロッパ政治文化の研究(2002-2003年度)』所収
2 0 0 0 OA 1E4-4 歩きスマホが反応時間および歩行動作に与える影響
- 著者
- 小松 史旺 小林 吉之 持丸 正明 三林 洋介
- 出版者
- 一般社団法人 日本人間工学会
- 雑誌
- 人間工学 (ISSN:05494974)
- 巻号頁・発行日
- vol.51, no.Supplement, pp.S178-S179, 2015-06-13 (Released:2015-08-06)
2 0 0 0 正倉院薬物「冶葛」と関連ゲルセミウム属植物に関する化学的研究
正倉院薬物「冶葛」の基原植物マチン科アジア大陸系Gelsemium elegansと同属北米産系G.sempervirensについて生理活性物質の大量供給と新規薬理活性物質・生合成中間体等の取得を目指し細胞・組織培養体の取得と二次代謝成分の探索を行った。また、これら植物についてDNA系統解析を試みた。1.植物本体と細胞培養体の含有成分の比較のためG.sempervirens植物本体について含有成分の精査を行った。その結果、茎部メタノール抽出物より既知アルカロイドGelsevirine,(Z)-Akuammidine,11-Methoxyhumantenineとともに新規オキシインドールアルカロイド4種、新規イリドイド1種を含む7種の化合物を単離することができた。また、HPLCによる部位別含有アルカロイドパターンの分析を行っている。2.タイ産G.elegans、北米産G.sempervirens葉・茎部より誘導したカルスの培養を行った。大量増殖したG.sempervirensカルスでは、β-Sitosterolなどテルペン4種が単離されたがアルカロイドは認められず、アルカロイド生産酵素系が発現していないことがわかった。また、G.sempervirensの液体培養においてジャスモン酸、イーストなどの添加による含有成分の変化について検討中である。3.G.sempervirens葉・茎部を用いてアグロバクテリウム感染による毛状根の誘導を試みている。4.タイ産G.elegansと北米産G.sempervirensについて遺伝子レベルでの差異を調査するため、DNA抽出を試みた。同じくマチン科のマチン、ホウライカズラとともにシュ糖含有抽出バッファーの使用により葉部からのDNA抽出に成功した。現在種々のプライマーによるPCRを行い、検出バンドの比較を行っている。
2 0 0 0 IR 翻訳 トランシルヴァニアの教会合同に関するレオポルト勅令(1699年)
- 著者
- 秋山 晋吾
- 出版者
- 千葉大学大学院社会文化科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学社会文化科学研究 (ISSN:13428403)
- 巻号頁・発行日
- no.12, pp.317-323, 2006-03
トランシルヴァニアでは、17世紀末にハプスブルク支配下に組み込まれてまもなく東方正教会のローマ・カトリック教会への合同が行われた。この教会合同は、ルーマニア人の民族意識の覚醒に決定的な影響を与えたとされているが、それだけにとどまらず、三ナティオ・四公認宗派体制を根幹とするトランシルヴァニアの国制に関わる問題性を内包していた。すなわち、宗派あるいは文化との関わりが概念的に強まることによるナティオの意味が大きく変化していく契機となったのである。ここでは、1699年2月16日に、神聖ローマ皇帝・ハンガリー国王レオポルト一世によって発布された、トランシルヴァニア侯国における東方正教会とローマ・カトリック教会の合同に関する勅令の全文を邦訳し、勅令発布の背景に関する解題を付した。
2 0 0 0 IR 翻訳 トランシルヴァニア侯国に関するレオポルト勅令(1691年)
- 著者
- 秋山 晋吾
- 出版者
- 千葉大学大学院社会文化科学研究科
- 雑誌
- 千葉大学社会文化科学研究 (ISSN:13428403)
- 巻号頁・発行日
- no.11, pp.146-156, 2005
ここに訳出したのは、1691年12月4日に神聖ローマ皇帝・ハンガリー王レオポルト一世(リポート一世)がトランシルヴァニア侯国の取り扱いを規定するために発布した勅令の全文である。この勅令は、16世紀前半からの中世ハンガリー王国の三分割を経て、1570年にオスマン宗主権下に成立したトランシルヴァニア侯国が、その国制を基本的に維持しつつハプスブルクの宗主権下に入ることを規定したものである。これは、1848年まで効力を保ち、トランシルヴァニアのいわゆる三ナティオ・四宗派体制を基軸とした侯国国制の基本文書となった。
- 著者
- 鈴木 賢子
- 出版者
- 美学会
- 雑誌
- 美学 (ISSN:05200962)
- 巻号頁・発行日
- vol.55, no.3, pp.62, 2004-12-31 (Released:2017-05-22)